
Kāyagatāsati〈身至念〉の三十二身分に続く「sabbe sattā marissanti」に始まる短い一節は、三蔵いずれかに伝えられている文句ではありません。しかし、Maraṇassati〈死念。 Maraṇasatiとも綴られる〉として唱えられている一節です。人は必ず死ぬものであることを念じる、すなわち「忘れない」ためのものです。
人は死ぬものです。わかっている、皆そんなことはわかっている…、つもりでいます。
ほとんどの人は皆、「僕は死にません」・「私はとりあえず大丈夫」とタカをくくっている。「死ぬ、そう、いつかは死ぬであろう。けれどもそれは今日ではない、明日でもない、来年ではない。さしあたって自分には関係がない」と。いや、そもそも自分が死すべき者であることすら、その日常の中で一瞬たりとも考えることもしないかもしれなせん。
「人は死ぬ、そしてその到来はおそらく予期できないものである」、それはあくまで言葉の上だけのものであって、これを真剣に、そして恐るべき事実として捉えている人は決して多くはないようです。在原業平の歌は、そのような人の心情を率直に、まさしく表しているものです。
ついに行く 道とはかねて 聞きしかど
昨日今日とは 思わざりしを
『古今和歌集』巻十六 哀傷歌
気づいたときにはもう遅い。それが多くの人にとっての老い、そして死です。あるいは、自分の死は受けいれられるけれども、自分の近しい人、父・母または可愛い我が子が生命を失うのは耐えられない、という人もあるでしょう。
仏陀が人の生命、死というものがいかなるものかを説かれた有名な話があります。ようやく歩けるようになったばかりの息子を失った悲しみのあまりに正気を失い、町をさまよい歩いて死んだ我が子の再生させる薬を探しまわる女がありました。それを見た仏陀は彼女を呼び、「一度も死者を出したことのない家族から芥子の実をもらい受けてくれば、その子を生返させよう」と約束。しかし、果たしてそのような家が一つもなかったことから、女は生命というものが死にゆく定めのもの、全ての人はどのような者であれ等しくその近しい者の死に直面するのであり、それは己一人の苦しみではないことを悟って正気を取り戻します。そして彼女は出家して、ついには阿羅漢となり、比丘尼の中でも頭陀を行じる者らの指導者的存在となる、という話です。
彼女の名はGotamī。貧しい家の出で、非常に痩せていたということから、Kisāgotamī(痩せぎすゴータミー)と呼ばれていました。仏陀の直接の導きに触れ得た果報者であったということに加え、彼女はもともと聡明で理知的であったのでしょう。
また、釈尊に親しく随行すること二十五年にしてその身の回りの世話をされた人に、阿難(Ānanda)尊者という方があります。ある意味自身の過失によって、久しく付き添ってきた優れた師、仏陀釈尊の涅槃(逝去)されるのが決定的となり、その時がまさにやって来ようとするとき、阿難尊者は釈尊から隠れ、住居の中に入って泣いていました。いまだ有学、すなわち修業によって高い境地には到達しているけれども、しかし学び行うべきことが未だ有る状態であり、円満なる悟りに至っていなかった阿難尊者にとって、師の死は容易く受け入れられるものではなく、その悲しみをこらえることが出来なかったのです。
阿難尊者の姿が見えないことに気づかれた釈尊は、比丘に阿難尊者が何処にいるかを訪ねます。尊者が影で泣いていることを知った釈尊は、これを呼んで重ねて無常の理を説かれます。
alaṃ, ānanda, mā soci mā paridevi, nanu etaṃ, ānanda, mayā paṭikacceva akkhātaṃ ―‘sabbeheva piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo aññathābhāvo’; taṃ kutettha, ānanda, labbhā. Yaṃ taṃ jātaṃ bhūtaṃ saṅkhataṃ palokadhammaṃ, taṃ vata tathāgatassāpi sarīraṃ mā palujjī’ti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
やめよ、アーナンダ、悲しむな。嘆くな。アーナンダよ、私はあらかじめこのように(繰り返し)説いたではないか。―「すべての愛しいもの、喜ばしいものからも別れ、異なるに至る」と。アーナンダよ、それはなんであれ、生じ、存在し、つくられ、滅びるものである。それを一体どうして「如来の身体が滅びないように」としえるであろうか。そのような理は存在しない。
DN, Mahāparinibbānasutta, Ānandaacchariyadhamma
このように語られて後、釈尊は阿難尊者に対し、それまでの長い間ずっと自身の世話をしてきたことを優しくねぎらわれています。結局、尊者は無常であることを念じてグッと堪えるも、やはり釈尊の死に実際に直面した際には涙を止めること出来なかったように伝承されています。その尊者が阿羅漢となるのは、釈尊の死後三ヶ月のことです。
以降、尊者は仏陀亡き後の仏教、僧伽存続に大きく貢献されています。阿難尊者という方の生涯は、釈尊の随行となるまでのいきさつ、悟られるまでの経緯と瞬間、そしてその生の最後を迎えるまでと、数ある仏陀の直弟子の中でも非常に印象的なものです。阿難尊者亡き後数百年を経た後のインドにおいても、特に比丘尼らから篤く尊崇されていたということが、玄奘の記録から知ることが出来ます。
さて、他者の死といっても、その死を看取ることのできた人の死と大往生であったと皆がある意味喜び得る死、理由なく無残にも殺害されて迎えた死、悲惨な事故死、自殺など様々です。釈尊の死は、その死の原因は恐ろしい痛みと下血とを伴うものであったとしても大変に安らかな、ある意味理想的な中で迎えられたものでした。
しかし、この世にあって死とは自からの病や老いなどによって起こるだけでなく、他者の関与によっても引き起こされるものです。そのような中に、受け入れられない死というものがあります。家族や恋人の死を受け入れられず、あるいはその死を理解できずにいる人が存在しています。
たとえば大東亜戦争中、物心こそついていてもいまだ幼い子供であったとき、はるか故国を離れた地にあって軍獣医をしていた父親について、ただ「戦死」とだけの通知と、遺骨も遺品も何もなく名前の書かれた木ぎれのみが入った小さな木箱を受け取り、それから七十年もその死を受け入れられず、いまだ寂しさ苦しみの中にあり続けているという方もあります。無論、今やもう八十にもなる高齢の方ですが、「おとうさん」という思いがその人生から離れることが決して無かった、何を見るに付けても父親を思いつづけている方があります。
また、ただ、ただその歩道をいつものように歩いていただけなのに、あるいは飲酒によって、あるいは運転者が病などにより意識を失ったことによって、突如として暴走した車が突っ込んで来、無残にもその生命が引き裂かれる。その恐るべき訃報を、いつものように何気なく出た電話などで聞かされる家族は、これをいきなり「人は死ぬものだから」と受け入れるわけにはいかない。
仕事を終え、いつもの家路についていたところを、暴漢に無残にも乱暴され、虫けらのように殺される。これを、殺される瞬間までの本人もその凶行を伝えられその遺体に対面した家族も、「無常だから、仕方のないこと」と平静を保つことなど普通できません。
突然でない、予期された自身の死についても同様です。現在、日本における死亡率の一位は癌で不動となっています。そして脳梗塞・心筋梗塞がそれに続いています。たとえば医師から余命半年を宣告された末期癌などの人が、それでもなんとか一日でも生命を伸ばしたい、なんらか奇跡によってあわよくば癌を克服したいと、多くの痛み苦しみと闘いつつ懸命に様々な治療を試みています。しかし、そうこうするうちにむしろ死を受け入れる準備が出来ぬまま亡くなる人、失意のうちに亡くなっていく人が多くあります。
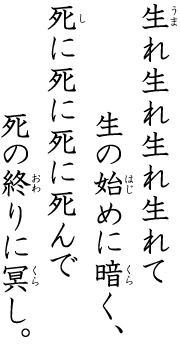
生きていたい、一日でも長く。生きていきたい、少しでも幸せに。けれども死は、人の願いなど関係なく、必ず訪れて来、その願いを打ち砕きます。そうかと思えば、あるいは病室の床にあり、あるいは家の布団の上にあって、「嗚呼、もうそろそろお迎えが来る頃だ」と落ち着きその死を受け入れ、多くの家族が看取る中で安らかに「良い人生だった」と回想し、皆に感謝しつつ静かに亡くなる人も、極めて稀にですがあるようです。
また、これは最近よく聞く話なのですが、老いた身体は人の介助なしに動かすことも排泄することも出来ぬようになり、心もぼんやりとした状態が長く続き、結局なんとなく死んで逝く人もあります。その死は、その家族にとって老人介護という大変な労から解放されることを意味し、喜ばしいことではないにしろ、むしろ家族をしてほっとさせるということでもあるのでしょう。
いや、あるいは誰にも知られること無く、ただ独り死に、その遺体が腐って周囲に異臭を放つにいたるまで誰も気づかない、というのも稀でなくあります。
これらは全て我々の周りで起こっている現実のことで、全く他人事などではありません。「人が死ぬことなど、いまさら仏教の坊主に言われなくとも分かりきっていることである。どのように死ぬか、という一点が重要なのだ」という人もあるでしょう、そしてそれは事実です。しかし、死に様は人それぞれで普通は想像だに出来ないものであり、またほとんどの人にはその選択も出来はしません。
人によって、また場合によって死は、人生は理不尽極まりなく感じるものです。直面しなければならないのは、自分の死だけではなく他人の死も同じであり、それは時として自分の死などよりもずっと苦しく、精神的に受け入れられないものとなるでしょう。たとえそれが事実であったとしても、これらの人に等しく、また単に「遅かれ早かれ人は死ぬものだ」、「無常だ。死とはその真理が、あたりまえに発現した現象にすぎない」などとは言えない。「自身の宿業、どう仕様にも無い業果のためだ」、「それは人の思義を超えたものだ」などとも、いきなりは言えません。
もし近しい人の死に際した者で、それを冷然として「お、死んだか。突然だったが、まぁ無常だから」などと言えば、常識的な感覚からすればどうかしているとされるに違いない。
今から十二世紀以上の昔、平安初期の空海は、人の生というものについてこのように言っています。
悠悠たり悠悠たり、太だ悠悠たり。内外の縑緗、千萬の軸あり。《中略》
杳杳たり杳杳たり、太だ杳杳たり。道と云ひ道と云ふに百種の道あり。
書死え諷死へなましかば、本何がなさん。知らず知らず、吾れ知らず、
思ひ思ひ思ひ、思ふに聖も心ること無し。牛頭、草を甞めて病者を悲しび、
断菑、車を機つりて迷方を愍ぶ。三界の狂人は狂せることを知らず、
四生の盲者は盲せることを識らず。生れ生れ生れ生れて生の始めに暗く、
死に死に死に死んで死の終りに冥し
それ生は吾が好 にあらず。死また人 悪む。しかれども猶を生まれ之き生まれ之いて六趣に輪転し、死に去り死に去て三途に沈淪す。我を生じる父母も生の由来を知らず、生を受くる我が身もまた死の所去を悟らず。過去を顧れば、冥冥としてその首を見ず。未来に臨めば、漠漠としてその尾を尋ねず。三辰、頂に戴けども暗きこと狗眼に同じく、五嶽、足を載すれども迷えること羊目に似たり。日夕に営営として衣食の獄に繋がれ、遠近に趁り逐て名利の坑に堕る。《原漢文》
限りなし限りなし、なんと限りないことであろうか、《中略》
内外の縑緗〈仏教および外教の書物〉には千も万もの巻軸がある。
暗く深し暗く深し、なんと暗く深いことであろうか、
道〈思想・宗教〉という道には百種の道がある。
書を絶やし、諷誦〈素読・暗誦〉することも無ければ、真理をいかに知られよう。
(もしそうなれば)知らず、知らず、私も知ることはなく、
思い、思い、思い、思ったとして聖者も知ることはない。
牛頭〈神農. 支那の伝説的帝王〉は草から薬を作って病める者を哀れみ、
断菑〈周公旦. 儒教における聖人〉は車を操り方角を示し迷った者を愍んだ。
三界〈全ての宇宙〉の狂人は自ら狂っていることを知らず、
四生〈全ての生物〉の盲者は己が盲ていることを識らない。
生れ、生れ、生れ、生れて、生の始めに暗く、
死に、死に、死に、死んで、死の終りに冥し。
そもそも生〈生まれ、そして生きること〉は私の好むことではなく、また死は人の憎むものである。しかしながらなお、(我々人は)生まれ変わり、生まれ変わりしながら(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天いずれか)六趣に流転して、死に去り、死に行きながら三途〈地獄・餓鬼・畜生〉に沈淪している。私を生んだ父母であっても、(我が)生の由来を知らず、生を受けた我が身もまた、死の行き先を悟れはしない。過去をかえりみたとしても、冥冥としてその始まりを見ることは出来ない。未来を臨んだとしても、漠漠としてその終わりを知ることなど出来はしない。三辰〈太陽と月と星々〉をこの空に頂いていながら暗暗としていることは犬の眼に同じく、五嶽〈支那における五名山、神話で盤古が死んで出来た山とされる。ここでは「大地」の意〉を足下に踏んでいたとしても迷えることは羊の目に似ている。昼夜に営々として衣食に追われる監獄に繋がれ、遠近わかたず追い求めて、名誉と財産という深い坑に堕ちている。
空海『秘蔵宝鑰』巻上 《原漢文》(『定本 弘法大師全集』, vol.3, pp.113-117)
しかし、仏教の観点からすると、そのような憂愁・悲泣、あるいは怒りなどは、やはりすべて真実を知らない無智、周囲で日々起こっていることについて盲目であることによって起こるものです。人は必ず死ぬものであり、それがどのような形であれ死んだからといって今更に驚き慌てふためくほうがむしろおかしい。
とは言え、近しい人の死、すなわち別れはまことつらく悲しいものです。いや、時にそれは、悲しいなどという言葉で言い表すことが出来ぬほどの痛みを伴います。しかし、しかしその別れが如何なる形であっても、それは並大抵のことではありませんが、それに対する悲しみをグッと堪え、無常という現実をまさしく再確認する時です。