ワルシャワからカイロに直行便があった。五時間強ほどのフライトだったかと思う。ワルシャワは随分肌寒かったが、エジプトはすこし蒸し蒸しとして暑いほどであった。夜九時であったか十時であったか、もう遅い時間だったように思う。
入国審査(イミグレーション)を通ってから手荷物受取所に向かっていると、コンコースを歩く私の姿を見たおそらく警備員でなく警察官であろう、恰幅の良いヒゲを生やした制服の男がたちまち血相を変えて飛んできた。
「おい止まれ。お前はなんだ。パスポートを見せろ」
と威圧して云う。見せると少し警戒を解いたようで、
「あれ…日本人?なんだ、カンフーかなんかの格好なのかそれは。何しに来た?」
と聞いてくる。
「いや、私は仏教僧で、友人を尋ねに」
といってもわからないらしい。きょとんとしている。それでも、
「そうか、日本人か…。仏教僧?まぁ、わかった。行って良い」
とパスポートを返され開放された。私のような者などそうそう眼にすることのない、西洋ともまた異なったイスラム文化圏にあることを強く意識させる出来事であった。国際空港でこれならば街に出た時にはどうなるのか、とおぼえず苦笑した。
荷物を受け取りゲートを出ると、そこに懐かしい友の笑顔が変わらずにあった。国際空港から車を走らせること一時間、いや、二時間近くだったかもしれない。彼が住んでいるというずいぶん立派な家に着いた。そこまでの夜道はひどく暗く、大通りでもあちこちに恐ろしく高いスピードバンプがあってその度に急減速しなければならず、それを超える度に結構な衝撃を感じなければならなかった。そのスピードバンプのあまりに高すぎることを云うと、彼は「そうなんだよ、これ冗談みたいに高いんだ。いくらなんでもひどいだろ?」と笑って答えた。
友が務めるガメーサは世界的な大企業で、彼ら海外に派遣する技術者に比較的良いホテルの部屋を借り、そこで寝泊まりさせるのが常であるらしい。もちろんホテルは朝食付きで、昼食も夕食も会社持ちだそうである。彼らは食事の度にそのレシートか領収書を必ず受け取っていた。そういえば、かつて友がギリシャにある時もでもそうであった。しかし、夜に着いた時はわからなかったが、エジプトで彼の滞在しているのはリゾートホテルがその中心部にあるヴィラ(別荘のような一軒家)であった。最初はリゾートホテルの一室で暮らしていたらしいけれども、もうホテル暮らしはうんざりだ、と別にヴィラを借りて住むようになったのだという。
一体どうして砂漠地帯に差し掛かる何もないところにそんなリゾートやヴィラを建てるのか私にはわからなかったが、どうやらリゾートをあちこち作って、そこに投資するのが流行っているらしい。他にも似たようなヴィラが、郊外のそこら中にあることに後日気付いた。おそらく不動産バブルが始まっていたのであろう。無駄な投資になるとしか思われない土地に何かどしどし勢いで作るのは、新興国によく見られる光景であろう。街は昨年から始まったアラブの春の雰囲気が濃厚に漂い、民主化運動の最中に生命を落としたらしい男たちの顔写真がそこらに飾られていた。
街のあちこちに軍が展開しており、いまだ少々物々しい様相であった。といっても、徴兵されて基礎訓練を終えたばかりであろう若い兵士たちが街の要所要所で暇そうに警備にあたっているだけで、緊張感はそれほどない。
友人は仕事の日も別に構わない、ということで、その仕事場であるあちこちの砂漠の風力発電所に連れられて行動を共にした。砂漠を見るのは初めてではなかったけれども、エジプトのそれはまた他と全く違う、眼にするもの全てが私には真新しく、新鮮だった。友人のエジプト人の同僚ムハンマドとも知り合いになった。彼は優秀な男で、英語ばかりかスペイン語も実に流暢である。どこで勉強したのか聞くと、PCの語学学習ソフトのロゼッタストーンで独習したのだという。あのソフトだけでそこまで流暢に話せるようになるとは、あなどれないものである。

それから友人は休みのたび私をどこかに連れて行ってくれた。せっかくの休みに気の毒に思ったけれども、彼も行きたいところだから一緒に行くのだと言ってくれる。友人はそういう男だった。砂漠地帯に点在するキリスト教で最古とされるコプトの修道院につれられていった。随分あちこち見せてもらったものだが、その中でもとびきり古く、また印象に強く残ったのが聖アントニウス修道院だった。
四世紀にまでその起源を遡り、幾世紀にも渡って俗世界と隔絶した修道生活を送ってきたのが、近年ようやくその門戸を開いたのだという。その門をくぐると老齢のコプト神父が近づいてきた。その神父は白く長いヒゲを蓄え、優しげな眼を持ついかにも神父という威厳を備えた人であった。老神父は驚いた顔で開口一番、
「お前は一体何だ!?」
と聞く。そこで私は仏教僧で、日本人ですと答える。すると神父は
「仏教!?…おお、聞いたことがある。へぇ、仏教僧か」
というや、左に肩を並べていた友人の方を向き、
「どこから来た?」
と問う。友人はスペイン人でエジプトで働いていると答えた。すると、やにわに神父は
「お前は神を信じるか?」
とまず友人に尋ねてきた。ただ観光しようと修道院の門をくぐって間もないことである。私はその唐突の問いに驚くとともに面白さを感じた。友人はスペイン人であってカソリック教圏の人であり、国には宗教をカソリックで登録しているらしい。けれども彼は今どきのスペイン人であってキリスト教など信じておらず、いわば「Resistered Christian(登録上のクリスチャン)」なのだという。特に若い世代における教会に対する不信感は甚だ強いことを、昔話してくれた。そこでそんな彼は、
「私はクリスチャンです」
と上手く答えた。すると神父はニヤリと笑い、そうかそうか、良し良し、といかにも言わんばかりに満足気に
頷
く。そして、くるりと私の方を向き、
「お前は神を信じるか?」
と同じく尋ねてきた。友人が聞かれたならば私も当然尋ねられるであろう。いや、むしろそれを私に尋ねるため、まず友人に問うたのであろう。しかし、まさか神父から修道院でこれを聞かれるとはそれまで思いもよらなかった。こりゃ、どう答えたものかと一刹那逡巡した。けれども、
「いや、私は神は信じていません、神父よ。仏教では神の存在を認めないのです」
と忌憚無く答えた。その我が答えを耳にした途端、待ってましたとばかりに神父はサッと胸ポケットに刺してあった万年筆を私の面前に突き出し、こう問うてきた。
「なぜ、この万年筆はこうして存在している?」
瞬時にその問いの意図とその問いの行き着く先を解したけれども、ここは素直に答えることにした。
「それは職人がそのペンを作ったからです」
「そうだ、その通り。職人がこれを作ったからこのペンはここにある。では、お前は何故ここに存在している?どうしてお前はこの世にあるのか?」
その問いは私ばかりでなく友人にも答えさせた。当然、父母があったからである。老神父は我々の答えを聞くや、
「そうだ!その通り!父と母とがあったからだ。父と母がなければこの世にお前はない。我々は父と母とがあってこそ存在しているのだ」
と右手の人差し指を立てながらいう。すると今度は大地に両足を開いて踏ん張り、おもむろにその指で天と地とを順に指して言った。あたかも歌舞伎の見得である。しかし、老神父はこれをごく自然にやっている。実に面白い。
「では何故、この天と地はこうしてここにあるのか!?」
そら来た。そりゃそう来るだろうと思っていた私は、しかし、では神父相手にしてならばどう答えれば良いのか、英語ばかりか日本語でも怪しいもんだと思いつつ、
「それは自然の摂理として諸々の原因と条件とが…」
と言いかけたところ、たちまち神父の大喝が飛んできた。
「違う!!!神だ、神が造ったからあるのだ!!!」
隣で友人はニコニコ、いや、ニヤニヤしてこれを聞いている。私はどうしようかまた迷った。最初の問いが発せられた時にこうなるのはわかっていた。そもそも、私達はここに問答しに来たわけではない。そしてここで私が神父の言葉に「いや、神父よ、ならばその神も神以外の誰かが造ったものとなるでしょうに」などと反論しても、彼の信仰が揺らぐはずもない。私も東京の星美に通い、幼くしてキリスト教教育を受け日曜にはミサで讃美歌すら歌っていた身。その教義の大綱と世界観はしっかり心得ている。これは古くて新しいキリスト者と異教徒や無神論者との対話であった。まさか逆にこちらからトマス・アクィナスの『神学大全』など持ち出してさらに問答を展開する必要など全く無いし、それは不毛である。なにより、老神父のキリスト者としての実直な姿と信仰に基づく言葉に敬意を憶えていた私は、あえて一瞬言おうかと迷った言葉を口にせず、
「そうですか、神父よ」
とだけ答えた。老神父のなしたその時のご満悦の顔は、実に愛らしいものであった。門を入ったところにある修道院の事務所のすぐ前でのことである。私はなぜここでこんな問答をしているのか。老神父は、
「よろしい!では、ツアーを始めよう」
と言った。私は心愉快であった。老神父はそうして我々に修道院の歴史を紹介しながら、城塞都市のようになっている施設内のあちこちをゆっくり案内してくれた。修道院では働かざるもの食うべからずで、そこに起居する修道士は例外なく誰でも手に職を持っており、老神父は参拝者や観光客のガイドがその勤めであった。

砂漠の只中にある聖アントニウス修道院は東南アジアや日本の僧院などとはもちろんまったく異なる雰囲気である。中には種々の工場があり、また緑も多く、畑すらあって涼し気である。ひっそり静まり落ち着いた、大変美しいところであった。一時間ほどであろうか、あちこち見せて回ってくれたあと、入口の近くの事務所の中に通された。
中は修道士たちが拵えた革で編んだ十字架や、よく教会で使われる、あの独特な香りのする乳香や没薬を練り込んだであろう香など手作り品の並ぶ土産物売り場となっていた。老神父はまだ色々仏教について聞きたいから、と事務所の木机にならんだ椅子に座って話すことになった。「異教の修道士」がどのような生活を送っているか知りたいのだという。
そのとき、修道院には他に観光客は一人としておらず、誠に静かなものである。そこで私は根掘り葉掘り聞かれることになった。まず起床時間、起床して何をするのか、食事はどうする、それはどんなものだ、などなど。
「朝四時頃に起き、顔を洗ってから一時間ほど瞑想し、陽が登ってから朝食をとります。その朝食はいたって簡単なもので、赤豆の煮たのと少しばかりの白米だけ。本来は律で白粥のみが許されており、実際白粥のことも。それが終わったら托鉢に行きます」
「托鉢?それはなんだ」
「托鉢とは鉄鉢を持って町や村を歩いて家々から毎日の食事の施しを得ることで、仏教僧の義務であり日課なのです」
「毎日?」
「ええ、毎日です」
すると老神父の顔色が変わり、すぐさま興奮した様子で腕を振り上げ、指を指しつつこう言った。
「それは良くない。ひどく悪いことだ!!!」
これを聞いた友人がすかさず横から
「いや、神父様。仏教ではそういうことではなくて、これを信仰してきた国では歴史的に社会全体で僧を…」
と説明した。友人は仏教徒ではないし、仏教のこともよく知らない。けれども東南アジアや南アジアを長く旅した経験から、彼の地で日々なされる托鉢というものがどのようなものであるのかはある程度心得ていた。仏教における出家とは、いわゆる職(俗)の放棄を意味し、法(真理・教え)の保存と実現に専従することである。その故に人々はこれを敬して経済的に支えるという構造となっている。しかし、老神父はまるで釈然としない様子である。幾世紀にも渡って自給自足生活を続けてきた修道士たちからすれば、我々仏教僧が毎日托鉢して食を人々から得ることは極めて不勤勉であり、搾取であると思うのも無理はないのであろう。しかし、私の胸中では、それを言うならかのアッシジのフランチェスコはどうなるのだ、と思ったが口にはせずにいた。老神父はさらに質問を加えて来る。シャワーは?寝床は?僧院とはどのようなものだ?、と色々事細かく知りたいらしい。
「いわゆるシャワーというのを備えている僧院もありますが、大抵は外にある水を張った水浴場で手桶を使い、バシャバシャ水を浴びるだけです。素っ裸になることはなく、沐浴用の腰衣を巻いて石鹸で身体を洗うのです。普通は托鉢から帰ってからと、夕方にもう一度の一日二度で、だいたい皆が同じ時刻に行います」
「水?お湯は?お湯は出ないのか?」
「僧院にお湯を作るような設備はまずありません」
「寒くないのか?冷たいであろう」
「暑季や雨季は良いですが、水場は蚊が多くてかないません。寒気の朝は震えるほど寒いです。でもお湯などないので水を浴びるのです」
老神父はすこし怪訝な顔をする。
「では寝床は?どういう風だろう」
「ベッドで寝るのですけれども、普通は木の硬いベッドの上に竹などを編んだマットを敷くだけです。場所によってはベッドなど無く、床にそれを敷いて寝ます」
「それでは身体が痛くて休められないだろう。痛くないのか?」
「慣れないうちはずいぶん痛く、落ち着かないものですが、慣れたら平気なもんです」
このあたりから老神父が気の毒がるような顔になる。そして、さらにアレコレ非常に事細かく聞かれ、仏教寺院とはどのようなものか、僧院生活とはいかなるものかを話していくと、何かショックを受けた様子となっていった。話が終わる頃には最初の意気揚々とした感じはすっかりなくなっていた。
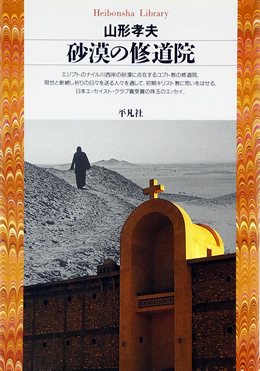
後年、私に宮城県仙台から少し離れた小高い山の上にある小さな寺の住職にならないかとの誘いがあった時、何故かその寺で東北大学の山形孝夫先生とお会いすることになった。そこで話ついでにこの話をしたところ、先生は笑い出されて言った。
「そりゃ、コプトの修道士たちは世界中で自分たちほど清貧生活を続けている者など無い、と大変な自負を持って生きているのです。そうしたところに、よく知らない遠い彼方の東洋にある仏教僧の方がまさかより貧しい生活を送っていることを知り、少なからぬショックを受けたのですよ。非常に面白いご経験をされましたな」
ああ、そういうことでしたか、と納得したものである。無知な私は先生がその専門家であることを初めて知ったが、ずいぶんそれから話がはずんだ。
老神父との会話を終えると、私と友人は修道院にいくらか寄進し、私はキリスト教徒の親族のために黒い革を編んで作った比較的大きな十字架と香を買った。黒革の十字架は老神父も首に掛けているのと同じ、よく出来た格好の良いものである。異教徒の私が修道院に寄進し、そういう物を求めるのをかなり不思議がっていたが、老神父はまた深い愛嬌のある様子に戻っている。
門の外まで見送ってくれるいという老神父は歩きながらこういった。
「仏教というのがどういうものか知るのにいい本はあるか?英語の」
「あります。Dhammapadaという経典があって真理の言葉という意味ですが、それが良いでしょう」
「そうか。じゃあ、もし良かったらそれを送ってくれないか?」
「もちろんです、神父」
まさか老神父がDhammapadaを読んで仏教に改宗するはずもない。けれども、エジプトで聞くことも見ることもまず無いであろう仏教に少し興味を持ったようだった。
「この一千年以上の長い伝統を誇るアントニウス修道院に仏教僧が来たのはあなたが初めて、歴史上初のことだ。一つ記念写真を撮ろう。この修道院の前の土産物屋は私の親族がやっているんだ。彼に写真を頼もう」
「それは喜んで。私も是非」
その親族の人に紹介されると一緒に修道院の門の前に立ち、老神父と並んで写真を撮った。

写真を撮るのに老神父は最初、手に何も持たずにだらりと手をぶら下げていた。けれども、横で何やら私のほうをチラチラと見だしたかと思うと、懐から手作りらしき木製の十字架をすっと出してきた。「いいか?キリストだぞ?」と言わんばかりの、しかしごく自然で気張らないその仕草もまた、老神父のまっすぐな徳を表しているようであった。友人は横でずっと笑顔でいる。そうして写真を撮り終えると、老神父に案内してくれたことへの感謝を述べて別れを告げ、もう陽もずいぶん傾いていたその日、我々はまた砂漠にずっと伸びる道をひた走ってカイロに戻った。
帰路、友人は面白かったと終始ご機嫌であった。私は思いがけない経験をさせてくれた友人に深く感謝するばかりである。彼の家までの途上、あの老神父についての話が途切れることはなかった。
あれからもう十三年、私はその老神父のことが今も強く印象に残っている。老神父は彼の地でご健在であろうか。
生来の粗忽者である私は、老神父から手渡されたその名前が書かれていた小さな名刺を東南アジアの僧院にあるとき紛失してしまった。ずいぶん探し回ったけれどもついにでてこなかった。嗚呼、果たして約束の本を老神父に送れないままとなったのが、今も悔やまれてならない。