大乗の立場からの四念住理解は、大乗の諸教論にてアレコレ広範になされていますが、ここでは支那におけるその大凡を簡便に記す『翻訳名義集』の一節を紹介しておきます。
『翻訳名義集』とは南宋の学僧、法雲によって編纂された梵漢辞典です。仏教における述語や人名など重要語句の原語、すなわちサンスクリットを音写で示し、その異訳や意味内容を種々の出典を挙げた書で、収録されている語はおよそニ千余り。その中、やはり四念住は重要であると認識していたようで、比較的多くの項を割いて説明されています。
法雲はその一節にて、何やらとぼけた事を一部述べてはいるものの、やはり有部における理解を前提としつつ、特に天台の教義からする四念住(四念処)に対する理解をよくまとめ示しています。といっても、智顗や湛然など天台の学匠らの四念住に対する所説がまさしくそうであったように、その内実は説一切有部の説を踏襲したものでほとんど変わりなく、少しばかり空観による大乗的「表現」を加えているだけです。
ただし、その記述は、一定以上の仏教に対する素養を有する者が読むのでなければ、まるでチンプンカンプンで「何を言っているのかサッパリワカラン」であろうものとなっています。しかし、その素養をすでに備えた者が読めば、四念住を理解するに大きな助けとなるものでしょう。
毘跋耶斯。 此云四念處。念即是觀。處即是境。智論釋曰。初習善法爲不失。故但名念。能轉相轉心。故名爲想。決定智無所疑。故名智。大經云。更有新醫從遠方來。曉八種術。謂四枯四榮。言四枯者。人於五陰。起四倒見。於色計淨。於受計樂。想行計我。心起常見。故令修四念處破其四倒。初觀身不淨。一切色法名之爲身。己名内身。眷屬及他名外身。若己若他名内外身。此三種色。大論明五種不淨。一生處。是身爲臭穢。不從蓮華生。亦不從薝蔔。又不出寶山。二種子不淨。是身種不淨。非餘妙寶物。不由淨白生。父母邪想有。三自性不淨。地水火風質。能變爲不淨。傾海洗此身。不能令香潔。四自相不淨。種種不淨物。充滿於身内。常流出不止。如漏嚢盛物。五究竟不淨。審諦觀此身。終必歸死處難御無反復。背恩如小兒。二觀受是苦。意根受名内受。五根受名外受。六根受名内外受。於一根有順受。違受。不違。不順受。於順生樂受。於違生苦受。於不違不順。生不苦不樂受。樂受是壞苦。苦受是苦苦。不苦不樂受是行苦。諸受麁細無不是苦。三觀心無常。心王不住。體性流動。今日雖存。明亦難保。山水溜斲石光。若不及時。後悔無益。四觀法無我。法名軌則。有善法惡法無記法。人皆約法。計我。我能行善。行惡行無記。此等法中求我決不可得。龜毛兎角。但有名字。實不可得。故經云。起唯法起。滅唯法滅。但是陰法起滅。無人無我衆生壽命。是名無我。此説別相念處。總相念處者。縁一境總爲四觀。此中應四句料簡。一境別觀別如上別説 二境別觀總。三境總觀別此二是總相念處之方便 四境觀倶總。是總相念處。若作一身念處觀。或總二陰。乃至總五陰。是名境總觀別也。受心法念亦復如是。阿毘曇中。明三種念處。謂性共縁。對破三種外道。四教義云。一性念處。智論云。性 念處是智慧性。觀身智慧。是身念處。受心法亦如是。解者不同。有但取慧數。爲智慧性。即是性念處。南岳師解。觀五陰理性。名性念處。故雜心偈。是身不淨相。眞實性常定。諸受及心法亦復如是説。二共念處。智論云。觀身爲首。因縁生道。若有漏若無漏。受心法念處亦如是。解者不同。有師解云。共善五陰。諸善心數法合明念處。若南岳師解。即是九想背捨勝處諸對治觀門。助正道。開三解脱。故名爲共念處。故經云。亦當念空法。修心觀不淨。是名諸如來甘露灌頂藥。三縁念處。有師解。通一切所觀境界。皆名縁念處觀。有言。十二因縁境。有言慈悲所縁境。若南岳師解。縁佛教説所詮一切陰入界。四諦事理。名義言語音詞因果體用。觀達無礙。能生四辯。於一切法。心無所礙。成無礙解脱。是縁念處觀也明小乘竟 若依大乘。以明四榮。如後分云。阿難如汝所問。佛涅槃後依何住者。阿難依四念處。嚴心而住。觀身性相同於虚空。名身念處。觀受不在内外。不住中間。名受念處。觀心但有名字。名字性離名心念處。觀法不得善法。不得不善法。名法念處。華手經云。一切諸法皆名念處。何以故。一切諸法。常住自性無能壞故。斯乃即法是心即心是法。皆同一性。性豈能壞乎
【毘跋耶斯】
ここ〈支那〉では四念処〈四念住〉と云う。念とは即ち観、処は即ち境〈対象〉。『智論』〈龍樹『大智度論』〉に、「初めて善法を修習するとき、(認識対象を)失わせないようする為の故にただ念と名づける。よく相を転じ、心を転じ、故に名づけて想という。決定の智によって疑う所が無いことから智と名づける」と注釈されている。『大経』〈『大般涅槃経』を意図したか?しかし直接的には智顗『四念処』〉には、「更に新しい医師があって遠方より来たったが、八種の術を極めていた。謂わく四枯四栄である」と云う。四枯〈不浄・苦・無我・無常〉とは、人が五陰〈五蘊〉に四倒〈四顛倒〉の見を起こすことの謂である。色を浄であると考え、受を楽であると考え、想と行とを我であると考え、心に常見を起こす。故に四念処を修して、その四倒を破すのだ。
初めに身〈kāya〉は不浄であると観じる。一切の色法を名づけて身とし、己を内身とし、眷属及び他人を外身とする。もしくは自己もしくは他者を内外身と名づける。これが三種の色である。『大論』〈『大智度論』〉には五種不浄が明かされている。一には生処。この身は臭穢であって、蓮華より生じたものでなく、また薝蔔〈香り高い名花〉より生まれたものでなく、また宝山より出たものでもない。二には種子不浄。この身の種〈精液・経血〉は不浄である。他の妙宝物でもなく、浄白より生じたものでもなく、父母の邪想によって有るものである。三には自性不浄。地・水・火・風の質は、よく変化して不浄となる。海を傾けてこの身を洗ったとしても、香潔にすることなど出来ない。四には自相不浄。種々の不浄物が身の内に充満し、常に流出して留まることはない。あたかも穴の空いた袋に物を入れるようなものである。五には究竟不浄、審らかに諦かに、この身が終に必ず死処に帰すことを観じる。(死を)制御することは出来ず反復することも無く、あたかも恩に背くこと小児のようなものである。
二に受〈vedanā〉は苦であると観じる。意根の受を内受という。五根の受を外受という。六根の受を内外受という。一つの根に順受と違受と不違不順受とがある。順〈好ましい事物〉に於いて楽受を生じ、違〈好ましからざる事物〉に於いて苦受を生じる。不違不順〈興味のない事物〉に於いて不苦不楽受を生じる。楽受は壊苦であり、苦受は苦苦であり、不苦不楽受は行苦である。諸々の受には、麁大であれ微細であれ、苦でないものは無い。
三に心〈citta〉は無常であると観じる。心王〈cintā-rāja〉は(一瞬であっても)留まることなく、その体性は流動する。今日まで存ったとしても、明日までまた保つことは難しい。それはあたかも山水の溜り、斲石〈斧と石. 石を刃物で打つこと〉の光〈火花〉のようなものである。もし時を逸してしまえば、後悔しても無益である。
四に法〈dharma〉は無我であると観ずる。法とは軌則である。これに善法・悪法・無記法がある。人は皆な法に約して〈束ねること〉、我であると考える。我がよく善を行い、悪を行い、無記を行う。(しかしながら、)これ等の法の中に我を求めたとしても、決して不可得である。亀毛〈毛の生えた亀〉や兎角〈角の生えた兎〉は、ただその名字〈概念〉のみあって、実には不可得である。故に(智顗『四念処』では)、「経〈『維摩詰所説経』〉に、「起るも唯だ法の起るなり。滅するも唯だ法の滅なり」と説かれる。但だ是れ陰法の起滅なり。人も無く、我も衆生も壽命も無し」とある。これを無我という。以上は別相念処を説いたものである。
総相念処とは、一つの境〈対象〉を縁〈認識〉ずるのに、総じて四観とする。これを、まさに四句に料簡〈分別〉する。一には境別観別上に別説した通り、二には境別観総、三には境総観別この二つは総相念処の方便である、四には境観倶総、これが総相念処である。もし一つの身念処観を作すには、あるいは二陰〈二蘊〉を総し、乃至、五陰〈五蘊〉を総する。これを境総観別という。受念・心念・法念もまた同様である。
(智顗『四念処』に、)「『阿毘曇』〈法救『雑阿毘曇心論』〉の中で三種の念処が明らかにされている。いわゆる性と共と縁と、三種の外道を対破せり」とある。
(智顗)『四教義』に、「一には性念処。『智論』に云く、性念処は智慧の性である。身を観る智慧は身念処である。受念処・心念処・法念処もまた同様であるが、解釈は不同である。ある者はただ慧数を取って智慧の性として、即ち性念処と云う。南岳師〈湛然〉は、五陰の理性を観じることを性念処という。故に『雑心』〈『雑阿毘曇心論』〉の偈に、「この身は不浄の相である。真実の性は常に定まり、諸々の受および心、法もまた同様である」と説かれる。二つに共念処とは、『智論』に「身を首として、因縁生の道までも、若しくは有漏、若しくは無漏であると観じる」とある。受念処・心念処・法念処もまた同様であるが、解釈は不同である。ある師はこれを解釈して、「善の五陰は、諸々の善の心数〈心所〉の法を共にし、合わせて念処を明かす」と云う。南岳師は、「即ちこれ九想〈九想観〉・背捨〈八背捨〉・勝処〈八勝処〉など、諸々の対治の観門である。正道〈八聖道〉を助けて三解脱〈三解脱門.空解脱・無相解脱・無願解脱〉を開くことから共念処という」と解釈している。故に経〈『治禅病祕要法』〉に、「またまさに空法を念じて、心を修め、不浄を観ずべし。これを諸如来甘露灌頂薬という」と云われる。三つに縁念処。ある師は解釈して「一切の所観の境界を通じて、皆な縁念処観という」と云う。ある者は言う、「十二因縁の境である」と。ある者は言う、「慈悲の所縁の境である」と。南岳師〈湛然〉の注釈は、「仏の教説を詮ずる所の一切陰入界・四諦・事理・名義・言語・音詞・因果体用を縁じ、観達無礙にして能く四弁〈四無礙智〉を生じる。一切の法に於いて、心に礙げられるところ無くして無礙解脱を成就する。それが縁念処観である」とある。小乗を明かし竟る。
もし大乗に依って言えば、四栄〈浄・楽・我・常〉を明かにする。『後分』〈若那跋陀羅訳『大般涅槃経』後分〉に説かれてる通りである。「阿難よ、汝が問う所の通りである。仏涅槃の後は何に依って住すべきかといえば、阿難よ、四念処に依って心を厳にして住せよ。身性の相を観ずるに虚空に同じきを身念処という。受を観るに、内外に在らず、中間に住せずを受念処という。心を観るに、ただ名字のみあり、名字も性も離れたものであるのを心念処という。法を観るに、善法を得ることなく、不善法も得ることはないのを、法念処という」と。『華手経』〈『仏説華手経』〉に、「一切の諸法を皆な念処という。なんとなれば、一切の諸法は常に自性〈無自性空という自性〉に住して能く壊することが無いためである。すなわち、法に即して心、心に即して法、皆な同一性である。その性をどうして能く壊すことがあろうか」と説かれる。
法雲『翻訳名義集』巻四 衆善行法篇第四十八(T29, P119a)
ここで法雲は、四念処(四念住)の原語として「毘跋耶斯」を挙げています。四念処であるならば、[S]catvāri smṛtyupasthāna(あるいは単にsmṛtyupasthāna )である筈ですが、「毘跋耶斯」とはかけ離れ、どう見ても合致しません。
これは、真諦が無著『摂大乗論』巻中を漢訳していく中で敢えて訳さず、ただ音写して「阿娑離娑羅摩多耶 毘跋耶斯者修絺多 離施那者僧柯履多 羅槃底菩提物多摩」と載せている偈文のうち「毘跋耶斯」を、世親がその注釈書『摂大乗論釈』において「謂四念處智慧(謂く四念処の智慧なり)」と解釈しているのを、法雲がおそらく何ら考察を加えることなく、しかも智慧を脱落させ、ただ「四念処」の意であるとして採用したものです。
しかし、法雲はその両書を読んでいたはずですが、そもそもその原語もその意味も知らなかったものと思われ、さらになぜ世親がそう解釈したかもそれほど理解せぬままに記したようです。
なんとなれば、後代に改めて『摂大乗論』を訳した玄奘は、この偈文を「覺不堅爲堅 善住於顛倒 極煩惱所惱 得最上菩提(不堅を覚して堅と為し、善く顛倒に於て住し、極めて煩惱に悩まされば、最上の菩提を得る)」と訳しているためです。そこで、『摂大乗論』には梵本が伝わっていないのですが、これらを併記することにより、その元であった梵文での偈がどのようなものであったか、ある程度予想して復元することが出来ます。
真諦訳】阿娑離娑羅摩多耶 毘跋耶斯者修絺多 離施那者僧柯履多 羅槃底菩提物多摩
玄奘訳】覺不堅爲堅 善住於顛倒 極煩惱所惱 得最上菩提
復梵文】asāre sāramatayaḥ, viparyāse susthitāḥ, kleśanasya susamkliṣṭāḥ, labhatebodhim uttamāṃ.
不確か(な価値無きもの)〈asāra. 不堅〉において確か(な価値あるもの)〈sāra. 堅〉とし、逆様事〈viparyāsa. 顛倒〉において確かに立脚〈susthita. 善住〉して、苦悩〈kleśana. 煩惱〉によってひどく(精神的)痛みを味わう(者は)、最上〈uttamā. 至上〉の菩提〈bodhi. 目覚め・悟り〉を得る。
無着『摂大乗論』(真諦訳:T31, p.121b, 玄奘訳:T31, p.141b)
《復梵文は菲才が仮に復元した梵文。定めて誤りあらん歟》
以上のように、法雲が言った「毘跋耶斯」とは、viparyāsa(処格のviparyāse?)の音写「毘跋耶斯者」に基づいたものであったことがわかります。viparyāsaとは、反転・反対・裏返し、あるいは劣化・(善からの)逸脱を意味し、これを漢訳では一般に顛倒と訳し、実際玄奘はそうしています。そして仏教において顛倒とは一般に、「無常・苦・無我・不浄」なる世界を逆様に「常・楽・我・浄」であると捉える四顛倒が意味されます。
と、ここまでわかれば充分かと言えば、そういう訳にはいかない。何故、世親が「毘跋耶斯者(viparyāsa)」、すなわち顛倒をして「四念処の智慧」と解釈したのかが不明のままであるからです。そもそも、この偈文の言うところをそのまま素直に理解すれば、それ自体が一般的な仏教の理解からして、まるで真反対のことを説いたものとなっています。それで「最上の菩提を得る」とは一体どういうことか。
そこで『摂大乗論釈』における該当部分の出番となります。
論曰。阿娑離 釋曰。謂定。何以故。娑離者有二義。一實二動。阿娑離謂不實不動。不實是文句明了義。不動是祕密義。不動故名定
論曰。娑羅摩多耶 釋曰。名起實心。謂於定起尊重心
論曰。毘跋耶斯者 釋曰。謂四念處智慧。何以故。毘跋耶斯者。亦有二義。一倒謂於無常起常倒等。二翻倒謂於常作無常解。倒是文句明了義翻倒是祕密義
論曰。修絺多 釋曰。謂善住。善住於念處
論曰。離施那者 釋曰。謂正勤。何以故。離施那者亦有二義。一煩惱二苦難。煩惱是文句 明了義。苦難謂正勤是祕密義
論曰。僧柯履多 釋曰。亦有二義。一染汚二疲惓。染汚是文句明了義。疲惓是祕密義。 菩薩爲衆生於生死。長時恒行苦行。是故疲惓如羅睺羅法師言。世尊長時於生死劬勞。但由大悲不由餘事
論曰。羅槃底菩提物多摩 釋曰。羅槃底言得。菩提言覺。物多摩言勝。若取此偈明了義 判文。則成相違。若取祕密義判文。則是正説。欲令衆生依理判文。以理爲依不應依文故説此偈。或有人憍慢輕蔑説者。自不能如理判義。欲破彼慢心故説此偈。是名翻依
《論》:阿娑離〈asāra〉 《釈》:定である。なんとなれば、娑離〈sāra〉には二義あって、一つは実〈堅実.力強さ〉、二つは動〈動き.拡大〉である。阿娑離とは不実不動である。不実は文句明了〈文字通り・見たまま〉の義、不動は祕密の義。不動の故に定という。
《論》:娑羅摩多耶〈sāramatayaḥ〉 《釈》:実心を起こすことである。いわゆる定に於いて尊重心を起こすこと。
《論》:毘跋耶斯者〈viparyāse〉 《釈》:四念処〈四念住〉の智慧である。なんとなれば、毘跋耶斯者にはまた二義ある。一つは倒〈逆様.逆転〉、いわゆる無常に於いて常倒〈常見という顛倒〉等を起こすこと。二つは翻倒〈顛倒をくつがえすこと〉、いわゆる常に於いて無常の解を作すことである。倒は文句明了の義であり、翻倒は祕密の義である。
《論》:修絺多〈susthitāḥ〉 《釈》:よく留まること、念処〈念ずべき対象〉によく留まることである。
《論》:離施那者〈kleśanasya〉 《釈》:正勤である。なんとなれば、離施那〈kleśana〉にはまた二義ある。一つは煩惱、二つは苦難である。煩惱は文句明了の義。苦難は正勤であって、いわゆる祕密の義である。
《論》:僧柯履多〈susamkliṣṭāḥ〉 《釈》:また二義ある。一つは染汚、二つは疲惓である。染汚は文句明了の義。疲惓は祕密の義である。 菩薩は衆生の為に生死に於いて、長時にわたって恒に苦行を行じる。その故に疲惓することは、羅睺羅〈Rāhula〉法師の言葉通りである。「世尊は長時、生死において劬勞す。(それは)ただ大悲に由るものであって、他事に由るものではない」と
《論》:羅槃底菩提物多摩〈labhatebodhimuttamāṃ〉 《釈》:羅槃底〈labhate〉は得〈獲得する・見つける〉の意、菩提〈bodhi〉は覚〈悟り・目覚め〉の意、物多摩〈uttama〉は勝〈最高・第一・主要〉の意である。
もしこの偈を明了の義〈文字通りの意味〉に取って文を判じたならば、(本来の趣旨とは)相違となる。もし祕密の義に取って文を判じたまらば、(本来の趣旨通りの)正説である。衆生をして理に依って文を判じさせようと欲し、理を以って依り処として、文に依ることをしない故にこの偈が説かれた。あるいはある人が憍慢輕蔑にして説いたならば、自ら理の如くにその義を判じることは出来ない。彼の慢心を破ろうと欲するが故にこの偈が説かれたのだ。これを翻依という。
真諦訳 世親『摂大乗論釈』巻六(T31, pp.194c-195a)
なお、この偈文と同一のものがまた無著『大乗荘厳経論』にて言及されており、これを無著は「大乗経偈」であるとしています。「経偈」というからにはいずれか大乗経典に説かれたものであったのでしょう。けれども、菲才はその出典を未だ見出すことが出来ません。
以上のように、真諦が敢えてこの偈文を訳さず音写するに留めたのは、「文句明了の義」すなわち文字通りの意味では仏教として暴言とすら言える誤りとなるからです。ところが、しかし「秘密の義」で理解したならば、それが確かに真であると首肯出来るものとなっているという、正反対の二つの意味があること、ある意味において偈文全体が反語、逆説となっていることに依ります。
このような反語表現、逆説的に人を驚かす表現は後代、支那において生じた禅宗で用いられるような修辞法(レトリック)によく似たものです。必ずしも常にそのような修辞を用いる必要などありません。が、ある場合、ある種の人に対してはむしろ、そうしたことで理解の一大転換、いわばハッとさせる意味での頓悟を生じさせることはある。
そしてこのような表現は、その意味や用法は異なりますが、特に四念住によって退治すべき、世の事物を常・楽・我・浄であると捉える四顛倒を超えた涅槃について、大乗(『涅槃経』等)が常・楽・我・浄であると表現する手法に重なります。それは冒頭示した『翻訳名義集』において言及されている「四枯四栄」についても然り、またその最後に引用される『華手経』の表現も然り。
『摂大乗論釈』の理解がなければ、『翻訳名義集』にてなされている四念住の概説は、その半分も理解できないことになるでしょう。いや、それは少々大げさですが、しかし、これに触れておくことは、それを受け入れるか否かは別としても、大乗の所説を理解する一助になるに違いありません。
西暦3-4世紀頃の印度で著されたと論書、『成実論』という典籍があります。中インド出身の僧、訶梨跋摩〈Harivarman. 師子胄〉(以下、ハリヴァルマン)の手によるものです。ハリヴァルマンの所属部派がいずれであったかは不確かなものの、説一切有部の学系を引いていることはその書の内容から疑いなく、しかしその説に反駁を加えるなど経量部に近接した見解を有していたことが知られます。『成実論』はその上で広く諸部派の見解を示し、さらに大乗(中観)の影響も見受けられるものとなっています。
五世紀初頭、『成実論』が支那に伝わり鳩摩羅什により漢訳されると、その門下によって熱心に研究され広く支那の南北でこれを学ぶものがあり、梁代には一斉を風靡するまでとなっています(その後、三論宗の勃興によって次第に衰退)。
日本には飛鳥時代に伝来して以降、鎌倉期初頭までは、これを専らに研究する成実宗が存在し、元興寺・大安寺・西大寺・法隆寺、そして興福寺や東大寺など南都の諸大寺に伝えられていました。これは今言うような宗派というより、学派と称すべきようなものとして伝えられ、学ばれていたものです。
往古は『成実論』は宗旨宗派など問わず広く学ばれていた書ではありますが、特にいわゆる中観の学派である三論宗および律宗に付属するものとして伝えられていました。なぜ律宗で本書が学ばれたのか。それは、支那(吉蔵)以来、『成実論』は法蔵部(曇無徳部)の論書であると考えられており、律宗が依った『四分律』はその法蔵部の律蔵であるためです。
『成実論』は広く仏教の諸々の教義を明かし、また諸部派や外道の見解を批判的に論述するなど非常に広範な内容をもつものでありますが、その中、止観という観点から三十七菩提分法などを論ずる一章が設けられています。そしてそこに、非常に短い一節によってではありますが、身・受・心・法の四念住(四憶処)を止観のいずれかに分類して理解するということが行われています。
そこで以下、参考になることもあろうかと、ただ当該箇所だけに限らず、その前後も併せて示しておきます。
問曰。佛處處經中告諸比丘。若在阿練若處。若在樹下若在空舍。應念二法。所謂止觀。若一切禪定等法皆悉應念。何故但説止觀。答曰。止名定觀名慧。一切善法從修生者。此二皆攝。及在散心聞思等慧亦此中攝。以此二事能辦道法。所以者何。止能遮 結。觀能斷滅。止如捉草觀如鎌刈。止如掃地觀如除糞。止如揩垢觀如水洗。止如水浸觀如火熟。止如附癰觀如刀決。止如起脈觀如刺血。止制調心觀起沒心。止如灑金觀如火炙。止如牽繩觀如用剗。止如鑷鑷刺觀如剪刀剪髮。止如器鉀觀如兵杖。止如平立觀如發箭。止如服膩觀如投藥。止如調沒觀如印印。止如調金觀如造器。又世間衆生皆墮二邊。若苦 若樂。止能捨樂觀能離苦。又七淨中戒淨心淨名止。餘五名觀。八大人覺中六覺名止。二覺名觀。四憶處中三憶處名止第四憶處名觀。四如意足名止四正勤名觀。五根中四根名止慧根名觀。力亦如是。七覺分中三覺分名止。三覺分名觀。念則倶隨。八道分中三分名戒。二分名止。三分名觀。戒亦屬止。又止能斷貪觀除無明。如經中説。修止則修心。修心則貪受斷。修觀則修慧。修慧則無明斷。又離貪故心得解脱。離無明故慧得解脱。得二解脱更無餘事故但説二。
問:仏は処処の経の中において諸比丘に告げられている、「もしくは阿練若〈araṇ̣ya. 阿蘭若.閑静な林野〉の処にあり、もしくは樹下にあり、もしくは空舍にあっても、まさに二法を念ぜよ。いわゆる止観である」と。(そこで不審であるのが、)もし一切の禅定等の法が、皆な悉くまさに念ずべきものであるならば、どうしてただ(この経説では)「止観」とのみ説かれているのか。
答:止〈śamatha〉とは定〈samādhi〉であり、観〈vipaśyanā〉は慧〈prajñā〉である。一切の善法を修めることにより生じるのは、この二つにすべて包摂される。および散心にある聞・思等の慧〈聞・思・修の三慧〉もまた、この中に包摂される。この二事〈止観〉を以て能く道法を成就するのだ。所以者何、止は能く結〈saṃyojana. 煩惱〉を遮し、観は能く断滅するからである。
止は草を捉えるようなもので、観は鎌で刈るようなもの。止は地を掃くようなもので、観は糞を除くようなもの。止は垢を揩るようなもので、観は水で洗うようなもの。止は水に浸すようなもので、観は火で熱すようなもの。止は癰に(薬を)つけるようなもので、観は刀で削ぎ落とすようなもの。止は脈を起こすようなもので、観は瀉血するようなもの。止は心を制調し、観は没心を起こす。止は金を(薬品で)洗うようなもので、観は火で炙るようなもの。止は繩を牽くようなもので、観は剗〈農機具〉を用いるようなもの。止は鑷で刺を鑷むようなもので、観は剪刀で髮を剪るようなもの。止は器鉀〈甲冑〉のようなもので、観は兵杖のようなもの。止は整列するようなもので、観は箭を発つようなもの。止は膩を服するようなもので、観は薬を投じるようなもの。止は泥をこねるようなもので、観は印を印するようなもの。止は金を調合するようなもので、観は器を造るようなものである。
また、世間の衆生は皆、(常見と断見の)二辺に墮しており、もしくは苦しみ、もしくは楽しむも、止は能く楽を捨て、観は能く苦を離れる。
また、七浄〈戒浄・心浄・見浄・断疑浄・分別浄・行浄・涅槃浄〉の中の戒浄と心浄は止であり、他の五は観である。八大人覚〈少欲・知足・遠離・精進・正念・正定・正慧・不戯論〉の中、(最初の)六覚は止であり、(後の)二覚は観である。四憶処〈四念住に同じ。身念住・受念住・心念住・法念住〉の中、(最初の)三憶処は止であり、第四憶処〈法念住〉は観である。四如意足〈四神足に同じ。欲如意足・精進如意足・心如意足・思惟如意足〉は止であり、四正勤〈律儀断・断断・随護断・修断〉は観である。五根〈信根・精進根・念根・定根・慧根〉の中、(最初の)四根は止であり、慧根は観である。力〈五力.信力・精進力・念力・定力・慧力〉もまた同様である。七覚分〈七覚支.念覚支・択法覚支・精進覚支・喜覚支・軽安覚支・定覚支・捨覚支〉の中の三覚分は止であり、三覚分は観である。念〈念覚支〉は則ち(止観)倶に随う。八道分〈八聖道.正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定〉の中、(正語・正業・正命の)三分は戒であり、(正念・正定の)二分は止であり、(正見・正思惟・正精進の)三分は観である。戒はまた止に属す。
また、止は能く貪を断じ、観は無明を除く。経の中の説の通りである、「止を修せば則ち心を修し、心を修せば則ち貪受が断じられる。観を修せば則ち慧を修し、慧を修せば則ち無明が断じられる」と。また貪を離れることによって心は解脱を得、無明を離れることによって慧は解脱を得る。二解脱を得たならば、更に他事など無いことから、ただ(止と観との)二つを説くのである。
訶梨跋摩『成実論』巻十五 止観品 (T32, p.358a-b)
このようなハリヴァルマンの記述には、前項にて示した有部の『大毘婆沙論』にて言われていた説を含むものであって、確かに有部の影響をそこここに看取できます。しかしながら、と同時にあちこちで独自の見解を表していることも見て取れ、例えば四念住を全面的に「観」の修習であるとしていません。身念住・受念住・心念住は止に属するものであるとし、ただ法念住のみが観に属する修習であるとしています。四念住を総じて観の修習のためのものとしている有部とはこの点、明らかに異なっています。
そこで以下、本稿で言及した部派において、四念住に対する止観という観点からの位置づけがどのようであったかを比較する表を示します。
| - | 分別説部 | 説一切有部 (説因部) |
『成実論』 (経量部?) |
|
|---|---|---|---|---|
| 無畏山寺派(法喜部) | 大寺派(上座部) | |||
| 身念住 | 止観 | 止 | 観 | 止 |
| 受念住 | 止観 | |||
| 心念住 | ||||
| 法念住 | 観 | 観 | 観 | |
これら部派において共通するのは、ただ最後の法念住を観であるとしていた点のみであり、それ以外についてその所見は相違しています。
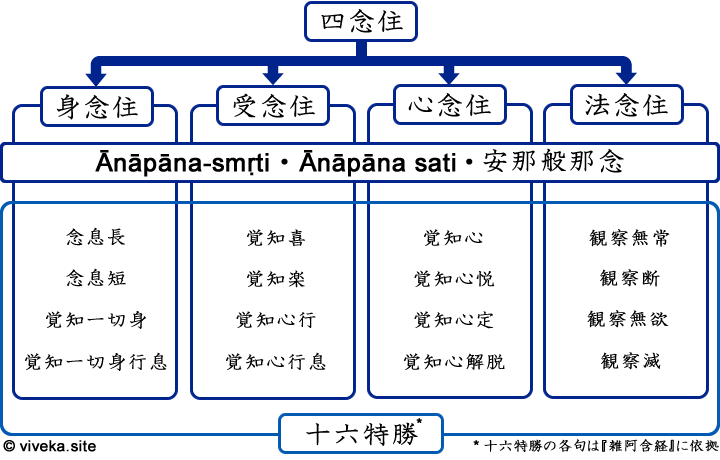
ところで近年、といっても最近はそれが誤りであることを認めざるを得なくなったようで随分おとなしくなり、そう主張する者もめっきり減りましたが、念([S]smṛti / [P]sati)をして「気づきである」などと誤認して言いつつ、さらに戦後のビルマにて生じたVipassanā movement(ヴィパッサナー運動)というべき潮流の世界的流行に乗って、「Vipassanā(観)だけで良い」、「ヴィパッサナーの瞑想こそ修めるべきで、Samatha(止)の瞑想は不要でむしろ時に害毒」などといった見解を奉じる、日本ヴィパッサナー一向宗とでも称すべき一類の人々がありました。
これは日本だけでなく、欧米でより流行した「マインドフルネス」を標榜する人々によく見られたことで、今なお世界中にあります。最近の日本では、むしろその「マインドフルネス」の世間的流行に従来の「ヴィパッサナーこそ」という主張を紛れ込ませ、誤魔化すようになっているようです。
その類の者の中には、「四念住は観の修習法である」・「仏教の瞑想とは純粋なヴィパッサナーだけである」と人にそう教え、実践させているようです。確かに、前項および上に挙げた表でも示したように、有部では四念住を総体的に観の修習であるとしています。しかしながら、その類の者が拠り所としている筈の分別説部大寺派(上座部)の見解としては、四念住がすべてヴィパッサナーであるなどとされていません。特に彼らがよく人にマインドフルネスとして行わせている身念住に属する諸々の修習は、まぎれもない止(samatha)であるとされます。
そしてまた説一切有部の見解についても、別途、特に持息念(安那般那念・Ānāpāna-smṛti)の何たるかを確かに知ったならば、そのような見方は一面的で必ずしも正しいものでないことに気づくに違いありません。
そもそも、教学的な知見は別として、その実践において一概にあるいは一面的に、止と観とをまったく別個のものとして断定し、それぞれ切り離して修めようとする仕方・態度が誤っています。そこで、先に示したように諸部派によってその理解が異なっていることを承知した上であえて言うならば、四念住とはいわゆる止観双運・止観双修の修習です。
これら教学的な理解はしかし、これを実習・実践する始めにはほとんど何の役にも立たない。頭で理解することと、実際に行うこととはまるで違います。最初はとにかく自らの身体をもって坐る、という物理的行為に慣れさせなければならず、また身体が慣れたとしても次は「念住」という、まさに「一定の対象に意識を向けて留めること」に我が精神を慣れさせなければなりません。
身体と心をその方向にあるいは強いて向かわせ、そしてそこに向かうこと、そこでの振る舞い、感じ方に自ら染めていくのです。
四念住とは斯々然々なる言葉であって如是に行うものである、などと頭でタンと理解したところで、いざ坐ってみたところが半刻もまともに修められはしないでしょう。まず身体が坐っていられない。そして靜かに形ばかり坐れたとしても、頭でアレコレ思い巡らせて迷い、疑い、須臾として念(sati)をたもてず、無論三摩地(samādhi)など得られるわけもなく、また法を観ることなど出来ようはずもありません。
これは勉学であれ運動であれ音楽であれ、あらゆる稽古事に同じく言えることでが、なんであれ一つ事を真に為すには一定以上の努力とそれに費やす時間が必要です。何より、事を自ら成就しようとする強い意志、決意がなければいけない。巷間、これを行うに一日ただ十分、二十分でも良いなどと 宣う輩がありますが、世間に迎合しようとした欺瞞の言葉、まやかしです。そんなことは決してない。
仏教とはある種、非常識な教え・思想であります。しかし、このようなことについての常識的な話として、何を学び習うのであれ、一日十分二十分の教習・練習で事足りることなどありはしません。いや、そればかりのことで習得できる事物も世にありはするでしょう。けれども、四念住とは、 生死一大事を解きほごす要。それがどうしてわずかばかりの時と努力で充分果たしうることであるでしょうか。
前述の四念住にまつわるあれこれを頭で知ったとして、それを実際に自ら経験しなければ意味はありません。「自灯明法灯明」という言葉が四念住を修習することを意味する、ということがわかったとして、そこで自らそれを行い経験しなければ、わからないままでいるのと変わりありません。しかし、これを日々修め続け、深めて云ったならば、初めて諸々の先徳の見解の正しいこと、そのありえること、まさに仏陀の遺教が真であることを、その真の功徳の何たるかを、目のあたり自ら観て知るでしょう。そうしてこそ仏教は仏教たりえる。
それを為すか為さぬかは、あくまで自分次第です。仏教をして自ら仏教とし得る人が一人でも現れる、その機と本稿がなれ得れば、なにより欣幸。
下愚沙門覺應 和南