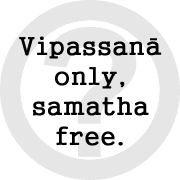
現在、いわば一種の流行として、「Vipassanāこそが仏教の瞑想であり、それをこそのみ修められるべきである」などと、巷間言う人々があります。
ヴィパッサナーとは、漢訳では「観」とされる修習(瞑想)の大きな枠組みです。「観る」といってもただ何事かを観察するというのでなく、それは特に人と事物すなわち一切の、無常・苦・無我という真理なる有り様を洞察することがヴィパッサナーです。
そのようなヴィパッサナーについて、「ヴィパッサナーこそ」など近年の輩が主張する言は果たして真のものか。それは仏教の伝統的立場から言われるものであるのか。結論から言うと、それは真ではない、伝統的仏教の立場からするとまったく適切でない主張です。
しかもそれは比較的最近、第二次大戦後におけるビルマ上座部のMahāsī Sayādaw(Sobhana; 1904-1982)が、ヴィパッサナーのみを修めるべきとする主張とその実践を布教の手段として用いたことを端緒とするものです。あるいはまた、大戦中からビルマに入って成功を収めていた印僑の子で、商売人であったインド系ビルマ人のS.N.Goenka(1924-2013)が、ビルマでなくインドを本拠として脱宗教の手段(ビジネス)として用い、それぞれ支持を得て世界的に有名になったことを嚆矢とするものです。
なお、Sayādawとは、ビルマでの徳高い僧への敬称です(Sayāは教師・先生の意)。また、Mahāsīとは、彼が大東亜戦争の戦乱を避けて後進たちに学問を教授していた寺院の名で、それが後に彼の通称となったものです。それはパーリ語とビルマ語の混成語で、その意味は大太鼓(Big drum)。
今でこそビルマは僧俗共に修禅に打ち込むことが出来る環境を備えたいわゆる「瞑想センター」(ビルマ語でYekta)なるものが極めて数多くあり、多数の外国人も受け入れていることから、瞑想に興味をもつ者の間で国際的によく知られた国となっています。が、このような施設が多く作られ、「ヴィパッサナーこそ」などと言い、特にヴィパッサナーを強調して専らこれを行うといった運動が開始されたのは、実はいずれもいまだ百年にも及ばないごく最近のことです。
いずれにせよ、いま世間に見られるそのような世界的潮流、流行は、二十世紀中頃のビルマから発されたものであることから、ここではもっぱらビルマにおけるその運動の流れを紹介していくこととします。

マハーシ・セヤードウが「ヴィパッサナーこそ」というような運動を始めるに至った経緯・背景は、どのようなものであったか。
それはまず、彼が若く、いまだ特に修禅に励むこともなく、ただビルマ政府が定める僧の国家試験に合格するための修学に励んでいた頃、特に瞑想修行に関しての経典、中でもDīgha Nikāya(長部)に収められているMahāsatipaṭṭhāna sutta(『大念住経』)に興味を覚えていたことが、先ず第一の理由であったといいます。
そして、決定的であったのは、それから幾ばくの時を経て迎えた1938年の当時、南ビルマの古都Thatonに住していた、Mingun Jetavana Sayādaw(Nārada; 1868-1955)という僧侶のもとを訪れ、(おそらく雨安居と衣時の)四ヶ月間という短期ではあるものの、その指導のもと瞑想修行したことであったと云われます。
ビルマでは、有名になった僧侶を呼ぶのにその出身僧院や出身地の名で呼ぶ慣習があるのですが、ミングン・ジェータバナ・セヤードウもやはり、Mingun Jetavana Yektaという瞑想道場の開創者にしてその主であったことから、そのように呼称されます。
(大東亜戦後のビルマ仏教興隆運動の中で輩出された、三蔵の典籍全てを完全に記憶した最初の人として今も大いに称えられる僧Vicittasārābhivamsaもまた、Mingun Sayādawと云われるけれども別人。)

さて、実は、このミングン・セヤードウこそ、現在のビルマ国内のそれこそどこにでも見られるような、いわゆる瞑想センターの原型と言える施設を設立した最初の人です(於:Myou Hla)。それはすなわち、僧俗・老若男女・民族の違いを問わずにその門戸を開いて受け入れ、瞑想法を教授し実践させる、初めての場の創出でした。それは1911年のことです。
そのような場所で、彼はミングン・セヤードウの直接の指導を受け、『大念住経』などに説かれるSatipaṭṭhāna(念住)を特に修めることを専らとする術を説かれたのであると云います。
(念住については、別項「四念住(四念処) ―自灯明法灯明とは 」を参照のこと。)
ミングン・セヤードウが教授していたその術、修習法は、彼が道を探求して彷徨するうち、自らが『念住経』とその注釈書を読み込むことに依って始められたものであったといいます。それは、彼が全く新たに創りだしたというのではなくとも、誰か先徳の指導を仰いで長年修行し、それを継いで始めたものではありませんでした。
そして、ミングン・セヤードウは、『念住経』の中でも特に、地水火風の四大を分別して修習の対象とするDhātumanasikāra、いわゆる界分別観に特に着目しています。中でも彼のそれは、四大(あるいは五大)でいうところの風大、すなわち事物に備わる「動きという性質」を特に取り沙汰したものです。それは先に触れた四念住のうち、最初の身念住の一つとして経の中で説かれている修習です。
ところで、これは一概に言うことも出来ないのですが、界分別観は伝統的に観(ヴィパッサナー)ではなく、むしろ止(サマタ)の範疇に分類されている修習です。ところが、彼はこれをあくまで観であるとし、観の修習として修めていくことになります。
最初、ミングン・セヤードウがこれを世間に説き出した時、たとえば「動き、動き」、「私は坐りつつある、坐っている」、あるいは「お腹の膨らみ、凹み」などと自分の動作に注意を向け続けるという彼の修習についての説法に対し、世間の人々は嘲笑してまったく歯牙にもかけなかったようです。それは、今のビルマでこそ考えられないことです。が、流行などというものはそのようなもの。
彼のその教えは、当初世間の人々から「非常識なもの」・「可笑しなもの」として扱われ、彼は変な僧侶、頭のおかしな僧侶と見なされています。しかし、むしろ常識にとらわれなかった(?)若者のカップルが、彼の説法に興味をもってその瞑想法を修め始め、これに効果のあることを認めたことをきっかけとして、次第に人々から認められていくようになったのでした。
そもそもミングン・セヤードウがそのように『念住経』とその注釈書を読んで、そのように世間に説き出すようになったのは、以下のようなきっかけによるものであったといいます。北ビルマはマンダレー近郊、エーヤワディー河畔にあるミングンの森に、聖者と近隣の人々から噂されていた「或る隠遁僧」が住んでいました。そこで彼は、その僧に会いに往って教えを請います。けれどもその僧は、瞑想についての指導も教えを示すことも一切せず、ただ「なぜ外に教えを求めて探すのか。『念住経』とその注釈書を読め」と言っただけでした。そこで彼は、住房に戻って言われたとおりにそれらを熟読します。その結果、ハタとして着想を得たのがそのような修習法であり、教えでした。
ところで、瞑想センターなどというものが作られるまでのビルマでは、修行とくに修禅というものがどのように行われていたか。
それは、学問だけではなく律を厳持しつつ実践を志す極々一部の僧侶のみが、都会を離れた寺院や森林・洞窟に籠って社会との交わりを出来るだけ避け、ただひたすら自らの修行に励むのみ。そのような僧らが在家信者を指導して修禅させることなど、絶無とまでは断言出来なくとも、ほとんど全く無かったのだといいます。在家信者の仏教との関わり、修行ということについては、信者らはただ僧伽や仏塔に布施をなし、仏前に香華を供えてパリッタを唱え、あるいは仏塔や祠堂、寺院を建立することを専らとするものであったのだといいます。
もっとも、そのような僧たちの傾向は、十九世紀中頃(1871)のビルマの都マンダレー(当時)にて行われた第五結集以前、戒律復興の機運が高まってより、やはり僧は律を厳しく持たなければならないという流れの中で立てられた集団(Shwejin派等)の流れに強く見られたことです。対して既存の集団で、現在に至るまで多数派であるSudhamma派は、そのような動きが起きるまでかなり綱紀が乱れていたということですから、修道以前の問題であったといいます。
なお、トゥダンマ派の綱紀が乱れているのは現在も同様で、おそらくさらに悪くなっていると思えるほどです。しかし、瞑想センターと云われるものの出現以降、その運営に関わっていくのは、第五結集以降の引き締めがあったものの、やはり律についてそれほど厳しい態度を取らぬままにあった、旧来のトゥダンマ派の僧が多かったということです。
瞑想センターなどというものが初めて作られたのは、今から百年余り前の1911年のことで、無論、その当時はイギリス統治時代です。とは言え、そのような時代下であったこともあるでしょう、ミングン・セヤードウに倣って小規模なセンターを設立するものがポツポツと現れ出したものの、それはいまだ小規模な動きに留まるものであったようです。
ここで、本題には全く関せぬことのように思われるかも知れませんが、しかしそれを知ることが必要なことであるため、近世から現代にかけてのビルマ史をごくごく簡略に示していきます。
十六世紀、ポルトガルのビルマ進出によって国情不安となり、続いて十七世紀後半には北からは支那、東からはシャム(タイ)が続々と侵入。そして西の海からはイギリスとフランスの進出とがあって、さらに南部ではモン族による内乱が勃発。それまでのビルマ王朝Toungu朝は、1752年ついに倒れます。そこでモン族を制圧して起こったのがKonbaung朝です。この王朝では、東は逆にシャムに侵入し、これに打ち勝ってアユタヤ朝の滅亡を誘い、西はアラカン王国を攻略。北に対しては支那の侵入を防ぐなど、タウングー朝で弱体化していた国勢を盛んにし、多くの戦が行われています。
しかし十九世紀、イギリスによるインド領有から、東南アジアへの本格的勢力拡大が開始された結果、1824から1886年までの間に三次に渡る戦争が行われます。イギリス=ビルマ戦争です。十九世紀中頃、コンバウン朝は、そのような戦乱の渦中にありながらも、規律の弛緩していた僧伽の引き締め、いわば興律運動を後援し、また国家として第五結集を開催するなどビルマ仏教興隆に努めています。これは、強大な脅威に晒されて国情不安となる中、仏教によって今一度国を一つにまとめ、外患に対抗せんとする手段の一つであったとも見ることが出来ます。
けれども結局、三次イギリス=ビルマ戦争の結果、ビルマは完全に敗れて王は印度に追放され、ついにコンバウン王朝は滅亡。1886年、ついに全国土が併合されてイギリス領インドの一州とされます。ビルマという国は、ここに一旦消滅したのでした。
しかし、1906年に大学生など教育を受けた若者らにより、ビルマの地位向上のためにビルマ仏教青年会が立ち上げられ、1914年には、当時アジアで唯一、西洋に対向する力をつけていた日本に留学経験のあるU Ottamaという僧がこれに参加。彼を中心とするビルマ民族主義運動が展開されます。その結果、1937年には、なんとかインドの一部という立場を脱して、その実際は植民地支配継続ではあったものの、イギリス準自治領の地位にまで格上げされるまでには至ります。
そして、その後まもなく、日本が南方に進出したことにより、その力を全面的に頼ってようやくイギリスを駆逐。日本の協力の下、念願であった独立政権が誕生します。しかしながら、実質的には、日本軍による戦略的統治が背景にあるという、形式的なものに過ぎませんでした。
日本の力によって念願の英国を駆逐を果たし得たものの、これは当時の東南アジアで全般的に言えたことでしょうが、日本政府と軍部による事後の当地の政治への介入方法は全く賢明なものでありませんでした。その故に、それは一種の騙し・裏切りであると、むしろ日本によって教育され力と自信をつけたビルマの若き戦士たちには思われたようです。しかし実際のところ、当時のビルマ人ら自身だけの力でそのまま全く独立した新政府を立ち上げ、運営することなど全然出来なかったでしょう。そこに西欧列強に対抗し得るほどの知見を備えた政治家、優秀な知識層や技術者など存在しませんでした。
結局、日本の諜報機関により海南島(当時は日本領)にて軍事教育を受けたAung Sanら率いるビルマ国民軍は、主力の日本軍、そして合流したChandra Bose率いるインド国民軍らと共に、英印軍・豪軍・米軍・支那軍との戦闘を継続していきます。
ところが1945年3月、戦局すでに日本の敗戦決定的となっていたとき、アウン・サン(ビルマ国民軍)は英軍にたちまち寝返り、混乱のさなか敗走する日本軍の背後から容赦無い攻撃を加えるに至ります。これによって、およそ二万の日本軍将兵が殺傷されたといいます。
(ビルマ戦線における日本軍の戦死者はおよそ十九万人。とてつもない数の将兵が彼の地にて、あるいは彼の地への途上にて無残にも散っています。)
かくて1945年8月、日本の敗戦によって大東亜戦争が終結。これでようやくビルマは真に独立し得るかに見えたものの、たちまち英国が舞い戻って来て再び領有されます。けれども戦後、それまで大英帝国によって当たり前に行われていた、アジアでの植民地支配に対する状況は、戦前とは異なったものへと変化していました。
前世紀中頃より非常なる犠牲を出しつつも、粘り強く続けられていたインド独立運動が、第二次大戦中ますます盛んとなり、ついに最初の独立を果たしたのは隣国インドでした。それは1947年7月のことです。ビルマもその機に乗じて大英帝国との独立交渉を続け、数世紀に及んだ西洋列強からの脅威、英国による植民地支配、そして日本による被征服と、常に他国から脅かされ主権を侵され続けた状態から晴れて脱し得たのは、1948年1月4日でした。
しかし、国内には問題が山積していました。大英帝国領時代、その分断支配政策の一環として行われていた少数民族のキリスト教徒化、また植民地での生産活動の為にインドやネパール(グルカ)から呼び入れられていた、イスラム教徒やヒンドゥー教徒らの人足や商人・技術者たちの定住化などに伴う、人種・民族・宗教間抗争。
そして、英国の愚民化政策による社会構造に由来する様々な、たとえば印僑・華僑による経済支配、いわば搾取に対するビルマ人らの嫌悪そして反発などによる、人種間の深刻な対立。戦後はそれらがいっぺんに噴出するような混乱、例えば英国の手によってキリスト教徒化していた少数民族の一つであるカレン族による内乱勃発と、それらに対する社会不安の著しい増大があったようです。
そのような多難な状況にあって、その人口の七割と大多数を占めるビルマ族のアイデンティティ鼓舞と結束の為という側面が大いにあったのでしょう、ビルマが国家として正式に独立宣言する直前の1947年11月、The Buddha Sāsana Nuggaha Organizationなる組織が設立されます。それは、当時ビルマ随一の大富豪で「Sir」の称号さえ大英帝国から送られていたU Thwinと、独立後の初代首相となるU Nuを始めとする、いずれも一角の社会的地位を持った裕福な九人の在家居士によるものでした。
戦争が終わり、また念願の独立を果たし、大きく時代が動く渦中にあった彼らは、ビルマの歴史・文化の中心的存在、いや、核であるビルマ仏教興隆のため、たとえば経律論の三蔵典籍すべて記憶する僧(Tipiṭakadhara)の輩出を目指したり、独立国家として再び聖典の大編纂会議すなわち第六結集(Caṭṭhasaṅghāyāna)を行うことを目指したりするなど、多岐にわたる興教活動を展開。それら計画は、後に次々とすべて実現されていきます。
その一環として、いわばミングン・セヤードウの試みにならい、僧俗共に瞑想修行が出来る大規模な施設を作り出すことを計画。ウ・トゥウィンは私費を投じて首都ラングーン(現ヤンゴン)のBahan市に、およそ70 acre(約283,000㎡)という広大な土地を購入し、施設を整えていきます。しかし、その適切な指導者を見つけられずにこれを探していたところ、戦争の混乱を避けて北ビルマはマンダレー近郊のサガインにて、後進の学問教育にあたっていたU Sobhana、すなわち後のマハーシ・セヤードウを見出します。
そして1950年、彼を正式に指導者として迎え、ここにMahāsī Sāsana Yeiktha Meditation Centre(マハーシ仏教瞑想センター)を設立。彼により、特にヴィパッサナーを強調した、マハーシ流の着想と方法でもって、といってもそれは前述したミングン・セヤードーから教授されたDhātumanasikāra(界分別観)を本とするものですが、僧俗に教授し実践させるのを布教の手段としていったのでした。