anekajātisaṃsāraṃ, sandhāvissaṃ anibbisaṃ;
gahakāraṃ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṃ.
gahakāraka diṭṭhosi, puna gehaṃ na kāhasi;
sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ;
visaṅkhāragataṃ cittaṃ, taṇhānaṃ khayamajjhagā.
私は幾多の生涯を経巡ってきた、家屋の作り手を探し求めて。あの生涯、この生涯と、生まれることを重ね繰り返すことは苦しい。
家屋の作り手よ 汝(の正体)は見られてしまった。汝が再び家屋を作ることはない。汝のすべての梁は壊れ、屋根は打ち破れた。(我が)心は行〈saṅkhāra〉を離れ、渇愛〈taṇhā〉を滅ぼし尽くしたのだ。
Anekajāti gāthāとは、釈尊が六年間に及ぶ過酷な苦行を経、果たして苦行によって悟りを得ることは出来ないとこれを放棄して、菩提樹下に坐し、ついに無上正等正覚を得られたその直後、まだ夜も開けぬ早朝に初めて発せられたと伝えられるUdānaです。
gāthāとは、いわば詩のことであって、一定の体裁を以て説かれた韻文です。漢訳経典では、偈や頌と訳され、あるいは伽陀・偈陀と音写されています。この偈の場合は、一句八音節で、十句からなっています。
また、Udānaとは、仏陀が何事かに感慨された際、誰からも問われず自ずから発せられた言葉のことです。つまり、それは「問わず語り」であり、いわば「高尚で詩的な独り言」です。これを支那では古来、無問自説、あるいは自説などと漢訳してきました。近年は文献学者らによって、感興偈という新しい訳語が作られ用いられています。なかなか優れた訳です。
この偈が説かれている経は、Kuddhaka Nikāya(小部)所収のDhammapada, Jarāvagga(『法句経』老耗品)で、その第153-154偈です。古代末期から中世の日本でしばしば取り沙汰された漢訳経典の『出曜経』では、これに対応する偈文とその注釈が載せられています。
以觀此屋 更不造舍 梁棧已壞 臺閣摧折以觀此屋者。危脆不牢要當壞敗爲磨滅法。正使安明巨海盡當融爛。更不造舍者。所以然者。以知根原病之所由。更不受形造五陰室。是故説曰以觀此屋更不造舍也。梁棧已壞臺閣摧折者。所以論此者。乃論結使之原本。身壞四大散。萬物不久合。此乃論成道之人。捨形神逝澹然虚空。肢節形體各歸其本。地還歸地水還歸水。火還歸火風還歸風。神逝無爲不復懼畏更來受形。是故説曰梁棧已壞臺閣摧折也心已離行 中間已滅 心爲輕躁 難持難護心已離行者。所謂行者衆結之首。所以群萌沈湮生死者。皆由造行致斯災變。聖人降世精懃自脩。斷諸行本使不復生。是故説曰心已離行也。中間已滅者。三世之法永盡無餘。是故説曰中間已滅也。心爲輕躁者。如佛契經所説。我今説心之本輕躁速疾。一日一夜有九百九十九億念。念念異想造行不同。是故説曰心爲輕躁也。難持難護者。發心之頃造善惡行。念善之心尋響即至間無滯礙。念惡之心如響應聲。欲令守護者未之有也。猶若惡獸之類。虎狼蛇蚖蝮蠍之屬。欲使將護其意。使不行惡者亦未前聞。是故説曰難持難護
この屋を観ずるを以て、更に舍を造らず。梁棧已に壊し、臺閣も摧折す。「この屋を観ずるを以て」とは、脆くて堅牢でない、必ず壊敗するものは磨滅の法なることである。安明〈須弥山〉と巨海であろうとも、すべて融爛〈朽ちて滅びること〉するであろう。「更に舍を造らず」とは、然る所以は、根原なる病の原因を知ったことによって、再び形〈生命〉を受けず、五陰〈五蘊〉という室を造らないことを云う。そのことから、「この屋を観ずるを以て 更に舍を造らず」という。「梁棧已に壊し 臺閣も摧折す」とは、これを論じる所以は、すなわち結使〈煩悩〉の根源を論じたものである。身体が壊れ、四大〈地大・水大・火大・風大〉が散じたならば、もはや万物は久しく合して存在することはない。これはすなわち成道の人〈仏陀・阿羅漢〉を論じたものである。形〈物質〉を捨て神〈精神・意識〉は逝き、澹然虚空にして、手足やその身体は各々その本〈四大〉に帰る。地は地に還り、水は水に還り、火は火に還り、風は風に還る。(仮に仏陀・阿羅漢の境地まで達し無くとも、預流以上の境地に達したならば)神は逝き無為となって、また更に生まれ変わって形を受けたとしても、もはや懼畏することはない。そのことから「梁棧已に壊し 臺閣も摧折す」という。心已に行を離るれば、中間已に滅す。心を軽躁と為す。持ち難く護り難し。「心已に行を離るれば」とは、いわゆる行〈saṅkhāra〉とは諸々の煩悩のはじめである。群萌〈衆生〉が生死に没する所以は、すべて行を造ることに由るのであり、この災変〈迷いの中に流転すること〉を致すのだ。聖人が世に降って努力して勤め、諸行の本を断ち切って再び生ぜさせない。そのことから、「心已に行を離るれば」という。「中間已に滅す」とは、三世の法が永く尽きて余り無いこと。そのことから、「中間已に滅す」と説かれている。「心を軽躁と為す」とは、仏の契経〈経典〉に、「我、いま心の本の軽躁速疾なるを説かんに、一日一夜に九百九十九億念有り〈一念=0.0086秒〉。念念、想を異にし、造行同じからず」と説かれているとおりである。そのことから、「心を軽躁〈極めて早く動くもの〉と為す」という。「持ち難く護り難し」とは、発心の頃も善悪の行を造り、善を念う心は、重ねて響いて一瞬として滞ることはない。悪を念う心は、響きが音に応じるようなものである。これを守護しようとする者など未だかつて無い。あたかも悪しき獣の類、虎・狼・蛇・蚖・蝮・蠍の属のようにして、その意を守護し、悪を行ぜさせないようとしすることも、また未だかつて聞いたことがない。そのことから、「持ち難く護り難し」という。
『出曜経』巻廿八(T4, p.759b-c)
このように漢訳仏典で同偈が収録され、またその注釈も併せて伝えられおり、今なお往古の理解に触れることが出来るものとなっています。
とはいえ、Dhammapadaと『出曜経』とでは、テーマは同じであっても、その原文は比較的異なっていたものであったようです。そしてその本文は、これは漢訳であるからということもあるのでしょうが、さらに抽象的で一見して理解し得るものではありません。それがサンスクリットであれパーリ語であれ、やはり釈尊が話されていたインド語に属する言語、あるいはそれに準じた言葉から直接、現代日本語に訳するのに如くものではありません。
なお、最初の一偈における、パーリ文の中でいわれている「家(gaha)」とは、色・受・想・行・識の五蘊、すなわち「身体と心」を意味するものである、と分別説部の伝統において注釈されています。それに対し、この『出曜経』の最初の一偈では、「屋」が万法(あらゆる存在・事象)であり、「舎」が生命であるとされ、注釈において「室」が五蘊であるとされています。この一偈については両者の意味はほとんど同じように解されてます。しかし、次の偈文については、その意味合いが両者ずいぶん異なっています。
さて、Anekajātisaṃsāraṃ、直訳すると「一つきりではない人生を経巡って」となる言葉から始まることから、Anekajāti gāthā(一度きりでない人生の偈)と言われます。しかし、それを直訳したような訳では気品が感じられないので、ここではこれを且く「生死流転偈」と訳し題しています。
この偈が発せられたのは、南方に伝わり繁栄した分別説部(上座部)の伝承によれば満月の旧暦5月10日の明け方のことです。釈尊は、それまで法を求めて得られず、数知れず生死流転を繰り返すもついにその日、マガダ国ガヤー〈現インド・ビハール州ブッダガヤー〉の菩提樹のもと、Buddha(仏陀)すなわち「目覚めた人」となられました。
多くの人生を生まれ変わり死に変わりしてきたことをその前日の早晩、宿命智を得たことによって明らかに知られ、深夜に天眼智を、そしてあくる朝には漏尽智を得て仏陀となられ、のち初めて発せられた深い感慨の言葉、それが「Anekajātisaṃsāraṃ」と始まるこの偈文です。
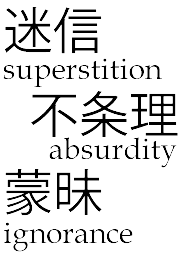
伝統的にいうところの生死流転、今世間一般で謂うところの輪廻転生は、仏教が大前提とする世界観です。
それは、少々それが現実とかけ離れていても許される程のものでなく、仏陀の教えの核心に深く関わる「真実なる、世界のそして生きとし生けるものの苦なるあり方」です。輪廻転生を否定しては仏教の説く倫理・道徳も、修行もそしてその結果としての涅槃も何も、究極的には意味がなくなってしまいます。
とはいえ、これはなにも自然科学がある程度発達した近現代に始まったものでなく、「輪廻など世迷い言に過ぎない」・「転生など如何にしても認識することの出来ない、すなわち愚人の迷信、狂者の妄説」、「この世には事物を構成するところの原子ならびにこれを支配する法則のみしか存在していない。一生命など死んでしまえばそれで全ておしまい。いや、生命などそもそも幻の如きものである。世界はただモノが巡り続けるのみであって、輪廻転生などありえない」などとする人々が古来あります。
むしろインドなどは、現代の社会一般の人にしばしば見られる「生ぬるい半ちく唯物論者」とは異なって、筋金入りの唯物論者が仏陀ご在世の往古からあり、どうやら逆に現代には見られなくなったようですが、近代にまで存在し行われていました。その代表的なものがLokāyata(順世外道)、あるいはBārhaspatya(唯物論者)などの、いわゆるCārvākaです。
また古代ギリシャにおいても、釈尊とほとんど時を同じくして現れていた原子論者LeukipposやDemokritosなどが唯物論を説いています。そして、これに根ざしたEpikourosは、先行するAristipposとはまったく異なる享楽主義を説いて世の尊敬を集めていたといいます。
後代、暗黒の中世を乗り越えたヨーロッパでは、ギリシャのそれを引き継ぎ、イギリスのR. BaconやT. Hobbes、そしてJ. Rockら、次にフランスのD. DiderotやLa Mettrie、さらにドイツからはJ. Moleschottなど、多くの場合科学者を兼ねていた諸々の哲学者によって、それぞれの立場から唯物論は主張され初めています。宗教を初めとする権威主義などいかなる呪縛からも脱却し自由となって、理性と科学的知識とのみによってこそ、人は生きるべきだとする啓蒙思想(the Enlightenment)です。
また近代には、K. Marx、そしてF. Engels によって共産主義が宣揚され、弁証法的唯物論ならびに史的唯物論が展開していきます。共産主義の掲げる理想は一見、これ以上なく素晴らしいものに思えるものであったようです。しかし、現実はその真逆であって、多くの恐るべき共産主義国家の誕生を見、そこに属する人々はまさに生き地獄を経験することになっています。また結果として二十世紀の世界は大きく二つに分断されるにまで至り、その影響は二十一世紀の今なお根強く残っています。そしてまた、未だそれを至上の思想であり国家のあり方であると信奉する残党が、その恐るべき独裁と残虐を内に秘めながら民主の皮を被って公然と今もあります。
さらに現代では、自然科学の発達に伴い、物理学・化学・医学など種々の立場から言われる「世界に神などといった存在を認め得る事象は無い」、「精神・意識なるものは所詮、大脳の一機能に過ぎない」という(今のところ)仮説が、大勢の承認を得られるに至っています。「いまだ多く解明されない謎は残されているものの、モノ以外の何ものかが存在していることは観察されえず、故に認められない」という実証的立場が、いわば科学的唯物論を導き出しています。そして、それがまた様々な実証主義を産み出しています。
時代の趨勢としては、そのような態度を持つことが知的に良しとされるものですが、しかし、世界の大勢としては、そのような態度を持つ者が多数を占めるには至っていません。けれども、いわゆる現代の先進国における人には、概ね自然科学的態度や啓蒙思想に基づいた教育を受けてきた結果として、これは必然的にでしょうが、科学的に承認され得ない概念や思想内容は総じて迷信であり、これを保つものはいわば知的に劣った者、前時代的であると考える人が、比較的多くあるようです。
このようなことから、日本はもとより西洋には、仏教の説く輪廻転生について「仏陀がまさしく説いたと科学的文献学的に推論され、一定の確度を持っている言葉の数々の内容は、誠に首肯し得る人道主義的英知・理性に満ちたものである。けれども、輪廻転生などは科学的に観察され得ないし、実証し得ない。故に到底認められないし、受け入れられない」と考える人々があります。
なるほど、それは確かにそうでしょう。そう思うのが現代における科学的教育の結果として、当たり前の感覚であり態度であると思います。実際、啓蒙思想は多くの恩恵を人類にもたらし、知ってか知らずか、現代の我々すべてはその利益を享受し続けています。しかしながらそれは、やはりこれも現代だからこそかく考えるというようなものではなく、人間である以上ある意味当たり前に持っている思考・感覚であると、仏教では考えています。業や輪廻と聞いて、それを疑問に思わないほうがむしろおかしい。

例えば、これは実に極端な例ですが、「私は前世、遥か彼方M78星雲のとある惑星で修行してた者ですが、このたび衆生救済の誓願を立てたことからここ地球に転生してきました、ジョワッ!」、あるいは「余と汝とには前世からの分かちがたい絆があるのだ。さあ、いざ宿世からの思いを今こそ遂げようぞ」、はてまたは「あなたは気づいていないかも知れないが、あなたは前世で私の母だった。私はずっと母、そう、まさにあなたをこそ探し続けていました。ママァ!」などと言われて、「…は?」などと思わず聞き返してしまう、いや、返す言葉を全く失ってしまうのは、何も輪廻を信じていない人だけではありますまい。
鳩が豆鉄砲を食らった顔、というのは、このような場面に出くわしたときに現れる表情に違いない。輪廻を信ずる、と言ってもこういう輩は例外としておくべきで、困った人の部類に入るものでしょう。「お花畑組」、「お星様組」とでも申しましょうか。そのような人には違う意味での、しかも終わらない春、が訪れてしまっているようです。