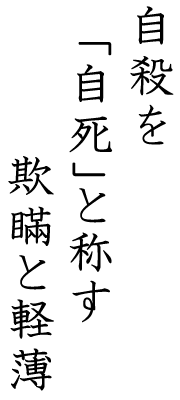
では自殺について、仏教としての見解は如何。端的に、結論から先に言えば、仏教では「条件付きで自殺は可」とされます。
仏教は輪廻からの解脱を果たした人、すなわち仏陀もしくは阿羅漢、あるいは我が命を投げ出すほどの自己犠牲をする菩薩についてのみ、自殺することを許しています。故に誰でも死にたくば死ねば良いでしょう、悟りを確かに得た後ならば。あるいは、そのような機会に合うことは実にまれとなるでしょうが、人や社会のために我が生命を捧げるという場合があるならば。
さもなければ、無闇に自殺することはむしろ自他をさらに多大に苦しめる結果を引き起こすことになり不毛である。故に軽はずみに死んではいけない、と仏教では考えます。そもそも、「全身全霊で死を望む人」など、決して存在しません。それは決して存在し得ない。そのような人がもしいたとしたら、その人はわざわざ自らを強いて「殺す」必要などなく、勝手に身体が死を迎えるでしょう。
我々の身体は、その隅々にいたるまで、我々が生きるのを出来うる限り維持しようとする機能で満ち溢れ、最大限その機能を発揮せんとして日夜休み無く働き続けています。
近年、自殺でなく自死という語、それは近世において現れ、極一部で用いられていた言葉ではありますが、それをこそ使いたがる一類の人々があります。しかし、もし自死すなわち「自ずから死ぬ」・「自ら死ぬ」というならば、病死あるいは老衰による死に対してこそ言うべきもの。もし、仮にある者が「全身全霊をもって死にたい」のであれば、そのものの身体は何もせずとも勝手にその活動を止め、死ぬでしょう。にも関わらず、自らの身体も、実はその精神も元来懸命に生きようとしているのを強制的に自ら絶って捨てることは、まさに「自ら殺す」あるいは「自ら害する」というに相応しいものです。これ以上に適当な言葉はありません。
余談ながら、自と死を組み合わせた漢字「臰」は「くさい」・「におう」・「かぐ」と訓じられるものであって、悪い噂・不芳を意味する語です。
その理由が何であれ自殺者に対する偏見、あるいはその家族に対するいわれのない誹謗中傷が、実はその影で多く生じていることに対する緩和策、いわば配慮の一つとして、そのような言葉狩り、レッテルの張替えを行おうとしているのだ、ということも耳にします。しかし、それはとんだお門違い、過剰で不合理な配慮というべきことです。ただ言葉を少しばかり変えてみたところで、そのような苦しみの死を迎えた者とその家族に対して鞭打つ愚昧にして卑賤な人々等の偏見や行動が変わるわけがない。
それはあたかも「交通安全」と書いた安っぽく醜い幟旗を道端にいくつも指したところで、交通安全になることなど決して無いようなもの。その上ただ日本の街がさらに醜く、視覚的に汚くなるだけのようなものです。
それを自死なる語に代替させ一般化、標準化しようと運動する者らのなんと愚かなことか。自死という語を好んで使いたがる人輩は、もはや漢文どころか漢字の意味をすらわからぬようになったかのようです。あるいは障害者を「障がい者」などと表記したがるのと同じ、実はまるで意味のない、まったく無駄で過剰な配慮を他に強制しようとする一群の者らと同じ感覚でそうせよとしているのでしょう。
おそらく、自死という語を好む人々は、ただ西洋の風潮をただ模倣して安楽死も人の権利、基本的人権であると法的に認めろと叫びだすことでしょう。もっとも、前述したように、人の理性や知性を唯物論的に捉え、突き詰めていった場合、そのような意見が出ることはある意味必然、当然であります。
けれども仏教はそう考えることはありません。悟りを得ない限り、私という意識は死を超えてなお相続し続け、幾多の苦しみを受け続けます。それが、仏教通じての見解です。心が解脱し、智慧の解脱をみない限り、たとえば天に唾すれば自らに振りかかるように、自らが作り出した苦しみを無闇に被り続けて果てることがない。それを今、この世において止めようとしないかぎり、我が苦しみの連環は止むことはありません。
したがって、その意義を認める限りにおいて、この世の生は尊い。ただ「生きること」自体に価値や意味などない、それはただ不毛な苦しみでしか無い、そう仏教では考えるのです。
「いやいやいやいや、輪廻などという虚妄を前提としなくとも、死んでしまえば全ておしまいであるからこそ、この生が尊いのではないか」
そう、そのように言う人ももちろんあるでしょう。「終わりがあるからこそ、それは輝く」と。そのような思想を持っている人こそ、今の日本人(に限ったことではないでしょうが)には多いように思われます。ならばエピクロスのように、「人は神だの来世だのというものへの恐怖心から脱却し、少欲知足を旨として精神的平静と充足を探求すべし」とする、快楽主義者となる道もあるでしょう。

「仏教が好きだ、キリスト教など一神教に比せば仏教には大変好感を持ちえる。そこでしかし、その仏教からどうしても自分が気に食わない『迷信に過ぎない』業や輪廻という教え・概念は取り除きたい。けれども道徳の根拠を失うのは遺憾である」と考える人々は、わざわざ仏教に執着して無輪廻派とでも云うべきものを形成しようとするのではなく、エピクロス主義を学び、一先ず彼に従ってみるのが良いのではないでしょうか。
ああ、かく言ったならば、「暴言だ!すべての者を救わんとするのが宗教というものであろう。宗教者としてあるまじき言だ!」などという批判が投げつけられるかもしれません。まず、そのような宗教一般に対する理解が全く誤っています。そして、物事には時機というものがあり、人には能力の差というものがある。仏教、特に大乗において「衆生愚蒙ならば、強いて度すべからず。真言行者方便して引進せよ」〈『菩提心論』〉とは云うものの、「縁なき衆生は度し難し」との巷間言われる言葉もまた真実。
実際、エピクロスの主義主張、たとえば彼の言ったataraxiaという境地は、「そのような人々が思い思いに想い描いている涅槃」のように思われます。伝えによれば、エピクロスは優れた尊敬すべき哲人、いわば真のバラモンであったに違いない。古代ギリシャの哲人たちの思想は、常にその人生生活における実践をともなってこそだったものであり、多くの点で仏教との共通点を見出し得ます。しかしもちろん、そこに多くの似通った点が見られるとしても、仏教とエピクロス主義とは全然違うものです。
けれども、そう言えばたちまち「そら見たことか。仏教から輪廻だの業だのという蒙昧の概念を取り除き、人生はこの世限りで死んでしまえば全てオシマイだとしても、そのギリシャのエピなんとかという哲人の主張のごとく、仏教が無価値なものなどにはならないであろう。仏教は理性・知性を尊ぶ合理的な教えとして、依然として意義ある、人類に貢献するものとしてあり得るのだ」という人もあるでしょう。いや、それはもう仏教ではなく、むしろエピクロス主義です。しかし確かに、輪廻や業の思想を受け入れずとも、仏教の部分部分には、数多くの人や社会に有益な事柄があります。

故に、これを実用主義(pragmatism)的に用いることは充分可能で、実は特にアメリカの教育や心理学の領域では、むろん東洋や仏教というステッカーはべりっと剥がされて、すでに行われています。この点を西洋と比較した場合、いつものことというべきか、日本はこの種のことは全く遅れています。しかしながら、アメリカや欧州で実用され成功しているからといって、日本で同じことが出来るかといえば多くの場合そうではありません。大抵、その形だけを猿真似し、ただ何事かやっているような気になる一団を作り出すのみ。
さて、エピクロスが立脚したデモクリトスの唯物論を、なんとか物理学や脳科学に挿げ替えさえすれば、それは彼らの思想、好みにきっと適合することでしょう。日本の有智有能なる人があってこれを行えば、イギリスやアメリカで行われたそれとはまた違ったものが生み出されるかもしれません。いや、エピクロスや唯物論云々など全然関しませんが、それはすでに江戸期の禅僧によって果たされていると言える。
しかし、何故かそのような人々には、自分が「唯物論者」・「虚無主義者」・「快楽主義者」あるいは「Anarchist」と呼ばれるのを好まない者が多いようで、なんとも世の中は色々難しいことです。自分がそうであるならば、堂々と自信を持ってそう言えば良いのでしょうに。
他人からどのようなものであれ「枠」に嵌められて自分が眺められるのを好まず、そして自身の主義主張を開陳することが躊躇われるような日本社会一般の風潮ということがあるのでしょう。
また一方、仏教に属する側にもそれと似たような人々があり、(自分が信ずるところの)仏教を宗教と見られたくない者があります。言っていることが国家神道を唱導して「国家神道とは宗教などという低級なものではないのだ」とした当時の日本政府とまるで変わらないような欺瞞、あるいは仏教はそもそも科学や哲学そのものであったかのようなことを社会に対しては吹聴しつつ、裏では多くの努力を払って宗教法人を取得し、盛んに宗教活動に勤しんでいる輩があるなど様々です。
仏教が宗教では決してなく科学だなどと言うのであれば、宗教法人などではなく、何故に(宗教法人を背景にもつ仏教系大学などではない)大学など学校法人あるいはたんなる研究所をこそ設立し、宗教活動ではなく、純然たる学究活動を専らにしないかと不思議に思えてなりません。いや、それなら最初から旧帝大のいずれか研究室に入って精を出せ、ということになるでしょう。
仏教を哲学とのみ見たがる人も多くありますが、仏教に哲学的側面はあっても哲学ではありません。

仏陀の滅後、たしかに仏弟子たちは仏陀の法に対する「何故か」・「何か」という問に対する回答を様々に求め、それぞれに出して諸派を形成しました。
結果、多くの部分ですでに(絶対的)回答が出されています。その故に、誤解を恐れずに言えば、仏教という大枠においては、「何故か」という問いから様々に展開し、あるいはその回答を覆すほどの余地はもはやありません。仮に覆したとしたら、それはもはや「仏教」ではありません。ことさらに「~でなければならない」と思っているからかく言うわけではないのですが、そう、仏教は宗教です。
ダライ・ラマ十四世法王がよく語っているように、仏教という宗教には、大きく言えば三つの側面・要素があります。いわゆる宗教(信仰・呪術・救済)的側面・哲学的側面・心理学的側面です。それらのうち一側面だけをもって「これが本当の仏教である」などとすると、木を見て森を見ざるが如き、群盲象を評するが如きものとなるでしょう。おっと、これはいけません、また横道にそれてしまったようです。
しかしさて、現実としては、自身の思想信条がいかなるものかを考える人などごく少数。社会に出ればそんな時間など無いし、そんなことを考えるのは思春期から大学生ぐらいの間にとっくに済ませた(ような気持ちでいる)。「後悔はとっくに済ませた。あとはそれをどうやって忘れるかだ」といったところでしょうか。
多くは「なんとなくそう思う」、「そう考えることが自然だと思うから」、「何故だか知らないが私がそう考えるからそう言うのだ」という如きものであって、しかも多くの場面において、社会での多数の意見や自身の周囲の見解にくるくると変化させられるのが、いたって普通というもの。事大主義というのですが、それを。マスコミや政治家など、人がそのようなものであることをよくよく熟知している。
嗚呼、実に人は多面的であって社会は矛盾に満ちて奥深く、ある意味においては、まこと面白く感ぜられるものです。とはいえ、それは他人事ではなく、自分はまさにその人であり社会の一員である以上は当事者であって、ただ笑い事で済ますことは出来ません。
一点だけと言いつつ、また要らぬ余談ばかりで長くなりました。輪廻を信じていても、一番重要なのは現世におけるこの人生です。来世ではありません。来世で「こそ」救われよ、などという教えを仏陀は説かれはしなかった。
また、この現世において「生きることは苦しい」、「人生は苦だ」などとオウムのように繰り返し、ある意味苦しみに酔っても仕方ありません。本当に苦しみの只中にある者には、苦しいなどという言葉すら発することも出来ず、泣くことも叶わないでしょう。苦しい苦しいとの題目を無闇に唱え続け得る間は、「饅頭怖い」にすぐ成り得る程度のものと言えるかもしれません。
しかし、…しかしやはり、まことに人生は苦しく、どこまでも悩ましいものです。私という矛盾しきった存在、この身勝手で薄汚れた自分、時として全く言動不一致となって自ら呆れるばかりの愚かな私というものと死ぬまで、どこまでも付き合わなければならないことを知りつつ、もう無理か、もう駄目だなどと思いつつそれでも生きている。いつかわからぬとも、結局は絶対に死んでしまうという恐るべき事実を知りつつ、七転八倒しながらも生きている。いずれ死んだらそれですべて終わりならば、むしろどんなに良いであろうか。いや、このような心情からも啓蒙思想は生み出されてきたのでしょう。
無常であるが故に人は変わり得、無我であるからこそ私はかく有り、我が善悪業によってこそ私は私自身を救いもしえるし地獄にたたき落とせもし得る。そのように私は確信しています。しかしながら、その体験、内容自体は他者に各云々と客観的に開陳し、さらに共有できるものではないために、これはまったく私一人の内なるものです。
この信は、初め我が人生における諸々の苦しみ、自らの愚かさとそれに基づく諸悪行がもたらして生じたもの、ある意味極めて独りよがりで自分勝手なものです。けれども今は、それをただいわゆる「信仰する」というのではなく、自分自身によって確認し得、その恐るべきことを確認してきたことであります。
人は、その人生が苦しみであること、仏陀の教えに従ってそれを根本的なところで知れば知るほど、人生は少しずつ楽なものとなっていくことを、自らのうちに確認しうるでしょう。日々の弛まない努力によって。
仏陀が成道されて初めて発せられたといわれる、この生死流転偈。それは、数えきれないほど多くの人生をさまざまに繰り返してきたという実感、多く苦しみを重ねてきたがついにその苦しみの終焉に至った、涅槃を得たとのまことに深い感慨があってこそ発せられた、静かで揺るがぬ、深い喜びに満ちたものです。
Ñāṇajoti