
伝統的に、その生において解脱に至り、死を迎えるまでを有余依涅槃と言います。
何故に「余依が有る涅槃」なのかと言えば、いまだ業果としての身体(六根)そして命(命根=前世の業によって定まった寿命)が共にあるからです。そこには、いまだ老病死という果、肉体的苦を受ける余地がある。これに対し、終に命根盡き死を迎えることを、無余依涅槃と言います。声聞乗における究極の解脱です。すなわち、声聞においては、仏陀もしくは辟支仏(独覚)あるいは阿羅漢となって死を迎えることが、最高にして究極の平安とされます。
そうでなく、人が解脱に至らず、あるいは聖者の境涯にまで至らずして、ただ老いや病い、あるいは事故や自殺・他殺などによって死を迎えても、それは平安でもなんでもなく、新たな苦しみの門出でしかありません。たとい一生何事もなく平穏無事に、衣食住に差し障りなく、そしてほぼ健康にその生を全うしたとしても、それはそれでめでたいことであるとは言います。が、しかしそれだけでは詮無くまた虚しいことである、と仏教では説きます。そしてそのようなあり方は、ほとんど全ての人、いや、鳥獣などと同様の生死の様相であると、仏教では見ます。
話は変わって、ここからまったくの余談になります。これは大変面白いことに、東南アジアの仏教諸国において僧侶に対し「枯れ木の様だ」などと言うのは最高の褒め言葉の一つとなっています。対して支那から日本では、「(悟りを開いたなどと言って)枯れ木の様になった僧侶など無価値」とする、これは禅の祖師らの言葉に基づいたものでもあるのでしょうが、支配的思想があり、それは全く対照的です。
同じく大乗を信奉するチベットでも、「枯れ木」は蔑みでこそありませんが、褒め言葉でもありません。チベットでは一部に、これは往時の禅宗でもそのような傾向があったのと同様、エキセントリックな僧をして何らか悉地を得た人だと見なすことがよくあります。
どのような譬えをもって賞賛の言葉としているかは、それぞれの涅槃観あるいは僧侶観というべきものの違いを端的に表していると言って良いでしょう。何故に南方において枯れ木のようになるのが良いとされるのかは、以上に見てきた十二縁起に基づいたものです。
すでに先に述べたことの繰り返しとなりますが、ここでもう一度おさらいです。
身体が存在する以上、そしてその身体が五体満足でなにも機能不全がなければ、我々の五感そして心は正常に働いて様々の外界の刺激を感受します。これを仏教では受(vedanā)といいます。十二縁起の第七、受です。仏教では、その受には大きく分けて楽(sukha)・苦(dukkha)・不苦不楽(adukkhamasukha)の三受があるとされます。あるいは、楽と苦から精神的なものを別して喜(somanassa)と憂(domanassa)とし、これを加えて五受があるとされます。
人が解脱するためには、縁起が順に生起して無限の連環を繰り返すのを止めるためには、自らが受けるところの感覚が楽であろうが苦であろうが、これをただ「受け止め」て頓着しない事。すなわち、いかなるものであれ感受したものに対して愛着・嫌悪いずれもしないよう、少しづつ訓練してくしかありません。
人間は習慣性の動物、仏教的に言えば(自分で発生させた)業の暴風にエイエイと、行という爆流にグイグイと押され流されるように生きる存在ですので、いきなりこれを完全に止めることはほとんど不可能です。故に自分の行いをさまざまに制約し、漸次に条件付けしていきます。具体的にこれは、先ず戒を持ち、そして瑜伽の修習によってなしていきます。けれども、四六時中瞑想するわけには人間いきません。そこで日々、我が心身の動きに注意を払って「よく気をつける」ことが最も肝要となってくるわけです。その訓練、それを修行というのですが、その方法は幾多も用意されています。その果てにあるのが解脱です。
さて、何故に南方で枯れ木が一つの理想とされるのかは、十二縁起の順観で説かれる「受→渇愛→取→有→生→老死」という過程に関係があります。なんであれ自分の好き嫌いを問わず感受したものに対して、さらに欲して求めよう衝動を起こさず、また執着しないことが解脱の要件であるためです。この生において焦点を当てるべきは渇愛の滅で、それは取りも直さず無明の滅に直結します。故に釈尊は、時として無明から始まる十二縁起を説かれず、渇愛から始めるいくつかの縁起支のみを説かれることもあった、というのが伝統的な見解です。
このようなことから、日常(六根がその対象に触れ、苦・楽・捨さまざまに感受が起こりつづけている)→平静である(あらゆる感受したものに対しての渇愛・取を制し抑えている)⇒無表情・無動作・無反応・無口である(有・業を制している)⇒修行ができて徳がある(常日頃よく気を付けている!)、という思考図式が、彼らの中で出来上がります。
先に受には三つあり、そのうちには不苦不楽すなわち「感受したものに何ら関心が払われないこと」があると述べましたが、これをまた別に捨(Upekkhā)とも言います。それはまた「無関心」を意味する言葉です。仏教は感受したものがなんであれ、ただ不苦不楽のみの不感症となれなどと説く教えではありません。誰であれ、感受したものには間違いなく楽・苦・不苦不楽があります。好ましいものは好ましい、好ましくないものは好ましくない、として全く問題ない。
例えば比丘が食事の供養を受けたとして、それについて「美味しい」・「不味い」・「味がない」という感覚・感想があってしかるべきです。気持ちよければ気持よくてよく、苦しければ苦しくてよく、喜ばしければ喜んでよく、苦々しければ苦々しくしてよい。ただし、そのような感覚を、感情に転化して増幅する必要はなく、またすべきではありません。そこで文字通り「受け止める」。それを動機としてさらに欲求せずあるいは嫌悪せず、これに執着しないこと、受から愛そして取という過程をとらないことこそが、最も肝要な点です。
そして、そのような態度は、先程挙げた三受あるいは五受のうちの捨とは異なるものです。分別説部では、そのような心の状態を中捨(tatra-majjhattatā)として、心所の中に挙げています。また説一切有部では、受のそれとは別物の心所たる捨(upekṣā)として挙げています。

しかし、これは結果的にですが彼らの社会においては、自分が感受しているものが楽であれ苦であれ、これを一切おくびにも出さないことこそが徳とされ、むしろブスッとしたりシラ~ッとしたりするような無表情・無感動的態度をとることが賞賛されるにいたっています。
渇愛を起こさなければ取以下から連なる苦が滅びる、という十二縁起の逆観の教えに従った一つの結果と言えるでしょう。それは、その背景にある思想が別であるとしても、結果として古代ギリシャのストア派が理想として説いたApatheia、すなわち超然として何事にも動ぜず無感動である境地・態度と同様のものです。
いずれにせよ、上に述べたような理由から、南方ではいわば「枯れ木」になることが一つの理想像とされ、賞賛の対象となっているのは事実です。実際、タイやカンボジア、ラオスの僧侶らは在家信者の前にあるときや写真を取る際に、枯れ木的ポーズを取る者が多くあります。しかし、そのほとんどが「良く気を付けている」からそうしている、自然にそうなっているというのではなく、あくまでポーズをとっているに過ぎません。故に、下手をするとただの呆けた、悪い意味で「空っぽ」の表情となるか、無表情・無反応であろうとした結果、穏やかなどと言うよりむしろ、傲岸不遜な態度にしか見えないものとなってしまっていることがあります。
なんでも長短あるものですが、これは、伝えられるものをただ丸覚えし、とにかくコピーさえしていればそれでよいとする分別説部一般の価値観が、思考停止して度の過ぎた形式主義・教条主義となって表れている点の一つです。これは彼ら個人が思い思いにそうしているのでなく、(「何故か」という理由を教えられること無しに)そのようにしなければならない、僧侶というものはそういうものなのだ、と教育され、沙弥から出家している者ならばなおさら、小さい頃から訓練され、もはや(その目的や内容と関しない)習慣となっていることによります。
そしてそれはまた、それら各国の在家信者たちが、そのような態度をとる僧侶をして「若いのになんと穏やかであろうか」、「なんと平和的な生活でしょう」、「俗世に住まう者とは次元の異なる、静かで尊い生活である」などとむしろ賞賛する、社会一般の傾向も手伝っています。
また一点、これも重要な点なのですが、そのような国々では僧侶は社会的に特別な存在であり、総体としてあくまで上位に位置しています。そのような中にあって、僧侶が在家信者に対して(一般的な意味で)愛想よく振舞い、(説法の場以外で)よく喋り、よく笑うことは、むしろ人々から批判対象となってしまいます。
特にタイでは、国家として僧侶を特別扱いする社会を構築しているのと同時に、であるからが故にか、社会が非常識と考える僧侶や破戒したのが明白な僧侶などを、(重戒を犯した僧侶は国法によっても罰せられますが)社会的な意味で血祭りにあげようとする傾向があります。これはもはや、タイ人の娯楽の一種とすらなっている、と言ってもいいかも知れません。芸能人のゴシップの類に近いものとなっています。

「僧侶は一般人と同様の生活を送ってはいけない」というと、これは寺院関係以外の日本人でも同様に考えている人があるでしょう。しかし、「僧侶は托鉢時などを除いて寺院の中に閉じこもって一般社会と極力関わるべきではない」となると、日本人ならばこれについて「ん?」となる人が多いでしょうか。「その様であるから彼奴らを小乗と言うのだ」と叫びだしてしまう人もあるかもしれませんが、それは性急というものです。寺の中で閉じこもって非日常的生活を送る限り、在家信者はこれを尊敬して布施し、その生活を支える。というのが、それらの国での一般的感覚です。
しかし確かに、むしろこのような風潮がタイの比丘たちをさらに内向きにさせてもおり、僧院の中にあって自坊のドアに鍵をかけてしまえば何をやってもいい、と言っても限度はありますが実際やりたい放題に近い、というような態度にすらさせています。
先になぜ枯れ木が理想とされるかの理由を述べましたが、しかし彼らは縁起法を根拠として意識しそのようにしている、と言うよりむしろ、もはや社会のそのような要望にただ従っているだけという、いわば本末転倒となっている側面もあります。しかし、その枠内では「一応」それで良しとされていることです。いずれの国や地域にも存在する、文化・習慣の異なりに属する問題でもあるでしょう。
このような本末転倒は何も南方の仏教だけに見られることではなく、日本の真言宗であろうが禅宗であろうが、また宗教に限らず、およそありとあらゆる文化的活動に見られることのように思われます。その枠内にある人でこの本末転倒を問題視し、原点回帰を志す者が現れたとき、その人がどこまで出来るかということに掛かってくる問題です。
実際、それぞれの枠内において、そのような志をもち実行しようとしている者、すでに実行している者があります。しかし、ここでまた問題となるのが、その現状を問題視するあまり、彼らが文字通りラディカル(Radical)となって排他的・攻撃的・急進的もしくは極端な教条主義になり、原点回帰のはずがあらぬ方向へと走ってしまうことがまま見られることです。
さて、ビルマも同様なことが言え、在家信者の前ではあまり喋らず前方下方の一点を見つめている(格好を取り繕う)ことが、「よく気を付けている」「念を保っている」「心一境性がある」証・理想とする点は変わりません。しかし、タイ等の僧侶と同じような(枯れ木的無反応な)態度を取る人は比較的少なく、ある意味愛嬌のある人のほうが多いようです。これは、他国と比してビルマにおける僧の数が圧倒的に多すぎ、その他の国では考えられないほど朝から晩まで街のいたるところで見かけるため、ということもあるのですが(2011年結夏時点でおよそ55万人:人口比約1%)。
現在のスリランカでは、枯れ木などというのとは正反対に、太っていて尊大な態度をとることがすなわち徳がある、威厳や風格がある、裕福で健康である、とする(インド亜大陸にほぼ通じて見られる)社会通念があるためか、在家信者の前にあるときや写真を取るときなどは、例えば腕を組んで背をそらし顎をあげる、あるいは顎を引いてグッと視線を上げるなど、そのような態度を示す人が多い傾向があるようです。
このような背景を全く知らずして彼らと交流する機会を持った者、たとえば旅行者などが、「南方の小乗の僧というものは、なんと傲慢であることか」と怒り心頭に発し、帰国してから声高にその批判を始めてしまう人があります。
もっとも、外国人を相手にする機会の多い観光地辺りの寺などで住んでいる、あるいはそこらをウロウロしている比丘や沙弥などは、外国人相手には愛嬌を見せたほうが色々とメリットがあることを十二分に学習しているため、普段とまったく異なる態度で接することもよく見られます。故に、無愛想・無反応などではなく、むしろ「南方のお坊さんは非常に明るくて愛嬌がある」との感想を持って帰る旅行者もあるでしょう。
また、南方の比丘らから、日本など大乗の僧職の人々は非常に裕福であると認知されているため、その高額の布施や後援を期待して、頭では大乗を軽蔑し彼らを僧侶とはまったく見なしていないのとは裏腹に、彼らに対しては特に愛想よく振舞うことが、非常に多く見られます。
さて、それらの国の比丘といっても様々で、最初から還俗するつもりで数ヶ月の極短期間から十年ほど中学から大学を卒業するまで若い間だけ比丘をしている者と、生涯出家を志しているいわば本来的出家者とは本質的に異なり、その態度にも異なりがあります。例えばタイやカンボジアなどには、数日間から数ヶ月間通過儀礼的・義務的に比丘あるいは沙弥となる、いわば「なんちゃって出家」「プチ出家」ではなく、すでに法臘五~十歳を重ねていながら婚約者のある比丘というのがあります。彼らは比丘をしながらすでに世俗で何をするか、どのような仕事に就くかアレコレ考えています。むしろそのような種の者が多いようです。
スリランカには通過儀礼的一時出家、短期出家という習慣はありません。スリランカでは、僧の数がおよそ17,000から18,000人程度とその他の国に比して非常に少ないのは、そのような習慣が無いことも一因です。さてしかし、小さい頃から(多くの場合貧しさが原因で)家を出され、サンガに身を置いている若い沙弥や比丘らには、端から大学卒業とともに還俗するつもりでいるのがあり、実際に八割から九割方の大多数が還俗していきます。
若い頃に出家しサンガに身を置くことは、貧困社会にある彼らにとって安く教育を受ける手段に過ぎなくなっている側面があるのです。そして、それを彼らは(社会的世間体的にマズイという気はあるけれども)悪いともおかしいともなんとも思っていない。結果、終生僧侶としてサンガに居残った者、すなわちスリランカの比丘の大多数が、還俗する機会を逸した、あるいはその機会の無かった、僧侶以外に出来ることがない者、現代的な意味での学などほとんどなく、つぶしが全く利かない世間知らずになっています。
これを問題視し、そのような者らを「サンガをただ経済的に利用し、その質を低下させている」と批判する在俗の人々も存しています。これは確かに事実で、彼らはある意味短期出家者よりもタチの悪いものと言えるのです。「結果的にサンガに残っている者」の多くが、いわばその昔の支那の宦官、あるいはインドのバラモンのようなものとなって、名聞利養をただ追い求めるだけの存在となっています。しかし、その背景には貧困という深い闇が横たわっているので、この是非は他所からたやすく言い得るものではありません。
なお、これは、ポル・ポトによって僧侶がほとんど皆殺しにされ、サンガが壊滅したカンボジアでも、現在復興されているとはいえ似たような状況です。
ちなみに、儀礼的出家のある他の国々では、その期間にかかわらず還俗した者に対する蔑称はないようです。たとえば、ビルマにも通過儀礼的短期出家の習慣がありますが、そのような短期出家をDullabhaと呼称して他の本来的出家者と区別します。ただ区別するとは言っても、それはパーリ語の「得難い」という意味の形容詞で、いくらそれが短期間であってもその意味の通り「ありがたい」ものとしています。本来的出家者からすれば、そのような短期出家者は、その寺の壇越自身であったりその子息であったりするため、彼らは「お客さん」であり特別扱いされます。
短期出家という習慣の是非はおくとして、仏教への信仰がこのような通過儀礼を生み出し、そこに大きな社会的価値が認められているのす。
また、以前短期出家でなく、出家していた者が還俗して俗人になったのをビルマ語でluthwekと呼びますが、そこに軽蔑の意は全く含まれていません。しかしながら、短期出家の習慣のないスリランカでは、かつて出家していながら還俗した者をHiraluwaと呼びます。これは少なからず侮蔑の意が込められた言葉です。
さて、近年はまた一つ、面白い葛藤を見ることも出来ます。枯れ木が理想とされつつも、ビルマにしろスリランカにしろタイにしろ、ここ百年間ほどの各国で高徳とされた僧たちの現存する写真を並べて見ると一目瞭然なのですが、過去の大徳たちがほとんど細身で文字通り「枯れ木」的であるのに対し、近年の有名な僧侶というのは、どこでもブクブクとだらし無く太っているのが全体を占めるようになっています。これらの国の僧侶らの間では、もはや痩せていることは決してその人の徳を示すことでなくなっているのです。
インターネットの世界的普及によって高度情報化社会となった現在、第三世界の人々が先進国での社会の暮らしぶりに間接的に触れ、自身らが物質的に非常に貧しいことを知った結果、むしろ精神まで貧しくなってしまい、拝金主義という霧がそれらの国に色濃く立ち込めています。
あるいは、農業国から工業国へなど、発展途上の過程においてしばしば見られる、異常なまでの投機熱を中間層が持ち始め、他者との競争に勝つための数々の不正が行われるなど、第三世界においても、すでに先進国各国に見られた伝統的道徳観や社会のあり方の急速な崩壊、変化が起こっています。「衣食足りて礼節を知る」とは言いますが、物質的に豊かであれば精神的に豊かになれるに違いない、という幻想を抱いている人が多くあります。
(しかし、彼らがそのまま極貧の、将来の展望など全くない状態で良いわけなく、やはり満足な衣食と、なにより高度の教育が必要であることに変わりありません。社会がそのような過程を経ることは、人の世において必然的なことであるのでしょう。)
また、東南アジアなど第三世界の人々は自身たちの国のそれに比して心が豊かである、などという感想を抱いて帰る先進諸国からの旅行者、短期滞在者は多くあります。が、それもただ表層を眺めたのみの、幻想にすぎません。この世はどこまでも娑婆(忍土)であり、人はどこまでも人です。
さて、確かに、托鉢など外を歩いているとき下を見つめてキョロキョロとせず多くの挙動をとらないこと、必要でないときには口を開かず寡黙であること、仏法に何ら関しない世間の話に華を咲かさない(無駄口を叩かない)こと、念を保って落ち着いていることなどは、、諸経典にて徳として賞賛され、またそうあるべきものとして説かれています。
最初はあくまで真似事に過ぎなくとも学に行にと修行を重ねていくうち、すなわち基礎からコツコツと学んだ教えを実践し、ひたすら繰り返してその経験を積み上げて理解していくうち、自然に必然的に理想とされる状態になっていくものです。そのようにするのであれば、形から入ることは決して悪いことではありません。むしろ多くの職業や立場においてその外見・形が人を育てていくことがあるように、仏教の修行もまた同様のことが言い得ます。いずれにせよそこで肝要なのは、何故その形であるかを「理解すること」ですけれども。
しかしそこで、解脱を迎えた人がおしなべて「枯れ木」になるかというと、これは私が日本人であるからということもあるでしょうが、非常に疑問です。そういう人もあるでしょう。いや、仏陀ご在世にも実際にあったことが、諸経典から伺い知れます。しかし、誰もが全く同じようになる、同じようになるべきだ、というのはどうでしょうか。
声聞の教学からしても、このような見方・思想は、正しいものとは言えません。なんとなれば阿羅漢であったとしても、(これは言ってしまえば当たり前のことなのでしょうが、)ぞれぞれ能力に隔たりがあるだけではなく、性格や志向、その行動の傾向の異なりがあることが認められているのですから。
日本仏教には新旧あわせて十三宗の宗派が存在しており、それらから派生した有象無象の新興宗教がそれこそ山のように存在し、それぞれが時としてまったく別のことを説いて、およそそれらが同一宗教に属するものとは思えないものとなっていることがあります。上に縁起ならびに四聖諦は仏教の根幹だと述べましたが、これをさまざまに解釈し体得せんと、多くの道を様々に説き示したのが、それら部派・学派なるもので、日本の諸宗もその流れを組んで起こった、はずだったのものです。
大乗においては、縁起と一口に言っても種々様々の説が展開しており、例えば縁起は中観の無自性空と同義とされ、または阿頼耶縁起・如来蔵縁起・法界縁起などの縁起説が説かれ、それらは十二縁起よりも深遠な教えであると位置づけられている場合があります。ただし、そのように十二縁起が大乗のそれに対して低いものと位置づけられる場合があったとしても、無価値なものなどとは決してされていません。
ところが今の日本では、十二縁起と聞いて「縁起?あぁ、釈尊が最初に説いたと“言われている”やつね」ととぼける者や、「釈尊は十二縁起など説かず、最初は四縁起等より簡単なものに過ぎなかった。十二縁起など後代の作り物、仏教教義が出来上がって後の創作物である」などと誰か学者の説のオウム返しを得々と言う者が多くあります。しかしそこで、ではそれは何かと問うたならば、「十二縁起という言葉は知っているけれど、その内容を説明しろとか、どうこれを解釈するかなどは知らないし、言えない」と平気で言う人があります。
「我が宗は大乗に属するものであり、四諦十二縁起など声聞や独覚の教えであって、程度の低いものに過ぎない。対して我が宗では、そもそもお祖師様が」云々と鼻息荒く言うものの、その実その程度の低いと断ずるものを、頭の中だけですらも全く理解出来ておらず、必然的に「深淵にして崇高」だと誇る「我が宗云々」のことをまるで理解していないという人が多くあるのです。
ひどいのとなると、いや、むしろこれが一般的なのですが、「そもそも十二支縁起の一一が何か覚えていない」、「本で読んだことある程度で、やっぱり知らない」、「いやぁ私、物覚えが悪くてすぐ忘れてしまうのですよ。ハハハ」という、謙虚さからそう云うのとは異なる僧職者が、これはおそらく在家の人が想像物出来ないほどの、驚くべき高比率で存在しています。
何故か。日本の僧職者にとって仏教はいわば飯の種ですが、しかしそれも主としてまるきり儒教の祭儀祭式を仏教的作法に糊塗して行う祖霊崇拝をこそ専門としているのであって、そこに縁起が云々、四聖諦が然々などほとんどまったく関係がなくなっている為です。故に飯の種ではあっても、面白いことにその本質となる縁起云々は専門の範疇に無く、知らなくても問題ない、人に説かなくとも何等差し支えない業態となっているためです。
また、「檀家に説いてもどうせ興味もないし、わかりもしない。実際のところ、私もわからない。衆人もわからないし、望んでもいない。であるからこれを学んで説こうとするだけ時間と労力の無駄」と、釈尊が説法を躊躇したのとはまるで異なる方向性で、大衆は愚であると、端から無駄であるとしている人も多くあります。これでは梵天の出る幕などありません。
日本仏教界全般が、仏教の看板を上げておきながら中身がまるで別ものとなっていることを、このように譬えることが出来るでしょう、それはあたかも三河屋のようなものであると。しかし、もはや三河屋なるものすらも、コンビニの出現と普及によって社会から消えてなくなってしまったようです。故にまた進んでこれを譬えると、三河屋が消えてコンビニが出現してきたのと同様、日本の寺が三河屋からさらにコンビニへと変化し、僧職者のほとんどがコンビニの店員化しているようなものだ、と言えるでしょう。
ピコピコとレジを打つように、「葬儀導師料15万円、助法僧5万円、院号30万円、その他お車料・お膳料合計して60万円になります」(地方地域によって相場は大きく異なる)などとよどみなく言い、これをあくまで布施として受け取るや、流れるような作業で葬儀屋という仲介業者の誘導のもとにモジャモジャと読経を開始。要所要所でポコポコチンチンと木魚あるいは鈴をならし、ジャンジャンゴーンと鐃や馨を叩いて、きっちり約四十五分から一時間以内にて「本日はまことにお悔やみ申し上げます。これにて葬儀一式、円満終了でございます」と相成ります。
商品の戒名は、戒名ソフトまかせであれこれ考えることなしに簡単に決定できる。寺に納められた骨や位牌の管理も過去帳という名の帳簿(最近はこれも檀家管理ソフト)で、その置き場所や日にち・持ち主等々なども整理され、いわば棚卸しも自由自在。葬式という日常のイベントは儀式として合理化され、状況に合わせて三十分でも一時間半でも自在に時間内に収められる、きわめて洗練されたものです。ところが、ではそれらの背景を説明せよ、となるとほとんどの場合何も言えない。いや、実にいい加減なことを言い出す。
コンビニの店員がレジで商品を袋に詰め、合計料金を言って金を受け取り、レシートを渡すという一連の行為を、多数の顧客相手にスムーズにこなせるのと一緒です。しかし、彼らは売りさばいている商品の一一を由来・効用を説明する必要もないし、そもそも出来ない。コンビニの場合、また客はそれを求めてもいない。そんなことをされると客は逆に困ってしまうでしょう。
コンビニについては、早くて便利という理由から、大きな需要があります。寺もそうした理由で一部から必要とされているところもありますが、しかしこれに関してコンビニと同じようなわけにはいきません。寺の場合、コンビニのレジ打ちの如きことをするのを含め、さらに、そもそも売っている商品を逐一説明すること、またその商品の効用を示すことに価値があるものだからです。またコンビニのように全く不特定多数の者が顧客ではない。檀家寺でも信者寺であっても、相手はある程度特定された人々で、どこまでも三河屋的です。
そして実際、馴染みにしろ新規にしろ、その客の中には本来の商品であった上質な味噌をこそ求める人があります。いや、この三河屋は、積極的に三河の味噌の良さを人に宣伝し、薦めなけれなならない。
かといって、僧職の人や寺族一統に、「今の坊さんなんてコンビニの店員と同じようなもんでしょう?」などと言ってしまえば、「なんと非常識な、失礼な輩であるか」と怒りだしてしまう人が多いでしょう。プライドだけはその実に比して異常なまでに高いのです。コンビニは現代社会の役に十二分に立っているというのに。
日本の寺院がなぜ三河屋化し、そしてまたコンビニと化したかを、あるいは社会の要請によってそうなったのだ、と説明することも可能でしょう。「何故そうなったか?それは社会の需要と供給という観点からすれば一目瞭然なのだ」と。確かに寺院のあり方というものは、経済的に社会に依存することを前提としているために、社会の経済的状況・人々の宗教的要求によってもそのあり方を変化せざるを得ないものです。しかし、何故そのようになったかの理由をいくら歴史的客観的に斯く斯く云々と説明したところで、それが彼ら僧職者がそのような状況で良いという釈明や根拠には全くならない。
僧職者・寺族の人がこの点についていかに客観的な言を振るったとしても、それは単なるおためごかしにしかならないでしょう。けれども、そのような説明をもって充分な釈明・自身のあり方の根拠となっているつもりでいる者は、現実には多くあります。衆寡敵せず。もはや日本の寺院というもののほとんどが、完全に「家族を囲うための、寺の形をした家」に過ぎなくなっている現在そして未来、このような状況が変化することはきっとないでしょう。
そのようなこともあって、今の日本社会において、その内容はともかくとしても仏教を世に説き示す役割を担っているのは、学術的にのみ云々しつつ、しかし何故か滔々と「説法」しだしてしまう一部の仏教学者・文献学者と、多くの仏教系新興宗教団体となっています。
漸々と寂れていく三河屋がある町に、化学調味料をたっぷり使った味噌専門店が新規に出店し、様々に宣伝広告を駆使して繁盛しているようなものです。しかしながら、せめて僧職の人々は、いや、それだけなく多くの仏教系新興宗教をこそ信ずる人々も、自身が仏教徒であるとする以上は、せめて四諦十二縁起だけは、机の上だけでも確実に学び、さらに修めてこれを日々に念じ、その上で空を説くならばこれを確かに学び理解して説いて欲しいものです。
あるいは、あくまでそれらを全く踏まえた上で、さらに進んで華厳の重々縁起を世に示したければ世に示し、また例えば私はどうしても南無阿弥陀仏、あるいは南無妙法蓮華経と称えたいのだなどと言う人があれば、いくらでも称えればよいと思います。自身が大乗の流に属する派を信仰しているからといって、これらを小乗の教えで低い劣ったものである、などと端から断じて顧みないようではいけない。
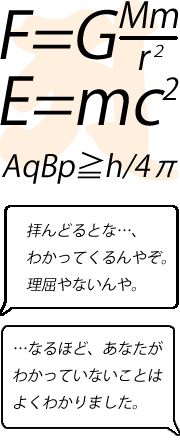
拙い例えですが、譬えば良い餅を求めてこれを作るには、まず良い餅米が必要であるようなものです。そして、その餅米を手に入れたとしても、それを米びつに後生大事に仕舞っておいても仕方がありません。それを上手く搗かなければ、餅になることは決してないでしょう。「いや、そんな面倒なことをせずとも、私は初めから老舗の餅屋に買いに行く」というのは、この場合通用しません。
または、家を建てるのに、その確かな土台・基礎を作ることがなければ、どれだけ「設計図上は」素晴らしいように思われる家であっても、建ちようがないようなものです。あるいは一時的にこれを建て得たとしても、それは砂上の楼閣に等しき虚妄にすぎません。なにより基礎こそが、まず最も重要なものであることは、あらゆることについて言い得るものでしょう。
算数すらまともに出来ない者が、なにやら難しげな数式がずらりと並んだ紙をただありがたがって神棚に飾ってただ崇め奉り、勉強そっちのけで「理解できるようになりますように」などと一心に祈るようなのを、愚かと思わぬ人があるでしょうか。基礎的な技術や知識・経験を積み重ねることなく他所から剽窃し、これを元来我が物であったかのように言って、表面だけ豪盛にさも実があるかのように見せかけたものを、一体誰が真から求めるというのでしょうか。
日本には、僧侶が葬式自体に関わることを批判する人もいますが、僧侶が葬式に関係することは決して悪いことではありません。世の中には捉え違いをしている人があるようですが、釈尊は「私(仏陀)の遺骨の供養に比丘たちは関わってはならない。比丘たちは出家した目的を目指してひたすらはげめ」などと言ったのであって、比丘が社会の人々の葬式に関わってはならない、などと説かれたことはありません。
また実際、そのような律の条項も一切ありません。ただ確かに、仏教の修行そしてその結果云々と葬式とは、まったく関係のないことではあります。しかし実際、世界的にみた場合、多くの国・地域の僧侶らは、なんらかの形でそれぞれ葬式に関わっています。
その時こそ、僧侶は人の死を、世の無常なることを重ねて説くのです。故に、人の死の場面に、出来るならばその死の前にも、僧侶が行って経を読むなり、(仏教の)様々な話をするなりすることは大変良いことです。人の死という場面は、それが葬式であったとしても、人がまさしく無常に直面する機会であるからです。
愛する人を失った悲しみに打ち震え、止めることの出来ぬ涙を流しつつ、「愛する人はもはや息を止め、体は冷たくなってもう二度と動くことはない。人は誰であり死に逝く者、私もいずれ必ず死ぬ」という、あまりに当たり前の、そして誰も本当に理解していない事実と真剣に対峙することも可能でしょう。
とは言え、死と向き合うのは病院までのことで、その遺族は葬式そしてそのそれに伴う社会的なあれこれに忙殺され、葬式時にそのような暇など全く無い、というのが大方の現状のようです。これは、社会全体が利便性合理性を追求し、商業主義的になりすぎた結果とも言えるかも知れません。町や村といった地域共同体が昔とはまったく異なる現在、しかし、その代替案はなかなか見出しがたいようです。
現代社会、特に日本では死というもの、さらには老いというものをすら覆い隠そうとする風潮がますます強まっていくようです。しかし、十二縁起というものを理解せんとするとき、まずもっとも重き意味を持つものがその最後支である老死です。
十二縁起は無明に始まるものではありますが、これを我が事として捉えるとき、いや、そもそも十二縁起は我が事として捉えなければただの知的遊戯に成り果てる可能性の大なるものですが、最後の老死すなわち我が人生の老死ならびに諸々の苦しみというものをいかに真剣に捉えるかということは、その人の縁起理解に大きく関わるものとなるに違いありません。
無常迅速 生死事大。
老死そして愁・悲・苦・憂・悩を契機としてこそ人は、仏陀が説かれた十二縁起を、まさしく法として理解していくことが出来るでしょう。生あるうちに訪れるのは老・病・死ばかりではなく、愁悲苦憂脳それぞれ海波のごとくやってきますが、それは多くの場合、喉元過ぎれば熱さ忘れてしまうものかもしれません。
私達は今まさいく老いていきつつある。いや、もうすでに充分老いている。そして様々に病み、あるいは徐々に、あるいは突如として死んでしまう。私の死はもう、すぐ目の前にある。この当たり前の、いや、人が無意識に呼吸していることのような、まったく当たり前のものであるが故に普段すっかり忘れてしまうこの事実を見つめたときにこそ、たとえ初めは到底理解できぬものであったとしても、誰でもこの十二縁起の教えを聖なるものとして、四聖諦と不可分のものとして我が身に受け入れることが出来ようと私は信じます。
また少しでも多くの人が、この甚深微妙なる聖なる教えを、まさしく我が事として受け入れて、これをジッと見つめ、やがてこの束縛から解き放たれることを願ってやみません。
非人沙門覺應 拝記