仏陀の遺教たる「自己を灯明として法を灯明とし、他を灯明とせざれ。自己に帰依し、法に帰依して、他に帰依することなかれ」とは、具体的に四念住を修めることです。
まず、語として四念住とは、[S]catvāri smṛtyupasthānaあるいは[P]cattu satipaṭṭhānaの玄奘による新訳語です。玄奘がこれを四念住と訳す以前、それまでの古訳や旧訳の漢訳仏典では、四意止・四憶処・四念処などと訳されていたものです。そこで本稿では、先程からほとんどそうしているように、基本的に「四念住」を用います。
(ただし、旧訳の漢訳経典を示す中に「四念処」とされている場合はそれに従い、朱字にて〈四念住〉と傍注します。)
その内容について具体的に述べる前に、仏陀は四念住についてこのような教説を我々に遺されていたことを紹介しておきます。
諸比丘。有一乘道淨諸衆生令越憂悲滅惱苦得如實法。所謂四念處。
比丘たちよ、一乗道がある。それは諸々の衆生〈生命あるもの〉を浄め、憂い悲しみを超えさせ、悩み苦しみを滅し、如実の法〈真理. 涅槃〉を得さしめる。いわゆる四念処〈四念住〉である。
求那跋陀羅訳『雑阿含経』巻廿四 [No.607] (T2, p.171a)
併せてパーリ仏典での該当箇所を徴します。
ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo sattānaṃ visuddhiyā sokaparidevānaṃ samatikkamāya dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya ñāyassa adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ — cattāro satipaṭṭhānā.
比丘たちよ、唯一の行くべき道〈ekāyana magga〉がある。(それは)諸々の生ける者を浄め、憂い悲しみを超え、苦しみ悩みを鎮め、真実の獲得をして涅槃〈nibbāna〉を現証〈sacchikiriyā〉する。いわゆる四念住〈cattāro satipaṭṭhāna〉である。
SN. Mahāvagga, Satipaṭṭhānasaṃyutta, Ambapālisutta
漢訳で「一乗」などとあるのを見ると、少し仏教の知識のある人ならば、たちまちekayānaとのサンスクリットを想起するかもしれません。しかし、こうしてパーリ仏典と比較して見たならば、「一乗道」との漢訳は、パーリ語のekāyana magga、すなわちeka(一つ、或る) + ayana(行くこと・前進・道) + magga(道)に該当することがわかります。
ekayānaとekāyana、それらは似て非なる言葉です。
漢訳に従事した三蔵の当時、底本とされた原本においてすでにその混同がされていた、あるいは経典を暗誦していたものの記憶違いなどに由って、ekayānaとekāyanaとが混同されて「一乗道」となった可能性も一応考えられはするでしょう。しかし、漢訳の一部に一乗とあるからといって、大乗とくに『法華経』などで説かれる一乗とただちに同一視するのは早計というものです。なお、同内容の教えを伝える『中阿含経』「念処経」の該当箇所では、一乗道ではなくただ一道と訳されています。
さて、仏陀はまた、四念住が如何に仏道において重要な、いや、不可欠のものであることをこのようにも説かれています。
若比丘離四念處者。則離如實聖法。離如實聖法者。則離聖道。離聖道者。則離甘露法。離甘露法者。不得脫生老病死憂悲惱苦。我說彼於苦不得解脫
もし比丘が四念処〈四念住〉を離れたならば、如実の聖法を離れる。如実の聖法を離れたならば、聖道〈八聖道・八正道〉を離れる。聖道を離れたならば、甘露〈涅槃〉の法を離れる。甘露の法を離れたならば、生・老・病・死、そして憂・悲・悩・苦から逃れ得ることは無い。私は、そのような者は苦より解脱することは無い、と説く。
求那跋陀羅訳『雑阿含経』巻廿四 [No.608](T2, p.171a)
以上に示した諸々の経説に依れば、「四念住とは、仏道に決して欠かせることの出来ないその核心である」と断じて誤りありません。ただし、このように言えばたちまち、「ならば四念住をのみ」・「ただ四念住だけを修めれば」・「仏陀の教法は数あれどいえど、その他は枝葉末節の価値なき云々」などと言い出す者が、屹度ぞくぞく現れるに違いありません。
実際、これは菲才だけのことかもしれませんが、そのような言を発する粗忽の人にたびたび出会うことがあります。けれども、それはあまりに浅薄に過ぎるというものです。そう早まってはいけない。そのような立言が正しいものであれば、仏教に「八万四千の法門」などと言われる数々の教説など全く必要なかった。
実のところ、そのような言を放つ者が現れるのは今に始まったことではありません。二千年の昔の印度にすらそのように早合点する人、一知半解の者が多くあったであろうことが知られます。そのような軽はずみな理解をする者に対する回答は、二千年の昔の大乗においてすらすでになされているのです。
問曰。四念處則能具足得道何以説三十七。若汝以略説故四念處。廣説故三十七。此則不然。何以故。若廣應無量。答曰。四念處雖具足能得道。亦應説四正懃等諸法。何以故衆生心種種不同。結使亦種種。所樂所解法亦種種。佛法雖一實一相。爲衆生故。於十二部經八萬四千法聚。作是分別説。若不爾初轉法輪。説四諦則足。不須餘法。以有衆生厭苦著樂。爲是衆生故。説四諦身心等諸法皆是苦無有樂。是苦因縁由愛等諸煩惱。是苦所盡處名涅槃。方便至涅槃。是爲道。有衆生多念亂心顛倒故。著此身受心法中。作邪行。爲是人故説四念處。
問:「四念処〈四念住〉とは、これをよく習得したならば道〈聖果〉を得るものである」というのであれば、何故に三十七〈三十七菩提分法〉が説かれているのか。もし汝が「(仏陀の教説すべてを)略説すれば四念処となるのであって、広説〈詳説〉したならば三十七となる」と主張するのであれば、それは誤りである。なんとなれば、もし広説ということをいうのであれば無量となるべきであるから。
答:「四念処とは、これをよく習得したならば道を得る」といっても、また同時に四正勤等の諸法が説かれなければならなかったのだ。なんとなれば、衆生の心は種種不同であって、その結使〈煩悩〉もまた種種であり、(衆生がそれぞれ)理解・習得しようとする教えもまた様々であるから。もとより仏法とは一実一相である。とはいえ、(仏陀は)衆生のために十二部経〈全ての経文を十二種に分類した称〉、八万四千の法聚において、それぞれ分別説を作されている。もし、そのようでなかったとしたならば、初転法輪において説かれた四諦のみで事足りたのであり、それ以降も他に説かれることなど無かったであろう。衆生は苦を厭い、楽に執着するものであるから、そのような衆生のために四諦を説かれ、「身心等の諸法はすべて苦であって楽のあることはない。この苦の因縁は渇愛等の諸々の煩悩に由る。この苦が盡くされた処を涅槃といい、涅槃に至る方便〈手段〉を道という」とされたのだ。衆生は多念・乱心・顛倒しているから、この身・受・心・法において様々に執着して邪行を作している。そのような人というものの為、四念処が説かれたのだ。
龍樹『大智度論』巻第十九 初品第三十一(T25. p.198a)
八宗の祖などと日本で称えられる龍樹もまた、上に示した『雑阿含経』の所説などに則り、四念住がまさしく道の至要であることを述べています。その上で、では何故に仏教では他の法が種々様々に説かれているかの答え、それは大乗の立場からの理解ではありますが、示されているのです。
仏陀の教えの精髄、それは四聖諦です。
| 1. | 苦聖諦(苦諦) dukkha ariyasacca |
この世界に存在することは「苦」を本質としているという真理。四苦八苦・三苦。 |
|---|---|---|
| 2. | 苦集聖諦(集諦) dukkhasamudaya ariyasacca |
「苦」の本源についての真理。無明・渇愛を因縁として生起すること。縁起法。 |
| 3. | 苦滅聖諦(滅諦) dukkhanirodha ariyasacca |
「苦」の滅についての真理。その本源がなくなり、「苦」が滅した状態、すなわち解脱・涅槃について。 |
| 4. | 苦滅道聖諦(道諦) dukkhanirodhagāmī paṭipadā ariyasacca |
「苦」の滅へと導く道についての真理。いかにして無明・渇愛を超克し、「苦」を滅するかの術。八聖道(八正道)・三学(戒・定・慧)。 |
このうち、第四の苦滅道聖諦(道諦)を開いたもの、それが八聖道です。八聖道は一般に八正道とも書かれますが、その原語は[S]āryâṣṭāṅga-mārgaあるいは[P]ariyâṭṭhāṅgika-maggaであるため、八聖道が正確な訳語となります。
八聖道について、釈尊は成道された時のことを回想し、以下のように説かれています。
我時作是念。我得古仙人道。古仙人逕。古仙人道跡。古仙人從此跡去。我今隨去。譬如有人遊於曠野。披荒覓路。忽遇故道古人行處。彼則隨行。漸漸前進。見故城邑古王宮殿。園觀浴池。林木清淨。彼作是念。我今當往白王令知。即往白王。大王。當知。我遊曠野。披荒求路。忽見故道古人行處。我即隨行。我隨行已。見故城邑。故王宮殿。園觀浴池。林流清淨。大王可往居止其中。王即往彼。止住其中。豐樂安隱。人民熾盛。今我如是。得古仙人道。古仙人逕。古仙人跡。古仙人去處。我得隨去。謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念 正定。我從彼道。見老病死。老病死集。老病死滅。老病死滅道跡。見生有取愛受觸六入處名色識。行行集行滅行滅道跡。我於此法。自知自覺。成等正覺。爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及餘外道沙門婆羅門。在家出家。彼諸四衆。聞法正向信樂知法善。梵行増廣。多所饒益。開示顯發。
私はその時、この念いが起こった。「私は古の仙人〈[S]rsi / [P]isi〉の道、古の仙人の径、古の仙人の道跡を得たのだ。古の仙人はこの跡に従って(生死輪廻を)去り、私も今、(その跡に)随って去る」と。
譬えばある人が広野に遊び、荒れた地を披いて路を覓めたところ、忽ち故き道で古人の行処を見つけた。彼はそこで(その道に)随って行くことにした。漸漸として前に進むと、故き城邑、古の王の宮殿、園観や浴池、林の清淨なるのを見つけたのである。そこで彼はこのような念いを起こした。「私は今、まさに還って王に報告してこれを知らせるべきであろう」と。そこで還って王に報告した。「大王よ、まさに知るべし、私は広野に遊び、荒れた地を披いて路を覓めるところ、忽ち故き道で古人の行処を見つけました。私はそこで(その道に)随って行くことにしました。(その通り)私が随って行ったところ、故き城邑、故の王の宮殿、園観や浴池、林や流れの清淨なるのを見つけました。大王よ、そこに往ってその中に居住するのが良いでしょう」と。そこで王はそこに往き、その中に居住すること豊楽にして安穏であり、人民もまた繁栄したようなものである。
今の私も同様である。古の仙人の道、古の仙人の径、古の仙人の跡、古の仙人の去処を得て、私は随って去ることを得たのだ。(その道とは)謂く八聖道〈[P]ariya-aṭṭhāṅgika-magga. 八正道〉、正見・正志〈正思惟〉・正語・正業・正命・正方便〈正精進〉・正念・正定である。私はその道に従って、老・病・死〈苦聖諦〉、老・病・死の集〈苦集聖諦〉、老・病・死の滅〈苦滅聖諦〉、老・病・死の滅への道跡〈苦滅道聖諦〉を見た。生・有・取・愛・受・触・六入処〈六処〉・名色・識、行・行の集・行の滅・行の滅への道跡を見た。私はこの法に於いて、自ら知り、自ら覚って、等正覚〈[P]sammāsambuddha〉を成就して、比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷、及び他の外道の沙門・婆羅門の在家・出家、その諸々の四衆の為に、法を聞かせて正しく信楽〈教えを信じ喜ぶこと〉に向かわせ、法の善なるを知らしめ、梵行を増広せしめて饒益すること多く、(古の仙人の道を)開示し顕したのである。
求那跋陀羅訳『雑阿含経』巻廿二 [No.287](T2, pp.80c-81a)
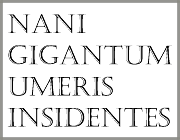
釈尊にとって八聖道とは「古の仙人」が開き、すでに歩かれていた道でした。ここで「古の仙人」を、往古の婆羅門あるいは先代の仏陀などと表しても良いでしょうが、とにかくそれは釈尊が初めて切り開いた道ではなく、すでに存したものを今あらためて再発見したものであったと云われます。
それは古の支那の聖人、孔子の言った以下のような態度にも通じたものです。
子曰、述而不作。信而好古。窃比於我老彭。
子曰く、述べて作らず。信じて古を好む。窃かに我が老彭に比す。
子〈孔子〉は言われた、「私は(古の道を)述べているのであって(何か新しい道を)作っているのではない。(私はその古道を)信じて古を好むものである。そして窃かに我自身、老彭〈殷時代、古典に精通していたという大夫〉に比して(彼のようでありたいと思って)いる。
『論語』述而第七
そしてそれは、しかし、解脱に至るただ一つの道であり、それが(仏教であれ)何であれ法であるならば、八聖道を欠いたならば決して菩提を成就することなど叶わぬものであるとも説かれています。
須跋即入問訊已一面坐。而白佛言。我於法有疑。寧有閑暇一決所滯不。佛言。恣汝所問。須跋即問。云何瞿曇。諸有別衆自稱爲師。不蘭迦葉。末伽梨憍舍利阿浮陀翅舍金披羅。波浮迦旃。薩若毘耶梨弗。尼揵子。此諸師等各有異法。瞿曇沙門。能盡知耶。不盡知耶。佛言。止止。用〈勿の写誤か?〉論此爲。吾悉知耳。今當爲汝説深妙法。諦聽諦聽善思念之。須跋受教。佛告之曰。若諸法中無八聖道者。則無第一沙門果第二第三第四沙門果。須跋。以諸法中有八聖道故。便有第一沙門果第二第三第四沙門果。須跋。今我法中有八聖道。有第一沙門果第二第三第四沙門果。外道異衆無沙門果。爾時世尊爲須跋而説頌曰
我年二十九 出家求善道
須跋我成佛 今已五十年
戒定智慧行 獨處而思惟
今説法之要 此外無沙門
須跋〈[P]Subhadda. 仏陀の最後の直弟子となる人〉はすなわち(仏前に)来たり入って問訊〈挨拶〉してから傍らに坐した。そして仏に申し上げた。
「私は法〈dharma. 真理〉において疑いがあります。もしその時間があるならば、一つ(その我が疑いという)滞りを決していただけるでしょうか?」
すると仏は、
「汝の思うように問うがよい」
と言われた。そこで須跋は問いを発した。
「瞿曇〈[P]Gotama〉よ、諸々の別衆〈別の教団.外道〉があって自ら『師』を称しているのはどういうことでしょうか?不蘭迦葉〈[P]Purāṇa Kassapa〉。末伽梨憍舍利〈[P]Makkhali Gosāla〉、阿浮陀翅舍金披羅〈[P]Ajita Kesakambala〉、波浮迦旃〈[P]Pakudha Kaccāyana〉、薩若毘耶梨弗〈[P]Sañjaya-Velaṭṭhiputta〉、尼揵子〈[P]Nigaṇṭha Nāthaputta〉です。これら諸師らは各々、(相矛盾して)異なる法〈教え・思想〉を(真理であると)主張しています。瞿曇沙門〈[P]samaṇa. 努める人〉は、(それらについて)能く盡く知られているでしょうか、盡く知られてはいないでしょうか」
仏は言われた。
「止めよ、それらを論じることなど止めよ。私は『全て』を知るのみである。今、まさに汝の為に深妙なる法を説こう。諦かに聞き、諦かに聴いて善くそれを思念せよ」
そこで須跋はその教えを受けることとし、仏はこれに告げられた。
「もし(世間の『師』を称する者が主張する)諸々の法〈教え・思想〉の中に八聖道〈[P]ariya-aṭṭhāṅgika-magga. 八正道〉が無いならば、すなわち第一沙門果〈[P]sotāpanna. 預流果〉・第二〈[P]sakadāgāmin. 一来果〉・第三〈[P]anāgāmin. 不還果〉・第四沙門果〈[P]arahat. 阿羅漢果〉は無い。須跋よ、諸々の法の中に八聖道があることによって、すなわち第一沙門果・第二・第三・第四沙門果が有る。須跋よ、今、我が法の中には八聖道が有り、第一沙門果・第二・第三・第四沙門果が有る。外道の異衆には沙門果は無いのだ」
その時、世尊は須跋の為に頌〈gāthā. 詩句〉を説いて言われた。
私は年二十九にして、善なる道を求めて家を出た。
須跋よ、私が仏となってから、今已に五十年である。
戒と定と智慧の行あって、独処して思惟したのである。
今、法の要諦を説いたが、この他には(解脱に達し得る)沙門は無い。
『長阿含経』巻四「遊行経」第二後(T1, p.25a-b)
これは仏陀が般涅槃される直前、非常な高齢であったものの釈尊最後の直弟子となる栄誉に預かれた須跋、すなわち[P]Subhaddaへの教説において語られた一節です。ここで八聖道とは、悉地を得るに唯一の道として説かれ、それは先に言及した「一乗道」の言に重なるものです。

その八聖道の中、第七に挙げられる正念の具体が、本稿で講じている四念住です。四念住はまた、仏教の要道としてまとめられた三十七菩提分法(三十七道品 )の最初として挙げられます。しかし、実はその中、修習として具体的な術であるのは、四念住以外にありません。三十七菩提分法については、その名目のみ比較的知られていますが、その内実を知る者は非常に稀です。
「阿含経」において、四念住と共に七覚支が多くの場合同時に説かれていますが、七覚支は修習というよりむしろ四念住によって開発・陶冶された心に生じる徳性です。覚支とは[S]bodhyangaあるいは[P]bojjhaṅgaの漢訳ですが、「覚」〈bodhi. 菩提〉 + 「支」〈anga. 部分〉と言われるのはそのようなことに基づきます。それはあくまで、四念住を修めたことによって生じる「七つの菩提の要素」です。
その故に、「七覚支とは独立した修習の総体である」などと誤解し、ただ七覚支法なるものを自身に具えようと務めても、それはまったく虚しい努力となってしまうでしょう。四念住なくして七覚支はありえません。
以上のことからしても、これは先に示した『大智度論』の中でも言及されていたことですが、仏教には数多くの修習が説かれているとは言え、特に四念住がまず最も重要な修習法であるとされます。就中、身念住については、その他の内的・精神的対象とする念住と異なり、身体といういわば物質を対象とすることもあって、より具体的なものとなっています。なぜ念住において身が第一に挙げられたのかは、あるいは『倶舎論』の一説にもあったように、身体がその他に比して麁大なものであるからこそ様々に説き示された、ということでもあったのでしょう。
一般に、八聖道にある正念というものについて、日本における僧職者や学者らは「正しい念い」・「正しい気づき」などといった抽象的な説明を加えて済ますのみです。しかし、正念とはそんな漠然とした意味のわからないもの、市井の徒や学者が適当な言葉で言い回るようなものでなく、四念住に他なりません。
では、四念住とは何か。それは一体、具体的にどのような内容のものか。
それを吾人がアレコレどれほど考えたところで解り得るものではなく、前述したような宛のまるで外れた珍妙な解釈に達するのがせいぜいでありましょう。
子曰、吾嘗終日不食、終夜不寝、以思、無益、不如學也。
子曰く、吾れ嘗て終日食らはず。終夜寝ねず。以て思ふ。益無し。學ぶに如かずと。
子〈孔子〉は言われた、「私はかつて(何かわからぬことがあれば)終日食事することもなく、終夜寝ることすらせず思案に明け暮れた。そうして結局、わかったことがある。(自ら独り思案したところで)益は無い。(古の道、古典を)学ぶに及ぶものでないと」。
『論語』 衛霊公第十五
まさに至言。そこで我々もまた、仏陀およびその大弟子ら先達、古哲の言葉から学ばなければなりません。
四念住は一般に、①肉体が不浄のものであると知る「身念住」・②感覚されるものは畢竟苦であると知る「受念住」・③心は無常であると知る「心念住」・④事物は無我であると知る「法念住」である、と説明されます。
それはまた、我々が真理に昏く智慧なきが故に、その煩悩の故に、自身や世界をして「常なるもの」・「楽なるもの」・「真の自我である」・「清らかであって、求め楽しむべきもの」であると捉える、いわゆる常・楽・我・浄の四顛倒を退治する修習であると云われます。
これをまとめ、表にして示したならば以下のとおり。
| - | 念の対象 | 理解されるべき相 | 退治されるべき顛倒想 |
|---|---|---|---|
| 身念住 | 身体 | 不浄 | 浄 |
| 受念住 | 感覚 | 苦 | 楽 |
| 心念住 | 心 | 無常 | 常 |
| 法念住 | 法 | 無我 | 我 |
このような理解は、大乗小乗の別を問わず、北印度の説一切有部や南印度および獅子国の上座部(分別説部)、チベットの諸派、そして支那・日本の諸宗においても、通仏教的に行われてきたものです。しかしながら、翻ってこの四念住が説かれている契経そのもの、すなわちその典拠である諸経典に直接触れた時には、事情が異なってくる。その時、そのような単純な理解にのみ留まるのは、妥当と言い難いものであることに気づくことになるでしょう。
そもそも、仏教を学び修めんと志す輩は、なによりまず経蔵と律蔵、そして種々の論書から直接学ばならない。仏教を学び、考え、修めるならば、その根拠はあくまで経律論の三蔵、それらに基づく諸論書でなければ屹度なりません。
けれども今時は、誰か著名な僧侶や学者などがアレコレ簡便・簡略に書き記した概説書、あるいはただ辞書に依り、それらはそれらで大変に有用・有益なものも多くあるのですが、しかしそれだけに触れるのみで「コト足れり」・「我その蘊奥を得たり」とうそぶくような傾向が、多くの人に見られるようです。あるいは、三蔵はもとより伝統教学すらからも全く離れた新思想の主張・解釈を、「旧来の思想を打破した価値ある教え」などと褒めそやす日本的自由主義に染まった左巻きの人々も、仏教学者はもとより僧職者の中にすら、今よりそれほど古くない昔には少なからず存在しました。
しかし、それではいけない。まったくけしからんことであります。
無論、三蔵に通じ禅観に達した僧侶や、深く仏教を学び修めている在家居士など、いわゆる善知識と呼び得る人々との出会いにより、その会話・対話から法を学び、知ることは大変に有益でしょう。むしろそれによって仏教に惹かれ、菩提心を発して涅槃を志す人もあるでしょう。それは仏教本来の、釈尊の当時や仏滅後しばらくの間のあり方であったに違いない。けれども今や時は末世。それは大変稀有なこととなり、そうも行かない時代となって久しい世です。
古人は「悉く書を信ずれば則ち書無きに如かず」と謂い、それは多くのものが心奥に刻みつけるべき箴言です。とは言うものの、仏教者として先ずなにより亀鑑とすべきはどこまでも法と律、すなわち経蔵と律蔵そして論蔵です。ここはやはり、自らがその典拠にあたって直接読み深め、さらに己自身が修めて理解するに如くものではありません。

念住とは、先ほども触れましたが、[S]Smṛtyupasthāna([P]Satipaṭṭhāna)の訳です。
Smṛtyupasthānaとは、smṛty + upasthānaの複合語です。[S]smṛty([P]sati)は、従来主として「念」と訳された語ですが、その意味や働きなどの詳細は、別項「念とは何か」にて詳しく講じている通りです。よってここでは、漢訳で「住」や「処」、「止」などと訳されている、upasthānaの意味内容をのみ確認していきます。
upasthānaという語の構成は、upa-(「近くに」「側に」「共に」を意味する接頭辞) + √sthā(立ち上がる) + -ana(名詞語基を作る接尾辞)です。その原意は「近くに立つこと」・「側にあること」・「近づくこと」・「さぶらうこと」で、転じて「現れること」・「留まること/場所)」・「仕えること」・「看護」・「崇拝」などの意として用いられます。
以上を踏まえ、ここでサンスクリットの幾つかの意味と漢訳とを対照し、印度や胡国、あるいは支那の三蔵らがどのようにこの語を解していたか、訳したかを確認します。
| - | smṛty | upasthāna |
|---|---|---|
| 記憶・追憶・回想・思い出すこと・ 意識・気をつけること・注意 |
現起・そば立つこと・仕えること・ 付き従うこと・留まること/場所 |
|
| 意止 | 意 | 止 |
| 憶処 | 憶 | 処 |
| 念処 | 念 | 処 |
| 念住 | 念 | 住 |
これら漢訳から、upasthānaは「留まること(住・止)」「留まる場所(処)」の意として、諸々の三蔵によって解され、訳されたものであったことがわかるでしょう。すなわち、smṛtyupasthānaとは「念じられる所」、噛み砕いて言ったならば「気をつけられる所」・「注意を向けるべき対象」と一様に訳されているのです。
しかしながら、この語のパーリ語形を見ると話しが少し変わります。何故ならば、smṛtyupasthānaのパーリ語形satipaṭṭhānaは、その構成・語義を二種に解釈することが出来るためです。一つはサンスクリットの場合と同様の、sati + upaṭṭhāna。また一方は、sati + paṭṭhānaです。
後者の解釈は、サンスクリットの綴りから見たならば決して妥当なものではありません。しかし、サンスクリットを意識せず、ただパーリ語の綴りだけから見た場合、samdhī(連声)の関係上、そのようにも解釈することが可能となります。実際、このことからパーリ語に依って仏典を伝えてきたセイロンの上座部では、この語について二つの解釈が行われていました。
(サンスクリット√sthāはパーリ語の場合√ṭhā。)
| - | 構造 | 意味 | |
|---|---|---|---|
| satipaṭṭhāna | sati (√sar+ti) |
upaṭṭhāna (upa+√ṭhā+ana) |
念の現出 念の留まる所 |
| paṭṭhāna (pa+√ṭhā+ana) |
念の確立 念の出立 |
||
パーリ語の場合、このように「upa + √ṭhā」と「pa + √ṭhā」との二様に理解し得ます。後者の[P]pa-([S]pra-)は、「先に・前に」を意味する、あるいは続く語の強意をする接頭辞です。その故に、paṭṭhānaという語はまた二様に理解することが出来ます。前者の意味では「前に立つ」で、「出発」・「進行」・「旅立ち」・「原点」・「原因」さらに「(何事かを得る)手段」・「方法」などの意。後者の強意で解する場合には、「確立」・「起立」といった意味となります。
paṭṭhānaと言えば、上座部の阿毘達磨七典籍の最後に挙げられる論書、Paṭṭhānaの題目に同じです。これは前者の意味で云われているもので、その故に近現代の日本の文献学者によって『発趣論』と訳されています。
このPaṭṭhānaという語は例えば、多くの場合、蔵外文献として扱われるPeṭakopadesa(『蔵釈』)に、samatha(止・奢摩他)の定義において用いられています。
tattha katamo samatho? yā cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti ṭhānaṃ paṭṭhānaṃ upaṭṭhānaṃ samādhi samādhānaṃ avikkhepo avippaṭisāro vūpasamo mānaso ekaggaṃ cittassa, ayaṃ samatho.
この止〈samatha〉とは何であろうか?なんであれ心の止住〈ṭhiti〉・平静〈saṇṭhiti〉・定立〈avaṭṭhiti〉・住処〈ṭhāna〉・確立〈paṭṭhāna〉・停留〈upaṭṭhāna〉・三摩地〈samādhi〉・定〈samādhāna〉・不悔〈avikkhepa〉・平安〈vūpasama〉・意の寂静なる心、これが止である。
KN. Peṭakopadesa, Suttatthasamuccayabhūmi
ここではひとまずpaṭṭhānaを文脈上「確立」と訳しましたが、以上のように、それはsamatha(止)を定義する一節にて見られるもので、同根(√ṭhā)のṭhānaとupaṭṭhānaとが共に挙げられています。止(samatha)を定義するため、ṭhānaとpaṭṭhānaとupaṭṭhānaとの語が併せて用いられているのですが、いずれにせよ「心の確たるもの・状態」を示すものであって、この場合、さしたる意味の違いが認められません。
現在の上座部では、むしろ先に挙げたもののうち後者の解釈を主に採っており、それは蔵外の注釈書や復注書などに多く見られます。以上のことから、satipaṭṭhānaを、sati + paṭṭhānaであると理解する場合、これを平易に言ったならば、自らの念を確固としたものにすること、念を確立することを意味したものとなります。