慧雲寥海とは、近世慶長年間、俊正明忍と共に戒律復興を成し遂げた律僧の一人です。生国は和泉であることは知られていますが、その他の出自と生年とは不明です。なお、諱ははじめ道渓としていたのを、(おそらくは明忍らと自誓受戒して比丘となった)後に変えて寥海としたようです。
慧雲は幼年から法華宗にて出家しており、長じてからは特に支那の天台教学に通じた学匠として洛西桂の某寺にあり法筵を開いていたと言います。しかし、より多くの布施を得るために世俗に迎合した説を競って仏教の名のもとに説くなどしていた同じ日蓮宗僧らの堕落した有り様を嫌い、それはいわゆる「説法とは物取り・銭取り」としていたということで現在も広く日本仏教の僧職者ら全般に全く変わらず見られることですけれども、そんな彼らと共にあることを願わず、避けていたといいます。
そして、例えば日蓮宗の僧徒には自ら「上人」を称しまた他称する習慣があって、それは現在に至るまで続いていますが、慧雲はそれを自身を含め門弟らにも決して許さなかったようです。そんな慧雲はついに、結局自身も顧みたならば正しく戒を受けず、持さぬ無戒の者であることに気づいたのでしょう、またそのような状態で僧を名乗って檀施を受けることを決して善しとせず、寺を出て丹波に行って炭焼きにまで身を落として生活するようになっています。
それは決して生半可な決意で到底なし得ることではありません。そのような生活であっても、しかし内実無く僧を騙って布施を受けるよりはよほど良いと考えてのことであったのでしょう。けれども、幼少より出家し、多くの僧徒が出家を称しながら俗界の名聞利養を多くえることを目的にそうしていたのと異なり、ただ解脱を求めてこそ仏法を学んできた慧雲にとって、やはり在俗にて生活する中で様々な日常の出来事に心を惑わされることは不本意極まりないことであったようです。未だ不退転の境涯に至らず、出離の道半ばでその志を捨てきれなかったのでしょう。
そのような意味で悶々とした生活を送る中、失意のうちに奈良の旧跡・霊跡を当て所もなく経巡っていたある日、偶然にして同じく真に出家たりえるその術を探して奈良の諸寺を巡っていた俊正明忍と、期せずして三輪山の麓〈平等寺?〉にて出逢っています。それは宿世の因縁によるもの、まさに運命であったと言える劇的なものでした。
上に述べたそこに至るまで経緯は、本稿にて紹介している『慧雲海律師伝』にても極簡単に触れられていますが、実は『明忍律師之行状記』においてより詳細に伝えられているため、以下にその出逢いについて語られている一節を示します。
爰ニ惠雲道渓トテ日蓮宗ノ學匠アリ幼年ニシテ入道シ攝州堺ノウラニ住、十歳ナルラン、施齋ヲウケテ親里ノ家ニイタリヌ親里兒心ヲナグサメントテ施物ニ錢ヲ與しに取モチ寺ニカヘリ佛前にサシ置、涙ヲナカシ、カカル物如何スヘキコトハリヲ明ラムル出家にならはやとて祈願セシトカヤ年漸かさなるにそへて才智多聞ナリシカハ彼衆ノ諸侶、專能化と仰ク洛西カツラト云處ニテ徒衆ヲ御シテ法花等を講セリ始ヨリ專ラ出離解脱ニ學セシ故ニ章安妙樂ノ祖意ヲ得テ世ニナソラヘテモタシカタク外ハ日蓮の流ヲクメトモ内ニハ邪濁ヲ嫌テ入ルコトナシ常ニ法花一實ノ理ヲホカラカニセリ皆人觀行卽ノ惠雲ト呼リ
門侶活命ヲ競テ邪法弘說セルヲウラミテ上人號ヲトルヘカラスハ我カ會下ニ來テ學スヘシトテ門弟ニ一紙ノ起請ヲカヽセテ講談セルトナン猶虛名無實ノ受施鐵湯ヲ飲ノ因ナルコトヲナケイテ持戒ニアラサレハ出家ニアラス出家ニアラアラスンハ壇施ヲ受ンヤトテ丹波國ニ身ヲカクシスミヲヤキワラタツヲ作テ生命ヲクリシカ凡心境ニ隨フノナケキ又アリシカハ是ヨリ南都ニ行、霊跡ナツカシク滅法ノナケキ我ノミニ覺テコヽカシコサマヨエルトナン此時三輪ホトリニシテ忍師ト行會テ懐セルニ兩師ノ所存宛乳水ノコトシ手ヲ打涙ヲナカシテ倶ニ興起正法ノ契約ヲナス
ここに恵雲道渓〈自誓受具後に諱を「寥海」と改名〉という日蓮宗の学匠があった。幼年ながら入道〈出家〉し、摂州の堺浦に住んでいた。十歳になった頃であろうか、施斎〈食事の招待〉を受けて親里の家を訪れた。親が(早くして出家した)子の心を慰めようと施物として金銭を与えてきたので、(幼い恵雲は)それを取り持って寺に帰り、仏前に差し置いて涙を流しつつ、「このような物をどのように取り扱うべきかの理を明らかにする出家者になりたい」と祈願したことがあったという。それから年月を重ねていくに従って才智優れ、博学多聞となっていったため、法華衆の僧侶らは専ら彼を能化〈師範〉と仰いだのであった。そこで洛西の桂という処で徒衆を指導し、『法華経』等を講じていた。(恵雲は幼少に出家した)始めより専ら出離解脱を目的として修学してきたが、章安大師〈天台宗第四祖、灌頂〉や妙楽大師〈天台宗第六祖、荊渓湛然〉などの祖意を会得して世間〈恵雲の周囲。日蓮衆徒らの有り様〉を眺めてみたならば看過できないことは多く、外儀〈外面。立場〉は日蓮の流れを汲んだものではあったものの、内心では(日蓮宗徒らの)邪濁な振る舞いを嫌って交わらなかった。そうして常に法華一実〈一乗真実〉の理を明らかにしようと勤めていた。(そのようなことから)人は皆、「観行即の恵雲」と称賛していた。
(恵雲は、同じ日蓮宗の)門侶らが、より多くの収入を得ようとして競って邪法を人々に説法しているのを悲しみ、「(邪命説法する他の日蓮宗徒らのように)上人号を名乗らないのであれば、我が会下〈門下〉に来て学ぶことを許す」として、その門弟らに一枚の起請文を書かせてから講談していたということである。そうしてさらに、(結局は恵雲自身も含めて無戒であって)虚名無実〈名ばかり形ばかりで内実が全く無いこと〉の僧が(信者らから)布施を受けることは、(来世に地獄に堕して)溶けた鉄を飲んで苦しむ因となることを嘆き、「持戒者でなければ出家ではない。出家でないならば、どうして信者から布施を受けることが出来ようか」と言って(日蓮宗僧たることを捨てて)丹波国に身を隠してしまい、炭を焼き、藁を編むなどして生計を立てるようになった。しかし、(堕落した寺門から脱し、質素で静かな俗に身を置いたとしても、自らの)凡心が見聞覚知する境〈対象〉にたちまち惑わされることへの嘆きは依然としてあったため、意を決して丹波から南都に行って(その昔まだ仏法が盛んであった時の)霊跡に心惹かれつつ、「仏法は已に滅んでしまったか」と嘆きを懐くのは自分のみであるかのように思いながら、ここかしこと彷徨っていたのであるという。そんな時、三輪山〈三室山〉の辺りにて忍師〈明忍〉と行き逢った。互いにその志を述懐したところ、二人の懐いはあたかも乳水がたちまち相交わるかのように通じたのである。(二人はそのあまりの感動に)手を打ち、涙を流して倶に正法を興起せんとの契約を交わした。
『明忍律師之行状記』(西明寺文書)
明忍との劇的な邂逅を果たした後、慧雲と明忍とは共に西大寺に行きます。
すでに当時、西大寺はかつてのように持律峻厳の道場などではなく、誰も律など実際に守りも行いもせぬようになった、律宗とは名ばかりの看板を揚げた寺の一つとなっていました。しかしそこには、鎌倉期の嘉禎年間、叡尊らによって果たされた戒律復興の術であった通受自誓受の法式、あるいは戒律についての典籍と知識、いわゆる律学がいまだ保存されていました。
西大寺にて律学を学ばんとする時、また期せずして志を同じくする僧と出逢っています。その名は友尊全空、西大寺僧であった人です。彼ら三人は、そもそも正しく出家とは何かを律蔵および南山大師道宣の諸論に深く訪ね、またどのように鑑真によってもたらされた律が嘉禎二年〈1236〉の昔に復興されたかを西大寺にて学んでいます。
そしてついに慶長七年〈1602〉、慧雲と明忍そして友尊の三人に加え、明忍の師にして高雄山神護寺の中興、守理晋海そして玉圓空渓の五人は栂尾山高山寺の春日社・住吉社前において、叡尊らがしたそれに倣って自誓受による受具を果たし、ついに念願であった比丘、すなわち正しく仏教の出家者となっています。
その後、晋海による経済的支援を受け、栂尾山高山寺と高尾山神護寺の間にあった槇尾山平等心王院の荒廃し尽くて寺名だけ残っていたのを律院僧坊とするべく、その礎を築いています。しかし、晋海の後援を受けたといっても神護寺の御朱印地二百六十二石からわずか三十五石ばかり。彼の地に諸堂伽藍を整備するには全く不十分であったようです。
実際、自誓受具の後すぐに彼らが平等心王院を律院僧坊として腰を据え活動したということはなく、神護寺の子院に間借りしつつ、また慧雲と明忍とは奈良の西大寺の塔頭に滞在して『行事鈔』をほとんど間断なく、一年近く掛けて講義するなどしています。その間、友尊も平等心王院に入ってはおらず、あるいは西大寺に戻っていたのかもしれません。
そうこうするうち明忍は、いくら覚盛や叡尊らによってその昔行われたものであるとは言え、いわば緊急避難的受戒法であった通受自誓受だけでなく、やはりどうしても本来の受具の方法である現前の十比丘いわゆる三師七証による、別受従他にての受戒を改めて受けること求めて、明代の支那に渡ることを決意。そして慶長十一年〈1606〉、ついに明忍師は槇尾山を離れ、支那に渡るべくまず対馬に旅立っています。それは彼らが比丘となって足掛け五年を経ていた時のことです。
俊正明忍律師はその戒律復興における旗手でありその先頭に立った人で、平等心王院の初代住持であり、律が再び復興されたとの噂を聞いた諸方諸宗の持戒持律を志す人々がその門を叩いていました。そしてそれぞれ改めて沙弥として律師らの門下に入り、律学に励んでいたのです。しかし、ここに明忍はその後を慧雲ならびに友尊に託し、求法のため不退の決意のもと旅立っています。
この外国へ求法の旅に出ようとした明忍律師の後ろには、その昔同じくそうしようとして果たせなかった明恵上人への思慕もあったことでしょう。実際、明忍は明恵上人手づからの書をいくつか筆写しており、明忍が叡尊だけでなく明恵を深く敬していたことは間違いありません。
さて、そこで慧雲は明忍の後を託されて平等心王院の第二代住持となり、その門下に集った衆僧を領して指導にあたっています。そして、第二代住持となってから五年後の慶長十六年〈1611〉、慧雲と明忍らのそれに次ぐ二回目の自誓受具が平等心王院にて行われています。その時、自誓受具した者の数は十一名。その中には後に高野山真別処に円通寺を開き、また法隆寺北室院を律院僧坊とするなど近世興律の立役者の一人となった賢俊良永もいました。
賢俊とは、もと高野山にて出家していた対馬の宗氏出身の真言僧で、受具する以前に明忍に対馬にて偶然出逢っており、その指示によって槇尾山にて正式に沙弥として出家し、入門しています。時は慶長十五年十月のことです。賢俊は明忍その人ではなく、まさに慧雲の弟子として改めて沙弥出家したのでした。
(賢俊良永については別項「戒山 『霊嶽山圓通寺賢俊永律師伝』」を参照のこと。)
その時、これは必ず留意しておかなければならない点ですが、すでに友尊は慶長十五年六月二日に没して無く、また明忍もその五日後の同年六月七日の対馬にて示寂していました。
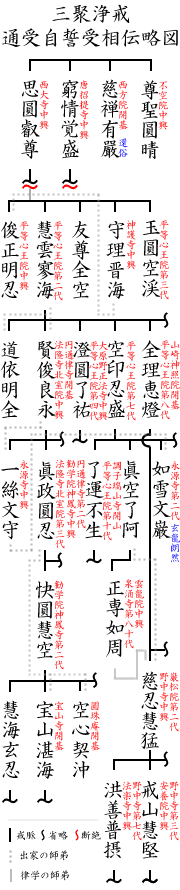
ところで、今一般に、近世の戒律復興の有り様を知る人は僧職者および学者にも極限られており、しかも特に重要であると言えるその黎明期について研究する学者など片手で数えられるほどで、時折それに触れる者が思い出したかのように現れはするものの継続されず、その全貌はいまだ明らかとされていません。そもそも近世の日本仏教は全般的に、僧職者らにも学者らにも軽視されてきた歴史があるようです。また、そのような極少数の学者や僧職者が近世の戒律復興の系図・戒脈を作るときには、その全ての人が全く単純に明忍を起点とし、慧雲にまったく触れず記すこと無く、それぞれ後続の律僧らへと適当に線を引くことが行われています。慧雲律師は、明忍律師の介添え役、いわば刺し身のツマ程度に扱われているのです。
しかし、これは正しくない。明忍が近世復興の立役者でその象徴であったことは確かであり、その後の法孫となった律僧らが明忍を始祖として仰ぎ敬したことも間違いはありません。そして、慧雲もまた、それから程なくして慶長十六年あるいは十七年に没しており、興律して後にその門弟を育てるための活動の期間は決して永いものではありませんでした。
(慧雲の没年月日については伝承に混乱があり、今の所それが正確にいつであったか確定されません。詳しくは本文脚注に記す。)
けれども、本書『慧雲海律師』にて著者戒山も述べているように、実際にその後の律を志した者らの師となり、その指導にあたったのは慧雲でした。そして慧雲と明忍とは師弟の仲であったのではなく、まったく同列なる同志であり、どちらが欠けても興律は果たし得なかったと言える存在であった人です。
その意味では友尊も玉圓も、そして晋海も同じではありますが、やはり慧雲が明忍の跡を継いでおり、実際に重要な位置にあったからこそ、戒山も『律苑僧宝伝』にその伝記を記したのでありましょう。むしろ、なぜ友尊と玉圓の伝記がまったく無いのかが不審なほどです。よってその系図を引く時、慧雲に触れないのは全く正確ではない。いや、明忍と慧雲とを同列に示した上で、むしろ慧雲からその系図を引いていかなければなりません。
(ただし、通受自誓受の場合、本来の別受従他受による受具の戒脈と全く異なって、実態を伴った戒和尚も教授師、羯磨師の存在など無いため、その証明師の系譜ということになります。)
確かに、ここに紹介する『慧雲海律師』は明忍律師やその他の律師伝に比して短く、極簡略なものではあります。しかし、繰り返しますが、慧雲もまた近世の興律運動において掛け替えない重要な人です。それをまた微力ながら世に伝え明らかとするため、ここに拙訳を併せて慧雲の行業を示します。
興律は決して誰か優れた一人が出現することでなしえることなどでは到底無く、これは「絶対に」四名以上、出来うることなら五名以上の同志が必要なことです。僧伽の成立と存続にはそれだけの人数が不可欠であるためです。ただ一人孤軍奮闘せんとして気焔をあげたところで、それは後代の結縁にはなるでしょうけれども、今どうにかなるものではありません。
さて、今から四百年ほどの昔の日本において、短きながらもかくも熱い求道求法に命を燃やし、その後の律僧らに強い影響を与えた僧らがあったことを多くの人が知り、その伝承がある限りは決して立ち消えぬ熾のようにある遺志を、いつかまた灯して世に掲げる人々の現れることを願ってやみません。
小苾蒭覺應 拝記