賢俊良永とは、江戸前期に日本仏教諸宗諸派における興律運動の一端を担った僧です。もと高野山にて出家した真言宗徒で、京都の槇尾山平等心王院に参じて比丘となった人です。槇尾山を離れた後は、高野山に還って圓通寺(真別処)を律学の道場として復興し、また法隆寺北室院を中興して律院として定めたことで知られています。
賢俊は天正十三年〈1585〉、対馬の守護代であった宗氏の子として誕生。幼年から高野山に登って出家し、真言を修学しています。賢俊は日頃から密教であれ仏教の肝要は戒律にあることを思い、その護持を望んでいたといわれます。しかしながら、当時はそれを正しく受け、行う術など高野山はもとより日本の何処にももはやありませんでした。
そんな中、賢俊は起居していた高野山金剛峯寺の子院の一つ、中性院にて俊正明忍の存在を聞かされ、知ったようです。明忍は慶長七年、その他四人の同志と共に自誓受戒による戒律復興を成し遂げた後、槇尾山平等心王院を復興して律院僧坊とした戒律復興の旗手であった人です。なぜ賢俊が遠く離れた京の明忍の存在と動向を比較的早い時期(慶長八年頃)に知り得たかと云えば、明忍の師である晋海 と高野山の中性院との間に繋がりがあったことが知られるためです。
そこで賢俊が対馬に里帰りしていた折、本来の正統な受戒法である別受従他受を求めて支那に渡らんとして対馬に逗留していた明忍に邂逅、というより中性院にてその動向をある程度掴んでいた賢俊は敢えて会いに帰ったのでしょう。そして賢俊は、明忍に会うや自身に律を授けることを請うたとされます。しかし、賢俊は、明忍の弟子となることを断られ、槇尾山に赴いて修学・受戒すべきと答えられています。これは明忍が自ら謙譲して断った、という類の話ではありません。そもそも誰であろうと比丘一人が律を人に授けるなどことは出来ず、また当時の明忍には人の師となる資格はまだ無く、賢俊を弟子とすることも出来ないため、最初から賢俊の願いは無理な話でした。おそらく、賢俊はそのような僧としてごく基本的なことをいまだ知らず、為に明忍に無理な願いを申し出たのでしょう。
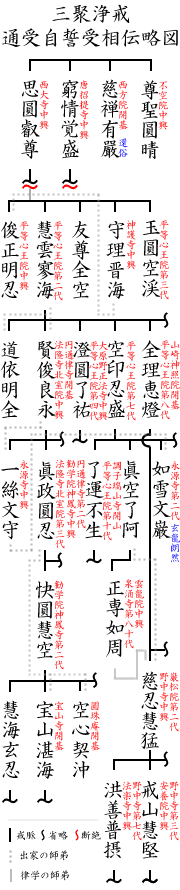
そこで賢俊はその勧めに従って平等心王院に入ることになるのですが、対馬から帰って直ちに槇尾山に向かったということでもなかったようです。それは賢俊が高野山を下山するにあたっての準備が必要であったのか、その何年か後のことであり、すでに明忍は対馬にて没していました。慶長十五年〈1610〉十月、賢俊は、槇尾山にて明忍の同志であり平等心王院第二代衆首を継いでいた慧雲を師としてその弟子となり、改めて沙彌戒を受け交衆したのでした。そして、その翌十六年〈1611〉三月には他十名と共に自誓受戒し、晴れて比丘となっています。
(学者の中には、賢俊をして明忍の弟子であったとする者が多くありますが誤認です。賢俊が明忍に私淑したということはあるかもしれませんが、現実の師となり律の実際を教授したのは慧雲であって、明忍では決してありません。)
ところが賢俊は、その年の夏安居を終えて法臘ようやく一歳になったばかりにも関わらず、槇尾山を離れて高野山に帰りたい旨を申し出ていたようです。しかし、それを槇尾山の他の衆徒は許さず争議となっています。なんとなれば、律には新学の比丘はその和上あるいは阿闍梨のもとで、五夏の間は必ず依止しなければならないという規定があるためです。
結局、この争議は幕府〈京都所司代〉が取り扱うにまで発展。ついに賢俊は、ただ一夏を過ごしただけで槇尾山を離れることを幕命として許されています。それに対し一方の槇尾山は、今後は律に基づき、新学の比丘は誰人たりとも五夏の依止を過ごすこと無く離れてはならないことを寺規として定めることを、これも幕命として制されたといいます。
なお、賢俊がそのような争議を起こした時、当然明忍は対馬に没して無く、友尊は明忍に先んじること五日の慶長十五年六月二日に逝去しており、また明忍の師であった晋海は翌十六年三月二日に示寂していました。すなわち、賢俊が槇尾山にて沙弥出家し、自誓受具してすぐ迎えた夏安居を終えた時、明忍ら戒律復興を果たした五人のうち、残っていたのは慧雲と玉圓のみです。
(賢俊の師であった慧雲は慶長十七年二月二日に、玉圓は同年四月十八日に遷化。)
ところで、賢俊が槙尾の僧衆を相手に一夏を過ごしたのみで槇尾を離れるため争議を起した経緯を少しく述べる、しかし唯一のもの、『三国毘尼伝』なる書が高野山に伝わっています。そしてそこには諍論の相手は慧雲と友尊であったとされています。けれども、慧雲はともかく友尊の名が挙げられているのは本来ありえないことです。そして、慧雲が賢俊にとって正式な出家の師(出家阿闍梨)であったことからすれば、慧雲に対して争いを起こしたとも考えにくいことです。『三国毘尼伝』は賢俊から下ること百年余りの後の圓通寺の門流、密門本初によって著されたものですが、この点に関する記事の信憑性は高くありません。いずれにせよ、賢俊がなぜそのような争議を生じたかの動機をその言葉として伝えたものでなく、そもそも賢俊自らがこれについて書き遺した書など無いため、実際のところは全く不明です。
自ら持律を志しておきおながらそれに反し、また衆僧の反対にも関わらず自らの主張を公儀まで巻き込んで、律に依るのではなく政治の力によって押し通したとされる賢俊の行動は暴挙といって過言ではなく、全く解し難いものです。そのような訴えを扱った所司代は、当然仏教における律の規定など知っていよう筈もなかったのですが、その双方の主張に理があるとして、賢俊のみ例外として一夏で僧房を離れることを聴し、以降の余人は誰も許さないと評決したとされます。
ところが、そのような諍論を経て槇尾山を離れたのであれば、当然その後の槇尾山と賢俊とは決裂して没交渉となったかといえばそうではありません。実は賢俊は槇尾山を退衆しておらず、その後も槇尾山を本寺とする衆徒として関係は続いているのですから、どうにも不思議です。しかしその事実は、賢俊が諍いを起こしたとはいえ、自身が独立して何事かせんとするつもりは全く無かった、ということではあるのでしょう。
いずれにせよ、政治を巻き込こんだ結果として自身の希望通りに高野山に帰った賢俊は、その後、東南院で蟄居させられていた山口重政の後援を得たことにより、高野山の奥深い地の新別所と言われていた地に霊巖院圓通寺を建立。ここを高野における律の道場として衆徒に律学を講演し、行じていく拠点として弟子を育成しています。弟子の中には特に圓通寺二世を継いだ眞政圓忍があり、またこの流れから快圓恵空など数々の優れた僧が出ています。その後、賢俊は高野山圓通寺を弟子眞政に託して離れ、槇尾山にて同時に自誓受した了性明空と共に法隆寺北室院を律院として定めてこれを中興、その第一世となって活動しています。
ところで、賢俊が槇尾山を一夏で離れることを政治的に許されたことをもって、賢俊の元では他派他宗の僧がより自由に具足戒を受けられるようになったと考え、その後の律宗以外の諸宗に生じた興律運動に大きな貢献を果たしたと評価する幾人かの学者があります。しかし、それは戒律について知識が乏しく、またその後の流れや問題を無視した誤認に基づいた、まるで宛ての外れた評価です。
例えば、「比丘となるのに五夏を要せず、ただ一夏で比丘となることを賢俊は可能にした」等といった類の幾人かの学者らに依る言説、その見方は、比丘とは何か、具足戒とは何かなど、極めて根本的なところを全く理解していない無知に基づいたものです。戒律研究、戒律史研究などに従事しながら、そもそもその戒律のごく基礎的知識をよく知らず学ばずその研究者を称する者は、今案外多く見られます。
さて、正保四年〈1647〉、賢俊は河内の叡福寺にて逝去。享年六十三、法臘三十六。その墓は圓通寺境内にあります。
賢俊は、鎌倉期以来の律僧らがしばしばそうしたような浄土往生を願わなかった、と伝えられています。これはいわゆる大悲闡提の誓願を、賢俊が立てていたであろうことを示すものです。そのような意志は、あるいは自身もその法系に連なる叡尊の言葉(『興正菩薩御教誡聴聞集』)や忍性の行業などに影響されたものであったかもしれません。
なお、賢俊の伝記には他に、元禄十五年〈1702〉、臨済宗僧の卍元師蛮によって著された『本朝高僧伝』巻六十三 浄律五之七に収められた『紀州高野山沙門良永伝』としてがあります。が、それはこの『霊嶽山圓通寺賢俊永律師伝』(戒山『律苑僧宝伝』所収)をもとにただ簡略して書かれたものに過ぎません。『本朝高僧伝』に載せる近世の律師らの伝記は、同様にほとんど全て『律苑僧宝伝』における伝承をなぞりまとめたものです。
賢俊が槇尾山にて一年も経たずうち、ただ一度の夏安居を過ごしただけで去ろうとしたことが槇尾山の衆徒との間で争議となり、実際に去ってしまったことについて、その何が問題であったのか。それについて知るには、まずそもそも依止について、いや、和上(和尚)と阿闍梨とがいかなるものかを正確に知る必要があります。
和上とは何か、なぜ和上というものが定められたのかを知るには、律を見るのが最も適しています。
爾時尊者欝鞞羅迦葉。將諸弟子出家學道。刪若弟子。亦將二百五十弟子出家學道。羅閲城諸豪姓子。亦出家學道。大衆皆集遊羅閲城。時彼未被教誡者。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時有一病比丘。無弟子無瞻視者命終。諸比丘以此因縁往白世尊。世尊言。自今已去聽有和尚。和尚看弟子。當如兒意看。弟子看和尚。當如父意。展轉相敬。重相瞻視。如是正法便得久住。長益廣大。
その時、尊者欝鞞羅迦葉〈Uruvela-Kassapa〉は諸々の弟子と共に出家学道し、 刪若〈Sañjaya〉の弟子もまた二百五十人が出家学道し、 羅閲城〈Rājagṛha. 王舎城〉の豪族の師弟らもまた出家学道した。それら(出家して比丘となった)大衆が皆集まって羅閲城にあった。しかしそこで、未だ(比丘として)教誡を受けていない者が、その威儀を正さず、衣も正しく着られず、乞食も如法に行わず、あちこちで不浄食〈律の規定に反した食事〉を受け、あるいは不浄鉢食〈律の規定に違反した托鉢で得た食事〉を受け、小食〈粥食〉・大食〈中食〉において声高に騒ぐなど、まるで婆羅門〈brāhmaṇa. 婆羅門。インド教の祭式執行者〉の聚会法のようであった。またその時、ある病に罹った比丘があったが、彼には弟子が無く、また看病する者も無くて独り死んでしまった。そこで比丘たちはこれらの顛末を世尊に報告した。すると世尊はこのように言われた。
「今より以降、和上のあることを許す。和上がその弟子を看ることは、まさに父が子を看るようにしなければならない。弟子が和上を看ることは、まさに子が父を看るようにしなければならない。相互に尊敬しあい、互いに見守り合わなければならない。そのようにすれば、正法は久しく世に行われ、その利益は広大なものとなるであろう。《後略》」
『四分律』巻三十三 受戒揵度之三(T22, p.799b)
そもそも言葉としての和上とは、「先生」・「教誡師」を意味する、[S]upādhyāyaあるいは[P]upajjhāyaなどインド語から直接でなく、コータンなど中央アジアの胡語に転訛した語の音写です。よって、転訛した語からのいわば誤った音写ではなく、サンスクリット原語であるupādhyāyaを忠実に再現しようとなされた玄奘による新訳の音写では、鄔波馱耶とされています。確かにこの音写は比較的正確と言えるもので、日本では多く授戒法則にて用いられる語となっています。漢訳ではこれを親教師または力生とされますが、一般にあまり用いられません。
日本では、和上とは僧侶の敬称、あるいは称号や階級・地位の名称であると解している者が多くあります。しかし、和上とは本来、まず僧侶個々人が受戒して比丘となる際の個人的な師僧のことであり、比丘となって後にはその膝下にて様々な教えを親しく請い、諸々の行儀作法を習う比丘のことです。
そんな和上すなわち師僧というものが仏陀の指示によって定められた経緯は、いま上に示した律蔵の一節にあるように、他の宗教の徒弟や豪族の子弟らが仏教の比丘となりはしたものの、先輩比丘から何も出家者としての行儀作法を教わらず、はなはだ見苦しい様相を呈することがあったためです。また、すでに比丘となっていた者が、その弟子も看病者も無かったがために、独りそのまま亡くなってしまうことがあったためでもありました。
すなわち、比丘僧伽における和上の制定は、新学比丘の教育目的を第一とし、併せて旧比丘が病床に臥せった際の措置、いわば孤独死を防ぐ策としてもなされたものです。そしてその和上と弟子との関係は、あたかも世俗の父子のようなものでなければならず、相互に尊敬しあい、また(互いに信頼し合っているからこそ)その非を指摘し合い、高め合う関係でなければならないと位置づけられています。
出家というものは、世俗の家族から離れ、また妻帯などして家庭を持たず、僧伽という脱俗の自治組織において暮らすが故に、むしろそのような年少者と年長者といった個々人の関係が父子のように尊敬と信頼、愛情あるものでなければならないと、ある意味必然的に形成されたものです。
もっとも、この時、比丘となるといっても、現在知られているような三師七証・白四羯磨による受戒などというものは未だ制定されていませんでした。ただ仏陀から直接に「善く来たれ比丘よ!」などと声をかけられることや、仏陀によって比丘となった弟子のもとで三宝に帰依し、出家の意志を示すだけで比丘となっていたのです。いわゆる善来受具、三語受具です。
むしろこの和上の存在が制定されたことをきっかけに、それまでの善来受具および三語受具によって比丘となることは許されず、三師七証・白四羯磨による受戒を標準とすることが定められたのでした。
そして比丘が、和上(師僧)となって弟子をとって具足戒を授けるためには、比丘となって最低でも十年を過ぎていること、法と律とに通じていること、智慧高くまたその行業が正しく、年少者を教導するに足る人徳あることが、その必須の条件として定められています。比丘となって十年たってさえいれば、誰でも彼でも和上となって弟子を持てるなどということではありません。
次に依止とは、原則として自身の師僧たる和上のもとで様々な教導をうけることを言う言葉です。人は具足戒を受けるたことによって直ちに比丘となることが出来ます。しかし、具足戒を受け比丘となることはその最初の一歩を踏み出した過ぎず、比丘としての行儀など多くの事柄をその師から学ばなければなりません。
しかしながら、もし自身の和上が死去してしまった場合はどうするか。実際にそのような事例があり、その対処として以下のように定められたことが律蔵に伝えられています。
時諸新受戒比丘。和尚命終。無人教授。以不被教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。 在大食小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法無異時諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去聽有阿闍梨聽有弟子。阿闍梨於弟子當如兒想。弟子於阿闍梨如父想。展轉相教。展轉相奉事。如是於佛法中倍増益廣流布。
ある時、諸々の新たに受戒したばかりの比丘の和上が命終し、その者に教授する人がなくなってしまった。(その新学の比丘は)教授する者がなくなってしまったが為に、その威儀を正さず、衣も正しく着られず、乞食も如法に行わず、あちこちで不浄食〈律の規定に反した食事〉を受け、あるいは不浄鉢食〈律の規定に違反した托鉢で得た食事〉を受け、小食〈粥食〉・大食〈中食〉において声高に騒ぐなど、まるで婆羅門〈brāhmaṇa. 婆羅門。インド教の祭式執行者〉の聚会法のようであった。そこで比丘たちはこれらの顛末を世尊に報告した。すると世尊は数々の方法によって(その新学の比丘を)呵責し、その後に比丘達に告げられた。
「今より以降、阿闍梨のあることを許し、その弟子あることを許す。阿闍梨は弟子を父が子を想うようにし、弟子は阿闍梨を子が父を想うようにせよ。互いに教え合い、互いに仕え合え。仏法の中においてそのようにすれば、その利益はますます広大なものとなるであろう」
『四分律』巻三十三 受戒揵度之四(T22, p.799b)
阿闍梨とは、[S]ācāryaあるいは[P]ācariyaの音写で、その意は先生・教師。より正確に阿闍梨耶と音写された語もしばしば用いられます。漢訳では規範師などともされますが、語義としては和上に同じです。ただし、仏教においては、和上とは自身が比丘となるに際しての師匠であってある意味特別な意味が込められたものであるのに対し、阿闍梨とは一般的な先生のことをいう語として用いられます。
(密教における阿闍梨の定義や位置づけはごく特殊なものであり、特に『大日経』および『大日経疏』に基づくもので、律蔵において定められる本来のそれと全く異なることに注意。)
和上が死去するなどした際だけではなく、何か所用で遠出して不在となったとき、あるいは和上が還俗してしまった際にもまた、その代わりとして依止すべき人が新学の比丘にはどうしても必要となります。そのような人のことを阿闍梨、この場合は特に依止阿闍梨と言います。そしてやはり、そのような依止しえる阿闍梨もまた、和上に同じく具足戒を受けて十年以上経ており、経律に詳しく、威儀を知り、よく人を教導しうるなどの必須とされる諸条件が定められています。そして、阿闍梨と新学の比丘との両者の関係は、和上と弟子との関係と全く同様に父子のようでなければならないとされます。このような師弟の関係、それぞれのあり方は和上法や弟子法などといって律蔵に規定されています。
そしてまた、新学の比丘は最低でも五年、十歳以上の比丘に必ず依止しなければならない、と定められます。それは以下のような顛末によるものです。
爾時世尊。遊羅閲城。時欝毘羅迦葉。將諸徒衆捨家學道。刪若弟子將二百五十弟子捨家學道。羅閲城中有大富豪貴家子亦出家學道。如此大衆等住羅閲城時諸大臣自相謂言。今諸外道出家學道。春秋冬夏人間遊行此沙門釋子。聚住此間不餘處遊行。將由此處爲最勝故。爾時諸比丘聞已以此因縁具白世尊。世尊爾時告阿難。汝往房房勅諸比丘言。世尊今欲至南方人間遊行。若有欲侍從者各隨意。阿難受教。往房房語諸比丘言。世尊今欲往南方遊行。諸比丘若有欲侍從者各隨意。時有信樂新受戒比丘。白阿難言。若我等和尚阿闍梨去我當去。若不去我等不去。何以故 我等新受戒比丘。若去須依止。還此復當受依止。人當謂我輕躁無志爾時世尊。將少比丘。遊行南方。後還王舍城。時世尊觀南方遊行比丘衆少。知而故問阿難諸比丘何以故少。阿難具以上事白世尊。世尊。爾時以此因縁集比丘僧告言。自今已去。聽五歳有智慧比丘。十歳有智慧比丘。五歳比丘。應從十歳比丘受依止。若愚癡無智慧者。盡形壽依止。
その時、世尊は羅閲城〈Rājagṛha. 王舎城〉に留まられていた。そこで欝毘羅迦葉〈Uruvela-Kassapa〉は諸々の徒弟を率いて出家学道し、また刪若〈Sañjaya〉の弟子も二百五十人が共に出家学道し、羅閲城にある大富豪や貴族の子弟もまた出家学道し、その出家した大衆が羅閲城に留まっていた。そこで、この地の大臣らは口々に噂していた。
「今、多くの外道らは出家学道し、春秋冬夏の一年を通して世間をあちこち遊行している。しかるに沙門釈子らはこの地に集まり留まり、他所に遊行することが無い。あるいはこの地がもっとも優れて居心地が良いためであろう」
これを聞いた比丘らは、この話を詳しく世尊に報告した。すると世尊は阿難〈Ānanda〉に告げられた。
「汝は諸坊に行き、比丘たちに『世尊は今から南方に向かわれ、世間を遊行しようとされている。もし付き従って行こうと思う者があるならば、各自の意志のままに来たれ』と告げよ」
そこで阿難はその指示を受け、諸坊を廻って比丘たちに伝えた。
「世尊は今から南方に向かわれ、世間を遊行しようとされている。もし付き従って行こうと思う者があるならば、各自の意志のままに来たれ」
すると信楽〈喜びを伴う信仰〉ある新受戒の比丘が、阿難に申し上げた。
「もし私達の和上・阿闍梨が(仏陀に付き従って)行くのであれば、私もまた同じく行きましょう。もし行かれないのであれば、私達も行きません。なんとなれば、私達新受戒の比丘が、もし(和上・阿闍梨の元を去って仏陀と共に)行って(彼の地で誰かに)依止を求めたとしても、この地に還った時には再び(同じ和上・阿闍梨に)依止しなければなりません。すると(世間の)人々は、私達のことを軽薄で志し無き者らであると、噂することでしょう」
結局、世尊は幾人か少数の比丘らと共に南方を遊行され、後に王舎城に還って来られた。そして世尊は、共に南方に遊行した比丘衆が少なかったその訳を阿難に問われた。
「(共に南方に遊行した)比丘らは、どうして少なかったのであろうか」
阿難はその理由を詳細に申し上げた。すると世尊はその時、その経緯を聞いたことによって比丘僧伽を集められ、このように告げられた。
「今より以降、五歳にして智慧ある比丘と十歳にして智慧ある比丘とに、五歳の比丘は十歳の比丘に従って依止することを許す。もし智慧無き者は、(五歳を過ぎようとも)盡形寿〈生涯〉依止すること」
『四分律』巻三十四 受戒揵度之四(T22, p.805c-806a)
ここで初めて、受戒して比丘となった者で最低でも五歳を満ずるまでは、自身の和上あるいは阿闍梨など十歳以上の比丘に依止すべきことが定められています。そしてそれは、世間の批判や噂の生ずることを恐れた新学の比丘たちが行動を制限されることへの配慮としてなされたものでした。
しかし、この五年というのはあくまで「最低限」ということであって、能力の無い者は一生涯、誰か上座比丘に依止すべきとされます。誰でも五度の夏安居を過ごせば依止を必要としなくなる、という訳ではありません。
ここでさらに、和上と阿闍梨とは何かについて、総じて定義されている一節があるため以下に示します。
和尚者。從受得戒。和尚等者。多已十歳。阿闍梨者。有五種阿闍梨。有出家阿闍梨。受戒阿闍梨。教授阿闍梨。受經阿闍梨。依止阿闍梨。出家阿闍梨者。所依得出家者是。受戒阿闍梨者。受戒時作羯磨者是。教授阿闍梨者。教授威儀者是。受經阿闍梨者。所從受經處讀修妬路。若説義乃至一四句偈依止阿闍梨者。乃至依止住一宿。阿闍梨等者。多已五歳。除依止阿闍梨。
「和上」とは、(自分が)従って戒を得た者であり、和上等とは、多く已に十歳を超えた者である。
「阿闍梨」とは、これに五種の阿闍梨がある。出家阿闍梨・受戒阿闍梨・教授阿闍梨・受経阿闍梨・依止阿闍梨である。出家阿闍梨とは、所依として出家を得た者である。受戒阿闍梨とは、(具足戒の)受戒の時、羯磨をなす者である。教授阿闍梨とは、(具足戒の受戒の時、)威儀を教授する者である。受経阿闍梨とは、自身が経典を教わり習う処において、修妬路〈sūtra. 修多羅・経〉を読み、あるいはその意味を教え授けて、四句一偈以上に及ぶ者である。依止阿闍梨とは、自分が依止すること一晩以上の者である。「阿闍梨等」とは、多く已に五歳を超えた者である。ただし、依止阿闍梨は(十歳以上でなければならず)その限りではない。
『四分律』巻三十九 皮革揵度之餘(T22, p.848a)
ここに定義されているように、和上とは「(自分が)従って戒を得た者」、すなわち具足戒を受けた時の身元保証人である自らの師僧です。そして誰か人の師僧となるには、具足戒を受けてから最低でも十年を経ているのが必要不可欠とされることも前に述べたとおりです。
また阿闍梨という存在について、実は阿闍梨にはその役割によって五種あるとされるものです。受戒時に新たに受戒しようとする者に対してあれこれ指導する役、あるいは受戒を進行する役などを果たすことが出来るのは、智慧ある有能な五歳以上の比丘で、それも阿闍梨と呼ばれます。しかし、新学の比丘が依止出来るのは十歳以上の智慧ある有能な比丘であって、その他の阿闍梨とは異なるものとされます。
いずれにせよ、依止とは、受戒したその場所ではなく、自身が受戒した和上あるいはそれに相当する上座比丘という人物に「最低」五年以上付くことを意味するもので、その年月を過ごす間に比丘としての様々な素養を備えていくための、仏陀によって律に明示された規定です。