寄此略辨祇支覆肩二衣 初制意者。尼女報弱。故制祇支。披於左肩。以襯袈裟。又制覆肩。掩於右膊。用遮形醜。是故尼衆必持五衣。大僧亦有畜用。但是聽衣耳。二釋名者。梵語僧祇支。此云上狹下廣衣此據律文。以翻全乖衣相。若準應法師音義。翻云掩腋衣。頗得其實 覆肩華語。未詳梵言。三明衣相。僧祇二衣竝長四肘廣二肘。故知亦同袈裟畟方。但無條葉耳。四明著用世多紛諍。今爲明之。此方往古。並服祇支。至後魏時。始加右袖。兩邊縫合。謂之偏衫。截領開裾。猶存本相。故知偏衫左肩。即本祇支。右邊即覆肩也。今人迷此。又於偏衫之上。復加覆肩。謂學律者。必須服著。但西土人多袒膊。恐生譏過。故須掩之。此方襖褶重重。仍加偏袖。又覆何爲。縱説多途終成無據若云生善者。是僧應著。何獨律宗餘宗不著。豈不生善。況輕紗紫染體色倶非。佛判俗服。全乖道相何善之有。或云。分宗途者。佛教但以三學分宗。而謂形服異者。未之聞矣 且三衣大聖嚴制。曾未霑身。覆肩祖師累斥。堅持不捨。良以弊風一扇。歴代共迷。復由於教無知。遂使聞義不徙。更引明證。請試詳之。章服儀云。元制所興。本唯尼衆。今僧服者。僣通下位。又住法圖賛云。阿難報力休壯。圓備具足。士女咸興愛著。乃至目悦淨色。心醉神昏。繋子頸而沈殺者。由此曲制。令著覆肩之衣。今則僥倖。而妄服者濫矣據此乃斥内無偏衫。單覆者耳。若今重覆。彼時既無。不渉言限。且單覆猶爲僥倖況今重覆非法何疑。廣如別辨
漉水嚢第六物賞看病中。則以針筒爲六。今準二衣篇首列之
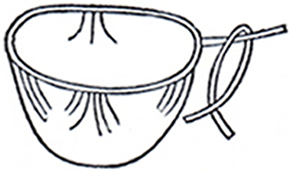
初制意鈔云。物雖輕小所爲極大。出家慈濟厥意在此。今上品高行。尚飮用蟲水。況諸不肖焉可言哉。四分不得無漉袋。行半由旬二十里也 無者僧伽梨角漉。二漉法者。薩婆多云。欲作住處。先看水中有蟲否。有者作餘井。猶有者捨去。凡用水法。應清淨者。如法漉置一器中。足一日用。令持戒審悉。漉竟著淨器中。向日諦視看。故有者如前説即作餘井捨去 然水陸空界。無非皆是有情依處。律中。且據漉嚢所得。肉眼所見以論持犯耳。三作嚢法多論。取上細㲲一肘作嚢此間宜用密練絹作 僧祇。蟲太細三重作。四分作漉水袋。如杓形。若三角。若作宏㨯。若作漉瓶。若患細蟲出。安沙於嚢中。漉訖還著水中此是私用者。若置於衆處。當準寄歸傳式樣。用絹五尺。兩頭立柱。釘鉤著帶繋上。中以横杖撑開。下以盆盛等 鈔云。今有不肖之夫。見執漉嚢者言。律學唯在於漉袋。然不知所爲處深。損生妨道者。猶不畜漉袋。縱畜而不用。雖用而不瀉蟲。雖瀉而損蟲命。且存殺生一戒。尚不遵奉。餘之威儀見命。常沒其中不加受者。輕小物故。或常持故。如律無者。不得行半由旬是也 昔孤山嘗著漉嚢誌。乃云。懸於草堂。以備法物之數。如用之則未能也。余謂中庸子。知教孰不知教。來者幸無取焉
智論云。受持禁戒爲性。剃髮染衣爲相。然濁世凡庸。鮮能修奉。且憑儀相。用光遺教。苟内外都亡。則法滅無日。願諸上徳。同志持危。即華嚴云。具足受持威儀教法。能令僧寶不斷。受佛遺寄。得其人矣。
佛制比丘六物圖
此に寄せて略して祇支・覆肩の二衣を辨ず。 初めに制意とは、尼・女は報弱し。故に祇支を制して、左肩に披て、以て袈裟に襯しむ。又、覆肩を制して、右膊に掩て、用て形醜を遮らしむ。是の故に尼衆は必ず五衣を持す。大僧も亦た畜用すること有り。但だ是れ聽衣のみ。二に釋名とは、梵語には僧祇支、此には上狹下廣衣と云ふ此は律文に據て、以て翻ず。全く衣相に乖けり。若し應法師の音義に準ぜば、翻じて掩腋衣と云ふ。頗る其の實を得たり。覆肩は華語なり。未だ梵言を詳らかにせず。三に衣相を明す。僧祇に二衣、竝びに長四肘廣二肘なりと。故に知ぬ、亦袈裟の畟方に同じと云ふことを。但だ條葉無きのみ。四に著用を明す。世に紛諍多し。今、爲に之を明さん。此の方、往古には並びに祇支を服す。後魏の時に至て始めて右の袖を加へ、兩邊縫合せて、之を偏衫と謂ふ。領を截ち裾を開て、猶ほ本相を存せり。故に知ぬ、偏衫の左肩は即ち本の祇支、右の邊は即ち覆肩なることを。今の人、此に迷ふて、又偏衫の上に復た覆肩を加ふ。學律の者は必ず須く服著すべしと謂ふ。但し西土の人は多く膊を袒ぐ。譏過を生ぜんことを恐るるが故に須らく之を掩ふべし。此の方は襖・褶重重にして、仍て偏袖を加ふ。又、覆て何かせん。縱ひ説くこと多途なりとも終に據無きことを成す若し生善と云はば、是の僧、應に著すべし。何ぞ獨り律宗のみにして餘宗は著せざるや。豈に生善にあらんや。況や輕紗・紫染、體色倶に非なり。佛は俗服と判じたまへり。全く道相に乖く。何の善か之れ有らん。或は宗途の分と云ふは、佛教には但だ三學を以て宗を分つ。而も形服の異を謂ふことは、未だ之を聞かず。 且らく三衣は大聖の嚴制なる。曾て未だ身を霑さず。覆肩は祖師の累りに斥けたれども、堅く持して捨てず。良に以みれば弊風一たび扇で、歴代共に迷ふ。復た教に於て知ること無きに由て、遂に義を聞て徙らざらしむ。更に明證を引かん。請ふ試みに之を詳らかにせよ。章服儀に云く、元制の興る所、本と唯だ尼衆なり。今、僧、服するは、僣じて下位に通ずと。又、住法圖賛に云く、阿難の報力、休壯にして圓備具足せり。士女、咸く愛著を興し、乃至、目に淨色を悦んで心醉ひ、神昏くして、子の頸に繋けて沈め殺す者あり。此に由て曲げて制して、覆肩の衣を著せしむ。今は則ち僥倖にして妄りに服せるは濫せるなり此に據るに、乃ち内に偏衫無くして單に覆せる者を斥くのみ耳。今の重ね覆ふが若きは、彼の時既に無し。言の限りに渉らず。且らく單に覆ふ、猶ほ僥倖と爲す。況や今重覆するは非法なること何の疑かあらん。廣くは別辨するが如し。
漉水嚢第六物賞看病の中には、則ち針筒を以て六と爲す。今は二衣の篇首に準じて之を列す
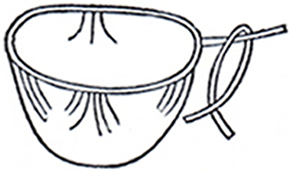
初めに制意。鈔に云く、物、輕小なりと雖も所爲、極大なり。出家の慈濟、厥の意、此に在り。今上品の高行すら、尚ほ蟲水を飮用す。況んや諸の不肖は焉ぞ言ふ可けんやと。四分には、漉袋無くして半由旬二十里なりを行くことを得ざれ。無くんば僧伽梨の角を以て漉すべしと。二に漉法とは、薩婆多に云く、住處を作らんと欲せば、先ず水中に蟲有るや否やと看るべし。有らば餘の井を作れ。猶ほ有らば捨て去れ。凡そ水を用ひる法は、應に清淨なるべき者なり。如法に漉して一器の中に置て、一日の用に足すべし。持戒審悉の者をして、漉し竟て淨器の中に著けて、日に向ひて諦かに視看せしめよ。故らに有らば前の説の如くせよ即ち餘の井を作り捨て去れ。 然れども水・陸・空界は、皆是れ有情の依處に非ずと云ふこと無し。律の中には、且らく漉嚢の得る所、肉眼の見る所に據て、以て持犯を論ずるのみ。三に作嚢法。多論に、上細の㲲一肘を取て嚢を作ると此の間には宜しく密練の絹を用ひて作るべし。 僧祇に、蟲、太だ細なれば三重に作るべしと。四分に、漉水袋を作ること杓形の如くすべし。若しは三角、若しは宏㨯に作れ。若しは漉瓶に作れ。若し細蟲の出んことを患へば、沙を嚢中に安じて、漉り訖て、還て水中に著けよと此は是れ私用の者なり。若し衆處に置かば、當に寄歸傳の式樣に準ずべし。絹五尺を用て、兩頭に柱を立て、鉤を釘うちて帶を著け、上に繋げ。中に横杖を以て撑へ開て、下に盆を以て盛る等。鈔に云く、。今不肖の夫有り。漉嚢を執する者を見て言く、律學は唯だ漉袋に在りと。然れども所爲の處深きことを知らず。生を損し道を妨ぐる者にして、猶ほ漉袋を畜へず。縱ひ畜ふとも而も用ひず。用ふと雖も而も蟲を瀉さず。瀉すと雖も而も蟲命を損ず。且らく殺生の一戒を存するすら、尚ほ遵奉せず。餘の威儀・見・命は、常に其の中に沒せり受を加へざるは、輕小の物なるが故なり。或は常に持するが故に、律の如き、無くんば半由旬を行くこと得ざれと云ふ、是れなり。 昔、孤山、嘗て漉嚢の誌を著はして乃ち云く、草堂に懸て、以て法物の數に備ふと。之を用ふるが如きは則ち未だ能はざるなりと。余謂く、中庸子、教を知らば孰れか教を知らざらん。來者、幸くば取ること無かれ。智論に云く、受持禁戒を性と爲し、剃髮染衣を相と爲すと。然れども濁世の凡庸は、能く修奉すること鮮し。且らく儀相に憑て、用て遺教を光す。苟とに内外都亡せば、則ち法滅し、日無けん。願くは諸の上徳、志を同じくして危を持せよ。即ち華嚴に云く、威儀の教法を具足し受持せば、能く僧寶を斷へざらしむと。佛の遺寄を受くること、其の人を得ん。
佛制比丘六物圖
[S]saṃkakṣikā / [P]saṅkacchikaの音写、僧祇支の略。仏陀がその教団を形成していく当初、比丘には原則として三衣のみがその装束として許されていた。けれども諸般の事情によっていわば下着の如きものとして更に二衣が、特には比丘尼のため必須のものとして制定されることとなった。その二衣のうち上に着るものが僧祇支である。基本的にその形状は長方形で左肩に掛け、そのまま右脇に回しこんでまた左肩上に安じる。あるいは右腋にて紐などで留めて着ける。すなわち、いずれにせよ偏袒右肩で着けるものとされるが、その着け方には厳密な規定は無い。よって都合次第で通肩にても着る。そのような僧祇支の着法はいまだ南方の東南アジアにおいて息づいており、特にビルマに於いてよく保存されている。▲
右肩を覆うための長方形の布。ここで元照は、僧祇支と覆肩とを別物と考えている。けれども、物としては僧祇支とまったく同じであって別物ではない。道宣および元照がこれらを別物として理解したのは、『四分律』などにそのように記されているためである。いや、「訳されている」と言ったほうが正確であろう。『四分律』の訳者仏陀耶舎が、僧祇支は比丘のいわば下着として左肩を覆うものとして許された布であって、(特に比丘尼の胸の露出を防ぐための)右肩を覆うための布は僧祇支と同じであるけれども、区別するためにあえて別の語に訳し分けた可能性がある。▲
女性は男性に比して身体的にも制約が多く、それは当然その外装にも反映されるため、「報弱し」と言ったのであろう。そもそも仏陀は尼僧の出家を許可することを躊躇された。仏教では女性も男性も同じく悟りに達しうることはできるが、しかし男性に比すれば女性は多くの困難・障礙があるとする認識があり、その認識はそのまま後代にも引き継がれてきた。大乗においてそれはさらに顕著となり、変成男子なる思想すら生まれるほどとなった。『法華経』の説く龍女成仏はその裏返しである。▲
比丘尼、すなわち女性がその乳房を公然とあらわにすることを防ぐためのものであること。▲
比丘尼は女性であるということで、乳房を三衣のみで覆うことは難しい場合があった。実際、豊かな乳房をもつ比丘尼がその乳房や性器を意図せず露わとしてしまうことがあり、あるいはその豊満な乳房を俗の男衆に揶揄されることがあったため、その再発を防止するために三衣の他に僧祇支と覆肩衣の二衣が必須のものとして制定された。ただし、五衣が何かについては律蔵によって若干の異なりが有り、僧祇支の他に筒状の裙すなわち厥修羅(圌衣)をもって二衣とするものや覆肩と雨浴衣とを二衣とするものもある。▲
本制の三衣とは別途に、例外的・補助的に許された衣装。必ずその所有・着用すべきとはされていない衣。▲
上部が狭く下部が広くなった衣(下着)。▲
元照が理解する、あるいは彼が知りえた僧祇支の形状は、ただ長方形の布にすぎないものであった。しかし、上述のように僧祇支は一応必須の内衣とされたものではあるけれども、律蔵において三衣のように厳密な規定がされたものではない。ただ大きさの上限が定められたものであって、その形状には単純な長方形のものもあれば、長方形を縦に折りたたんで上部の角を縫い付けたものや、右肩部がない貫頭衣いわば現代のタンクトップの右肩無しの如き形態の物もあった。この事実は印度や支那の古い仏像などにおいて確認することができる。また現代の東南アジア(タイやスリランカ)における比丘らには、まさしくそのような形態の僧祇支を着用するものがいまだある(何故かビルマでその形状の僧祇支はほとんどまったく用いられていない)。ここで「此には上狹下廣衣と云ふ」とあるが、それはそのような形態の僧祇支をこそ意図して訳した語であったろう。それは妙訳というよりも、ただその見たままを語としたものであった。しかしながら、元照はそのような形状の僧祇支の存在を知らなかったため、ここで「全く衣相に乖けり」と批判しているのである。
なお、角を縫い付けた形状の僧祇支はビルマの尼僧が用いており、それはまさに『内法伝』にて義浄が報告している南海の尼僧が用いていたという僧祇支の形態そのまま。▲
玄応『一切経音義』二十五巻。玄応は玄奘の訳経事業に参加した人で、梵語に通じていたといわれる。もとは『大唐衆経音義』と題したが後に『一切経音義』と改題された。後代、慧琳は玄応の仕事を引き継ぎ、それを下敷きとしてまた『一切経音義』を著している。▲
あくまで元照は僧祇支と覆肩とを別物として理解しているが、それは『四分律』においてそう記されているから仕方のないことではあるけれども、実は覆肩衣は僧祇支の訳語の一つであった。義浄の『南海寄帰内法伝』では様々に道宣の律に対する理解、三衣の理解について批判を加えており、多くの非常に有益で貴重な情報を現代の我々にも残されている。しかしながら、僧祇支と覆肩衣の違いについては決定的といえるほどのものは提示しきれていない。
ところが、これは日本の江戸末期にいたるまで種々に論じられることとなる。結局、日本の江戸期の律僧・禅僧らからはおおよそ、「覆肩とは僧祇支の訳語であって、特に襞畳の僧祇支のことである」と断じられている。▲
『摩訶僧祇律』巻三十八「佛言。從今日後。應作浴衣。乃至已聞者當重聞。若比丘尼作雨浴衣。應量作。長四修伽陀搩手。廣二搩手。若過作截已波夜提。如上僧祇支中廣説」(T22, p.529b)▲
後魏は南北朝時代の北朝の一つ。四世紀末に建国され五世紀中頃に北支を統一。六世紀中頃に滅んだ。
ここで元照が言及しているのは、賛寧『大宋僧史略』服章法式に「又三衣之外。有曳納播者。形如覆肩衣。出寄歸傳。講員自許即曳之。若講通一本則曳一支。講二三本又隨講數曳之。如納播是也。又後魏宮人見僧自恣。偏袒右肩乃一施肩衣。號曰偏衫。全其兩扇衿袖。失祇支之體。自魏始也」(T54, p.238a)とあるのに拠ったのであろう。この『大宋僧史略』の説を受けてか、道誠もまた『釈氏要覧』に「偏衫 古僧依律制。只有僧祇支此名覆膞。 亦名掩腋衣此覆左膞及掩右掖蓋儭三衣故即天竺之儀也。竺道袒魏録云。魏宮人見僧袒一肘不以爲善。乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫今開脊接領者蓋遺魏制也」(T54, p.270b)と記しているが、これに拠ったのかもしれない。元照が『釈氏要覧』を読んでいたのはその説に批判を加えているので間違いないため、むしろ元照はこちらに拠ったか。この偏衫の由来の説は以降も宝雲『翻訳名義集』や徳煇『勅修百丈清規』に引き継がれた。▲
後魏代の支那において、その風土・風俗に応じたものとするべく、僧祇支と覆肩衣とを縫い合わせて成立したといわれる内衣。後代に褊衫とも書くようになり、また[へんさん]とも読む。衫とは下着・襦袢の意。
その昔、支那および日本の僧徒らは、律宗・禅宗・天台宗・真言宗などと問わず、專ら偏衫と裙(涅槃僧に襞と帯とを縫い付けた腰衣)とをその内衣として用いていた。宋代の支那において、この偏衫と裙を上下綴り合せた如き直綴[じきとつ]が考案され、日本には鎌倉期に禅宗と共に持ち込まれた。臨済宗の栄西や曹洞宗の道元らも偏衫をこそ「着用すべきもの」とし、直綴はあくまで誤ったものであるとの認識であったことが知られる(栄西『出家大綱』・道元『宝慶記』)。しかしながら、彼ら以降はなし崩しに直綴をこそ着用するようになり、禅宗において偏衫はほとんど忘れられている。現在に於いても日本で偏衫を着用しているのは、律宗・真言宗・真言律宗に限られている。現代の支那・台湾では(知識としては若干残っているものの、実物としては)まったくこの衣は忘れられて無い。
なお、日本の鎌倉期に叡尊らによってなされた戒律復興においては、直綴は論外として、しかし偏衫ですらもやはり改変されたものであって本義ではなく、僧祇支こそ本来着けるべきものだとされた。そして実際に僧伽の重要な行事では僧祇支が着用されていた(『興正菩薩御教誡聴聞集』袈裟幷直突事)。この遺志は、室町期に律の伝統が途絶えたのを再び復興するべく奮闘した明忍の流れに位置する慈雲によっても再度行われ、慈雲の正法律運動において僧祇支はやはり重要な儀式の際に着用された。この事実は『高貴寺規定』やその肖像などにおいても確認されるであろう。慈雲の肖像のほとんどで、尊者は衣の下に僧祇支と涅槃僧をこそ着している。
ちなみに、現代の(唐招提寺系を除く)日本の偏衫という内衣を知る僧職者のほとんど多くが、偏衫というものは「左前に着るものである」という認識にある。しかし、実は偏衫は支那以来左前に着るものではなかった。偏衫を左前に着るようになったのは叡尊以来のことであって、それは俊芿によってもたらされたこの『仏制比丘六物図』における「故に知ぬ、偏衫の左肩は即ち本の祇支、右の邊は即ち覆肩なることを」という記述に由るものであろうと推測される。叡尊の日記やその他の記録に「偏衫の形態を変えた」などという記述は私の知る限り無いが、鑑真和上像および俊芿像ならびに彼が宋の優れた画師に描かせて持ち帰った道宣・元照像、そして覚盛像と叡尊像の比較に由って、このことは極めて明瞭である。唐招提寺の律宗においては、偏衫は左前に着るものではないのである。叡尊がそのような衣の改変を行い得たその根拠は、今のところ上記の一節以外には見いだせない。が、そのような改変をなしたのは律師が新来の本書を非常に細かく読み込んでおり、律師の戒律復興・仏教興隆の志がこのような細かな点まで及んでいた一つの証と言えよう。▲
今、日本の華厳宗や真言宗、そして天台宗などにおける僧職者らが、最も正装であるとする衣服、衲衣(のうえ)と称する多く金襴などで華美な意匠を施した正絹の衣を着る際、右肩を覆って前に垂れ下げる「横被(おうひ)」というものがある。その淵源は、まさに宋代において元照が批判した僧徒らの無知に基づいた、褊衫の上にさらに覆肩を重ねて着用するという習慣に基づいたもの。無知と非法が時代と国を超え、今の日本にまで伝えられているのである。▲
奈良・平安期中期までの日本において、宗派による外儀の異なりなど無く、皆一定の奈良期以来の風儀を保っていたと考えられるが、律儀(戒律)の頽廃にしたがって袈裟衣が改変され、もはや袈裟衣とは名ばかりの衣装を僧徒らが身につけるようになっていった。鎌倉期には南宋から禅僧の渡来が多くあったことと、戒律復興運動の勃興により、大きくは官僧・律僧・禅僧の三種の衣の違いが見られた。そして、宗旨宗派毎に外儀を異にしようとする傾向は江戸期において顕著となり、それぞれ外見的にも独自性を強め、各宗派はなんら仏典の根拠などない奇態な装束を生み出している。そのような傾向はしかし、すでにここで元照が批判するように南宋において見られており、それは当時の禅僧に多く生じていたことであったろうと思われる。彼らのいう仏祖相承の袈裟であるとか伝法衣などというものは、その言葉とは裏腹にまったく仏祖から相承したものでもなく、法を伝えてもいない虚妄の産物であった。▲
『章服儀』「元制所興。本唯尼衆。今僧服著僣通下位」(T45, p.838a)▲
道宣『住法図賛』。散失したか。ここに載せる話は『大智度論』巻三「」およびに拠るもの。▲
水漉し。[S]pariśrāvaṇaの漢訳。鉢里薩囉伐拏などと音写される。比丘・比丘尼が飲用、あるいは日用する水に、虫など小さな生命があってこれを直接飲用、もしくは殺傷することを防ぐためのもの。いわゆる浄水するための具ではない。▲
『行事鈔』巻下 二衣総別篇第十七の冒頭に、「夫形居世累。必假威儀。障蔽塵染。勿過衣服。 若受用有方。則不生咎戻必領納。乖式便自陷深愆。故初總分制聽後依門而解。何名爲制。謂三衣六物。佛制令畜。通諸一化並制服用。有違結罪。何名爲聽。謂百一衣財。隨報 開許。逆順無過。通道濟乏也。就初分三。謂三衣坐具漉水袋也」(T40. P104c)とあって、六物を三衣・坐具・漉水嚢としている。しかし、道宣はまた「四分六物者。三衣盛衣器襆鉢及袋坐具針筩也」(T40, p.116a)ともして、『四分律』における六物とは三衣・鉢・座具・針筒であることを認めている。そしてさらに、「今亦未須問徳。律無正文。若知辛苦有功者。上座告云。長老看病有功。佛令優賞。當胡跪受羯磨也。 看病者謙退陳訴。無徳有愧不堪重賞。僧當抑伏令受。然後索欲問和。答作賞看病人六物羯磨。即白二與之。大徳僧聽。比丘某甲命過。所有三衣鉢坐具針筩盛衣貯器隨有言之」(T40, p.116b)として、死んだ比丘の遺産として六物の分与をするにも、やはりそれと同じ説をとっている。▲
『行事鈔』巻下「三漉水袋法。 物雖輕小所爲極大。出家慈濟厥意在此。今上品高行尚飮用蟲水。況諸不肖。焉可言哉」(T40, p.109a)▲
『四分律』巻五十二「比丘不應無漉水嚢行乃至半由旬。若無應以僧伽梨角漉水」(T22, p.954b)
万一、漉水嚢を携帯していない時に(虫のある)水を飲まんとするとき、大衣の角を用いて水を漉すべきとするこの規定は、時代を大きくこえて明治期の河口慧海の西蔵行の大冒険においても大いに役立っていた。
河口慧海『チベット旅行記』「今夜も水を得られずにいた日にゃあこのまま死にはせぬかと非常に苦しくなった。その度たびに宝丹を出して飲むけれども飲むとかえって余計喉が乾く位、しかし幾分の助けにはなったろうと思います。それからだんだん進んで十一時頃になると向うの方にちょっと低い溜たまりのあるような所が見えた。あすこに水があるだろうと思ってそこへ指して砂を踏み分けつつ行きますとなるほど水がありました。その時の嬉しさは何とも堪え得られんほど嬉しかった。まあこれを一つしっかりと飲んでそれから茶を沸かそうともう片時も待って居られないから、早速荷物を卸して懐ろから椀を出して汲もうとするとその水が真赤になって居る。これは何か知らんと思うとチベット高原にある一種の水なんで、それは何百年この方そういう風に腐敗してそこに溜って居ったものであろうかと思われる位。早速汲んだところが細かな虫がウジウジして居る。これじゃ直すぐ飲むという訳にはいかない。殊に虫のあるような水を飲むことは私共には許しませず、どうもこいつあ困った、しかしこれを飲まなくちゃあ立ち行かず、飲んじゃあ仏戒にも背くし第一自分の身体を害するがどうしたら宜よかろうかと暫く考えて居りましたがじきに案が浮びました。かねて釈迦牟尼如来しゃかむににょらいが戒法をお立ちになった中にもし水の中に虫が居たならばその虫を切布きれで漉こして飲めというお教えのあった事を思い出して、こりゃいい事を思い出したというので早速切布とチベット鍋を出してその水を切布で漉したです。そう致しますと外側に虫が残って水が下へ落ちた。それが清水かと思うとやっぱり赤い。けれども虫のウジウジして居るのが眼に掛からんからそれを椀に盛って一盃飲んだ時のその味は 極楽世界の甘露かんろも及ばなかったです。」 ▲
いかに水を漉すべきかの方法。▲
『薩婆多論』巻六「若欲作住止處法先應看水。用上細疊一肘作漉水嚢。令持戒審悉者漉水竟。著器中向日諦看。若故有蟲者。應二重作漉水嚢。若三重作漉水嚢。故有蟲者。此處不應住」(T23. P545a)、あるいは巻八「第三誦九十事第四十一 此是共戒。比丘尼倶波逸提。三衆突吉羅。前制有蟲水澆草土和泥。此制一切不得用蟲水者。若眼所見若漉水嚢所得。一時舍利弗。 以淨天眼見空中蟲。如水邊沙如器中粟。無邊無量見已斷食。經二三日。佛勅令食。凡制有蟲水。齊肉眼所見漉水嚢所得耳。不制天眼見也。凡用水法。應取上好細疊縱廣一肘作漉水嚢。令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者。令其知水。如法漉水置一器中足一日用。明日更看。若有蟲者。應更好漉以淨器盛水向日諦視。若故有蟲。 應作二重漉水嚢若二重故有蟲者。應三重作。若故有蟲。不應此處住。應急移去。是中犯者。若比丘知水有蟲用者。隨所有蟲死。一一波逸提。若比丘用有蟲水煮飯羹湯浣染洗口身手足一切用者。隨爾所蟲死。一一波逸提。若有蟲水無蟲想用波逸提。若有蟲水有蟲想有蟲水疑用波逸提。若無蟲水有蟲想無蟲水疑用突吉羅。若無蟲水無蟲想用無罪」(T23, p.552b)▲
『四分律』巻十六「若比丘飮用雜虫水者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。不知有虫無虫。後乃知。或作波逸提懺。或有畏愼者。白佛。佛言。不知者無犯。自今已去當如是説戒。若比丘知水有虫飮用者波逸提。比丘義如上。彼比丘知是雜虫水飮用者波逸提。除水已若雜虫漿苦酒清酪漿清麥汁飮用波逸提。有虫水有虫想波逸提。有虫水疑突吉羅。無虫水有虫水想突吉羅。無虫水疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知有虫無虫想。若有麁虫觸水使去。若漉水飮者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒」(T22, p.677c)
『比丘六物図』において「律」といえば特に『四分律』を指したものであるけれども、ここでは諸律に一般のこととして述べたことであろう。▲
特に上述の『薩婆多論』にある「凡制有蟲水。齊肉眼所見漉水嚢所得耳。不制天眼見也」に拠っての言であろう。しかし、これも上述の『四分律』に明示されているように、「肉眼で見えないこと」だけが条件ではない。他に「虫がいる恐れがない」・「虫がいるとは思えない」こともその条件とされる。いずれにせよ、これは前述したように現代の法律の如きものであるため、その範囲や条件が比較的厳密に定められている。そして意図の有無(故意か故意でないか。正気であったか正気でなかったか)も重要な要件となっている。▲
漉水嚢の制作方法。▲
『薩婆多論』巻六「用上細疊一肘作漉水嚢」(T23, p.545a-b)▲
三衣においてあれほど絹の使用を厳禁だとし、それを可とする義浄を激しく批判したにもかかわらず、ここでは一転、密練の絹を使用することを認め、むしろ推奨している。むしろ元照自身の論法からすれば、虫を殺さぬために虫を殺して得たものを用いるのは甚だしい自己撞着であって「慈悲を解せぬ者」の所行となる。▲
『摩訶僧祇律』巻十五「若故有虫者當重嚢漉之諦觀。若故有虫者乃至三重」(T22, p.345a)▲
『四分律』巻五十二「佛言。如勺形若三角 若作撗郭若作漉瓶。若患細蟲出。聽安沙嚢中。彼以雜蟲沙棄陸地。佛言不應爾。 聽還安著水中」(T22, p.954b)▲
義浄『南海寄帰内法伝』巻一「若是生絹。小蟲直過。可取熟絹笏尺四尺。捉邊長挽襵取兩頭刺使相著。即是羅樣。兩角施帶兩畔置𢂁。中安横杖張開尺六。兩邊繋柱下以盆承傾水之時罐底須入羅内。如其不爾。蟲隨水落墮地墮盆還不免殺」(T54, p.208a)
元照は義浄による南山律宗(あるいは支那における律儀の理解と実際全体)に対する厳しい批判を許せず、その説に感情的な反発をしている。しかし、現実に印度の実際を事細かに伝えたその説を、やはりまったく否定することなど出来なかったのであろう。先にはその理解と説について反発していたものの、ここではこうして義浄の所伝に依るべきことを自註に述べている。一般に、義浄の批判は支那の律僧らにほとんど無視されたと考えられているが、しかしその言舌は公然と取り上げられ摂取されることはなくとも必ず意識されていたであろうことが伺える。▲
『行事鈔』巻下「今不肖之夫。見執漉袋者言。律學唯在於漉袋。然不知所爲處深損生。妨道者猶不畜漉袋。縱畜而不用。雖用而不寫蟲。雖寫而損蟲命。且存殺生一戒。尚不能遵奉。餘之威儀見命常沒其中」(T40, p.109b)▲
宋代の天台僧、孤山智円。字は無外あるいは中庸子と号した。南宋時代に天台教学を再編・再興せんとした四明知礼の山家派に対抗し、またその異なる説を主張したいわゆる山外派の中心人物。孤山の云ったという言葉はやはり到底賛同できるものではない僻事というべきであるけれども、仮にこれが四明知礼の言葉であったならば、果たして元照が同じく批判したかどうか。元照は山家派の信奉者であり、その理解を南山律宗に持ち込んだ人であったためである。▲
『大智度論』巻三十一「有人言。性相小有差別。性言其體相言可識。如釋子受持禁戒是其性。剃髮割截染衣是其相」(T25, p.293b)▲
仏駄跋陀羅訳『華厳経』巻十「具足受持威儀教法。是故能令僧寶不斷」(T25, p.293b)
律儀は仏法の命根である。僧徒が戒と律とを守り行えば、仏教は正しく行われ、正しく世に伝わっていく。それは大小乗問わない、いわば通仏教的理解である。それは日本の過去のまっとうな僧徒、大徳らもまた同じく共有した信念であり、事実でもあった。今現代の日本仏教界においては、その誰もが無戒無律の相似仏教、似非仏法で生計をたて、その姿形すらも甚だしく乱れてまったく俗と変わることがない。その事実は真逆の形で「律儀は仏法の命根である」ことが真であることを我々に示している。姿形だけ仏者に似せるだけではいわゆるコスプレに変わりはしないが、その姿形さえまともに正せず正すつもりもなければ、そのような者らに何ら期待できることは微塵としてない。▲