『悉曇字記』の構成について、現代的観点から云えば序説・概説・本論の三部構成となっています。序説において先ず悉曇とは印度の文字であり、それをいかに智廣が般若菩提という南天竺の僧から学び受けたかの経緯が明かされています。智廣が何故、悉曇に興味を持ったのかの契機とその問題意識が示され、おそらくは偶然に梵僧から受学することが出来た悉曇について『悉曇字記』という書として世に呈する目的が述べられます。
そしてその概説に入っていくのですが、しかし、これを梵字悉曇について全く触れたことのない者が読み進めても、何を言っているのか全く理解できないようなものとなっています。最低でも、それは概説を終えた後の本論の冒頭で説かれるのですが、梵字の字表および十八章建てで示される諸字を見て知っていなければ、意味不明となるでしょう。
したがって、『悉曇字記』はむしろ序説を読んだ後に概説を飛ばし、先に本論に目を通した後に概説を(本論を適宜参照しながら)読んだならば、理解しやすいものとなるでしょう。あるいは、もし順に読み進めていくのであれば、その概説で言っていることは本論を読んだ後に再度読めばようやく理解できるものであって、その最初は意味がわからないのが当然であり、とりあえず目を通しておけばよいもの、と承知しておかなければなりません。さもなければ、その途中でこれを学ぶのを放擲することになりかねない。
智廣は般若菩提から本論(悉曇章)を聞き、その概説を自ら記して敢えて前に置いたのでしょう。ではその概説が酷くわかりにくい稚拙なものであるかといえば、そんなことは決してない。しかし、書の構成としては、初心の人に示すには決して上手いものとなってはいません。
とはいえ、その概説の初めはまだ理解しやすいものとなっており、まず悉曇という語は特に六つの韻、すなわち (a)・
(a)・ (i)・
(i)・ (u)・
(u)・ (e)・
(e)・ (o)・
(o)・ (aṃ)を意味するものであることが言われます。そこでまた、その一韻には長短の別があり、それをまた分かったならば
(aṃ)を意味するものであることが言われます。そこでまた、その一韻には長短の別があり、それをまた分かったならば (ā)・
(ā)・ (ī)・
(ī)・ (ū)・
(ū)・ (ai)・
(ai)・ (au)・
(au)・ (aḥ)となって、その六つを加えた十二字が悉曇であるとされます。
(aḥ)となって、その六つを加えた十二字が悉曇であるとされます。
| 短 |  a |
 i |
 u |
長 |  e |
 o |
 aṃ |
六韻十二字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 |  ā |
 ī |
 ū |
短 |  ai |
 au |
 aḥ |
| 短 |  ṛ |
 ḷ |
二韻四字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 |  ṝ |
 ḹ |
||||||
今一般に、悉曇とは往古の印度において通用したその文字体系の称であると考えられています。けれども、本書において悉曇とは、その「六韻を表す十二字をのみ指して云うもの」であることに注意する必要があります。
そもそも悉曇とは
 (siddhaṃ)の音写で、『悉曇字記』ではその語の意を漢語に訳すなど述べられてはいないのですが、√sidh(成功する・達成する・完成する)の過去分詞(sidh+ta⇒内連声⇒shiddha)の名詞化したものです。これが男性名詞(男声:siddha)としてならばsiddhaṃはその業格単数形で、中性名詞(非男非女声:siddha)としてであれば主格あるいは業格の単数形です。
(siddhaṃ)の音写で、『悉曇字記』ではその語の意を漢語に訳すなど述べられてはいないのですが、√sidh(成功する・達成する・完成する)の過去分詞(sidh+ta⇒内連声⇒shiddha)の名詞化したものです。これが男性名詞(男声:siddha)としてならばsiddhaṃはその業格単数形で、中性名詞(非男非女声:siddha)としてであれば主格あるいは業格の単数形です。
例えば前項にて示した義浄『南海寄帰内法伝』の一節にもあるように、悉曇とは古来「成就」の意で解されています。
一則創學悉談章。亦名悉地羅窣覩。斯乃小學標章之稱。倶以成就吉祥爲目。
(学問の)一めはすなわち「創学悉談章」であり、また「悉地羅窣覩〈siddhirastu〉」ともいう。これはすなわち小学〈幼少〉の標章の称であり、いずれも「成就吉祥 」を以て目としたものである。
義浄 『南海寄帰内法伝』 巻四(T54, p.228b)
ここで義浄がいう「悉地羅窣覩」とは、siddhirastu(←連声―siddhis + astu)の音写です。それはsiddhi(成就・完成;女性名詞)の単数・主格siddhisと、asti(ある・存在する;動詞)の三人称単数・命令形astuからなる語で、これを訳したならば「成就あれ!」との意となります。義浄のこの報告をそのまま受け取ったならば、その言葉が当時の印度において梵字を学ぶいわば初等教科書の題目として用いられていたのでしょう。
これを義浄は「成就吉祥」を目したものだと言っていますが、確かにsiddhiには「成就」や「完成」以外に「幸運」や「繁栄」の意味もあり、したがってこれはその語義を複数連ねて示したものであると解し得るでしょう。あるいは、astuの「~あれ!」・「~たれ!」を「成就」と意訳したものか、と解することも出来るでしょう。いずれにせよ、その「siddhirastu(成就吉祥)」という文句は、小学の者達の学問を成就を願う、吉祥な語として用いられていたことを言わんとしたものであったと考えて大過ない。すなわち、幼児らの教師となる人が、その学問の大成を願って唱えていた定型句であったように考えられます。
ただし、『悉曇字記』にて悉曇の原語は
 (siddhaṃ)でなく、
(siddhaṃ)でなく、
 (siddhāṃ)と綴られています。これは空海がもたらした『悉曇字記』にそう記されており、それはもちろん智廣の書いた原本でなく写本であったと思われます。そこであるいは、その伝承あるいは写本の過程で誤読か語写があったのかもしれません。
(siddhāṃ)と綴られています。これは空海がもたらした『悉曇字記』にそう記されており、それはもちろん智廣の書いた原本でなく写本であったと思われます。そこであるいは、その伝承あるいは写本の過程で誤読か語写があったのかもしれません。
といっても、
 (siddhaṃ)と
(siddhaṃ)と
 (siddhāṃ)とで何が違うかといえば、いずれも語根sidhから生じた名詞であることには変わりなく、前者の場合は先に述べた通りで、後者は女性名詞(女声:siddhā)であってその業格・単数であるという程度の違いです。
(siddhāṃ)とで何が違うかといえば、いずれも語根sidhから生じた名詞であることには変わりなく、前者の場合は先に述べた通りで、後者は女性名詞(女声:siddhā)であってその業格・単数であるという程度の違いです。
 (siddhāṃ)とあるからといって、それが必ずしも間違いである、ということではない。
(siddhāṃ)とあるからといって、それが必ずしも間違いである、ということではない。
また本来、梵語には母音として他に (ṛ)・
(ṛ)・ (ṝ)・
(ṝ)・ (ḷ)・
(ḷ)・ (ḹ)の四音四字がありますが、本書においては、これらも悉曇ではあるけれども実際としてあまり用いられない、ということから略されています。では本書では以降、全くそれら四つの母韻に言及していないかといえばそういうことは決してなく、これら四字は後に「別摩多」すなわち「特別な母韻」として挙げられ、扱われます。
(ḹ)の四音四字がありますが、本書においては、これらも悉曇ではあるけれども実際としてあまり用いられない、ということから略されています。では本書では以降、全くそれら四つの母韻に言及していないかといえばそういうことは決してなく、これら四字は後に「別摩多」すなわち「特別な母韻」として挙げられ、扱われます。
摩多とは
 (mātā)の音写です。あるいは摩多囉とも言われますが、その場合は
(mātā)の音写です。あるいは摩多囉とも言われますが、その場合は

 (mātaraḥ)の音写か、とも思われます。いずれも「母」を意味する女性名詞
(mātaraḥ)の音写か、とも思われます。いずれも「母」を意味する女性名詞
 (mātṛ)に基づく語で、前者はその主格単数形、後者は主格複数形です。そのことから、摩多は母音を意味したものとなろうものです。しかし、梵語において一般に母韻はsvara(稀にvarṇaあるいはvyakti)と云われます。
(mātṛ)に基づく語で、前者はその主格単数形、後者は主格複数形です。そのことから、摩多は母音を意味したものとなろうものです。しかし、梵語において一般に母韻はsvara(稀にvarṇaあるいはvyakti)と云われます。
そしてまた本書において摩多とは、上記十二の「字」ではなくあくまで「韻」を表する記号、すなわち子音字+母韻の十二字に展開する際に付する記号を意味します。これを伝統的に点画、あるいは十二摩多、十二点などと称します。それがいかなることかを示せば以下の通り。
 -a |
 -i |
 -u |
 -e |
 -o |
 -ṃ |
 -ā |
 -ī |
 -ū |
 -ai |
 -au |
 -ḥ |
以上の摩多には、たとえば (-u)は、これを付する子音の字形によっては
(-u)は、これを付する子音の字形によっては や
や など全く別の形をとる場合があり、上記の表で示したものはその一例に過ぎません。
など全く別の形をとる場合があり、上記の表で示したものはその一例に過ぎません。
また、特に日本において梵字において最も重要なものであるなどと非常に強調される「a」の韻を示すとされる一点 は、これを伝統的に「明点」などと云い、あるいは「一点阿字」などとも言うのですが、そのような理解は『悉曇字記』(ひいては印度以来)の説に則ったものではありません。本書(さらには『大日経義釈』)の説に率直に従ったならば、それは点などでなく、梵字各字が備える上部の横一画全体を意味するものです。しかし、日本では古来その横一角の最初に筆を置いて少し引いた一点
は、これを伝統的に「明点」などと云い、あるいは「一点阿字」などとも言うのですが、そのような理解は『悉曇字記』(ひいては印度以来)の説に則ったものではありません。本書(さらには『大日経義釈』)の説に率直に従ったならば、それは点などでなく、梵字各字が備える上部の横一画全体を意味するものです。しかし、日本では古来その横一角の最初に筆を置いて少し引いた一点 であるとして、しばしばひどく「(現代的否定的な意味での)宗教的理解」と共に強調されます。
であるとして、しばしばひどく「(現代的否定的な意味での)宗教的理解」と共に強調されます。
(早くは鎌倉中期には「a」を表する摩多は梵字の上部横一画であるとする理解があり、近世江戸期には、一点阿字などという説の不合理あるいは無根拠なものであることが既に意識されていたのか、点ではなく上部の横一角全体が「a」の韻を示すものとする説も、併行して云われています。)
そうして母韻を示した後に示されるのが子音です。これを本書にそう称していることから、今も一般に体文と言い習わしています。サンスクリットで子音に該当する原語はvyañjana(便繕那)ですが、子音の他に装飾や顕示あるいは支分の意があります。これが体文と意訳されたのは、摩多(母韻)が付されて初めて完全な字となるものであり、また他の子音と重ねて新たな字を生み出す基体となることに依るのかもしれません。体文はまた字母とも云われます。
そして体文は、その発声の部位・仕方、いわゆる調音部位により、支那では五類声と称される五種と遍口声(「へんこうしょう」とも)との二つに分類されます。
現代の僧職者らは一般に、梵字を発音するのに必ず意識せられなければならない調音部位である、体文の五類声と遍口声の組織をまったく等閑視し、まるで意識もせず、その構成どころか語としてすら憶えもしません。しかし、梵字悉曇を学ぶにあたってそれらは非常に重要なものであって、必ず憶え、常に意識し踏まえておかなければならないものです。
| - | 軽音 (無気) |
重音 (有気) |
軽音 (無気) |
重音 (有気) |
(鼻音) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五類声 | 牙 kaṇṭhya |
 ka |
 kha |
 ga |
 gha |
 ṅa |
舌根 | |
| 歯 tālavya |
 ca |
 cha |
 ja |
 jha |
 ña |
舌本 | 三内 | |
| 舌 mūrdhanya |
 ṭa |
 ṭha |
 ḍa |
 ḍha |
 ṇa |
舌中 | ||
| 喉 dantya |
 ta |
 tha |
 da |
 dha |
 na |
舌末 | ||
| 唇 oṣṭhya |
 pa |
 pha |
 ba |
 bha |
 ma |
転唇 | ||
| 遍口声 |  ya |
 ra |
 la |
 va |
半体文 (半母音) |
|---|---|---|---|---|---|
 śa |
 ṣa |
 sa |
- | 索音 (摩擦音) | |
 ha |
- | - | - | (気音) | |
 llaṃ |
 kṣa |
- | - | 重字 (結合音) |
智廣は梵語の文法書にてそう云われている通り、体文のうち二十五の字音を、調音部位(発声に用いられる口内の部位)にしたがって牙・歯・舌・喉・唇の語をもって五種に分かち示しています。
なお、五類声として挙げられる牙・歯・舌・喉・唇という語、その理解は、支那の六朝時代に淵源し、あるいは南北朝時代に著された漢字字典『 玉篇 』に端を発する「韻学」、すなわち漢字音の説明・考究において用いられていたものからの転用です。すなわち、これら五類声は、支那人が梵語を理解するのに考案し、初めて用い出したものではありません。
そこでしかし、智廣が五類声として挙げたその順には、梵語として大きな誤りが潜んでいました。梵語では確かに子音のうち二十五音を五種の調音部位に分かって説明されます。ところが、智廣が挙げた順は、正規の梵語で云われるものと違っています。すでに上掲の表で示しましたが、その順をサンスクリットで示せば①kaṇṭhya・②tālavya・③mūrdhanya・④dantya・⑤oṣṭhyaです。これをより理解しやすいよう、現代日本語および英語で示したならば、①軟口蓋音(Velar)・②硬口蓋音(Palatal)・③半舌音(Retroflex)・④歯音(Dental)・⑤唇音(Labial)となります。
ここで問題となるのが②tālavya(口蓋音)と④dantya(歯音)です。②のtālavyaを「喉」と訳すことは一応可能であるでしょう。しかし、これを「歯」とすることは決して出来ません。何より、歯音に該当する語は④のdantyaであり、また実際に『悉曇字記』にて「喉」として列挙される (ta)以下の五字は本来、まさに(上顎の)歯(の裏)に舌先を当てて発するものです。そういうならば、そもそも①kaṇṭhyaを「牙」とするのも、従来の韻学の用語や理解に無理に合わせ、あるいはhanumūlaすなわち顎の根本(奥歯)に該当するものとして転用したのかもしれませんが、曖昧として不明確であることから妥当ではない。
(ta)以下の五字は本来、まさに(上顎の)歯(の裏)に舌先を当てて発するものです。そういうならば、そもそも①kaṇṭhyaを「牙」とするのも、従来の韻学の用語や理解に無理に合わせ、あるいはhanumūlaすなわち顎の根本(奥歯)に該当するものとして転用したのかもしれませんが、曖昧として不明確であることから妥当ではない。
以上を踏まえ、智廣の用法を敢えて踏襲して、しかし梵語の発音についての規定に従いその正しい順を云ったならば、牙・喉・舌・歯・唇となります。『悉曇字記』にいわゆる五類声として挙げるうちの二番目の歯音と四番目の喉音は、その順序が倒錯しているのです。これは日本における平安時代以降の悉曇学者らがその音韻を考えた時、その理解に非常な混乱をもたらした原因の一つとなっています。
本書にそのように記述されていたことにより、日本で歴史的には「牙・歯・舌・喉・唇」の順で五類声は憶えられ、伝統的に理解されてきました。しかしまた同時に、悉曇学における根本典籍の一つでもあった『大般涅槃経』文字品の注釈書の理解が用いられ、第二から第四の「歯・舌・喉」は、それぞれ舌本・舌中・舌末を調音部位とするものであって、それを「三内」であると称されてもいます。
しかし、発音について今これを見た場合、それが印度以来の伝統からまったく乖離した誤りである、あるいは文字通りのものではないことを認識し、よくよく注意する必要があります。
もっとも、ではそのように言えるのは、近現代に初めて西洋由来の学問がもたらされて以降ようやくのことである、というのでもありません。これは従来の学者らが指摘しておらずよく知られていないことですが、入唐して印度および支那の学僧からその字と音とを直接学び帰った円仁は、五類声の順を本来通りに正しく認識していたことが知られるのです。これにより、智廣の記述が支那当地でも普遍的に行われていた理解では必ずしもなかったものであることがわかります。
それは円仁の悉曇学における業績として非常に大きな価値ある点の一つですが、円仁における梵字の発音に関する最も大きな功績は、それぞれの字をいかに発音すべきかを、漢語よりむしろ当時の日本語(本郷の音)を用いてなるべく詳細に記し遺していることです。
(詳細は別項”円仁『在唐記”を参照のこと。)
ところで、智廣は五類声について、支那古来の伝統的音階である宮・商・角・徴・羽の五音に同じなどとも述べています。しかし、それはただ「印度でも支那でも同じように音が五つに分類されている」と言わんとしただけのことであったろう、と思われるものです。ところが、日本では後代、五類声と五音とは文字通り対応するものだと捉えられています。それらは所詮、誤解の産物であって、『悉曇字記』を初めて学ぶに際し、このあたりのことは全く無視して構いません。
さて、『悉曇字記』は悉曇と体文などの計四十七字(五十一字)を示した後、悉曇の韻(摩多)と( (llaṃ)字を除いた)体文三十四字をその根本として用い諸字を構成するのに、一定の規則に基づいて十八章建てにて説明されています。その十八章というのも、智廣が独自に発案したものでなく、印度にて一般にそうされていたのに倣ってのことであり、それは師の般若菩提から教わった通りのことであったでしょう。
(llaṃ)字を除いた)体文三十四字をその根本として用い諸字を構成するのに、一定の規則に基づいて十八章建てにて説明されています。その十八章というのも、智廣が独自に発案したものでなく、印度にて一般にそうされていたのに倣ってのことであり、それは師の般若菩提から教わった通りのことであったでしょう。
八世紀の印度にて梵字悉曇が『悉曇章』の名のもと十八章建ての教えられていたことは、先に引用した『南海寄帰内法伝』の一節に続いて以下のようにあることによっても確実です。
本有四十九字。共相乘轉。成一十八章
(『悉曇章』で)その根本となるものには四十九字ある。(母韻と子音字とを)共に互いに合し転ずれば十八章となる。
義浄 『南海寄帰内法伝』 巻四(T54, p.228b)
ただし、『悉曇章』を構成する章数については、印度で時代によって変化していたか土地によって異なっていたことが知られます。
而開蒙誘進先導十二章。
(幼児らの)蒙〈無知〉を開いて教育するのには、先ず「十二章」から始める。
玄奘 『大唐西域記』 巻二(T54, p.228b)
玄奘が印度にあったのは七世紀中頃のことであり、それは義浄に先んじることおよそ半世紀前のことですが、こうして玄奘は(『悉曇章』は)十二章にて教えられていたことを報告しています。実際、奈良時代に仏哲によって伝えられていた『悉曇章』は十四章立てであり、また平安時代の空海よりやや遅れて唐に渡った僧が伝えた『悉曇章』の中にも十二章立てのものがあって、根本の字はもちろん同様であっても、その構成や内容が異なっていたようです。
(その後、現代に至るまでにいわゆる『悉曇章』の構成は、といってもそれは梵字によるものでなく現代印度で用いられているデーヴァナーガリーによるものではあったのですが、二十四章にまで拡大されていたことが、近代、実地に印度に入って梵語を学んだ比叡山の学僧、大宮孝潤によって紹介されています。といっても、その内容や新たな字が増やされたというのでなく、章立てがより細分化し整理されているため異なっているというのに過ぎません。)
しかしながら、いずれにせよ日本では『悉曇字記』が空海により伝えられて以降、そして宗叡や安然により本書が特に取り上げられ梵字悉曇を学ぶ根本とされて後は、あくまで十八章立てでその字を学び理解する習わしとなっています。
その第一章は、体文三十四字の各字に十二摩多を点じて十二字に転じるものです。例えばその最初の字である (ka)字を各韻をもって点じたならば、以下のようになります。なお、「点じる」とは摩多を字体に書き加えることを意味し、また「転じる」とは摩多を点じて元の字形をやや変化させることを意味します。
(ka)字を各韻をもって点じたならば、以下のようになります。なお、「点じる」とは摩多を字体に書き加えることを意味し、また「転じる」とは摩多を点じて元の字形をやや変化させることを意味します。
| 第一転 | 第三転 | 第五転 | 第七転 | 第九転 | 第十一転 |
|---|---|---|---|---|---|
 ka |
 ki |
 ku |
 ke |
 ko |
 kaṃ |
| 第二転 | 第四転 | 第六転 | 第八転 | 第十転 | 第十二転 |
 kā |
 kī |
 kū |
 kai |
 kau |
 kaḥ |
 字の場合、第五摩多(-u)と第六摩多(-ū)を点じる際には、単純にその元の字母の形どおりには点じられず
字の場合、第五摩多(-u)と第六摩多(-ū)を点じる際には、単純にその元の字母の形どおりには点じられず の字形とは異なる字形
の字形とは異なる字形 が用いられます。しかし、これは例外で、他の字の多くは字体を変えることなく摩多を点じ、場合によって字体でなく摩多を変形したものが点じられます。
が用いられます。しかし、これは例外で、他の字の多くは字体を変えることなく摩多を点じ、場合によって字体でなく摩多を変形したものが点じられます。
そもそも、字母の形を変化させずそのまま第五転を (ku)、第六転は
(ku)、第六転は (kū)とするのが、本書『悉曇字記』の説に従った字形であって、むしろ
(kū)とするのが、本書『悉曇字記』の説に従った字形であって、むしろ と異なった形の字母に摩多を点じるのが異例というべきものです。とはいえ、そのどちらが正しいとか誤っているということなどなく、いずれも字として可なるものです。ただし、上の図でそう示したように、今一般的であるのは
と異なった形の字母に摩多を点じるのが異例というべきものです。とはいえ、そのどちらが正しいとか誤っているということなどなく、いずれも字として可なるものです。ただし、上の図でそう示したように、今一般的であるのは (ku)そして
(ku)そして (kū)とする字形です。
(kū)とする字形です。
第一章は 字と同様に他の体文にも順次十二韻の摩多を点じたもので構成されます。いかに子音字を母韻にしたがって転開し、各十二字となるかを示す、最も基本となる章です。そのように各体文を十二字に転じるのは第一章以下第十四章まで同様ですが、第二章からは字体となる体文の下あるいは上、またはその双方に別の体文を半分にした字体、これを
半体といいますが、接合させ、より複雑な音を表現したものとしていきます。
字と同様に他の体文にも順次十二韻の摩多を点じたもので構成されます。いかに子音字を母韻にしたがって転開し、各十二字となるかを示す、最も基本となる章です。そのように各体文を十二字に転じるのは第一章以下第十四章まで同様ですが、第二章からは字体となる体文の下あるいは上、またはその双方に別の体文を半分にした字体、これを
半体といいますが、接合させ、より複雑な音を表現したものとしていきます。
第十五章以下はそれまでと異なった法則によってそのような結合文字が示されていきます。しかし、第十六章は例外となりますが、それらの字に十二韻の摩多を転じることは同様です。もっとも、第十七章では特に字体に接合する字、これを能合の字といいますが、それには一定の規則がないものであると伝統的に理解されてきました。ところが、そこに実際は明確な規則があったのですが、『悉曇字記』自身に誤伝が含まれているためにそれに気づくことはほとんど不可能となっており、そこで第十七章は「難学章」などと呼び習わされています。
また第十八章は、第一から第十七章に含めなかった字を集約し、かつ他の章のいずれにも含まれない独自の字および記号を示す章となっています。理論的にはその字数が無限とされ、しかしその例としていくつかの字が示されています。
| - | 半体 (上) |
字体 | 半体 (下) |
異称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 | - |
体文三十四字 | - | 単章 | 正章 |
| 第二章 | - | 体文三十四字 |  -ya |
余単章 | |
| 第三章 |  -ra |
||||
| 第四章 |  -la |
重章 | |||
| 第五章 |  -va |
||||
| 第六章 |  -ma |
||||
| 第七章 |  -na |
||||
| 第八章 |  r- |
体文三十四字 | - | 余単章 | |
| 第九章 |  r- |
体文三十四字 |  -ya |
||
| 第十章 |  -ra |
||||
| 第十一章 |  -la |
重章 | |||
| 第十二章 |  -va |
||||
| 第十三章 |  -ma |
||||
| 第十四章 |  -na |
||||
| 第十五章 |  ṅ- |
牙声の他四字 | - | 異章 (盎迦章) |
|
 ñ- |
歯声の他四字 | - | |||
 ṇ- |
舌声の他四字 | - | |||
 n- |
喉声の他四字 | - | |||
 m- |
唇声の他四字 | - | |||
 ṅ- |
遍口声の九字 | - | |||
| 第十六章 | - | 体文三十四字 |  -ṛ |
紇里章 | |
| 第十七章 | 規則無し〈実際はある〉 | 難学章 (阿索迦章) |
|||
| 第十八章 |  ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
孤合章 | |||
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 等 等当体重字三十二字 |
|||||
 等 等連声字 |
|||||
 ・ ・ ・ ・ 等 等両重摩多字 |
|||||
 等 等厳字 |
|||||
 ・ ・ 怛達(多達) |
|||||
 印文 |
|||||
ごく簡略に『悉曇字記』にて説かれる十八章の内容を示せば以上のとおりとなります。いずれにせよ『悉曇字記』を実際に読み、これがいかなる内容でどのような法則に基づいて章立てされているか確実にしなければなりません。中でも特によく『悉曇字記』を注意深く読まなければならないのは、第十七章および第十八章についてとなることでしょう。
(そして、『悉曇字記』が伝統的に標準とされ、学ばれてきたものではあるものの、しかしそこには梵語としてあり得ない誤謬も含まれており、その正しきを知ることも必要です。すなわち、日本における伝統的理解を『悉曇字記』を通して学ぶとともに、さらに梵語としての正しきを学ばなければならない。)
いずれにせよ、伝統的に悉曇を学ぶ者は、まず必ず『悉曇字記』を一度ならず数度に渡り読まなければ話になりません。より詳しくは、『悉曇字記』を確かに読み学んだ後、多く遺されている中でもいくつかの著名な註釈書にあたってその説の真偽を見分けつつ、本来の何たるかを学ぶが良い。
『悉曇字記』は、悉曇および体文、そしてそこから転じられた諸字の字形ばかりでなく、そもそもそれこそが智廣が知らんとした目的であってそれを伝えんとしたものですが、その発音について詳細にしようとされたものです。
頃嘗誦陀羅尼訪求音旨多所差舛 《中略》
以眞言唐書召梵語髣髴而已豈若觀其本文哉俾學者不逾信宿而懸通梵音
この頃、嘗に(梵字そのものでなく、漢字に音訳された)陀羅尼を誦して、その音旨〈音義〉を調べてみたところ差舛〈誤り〉が多くあった。《中略》
真言であるのに唐書〈漢字で記述されたもの〉によって梵語を読むのでは髣髴〈不明瞭〉でしかない。どうしてその本文を観るのに及ぶであろうか。(この『悉曇字記』により)学者をして信宿〈二晩〉を超えることなく、(梵語と漢語と)懸に(異なったものであっても)梵音に精通させられるであろう。
智廣『悉曇字記』
ただし、それが印度僧から直に教授されていたとはいえ、あくまで唐代の支那人の耳と口とを通した理解によって筆されたものです。特にその発音を説明するには、種々の工夫がなされているとはいえ漢字をもってなされています。当然それを後代の、しかも言語をさらに異にする異邦の者が筆者の意図を正確に理解するには、言うまでもなく非常な困難を伴います。
実際日本では、おそらく平安期の比較的早い時期、日本を出たことがなく、したがって異国の僧と交わりその説に接する機会をもちえなかった後進の僧徒において、やはり特に発音についての甚だしい誤謬が生じています。智廣が問題視した「訪求音旨多所差舛(音旨を訪い求めるに差舛する所多し)」という事態が日本で再現されていったのです。これは漢語がそうであったように、日本語もまた時代によって同じ文字であっても、その発音を時代により異にしていったということにもよります。
そしてその異なりは、今からすれば比較的大きなものであったと言えるものです。
したがって、今「伝統」とされる梵字の読みは、智廣の示したそれに全く異なり、また平安初期に唐に渡って梵字悉曇を学んだ空海を初めとする諸僧、いわゆる入唐八家らが発し、理解したそれとも異なっていると断じて疑いない。本稿にて底本とした江戸前期の澄禅により刊行された本には梵字のルビが付されており、それを本稿の本文にてもそのまま写して紹介していますが、それはあくまで日本の江戸前期において通用していた読みを示したものであって、本来の梵字のそれでは決してないことに注意する必要があります。
なお、そこで『悉曇字記』には梵字の音を正確に表現しようと、支那の四声と反切を以てしています。これについて事前に知っておかねば、『悉曇字記』の処々にて割り注されている言葉の意味がわかりません。
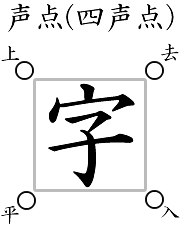
四声とは漢語における抑揚、声調のことで、平声・上声・去声・入声との四種をいうものです。それまでは他国の言語など蛮族の非文明的ものとして一顧だにしなかった支那人が、しかし仏教という外来宗教を熱心に信仰して梵語という他言語に積極的に触れた結果、それとの比較から漢語という自国語を客観視するようになってその声調を意識したのでしょう、南北朝時代(五、六世紀)頃から云われたしたものだとされます。以来、この四声を文字上に表現するのに声点(四声点)という発明がなされ、それを日本でも踏襲し、後代には独自の方法を編み出して日本語にも転用しています。
(現代日本語で用いられる濁点「゛」や半濁点「゜」は、声点を起源とするものであり、それが日本独自に発展して作られたものです。)
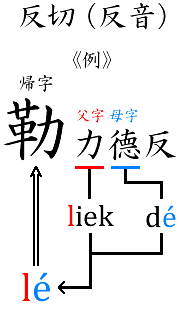
また反切とは、古くは反音ともいい、支那における伝統的標音法で、ある字の音をすでにその音が知られている二つの字を用いて示そうとするものです。
例えば、その音が不明である「勒」という字の音を示すのに、その字の直後に「力德反」とあるとします(本書での表記はほとんど「勒力德反」と割り注にてなされます。宋代頃からは「反」でなく「切」という字が用いられますが意味は同じ)。そこで勒を帰字といい、力を父字、徳を母字とします。帰字の音を示すのに、父字の頭子音(声母)をのみ取り出し、続いて母字の頭子音以外(韻母)を取り出して両者を組み合わせます。したがって、力徳反ならば、力(liək)の声母の「l」と徳(dé)の韻母の「é」をそれぞれ取り出し組み合わせ「lé」とし、それが勒という字の音(読み)であることが示されます。
当然ながら、智廣は唐代の人ですから、日本でいうところの漢音でもって諸字を理解しなければなりません。しかし、その漢音を復元するのは並大抵でありません。しかも、それを現代推測されている漢音にのみ依って復元した時には、その梵字の本来の音としておかしなことになる場合もままあることから、この問題は非常にやっかいです。
支那に伝えられ、日本で相承されていくうちに(本来からすれば誤り多くまったく的外れながら)独自の発展をみせた悉曇学あるいは梵学は、支那仏教の衰退とともに日本でのみ伝えられ、そもそもその文字体系としての悉曇は本国印度でも用いられなくなって、やはり日本でのみ使われるものとなっています。これは文化的観点から非常に面白く、貴重な価値あることでもあります。
ところが、近代に西洋からサンスクリット学がもたらされると瞬く間に、これは西洋由来の学問に携わる者としてそうなることは致し方ないとしても、日本仏教としても無反省・無批判に廃して無用のものとされ今に至ります。しかし本来、その伝統や相承の流れにある者がこれを全く捨て置くことなど出来ません。実際これを無視したならば、特に密教に関わる者にはその足元が瓦解するほどのものです。また、密教だけにとどまらず、そもそも日本仏教各宗派とは密教の影響を大なり小なり受けており、また梵字悉曇に全く感知しないものなどないことから、これを等閑視して良い筈もない。
かといって、古来の伝承に含まれる誤謬を誤謬・誤伝であると認識しながら、これで良いのだ等と愚かに強弁するわけにもいかない。いまだ日本仏教が(大勢としてはすでにそうでなって久しいとしても)伝統芸能や家族経営の商売でなく、宗教として生きたものであるというならば、これを今その立場から正し、また活かして用いる余地は充分すぎるほどにあります。
梵字悉曇が日本に伝えられた奈良時代、それが平安初頭に至って体系的にその文字としては盛んに学ばれるも、中世までその文法について足を踏み込む者はほとんど絶無のまま、さらにその音について取り返しのつかない多くの誤謬を膨らませつつありました。それが初伝からおよそ十世紀の久しき星霜を積み重ねた近世、当時としては出来うる限りその文法にまで踏み込んで追求した慈雲などが現れ、また音についてもそれまでの誤謬を打破して相当近いものを再現する行智 のような龍象が現れています。しかし、その先達らの遺志と成果を継ぐ者は今どこにあるのか。
往古からの種々の誤謬を正しつつ、もはや印度および支那では滅びてただ日本にのみ残されながら、すでに風前の灯となって久しい伝統を相承する礎とするべく、後学のためにその根本典籍として『悉曇字記』をここに示すものです。誰であれ好学の士であり、またこの縷縷として今にも断ち切れんばかりの伝灯を、後世につながんとする有志の人が幾らかでも現れることを期して。
貧衲覺應 記