
慈雲と神道との出逢い、それは先ず父上月安範が『大祓解 』を著すほどの信心家であったことにあります。末子であった慈雲は厳格で侠気のある父に心服しており、その姿を見て育ってたため幼心にも自ずから神道に対する敬意をもつようになっていたことでしょう。そもそも安範がそのように神道に心を寄せるようになっていたのは、法樂寺中興二世の 忍綱貞綱(左写真)に感化されたことによります。安範はその妻で慈雲の母お幸と共に、忍綱の信者であり仏神を奉じる人でした。
しかるに、慈雲が神道に具体的に触れることになるのは、忍綱から法樂寺住職を譲り受ける前、元文四年〈1739〉の二十二歳の時に菩薩流(西大寺流)の一流伝授を受け、さらに両部神道を伝授されてその灌頂を受けたときのことです。
両部神道とはまた御流神道ともいい、空海が嵯峨天皇から伝えられたと伝説される神道です。その実際としては、平安後期の慶円〈→三輪神道〉あるいは鎌倉前期の叡尊などにより理論的に成立し、伝えられたものです。両部とは、密教に伝わる『大日経』に基づく大悲胎蔵生曼荼羅と『金剛頂経』に基づく金剛界曼荼羅の二部を意味する語です。これを御流と称するのは、それが嵯峨天皇から伝えられたことに基づきます。
一般に両部神道とは、日本の神祇は仏菩薩の影あるいは分身として人々に則したより近しい形で現れたものであり、その本体(本地)はあくまで真理の具象化としての大日如来、あるいはそこから展開したその他の仏・菩薩であるという、いわゆる本地垂迹思想をその核としたものとされます。
ただし、慈雲は世間一般に理解される両部神道、たとえば伊勢神宮の内宮を大悲胎蔵生曼荼羅、外宮 を金剛界曼荼羅に充てるといった神道と仏教をまぜこぜにした俗説については、「世間に多く神と佛と合して兩部と云ふあり。謬りのみ」と、後代の人が歴史を無視した恣意的解釈、誤謬であるとその論拠を示しつつ完全に斥けています。
先ツ唯一兩部と云ふこと。今時やかましく云ふことなれば。是れを正すべし。唯一神道佛法を雜へずと云ふは 垂加翁云く。道貫天人。是謂唯一矣。謂不混佛儒爲唯一者甚非也 弘法大師の語にして 十種の神寶中の祝辭の註に。天津命なり不用佛法是のみ 又兒屋根ノ命廿一代の孫大職冠鎌足公が唯一の名を立られたと云ふ人あれど。其ノ語は名法要集に引く所の。我唯一神道は天地を以て書籍とし日月を以て證明とすと云ふ二三句より外には無い。彼の名法要集も。卜部兼延の作とあれど 兼延は延喜帝より後一條院の間の人也 是れも林道春疑ふらくは。時代の違もあれば此書兼倶の僞撰ならんと云へり 辯卜抄に曰。至兼倶兼右矯其祖業作神道護摩神道加持以稱自神代所相傳。且作名法要集而託兼延云云 何れにせよ。此の名法要集を見れば全く兩部神道なり。能々考へ見れば弘法大師より前に唯一と云ふ名を立テた人はたしかに無い。御遺告の中に中務省云々の語ありて。其ノ事をば書きあらはさねども。我傳には此の時嵯峨帝大師を野山より召請して中務省に於て神道を密談し給ふ也。帝の曰ク。我國に相傳の即位の時。手印を結ぶことあり 御卽位の式は二條家に傳へて。代々時に臨てこれを授奉ると。又大師の時御即位の寶冠に付て神道灌頂の基おこると雖。大師の世灌頂に緣なし。後三輪の慶圓上人神託を蒙りて始て行ひ。高野の宥快師も亦行へりと 師が傳ふる密教亦印多し。此ごろ我れ感ずること有て此の義を面談せんと欲する也と。遂に帝傳承の神秘を以 て大師に傳ふ。大師是れを受るに全く金胎の玄旨に合へり。即佛秘を開て帝に示す。是に於て皇帝大師の深意を得て神道を成立す。御流の名是れより起れり。神道の極處金胎の玄旨に合ふ故。亦兩部神道とも名る也。名法要集に大師流の神道と云ふは誤り也。若し大師自己に成立し給はゞ。人何ぞ御流と稱せんや 御の字を用るは天子と又皇后に限る故也 意を解し謬る人をば論ぜず。若し能く意を得る人に就て言はゞ御流卽唯一にして。唯一の外に御流なし。嵯峨帝御流の唯一と稱して可也。
まず「唯一両部」と云うことについて、今時やかましく云われていることであるから、これを正さなければならない。「『唯一神道、仏法を雑えず』と云うのは 垂加の翁〈山崎闇斎〉が「道は天人を貫く、これを唯一と謂う。仏・儒を混ぜざるを謂って唯一とするのは甚だ非である」と言っている。、弘法大師の言葉であって 十種の神宝の中の祝辞の註に「天津命である。仏法を用いず」というだけである、また 兒屋根命〈天児屋根命〉廿一代の孫、大職冠 鎌足公〈藤原鎌足〉が『唯一』の名を立られた」と云う人があるが、その語は『 名法要集』〈『唯一神道名法要集』.吉田兼倶が吉田兼延の著として捏造した書〉に引用される、「我が唯一神道は天地を以て書籍とし、日月を以て証明とす」と云う二、三句より外には無い。彼の『名法要集』も卜部兼延 〈吉田兼延, 平安中期の神職〉の作とあるが 兼延は延喜帝より後一条院の間の人である、これも林道春〈林羅山.徳川家康から家綱までの四代に渡り仕えた朱子学者〉が疑って「時代の違いもあればこの書は兼倶の偽撰であろう」としている 『弁卜抄』には「兼倶・兼右に至ってその祖業を偽り、神道護摩・神道加持を作って神代より相伝したものと称し、かつ『名法要集』を作って兼延に仮託した」とされる。 いずれにせよ、この『名法要集』を見ると(内容的には)全く両部神道である。よくよく考えて見れば、弘法大師より前に「唯一」という名を立てた人は確かに無い。『御遺告』〈空海の遺言とされる書〉の中に「 中務省云々」の語があってその事こそ書き表してはいないけれども、我が伝〈慈雲が相承した両部神道〉ではこの時、嵯峨帝が大師〈空海〉を高野山より召請して中務省〈太政官八省の一つ。帝に近侍して宮中の政務を司る省〉において神道を密談されている。帝は「我が国に相伝の即位の時、手印〈印契〉を結ぶことがある 御卽位の式は二条家に伝えられており、代々時に臨んでこれを(帝に)授け奉るという。また大師の時、御即位の宝冠に付けて神道灌頂の基が起こったともされるが、大師の世代で(神道)灌頂の縁は無い。後代に三輪の慶円上人が神託を蒙って始めて行い、高野の宥快師もまた行ったという。 師が伝える密教もまた印が多い。このごろ我は感じることがあって、この義を面談したいと思う」と云われた。遂に帝は伝承の神秘を以て大師に伝えられた。大師はこれを受けると、全く金胎〈『金剛頂経』と『大日経』〉の玄旨に合致しており、そこで仏秘〈密教〉を開いて帝に示したのである。ここに於いて皇帝は大師の深意を得て神道を成立された。「御流」の名はこれより起こったのだ。神道の極処が金胎の玄旨に合致するが故にまた「両部神道」とも名づけられた。『名法要集』に「大師流の神道」と言うのは誤りである。もし大師が自己に成立されたものであれば、人はどうして「御流」と称するのか 「御」の字を用いるのは天子とまた皇后に限られる故である。(このような)意を理解できず謬る人は論外とする。もしよく意を(理解し)得る人について言えば、「御流即唯一」であって唯一の外に御流はない。「嵯峨帝御流の唯一」と称して可である。
慈雲『入門十二通聞書』(『慈雲尊者全集』, vol.10, pp.387-389)
慈雲はその両部神道の相承を、若き日に受けていました。
江戸期に至る以前、それまで神道とは仏教の枝葉としての存在、いわば副次的なものと見なされつつ信仰されていました。正確には、両部神道が流行した鎌倉時代後期、伊勢神宮外宮の祠官、度会行忠が、仏教を主とする本地垂迹思想に対抗する説を唱えて伊勢神道(度会神道)の骨格を形成しており、また室町期には吉田神社の神官、吉田兼倶が仏教・儒教を神道に習合させた吉田神道(卜部神道)を立てるなど、仏教に対抗しようとする動きがすでに生じてはいます。
しかしながら、そのいずれもが結局は特に密教の教理、はてまたはその儀礼・作法の影響を多分に受けてそれらを換骨奪胎しようとしたものです。これは中世末期から近世の当時も非常に批判されていたことであり、慈雲もまたその杜撰なことを指摘しているのですが、吉田神道を立てた吉田兼倶など、種々の伝承や書典を多く捏造して展開しています。ところが吉田神道は政治的成功をおさめ、ついに従来神道を掌握していた白川家(神祇伯王)をしのぐ権威・権力を持つに至るのですが、その成立からして非常に性の悪いものです。
吉田神道(吉田神社)なるものは今なお京都に存在していますが、それが成立するに至った手口も主張も、現代の悪質な新興宗教などのそれとなんら変わりありません。現在の怪しげな神道系新興宗教の元祖、雛形というべき存在です。
ところが、江戸期に至り、それまでの日本で思想的中核を担ってきた仏教の座は朱子学に取って代わられ、むしろ仏教は蒙昧の徒の信ずる邪教と排撃されるようになります。すると今度は、仏教を雑えず、儒教・朱子学の立場から神道を理解する者が続々出ています。初期で言えば林羅山(林道春)がその代表的人物であり、朱子学の理気論をもって神道を解釈して種々の著作を遺しています。ついで山崎闇斎もまた同じく朱子学の立場から神道を理解し、垂加神道と称する一門を構えています。江戸期においてもっとも流行し、支持されたのはその垂加神道です。
それらは神道と儒教の折衷的神道でした。この垂加神道の門に学んで陰陽道を習合させたのが土御門泰福(安倍晴明の末裔)で、土御門神道(安倍神道)を形成しています。陰陽道が宗教化したのはこの時のことです。
慈雲が上に挙げた一節の中で「今時やかましく云ふことなれば」と言っているのは、そのような世間における神道の潮流が当時あってのことです。ちなみに、林羅山と山崎闇斎の両者とも、もと仏門にあったのが朱子学に傾倒して還俗し、廃仏論者となった人です。
(二世代も異なるため慈雲が山崎闇斎を直接知っていたことはありません。しかし、慈雲が志学を過ぎた頃に学んだ堀川にある伊藤東涯の古義堂の斜向いには山崎闇斎の私塾があるなど、その説に接して意識するに充分な地理的環境にありました。)
するとその一世代ほど後、儒者の内から朱子学の説に異を唱えたいわゆる古学派の偉才が次々出、それぞれ思想的、そして文献学的・語学的に大なる成果を挙げています。そこでそれら知の巨人たちを支持する人が多く現れ、世人にも復古主義の高まりが見られるようになったのでした。そのような復古主義的潮流は、やがて人の国粋主義をも刺激。その立場から仏教や儒教など所詮は外来思想「漢意」であると敵視し、それらが伝来する以前の神道をこそ日本固有のものとして理解し尊重しようとする立場が生じています。いわゆる国学です。慈雲の当時はその国学者の雄、本居宣長がまさに頭角を顕しだす頃です。
そのような優れた思想家が仏教外に多く立ち現れた時にあって、特に慈雲にとって見過ごすことが出来なかったのは、そのほとんど同世代の人である富永仲基でした。
(なお、慈雲は一世代前にいわゆる石門心学を唱えていた石田梅岩についても知っていましたが、何もわかっていない者などとして歯牙にもかけていません。)
大阪北浜の懐徳堂にて、その学問方針から世に鵺学問と揶揄されもした折衷的儒学を学び、さらに黄檗山萬福寺のいわゆる鉄眼版一切経校合に関わったことにより仏典に人一倍通じるようになっていた仲基は、延享元年〈1744〉に『出定後語 』なる一書を著しています。
その中、仲基は現代における文献学や比較思想と比しても遜色ない手法と論法でもって、大乗経典は後代の人によって仏説として捏造され次第に「加上」(思想的増広)されたものであり、仏説と言えるのは一群の阿含経典以外には無いという、いわゆる大乗非仏説を提唱。これは必ずしも仏教自体を排撃することを目的とした書ではなかったのですが、容易く反論することなど出来ない種々の根拠に基づき理路整然とした説に満ち満ちたものでした。そしてまた同時に、日本にある諸宗がいかなるものかの仲基による評価と指摘も述べられているのですが、それは今見てもなお端的で非常に鋭い、その核心を突いたものとなっています。 しかしそれは、大乗をこそ信奉してきた日本の僧、慈雲はもちろん当時の仏教者からすれば到底受け入れ難い説であって反仏教の書と見なされています。
『出定後語』にある仲基の説は、種々様々な思想家が躍動する当時にあっても飛び抜けて異彩を放ち、それほど世に広く読まれはしなかったようであるものの、一部の仏教外の人には大いに歓迎されています。本居宣長など、これを読んだ際には仲基の学徳と前代未聞のその鋭い論述とに感服し、「見るに目覚むる事ども多し」との感想を漏らしているほどです〈『玉勝間』巻八〉。
さらにまた仲基は延享三年〈1746〉、『翁の文』を刊行し当時日本において重要な位置にあった儒教・仏教・神道を、やはり比較思想的手法によりその長短を指摘しつつ、そのいずれの思想にも依ることなく独自の「道」を説くに至っています。
今の世に、神儒佛の道を三敎とて、天竺・漢・日本、三國ならべるものゝ樣におぼへ、或はこれを一致ともなし、或はこれを互に是非して爭ふことにもなせり。しかれども道の道といふべき道は、各別なるものにて、此三敎の道は、皆誠の道にかなはざる道也としるべし。いかにとなれば、佛は天竺の衢、儒は漢の道、國ことなれば、日本の道にあらず。神は日本の道なれども、時ことなれば、今の世の道にあらず。國ことなりとて、時ことなりとて、道は道にあるべきなれども、道の道といふ言の本は、行はるゝより出たる言にて、行はれざる道は、誠の道にあらざれば、此三敎の道は、皆今の世の日本に、行れざる道とはいふべきなり。
今の世では、神道・儒教・仏教の道を「三教」といって、天竺・漢・日本の三国に並び行われているもののように考え、ある者はこれらが(究極的には)一致したものだと言い、ある者は互いに(真偽優劣など)その是非を争っている。しかしながら、道ということについて、道というべき道はそれぞれ異なったものであって、これら三教の道はすべて「誠の道」には叶わない道である、と知らなければならない。なぜならば、仏教は天竺の道であり、儒教は漢の道であって、国が異なっているために日本の道ではない。神道は日本の道ではあるけれども時代が異なっているため、今の世の道ではない。国が異なり、時代が異なっていたとしても、道は道である筈ではあろう。けれども、ある道を「道」という言葉の根本は、それが行われているからこそ出た言葉であって、行われない道は誠の道ではない。故にこれら三教の道とは、すべて今の世の日本に行われていない道だと言うべきである。
富永仲基『翁の文』
このように仲基は言い、当時その優劣を競っていた三教全てに一定の価値を認めつつ、しかしそのいずれも時代あるいは土地にそぐわぬものとして突き放しています。
といっても、仲基はそれら三教において神道がもっとも低劣であり、下賤なものであると見なしていました。隠すこと、秘すことを良しとするその性癖を卑しいと見たのです。さらに当時、儒教の古学に始まり仏教や神道などに大きな影響を与えた復古主義的潮流にも異を唱え、時と場に応じた、いわば「今、ここにおける誠の道」をこそ行うべきであると『翁の文』にて主張しています。しかし、孤高の偉才、富永仲基はその一門を構えることなく延享三年〈1746〉に早逝。わずか三十二歳の生涯でした。
慈雲は当時の朱子学者や古学者、そして神道家の諸著作はもとより仲基の著作を明らかに、そしてつぶさに読んでいました。慈雲は『出定後語』と『翁の文』の説には批判的ながらも甚大なる刺激を受けたようで、宝暦四年〈1754〉の三十七歳の時、『神儒偶談』を著しています。
『神儒偶談』は『翁の文』に同じく寓意小説で、道に迷った儒者の師弟に宿を与えた寒村の翁にそれぞれ儒教(主に朱子学)と神道を代弁させ、対論していくという体裁がとられた書です。旅の儒者が名もない翁と対話していくうちその説に圧倒され、敬服していく様を描くことにより、神道はむしろ儒教より全く優れ、日本だけでなく古今・万国におし通じる普遍の道であると述べられています。
では、そこで神道とは何かというに、翁の言葉をもって慈雲は以下のように定義しています。
唯一箇の赤心これ我神道の敎なり。此赤心天地の道なり。神明の敎なり。名目條目ありて。くだヽしく敎を設るに非ず。論語に。孔子曾子に告て。參乎我道一以貫レ之と。子貢に告も此れに同じ。其の多く學て是を識すは。孔子の本懷にあらず
ただ「一箇の赤心」〈「せきしん」とも〉、これが我が神道の教え〈核心〉である。この「赤心」こそが天地の道であり、神明の教えである。(神道には)名目〈事物の名称〉や条目〈箇条書きにするなど列挙された規則など〉などによる、くだくだしい教えは設けられていない。『論語』〈『論語』里仁第四〉に、孔子が曾子に対し「参〈曾子の名〉や、我が道は一以て之を貫く」〈一とは「仁」であって、仁が孔子の思想に一貫したものであること〉と告げているが、子貢〈孔子の弟子。孔門十哲の一人〉に告げたのもこれに同じである。多く学ばせてアレコレと識らせることは、孔子の本懐ではない。
(神道はまさしく元来そのようなもので「一箇の赤心」に貫かれており、儒教のようにアレコレ教条をいわないのだ。)
慈雲『神儒偶談』(『慈雲尊者全集』, vol.10, p.162)
「赤心」を神道の核心と見、それを日本の世界に対して最も優れた所以であるとすること。それは奇しくもこのやや後に名を馳せていく本居宣長の見解と同じであり、またその国家観についても多く重なるものです。
學問して道をしる事がくもんして道をしらむとならば、まづ漢意をきよくのぞきさるべし。から意の清くのぞこらぬほどは、いかに古書をよみても考へても、古への意はしりがたく、古へのこゝろをしらでは、道はしりがたきわざになむ有ける、そもそも道は、もと學問をして知ることにはあらず、生れながらの眞心なるぞ、道には有りける、眞心とは、よくもあしくも、うまれつきたるまゝの心をいふ、然るに後の世の人は、おしなべてかの漢意にのみうつりて、眞心をばうしなひはてたれば、今は學問せざれば道をしらざるにこそあれ、
学問して道を知る事学問して道を知ろうとするならば、まず漢意をきれいに除き去らなければならない。漢意がきれいに除かれないうちは、どれほど古書を読んでも(その内容を)考えたとしても、古えの意は知り難く、古えの意を知らないのでは、道は知り難いものとしてあるのだ。そもそも道とは、もと学問をして知ることではない。生れながらの真心こそが道である。真心とは、良くも悪しくも、生まれついたままの心をいう。ところが、後の世の人はおしなべてかの漢意にのみ移って真心を失い果ててしまったため、今は学問しなければ道を知ることができなくなったのだ。
本居宣長『玉勝間』(『本居宣長全集』, vol.1, p.76)
宣長からすれば仏教など真っ先に唾棄すべき蕃神の教え、いわゆる「漢意」の一つに過ぎませんが、その仏教における当時の智者たる慈雲は、宣長と同じ様に神道を眺めていました。そしてその故に、慈雲によるこの指摘については、国学者の観点からしても誤りなかったと言えるでしょう。
ところで、本居宣長のいう「道」とは、ここで「真心」であるとされていますが、時にまた「上に行ひ給ひて、下へは上より敷き施し給ふものにこそあれ、下たる者の、私に定めおこなふものにはあらず」(『うひ山ぶみ』)というようなものでありました。そしてそれは荻生徂徠が定義した儒教における「道」とまったく重なるものでもあります。
では慈雲が意図していた「赤心」とは何か。慈雲は上記の一節に続け、以下のように述べています。
我神道は强て孔子の道に適ふを取にはあらざれども。彼の海外邊地の人も。古今聖賢と稱せらるヽ人は。自ら神慮にかなふなり。易係辭に。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣と。此の中乾坤とは天地なり。確然は健なる趣き。示人易とは。むつかしきことを拵るに非と云ことなり。神道より看れば。天も一箇の赤心なり。此の赤心を人に與て小兒の心とす。既に小兒の心なれば。五十年。百年唯この赤心也。人に易を示すなり。その仁義禮智信と云は。一箇の赤心を文字に移して。横説縦説せるなり。孟軻氏云。大人者不失其赤子之心者也と。隤然は順なる姿。地の法として天に順ず。示人簡と云中には。仁義禮智等の學でしるすべき名目は有べからざるなり。支那の仁義と云だに乾坤天地の道にはあらず。其上惻隠の心。羞惡の心などの名目は。此簡易の中にはいらぬことなり。孟子すでに赤子之心の道たることを知る。此惻隠等の名目は假り設し辭なり。
我が神道は、強いて孔子の道に適ったものだと云うのではないけれども、彼の海外辺地〈慈雲にとって支那はもはや辺地であった〉の人であっても古今の聖人賢者と称せられる人は、おのずから神慮に適っている。『易経』係辞に、「夫れ乾は確然として人に易きを示す。夫れ坤は隤然として人に簡を示す」とある。この中の「乾坤」とは天地である。「確然」は健やかなる趣きを、「人に易きを示す」とは難しいことを拵ることでない、と云う意味である。神道より観たならば、(儒教の云う)天も「一箇の赤心」である。この赤心を人に与えたのが小児〈赤子〉の心である。すでに小児の心であれば、五十年、百年とただこの赤心である。これが「人に易きを示す」である。その(儒教が説く)仁・義・礼・智・信とは「一箇の赤心」を文字に移し、縦横に説いたものに過ぎない。孟軻氏〈孟子〉は「大人とは其の赤子の心を失わざる者なり」と云う。「隤然」とは従順なる姿であって、地の法として天に順ずることである。「人に簡を示す」と云う中には、仁・義・礼・智等の学んで知るべき名目など無い。支那にて仁義などと云われるものは、決して乾坤天地の道でない。その上、惻隠〈あわれみ、いたむ思い〉の心や羞悪〈悪を憎み、恥じる心〉の心などの名目は、この「簡」や「易き」の中には必要ないもの。孟子もすでに「赤子の心」が道であることを知っている。この惻隠などの名目は、仮に設けた言葉に過ぎない。
慈雲『神儒偶談』(『慈雲尊者全集』, vol.10, p.162)
赤心とは、幼稚な子供の心というのでなくて、うそいつわりや飾り気なく穢れのない、素直で純粋無垢な心の謂です。その意は神道のいう「神」という言葉が何に基づいたものであるかを説明する下りによって、さらに明瞭となるでしょう。
次神と云ふ名を知るべし。先神と云ふ名は。鏡の中略にして鏡と云ふこと也。夫れ鏡は醜穢を照してけがれず。淨妙の本心を表するもの。鏡より佳はなし。故に以て表すと佛家にて言へば三摩耶形也 唯表示とするのみに非ず。
次に「神」と云う名称について知らなければならない。先ず「神」と云う名称は、「鏡」の中略であって「鏡」と云うことである〈忌部正通の説〉。そもそも鏡は醜穢を映しても穢れることはなく、浄妙の本心を表するものとして鏡より適した良いものはない。故に(神を鏡に)よって表すのだ仏家にて言うところの三摩耶形である。(鏡は神の)ただ表示としただけのものではない。
慈雲説 天如記『入門十二通聞書』(『慈雲尊者全集』, vol.10, p.391)
ここでいわれる「淨妙の本心」は「一箇の赤心」と同じです。それがまさに「鏡」の如きものであることから「神」という、とされます。この理解は、南北朝期の神道家、忌部正通の『神代巻口訣』の説が近世前期の仏学・儒学・国学の諸家に注目されもてはやされていたのですが、それを慈雲も踏まえて云ったものです。
儒教が伝わる以前、日本には独自の文字も無く典籍も無く、また礼節も無い畜生に等しい野蛮の国であったとする儒学者らの見方。慈雲はその真逆から、むしろ文字も典籍も無く、また明文化された教条によって人を陶冶する必要も無く、しかし天から起こり万世一系の皇統をもって伝わった日本の神道こそ根源的であり、普遍的であると主張しています。
そのような『神儒偶談』からは、江戸初期に著されていた山鹿素行の『中朝事実』の影響も看取出来ます。近世中期には儒者の中にすら、支那を「中華」すなわち世界の中心、文明の中核であるとする従来の見方を否定し、むしろ日本こそが中華であろう、とする者が出てきていました。それもただ闇雲に国粋主義に没入した結果というのでなく、漢学の研究を進め、また儒教のいう天道・天命というものを真剣に考えてこそのことです。天命を受けて世を統べるのが皇帝であり、その帝に忠義を尽くすことを説きながら、歴史上二十数度も反乱・反逆が起こり、王朝が幾度も変わっている事実はいかなることか、という疑問から、その皇統を絶やさずきた日本の方がより優れており、まさに中朝(中華)である、という結論に導いているのが『中朝事実』です。
また、慈雲が神道の核心とした「一箇の赤心」は、中世にて明恵上人が口癖のように弟子たちに語っていたという「阿留辺畿夜宇和」に連なるものでもありました。慈雲は近世盛んに出版されていた明恵の本もよく読んで深く敬しており、その主張に大いに賛同してそこに普遍性を見出していたのでしょう。実際、『神儒偶談』をはじめ、その他慈雲の著作の端々には「あるべきようわ」の思想が顕れています。
就中、『神儒偶談』には、当時活発であった朱子学・古学・国学における学者らの活発な動向、そして特に仲基の著作に触れ、洋の東西や時の今昔など比較的相違を超えた「普遍の道」を示さなければならないという慈雲の意識の芽生え、ある種の強烈な使命感が伺えます。慈雲はこの頃、アメリカやヨーロッパにも眼を向けてその著のところどころにて言及しており、国際的視野も有していました。
(当時の江戸の知識人は、頑迷な儒者や仏者は除くとして、すでに地球が丸いという西洋由来の説を知り、それをすんなり受け入れています。)
この頃芽生えていた意識はその生涯を通してあり続け、慈雲はこの二十年後、仏教の十善業道をもって「普遍の道」を示さんとした『十善法語』を著し、さらにまた『人となる道』を著していくことになります。それは十善戒を慈雲から受けていた皇家に縁の深い女性信者(桃園天皇の皇子貞行親王の乳母)らによる請いに応えてのことでしたが、十善こそ諸々の思想・宗教を超えた道であることを、その該博な漢籍の知識と仏教の理解の深さから様々に説き示しています。
今一般に、慈雲が神道に造詣を深めていったのはその晩年のこととされています。実際、その詳細について諸々の文献を渉猟したのはその頃のことかもしれませんが、慈雲が神道に意識を向けていたのは壮年のころであって『神儒偶談』にそれがよく顕れています。それは前述したように、慈雲が弱冠を少し過ぎた頃に両部神道を受けていたことにそもそも基づいてのことです。しかし、『神儒偶談』を著す契機となったのは富永仲基の存在でした。そして『神儒偶談』を著す頃に強く持っていた意識が、『十善法語』および『人となる道』においても明瞭に顕れたのでした。
もっとも、そのような当時の日本における本居宣長など国学者や慈雲など仏教者からする神道というものに対する見方は、実は日本に宗教としてはほとんど全く根付かなかった道教の源である老荘思想がそれぞれの立場から形を変えて表出したものであった、と言うことが出来ます。そもそも『老子』や『荘子』自体が、支那において儒教の所説に対抗、反駁しものであったのですが、菲才はまさにそれが顕著に現れたものと断じて見ています。
大道廢、有仁義。智惠出、有大僞。六親不和、有孝慈。國家昬亂、有忠臣。
大道廢れて仁義有り。智惠出でて大僞有り。六親和せずして孝慈有り。國家昬亂して忠臣有り。
『老子道徳経』巻上 第十八
儒教が取り立てて強調する仁義などの徳目。それは本来、わざわざ言うまでもないことであって、口に出して言わなければならないのは、世にそれが行われていないからこそのこと。したがって、それは副次的・二次的なもの。あるいは「知る者は言わず、言う者は知らず」であって、『老子』からすれば、知らないからこそ言うものでした。
絶聖棄智、民利百倍。絶仁棄義、民復孝慈。絶巧棄利、盗賊無有。此三者、以爲文不足、故令有所屬。見素抱樸、少私寡欲。
聖を絶ち智を棄つれば、民の利は百倍す。仁を絶ち義を棄つれば、民は孝慈に復す。巧を絶ち利を棄つれば、盗賊有ることなし。この三者、もって文足らずと爲す。故に属ぐ所あらしめん。素を見し樸〈切り出しただけの丸太.転じて「本性」・「素直」の意〉を抱き、私を少なくして欲を寡くす。
『老子道徳経』巻上 第十九
したがって、『老子』の立場からすれば、そのような徳目をわざわざ学ぶということは愚かなことで、人の真実を知るにはむしろそのような学など捨ててこその話、とされます。
第十八の「大道廃れて仁義あり」もまさしくそうですが、これらの章に続く第二十の冒頭もまた、国学者が儒教を批判した趣旨とほとんど同じようなものとなっています。
絶學無憂。唯之與阿、相去幾何。善之與惡、相去何若。人之所畏、不可不畏。荒兮其未央哉。
学を絶てば憂いなし。唯〈同意を表す言葉。「はい」〉と阿〈ゆっくり答える声。「うん」〉と相い去ること幾何ぞ。善と悪と相去ること何若ぞ。人の畏るる所は、畏れざるべからざるも、荒としてそれ未だ央きざる哉。
『老子道徳経』巻上 第廿
このような『老子』の思想は、日本でも奈良・平安期に比較的よく学ばれ意識されていたもののやがて潜んでいたのが、近世において突如として再び表出したのではありません。『老子』において記された精神性は、日本人の侘び・寂びなどといった美意識や世界観にも大きな影響、いや、その核となっていたとすら言えるものです。その例は挙げれば切りが無いほどながら、『老子』や『荘子』など全く読んだことなど無いのが大半となっているにも関わらず、老荘思想は外的・儀礼的な宗教としてでなく、今の日本人の精神にもあまねく染み込んでいます。
ただし、これは今の人も理解して置かなければならないことですが、老荘思想が存在し得るのは、あくまで儒教の素地があってこその話であり、儒教無しに老荘など有りえません。『老子』はあくまで儒教の経典・経学が存在してこそ価値があるものです。平城京の昔から日本で儒教も老荘も学ばれていましたが、特に近世において儒教が世に盛行したためその価値はいよいよ大きくなり、しかし儒教のカウンターパートとして神道(国学)の形をとって現れたのでしょう。
慈雲のいった「一箇の赤心」もまた、慈雲は『孟子』にその根拠を求めており『老子』をその元を探る対象にしていません。慈雲もそこまで気づくことはなかったのでしょう。しかしそれは、まさに『老子』がその理想としたものにこそ同じでした。
知其雄、守其雌、爲天下谿。爲天下谿、常徳不離、復歸於嬰兒。知其白、守其黒、爲天下式。爲天下式、常徳不忒、復歸於無極。
その雄〈男性・父性,陽〉を知りて、その雌〈女性・母性,陰〉を守れば、天下の谿〈谷川〉と為る。天下の谿と為れば、常の徳は離れず、嬰児〈赤子.ここでは人の根源、本性〉に復帰す。その白を知りて、その黒を守れば、天下の式と為る。天下の式と為れば、常の徳は忒はず、無極〈世界の根源〉に復帰す。
『老子道徳経』巻上 第廿八
なお、慈雲はそのように著した『十善法語』について、自ら「我を知り、我を罪するものはそれただ十善法語か」とまで述べています。その語は『孟子』における「知我者其惟春秋乎。罪我者其惟春秋乎(我を知る者は其れ惟だ春秋か。我を罪する者も其れ惟だ春秋か)」の言に重ねたものです。もっとも、直接的には慈雲が若かりし頃に古義堂にて受学した伊藤東涯の父であり師であった伊藤仁斎による名著『 語孟字義』〈『論語』・『孟子』に対する一種の注釈書〉においてこの一節を解釈するに用いた「我を知り我を罪する者は、其れ唯春秋か」という語を元にしてのものでした。当時の知識人は、それを信奉するしないに関わらず、押し並べて儒教などの漢籍の素養が必須でありましたが、慈雲も若い頃に積んだ学問の素地がこのような言葉の端々にもよく現れています。
いずれにせよ、『十善法語』などにおいて強調された「万国におし通じる」普遍を主題とするその基にして嚆矢となっていたのが『神儒偶談』です。慈雲がここでいった「一箇の赤心」は神道における表現で、それを仏教の立場からは「一箇の直心」と言っていますが同じことです。そしてその一箇の直心を展開したものが十善でした。それはもはや仏教がどうのということも超えた、普遍なる道としてのものです。
したがって、『十善法語』などその類書をより深く理解するには、また『神儒偶談』をはじめとする慈雲の神道関連の書にも触れる必要があります。いや、先に述べてきたように、慈雲が常に意識を向け、様々な意味で影響を受けていた近世における豊穣なる知の巨人たちの動向、その言葉を知らなければならない。
なお、慈雲は『神儒偶談』においてその書の体裁から、そして神道に対する信条として、仏教をさほど俎上に載せていません。ただ神道や儒教の概念を説明するための参考や事例として、仏教の典籍からの引用を所々でなしています。そして、「今時の坊主衆」により仏教を神道に雑えて理解する仕方がどれほど誤ったものであるかや、「近世諸宗の坊主衆の云ふところ。誠の道とは得おもはぬなり」と、いかにその見識が低劣で信じがたいことを、言葉少なくながらも厳しく批判しています。
儒教については、神道からすれば一段降ったものであるとしつつもその価値を認め、斟酌して学ぶべきとしています。もっとも、朱子学については「仏教の似せそこない」などとして、それはもうケチョンケチョンに否定し、杜撰な説を唱える儒者らを「腐儒」として強く批判しています。実際、朱子学は仏教の思想体系や世界観からの影響を強く受けて成立したのであり、慈雲のそのような指摘は多分に正しいものです。
両部神道の相承者であった慈雲は、神道の諸事について仏教の教理を確たる伝承や根拠もなくいたずらに雑えて理解すべきでないことを言い、しかし神道灌頂や神道三昧耶戒など密教の儀礼を通して他に伝授していました。そんな慈雲にとって神道とは有為の道であり、仏教は無為の道であって、いわば「普遍の光と影」のようなものです。
我が傳の大意は有爲の儘に無爲の邊を佛道 と稱し。無爲の儘有爲に住するを神道と稱す。達人の眼には唯一神道即佛道にして。本自妙合なれば。附會することを須ひざる也
私が(相承した神道の)伝の大意は、有為のままに無為の辺を(目指すことを)仏道と称し、無為のまま有為に住することを神道と称する。達人の眼には唯一神道〈両部神道〉は即ち仏道であって、元から妙合したものであるから、(仏教を以て神道を解釈するなど)附会しないのだ。
慈雲説 天如記『入門十二通聞書』(『慈雲尊者全集』, vol.10, p.390)
したがって、仏教と神道との両者をいたずらに交えて語ることなどできず、また交える必要の無いものとなっています。慈雲にとってその両者は表裏一体でした。けれども慈雲のいう神道とは、「密教に入るにあらざれば知ること能はず」と、密教が日本に伝わったことによってこそ理解できるようになったものです。
実際、慈雲もそれは百も承知ですが、「神道という確固たるもの」が儒教や仏教伝来以前にあったとはとてもいえず、ただ神話と古代以来の氏族や土地それぞれの祭式があったのみです。古代に仏教が伝来したという刺激に因ってその独自性が意識されつつ、しかし併行して信仰され、特には密教からの理解に基づいてその教義の如きが中世となってようやく形成されていったものです。そのようなことからすると、今の我々が知る神道とは、仏教と儒教の存在によってこそ形作られたものであって、それらと習合することなしには有り得ませんでした。
それは『老子』や『荘子』が儒教の存在なしには有り得なかったこと、儒教の教条や体系を抜きにしてはその言に意味などほとんど無いようなことと、その構造として全く同様です。
(より正確に言えば、現在我々が神道と思っている諸々のほとんどは、そのような近世末にいたるまでの神道・国学の潮流の上に、さらに明治新政府によって、これはある種の欺瞞であったのですが、名目上は「宗教でないもの」として形成された国家神道体制下の諸制度や概念を色濃く引き継いだものです。したがって、今我々の見る神道とはそう古いものではない、というよりごく新しいとすら言えたものです。現代の日本人が神道をして「宗教ではない」あるいは「宗教とも思われない」と考えるのは、実は明治から終戦後しばらくまで国家神道が宗教ではない、とされていたことがその理由の一つです。)
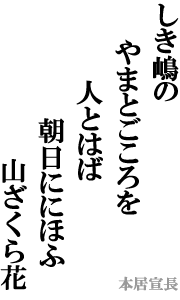
近世の中後期に国学者らが主張した古神道などは、儒仏を排そうとする復古神道という一種の意識形態(イデオロギー)であって実態を伴う特異で体系的な思想としてあったものではありません。とはいえ、当初の国学者らが探り追求したいわば純日本の精神というものが無かったわけはなく、それは確かにあった。賀茂真淵や本居宣長がそうしたように、『万葉集』や『源氏物語』など往古の歌や物語、随想・随筆など文学を通して今もそれを知ることが出来るでしょうし、事実彼らはそれを確かに見い出して「上代之道」あるいは「大和心」と称していました。それは儒教や仏教の教条を離れ、それらに縛られることのないより自然で素朴素直な心をいうものです。
慈雲はそれと同じものを「一箇の赤心」として日本独自の精神でなく人一般に備わる普遍のものと見ました。そこでそれを核とする神道は、故に他より一等優れた道であると考えたのでした。
前述したように、今それをさらに俯瞰する立場からすれば、それは老荘思想を日本人が代々咀嚼し、文学的・芸術的素地の中にも吸収してきた精神でした。それがまた日本において儒教が知的・道徳的な根拠として主流なものとなったことにより、それへの反発・反動として、しかし神道の名の元に、その核として見直されたものです。
慈雲は『神儒偶談』を著して後、自身が相承した両部神道に関する書をその晩年に至るまで盛んに著して、かなりの量にのぼっています。それはやがて、慈雲が伝えた神道であったことにより「雲伝神道」などと世に称されるようになります。しかし、慈雲からすれば師から相承した神道の真を世に示し伝えんとしたに過ぎず、それも『日本書紀』・『古事記』・『旧事記 』など三記はもとより儒教及び仏教をよく知り、さらに当時の神道の潮流を知った尊者であるからこそ出来たことではあったのですが、そのような慈雲に特殊の伝かのような後代の称は不本意なものであるでしょう。
しかるに今、その雲伝神道なる称を以てされる神道の正体は、慈雲の名声と同様に、ほとんど世に知る者も理解し得る者もなくなり、ただ現代の僧職の人によって細々とその形式的伝授が行われるのみとなっています。
下愚道人 覺應