仏教の術語を理解しようとその漢訳と英訳とを比較参照した時、その訳が適切かどうかを判じるのは確かに色々難しいことがあります。実際、先に示したように、satiもまたその範囲はそこまで広くはなくとも多義語であって、これを一つの訳のみで済ますことは出来ません。
例えば他に、サンスクリットでmaitrī、パーリ語でmettāという語があります。支那以来、日本でもこの訳は「慈」であり、現代語としてはこれを訓じた「慈しみ」でありましょう。そこで今、この語について、私自身もまったくそう思いますが、日本では「慈と愛とは同一のものではない」・「慈と愛とを混同してはならない」・「mettāをLoveと訳すのは不適切である」という意見が強くあるように思われます。ところが、欧米におけるその一般的な訳は、実は「キリスト教由来の造語」であるloving-kindnessですでに定着しています。
南方の学僧や学者らは、高度な学問を修得するにはどうしても自国ですますことが出来ず、イギリスかアメリカに渡り、主に英語で学問を積まねばなりません。また、セイロンやビルマにおける国立大学や最高学府といわれる所であったとしても、そこに属する彼らは母国語ではなく英語で仏教を学び、論文も英語で書かなければならないことが多いため、そのような欧米人に依る英訳をそのまま受け入れ、大体あたりまえのように使用しています。
これはほとんど全く日本語のみで学問を積んでしまえる日本の諸学会とは、まったく異なる点です。
それは、幕末から明治期、欧米の思想を学び導入する際、あらゆる分野における術語をいかに訳すべきかとする翻訳作業において、旧来の語を転用し、あるいは新造語を生み出すなどしてきた、有名無名の先学達が積み上げてきた成果です。そして、先学たちはただ外国の書を翻訳しただけでなく、砂が水を吸い込むかのごとくしてドシドシ理解、吸収し、大学や研究機関そのものやその前身を設立してさらにその知識を自ら磨いていった、その功徳です。
それが可能であったのは、近世の武士や裕福な町人達が、儒学(特に朱子学、そして古学)を主軸とする教養をごく当たり前に備えて合理的精神を育み、さらに進んで種々の新たな思想を自ら生み出していたという素地があったからこそのこと。それは今の日本を形作った不世出の先学達の偉大な、我々がその恩に報い盡くすことなど出来ないほどの果報というものです。
といっても、今の日本においても、その道の一流になるには、近代の先達のほとんど多くがそうしていたように、やはり必ず外国語の一つや二つは習得したうえで「まともな」留学経験を積む必要は未だあります。すでに道が敷かれ、あるいは地図が示されていても、そこを歩くのはあくまで自分自身であるのだから。
さて、学問の分野だけではなく、戦後にむしろ欧米で成功した瞑想法や瞑想道場の運営法・指導法などが東南アジア・南アジアに逆輸入され、英語によって書かれた本がそれぞれの言語に翻訳され行われている場合すらあります。世界のその様な潮流において英語は必須、話せて当たり前となっています。
そして、日本でsatiを「気づきだ」と言い始めた人、また続いてそう強調する人々は、まず必ず海外留学や生活の経験者で、そのような英語圏での潮流に触れた人間のようです。触れることは大いに結構なのですが、それですっかり「かぶれてしまった人」というのが出てきます。それは明治や大正期、当時洋行した日本人が「西洋かぶれ」になって無批判にその文物ばかりか思想もありがたがって導入し、古来の文物を穢れた塵芥かのように忌み嫌って捨て去ろうとしたことの、いわば再現が行われたようなものと私は見ています。
近世は支那の、近代は欧米の文物・思想がひどく珍重されたように。それで良い場合もあるのですが、そもそも「かぶれた文物」が間違っていたら困ったことになる。
そういえば、その昔、仏教を受け入れて次々ともたらされるインド語や中央アジアの言語などで記され伝えられた膨大な典籍を翻訳することが、国が傾くほどの大規模な国家事業でもあった支那では、翻訳に際して生じる諸問題に対処すべく、様々な原則・指針が立てられています。たとえば釈道安による「五失本 三不易」、玄奘の「五種不翻」です。そんな伝統的観点・基準からすると、smṛti(sati)について言えば、五種不翻すなわち「祕密故」・「含多義」・「此無故」・「順古故」・「生善故」のいずれにも該当しないものであるため音写などせず、むしろ必ず訳さなければならない語です。
しかし、諸大徳による危機意識と努力により、そのような基準が布かれたとは言え、それでもなお多くの難点が残りました。いまだ日本にもその弊害というべき影響が強く残っているほどに。それに対して、現代の優れた諸学者によってなされたサンスクリットやチベット語、パーリ語仏典などからの英訳は、漢訳仏典に見られるような修辞問題が少なく、またほとんど学究的になされたものであって、おおよそ信頼度の高いものではあります。しかし、それでもそこには西洋版の、いわゆる格義仏教的な要素・理解がところどころにひそんでいます。先ほど例に挙げた、[S]maitrī、[P]mettāはそんな語の中の一つです
とは言え、であったとしても、欧米における科学的な、実証主義的な知見から理解された仏教というものには、我々に仏教の価値の再確認や新発見をももたらす、まこと有益なものが多くあります。いや、おそらくその影響をまったく受けていない仏教者など、現代の日本の学者らや僧職者らはもとより南方の分別説部の比丘らであっても、まず一人としてありはしない。その少なからぬ影響、その恩恵ともいうべき様々な学的成果や、非常なる利便性をすら、我々は知ってか知らずか享受しているに違いない。
けれども、日本人は昔からそのような傾向が強いようですが、なんでもただ「海外(欧米)でそういわれているから」などと闇雲にありがたがって珍重してはならず、重要な語や概念に関しては、やはり原典や注釈書類に直接あたって自らその適否を確認し、理解しなければならない。
そして、そのような態度を取るべきことは、日本の伝統的理解についても全く同様に言えることです。伝統的であるから正しい、などということは必ずしも無い。でなければ言葉だけがひとり歩きしてしまうことがきっとあるでしょう。
satiという語はまさに、今そのような態度を取るべき語の最たるものと言えます。
仏教の伝統説からすればそれが決して正しいものでなかったとしても、現代の欧米において行われているMindfulnessという語に込められた、新しい解釈と実践法とが全然意味が無いだとか邪道だとかなど毛頭思いません。
彼らがMindfulnessの理解として好んでしばしば用いる「The here and now.(今、ここ)」だとか「The present moment(この今という瞬間)」や「The moment to moment(この瞬間、瞬間)」だとかという表現や捉え方も、形而上学的な思考を厭う啓蒙思想がある程度浸透した現代人好みで受け入れやすい、いわば時代に適したものであることも理解できます。
実は、そのような「今、ここ」という表現は、現代に西洋で受容された仏教から生み出されたものではなく、18世紀の欧州にて生まれた啓蒙主義から実存主義へ展開する中、そして19世紀のアメリカで生まれた実用主義の潮流において盛んに用いられたものです。それが西洋的に再解釈された仏教由来の修道法における一概念、Mndfulnessと融合した結果、さらに人口に膾炙され、世界的に用いられるようになったのでしょう。
西洋、特にアメリカには、それを受け入れる土壌というものが存していたのです。
ただし、そのような西洋でもてはやされた「今、ここ」という理解・表現に影響され、浅はかにもそれにかこつけて、日本で「念とは、今の心を見るから念である」・「心を今に留めることから念である」などと言った、その漢字の成り立ちを知らずして思いついた珍説を、さも昔からそうであったかのように言う者らは誠にあさましく、また愚かに過ぎるというものです。
そして、そのような欧米におけるsatiに対する理解と表現は、ただ上座部のみからの影響からそう言われているのでもありません。それはまた、特に日本の鈴木大拙によって欧米に紹介されたZen、それは必ずしも伝統的禅でなく、しかもかなり西洋的に理解され変質したと言い得るものですが、および近年物故したベトナム人僧Thich Nhat Hanh の活動の影響も受けてのものである、とむしろ欧米人自身らによって理解されています。
私見では、そのような西洋で受け入れられた東洋人によって主張された大乗の思想と、先ほどから述べている上座部の運動に端を発し西洋で受容されたMindfulnessに特別な意味を付してきた潮流とが、融合して形成されたものというのが正確です。
東南アジアの分別説部と日本の禅など仏教の修道法が欧米においてMindfulnessとして需要され、その実践による様々な「効用」が西洋人らによってカガクテキに確認・証明され、ますます流行してきました。ただし、それは欧米において、「解脱」などという仏教的・宗教的目標を目指すものでは到底なく、あくまでストレス軽減や精神の安定を目的として謳われているものです。
そこで、そのような西欧化された理解や方法であるにもかかわらず、それを以て「純正仏教(上座部)が古来そのように理解し実践してきたこと」だとか、それが「仏教本来の理解であって、我が純正仏教のみがそれを正確に伝えてきたこと」などと、日本における一類の人々が謳う主張が真であるかといえば、全くそのようなことは無いわけであります。
日本においてなぜそのような主張を盛んになす者等があるのか。それは、そのような西洋の潮流に乗じ、あるいはそれらが無自覚に併されて、日本でセイロンの分別説部が紹介されてきたという事情が大きく作用したに違いありません。それを行ってきた当人らも、おそらくビルマにおける新運動に端を発する西洋での新たな潮流・解釈というものに対する自覚や知識なども無く、「そもそもそういうものなのだ」などとまったく信じて疑わずにきてしまったようです。
その故に、上座部を日本で本格的に布教し、またそれを信仰した者の一部が「ヴィパッサナーだけ」などという偏向した主張を声高に、そして盛んになし、「日本の大乗諸宗や北伝の説一切有部などにおける『誤った理解』とは異なり、我が信奉する純正仏教は古来正しく念について理解してきた」といった軽々な物言いをしてしまったのでしょう。
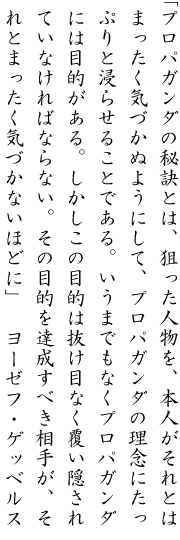
またさらに、そんな彼らがその独自性を強調して教線を拡張しようと急であったがあまり、大乗や説一切有部など他宗・他流に対してだけではなく、むしろ自身が信奉している部派への理解や知識ですらも不十分であるのに関わらず、なんとか他派・他流を矮小化しようと努めてしまった。そしてそのような誤認に基づく様々な排他的・先鋭的主張をなし、それをむしろ有効な布教の手段だと考えてしまったことが伺われます。
しかしながら、それは賢明な方法であったとは到底思えるものではありません。誠に残念な話でありましょう。それによってむしろ、日本における上座部全体に対する見方が否定的になってしまった向きも一部あるためです。上座部は部派としてただ一つ現存するものであるという点においても、またその教義と伝統においてもすぐれて有益で尊く、須らく学ぶべき仏教の一派であるのに。
先に指摘したように、 それに似たようなことは、日本の中世鎌倉期に生じたいくつかの「新仏教」などといわれる宗派においても連綿と行われてきたことです。すなわち浄土教徒や法華宗、そして曹洞宗などが主張してきた選択・一向・専修・只管打坐 などといった、「これだけが本当」・「これのみで良い」とする態度と同じです。
嗚呼、そうか…、なるほど。このようにして日本仏教の特徴、異常な点の一つして挙げられる、いわゆる祖師無謬説は形成されてきたのでありましょう。それがまさに現代において再現されているのを、我々は目の当たりにしていると云うべき事態です。このような頑ななる精神は、古代中世から、いや、有史以来変わらずあり続けているようです。
小人の過つや必ず文る。
(過ちは誰でも犯すものだけれども)小人は過ちを犯したならば、必ずその非を認めず、誤魔化しの言葉を述べる。
『論語』子張
人は誤って当たり前のものです。困ったことに、愚かな私などしばしば誤って直すべき点があまりに多くあります。けれどももし、我々は、我がうちに誤りのあることが知れた時には、「直に」とは中々いかなくとも、努めて修正していけば良いだけのこと。
それが本来の君子豹変というもの、でしょうに。
君子は豹変し、小人は面を革む。
君子は自らに非のあることを気づいた時には、豹の毛が生え変わる時のように、たちまちに非を改める。しかし、小人はただ表面上取り繕うだけで我説・我流に固執する。
『易経』革卦・上六
仏教の説く菩提(覚り・悟り)というものを、「それまで知らなかった事物の真のあり方に『気づくこと』である」とし、その修道法としての念あるいは観の瞑想がそれを目指し、到達するのに必須のものであるということからそのように言うのだ、と反論する者があるかもしれません。
Buddha(仏陀)やBodhi(菩提)の語根はbudhで、その意は「目覚める」です。故にBuddhaとは「目覚めた人」であり、Bodhiとは「目覚め」です。仏教とは、「人生の苦しみの由来・根源とその除滅、そしてその方法に関する真理」に対して目覚めることを目標とする宗教です。
今まで知らなかった真理について知るという点からすれば、厳密には不正確ではありますが、budhをまた「気づく」と訳し、Bodhiを「気づき」すことも一応可能ではありましょう。そのようなことから、「仏教は菩提という『大いなる気づき』を目標にするものであって、その修道においてsati(念)は不可欠であるから、satiを用いる修習法を『気づきの瞑想』というのだ」とするのであれば、仮にそのように言うことは出来る。けれども、念を重んじない、念を不要とする修習など、金剛乗・大乗・声聞乗の仏教通じて存在しません。すなわち、仏教の修習法・瑜伽法は、それが経論に基づいた正統なものであれば、総じて「気づきの瞑想」ということになる。
おそらく、彼らが「自分たちは日本で僧を自称する人々や大乗とは異なる」、「彼奴らと我々は違うのだ」などとやたらと強調した背景には、近世以来そして近年に至ってより一層悪化したと言える、ただ因襲としての祖先崇拝・葬祭儀礼を商いとして専らとするのみとなった、日本の伝統的宗派におけるほとんどの寺家らの、あまりにもヒドイ不勉強や甚だしく墮落したあり方を公然と続けているという状況に対する反発もあるのでしょう。
「日本の僧侶などという者等によっては、仏教というものが全然まともに説かれていないし、理解もされていない」、「あまりにもいい加減で、しばしば仏教とはまるで真逆のことを、その説法や著作などの中で恥ずかしげもなく『仏教では』・『大乗では』などと吹聴して回っている」、「もはや彼らに期待できることは全く無い」などといった、大多数の日本で僧を名乗る者らの惨憺たる有り様に対する不満、反動でもあったと理解できます。
世間でressentiment、などとフランス語で気取って言われてしまう心情に基づくものでしょうか。
事実、そのような日本で大乗を標榜する僧尼のほとんどのお寒い有り様、大乗にとってまさしく「獅子身中の虫」たる有り様を平然と続けている状態は、確かに彼ら自身も否定しようもないものです。