
ところで、仏教、なかでも阿毘達磨を学びだしている者や止観の修習(いわゆる仏教の瞑想)に興味を持って取り組みだした者の中には、念と心一境性、そして観の違いがよくわからず、それらを混同し漠然と理解している人が多くあるようです。
実際、私もしばしばこれらの語の意味の相違について質問されることがありますが、念と心一境性とは、先ほど譬えによって示したように異なったものです。すなわち、念には「集中すること」などという意味はなく、また「観察すること」などという意味も当然ありません。それらを表する語はまた別にあるのです。
仏教では、集中していること・集中している心の状態を、心一境性〈cittaikāgratā〉と言います。そして心一境性はまた、三昧・三摩地〈samādhi〉、あるいはまた等持〈samāhita〉とも言われ、それらに共通する漢訳が定です。すなわち、これらは全くの同義語です。
仏教はその初めから心(意識)というもの、知覚や認識の構造や過程というものを観察し、分析してきた宗教です。故にその分析してきた心の働きなどを詳細に定義し、それぞれ厳密に使い分けてきました。
(仏教の中には、本来は全く同義語である心〈citta〉・意〈manas〉・識〈vijñāna, viññāṇa 〉をして、それぞれ異なる精神の階層を示す異なったものであると捉え、六識以外に七識・八識という深層意識があるとする唯識学派が大乗に存します。彼らもまた同様に、その分析を独自に行なってさらに詳らかにしたとする体系を構築しています。)
そのようなことからしても、「念(sati)とは集中であり、また気付きであり、また観察することである」などと言うことは、それらはいずれも全く誤った念の定義ですが、出来ません。
ところで、vipaśyanā(vipassanā)すなわち観の定義というのも知る人は少ないようで、何でもかんでもただ観察することをもって「観」である、としてしまっている傾向が世間にはあるようです。しかしながら、何事かをただ観察するだけであれば、どれほど詳細に、いわゆる客観的・科学的に観察したとしても、それがただちにvipaśyanā(vipassanā)であるなどと言えはしません。
観の修習とは、ただ単純に観ること、客観的に観察することを内容とするものではないのです。
「ありのまま」だとか「あるがまま」、「如実に」という言葉もなかなか曲者で、そのなんとなく良いような語感に騙され、その語の実とは正反対の方向へ人を迷わせてしまうことがままあります。しかし、その語の実の通りにするということは、これがなかなかどうして、実に甚だムズカシイ。
いや、それを実に簡単でシンプルなのだと言い、そのように宣伝する人もあるでしょう。そうであれば誠に結構なのですが、しかし現実にはそれは決して一筋縄で行くような、簡単でシンプルなものでは全くもってない。
よって、無闇矢鱈に「ありのまま」・「あるがまま」という言葉を使う者には注意が必要です。そもそも「ありのまま」・「あるがまま」とは何でしょうか。単純に「ありのまま」・「あるがまま」と言われてたちまちわかる者ならば、最初から修行する必要などありません。しかし、そんな人はいない。要するにそれは、いきなり人に言っても全く意味の無い、空っぽの言葉でしかない。
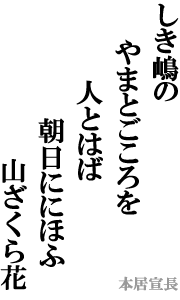
念のため言っておきますが、ここで心情としての「ありのまま」・「あるがまま」いわゆる赤心を良しとする、それこそ価値あるものとする日本古来の、特に近世の本居宣長が見出した「もののあはれ」を否定しているのではありません。それは素直で素朴な、しかし大変優れた文学的・詩情的心情でありましょう。そのような繊細で率直な心情を、自ら懐いて大切にしていることは、仏教を我が人生の核として生きるにも屹度必要なことではあります。けれども、こと仏教の修習にそれを持ち込んではいけない。それとこれとを混同してはならない。
するとたちまちただ情緒や浪漫ばかりの空虚な言葉を並べ立てる「浪漫仏教」・「印象派仏教」に堕することになり、その実例は枚挙に暇ありません。
そこで、では観(vipaśyanā, vipassanā)とは一体何であるか。それは「モノゴトが無常・苦・無我であることを、そのありのままに観ること」、すなわちあらゆる事物の本質を洞察することです。
「ありのままというのは空虚な言葉だ」と言ったそのそばから、自ら「ありのまま」を言い出すとは何事か、極度の痴呆か、と思われるでしょう。が、ここでは「モノが無常・苦・無我であること」という仏教の核心として提示される「ありのまま」の意味を示すため、あえて使いました。
すると「なんだ、もったいぶって偉そうに、そんなことは疾うの昔から知っていることだ」と云う人があるかもしれない。確かに言うだけ、聞くだけならば、全くシンプルで実に簡単ですが、では本当にそれを自ら観たのでしょうか?それを真から知っている、行なっているといえるのでしょうか?それは、仏陀がそう説かれていたというから、何かの本でそのように書かれていたから、それが正しいと何者かからすでに聞いていることであるからといって、「すべてのモノは無常・苦・無我」であると考えたり、思い込んで見ようとすることでは、断じてありません。
「モノが無常・苦・無我であること」という「ありのまま」を現観することは、並大抵なことではありません。「ありのまま」は本当に見難いのです。
吾人はすでに多くの仏教思想に触れているために、むしろ盲になってしまったような場合すらある。なにか教えを聞いたことにより、むしろ盲目的に思い込んだり、狂信的に信じ込んだりするのを廃し、それが真実であると紛れもなく自身で見ることは、そう容易いことではない。
けれども、それがムズカシイのは至極もっともな話で、そんな単純で容易なことであれば、往古から世間には仏陀や菩薩、阿羅漢で満ち溢れていたことでしょう。しかし、世間がそのようなアリガタイことに未だかつてなったことがないのは、言を俟つまでもありません。もう仏教が説かれてから二千五百年ほどの時が経っているにも関わらず。だからこそ「有り難い」のでありましょう。
そもそも、これを説き伝えられてきた仏陀を始めとする往古の大徳たちが、それをはなはだ見難く理解し難いことである、と率直に語られていることで、そんなやすやすと軽々に出来るものではありません。あるはずがない。
しかし、まことに拙い我が身ながら、かたじけなくも仏陀の教えに触れ得、世の無上の宝であるその法を学び知ることが出来ることは幸いです。ただ、その教えを自ら聞き、自ら考え、自ら行なっていくことは容易いことではありません。とは言え、それを自ら行えば行ったなりのその功徳を、その真実性を、その真理たることを、吾人は知ることが出来る。なんと恐れ多い、しかし誠に有り難いことでしょうか。
南無本師釈迦牟尼仏
南無三宝
南無三世十方諸仏諸菩薩
南無過去現在諸賢聖諸大徳
などと、誰か人が突然として言いだしたならば、ほとんどの人は「ギョッ!」とするに違いない。けれども、しかし、私にはそのように真底から思われ、またおのずと吐露されるのです。…まあ、わざわざ声に出して言う必要は、大体無いのですけれども。
真であると聞いていることと、自らが確かに真であると知見することとのその違いを、吾人ははっきりと知らなければならない。

なぜ我々は「つい」ミスをしてしまうのでしょう。
それは多くの場合、いま己が行なっているところの行為、己がすべきと決定した行為を、その行為するなかで「忘れてしまう」ためでありましょう。その時、意識はそのすべき行為から完全に離れ、それに対する意識を失い、その他の事柄に現を抜かしてしまっている。
現を抜かす!
我々は往々にして、今すべきことがあってそれに専注すべき時にすら、余所に現を抜かすがために、多く過ちを犯してしまう。
もっとも、我々の心があちこち周りの環境の刺激に対して飛び回ること、心がここにあらずとなってあれこれ考えることは、人が生きるのに必要なことでもあります。であるからこそ、心はあちこち飛び回る。必要であるがために、その性として。けれども、それと同時に、そのように心があちこちと飛び回ってせわしないがために、むしろ我々は自身の心に振り回され、懊悩するという羽目にもなっています。
なんたる自己撞着でしょうか。これではいけない。
けれども、そのような自己撞着したことを、吾人は日常的に行なっており、故にそれは人の性であると言い得るものです。人はまったく矛盾した存在でありましょう。かと言ってそれをただ「人間だもの」などと認めるだけに留めてしまえば、人に発展進歩、改善することの可能性は閉ざされてしまう。吾々は往々にして、その正反対へと導く諸行為を行いつつ、どうにかしてそのような諸行為から生じる苦悩・懊悩から免れ、幸せになりたいと願います。嗚呼、なんと人とは、いや、私というものはおかしなものでしょう。
仏教における念の意味、特に修習について云われる時の念とは、先ほどの拙い譬えによって示したように、あれで示し得たかどうかは甚だ疑問の余地がありますが、対象を「捉えること」・「保持すること」であるとも換言できます。
さらに例えるならば、人がその両手で何かを確実に捉え保持している時、その他の物がその掌中に入ってくることはなく、掌中にすることも出来ません。そのように、人が何事か心に対象を保持して離すことがなければ、その心にその他のもの、たとえば煩悩などといった汚れが入り込むことがありません。その意味で念とは「守意」、心を護るものです。故に古代の三蔵らが用いた守意なる語は、まこと正鵠を射たものであることがわかるでしょう。実際、諸部派において念の働きが説明される時に、念をして守護者、(五根という門を護る)門衛と例えられることがしばしばあります。
ただし、その念の対象がいわば「愛欲」などいわゆる煩悩そのものであった場合、いずれか認識対象に対する愛欲・執着、すなわち五境ではなく五欲となってしまった場合には、話はまるで変わってしまいますけれども。それは、いわゆる邪念といわれるものです。また人が何かを確かに観察し、知ろうと思ったならば、そのように対象を保持していなければ観察しようがありません。念なくして慧はありえません。念は、智の基礎となるものです。また逆に、智によって念は確かなものともなります。
それは譬えば、以下のようなものです。観察するのには先ず、その対象とするモノをしっかりと把持しなければならない。しかし、掴むといっても最初は、ただがさつに「むんず」と掴むにすぎないかもしれない。けれども、それでは対象のモノが微細になっていくに連れ、確かに観察することができなくなってくる。故に、微細なものを観察する為には、それを繊細に「そっと」、しかし確実につまむようにしなければならない。
観察することに習熟するにつれ、把持の仕方もまた自ずから、必然的に詳細に観察するに相応しいものとなっていく。念と智の関係とはまた、そのようなものです。