パーリ語にはそれ独自の文字があったことはなく、今も存在していません。したがって、その表記は南アジアおよび東南アジア各国それぞれの文字でなされており、標準とされるものはありません。そこでここでは、今もっとも簡便で国際的に通用し、日本人にもただちに読むことが出来るラテン文字(ローマ字)によって表記しています。
パーリ語は8つの母音と33の子音で構成されている言語です。パーリ語について学ぶ者は、これはいわば日本語の「あいうえお」や「あかさたな」のようなものですから、先ず必ず母音と子音の順序と構成は基礎中の基礎として覚える必要があります。
母音についてごく基本的ながら極めて重要な点は、āやīなど長母音を長母音として発音することです。あえてカタカナで表現したならば「アー」または「イー」と発音すべきところを、「ア」または「イ」などと発音してしまえば、全く異なる意味の単語となってしまう場合が多々あるため、長短の別ははっきりしなくてはなりません。a(ア)とā(アー)、i(イ)とī(イー)、u(ウ)とū(ウー)とははっきりと読み分けなければならないのです。
もっとも、これは感覚的な話になりがちなので、仮に日本人が普通に発する「あ」を2拍としてみたならば、パーリ語のaは1から2拍、āは3から4拍ぐらいである、と考えるのが良いでしょう。それほど厳密な話でもないのですが、長音だからといって長くし過ぎても間が抜けておかしいのです。
そこでまたしかし、同じ母音であってもeとo とは二重母音であって基本的には長母音であるため、例えばevaṃは「エヴァン」ではなく「エーヴァン」、Gotamaは「ゴタマ」ではなく「ゴータマ」などと、原則として常に「エー」や「オー」とはっきり長音で発音しなくてはなりません。ただし、そのすぐ直後に(鼻音を除く)子音が連続する場合、例えばmettaは「メーッタ」でなく「メッタ」、geyyaは「ゲーッヤ」ではなく「ゲッヤ」、obhāsetvāは「オーバーセートヴァー」ではなく「オーバーセットヴァー」と促音あるいは短音になります。
サンスクリットの場合、eとoは直後に子音の連続があっても常に長母音で変化しないので、これはパーリ語とサンスクリットではっきり異なっている点の一つです。
次に子音について言及する前に、パーリ語の母音と子音、そしてその音韻に関する表を示します。
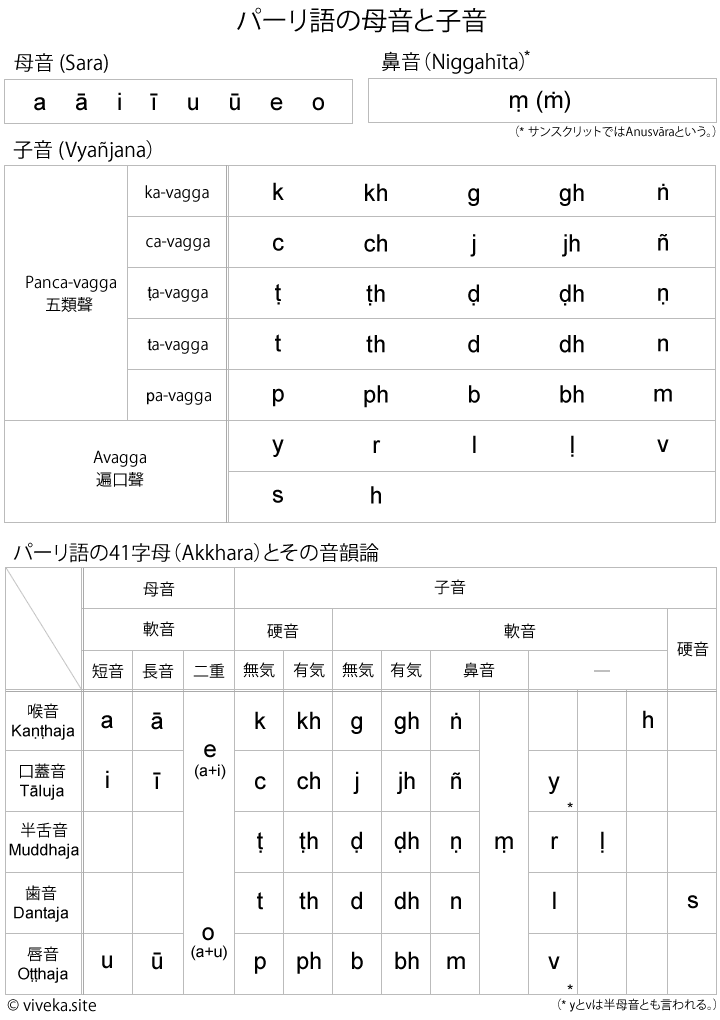
子音について、日本人がその聞き取りと発音でまず最も困難に感じられる点は、無気音と有気音(帯気音・含気)の違いであろうと思われます。有気音とは、その発声に強い気息を伴う音のことです。
例えばBuddhaのdha、DhammaのDha、Saṅghaのgha、あるいはPhala のPhaといった、ラテン文字で表記すると「h」を伴う有気音の発音です。Buddhaの場合、これを日本語でただ「ブッダ」と発音してはパーリ語としては誤りとなり、このdhaを発する時に多く息を吐き出さなければなりません。これを感覚的な表現として「ブッダハ」あるいは「ブッダ(ハ)」と記したならば、あるいはそれがどういうことかわかるでしょうか。
インド語派圏の人の発音を聞いていると、場合によっては「ブッダハ」と言っているように聞こえることもあるかもしれません。しかし、日本人が日本語と同じ様にこの「ハ」をはっきりと「ハ」と発音してはおかしなことになります。あくまで息を多く吐き出すため仮に示した「ハ」であって、「ハ」の音となる未然で止めるといった調子で発音してみれば…、まぁ、最初はどうしてもおかしなことになるでしょう。
無気音と有気音を有する言語を母語とする人からすると、それぞれ明瞭に異なった音です。そのため、有気音であるのに有気音として発音しないのはそもそも正しくなく、あるいは全く異なる意味をもつ別の単語となってしまうことが多々あります。頻繁に使用される単語の例を示せば、atta(自己・我)とattha(意味・利益・目的)です。これらはカタカナ表記したならばいずれも「アッタ」となりますが、後者は有気音であるため実際の発音は別です。
上座部の中でもビルマなど、ビルマ語にも無気音・有気音の別がありますが、その異なることを少々過剰なまでに強調して発音される儀式があります。 Saṅgha(僧伽)における儀式、具足戒の授戒や布薩などにおいてです。それらの儀式の中で行うKammavācā(羯磨)、すなわちその儀式(衆議)の内容(議題)をサンガに宣告してその承認を求める文言を発する際は、パーリ語の有気音が非常に強調されて発声されるのです(それがあまりにも強調されすぎて、少々滑稽にすら感じられる程です)。それは、その儀式が極めて重要であるため、そこでのパーリ語の文言が少しでも誤ったものとならないようにする配慮であるとされます。
そして次に日本人にとってやっかいなのが、上記の子音表の「Ṭa-vagga」にある「ṭa / ṭha / ḍa / ḍha / ṇa」の発音であるでしょう。これもカタカナ表記では「タ・タ・ダ・ダ・ナ」となって、歯音の「タ・タ・ダ・ダ・ナ」と全く区別できなくなってしまいますが、こちらは半舌音であり、文字通り舌を硬口蓋に反らせて発音する子音です。要するに、口腔内で舌を巻いてそれぞれの音を出せば良いのですが、これも現在の日本語に無いものであるため、それがどういうことかすらわからない人もあることでしょう。英語が必修化している日本では、巻き舌で発音するものといえば「r」くらいしか頭になく、それも出来ないという人がいまだかなりあると思います。しかし、インド語における反舌音は、英語の「r」よりも更に強い巻き舌で発せられます。
(インド語派の言語を母語とする人々の英語の発音で、特に「r」が特徴的なものとなっているのはこのことに起因します。また、彼らはおうおうにして「ta」も半舌音「ṭa」として発音するため、同じくその響きが特徴的なものとなっています。)
他にもまたraやḷaが反舌音であるため、同様に発音しなければならないのですが、これはとにかく意識して舌を巻き口蓋に反らせて発音する訓練を重ね、またこの音が他の音と違うことを聞いて慣れる以外ありません。
パーリ語やサンスクリットなどインド語では、たとえばdeva(神)というのを「デーヴァ」と読んだり「デーワ」と読んだり、vinaya(律・調伏)を「ヴィナヤ」と読んだり「ウィナヤ」と読んだりし、あるいはvajira(稲妻・金剛)を「ヴァジラ」あるいは「ワジラ」と読んだりするなど、vの発音について幅があるように思われるでしょう。しかし、これについては日本語に慣れ親しんだ我々の耳(脳)にはどちらにでも聞こえるということがあります。
そもそも、これはサンスクリットにも言えることですが、パーリ語には母音としても子音としても「w」、「wa」の音が存在しません。そのようなことから現在、印度で「va」が「wa」に代替して用いられることは実際にあります。
もっとも、「v」はあくまでその定義上は唇音(Oṭṭhaja / Labial consonant)であるため、最初からvaをwaであると決め込んで発音するのは本来的に正しくありません。たとえば、スリランカではその傾向が顕著ですけれども、それはあくまで転訛、訛っているだけのことです。結果的にwaと聞こえるのと、最初からwaと決め込んで発音するのでは話が全く違います。したがって、例えば上座部を意味するTheravādaを日本語で「テーラワーダ」と表記することは、実はシンハラ語の訛りを反映したものであって正しくありません。
それも例えるならば、タイではdhammaのdhaを濁音として発音できず、また「タンマー」と言っています。そしてまたBuddhaは「ブッダ」でなく」「プッタ」と発音されています。したがって仏法(Buddha-dhamma)を、タイでは「プッタタンマー」というのですが、それを日本語でパーリ語としてそのまま写して云うことは、誠におかしいようなものです。いずれにせよパーリ語の「va」を日本語の「ワ」と同じであると決めつけて日本語で云うことは、パーリ語など印度語の原則からして不正です。
最後に特に注意すべきは「ṃ」についてです。これも子音の一つで、特にNiggahītaと称される鼻音(抑制音)です。サンスクリットでいうところのAnusvāraに同じです。
このニッガヒータについて、「Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi(私は仏陀に帰依します)」いう三帰依文の一節を例としましょう。この発音をカタカナ表記すると「ブッダン サラナン ガッチャーミ」とせざるを得ませんが、しかしその最初の二語「ブッダン」と「サラナン」の最後のンは鼻音「ṃ」であって「n」ではありません。そうかといって「mu」でも決してありません。ではどのように発音すればよいか。上下の唇を閉じた状態で鼻から息を出すつつ「ム」と言おうとすれば、正しく鼻音としてのṃが発音できると思います。要するに「ṃ」を表記上は仕方なく「ン」としても、しかし発音としては「mu」でも「n」でも無いことに気を付ける必要があるのです。
これをさらに例えれば、朝鮮漬けのことを日本で「キムチ」と記述し呼称しますが、それは朝鮮語としては誤っているとされるようなものです。朝鮮語では、真ん中のカタカナ表記の「ム」に該当する音を「mu」とも「n」とも発音するのは誤りであり、鼻音の「m」で発音されなければならない、とされるためです。韓国の友人が「日本人はキムチの発音がおかしい、まちがっている。発音できないのか?」とよく憤っていましたが、それは日本でムが鼻音で発さられていないため、彼らからすると全く違って聞こえるためです。
(ニッガヒータではありませんが、「saraṇaṃ」の「ṇa」も鼻音であって「サラナン」とカタカナ通りに発音するとおかしく、どちらかというと「サラヌン」と聞こえるような発音が正しいものとなります。このあたりのことはカタカナでの表記にそもそも無理があり、先程の音韻表を理解した上でラテン文字などその違いを表し得る文字で読まなければどうにもなりません。)
ところで、パーリ語やサンスクリットなどインド語を完全に表し得る文字は、実は日本において縷縷としてながら今に伝えられています。いわゆる梵字悉曇です。これは現在インドで使用されているデーヴァナーガリーより古い文字であり、仏教の伝来と共に日本にもたらされ学ばれてきたもので、むしろ、これを文字として用いる伝統や習慣は印度でも支那でも全く失われており、ただ日本でのみ今も伝えられています。
ところが、今やこれを自在に読み書き出来る者は僧職者ですら限られるようになって、その伝統は風前の灯火となっています。もっとも、その文字だけであれば、半年から一年も鍛錬すれば誰でも達者になるものですから、これを習得してパーリ語を表することは誠に適当であり、また日本の伝統にも則ったものであって、その伝統を復興し継続するための大きな一助となるでしょう。
さて、パーリ語の発音など、これはサンスクリットでも同じことが言えますが、読解するだけならばそこに気に払う必要はほとんど全くなく、知らなくともなんら支障ありません。例えば仏教学者や文献学者としては、その大体がそれで何らの不自由無くやれています。故にパーリ語の発音など、日常会話で使うでもなし、気にする必要はないしこだわってもまるで意味がない、という態度である人が多いことでしょう。しかし、国を違えてパリッタを唱えたりその他経文を唱える場合、そしてまた多国間の僧が集って宗教的に交流する場合など、国際的な観点からは、その発音についてもその基本的なことを踏まえ区別できておかなければ種々の不都合が生じます。
(後述するように、現在、ビルマやタイ、ラオスなど東南アジア各国ではそれぞれ相当にパーリ語の発音に訛りがあります。しかし、インド語派圏の僧俗からすると、これは日本も同様のことが言えるでしょうが東南アジアにおけるパーリ語の発音は聞くに耐えない、あるいは失笑を誘うものであるようです。それは洋の東西を問わずみられる、都会の人が地方の人の訛りや方言に対する所感と似たようなものであるのでしょう。人によってはそれがひどく未開に感じられ、侮蔑や嫌悪の情すら沸くようです。)
いずれにせよパーリ語の発音について重要なのは、上掲のパーリ語の子音の構成および基本的な音韻論を理解し、その相異を認識した上で自らある程度正確に発せられるようにしておくことは有益です。
パーリ語というインドの古代言語が、上座部(分別説部)という部派において伝えられ、主として南アジアおよび東南アジアにて未だ用いられていますが、それは西洋におけるラテン語のように聖職者や知識人の教養としての言語としてであり、世間の日常会話で使用されることはない、ほとんど死語となった言語です。
もっとも、英語の習得が一般的でなく、今のようにほとんど必須とされなかった一昔前は、異なる国の上座部の比丘同士が互いに訛って相違した発音によるパーリ語で会話をし、意思疎通が図られていました。また、パーリ語の鍛錬などのために僧同士がその会話で用いる、という程度のことは今も稀ながらあるため、完全に死語ではありません。
菲才がビルマで師事しパーリ語の教授を賜った師の説によれば、師の学徳は広く三蔵に通じサンスクリットにも及んだ誠に偉大なものでしたが、西インドの地方部にパーリ語を母語とする人々が暮らす小さな村が未だあるとのことでした。印度には、同じく古代印度語であり聖典語であるサンスクリットの話者がいまだに約二千人(統計上は二万人)ながらもあり、実際これを自在に会話や何か公式の場の挨拶や演説などで流暢に操る知識人が今もあるのは確かです。そのようなことからすると、あるいはパーリ語についても無い話でもなかろう、とは思いますが、その真偽は定かでありません。
パーリ語の発音について、それが古代印度語であり、現在学術的に分類されるところのインド・ヨーロッパ語族インド語派に属するものであることから、同語派に属する言語の話者であるインド人(ヒンディー語)やベンガル人(ベンガル語)、そしてシンハラ人(シンハラ語)などによるその発音が、それぞれの訛りがあるにせよ、より近いものであろうと言えます。実際、シンハラ語を母語とするスリランカの上座部の僧は、自身達の行うパーリ語の発音こそがまさに正しいと自称しており、またバングラディシュにおける上座部の僧らは、ベンガル語こそが最もマガダ語を継承した言語であると考えている者が多いため、彼らもその発音の美しさ・正しさを自ら誇っています。
しかし、東南アジアにあっては、例えばビルマ語はシナ・チベット語族に、タイ語やラオス語はタイ・カダイ語族に属するものであるなど、そもそも語族が異なる言語のそれぞれ特性や習慣に基づいてパーリ語が学ばれ用いられてきた為に、同じ単語であっても全く違った発音で通用している場合が多くあります。時にはそれがパーリ語の単語であると思われないことすらあります。
たとえば、タイ語やラオス語についていえば、言語の特性として清濁音の区別がないためBuddha(仏陀)のBはPになりさらに語尾がoとなって「プットー」、Dhamma (法)のDhはThになり「タンマ」となっています。あるいはビルマ語では、パーリ語でいうところのCa-vagga(ca/cha/ja/jha/ña)が(sa/sha/ja/jha/nya)となっており、またsaがtaとなっている上にビルマ語風に訛っているため、例えばgaccāmi(私は行く)はgassāmi、paccaya(縁)はpassayaとなり、sati(念)はtatiと発音されています。
またそれらの言語には、パーリ語の単語が訛略し、それぞれの語彙に定着して日常用いられているものも多くあります。例えば、パーリ語のĀcariya(先生)は、タイ語やラオス語ではAjahn(またはĀcahn)となりビルマ語ではAshinとなって、もちろん同様の意味で日常使われています(ただし、ビルマではタイとは異なり、特に比丘に対してのみ用いられます)。
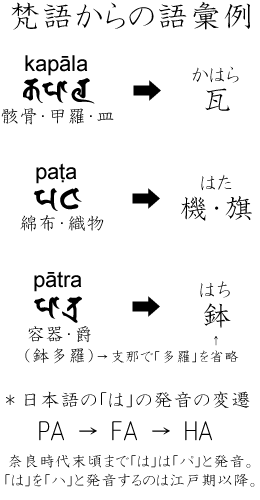
それは日本語においてさえも見られることで、例えばサンスクリットpaṭaka(布・衣服)が漢字の旗を「はた」(その昔は「パタ」と発音した)と、そしてkapāla(皿・蓋・骸骨)が瓦を「かわら」(昔は「かはら」と書いて「カパラ」と発音した)と訓じるようになった元となり、maṇḍalaやācāryaのそれぞれ音写である曼荼羅や阿闍梨という語が、そのまま日本語に定着しているようなものです。
以上のことから、パーリ語で伝えられたパリッタの唱え方、読誦の仕方は、国や地方あるいは派(Nikāya)によっても著しく異なっています。
タイやラオスのそれは、インド語の詠唱としては本来ありえないことではあるのですが、日本仏教における読経と雰囲気が非常に似通ったものとなっており、整然と調子を変えず連続的に唱えられます。ビルマでは、それが個人で唱えられる場合には独特ながらも素朴でまさしく詠唱と言った感のものであるのに、それが複数の僧が斉唱する場面となると個人個人が音程も調子も好き勝手に、断続的に唱えて全くバラバラで聞き苦しい場合が大変多くあります。ところが、それに対してビルマの尼僧達は整然と調子も声も揃えて斉唱し、ある種の美しさすら感じるほどです。
スリランカでは、これはやはりインド語派の言語を母語としているだけあって、北インドの婆羅門に言わせるとシンハラ訛りというのが強くあるらしいですけれども、上に示した音韻論はある程度踏襲された発音により、パリッタや経典が読誦されています。
もっとも、これは持律峻厳の長老に言わせると「まったく悪しき傾向」でありますが、これを独唱する際には長々と尾を引くように唱え、音階も工夫を凝らして過度に音楽的にしようとする者が多く見られます。印度において、サンスクリットなどその発声や調子をはっきりと美しくなすことは古来美徳の一つであり、伝統的五種の学問、Pañcavidyā(五明)の一つ、Śabdavidyā(声明)として挙げられています。しかし、今やスリランカのそれは、その調子や旋律があたかもイスラム教のAdhānに対抗したものであるかのようなものとして耳に迫ります。
上座部の律蔵では、それを聴く者(在家信者など)が、唱える者の是非好悪を判断してその内容にではなく聞き心地を云々しだすことになる為、比丘が経文を歌曲のように唱えることを全く禁じて非法とされています。したがって上座部に(伝統的学問としての声明でなく、仏教音楽としての)声明などあり得ないはずですが、スリランカの多数派であるSiam Nikāya(Siamopāli Nikāya)は戒律についてかなり弛緩しており、持戒への意識は極めて希薄であって、その実践的知識すらほとんど失っている派であることもあってか、近年のスリランカではどうやらそれがある程度一般化してしまったようです。
いずれにせよ、上座部が信仰されてきた国々では、パーリ語にそれぞれ独特の訛りや発音の変化などが見られ、またパリッタや経文の読誦の仕方や調子は異なっています。それらはそれぞれの言語的・文化的・風土的なもの、それぞれの国民性が反映された歴史的なものでもあります。
Ñāṇajoti