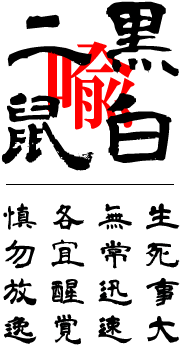
『仏説譬喩経』とは、仏陀が、人およびあらゆる生き物が生死流転、いわゆる輪廻して果てしないこと、そしてそんな人が世間の欲に溺れて生きてていることがどのようなことかを寓話によって説かれている非常に短い経典です。その経題の通り、巧みな譬喩をもってそれが説き示されたもので、世間でも比較的知られた仏教説話「黒白二鼠の喩え」の典拠となっている経です。
この『仏説譬喩経』に説かれた譬喩は、いまからおよそ一世紀前の帝政ロシアにおける偉大な文学者にして、ガンジーにならび称される平和主義者であったレフ・トルストイにも何故か知られており、その著『懺悔(Исповедь)』の中で引用されています。トルストイは、『仏説譬喩経』の所説を「東洋の寓話」としてどこかで聞きあるいは読んで知り、「これは決して単なる作り話ではない。まさしくこれは真実の、論じ合う余地のない、全ての人が知っている真理なのだ」と、賞賛しています。
古い東洋の寓話の中に、草原で怒り狂へる猛獸に襲はれた旅人の事が語られてゐる。猛獸から遁れて、旅人は水の涸れた古井戸の中へ駆け込んだ。が、彼はその井戸の底に、彼を一呑みにしようと思って大きな口をあけてゐる一疋の龍を發見した。そこで此の不幸な旅人は、怒り狂へる猛獸に一命を奪はれたくなかったので、外へ匍ひ出る事も出來ず、さればと言って、龍に食はれたくもなかったので、底へ降りて行く事も出来ず、仕方がなくて、中途の隙間に生えてゐる野生の灌木の枝につかまって、そこに辛うじて身を支へた。が、彼の手は弱って來た。で彼は、井戸の上下に自分を持ってゐる滅亡に、間もなく身を委ねなければならない事を感知した。それでも彼はつかまってゐた、と其處へ更に、黑と白の二疋の鼠がちよろちよろと齧り始めたのである。もう直き灌木はぶつりと切れて崩壞し、彼は龍の口へ落ちてしまふに違ひない。旅人はそれを見た。そして自分の滅亡が避け難いものであるのを知った。が、しかも彼は、其處へぶら下がってゐるその僅かの間に、自分の周囲を見廻して、灌木の葉に蜜のついてゐるのを見出すと、行き成りそれを舌に受けて、ぴちやりぴちやりと嘗めるのである。―私も亦この旅人のやうに、私を牙にかけようと思って待ち構えてゐる死の龍の避け難い事を知らないのだ。私もまた今まで自分を慰めてくれた蜜を嘗めてみる。が、その蜜はもう此の私を喜ばせてくれない。そして白と黑との二疋の鼠は、日夜の別なく、私のつかまってゐる生の小枝をがりがりと齧じる。私はまざまざと龍の姿をまのあたり見てゐる。で蜜ももう私には甘くないのである。私の見るのはただ一つ、―避け難い龍と鼠だけである、―そして私は彼等から目を外らす事が出來ないのだ。しかもこれは決して單なる作り話ではない。これは眞實の、論じ合ふ餘地のない、凡ての人の知ってゐる眞理なのだ。
原久一郎訳・トルストイ『懺悔』岩波文庫, 1935
(ルビは本稿筆者による)
トルストイが自身の生涯とその内面をさらけ出した『懺悔』、それはまさに傑作というべきものですけれども、それをここに引き合いに出すまでもなく、『仏説譬喩経』にて説かれている譬喩は、人というものの滑稽さと愚かさとが説かれた非常に優れた仏教の寓話であり、その真理を開示したものです。

一般に、「生を肯定し、(世法に反しない範囲で)欲望を肯定し、追求すること」、そして「度を過ぎない程度に諸々の欲望を満たしつつこの人生を謳歌すること」は否定されるべきでない見方であるでしょう。そしてそれに反した見方は、現代社会において支配的な価値観からすれば、実はそんなこともないのですけれども、「そんな世界観では何も生み出すことは出来ない」といわば非建設的・非生産的なものとして断じられてしまう。あるいは社会的価値の低いものと見なさることでしょう。むしろそれを否定することは、ただちに非常識で危険を孕む思想である、いや、反社会的思想であるとすら見なされてしまうこともあるかもしれません。
しかし、仏教はこの世を否定的に見ています。生きることを肯定的には捉えていません。
何故ならば、それが苦しみに満ちている、と考えるからです。そしてその苦しみは、無知に基づく自らの業に従って何もわからず延々と生まれ変わり死に変わりする限り、けっして止むことがない、とします。輪廻です。そのような輪廻の渦中にある限り、苦しみが止むことはないというのですから、これを肯定的に見られるわけがありません。仏教の目標はそこから脱すること、脱すると言っても魂が天国などといわれるどこか別の世界に行くということでは無いのですが、それがいわゆる解脱です。
そのように脱すべきとされる「生きること」・「存在すること」が良いもので肯定的に受け入れるべきものであれば、そんな目標など最初から立てられよう筈もありません。生きることは苦しいことである、そのような見方があるからこそ、解脱がその目標として掲げられます。
(例えば、そのような世界観・人生観を譬喩を交えて滔々と説いたものに、「明恵上人の手紙」がある。参照のこと。)
仏教の世界観、その大前提とする生死輪廻について、一般的にそれは、前時代的で非科学的な迷信にすぎない、いわゆる「宗教臭いもの」・「怪しむべきもの」と見られていると言って良いでしょう。
テレビの報道で、「では次のニュースです。今月八日、ついに亡くなった八丁堀は月島長屋の熊五郎氏がこの度、人に再び生まれ変わることになりました。その先は木場の林肥後守の妻が腹。実に氏にとっては大栄転であります」などと流されることは絶対にありません。誰も輪廻を証明することなど出来ず、それを科学的客観的に他者に示すことが出来ないからです。
いや、チベット仏教圏ではダライ・ラマに代表される活仏(トゥルク)の転生者が見つかったときには一大ニュースになることがあるため絶対とも言えないのですが、しかし日本では決してない。…いや、いやいや、今のダライ・ラマ14世が亡くなられると、確実に中国共産党政府が自分たちに都合よく動かしえる赤い傀儡とすべく、「共産党認定転生者 ダライ・ラマ15世」なる噴飯物の存在を発見して担ぎ上げ盛大に宣伝するでしょうから、それは日本でも比較的大きなニュースとして取り上げられることになる。事実、似たような、そして悲惨な事例がすでにあります。
けれどもそうなったとしても、それは科学的事実として輪廻が取り上げられるのではなく、あくまで文化的そして政治的事実として着目されるにすぎません。
そのような現代における見方は、実は何も近現代に西洋からもたらされて始まった自然科学教育の結果として生じたものではなく、江戸時代の人々の間にすでに起こっていました。日本では近世初頭以来、いわば人の合理主義的精神を開花させるに最も力あった朱子学と、そこから復古主義的精神の横溢に依って起こった古学の諸派や国粋主義的国学の隆盛に伴って、仏教は盛んに批判されていたのです。
その批判の主たる対象であったのが、仏教の生死輪廻、そして須弥山を中心とする九山八海 などの世界観であり、あるいは未曾有や神通力など不可思議なことを説いている点でした。それらは他に示して証明できないものであり、したがってまさに今で言う非科学的であると見なされ、そのような説を有する仏教はいわば知的に劣った者のみ信奉する迷信だとすらされるようになっています。
当時、仏教には往古のような国家や人々への思想的・社会的影響力など見る影もなく失われており、もはや旧態依然として迷信に満ちた邪教とする見方が、少なくとも当時の知識人の間では支配的となっています。家康以来の将軍の側にも僧侶が引き立てられていますが、それは寺院僧徒を掌握しまた制するために必要な存在です。
それもその筈、豊臣秀吉の天下統一以前まで、日本国中の諸大寺院は、広大な荘園を有してそれを守る武装組織いわゆる僧兵を抱え、少々の不如意があればたちまち暴力でもってその意を通さんとするなど傍若無人の限りを尽くしていた修羅や畜生と言うべき者達です。仏教者の皆全てがそうではあったわけではありません。しかし、その中心の力を有する者の多くが、あるいは宗教的権威や思想を利用し、あるいは単に富の利害関係から他の大名と結託して一方を責めては火を放ち、人を殺傷して土地や富を奪うなど、乱世の一端を担う恐るべき集団でした。
そんなつい最近まで暴虐を働いていた者らが奉ずる思想を、江戸幕府という新たな治世の中心に据えられる筈もありません。社会秩序の構築のためには、旧来とは異なる思想が必要だった。そこで新たな治世の中核思想として徳川家康が選択したのは、宋代の支那で起こった儒教の新解釈、朱子学でした。といっても、最初から家康が特に朱子学に注目して儒者を召し上げたということではありません。しかし、側仕えた朱子学者の思想は新時代の核とするに相応しいものでした。
皮肉なことに、朱子学は、鎌倉期初頭に天台の学僧でありまた律僧でもあった俊芿という人に日本にもたらされて以降、主として禅の五山僧により一種の教養として学ばれていたものです。事実、徳川家康に重用された、江戸最初期の最も重要な朱子学者である藤原惺窩や林道春(林羅山)などは元禅僧あるいは禅門にて学問を積んだ人です。当然彼等は仏教の教義にも寺家や仏僧の内部事情に通暁しており、故になおさら仏教を批判の対象としています。
一般大衆には仏教を信仰する者も依然として多くありましたが、しかしそれは大抵古来の社会的・文化的慣習や風習に従ってのことであり、その意味では現代と大した異なりはありません。
いや、今とは大分異なって一般大衆の中にも仏教についてよほど造詣が深い人がままあり、その心意気も高い人のあったことが知られます。仏教の説く伝統的世界観、輪廻や業報というものは、むしろそのような民衆のうちに保存されていたと言えるかもしれません。たとえば幕末から明治にかけて活躍した落語中興の祖、三遊亭圓朝が特異とした人情噺など、まさに仏教の業報思想に裏打ちされたもので、それは今も人の心を打つ、非常に優れたものです。
しかし僧の多くは、中世から続く僧徒の堕落・頽廃したあり方を近世に至ってもなお平然と続け、さらにキリスト教への締付け政策の一環として布かれた、庶民の思想や戸籍を管理するための国家制度いわゆる寺請制度に組み込まれたことにより、いよいよ自堕落となっていました。それは、儒教やキリスト教の信奉者からはもとより、世間の人々から仏教の僧尼らが批判される大きな要因となっています。
ただし、仏教諸宗派すべての内にて腐敗と堕落が極まっていたことが逆に機縁となり、極一部の僧らにより仏教復興を目指した戒律復興運動が起こされています。それは当初、超宗派的に行われたものでしたが、時を経るにつれ派閥化・宗派化していき、その内実は失われています。しかし、儒教や国学など外から仏教への激しい批判に対抗するため、また世間にても合理主義的精神が高まったていたことに呼応して、仏教内部でも復古的かつ合理的・批判的な活動や学問が隆盛。非常に優れた律僧や学僧が江戸期には複数排出されています。
その中には、未だ世間にそれほど知られてこそいないものの、抜群の天才というにふさわしいような人も幾人かあります。しかし、そのような潮流は決して大勢を占めることはなく、明治維新を迎えて仏教は急速に衰退していきます。
何も現代となってから仏教(の世界観など)が非科学的であると考えられ、その僧侶らがいわゆる「まなぐさ」で胡散臭いと見なされ始めたのではなく、そのような見方はすでに四世紀以上の昔から続いてきた歴史ある、もはや日本人の伝統的見方とすら言えたものです。明治維新前後に起こった廃仏毀釈は、起こるべくして起こったと言える事態でもありました。
そのように江戸期からすでに批判され、懐疑の目が向け続けられてきたのが、仏教の説く輪廻です。
儒教および道教の立場から仏教の種々の思想や仏僧に対する懐疑の眼が向けられ、盛んに批判の矢が浴びせられたのは、支那の南北朝という昔にすでに見られたことです。そのような批判に答えるべく著されていたのが牟融〈牟子〉によるとされる『理惑論』であり、また僧祐による『弘明集 』などでしたが、まさに日本の近世における仏教への懐疑は、それらで論じられていた議論に多く重なるものです。むしろ日本では、そのようなむしろ健全といえる議論が活発になったのが、ようやく近世となって初めて生じたと言ったほうが良いかもしれません。
しかしながら仏教は、神通力などの不可思議な事柄や須弥山世界であるとかいう世界観は一応脇に寄せることが出来ますが、しかし生命の生死輪廻を大前提としたものです。そして、その故に、そこからの解脱を、もはや再び生まれ変わらず存在せぬようになることを最終目標とします。したがって、いくら時代が変わり、世間での流行する思想が移ろおうとも、仏教において生とは決して無条件に肯定され、賞賛されるものではありません。
今こうして生きていることは過去の業の結果であり、それはまた苦しみに他ならないもので、せっかく人として今この生を受けているならば、ここで苦しみの連鎖を止めずんばあるべからず、とするのが仏教です。そのように理解したときには、この生にも肯定的意味が生じますが、しかしそれはやはり存在することの否定的見方が根底にあってこその話です。