『梵字悉曇字母井釈義』とは、梵字悉曇とはいかなるものかが簡略に示された、空海による小著であり、日本人としては初の悉曇に関する解説書です。異称として『悉曇字母釈』あるいは『梵字悉曇字母釈義』などとも云われます。
本書がいつ著されたものかは定かでありません。しかし、空海は弘仁五年〈814〉閏七月廿八日、『梵字悉曇字母井釈義』他六部十巻の書典を嵯峨天皇からの勅命によって奉献していたことが、空海の遺した漢詩文集『遍照発揮性霊集』(以下、『性霊集』)から知られます。このことから本書は弘仁五年〈806〉以前に著されたものであろう、と一般に考えられています。
が、果たしてそれは本当か。そこでまず実際にその記述を見てみましょう。
獻梵字幷雑文表一首
《中略》
伏奉布勢海口勅欣踊。繕装古今文字讃。右軍蘭亭碑。及梵字悉曇等書都十巻。敢以奉進。
《中略》
梵字悉曇字母幷釋義一巻 古今文字讃三巻
古今篆隷文體一巻 梁武帝草書評一巻
王右軍蘭亭碑一巻 曇一律師碑銘一巻草書
大廣智三蔵影讃一巻弘仁五年閏七月廿八日 沙門空海進
梵字并びに雑文を献じる表、一首
《中略》
伏して布勢の海の口勅〈天皇の勅命〉を奉って欣踊〈踊るばかりに喜ぶこと〉す。古今文字讃〈廿一種の雑書体を示し解説した書〉、右軍〈王羲之〉の蘭亭碑、及び梵字悉曇等の書、都て十巻を繕装して、敢て以て奉進する。
《中略》
梵字悉曇字母幷釈義一巻 古今文字讃三巻
古今篆隷文体一巻 梁武帝草書評一巻
王右軍蘭亭碑一巻 曇一律師碑銘一巻草書
大広智三蔵影讃一巻弘仁五年〈814〉閏七月廿八日 沙門空海進
『遍照発揮性霊集』巻四(『定本 弘法大師全集』, vol.8, pp.62-64)
以上のように、空海は先に「都て十巻」と言っておきながら、末に付した目録では九巻しか挙げていません。この前後撞着した点について、近世前期の真言宗を代表する大学僧、智積院の元春運敞(泊如)は、『性霊集』の詳細な註解を施す中、ここにいう『梵字悉曇字母幷釋釈』とは、本稿にて講じている『梵字悉曇字母幷釋釈』ではなく、『悉曇字母』一巻と『悉曇釈義』一巻のことであって目録にて「各」の字が脱したものであると理解しています。
伏奉布勢海口𢽟欣踊繕装古今文字讃右軍蘭亭碑及梵字悉曇等書都一十巻敢以奉進 問此稱十卷下目錄所載唯有九卷首尾齟齬如何答曰推悉曇字母一卷悉曇釋義一卷但目錄脱一各字矣
伏して布勢の海の口勅を奉って欣踊す。古今文字讃、右軍の蘭亭碑、及び梵字悉曇等の書、都て一十巻を繕装して、敢て以て奉進する。 問う。ここには十卷と称しているが、下の目録に載せるのはただ九卷である。首尾齟齬しているのは何故か? 答えて曰く。推察するに、『悉曇字母』一卷と『悉曇釈義』一卷と、ただ目録では一つの「各」の字が脱したものであろう。
運敞『遍照発揮性霊集便蒙』
このような運敞の見方により、確かにその矛盾は解消されはしますが、真偽は定かでありません。それに、これについては後述しますが、『悉曇字母』と題する書は空海がもたらした事物の目録の中にありません。それはあるいは、空海が唐から請来した『梵字悉曇章』をいうものであったかもしれません。
しかし、運敞がそのように別物であると見たのも無理からぬ話です。というのも、空海は本書の末尾において、その著した目的を以下のように述べているためです。
若有人欲得不妄語常修實語學如来真實之語速證大覺常住之身應當覺此實語字門。如来慇懃説歎此字門。是故聊為童蒙鈔録斯記。好學同志代彼口實。
もし人あって、妄語せずして常に実語を修め、如来の真実の語を学んで、速かに大覚〈大菩提〉の常住の身〈法身〉を証することを得ようと望むならば、応にこの実語の字門〈悉曇四十七字とその字義〉を覚るがよい。如来は慇懃に説かれ、この字門を讚歎されている。そのようなことから聊かながら童蒙〈物の道理に暗い者〉の為にこの記〈『梵字悉曇字母井釈義』〉を鈔録した。
空海『梵字悉曇字母井釈義』(『定本 弘法大師全集』, vol.5, p.113)
このように、空海自らが本書はあくまで「童蒙の為」に著したものと記述していることは、天皇に献じる文書の序文に用いるには不穏当、不適当のように思われます。したがって、天皇に献上したという同題の書は、それが具体的に何を意味したかはともかく、運敞が別物であったと考えたのも無理はないでしょう。
そこで、仮に本書が天皇に献じた書とは異なるものであるとして、改めて本書が著された年を考えたならば、後述する法相宗の学匠、徳一による真言密教への種々の不審点を突いた『真言宗未決文』(以下、『未決文』)との関係から予想することが出来ます。といっても、『未決文』もまた正確にいつ空海に対して提出されたかは判然としていません。学者による弘仁六年〈815〉頃のものとする説に従ったならば、それからあまり時を遡らない頃のことであるでしょう。そしてそれは、空海40歳頃のことです。
空海が没するのは63歳のことですが、確かにその内容からして晩年にかかる著作ではないであろうとは思われます。しかし結局、その撰述年代を知るに確実な根拠となるものが遺されていないため、いずれも推測の域を出ません。ただ以上のことから、本書は弘仁四年から五年の間、すなわち西暦814から815年頃に著されたものと見て差し障りありません。
空海が延暦廿三年〈804〉十二月、31歳にて唐に渡って滞在することわずか二年足らず、長安にて密教を受法し帰朝したのは大同元年〈806〉十月のことです。空海は、唐から持ち帰った膨大な典籍や仏像・法具など一切を目録としてまとめ、帝に上表したものが残っています。後代、『御請来目録』と銘打たれたのがそれです。その中、「梵字真言讃等都四十二部四十四巻」と、特に梵字悉曇で書かれた書籍が四十二部が挙げ連ねられています。
梵字梵字大毘盧舍那胎藏大儀軌二卷
《中略》
梵字悉曇章一卷右四十二部四十四卷釋教者也本乎印度。西域東垂風範天隔。言語異楚夏之韻文字非篆隸之體。是故待彼翻譯乃酌清風。然猶眞言幽邃字字義深。随音改義賒切易謬。粗得髣髴不得清切。不是梵字長短難別。存源之意其在茲乎。
梵字梵字大毘盧舍那胎藏大儀軌二卷
《中略》
梵字悉曇章一卷右四十二部四十四卷釈教〈仏教〉は印度を本としたものである。西域〈印度〉と東垂〈極東〉とでは、風範〈風儀〉を非常に隔てている。(西域の)言語は楚夏〈支那〉の韻とも異なり、文字は篆・隸の書体ではない。したがって、その翻訳を待ってこそ(仏教という)清風を酌むことが出来るのだ。しかしながら、なお真言とは幽邃なものであって一字一字の(象徴する)意義は深遠である。音にしたがって義を改める〈梵語を音写した漢字表記〉のでは賒切〈音の長短や促音等〉に謬りが生じ易い。およそ髣髴〈ぼんやりとして不明瞭なこと〉を得ることは出来ても、その清切〈明瞭・正確なこと。ここでは正確な音〉を得ることは出来ない。この梵字でなければ(厳密にすべき音の)長短を別かち難い。(仏典の原語たる梵字という)源が(翻訳してもなお)存るべき意味はまさに茲に在る。
空海『御請来目録』(『定本 弘法大師全集』, vol.1, pp.22-26)
空海が日本にもたらしたと報告している『梵字悉曇章』は、その原本は失われていますが、今に伝えられています。ここで空海が、真言陀羅尼などを音写して漢字表記したものを否定的に述べていることは重要です。実は空海は本書において「漢訳」という営為に存する問題を指摘してもいるのですが、この一節には特に真言陀羅尼の発音について正確にすべきとする空海の意識が明瞭に表れています。
漢語を流暢に話し、また流麗な漢文を筆することが出来た空海は、唐は長安にあって漢語ばかりでなく梵語など他様々な言語に触れ、「言語」というものをある程度客観視することが出来、その相違を意識していたのです。そこで空海が(過剰に)神聖視した悉曇について、その発音の正しきを明らかにして伝えるべきと考えるのは自ずから宜なることです。
そのような問題意識のもと、空海により「童蒙の為に」著されたのが『梵字悉曇字母井釈義』です。
なお、空海は以上の他に梵典を持ち帰っています。
梵夾三口右般若三蔵告曰。吾生縁罽賓国也。少年入道経歴五天。常誓傳燈来遊此間。今欲乗桴東海無縁志願不遂。我所譯新華嚴六波羅蜜経及斯梵夾将去供養。伏願結縁彼國抜濟元元。恐繁不一二。
梵夾〈梵字で書かれた経典〉三口右、般若三蔵〈梵字で書かれた経典〉が「私の生まれたのは罽賓国〈Kapiśa. 現在のアフガニスタン、カブール川中流域〉である。少年のとき入道して以来、五天竺〈印度全国〉を経巡ってきた。常に伝灯〈仏教を他に伝えること〉を誓い、ついにここ〈唐代の支那〉に来遊したのである。今、(さらに日本に行くため)桴に乗ろうと思うが東海〈日本〉には縁が無く、志願を遂げることは出来ない。そこで私が訳した『新華厳経』と『六波羅蜜経』〈『大乗理趣六波羅蜜経』〉、及びその梵夾を将って去り供養せよ。伏して願わくば、彼の国〈日本〉に結縁して、元元を伐済したい。繁を恐れて一二せず」と告げられたものである。
空海『御請来目録』(『定本 弘法大師全集』, vol.1, p.38)
これは特に般若三蔵から託された梵夾であったため、漢訳経典とは別にし挙げたようです。しかしながら、ただ「梵夾三口」とのみして、その内容が何かが示されていません。それはあるいは、併記される新訳の『華厳経』か『大乗理趣六波羅蜜経』かの梵典であったかもしれませんが現存しておらず、もはや確かめようもないものとなっています。
日本に悉曇で書かれた書、梵夾をもたらしたのは空海が初めてではありません。今、史書にて確認できる範囲では、その最初の人は小野妹子とされます。そしてそれは推古十五年〈607〉のことであって、その物は現在「法隆寺貝葉」〈東京国立博物館蔵〉と称され伝えられる、切り揃えた貝多羅葉に悉曇にて経文や陀羅尼の書かれた断片でした。
一尊勝多羅尼般若心經。多羅葉梵書。右者太子御前生。於衡州南嶽山。惠思禪師念禪法師申。六生間御持物也。太子三十七歳時。小野臣妹子自大隋國將來品也。
一.尊勝多羅尼・般若心経の多羅葉梵書。右は太子が御前生、衡州南嶽山において恵思禅師〈慧思〉・念禅法師と申されるときに、六生の間の御持物であるということである。太子が三十七歳の時、小野臣妹子が大隋国より将来した品である。
覚賢『斑鳩古事便覧』(新編『大日本仏教全書』, vol.85, p.152)
以上のように、「法隆寺貝葉」は南岳慧思〈北斉の僧.天台宗開祖で智顗の師〉が生生世世に渡って護持していたもので、(その転生者であると日本ばかりでなく支那においても信じられた)聖徳太子〈厩戸皇子〉が小野妹子に指示して隋から将来した品である、とされています。
ただし、『斑鳩古事便覧』が編纂されたのは天保 七年〈1836〉のこと。遥か12世紀も後代のことであるため、その伝承が事実であるかには検証の余地が大いにあります。しかし、物として貝多羅葉の梵夾が法隆寺に伝わっていたことは事実で、その貝葉という素材の性質と悉曇の字体からそれが相当に古く、また異国の物であることは確かです。
現在、日本には、法隆寺以外に東寺・清凉寺・海龍王寺・高貴寺・玉泉寺・四天王寺・知恩寺に貝葉が伝えられており、中でも高貴寺・玉泉寺・四天王寺・知恩寺がより古い七から八世紀の写本であろうと考えられています。そこで『法隆寺貝葉』は、世界中にも数少ない現存する貝多羅葉の断片として世界最古に属するもの、あるいは最古に次ぐものと目されています。
もっとも、法隆寺貝葉の『般若心経』梵文における悉曇の綴りには、写誤の類では決してない、単純ながらも重大な誤りがいくつか見られることから、それが印度人により書かれたものであるとは見難く、あるいは胡国か支那にて書かれた可能性があります。
また他に、空海より半世紀前の天平の昔、悉曇はすでに天平年間、菩提僊那〈Bodhisena〉や道璿と共に渡来した林邑僧〈崑崙国.現在のベトナム〉、仏哲により、『悉曇章』が著されたか、もたらされたかしています。しかしながら、仏哲の『悉曇章』は、江戸期までは伝えられていたらしいものの、誠に惜しいことに明治期前後に散失しています。
(ただし、注意しなければならないのは『悉曇章』と題された書は他に過去、非常に数多く存在していたことで、江戸期にまで伝えられたという書が本当に仏哲にかかるものであったか自体、必ずしも定かではありません。)
ところで、菩提僊那も仏哲も同じく、伝えによれば密教を行じる人でもあったようです〈『東大寺要録』巻三「大安寺菩提伝来記」〉。そもそも、菩提僊那は印度僧であったことからも、仏哲や『悉曇章』という書からだけでなくその両者により、悉曇に関する知識は当時の僧や知識人に披露され、ある程度は浸透していたと考えられます。例えば、菩提僊那は日本渡来後、師主(依止師)として公家の弟子をとって育成し、出家させていますが、その際、漢訳の諸経典ばかりでなく、梵本の陀羅尼のいくつかを教授し読ませていたことが知られます。
秦大蔵連喜達年廿七 右京四條四坊戸主 從六位下秦大蔵連弥智麃子
梵本陁羅𡰱佛頂陁羅𡰱 千手陁羅𡰱讀経
般若陁羅𡰱 如意陁羅𡰱㝡勝王經一部 梵網經一部 䟽二巻
理趣經一巻暗誦 瑜伽菩薩地 中論一部
肇論一巻已上破文 文選上怢音 脩行十二年天平十四年〈742〉十一月十五日大安寺僧菩提
「優婆塞貢進文」(『大日本古文書』編年文書, vol.2, pp.314-315)
ここに挙げられた陀羅尼および経論により、むしろ『華厳経』に通じていたという菩提僊那の学系やその見解を垣間見ることが出来、またある程度漢語を理解していたことも伺えます。それはともかく、ここで「梵本陀羅尼」が四部挙げられていることに注目しなければなりません。これは、菩提僊那が、梵語としてその文法にまで踏み込んでいたかまでは不明であるものの、少なくとも梵字悉曇の読み書きはその弟子に伝えていたことの明瞭な証となるものです。
実に日本における悉曇学(梵学)の黎明は、共に大安寺に居した菩提僊那と仏哲にあります。もっとも、それは現代的な意味における「学」などというのではなく、ただ梵字という異国の文字の読み書きを教える程度のことであったのでしょう。
悉曇の知識が授けられていたのは、菩提僊那の「秦大蔵連弥智鹿子」なる弟子一人に限られたことではありません。ほぼ同時期の人、かの弓削の道鏡もまた、ある程度まで梵文に通じていたと云われます。
○丁巳。下野国言。造薬師寺別当道鏡死。道鏡。俗姓弓削連。河内人也。略渉梵文。
○(宝亀三年〈772〉四月)丁巳〈七日〉。下野国〈現在の栃木県〉が「造薬師寺の別当〈長官〉、道鏡が死す」と報告。道鏡は、俗姓弓削連、河内の人である。おおよそ梵文に通じており、禅行を以て名声があった。それに由って内道場〈宮中の仏殿〉に入り、列して禅師〈後の内供奉〉となる。
『続日本紀』(新訂増補『國史大系』, p.402)
このように、入唐経験が無い人であったにも関わらず道鏡が梵文の知識を有していたということは、南都においてその講義、学問がある程度広く行われていたことを示唆するものです。この一節における「略渉梵文(略ら梵文に渉る)」というのは、まさか語学としての梵語(サンスクリット)にある程度通じていたというのでなく、梵字の読み書きができる程度のことではあったでしょう。そして、ここで「禅行」とは単に修禅を深くしていたということでなく、なんらか密教の呪法であったようです。そして、その影にはやはり菩提僊那や仏哲の存在があったと考えられます。
また、それが必ずしも菩提僊那や仏哲の直接的影響であったかどうかは明確でないものの、当時すでに梵語の語彙が日本語のそれに影響を与えていたことが知られます。今も普通に用いられる「 瓦」や「機」・「旗」・「鉢」など漢字の訓の中に、その梵語からの痕跡が明瞭に見られるのです。
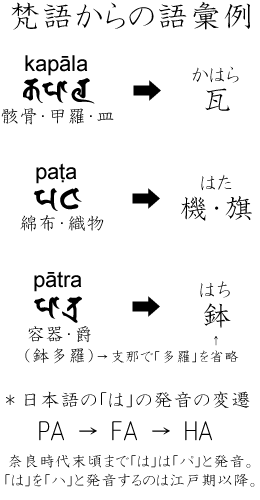
例えば、瓦という漢字は今「かわら」と読み、書きますが、戦前までは「かはら」と訓じていました。なぜ瓦を「かはら」と訓じていたのか?それは実はサンスクリットのkapāla(迦波羅)に由来するためです。kapālaとは、皿など器や蓋、骸骨や甲羅などを意味する語ですが、転じて屋根に載せて敷き並べる焼き物、すなわち瓦を指すようにもなっています。おそらく、菩提僊那や仏哲など渡来僧が、それを「カパーラ」と言っていたのに倣い、瓦を「かはら」と称してその訓としたようです。
そこで、ではなぜ「かぱら」あるいは「かわら」ではなく、「かはら」と訓じたのか?まず、当時は「ぱぴぷぺぽ」という表記は存在していませんが、奈良時代の日本語は、「は」と書いて「パ(pa)」と発音していたためです。そもそも当時、日本語に「ハ(ha)」の音列が存在していませんでした。しかしその後、「は」の発音が平安時代頃から「ファ(fa)」となり、やがて近世から現代と同じ「ハ(ha)」となっています。
すなわち、例えば般若とは[S]prajñāあるいは[P]paññāの音写ですが、その昔は日本でもこれを原音に近く「ぱんにゃ」と読んでいたのです。なお、「かはら」などと古来訓じていた歴史的仮名遣いを「かわら」とする現代仮名遣いに改めたのは、第二次大戦後のことであって比較的最近のことです。
先に指摘しておくべきことでしたが、そもそも平仮名・片仮名が漢字を元に創出されたのは九世紀前半から後半のこと。それまで日本語を表するには、いわゆる万葉仮名(真仮名)が使われており、例えば「は(ハ)」であれは「波」・「破」・「八」等の漢字が用いられていました。
奈良時代から平安時代前期の昔、万葉仮名にて「は」と書いて「パ」と発音していた、あるいは当時そもそも日本語に「ハ」という発音・音列が無く、故に梵字にしろ漢語にしろ外来の「ハ」の発音を「か(カ)」に置換していたということ。さらに付け加えるならば、「さ」(左・佐・作・沙)の発音も今我々が用いる「サ(sa)」と異なり、「チャ(ca)」あるいは「ツァ(tsa)」と発音していました。これらは単なる日本語豆知識などでなく、梵字を学ぶ者が必ず知らなければならず、また常に意識し、勘案すべき「極めて重大な事実」です。
平安初期に盛んとなる悉曇学はただその語彙だけでなく、やがて日本語の体系化、国語学にも多大な影響を及ぼしています。今、我々が用いる「あいうえお」であるとか「あかさたな」の五十音図は、悉曇学の知識に基づいてこそあり得たものです。それは梵語における母音と子音の配列、いわゆる摩多体文の構造に倣って構成されたものでした。悉曇学は、日本の国語学に非常に深く関わりを持ち、大きな影響を及ぼしています。
以上に加え、空海は支那で書かれた梵字悉曇についての註釈書二部も日本にもたらしています。
論䟽章等《中略》
悉曇字記一卷
悉曇釋一巻
《中略》右三十二部一百七十卷含理者也三爻。能敷者也十翼。若闕彖繋龜文何益。況乃一乗理奧義与文乖。不假論疏微言無功。雖有勞載車冀裨乎聖典。
論疏章等《中略》
『悉曇字記』一卷
『悉曇釈』一巻
《中略》右三十二部一百七十卷理を含むものは三爻〈卦. 上中下の三種の記号の組み合わせ〉であり、よく敷く〈ここでは解釈の意〉ものは十翼〈『易経』の註釈〉である。もし彖繋〈「彖伝」と「繋伝」.十翼の一〉を闕いたならば亀文〈亀卜〉に何の益があろうか。ましてや乃ち一乗の理は奧くして、(時として)その義は文〈文字通りの意味〉に乖いている。(そこで)論疏〈註釈書〉を借りなければ微言〈玄奥な言葉〉に功は無い。載車に労することあり〈その分量が多く読解するのに骨が折れること〉といえども、冀は聖典〈経律〉(を理解する)の裨けとなることを。
空海『御請来目録』(『定本 弘法大師全集』, vol.1, pp.27-30)
いずれも空海が初めて日本にもたらした書ですが、惜しいことに『悉曇釈』は現存していません。もう一つの『悉曇字記』は、八世紀は唐代の学僧智廣〈智広〉によるもので、今に伝えられています。智廣が五台山にて南天竺の般若菩提 〈Prajñabodhi?〉なる僧から直接梵字の字形と発音および意義とを学び、その十八章に分かって示されたものを漢語で註釈して著したものです。
もっとも、智廣であれ般若菩提であれ、どのような人であったかその詳細がまったく伝わっていません。般若菩提は、あるいは空海が学んだ後述する般若三蔵と同一人物かとも推測する者があります。しかし、それは根拠のまったく無いものであって、詮無い伝説に過ません。
なお、近現代には空海がここに挙げる『悉曇字記』は智廣の『悉曇字記』とは違うものだなどと見なす学者がありました。しかし、それは穿った見方であり、本書において『悉曇字記』の一節を借りた表現があちこちで見られるため、まず確実にそれは智廣の『悉曇字記』であったと見てよい。
真言宗では空海入滅の前年、承和二年〈834〉正月廿二日に真言宗三人の年分度者が勅許され〈太政官符治部省「応度真言宗年分僧三人事」〉、金剛頂瑜伽経業と大毗盧遮那成仏経業に並び、声明業という特に梵字を専門とする年分僧が設けられています。
年分度者(年分僧)とは、朝廷が毎年各宗に割り当てた出家者の定員です。当時、仏教を隠れ蓑にして脱税や脱法行為を行うものが多くあったため、なんらか国家の許しがなければ誰でも自由気ままに出家することは出来ませんでした。そして、その年分僧は、正月の御斎会最終日に宮中(清涼殿)にて新たに出家させていました。もっとも、声明業の年分僧が学ぶべきものと課さられた典籍は、空海がもたらした上記の『梵字悉曇章』および『大孔雀明王経』、そして空海の自著『声字実相義』の三で、そこに『悉曇字記』は含まれていません。
(遥か後代の中世室町期、東寺の杲宝は空海が智廣から直接、梵字悉曇を習い『悉曇字記』を授けられたなどという説を述べていますが、それは臆説の甚だしきものです〈『悉曇字記創学鈔』〉。)
空海が『悉曇字記』を等閑視したということは決して無かったのでしょうが、しかし少なくともそれを声明業の年分僧の課程に採用しておらず、また『真言宗所学経律論目録』(『三学録 』)の中にも記載していません。空海はあくまで『梵字悉曇章』を根本典籍として見ていたのです。とはいえ、『梵字悉曇章』はただ梵字の羅列に過ぎず、これを学ぶのには必ず註釈書が必要です。そしてその註釈書の役割を本書では果たしえません。
また、空海が著した『大悉曇章』もまた梵字の羅列に過ぎず、初学者が「梵字悉曇を学ぶ」に到底有益となるものでは全くありません。なにより、そこには梵字としてあり得ない字、梵語として存在しない音が多く記されており、梵字であれ梵語であれそこから正しく学び得るものとなっていません。『大悉曇章』は、むしろ空海が梵語を理解していなかった証拠とすらいてしまう内容となっているのです。
したがって、『悉曇字記』は必ず年分度者をはじめ、その他の真言僧らに確実に読まれていたことと思われます。
菲才が思うに、空海が『悉曇字記』をその著で言及しておらず、また年分度者の公式の学習課題としていないのには明確な理由があります。それはまず、次項にて述べる空海の「梵字悉曇」というものについての(自然道理の所作であるとする)認識に反すること、すなわち「梵天の所製」であると、『悉曇字記』はその冒頭において『西域記』に基づいて述べているためです。そしてまた、『悉曇字記』には梵字悉曇の一字一字が仏教の説く諸々の真理を表したものであるとする字義について一切問いていないためです。これは顕教の諸経典がすでに様々に説くところでもあったのですが、真言密教においてその根幹に関わる非常に重要な部分です。したがって、空海は少なくともその当初、『悉曇字記』の価値は認めつつも、真言宗として公的に用いることはしたくなく、所依のものとすることは出来なかったのでしょう。
しかし、そんな『悉曇字記』を重視した最初の人は、入唐八家の最後の人であり、天台および法相を兼学した真言僧、宗叡です。宗叡は『悉曇字記』に詳細な註釈を付した『悉曇私記』〈『悉曇字記林記』・『悉曇林記』〉を著しています。これ以降、『悉曇字記』は、日本で悉曇を修学するための最も重要な根本典籍として扱われ、明治期に入る頃までは盛んに学ばれています。
しかし、なんといっても体系的・総合的に梵字悉曇を把握しようと勤め、いわゆる「学」というに相応しい位置にまで高めたのは天台宗の安然です。安然は天台密教を大成した人ですが、最澄や円仁・円珍 、または宗叡などのように入唐することは果たせなかったものの、むしろその故にこそ、師の円仁からの説(安然の密教の師は遍昭、悉曇は主として湛契および長意に受けた)ばかりでなく、当時の日本に存在したあらゆる梵字悉曇関係の書を 蒐集し、字形およびその発音などその真を明らかにしようと『悉曇蔵』なる労作を著しています。その中には現存しない資料の引用が多く含まれ、その点からも今なお非常に重要な典籍であり、梵字を学ぶうえで必読の書の一つです。
安然もまた宗叡に同じく『悉曇字記』を重視し、もっぱらその説に倣って梵字を十八章立てで説明しており、以降の真言・天台の学僧らもこれを踏襲して今に至ります。
ただし、安然は、入唐を果たすことが出来なかったために印度僧どころか支那僧からの教授ももちろん受けていません。また、『悉曇蔵』は当時の説の集成ではありますが、それを独自に斟酌してあれこれ論じる中には、むしろ臆説というべきものが多く含まれています。そのため、近世江戸時代後期の慈雲 は『悉曇蔵』を厳しく批判し、決してその説に依るべきでないとしています。そうは云われるものの、やはり梵字悉曇を学ぶ者として、その説を信受するかどうかはおくとしても、『悉曇蔵』を読まずにあることはありえない、と云うべき書であるのに変わりありません。