一般に、空海が梵字悉曇を修学したのは、唐は長安の醴泉寺にあった罽賓(Kapiśa)の般若(Prajñā)および北印度の牟尼室利(Muniśri)という二人の僧からのことであったと云われます。
(罽賓という地名は、支那で時代によりその指し示す土地が変化しており、中唐頃まではカシミール、それ以降はさらに西北のカピシャすなわち現在のアフガニスタンのカーブル川流域を意味します。実際、般若の伝記〈『続開元録』巻上〉では「北天竺境迦畢試國人也言罽賓者訛略」とされています。)
しかしながら、実は空海自身は、般若および牟尼室利から「梵字悉曇を学んだ」などとは述べていません。
貧道大唐貞元廿一年於長安醴泉寺聞般若三蔵及牟尼室利三蔵南天婆羅門等説是龍智阿闍梨今見在南天竺國傳授秘密法等。云云
貧道〈沙門.ここでは空海自身の意〉、大唐貞元廿一年〈805〉、長安醴泉寺に於いて、般若三蔵〈Prajñā〉および牟尼室利三蔵〈Muniśri〉から南天の婆羅門等の説を聞いたところ、この龍智阿闍梨〈Nāgabodhi. 真言第四祖〉は今なお南天竺国に在って秘密の法等を伝授されている、という。
空海『秘密漫荼羅教付法伝』巻一(『定本 弘法大師全集』, vol.1, p.74)
空海はあくまで「南天の婆羅門等の説を聞いた」というのみで、必ずしも梵字悉曇を学んだなどと言っていないのです。しかし、特に般若の元で特別な何かを学んでいたであろうことは、空海が唐を後にする際に筆した書に自らそうしていることから確かです。
與本國使請共歸啓一首
留住學問僧空海啓。《中略》
著草履歴城中。幸遇中天竺國般若三蔵。及内供奉恵果大阿闍梨。膝歩接足仰彼甘露。
本国の使と共に帰らんと請う啓、一首
留住学問の僧、空海啓す。《中略》
草履を著いて城中〈長安〉を歴るに、幸に中天竺国の般若三蔵、及び内供奉恵果大阿闍梨に遇いたてまつって、膝歩接足して彼の甘露〈教え〉を仰ぐ。
空海『遍照発揮性霊集』巻五(『定本 弘法大師全集』, vol.8, p.85)
以上のように、空海は特に般若と恵果との名を挙げていることから、その二人を深く敬し、受けた教えを重要視していたことが知られます。実際、前項においても示したように、空海は密教を受法した恵果からだ諸々の付嘱物を授けられていただけでなく、般若からも新訳の経典と梵夾を託されており、それがわずかの期間であったとしても近しい間柄となっていたであろうことも伺えます。
しかし、恵果からは密教を相承したことは自明としても、般若からいかなる教えを受けたかは空海自ら明らかとしてはいません。とはいえ、般若三蔵の伝記およびその訳経から、彼もまた密教僧であってしかも恵果の弟子であったことが知られています。なにより、般若が罽賓出身でなおかつ五天竺に学んだ人であって、さらに唐に来たって三蔵を勤めている人であることから、サンスクリットに当然通じており、それをまた漢語にすることもある程度は自在に出来たことは間違いありません。
そこで、他にそれを為しえる者と空海が接触した痕跡が無いことから、般若(および牟尼室利)が空海に対し梵字悉曇を教えた、ということに一般にされているのでしょう。いずれにせよ、空海自らが般若から悉曇を学んだ、と必ずしも言っていないことには一応注意が必要です。
そこで空海が般若や牟尼室利など印度僧から(密教および)悉曇を教授されたとするならば、空海は漢語も流暢に話すことが出来たことからも、その発音を正確に把握し、発声することも出来ていたと考えてしかるべきです。このこともまた、現今の日本で伝統的とされる悉曇の読み、発音を考える時、非常に重要な点です。
また、空海は梵語の六合釈〈名詞の複合語の解釈法〉や七転・八転〈名詞・代名詞・形容詞・数詞などの八種の格変化〉といった文法についてその著作の中に言及があることから、それはあるいはただ支那撰述の華厳宗や法相宗の典籍での用例に倣っだけのことであったように思われますが、幾ばくかは梵語の文法についても習い知っていたようです。
そこで現代、「空海が梵語を(しかも数ヶ月で)習得していた」とする学者や僧職者があります。そしてその根拠として『恵果阿闍梨行状』の一節がよく挙げられます。
今有日本沙門空海来求聖教以兩部秘奥壇儀印契。漢梵無差悉受於心猶如瀉瓶。
今、日本沙門空海あって来りて聖教を求めるに、両部〈金剛界法と胎蔵法〉の秘奥壇儀印契〈灌頂〉を以てする。漢・梵、差無く悉く心に受けること、猶し瀉瓶〈水を瓶から他の瓶にすべて移し替えること〉の如し。
空海『秘密漫荼羅教付法伝』巻二(『定本 弘法大師全集』, vol.1, p.74)
この中、「漢梵無差(漢・梵、差無く)」という語のみを以て、空海が梵語を全く理解し習得していたと、一部の、いや多くの学者や僧職者らが主張してきました。これは恵果に出逢う以前、般若と牟尼室利の両三蔵から悉曇を習学していたとする見方を前提としたものです。しかし、これは伝記における修辞であって、これのみで「梵語を習得していた」とする根拠とするのには無理に過ぎます。むしろ「習得してはいなかった」と考えられる根拠のほうが多く遺されています。
いや、もちろん、空海は梵字悉曇を読むことは出来、書くことも出来たものと見て間違いありません。そうでなければ密教の受法など出来ないためです。何より、空海自身が自ら(恵果から)梵字・梵讃を学んだと書いていることから、梵字を読んでどのように書くべきものか、その発音が如何なるものかは必ず知っていたでしょう。
廿四年仲春十一日大使等旋軔本朝。唯空海孑然准勑留住西明寺永忠和尚故院。於是歴城中訪名徳偶然奉遇青龍寺東塔院和尚法諱恵果阿闍梨。其大徳則大興善寺大廣智三蔵之付法弟子也。徳惟時尊道則帝師。三朝尊之受灌頂四衆仰之學密蔵。空海与西明寺志明談勝法師等五六人同往見和尚。和尚乍見含笑喜歡告曰。我先知汝来相待久矣。今日相見大好大好。報命欲竭無人付法。必須速辨香花入灌頂壇。即歸本院營辨供具六月上旬入學法灌頂壇。是日臨大悲胎蔵大㬅陁羅依法拋花偶然着中台毗廬遮那如来身上。阿闍梨讃曰。不可思議不可思議。再三讃歎。即沐五部灌頂受三密加持。従此以後受胎蔵之梵字儀軌學諸尊之瑜伽觀智。七月上旬更臨金剛界大㬅荼羅重受五部灌頂。亦拋得毗廬遮那。和尚驚歎如前。八月上旬亦受傳法阿闍梨位之灌頂。是日設五百僧齋普供四衆。青龍大興善寺等供奉大徳等並臨齋筵悉皆随喜。金剛頂瑜伽五部真言密契相續而受。梵字梵讃間以學之。
(延暦)廿四年〈805〉の仲春〈二月〉十一日、大使〈遣唐大使〉等は本朝〈日本〉に帰ったが、ただ空海のみ孑然〈孤独であること〉として(皇帝の)勅に准じて西明寺の永忠和尚〈空海や最澄より二、三十年先に留学僧として入唐し、最澄と共に帰朝した日本僧〉の故院に留住した。そこで(長安の)城中を歴って名徳を訪れたが、偶然として青龍寺の東塔院の和尚、法諱〈僧名・法名〉恵果阿闍梨に遇い奉った。その大徳はすなわち、大興善寺の大廣智三蔵〈不空金剛〉の付法の弟子であった。その徳は当時に尊ばれて(世人を)導き、すなわち帝師であった。三朝〈三代の皇帝〉はこれを尊んで(恵果から親しく)灌頂を受け、四衆〈比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷。ここでは僧俗の意〉もこれを仰いで密蔵〈密教〉を学んでいた。空海は、西明寺の志明や談勝法師など五、六人と共に同じく往って和尚に(初めて)見えたのである。すると和尚は(私空海を)乍ち見て笑みを含み、喜歓して告げて言った。
「私は以前から汝が来ることを知っており、相い待つこと久しい。今日、相い見えた。大だ好し、大だ好し。(我が)報命〈寿命〉はもはや竭きようとしているのに、付法に(適当な)人が無かった。(けれども、こうしてそれに相応しい人に会うことができた。)必ず須く速かに香花〈密教を伝法するに必要な資具〉を準備し、灌頂壇に入るべし」
そこで(私空海は)本院〈西明寺〉に帰って(受法に必要な金品など)供具を営弁〈用立てること〉した。六月上旬、学法灌頂壇〈受明灌頂壇〉に入った。この日、大悲胎蔵大㬅陁羅に臨んで、法に依って花を拋げたところ、偶然として中台の毗盧遮那如来の身の上に着いた。阿闍梨はこれを讃え、
「不可思議である!不可思議である!」
と再三讃歎された。そこで五部の灌頂に沐して三密の加持を受けたのである。それより以後、胎蔵の梵字の儀軌を受け、諸尊の瑜伽観智(の儀軌)を学んだ。七月上旬、更に金剛界の大㬅荼羅に臨み、重ねて五部の灌頂を受けた。また(曼荼羅の前で花を)拋げたところ、毗盧遮那を得た。和尚が驚歎すること前と同様であった。八月上旬、また伝法阿闍梨位の灌頂〈伝法灌頂、具支灌頂〉を受けた。この日は五百僧の斎食を設けて普く四衆を供養した。青龍大興善寺等の供奉〈朝廷に仕える僧〉や大徳等、並びにその斎筵に臨んで悉く皆な随喜した。(その後、)金剛頂瑜伽五部の真言密契を相い続けて受けたが、梵字・梵讃はその合間に学んだ。
空海『御請来目録』(『定本 弘法大師全集』, vol.1, pp.35-36)
実際、その遺品として空海直筆の梵字が記されたものが現存しています(『三十帖冊子』第廿七帖)。そして真言の読みやその発音も、前述したように、恵果ばかりでなく印度僧からの直接の教授があったことから、どれほどまでのことかは知り得ませんが、印度のそれとある程度は同じく出来ていたと考えてよい。
しかしながら、例えば、前項にて空海は般若三蔵から「梵夾三口」を託され持ち帰っていたことを示しましたが、もし梵語を習得していたならば、「梵夾」の内容、その題目は当然理解出来、それが何かを明示していたことでしょうがしていません。このことからも、「空海が梵語を習得していた」ということは無かったと思われます。空海は密教の受法と修法に必要不可欠な程度まで梵字は習得していたとしても、梵語は習得していなかった。梵字とは梵語を記述する文字ですが、それらは当然、別個に考えるべきことです。
実は空海は、唐にて密教の正統を受法して帰国したものの、しかしその当初から真言というものの本質を全く理解してなどいませんでした。というのも、空海は本書『梵字悉曇字母井釈義』において、梵語・梵字についての自身の「甚だしく誤った」所見を以下のように述べているためです。
夫梵字悉曇者印度之文書也。西域記云梵天所製。五天竺國皆用此字。《中略》
世人不解元由謂梵王所作。若依大毗盧遮那経云。此是文字者自然道理之所作也。非如来所作亦非梵王諸天之所作。若雖有能作者如来不随喜。諸佛如来以佛眼觀察此法然之文字即如實而説之利益衆生。梵王等傳受轉教衆生。世人但知彼字相雖日用而未曾解其字義。如来説彼實義。若随字相而用之則世間之文字也。若解實義則出世間陀羅尼之文字也。所謂陀羅尼者梵語也。
そもそも梵字悉曇とは印度の文書である。『西域の記』〈玄奘『大唐西域記』〉には「梵王〈Brahman. 梵天〉が造ったもの」と云われる。五天竺〈印度を東西南北および中との五つに分けた称〉の国では皆、この字が用いられている。《中略》
世人はその元由を理解せず、(梵字は)「梵王の所作〈創造した物〉である」と言っている。しかし、もし『大毗盧遮那経』〈『大日経』.空海はここで『大日経』を根拠として以下のように言うが理解不足に基づく誤解〉に拠ったならば、この文字は自然道理の所作〈何者かによって作り上げられたものでも生み出されたものでもなく、自然の道理としてあるもの〉である。如来が作ったものでもなく、また梵王や諸天の作ったものでもない。もし「能作の者〈主体的に創造した者〉が存在する」などとしたならば、如来は随喜〈賛同して喜ぶこと〉されない。諸仏如来は仏眼を以て、これは法然の文字であると觀察し、そこで実の如くにこれを説いて衆生を利益されるのである。梵王等は、(そのような如来の所説を)伝え受け、それを転じて衆生に教えたにすぎない。世人はただその字相〈字の形〉を知って日々に用いてはいるけれども、未だ曾てその字義〈字の意味〉を理解してはいない。ただ如来のみがその実義を説かれている。もし単にその字相を以てこれを用いるだけならば、それは世間の文字である。(しかし、)もしその実義を理解したならば、それは出世間の陀羅尼の文字である。所謂、陀羅尼とは梵語である。
空海『梵字悉曇字母井釈義』(『定本 弘法大師全集』, vol.5, p.101)
ここには空海の大きな誤認が含まれています。
問題なのは、空海が「大毗盧遮那経に云く」などと、それが『大日経』の所説であるかのように云っているものの、しかしそのようには説かれてなどいないことです。そして空海のここでの主張は、縁起・無自性空を核とする仏教の思想から全く逸脱した発言ともなっています。印度から遠く離れた日本で、ましてや真言陀羅尼を記述する異国の文字であることからこれを神聖視せずにはおれず、また密教の正嫡として帰国した気負いがあって空海はそのように口走っていたのかもしれません。
当然のことながら、空海がそのような説を公然とした当時、早々に問題にされています。同時代の法相宗における俊才、徳一からその説が不合理であることが指摘され、梵字が「自然道理之所作」であるとはいかなることかや、その主張がいかなる理、あるいは典籍に基づくものであるか問われているのです。
梵字疑者。學眞言徒傳言。梵字是非梵天作非外道作。非佛所作。法然而有。但佛所顯示。今疑。問曰。法然有者。何等而有。爲無爲有爲耶。彼答曰。非有爲非無爲。但佛説顯耳。我疑問曰。有爲無爲所不攝法是無體法。此無體法三世不生。如菟角等。如何佛説顯令有詮用。又彼文字是翰墨所畫。現是等色法。是色等之有爲法非無爲法者。可如所言。何非有爲法。又遁倫師所造瑜伽疏第五云。劫初起梵王創造一百萬頌聲明。後慧命〈『成唯識論掌中樞要』・『瑜伽論記』では命恵〉減。帝釋復略爲十萬頌。次有迦單設羅仙略爲一萬二千頌。次有波膩尼仙略爲八千頌。今現行者唯有後二。前之二論竝已滅沒。又有開釋〈聞擇の写誤〉迦論一千五百頌。然護法菩薩造二萬五千頌。名雜寶聲明論。西方以爲聲明究竟之極論。盛行於世也。是名聲明根本。名號者。劫初時梵王於一一法皆立千名。帝釋後減爲百名。又減爲十名。後又減爲三名。總爲一品。又西域記第二云。詳其文字梵天所製。原始垂則四十七言也。準此等文。彼梵字實翰墨之所造畫。何故云法然而有。此疑未決
梵字の疑とは、真言を学ぶ徒〈空海〉が伝えて言うには、「梵字とは梵天の作ではなく、外道の作でもなく、仏の作る所でもなく、法然にして有り。ただ仏が顕示されたものである」〈『梵字悉曇字母井釈義 』〉とする。今、この説を疑って問う。「法然にして有り」とは、どのように有るというのか。無為〈asaṃskṛta. 作られたのでないもの。永遠不変のモノ〉なのか有為〈saṃskṛta. 作られたもの。因縁により生じた全て〉なのか。彼が答えるには、「有為でもなく、無為でもない。ただ仏が顕わされたのを説くのみ」という。私はそれを疑って問う。有為にも無為にも摂せられない法とは、無体の法〈実在しない空虚なもの〉である。無体の法は三世に生じることはない。たとえば兎角〈空華・亀毛などと同様、ただ空想上・概念上でしか存在し得ない物の象徴〉などのように。それをどのように仏が顕わに説き、実際に用いられるというのか。
また、彼の文字〈梵字〉は翰墨〈筆と墨〉によって書くものであって、それらは色法〈物質〉の現れである。もし色等が有為法であって無為法でないならば、そう言うように有り得はするだろう。(しかし、色とはまぎれもなく有為法である。)それをどうして有為法でないというのか。また、遁倫師〈新羅における法相の学僧. 道倫とも〉が造った『瑜伽疏』第五〈『瑜伽論記』〉に、「劫初の起こり〈現在の宇宙の創成期〉に梵王〈梵天〉が一百万頌の声明〈śabda-vidyā. 梵語の文法・音韻論〉を創造したが、後に(衆生の)智慧と寿命とが減じため、帝釈天がまた略して十万頌とした。次に迦単〈Kātyāyana. 前250年頃の文法学者〉・設羅仙〈Patañjali. 前二世紀頃の文法学者〉が出て、略して一万二千頌とした。次に波膩尼仙〈Pāṇ̣ini. 前五‐四世紀頃の梵語文法家でその大成者〉が出て、略して八千頌とした〈Pāṇ̣iniと、KātyāyanaおよびPatañjaliとが登場する時代が倒錯した誤認〉。今、現行するのはただ後の二人のものだけである。前の二論はいずれもすでに散失して無い。また、『聞択迦論』〈Muṇḍa. 梵語の語根を合成する法を記した文法書〉には一千五百頌〈『大慈恩寺三蔵伝』では三千頌〉がある。そこで護法〈Dharmapāla. 六世紀の印度における唯識の大論師〉菩薩は二万五千頌を造って、『雑宝声明論』〈現存せず〉と名づけている。西方〈印度〉ではこれを声明における究竟の極論とし、世に盛行している。これを(仏家における)声明の根本とする。名号とは、劫初の時、梵王が一一の法に於いてすべて千名を立て、帝釈天は後に減らして百名とし、また減らして十名とし、後にまた減らして三名とし、総じて一品とした」〈以上は、実は遁倫の説でなく基『成唯識論掌中樞要』の一節を遁倫が引用したもの〉とある。
また、(玄奘の)『西域記』第二に、「その文字〈梵字〉について詳かにしたならば、梵天が作ったものであって、原始〈太古〉に規則が布かれて四十七文字となった」とある。これらの文に準じれば、彼の梵字は実に翰墨によって描画されるものである(その始まりが明確なる「造られたもの」であり、すなわち梵字とは有為法)。一体いかなる理由・根拠から「法然にして有り」と言うのか。この疑いは未だ解決しない。
徳一『真言宗未決文』第八 梵字疑(T77, p.864c)
*但し一部の文字については註の「甲本」に従う
徳一からこのように問われた空海は後、『真言宗未決文』にて示されたその他の問いの多くには『広付法伝』などにて回答しているものの、どのような形であれ何ら反論していません。いや、示せるわけがありませんでした。そこで後代、この徳一からの鋭い疑問、論難について、空海の代わりにあれこれ答えようと、いわば空海擁護論を展開した者が幾人もあります。けれども、いずれもまともな答えになっていません。そして今も、その昔と同じように、徳一の問いに真言宗としての正答を与えようと試みる者がしばしば表れますが、まるで反論になっていません。
よく見られるのが、この梵字に関する空海の不合理な主張に対する徳一からの問いについて、空海と同様に梵字と真言とを混同した上で、あたかも徳一の問いがそもそも誤っているとか稚拙であったとする反駁です。しかし、それはまず徳一の問いが何かを理解しておらず、ただ無闇に空海ひいては真言宗を擁護しようとするものにすぎません。それはむしろ、空海が言ったところの「溺派子」、または慈雲が云った「宗派固まり」の徒の所行に相違ないものです。
ここで徳一が問うているのは真言についてでなく、あくまで文字体系としての梵字についての伝承、その位置づけです。上に示した徳一の問いはきわめて常識的で、仏教徒としてごく当たり前に感じてしかるべき疑問に基づくものです。これは空海が自身独自の見解を述べるために経説を牽強附会したのではなく、結局、単純に梵字というものの理解が、それはとりも直さず空海の『大日経』・『大日経疏』に対する理解となるのですが、その当初は読み誤っていたのでした。
では具体的にどのように誤っていたのか。それは空海自らが「若依大毗盧遮那経(もし大毗盧遮那経に依れば)」という、『大日経』の該当する一節を見ることにより、極めて明瞭となります。
復次祕密主。此眞言相非一切諸佛所作。不令他作。亦不隨喜。何以故以是諸法法如是故。若諸如來出現。若諸如來不出。諸法法爾如是住。謂諸眞言。眞言法爾故祕密主。成等正覺一切知者。一切見者。出興于世。而自此法。説種種道。隨種種樂欲。種種諸衆生心。以種種句種種文。種種隨方語言。種種諸趣音聲。而以加持説眞言道。
また次に、祕密主〈金剛薩埵〉よ、この真言の相は一切諸仏が作られたものではない。他に作らしめたものでもなく、また隨喜したものでもない。何故であろうか。この諸法は、法として是の如くしてあるからである。もし諸々の如来が出現されようとも、もし諸々の如来が(世に)出られなくとも、諸法は法爾〈真理.法然・自然〉として是の如くしてある。謂く、諸々の真言は真言として法爾であるのだから。祕密主よ、等正覚を成就した一切知者、一切見者が、世に出興して自らこの法によって種々の道を説き、種々の楽欲と、種々の諸衆生の心に隨って、種々の句、種々の文、種々の隨方の語言〈それぞれ異なる土地の言語〉、種々の諸趣〈六道または五趣などそれぞれ異なる生命のあり方〉の音声〈言葉・声・音〉により、しかも加持を以て真言の道を説かれる。
『大毘盧遮那成仏神変加持経』巻二 入漫茶羅具縁真言品第二之余(T18, p.10a)
以上のように『大日経』にて「法爾」、空海が云う所の「自然道理」であると説いているのは、あくまで「真言の相」すなわち真言の一音一音が表する本不生などの法、すなわち真理であって、それを書き表す文字について言ったものでは全くありません。ここで空海は、おそらく「真言の相」の「相」を文字であり、悉曇であると早とちりしたのだと思われます。もちろん、『大日経』はそのようなことはまったく説いていません。
そこでしかし、さらに『大日経』の善無畏による註釈書、『大日経疏』における当該の一説への解釈にはまた、空海がそのような誤解をなした基となったであろう記述があります。
經中次説眞言如實相。故云。復次祕密主。此眞言相。非一切諸佛所作。不令他作。亦不隨喜。何以故。以是諸法法如是故。若諸如來出現。若諸如來不出。諸法法爾如是住。謂諸眞言。眞言法爾故者。以如來身語意畢竟等故。此眞言相。聲字皆常。常故不流。無有變易法爾如是。非造作所成。若可造成。即是生法。法若有生。則可破壞。四相遷流。無常無我。何得名爲眞實語耶。是故佛不自作。不令他作。設令有能作之人。亦不隨喜。是故此眞言相。若佛出興於世。若不出世。若已説若未説若現説。法住法位性相常住。是故名必定印。衆聖道同。即此大悲漫荼羅一切眞言。一一眞言之相。皆法爾如是。故重言之也。若如是者。則是諸眞言相。畢竟寂滅不授與人。何故有時出興有時隱沒。故經復釋所由云。祕密主成正等覺。一切智者一切見者。出興于世。而自以此法。説種種道隨種種樂欲。乃至種種諸趣音聲。而以加持説眞言道。此意言。如來自證法體。非佛自作非餘天人所作。法爾常住。而以加持神力。出興于世利益衆生。今此眞言門祕密身口意。即是法佛平等身口意。然亦以加持力故。出現于世利益衆生也。如來無礙知見。在一切衆生相續中。法爾成就無有缺減。以於此眞言體相不如實覺故。名爲生死中人。若能自知自見時。即名一切知者一切見者。是故如是知見。非佛自所造作。亦非他所傳授也。
経〈『大日経』〉の中にて、次に真言の如実相を説くため、
「また次に、祕密主〈金剛薩埵〉よ、この真言の相は一切諸仏が作られたものではない。他に作らしめたものでもなく、また隨喜したものでもない。何故であろうか。この諸法は、法として是の如くしてあるからである。もし諸々の如来が出現されようとも、もし諸々の如来が(世に)出られなくとも、諸法は法爾として是の如くしてある。謂く、諸々の真言は真言として法爾であるのだから」と云うのは、如来の身・語・意は畢竟、(無自性空であって)平等であるからだ。この真言の相の声字は、みな常である。常であるから流転せず、変易あること無く、法爾として是の如く、造作の成すところではない。もし造成しえるものであれば、即ちそれは生起する法である。法で、もし生起するものであれば則ち破壊がある。四相〈生・住・異・滅〉と遷流するのであれば、それは無常・無我である。それをどうして真実語と言えるであろうか。この故に(真言の相とは)仏が自ら作られたものでなく、他をして作らせたものではない。たとい能く作る人があったとしても、また(如来は)隨喜されない。この故に、この真言の相は、もし仏が世に出興されようとも、もしくは世に出られなくとも、もしくはすでに説かれたことであれ、もしくは未だ説かれぬことであれ、もしくは現に説かれていることであれ、法は法位に住してその性相〈本質とその姿〉は常住である。この故に「必定印」という。諸々の聖者の道は同一である。すなわち、この大悲漫荼羅の一切の真言と一々の真言の相とは皆、法爾にして是の如くである。したがって重ねてこれを言うのだ。
もし是の如くであるならば、すなわちこの諸々の真言の相は畢竟、寂滅であって人に授与されることはないであろう。どうしてある時には(如来は)出興し、ある時には隠没するのか。故に経に、またその所由を釈して、「祕密主よ、等正覚を成就した一切知者、一切見者が、世に出興して自らこの法によって種々の道を説き、種々の楽欲と、種々の諸衆生の心に隨って、種々の句、種々の文、種々の隨方の語言、種々の諸趣の音声により、しかも加持を以て真言の道を説かれる」と云う。この意は、如来自証の法体とは、仏が自ら作られたものでなく、他の天や人によって作られたものでもなく法爾であって常住である。しかも加持神力を以て世に出興され、衆生を利益する。今この真言門の祕密の身・口・意は、すなわち法と仏と平等の身・口・意である。しかしながら、また加持力を以ての故に、世に出現して衆生を利益する。如来の無礙知見は、一切衆生の相続の中に在って、法爾に成就して缺減〈欠けて減じること〉あることが無い。この真言の体相に於いて如実に覚らないのを「生死の中の人」という。もしよく自ら知り、自ら見る時こそ、すなわち「一切知者」・「一切見者」という。この故に是の如く知見は、仏が自ら造作されたものでなく、また他が伝授するところでもない。
善無畏述 一行記『大毘盧遮那成仏経疏』巻七(T39, p.650b)
この『大日経疏』の一節にある「此眞言相。聲字皆常。常故不流。無有變易法爾如是。非造作所成(此の眞言の相の聲字は皆常なり。常なるが故に流せず。變易有ること無く、法爾として是の如く、造作の成す所に非ず)」という一節。中でも「此眞言相。聲字皆常」により、特に梵字悉曇という文字をして「自然道理」であると空海は理解してしまったのでしょう。
しかし、以上のように、『大日経』および『大日経疏』いずれもそのようなことは説いていません。それは「真言の相」が象徴する真理、法性が法爾であるということを強調したものであり、さらにまた密教における「声字」というものに対する理解を示したものです。
それは例えば、釈尊が悟られた法性について自ら説かれた阿含における経説に、これは『大日経疏』の別の箇所において引用されている一節ですが、結局同じものです。以下に示すのはパーリ仏典における該当する一節で、漢訳仏典では『雑阿含経』巻十二(T2, p.84b)にてほぼ同様に説かれています。
uppādā vā tathāgatānaṃ anuppādā vā tathāgatānaṃ, ṭhitāva sā dhātu dhammaṭṭhitatā dhammaniyāmatā idappaccayatā. taṃ tathāgato abhisambujjhati abhisameti. abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati deseti paññāpeti paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti. ‘passathā’ti cāha ‘avijjāpaccayā, bhikkhave, saṅkhārā’. iti kho, bhikkhave, yā tatra tathatā avitathatā anaññathatā idappaccayatā – ayaṃ vuccati, bhikkhave, paṭiccasamuppādo.
諸々の如来の出現が有ろうと、諸々の如来の出現が無かろうと、かの道理〈dhātu〉は定まって存する。法住性〈dhammaṭṭhitatā〉・法決定性〈dhammaniyāmatā〉・此縁性〈idappaccayatā〉である。彼の如来は(かの道理を)完全に悟り、全く理解する。(如来は自らが)悟り理解したように、(縁起を)説き、示し、証し、開き、分別し、明らかにする。「見よ、比丘たちよ、無明に依って行が生じる」と。そのように、比丘たちよ、それについての如性〈tathatā〉・不異如性〈avitathatā〉・真実性〈anaññathatā〉・此縁性、比丘たちよ、これを縁起という。
Nidānavagga, Paccayasutta (SN12. 20)
以上のことから、空海は唐にて当代の密教の正統を相承して帰国したとはいえ、弘仁年間頃は、未だ『大日経』ならびに『大日経疏』の所説を十分に咀嚼しておらず、真言というものの本質を完全に理解していなかったことが知られます。
空海が真言密教とは何かを示した『声字実相義』、ひいては『吽字義釈 』も成立年代が不明であります。しかし、本書『梵字悉曇字母井釈義』に見られた以上のような明らかなる誤解はもはやそこに見られないことから、徳一からの批判を受け、さらに『大日経』や『大日経疏』を充分に理解した上で著したものであったに違いない。
本書を著す頃に犯していた過ちは、徳一の鋭い指摘によって正され、むしろそれが空海の修学を深く綿密なものとさせ、その思想を円熟させていったと言えるでしょう。人は誤ちを犯すことにより、その反省によってむしろより一層向上するものです。
(もっとも、空海は徳一の批判に答えることが出来ないために、所見は捨てぬまま、ただその主張をその後は秘して公にしなかっただけの可能性も一応あります。)
いくら稀代の天才であったと古来評される空海であっても、唐は長安にて恵果阿闍梨から密教を受法したその初めからその理解や思想を全く完成させ、その死を迎えるまで何ら変遷せず一貫していたなどということはありません。空海が密教を受法して帰国してからも、その学を深め思想的にも成長していった、ということがここからも見て取れます。
これはわざわざ言うまでもない、人として極めて当たり前の話なのですが、空海をあたかも神のように崇め奉って妄信し、いわゆる「祖師無謬説」を奉じて刹那も微塵の疑問すら抱かずにいる多くの真言宗の僧徒らにとっては全く受け入れがたい見方かもしれません。それを認めたとして空海の学徳、その偉大性や価値が損なわれることなど無いでしょうに。そのように神格化して妄信することにより、むしろ空海自身および所伝の真言密教の真価を著しく毀損することにすらなる。事実、そのように思われることが多々あります。
とはいえ、本書に空海が記した「自然道理の所作」であるという梵字悉曇に対する理解は、真言ばかりか天台など後に続いた梵字悉曇を学ぶ諸僧の理解にも極めて大きな影響を及ぼしており、いわば権威ある言葉として今に至るまで語り継がれていくことになります。
これは現在の日本において密教者を自称する真言宗や天台宗の僧職者らの大部分も完全に誤認している点でもあるのですが、真言陀羅尼とは必ずしも「梵語でなければならない」というものではありません。
經云。祕密主云何眞言法教者。即謂阿字門等。是眞言教相。雖相不異體體不異相。相非造作修成不可示人。而能不離解脱現作聲字。一一聲字即是入法界門故。得名爲眞言法教也。至論眞言法教。應遍一切隨方諸趣名言。但 以如來出世之迹始于天竺。傳法者且約梵文。作一途明義耳。
経〈『大日経』巻二〉に「秘密主〈金剛薩埵〉よ、真言法教〈真言密教〉とは何であろうか。それはすなわち阿字門〈一切諸法本不生〉である云々」と(毘盧遮那〈Vairocana. 大日如来〉により)説かれていることについて、それがまさに真言の教相〈教えの特徴〉である。その相〈姿・特徴〉は体〈本質〉に異なったもので無く、その体は相に異なったものでは無い。(このような真言の)相とは(何者かによって意図的に)創造されたものでなく、(何故そうであるかの所以を)人に示すことなど出来はしない。それはしかし、解脱〈無自性・空たること〉を離れること無しに、声字〈音と文字〉として現にある。一つ一つの声字は、(それぞれあらゆる存在が無自性空・本不生であるという真理を象徴・開示しているものであって)すなわち法界に入る門であるから、「真言法教」と言う。これをさらに敷衍して言ったならば、真言法教とは、あらゆる方角のあらゆる趣〈境涯・生命のあり方〉における名・言語において普遍なるものである。ただし、如来が世に出られたのが天竺〈印度〉であったことから、その法〈教え・真理〉を伝える者は、仮に(印度の言語である)梵文を例とした一つの方法により、その意味を明らかにしているのに過ぎない。
一行『大毘盧遮那成佛経疏』巻七 入漫荼羅具縁品第二之餘(T39, p.651b-c)
釈尊が印度に生を受けて仏教が始まり、またその故に当然ながらその地の言語である梵語(など印度語)によってその教えが説かれ伝えられてきたものであるために、それを敬し、梵語によって真言を学び、また言うに過ぎません。とはいえ、そのようなことから、真言は梵語の語彙を前提としており、やはりそれに対する一定の理解が必須とはなります。
したがって、その意味においては、梵語は確かに特別な言語です。そして同時に、であるからが故に、そのように梵語の頭文字一字にて表される顕教(声聞乗および菩薩乗)の教理の重要な点を確かに理解することは欠くべからざるものです。
今もなお、「密教を行じるには、必ず顕教を理解しなければならない」ということまでは口にする密教者はそれほど多くはなくとも存在しています。ところが、「では、それは何故か?」という問に対して確たる返答をし得る者は非常に稀です。要するに、なんとなく誰かがそう言っていたのを聞いたことがある者が、オウム返しになんとなくそう繰り返しているにすぎません。
しかし、その答えは単純明快で、それ無しには真言として説かれる一連の言葉・音をどれほど懸命に、幾度も口にしたところで、それらはまるきり意味の無い迷信、世迷い言に等しい呪文の類となるためです。それではいくら複雑な密印をどれほど手に組んだところで、ただの詮無い手遊びにしかならず、また己が意識をその三摩地に運ぶことなど夢のまた夢となるためであります。
密教の本質は、この世のあらゆる言語を構成する声字、すなわち音あるいは字というものは、いずれもこの世のあらゆる存在・事象が縁起・無自性であるという真理を開示したものである、と理解する点にあります。声字というものに対する見方が世間のそれと全く異なっているという点からも、「真言密教」と言われます。それを確かに理解したならば、その者の世界は全く劇的に変わったものとなるでしょう。そしてその時、その者にとって密教はもはや密教では無い。
法身有義。所謂法身者諸法本不生義。即是實相。 《中略》
名之根本法身為源。從彼流出稍轉為世流布言而已。若知實義則名真言。不知根源名妄語。
法身にの義がある。いわゆる法身とは本不生の義であって、すなわちそれが実相である。《中略》
名の根本とは法身を源とするものである。それより流出して次第に転変し、世間に行われる言語となる。もし(あらゆる声字の)実義〈「本不生」等の諸々の声字に象徴される真理〉を知ったならば、それ〈ありとあらゆる音・言語〉は真言となり、その根源〈あらゆる音が開示している「本不生」などの真理〉を知らないままならば、(世間のあらゆる音・言語は)妄語である。
空海『吽字義釈』(『定本 弘法大師全集』, Vol.3, p.38)
空海もまたこのように、法身と阿字と本不生(実相)の等しいことを明らかとし、また真言のなんたるかを総括しています。阿に代表される声字とは畢竟「響き」、「ゆらぎ」であって、それは本不生であり、すなわちそのような万物を通底する無自性空たる有り様が法身と称されます。
現代、しばしば密教というものを説明するにあたり、真言についてなどまるで触れず、ただやたらと秘教であることを強調し、密教とは「梵我一如」であるとか「大宇宙〈マクロコスモス〉と小宇宙〈ミクロコスモス〉の合一」であるとかいうひどく神秘主義的な理解、外道の出来損ないのような説をもってする人が多くあります。それらは、実は仏教として噴飯物の言であって、まるで頓珍漢の宛が外れたものです。そもそも真言はどこにいったのか。どこか遠くに忘れてきてしまったのでしょう。
そこで真言について何か言い出したかと思えば、「真言とはホトケサマのオコトバです」であるとか「真実が秘める力を宿した言葉だ」とトボけたことをいい、酷いのになると、「普通の文章にも文字上には書かれていないが文脈としては存在するような言外の言葉のもつ力をはらむ言葉のこと」などという奇妙なこねくり回しをする者があります。彼らは一体何を、何に基づいてそう言っているのか。
少なくとも日本に伝わった密教は、これは真言宗であれ天台宗のそれであれ「真言密教」です。真言宗など、その別称は「真言陀羅尼宗」とすらいわれるものです。したがって、密教を説明するならば、必ず真言とは何かということを確かに踏まえた上で為されなければなりません。
以上示したように、世間一般に思われているように「梵語であるから真言である」・「真言であるならばそれは梵語でなければならない」などと言えたものでは決してない。「この世のあらゆる声字、音は真理を開示しているものである」という真言の本質からいえば、「真言は必ず梵語であって悉曇で書かなければならない」ということは無いわけです。
いや、もちろん仏典に悉曇で書かれているならばそれを悉曇としてそのまま正確に読み、発音しなければならないし、それを写すときも悉曇にて記述しなければなりません。空海が、前項にて示した『御請来目録』の中で「随音改義賒切易謬。粗得髣髴不得清切。不是梵字長短難別。存源之意其在茲乎(音に随って義を改めば賒切〈音の長短や促音等〉、謬り易し。粗、髣髴〈ぼんやりとして不明瞭なこと〉を得るといえども清切〈正確な音〉を得ず。是れ梵字にあらざれば長短別ち難く、源〈原語としての梵字〉を存す意、其れ茲に在り)」というように、悉曇において重要なのはその発音であり、またその一々の音、字が表する意義です。
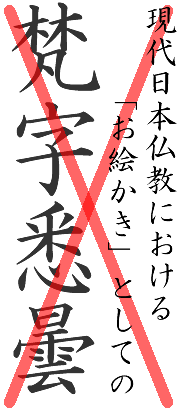
支那に始まり日本の近世に至るまで盛んであった悉曇学は、明治期に西洋から文献学としての仏教学とサンスクリット学がもたらされたことにより、たちまち衰亡して今ほとんど絶滅して無いが如きものとなっています。梵字悉曇は今やただ、僧職者らが自身らもただわけもわからず業務上必要とされる塔婆に書くため記号として、あるいは美術的鑑賞対象、はてまたは異国情緒漂う呪物的文様、迷信の類となっています。
その字形ももちろん重要ではあります。しかし、悉曇という文字自体は、義浄が印度において「六歳童子学之。六月方了(六歳の童子がこれを学んで、六月にてまさに了る)」〈『南海寄帰内法伝』〉ものだと報告しているように、六歳の子供でも六ヶ月もあれば充分習得できるものです。すなわち、英語のアルファベットと同様、悉曇を読み書き出来るくらいのことは本来、何ら驚くべきことでも特別なことでもありません。
大の大人が何年もかけてただ書くことばかり、しかもその書風・書体ばかりに工夫を凝らして学ぶようなものではない。先ず最も肝要な字音を無視して考究せず、またその字によって表される梵語の初歩をすらほとんど無視してただ字体や書体に拘泥するならば、それはもはや児戯に等しく、「お絵描き」に過ぎない。
事実、空海を初めとする先徳らが拘り追求した発音やその意義などまるで等閑視され、時代を経るなかで日本語の音が変化し、結果的に誤謬を含んだ伝統的読みを、なんら批判的考察を加えずに「これがデントーである」と強弁したまま、あり得ない発音で伝えるのみとなっているのが現状となってます。
その弊儀弊風を打壊し、おそらく極わずかながら在るであろう悉曇の真を求める者のため、ここに空海の『梵字悉曇字母并釈義』を示し、極拙いものながらも更にその註釈を并せます。おそらくは愚かな誤りを多く含むでしょうが、これが絶えんとする悉曇学を再び興し、縷縷としてでも後世に相承する微力とならんことを。
貧衲覺應 稽首和南