『末法灯明記』とは、延暦二十年〈801〉に日本天台宗祖最澄によって著された、と伝説される書です。
『末法灯明記』なる題目は、「末法にあっては、髪を剃り袈裟を着ただけの形ばかりで堕落した僧であっても、暗黒に等しい時代に光明をもたらすかけがえの無い存在である」というその内容を端的に表したものとなっています。本書の主眼は、今〈平安期初頭.最澄が著したと偽装するための設定〉や時代は末法に等しい、像法末期であることを人は理解しなければならず、したがって国家は正法および像法時における持戒の僧尼のあるべき姿を基準として、末法の「破戒することすら叶わぬ無戒の僧尼」を規制・排除すべきでなく、むしろ篤く敬って供養すれば国家も安寧たりえる、というものです。
そもそも末法とは、仏教の伝えられる時代を正法・像法・末法と三区分した最後の、文字通り「法の終末」時代を意味する語です。釈迦牟尼の入滅後、その教えが正しく行われてその証果を得る人もある時代としての正法。それが過ぎると、次にはただ教えは伝えられそれを修行する者はあっても証果を得る人が無くなる時代たる像法がある。そして最後には、教えはかろうじて伝えられても修行する者は無く、証果を得る人も絶えて無くなる時代があって、それが末法、とされます。
ただし、これが仏教における普遍的世界観かといえば、全くそうではありません。正法、すなわち仏陀の教えが仏滅後もなお正しく伝えられる期間は一千年、もしくは五百年であり、その後は形骸化するであろうとの説は『雑阿含経』や諸々の律蔵など仏典に説かれ、上座部など諸部派における論書などにも伝えられています。例えば上座部の教学大成者として過言でない大学僧、Buddhaghosaもいわゆる像法について言及しているほどです。
しかしながら、それは「末法」などという時の有ること、来ることを云うものでなく、ただ正法がどれほど長く世に行われるかを危機感を以って意識したものであるのですが、そこから「末法」なる時代の到来を予期、あるいは予言するものではありません。したがって、いわゆる末法思想など、声聞乗には存在しない。また、では大乗および大乗の徒に通じて共有されたものかといえば、そういうことも決してない。
(特に『末法灯明記』が主張する意味での末法思想は、日本における極一部の宗旨においてのみ通用したものです。これについては後述します。)
それは、仏教が伝えられて五世紀ほど経た後の支那において、仏教には正法・像法・末法の三時の区分があると主張されたことに始まるものです。その最初の人と目されるのが、南北朝の北斉における僧にして天台宗祖とされる慧思です。以降、後代の宗祖とされるような多くの学僧もまた様々に末法を意識し、言及した説を立てています。実のところ、正法・像法に類することを述べた経典は少なからずありますが、いわゆる末法なるものを明確に打ち出す経典は多くありません。その主たるものはただ『大集経』および『摩訶摩耶経』のみ。
けれどもその後、支那において醸成された末法思想が仏教の伝来と共に日本にも伝えられ、すでに飛鳥時代から存在していました。末法という時代のあることを意識し、その到来に対する漠然とした不安は、はや聖徳太子によるとされる『維摩経義疏』に見えます。また、『続日本紀』には、時代が像法に属していることの危機感とそれに基づく統治者としてのある種の責任感を、聖武天皇が有していたことが知られます。天平年間に渡来した鑑真の伝記『唐大和上東征伝』にも、像法にある僧の責務や、像法においても偉大な僧は数多あることが強調された言が記されています。
そして平安期初頭、『末法灯明記』の作者に擬せられた最澄本人は、法相宗の徳一と三一権実諍論を戦わす中、末法について以下のように述べています。
當今人機。皆轉變。都無小乘機。正像稍過已。末法太有近。法華一乘機。今正是其時。何以得知。安樂行品末世法滅時也。
まさに今の人機〈人の素質・能力〉は皆、転変して都て小乗の機は無い。正法・像法は稍く過已ぎて、末法は太だ近くなっている。法華一乗の機〈時機〉、今がまさにその時である。何を根拠にそれを知り得るかと言えば、(『法華経』)安楽行品に説かれる「末世法滅」の時だからである。
最澄『守護国界章』上之下「弾謗法者大小交雑止観章」 第十三
(『傳教大師全集』, vol.2, p.349)
最澄はこの書において、徳一の法相宗における止観に関する所説を小乗、あるいは小乗の混じった夾雑物であるとを断じて腐しつつ、様々に反論し、また論難しています。最澄は恐れや不安をもって末法に言及しているのではなく、むしろそれが自身の奉じる『法華経』(に基づく大乗の止観)こそ相応しい時代であって、徳一の小乗を交えた止観などもはや無益であり、教えだけあって修める者など無い、と断じる中での一節が、今上に示したものです。
最澄はまた、『末法灯明記』にも言及される『大集経』の一節にある「禅定堅固」という時代を表する語を用い、それは「小乗等の禅」に限ったものであると解釈しています。そして、その時代は過ぎ去って終わった。すなわち、徳一の云う止観は時代にもはやそぐわず、像法以降は一乗こそ得道することが出来うる時代であると主張しています。
末法においても菩提を得られるとするならば、それは末法ではないのではないか、と不審に思われます。すなわち、最澄のそれは前述した正法・像法・末法の定義とは異なった理解に基づく言で、論敵である徳一に対して大仰に言ったものであるのでしょう。しかし、この言だけ採って見れば、末法到来に対する恐れなどなく、むしろ今そして以降は我が時代とでも云いたげな勢いです。
(『守護国界章』は弘仁九年〈818〉に著されたものですが、徳一と最澄との論争はその後も応酬が重ねられてその死の前年、弘仁十二年〈821〉まで続いています。結局、一方的に最澄自身が勝利宣言して終わらせており、天台宗でもそれで最澄が勝ったことにしています。しかしながら、それは天台宗におけるどこまでも独善的な評価であって、実際のところ決着などしていません。)
さて、それから少し時代を下って平安中期にもなると、末法はいつ到来するのであるかと具体的な年が計算され、もはや自明のこととなっていたようです。例えば平安後期の天台僧、 皇円による史書『扶桑略記』には、末法時代に入ったことに言及した著名な一節があります。
永承七年壬辰正月廿六日癸酉。屈請千僧於大極殿。令轉讀觀音經。自去年冬疾疫流行。改年已後。弥以熾盛。仍爲除其災也。今年始入末法。
永承七年壬辰正月廿六日癸酉〈1051〉、千僧を大極殿に屈請して『観音経』を転読させた。去年の冬より疫病が流行しており、年を改めて以降はいよいよ盛んとなった。そこでその災いを除く為である。今年の始め、末法に入った。
皇円『扶桑略記』巻廿九(新訂増補『國史体系』, vol.12, p.292)
ただし、ここで皇円は淡々と「今年始入末法」と記すのみです。
疫病の流行とその除災の為の転読がなされた直後にこう書かれると、あたかも疫病と末法とが関連付けられたものかのような印象も持たれるかもしれません。しかし、疫病の流行など、それこそ往古から幾度となく生じ続けてきたことであって、末法に入った実感とは必ずしも直結するものとは云えません。
そこでまた、平安中期の公卿、春宮権大夫の藤原 資房の日記『春記 』にも、僧でない立場から、末法について言及した一節があります。
廿八日、天晴、《中略》
今日眞範僧正参入、督殿申云、長谷寺已以焼亡了、只今自彼寺告來、□〈虫喰欠損.眞であろう〉範彼寺別當也 《中略》 霊驗所第一也、末法之最年有此事、可恐之
(永承七年〈1052〉八月)廿八日、晴天。《中略》
今日、真範僧正が参入された。督殿が云われるには、長谷寺が焼失し、ただ今その寺から告げに来られたとのこと。真範はその寺の別当〈寺院の長官〉である。 《中略》 (長谷寺は)霊験所として第一であり、末法の最年にこのような事があるとは、恐ろしいことだ。
藤原資房『春記』(『丹鶴叢書』日本書紀・春記, pp.232-234)
ここでは長谷寺が焼失したことを末法の最初の年に絡め、極短く「可恐之」とではありますが、受け止められています。しかし、それでも長谷寺が焼失したのは実は天慶七年〈944〉以来、二度目のことであって、前代未聞ということでも末法となったから初めて起こったということでもありませんでした。
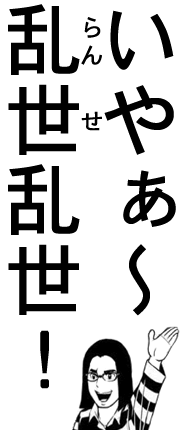
ところで、平安中期は律令制がすでに崩壊し、鑑真によりようやくもたらされた具足戒の制も九世紀中頃に形骸化、天台宗ばかりでなく南都六宗にても破戒僧が横行していました。そして、比叡山は山僧の一部が武装化して僧兵を組織するようになっており、諸大寺もまた、広大な荘園を有するようになっていたことから、同じくその領地を防衛するための僧兵を有するようになっています。やがて僧兵は、朝廷を脅して無理を通すための強訴を行い、また同宗内の派閥争いや他寺との諍い、そして他の領地を侵害するための暴力組織となっていきます。
当時、末法はただの「お話」としてだけでなく、ひどく人にそれを実感させる事態が、僧徒によって繰り広げられていたのです。末法が到来したのではなく、それは当時の僧徒らがむしろ自ら創り上げていったと云ったほうが良い。
『扶桑略記』はまた、末法に入ったとされる年から三十年後を経たことを、恐るべき未曾有の事件があったことと共に伝えています。
○九月十三日丙申。三井寺大衆。中不覊倫等三百人許。密々相招。夜半登山亂逆。不報一事被殘滅畢。十四日丁酉。公家被下宣旨。遣撿非違使幷前下野守源義家䒭三井寺殘房。令追捕登山僧䒭。翌日。件使等至彼寺。十五日戊戌。未時。山僧引率數百兵衆。行向三井寺。重焼殘堂舎僧房䒭畢云。堂院二十處。經藏五所。神社九處。僧房一百八十三處。但舎宅不注載之。不知其數幾千而已。門人上下各逃隠山林。或含悲入黄泉。或懷愁仰蒼天。今年入末法。歴三十年矣。
○(永保元年辛酉〈1081〉)九月十三日丙申、三井寺〈園城寺〉の大衆の中の不覊倫〈定めに従わない不貞の輩〉など三百人ばかりが密かに相謀り、夜半に山〈比叡山〉に登って乱逆を働いたが、結局その事は報われずに残滅させられた。十四日丁酉、公家が宣旨を下さられ、検非違使ならびに前の下野守源義家などや三井寺の残房を遣わし、登山した僧などを追捕した。翌日、件の使い等が彼の寺に到った。十五日戊戌、未の時〈13-15時〉、山僧が数百の兵衆を引率して三井寺に行き向かい、(本年の六月から)再度(焼けずに)残っていた堂舎や僧房などを焼き尽くしたという。堂院二十処、経蔵五所、神社九処、僧房一百八十三処。ただし、舎宅〈住居〉についてはここに注載していない。その数が幾千にも及んでいたためである。(三井寺の)門人は上も下も、それぞれ山林に逃れ隠れ、あるいは悲しみを含んで黄泉に入り、あるいは愁いを懐いて蒼天を仰ぐばかりであった。今年は末法に入って三十年を歴た。
皇円『扶桑略記』巻三十(新訂増補『國史体系』, vol.12, pp.323-324)
この一節にある延暦寺大衆による三井寺〈園城寺〉の焼き討ちは、同年六月にすでに行われていた大規模な焼き討ちの再現、三井寺へのとどめとも言えたものでした。事実、三井寺はこれによって堂舎の大半を失っています。その六月の焼き討ちについて、皇円は「開闢以來。世未有此之灾禍矣。《中略》廣考天竺震旦本朝佛法興廢。未有如此破滅。今記此災。落涙添點(開闢以来、世に未だ此の如き災禍有らず。《中略》広く天竺・震旦・本朝の仏法の興廃を考えるに、未だ此の如き破滅有らず。今、此の災いを記すに、落涙して點を添ふ〈「點を添ふ」は「襟を沾す」の誤写の疑い有り〉)」と非常なる衝撃をもって記しています。

そもそも、同年三月は興福寺の大衆が多武峯 〈多武峰寺(談山神社)〉を急襲しており、四月には三井寺の大衆が比叡神社の祭事を妨害するなど、寺家による騒乱が続いていました。そのような僧徒による暴力は平安中期頃から常態化しており、例えば比叡山の大衆や興福寺の堂衆などによる強訴がすでに幾度となく行われています。しかし、それでもなお永保元年〈1081〉における山門〈延暦寺〉と寺門〈三井寺〉の争いは熾烈を極めた異常なもので、ついに三井寺が未曾有の損害を出していたことは、特に畿内の人々から甚だしい畏れをもって眺められていたようです。
比叡山は最澄が死んで百年も経たない頃から羽織ゴロならぬ袈裟ゴロ、仏教ヤクザとでも云うべき悪僧の巣窟と化しており、その暴虐は目に余るものがありました。しかしながら、当時の天皇も公家も仏教を信じていたが故にむしろ迷信に没しており、そんな延暦寺にほとんど抗うことなど出来なくなっています。
『平家物語』は中世初期の成立ですが、以下の一節は、当時の比叡山の僧がいかなるものであったを伝えています。
賀茂川の水、双六の賽、山法師、これぞ我が御心に叶はぬものと、白河の院も仰せなりけるとかや。鳥羽の院の御時も、越前の平泉寺を山門へ寄せられける事は、当山を御帰依あさからざるによつてなり。非を以て理とすと宣下せられてこそ、院宣をば下されけれ。されば江帥匡房卿の申されしは、山門の大衆、日吉の神輿を陣頭へ振り奉て訴訟を致さば、君はいかが御計らひ候ふべきと申されければ、法皇、げにも、山門の訴訟はもだし難しとぞ仰せける。
「加茂川の水、双六の賽、(比叡の)山法師。これらこそ我が御心に叶わぬものだ」と、白河法皇も仰せられたということである。鳥羽法皇のご治世でも、越前の平泉寺を山門〈延暦寺〉の末寺とされた件については、(そもそも道理の通らぬ話であったが、法皇が)当山〈比叡山〉に深く帰依されていたからこそ、「不条理なことであるが理とする」と宣下され、院宣を下されたのである。そのようであったから、江帥匡房卿〈大江匡房〉が(法皇に)お尋ねになって「山門の大衆〈比叡山延暦寺の僧徒〉が、(比叡山の鎮守である)日吉神社の神輿を陣頭へ振り奉って強訴してきたならば、陛下はどのようにお計らいなさられますか」と申し上げたならば、法皇は「まことに山門の強訴は看過できないことである。(しかし、彼らの非法・暴虐なる振る舞いはどうにもならない)」と仰られた。
『平家物語』巻一(原文のカナを適宜漢字に改めた)
末法が到来したとされる年から一世紀ほど経た平安末期は、相変わらず諸大寺のの横暴が続いていた上に、多くの自然災害にしかも立て続いて見舞われ、国家のあり方として公家社会から武家社会へと大変革しようとしていた頃です。もっとも、その武士の台頭を許すきっかけを作ったのも、実は強訴によって朝廷を脅かし、隙あらば他の荘園・領地、そして寺社の権利をかすめ取ろうとする比叡山や興福寺の僧兵たちでした。実に皮肉な話です。それは末法というより、まこと「世も末」と感じさせる現実の脅威でした。
そんな中、突如として「最澄撰」として世に現れたのが『末法灯明記』です。それがいつ頃捏造され、世に現れたのか正確なところは今も不明です。が、『末法灯明記』のような衝撃的内容が書き連ねられた書が最澄の名の元に平安中期からすでに存在していたならば、同時代の書に必ずなんらかの形で言及されたであろうことから、平安末期であったろうと考えられます。
『末法灯明記』は、一見「なるほど、そう来たか」と感想させる、ある意味で面白い論述が一部なされてはいるものの、よくよく見ていけばひどく杜撰な僻事が陳列された内容です。しかしながら、衆人がこの書に飛びついて信じてしまう環境は上に示したように整っていました。それは時代精神というべき、当時の人々が共有していたであろう薄ぼんやりとした危機感に上手く嵌ったようです。
といっても、そのような環境は外的要因でなく、上にその一部示したように、むしろ当時の僧徒、しかも他でもない天台宗徒自らが多く作っていたものです。『末法灯明記』を偽作した者は、間違いなく天台宗に属する、ある程度の地位にあった学僧と考えられます。そこで、天台宗が天皇すら手に負えずに嘆かせるようなものであったからこそ、自身らの破戒、暴虐の数々を世に容認させる根拠として練り上げ、ついに個人的ながらもひそかに世に提出したものであったのでしょう。
(ただし、ここで注意すべきは、その天台宗本体では『末法灯明記』を殊更に引用し、「末法」ということを前面に打ち出した人が当時存在していない点です。そしてそれには明瞭な理由が存していたと思われるのですが、これについては後述します。)
そこで『末法灯明記』が最澄作の書として世に現れて以来、もっとも取り沙汰され、現在ですら必ずといっていいほど言及されるのが以下の一節です。
末法唯有名字比丘。此名字爲世眞寶。更無福田。設末法中。有持戒者。旣是恠異。如市有虎。此誰可信。
末法にはただ「名字の比丘〈名ばかり・形ばかりの偽比丘〉」しか存在しない。(したがって)その名字の比丘を世間における真実とする以外、他に(世間に善果報をもたらし得る)福田など無い。設い末法の中に持戒の者あらんも既に是れ怪異なり。市に虎有るが如し。此れ誰か信ずべけん。
『末法燈明記』(『傳教大師全集』, vol.1, p.418)
この一節は鎌倉新仏教などといわれる宗派の祖師とされる人々が軒並み引用しています。その事実によっても、どれほどこの書が当時の比叡山出身、あるいはそこに学んだ僧徒の耳目を集めていたかを知ることが出来るでしょう。『扶桑略記』を著した皇円に師事していた法然は、まさにその内の一人です。
蓋於近來僧尼凡不可論持戒・破戒。何者論持戒・破戒者。是在正法・像法之時。至今末法但是名字比丘而已。故傳教大師末法燈明記云。設末法中有持戒者旣是怪異。如市有虎。此誰可信。又云。於末法中但有言教而無行證。若有戒法可有破戒。旣無戒法。由破何戒而有破戒。破戒尚無。何況持戒。夫受戒之法中國請持戒僧十人證明得戒。於邊地請五人證明得戒。然近來求持戒僧尚難得一人。況五師乎。然則此經説破戒者。且約正・像時耳。
思うに近来の僧尼に於いて、およそ持戒・破戒を論じることは出来ないであろう。なんとなれば、持戒・破戒を論じ得るのは、正法・像法の時に在ってのことである。今の末法に至っては、ただ「名字の比丘〈名ばかり・形ばかりの偽比丘〉」のみしかないのだ。したがって、伝教大師〈最澄〉の『末法灯明記』に「設い末法の中に持戒の者あらんも既に是れ怪異なり。市に虎有るが如し。此れ誰か信ずべけん」とあり、また「末法の中に於いて、但だ言教有りて行証無し。もし戒法有らば破戒有るべし。既に戒法無し。何の戒を破するに由って、しかも破戒有らん。破戒なお無し。何に況や持戒をや」とある。そもそも、受戒の法とは中国〈都市部〉においては持戒の僧十人を請じ、その証明として得戒するものであり、辺地〈辺境〉においては五人を請じ、その証明として得戒するものである〈日本では東大寺戒壇院では十比丘、下野薬師寺・筑紫観世音寺の戒壇院では五比丘による受具が行われた〉。しかしながら、近来は持戒の僧を求めたとしても、なお一人として得ることも出来ない。ましてや五師など言うまでもない。そのようなことから、この経〈『観無量寿経』〉で説かれる「破戒」とは、仮に正法・像法の時に約したものである。
源空『黒谷上人語燈録』(T83, p.143c)
このように、法然は当時の僧が戒律など一向護らずあることを是認する根拠とし、またそこで阿弥陀の称名念仏こそ最も優れた行であることを言わんとして『末法灯明記』を挙げていたことが知られます。
ただし、ここにいわれる持戒や破戒の戒法とは、最澄が天台宗徒には無用であると宣言し、その後天台宗ではその通り放棄してきた具足戒、すなわち比丘律義についてのものです。そこで法然は天台宗徒であったことから、比丘律儀など受けておらず、ただ梵網戒のみを受持する人でした。
梵網戒とは、鑑真渡来以前、天平の昔から特に巷で流行していたことが知られる、(支那撰述の偽経たる『梵網経』に基づく)出家在家共通の菩薩戒です。ただ菩薩戒を受けることによって出家することなど全く出来ず、また比丘になどなれる筈も決してないものです。そして、その梵網戒を受けるのには、十人あるいは五人の持戒の僧など必要ありません。
したがって、そもそも天台宗徒が代々受けても守ってもいなかった比丘律儀の受戒をここで法然が持ち出し、その破戒・無戒を良しとすることは奇妙な話です。一般に、法然は「末法無戒を言っていたが、実際のところ自らは戒を厳しく受持していた」などと云われます。しかし、法然のいった破戒・無戒の戒と、梵網戒とは全く異なるものであって、その点まるでちぐはぐとなっています。
そしてまた、天台宗における梵網戒に対する教学的な見方に於いては、破戒など最初から問題となるものではありませんでした。
夫婦六親得互爲師授。其受戒者。入諸佛界菩薩數中。超過三劫生死之苦。是故應受。有而犯者勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。
この十重戒〈十無尽戒〉を授けるのには、夫婦など六親眷属が互いに師〈授者〉となり受者となるも可である。(十重戒を)受戒したならば、諸仏界の菩薩衆の中に入り、三劫に生死流転する苦を超過するであろう。そのようなことから(十重戒を)受けるべきである。(十重戒を受戒して)犯す者は、戒を受けていなくとも(十重戒の制する行為を)犯さない者に勝る。(受戒してなお)犯す者を菩薩といい、(受戒せず)犯さない者を外道という。
《伝》竺佛念訳『菩薩瓔珞本業経』卷下 釈義品第四(T24, p.1021b)
この『菩薩瓔珞本業経』(以下、『瓔珞経』)にある一節の内容は、一般的な見方からすれば、理不尽極まりないと感ぜられて然るべきものです。しかし、天台宗が円戒(円頓戒)であると主張した梵網戒に関して、このような『瓔珞経』の所説は併せて理解されていました。これは破戒を勧めたものではありません。しかし、その言葉通りに理解すれば、持戒などさておき、受戒すること自体が至上の価値あるものと述べたものです。
この『瓔珞経』の所説は、特に義寂や大賢など新羅の法相宗僧によって注目され、やはり言葉通りに理解されて日本にもそれが伝えられおり、例えば円仁はこのように言っています。
菩薩戒有受法而無捨法。有犯不失盡未來際。
菩薩戒には受法はあるけれども捨法は無い。もし(菩薩戒を)犯したとしても(、そしてその者が命を終えたとしても)未来永劫、失うことは無いのだ。
円仁『顕揚大戒論』卷第四 菩薩受戒法式篇七(T74, p.702b)
以上のことから、天台の云う円頓戒では、語弊のある言い方になりますが「一得永不失」である点において破戒はある意味容認されています。また、菩薩戒を授受する者の条件に、比丘律儀とは異なって、絶対的な制限など無く、さらに師が無くともただ自らが誓って受けるという自誓受戒が許されているため、全く無戒であることは有り得ません。これは時代が像法であるとか末法であるとかいう問題に関わらない話です。
もっとも、当時は同じ天台宗であっても、梵網菩薩戒でなく比丘律儀を東大寺などの三戒壇院にて受ける僧徒が存在していました。三井寺を本山とする寺門派の僧です。その理由は、延暦寺が三井寺との対立が激化したことにより、その戒壇における受戒(いわば延暦寺の授戒権)を持ち出して三井寺に属する僧徒を脅迫し、実際に授戒を拒絶していたためです。そこで、寺門派で新たに僧となろうとする者は、南都などの戒壇院で授戒していたのです。そうしなければ、これは国家の制度として、正式に僧とは認められなかったためでした。
そのように三井寺の僧徒が東大寺などにおける戒壇院で受戒するようになっていたことに対し、また延暦寺は激昂していました。けれどもそれは、そもそも自身らが極めて不合理で横暴な態度、いや暴力そのもので三井寺を脅し、圧していたことに起因するのですから、実に仕様がありません。
天台宗本体となる延暦寺が『末法灯明記』の所説を奉じ、その説く末法を全面に出すことはなかったと先に指摘しておきましたが、それもその筈。そのような意味での末法を認めてしまえば、延暦寺が振りかざしていた延暦寺戒壇の存在意義自体やいわば利権を自ら放擲することになるためです。延暦寺として『末法灯明記』の所説を全面的に認めることは、その立場として出来ることでは無かったと言えます。

たとえば戒壇についての話で特記すべき著名なのは、何と言っても三井寺の頼豪に関する伝承です。三井寺を焼き討ちするに到る前段として、承保元年〈1074〉、頼豪の祈禱によって敦文親王の誕生がもたらされたちする功賞として、三井寺に戒壇〈三昧耶戒壇〉を建立したい旨を白河天皇に上申していたことがあります。それを白河帝は許そうとするも、延暦寺の猛反発に依って実現しませんでした。しかしそこで、願いが叶わなかった頼豪よりむしろ、比叡山以外に戒壇を建てたいという願いを三井寺が持ったことへの延暦寺衆徒の怒り、反発は凄まじいものであったようです。比叡山は、頼豪が戒壇建立が許されなかったことを恨んで食を断って憤死し、鼠の妖怪となって延暦寺の経蔵を襲った、などという与太話を創り上げて語り継ぎ、死後もなおその名を穢して貶めています(『愚管抄』・『太平記』・『尊卑分脈』等)。
そのようにしていた比叡山が、自ら戒壇の存在意義を亡くしてしまうような『末法灯明記』の所説を受け入れられるわけがない。したがって、末法を強調し、および破戒・無戒を容認する主張を比叡山が唱えなかったのは何ら怪しむべきことではありません。これは三井寺も同様で、末法無戒を容認するならば、(国家公認の)戒壇を造る必要などなくなります。
けれども、法然は比叡山延暦寺(山門)に属した僧であってもすでに山を降りており、また三井寺(寺門)の僧でもないため、この問題に直接関わりありません。それは法然の弟子であった親鸞も同様で、この時の法然がなした説法の内容は、自ら書き留めた書『西方指南抄』にも載せています。親鸞は当然、このような法然の言を全く信じ切っており、後に著した自らの著作『教行信証』に至っては『末法灯明記』のほとんど全文を引用しています。
そして、浄土教徒らが好んでこれを引いたのに等しく、日蓮もまたこの書を好んで読んでおり、やはり先の一節を同じく引用していました。
問云。末代初心行者制止何者乎。答曰。制止檀戒等五度一向令稱南無妙法蓮華經爲一念信解初随喜之氣分也。是則此經本意也。疑云。此義未見聞驚心迷耳。明引證文請苦示之。
《中略》
文句云。問若爾持經即是第一義戒。何故復言能持戒者。答此明初品不應以後作難等。云云 當世學者不見此釋以末代愚人南岳天台二聖誤中誤也。妙樂重明之云。問若爾者若不須事塔及色身骨亦應不須持事戒。乃至不須供養事僧耶等。云云 傳敎大師云。二百五十戒忽捨畢。唯非限教大師一人鑒眞弟子如寶道忠竝七大寺等一同捨了。又敎大師誡未來云。末法中有持戒者是怪異。如市有虎此誰可信。云云
【問】末代における初心の行者には、何を制止するであろうか。
【答】檀・戒等の五度〈六波羅蜜の慧以外.慧をまた信に置換〉を制止して、一向に「南無妙法蓮華経」と称えさせることを、一念信解初随喜の気分とする。それこそが、この経〈『法華経』〉の本意である。
【疑】そのような説など未だ見聞したことは無く、心を驚かし、耳を迷わせるものである。明確な証文〈典拠〉を引いて、ねんごろにそれを示すことを請う。
【答】《中略》 『法華文句』〈智顗『妙法蓮華経文句』第十〉に、「《問》もしそうであるならば、持経〈『法華経』を肌見放さず信じ行うこと〉は即ち第一義戒であろう。どうしてまた『よく戒を持つ者』と言うのであろうか。《答》これは初品(の意)を明かしたものであって、後(品)について(今ここで)難を作してはならない」等とある。今の学者はこの釈を見ずに、末代の愚人を以って南岳大師〈慧思〉と天台大師〈智顗〉の二聖者と同じ様に考えている。誤りの中の誤りである。妙楽大師〈湛然〉は重ねてこれについて明かし、「《問》もしそうであるならば(等)は、もし事の塔〈仏塔〉及び色身の骨〈仏舎利〉を須いず、また須く事の戒〈二百五十戒〉を持つべきでなく、乃至、事の僧〈実際の僧伽〉を供養することを須いないのか」等としている〈湛然『法華文句記』〉。伝教大師〈最澄〉は、(弘仁九年〈818〉の暮春に)「二百五十戒を忽ちに捨て去った」と云っている〈釈一乗忠『叡山大師伝』〉。しかもそれは、ただ伝教大師一人に限ったことでなく、鑑真の弟子の如宝・道忠、並びに七大寺等の一同も(二百五十戒を)捨てていた〈!?〉。また伝教大師は未来について教誡し、「末法の中に持戒の者有らば是れ怪異なり。市に虎あるが如し。此れ誰か信ずべけん」と云っている。
日蓮『四信五品鈔』(『日蓮宗全書』, vol.1-2, p.771)
この一節で日蓮は、不可解な引用をした上にいくつかの酷い誤認をも開陳していますが、いずれにせよ『末法灯明記』を最澄の真撰であるとし、またそこに説かれる末法に関する説を全面的に受容した上で、先に示した一節を引用し、その主張の論拠としています。日蓮は、中でも特に「市に虎あるが如し」の一句を気に入っていたようで、その他著書でしばしば用いています。
もっとも、日蓮は『四信五品鈔』を著す以前、持戒の要について云っていました。しかし、その戒とは『法華経』のたった一句、そしてまた『涅槃経』の一節を援用して全く別様に捉えたものです。
法華經云。此經難持。若暫持者。我即歡喜。諸佛亦然。如是之人。諸佛所歎。是則勇猛。是則精進。是名持戒行頭陀者。於末代者無四十餘年持戒。唯持法華經為持戒也。是三
『法華経』に、「この経を持つこと難し。もし暫くも持つ者は、我即ち歓喜す。諸仏もまた然なり。是の如きの人は諸仏の歎じたまう所なり。是れ則ち勇猛なり。是れ則ち精進なり。是を戒を持ち頭陀を行ずる者と名づく」〈『法華経』巻四 見宝塔品第十一〉と説かれている。末代には四十余年の持戒は無い。唯だ『法華経』を持つことを持戒とするのだ。是三
日蓮『守護国家論』(『日蓮宗全集』, vol.1-1, p.388)
日蓮にとっての戒とは、一般的な五戒・八斎戒や比丘律義、あるいは菩薩戒などでもなく、『法華経』を徹底的に(あくまでも彼が正しいと思う理解の仕方で)信じ持つことでした。それは最澄(仮)のいう像法の破戒や末法の無戒の意味する戒とも異なるものです。
したがって日蓮にとって、末法において一般的な意味での戒律などむしろ全く無視すべきものであり、ましてや比丘の具足戒など端から論外で、その意味ではまさに「末法無戒」です。そのような見方を正統化するのに『末法灯明記』の説はまたとないものとなっています。
ただし、時はまさに末法であっても、「『法華経』をただひたすら信じることが戒」とする点において、彼の中では「末法無戒」ではありません。彼日蓮の中では、そう理解し得たことによって、仏道の正統たる戒・定・慧の三学の階梯を踏み外すことを回避し得たのでしょう。しかしいずれにせよ、それは極めて特殊な、後代「一文を取りて万経を捨てる」と評されるものです。
ところが、これら浄土や法華を一向に信じる者らが『末法灯明記』の説を全面的に受容していたのに対し、同時代の栄西は全く別の態度を取っています。
問曰。或人云。傳敎大師末法燈明記云。末法無持戒人。若言有持戒者是怪也。譬如市中有虎文 答曰。大般若經云。師子咬人狂狗逐塊。是此謂歟。汝何逐文字言語之塊。忘永有持戒修善之人也。廣見聖敎之施設。遠鑒衆生之善業矣。大般若經云。後五百歲文 大般𣵀槃經云。末法贖命文 法華經云。於後末世文 大論中論摩訶止觀同之。金剛般若經云。後五百歲有持戒修福者。於此章句能生信心。當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所。種諸善根聞是章句。乃至一念生淨信者文 並勸末世之戒行也。凡如來開口皆冠末世乎。祖師動舌併爲今後也。傳教大師釋可得意矣。或彼小乘律儀戒。非謂大乘菩薩戒焉。
《問》ある者は云う、伝教大師〈最澄〉の『末法灯明記』に「末法に持戒の人無し。若し持戒の者有りと言わば是れ怪なり。譬へば市中に虎有るが如し」とあると。
《答》『大般若経』に「師子は人を咬み、狂狗は塊を逐う」とあるのは、まさにこの謂であろう。汝はどうして文字・言語の塊を逐って、永く持戒修善の人のあることを忘れるのか。広く聖教の施設〈俗世について仮に説かれた教え〉を見たならば、(仏は)遠く衆生の善業を鑑みられている。『大般若経』には「後五百歲」とあり、『大般涅槃経』には「末法に命を贖う」とあり、『法華経』には「後の末世に於いて」とある。『大智度論』・『中論』・『摩訶止観』もそれらに同じである。『金剛般若経』には「後五百歲に持戒修福の者があって、この章句に於いて、よく信心を生じるであろう。まさに知るべし、その人は一仏・二仏・三・四・五仏に於いて、善根を種えるだけではない。すでに無量千万仏の所に於いて、諸々の善根を種え、この章句を聞いているのだ。乃至、一念に浄信を生ずる者である」と説かれている。いずれも末世における戒行を勧めたものである。およそ如来の開口〈説法〉は、すべて末世を念頭にしたものであろう。祖師の動舌もまた、あわせて今後の為のものである。伝教大師の釈〈『末法灯明記』〉については、その意を得べきである。あるいは彼は小乗律儀戒について云ったものであって、大乗菩薩戒を謂ったものではないであろう。
栄西『興禅護国論』巻上 第三世人決疑門(T80, pp.6c-7a)
栄西もまた、『末法灯明記』が最澄の真撰であろうと認めてはいました。しかし、その言葉を額面通りには取っておらず、むしろ反証を示しています。
そして栄西はこの一節の最後に、『末法灯明記』にある「末法に持戒の人無し」における持戒とは、小乗律儀戒について云ったものであって大乗菩薩戒ではないであろうなどと言っています。それは確かにその通りであるのですが、しかし、この『興禅護国論』はもとよりその他の著作において、栄西は大小の律儀を必ず厳持するべきことを主張し、実際に自身がその双方を受持しています。そんな栄西にとって、当時一部で流行し初めていた末法ということを認めるにしても、法然などが信じ主張したようなものでは決してありませんでした。
そもそも栄西は、最澄を「我が大師」などと云って敬愛している手前、最澄の説とされるものに真っ向から露骨に反論することはありません。栄西にとって最澄はどうあっても「正しい人」でなければならなかったのでしょう。この『興禅護国論』の一節では、それはかなり無理のある言であったと思われますが、「可得意」として最澄の本意は別にあると主張しています。
しかしながら、ではその「意」とは何か、いかように理解すべきであるかを、栄西は語っていません。「大乗菩薩戒を謂うに非ず」というのがその意としたものかもしれませんが、それでは全く答えになっていません。栄西は、それと似たような最澄を擁護する弁舌を『出家大綱』においても展開していますが、やはり肝心な「意」が何かをまるで語っていません。けれども、実は栄西の『興禅護国論』を含めた諸々の著作の中での主張は、むしろ『末法灯明記』はもとより、最澄の実際の説やその後の天台宗のあり方を全く否定しているのに等しい内容に満ちたものとなっています。
なお、いわゆる鎌倉新仏教などと現代いわれる祖師の中、残る道元は『末法灯明記』に直接触れる事はなく、末法思想そのものを否定しています。実際のところ、栄西とは異なり、道元における戒律に対する思想やあり方もまた仏教として極めて特殊で、それを「仏祖正伝菩薩戒」などという語を造って自称していましたが、実は印度・支那以来の伝統とも乖離し異なったものでした。それは正統とはとても言えたものでありません。しかし、少なくとも我が道と信じるものを現実に行っていた道元にとっても、『末法灯明記』が主張したような末法は存在していません。
鎌倉期といえば、叡尊や忍性、そして覚盛などが復興した新たな律宗(現代いうところの真言律宗ではない)にも言及しなければなりません。特に西大寺の叡尊や極樂寺の忍性を中心とした律宗教団は、実は鎌倉期の当時、日本で最も信仰を集め、最大の教団を擁していたことが知られます。そんな彼らは、これは南都における従来の諸大寺の見解をそのまま受けたものであったのですが、そもそも日本の破戒・無戒の風潮を作ったのは平安期の最澄〈『山家学生式』・『顕戒論』〉であると見なしており、特に天台の亜流でもてはやされた『末法灯明記』など歯牙にも掛けていません。
とはいえ、そのような戒律復興の動きが生じるまで、南都の諸大寺における僧徒が厳しく持戒していたかといえば全くそうでなく、破戒が常態化していました。しかし、南都の諸僧は破戒が「間違ったことである」、「堕落している」という認識は有しており、持戒なしに証悟は決してないとの理解も持っていた。であったからこそ、実範を初め、叡尊や覚盛などがそれを復興すべく現れています。また、日本の天台宗が比丘律儀を捨ててなお僧である、出家であると称していたことは、まったく仏教の伝統に背くものであって、なんら根拠のないものであると考えていました。したがって、彼らは当時の人々がよく口にした「末世」ということは言っても、そこに主張された破戒・無戒を是とする時代としての末法など問題外としています。
そのようなことから、鎌倉期に末法思想が流行っていたといっても、それはあくまで浄土教団と日蓮教団において信受された、極めて限定的なものであったと見るべきことです。
とはいえ、中世以降から今に至る日本仏教を眺める時、それが何故今のような有り様であるかを考える時、『末法灯明記』の所説を信じる信じないなど問わず、必ず触れていなければならない書であることには違いありません。法然と親鸞の浄土教や日蓮の法華思想を知るために必須の書であることは言うまでもなく、日本仏教においてその大勢を占めた戒律無視、あるいは戒律否定の思想や歴史の一端を知るためにも必ず読んでおくべき書です。
『末法灯明記』の最澄撰の真偽論争は、昭和中頃の仏教学会において盛んになされましたが、結局真偽不明ということで棚上げとなったままです。とはいえ、今これを最澄撰述という学者などよもやありはしません。そこでまた、浄土宗や真宗そして日蓮宗など、その教学の核心にこれを用いていた宗旨において、「『末法灯明記』はお祖師さまが引用された最澄撰述と云われていた書ですが、実は偽書で云云」などと平気で宣う者がいま実に多くあります。が、その言やいかに。
そのように飄々として当たり前のように云う人らは、一体自身が何処に立ち、何に基づいてそのように言うのでしょうか。大抵の場合、そんな小難しいことなどさて置き、悟りなど夢のまた夢としてうっちゃっても、坊さん稼業は十分商売としてなりたつからこれで良いのだ、という程度のことであるのでしょう。けれども、料理人は料理を作れるから料理人であり、大工は家を建てられるから大工です。医者は医学を知り、医術を為し得るから医者であります。では僧は、何故に僧であるというのでしょう。
特にその宗旨が根幹、核心としていたはずのものを「ありゃ偽書だ」と自ら放擲してなおそれに依拠した思想に基づいて「ナムナム」やり続け、「アルガママ」・「ニンゲンダモノ」と済ますのは実に奇妙で滑稽なことに思われます。
(これはいわゆる大乗非仏説を当たり前のように受け入れ、また自身も他に吹聴していながら、その大乗経典にあるホトケの所説をこそ用いて「ブッキョーデハ」であるとか「アリガタイ」と云う人々においても同様です。)
いや、このようなことを云うと、たちまち思春期の子供のようなことを言うな、青臭いことを抜かすな、と思われるかもしれません。しかし、例えば法然にしろ親鸞にしろ、また日蓮にしろ、その思想の是非はともかくも、彼らは彼らなりに苦悩し、真剣に考えぬいてそれぞれ依って立つ所を定め、その正当にして正統であろうことをそれこそ必死で証明しようとしています。
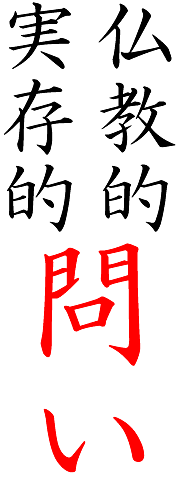
『末法灯明記』、それは僧としてあまりにも堕落し、横暴の限りを尽くしていた当時の僧に、自ら僧としての立場に正統性を失っていること、その立場を仏教として保証するものが全く欠けていること、すなわち「僧徒としての根拠がないのは非常にマズイ」という意識が強く働いていたからこそ、最澄撰として捏ち上げられたのに違いありません。
そして、当時の浄土や法華の僧らが一斉に飛びついてこれを最澄の名の元に奉じたのも、その思想やあり方を保証する根拠となるものであったからと考えられます。
このあたりのことは今の日本の僧職者らより当時の相似僧の方がはるかに「まし」と思える点です。とは言え、今の僧職者らは強訴も放火も殺人もしない点ではよほど善いでしょうが、そもそもそれは出家として当たり前の話です。何ら真っ当な根拠なく人々から死にまつわる金品を仏教の名の元に巻き上げ、一つもその本来の義務を果たさずして仏教僧を称して居直るのに『末法灯明記』の所論はまたとない、唯一のものであるでしょう。
しかしそこで、そのような僧職の立場にある人らが「『末法灯明記』は偽書だ」と平然と云うならば、詮無い人情や寺という宗教法人を私物化・公私混同して運営していくための経済事情以外に、彼らは仏教の一体何に基づいて「仏教僧である」と自称し、またそれとして存在しているのでしょうか。
貧衲覺應 記
一.本稿にて紹介する『末法灯明記』は、『傳教大師全集』第一巻所収のものを底本としている。
一.原文および訓読にては、底本にある漢字は現代通用する常用漢字に改めず、可能な限りそのまま用いている。これにはWindowsのブラウザでは表記されてもMacでは表記されないものがある。ただし、Unicode(またはUTF-8)に採用されておらず、したがってWeb上で表記出来ないものについては代替の常用漢字などを用いた。
一.現代語訳においては読解に資するよう、適宜に常用漢字に改めた。また、読解を容易にするために段落を設け、さらに原文に無い語句を挿入した場合がある。この場合、それら語句は括弧()に閉じてそれが挿入語句であることを示している。しかし、挿入した語句に訳者個人の意図が過剰に働き、読者が原意を外れて読む可能性がある。そもそも現代語訳は訳者の理解が十分でなく、あるいは無知・愚かな誤解に由って本来の意から全く外れたものとなっている可能性があるため、注意されたい。
一.現代語訳はなるべく逐語訳し、極力元の言葉をそのまま用いる方針としたが、その中には一見してその意を理解し得ないものがあるため、その場合にはその直後にその簡単な語の説明を下付き赤色の括弧内に付している(例:〈〇〇〇〉)。
一.難読あるいは特殊な読みを要する漢字を初め、今の世人が読み難いであろうものには編者の判断で適宜ルビを設けた。
一.補注は、特に説明が必要であると考えられる人名や術語などに適宜付し、脚注に列記した。
一.本論に引用される経論は判明する限り、すべて脚注に『大正新脩大蔵経』に基づいて記している。その際、例えば出典が『大正新脩大蔵経』第一巻一項上段であった場合、(T1, p.1a)と記している。
懸命なる諸兄姉にあっては、本稿筆者の愚かな誤解や無知による錯誤、あるいは誤字・脱字など些細な謬りに気づかれた際には下記宛に一報下さり、ご指摘いただければ幸甚至極。
貧道覺應(info@viveka.site)