そもそも正法律とは何でしょうか。世間では、「慈雲は正法律を説いた」という程度のことは比較的知られているものの、しかし「正法律とは何か」については全くと言って良いほど知られていません。
例えば『岩波仏教辞典』では、正法律について以下のように解説されています。
正法律 しょうぼうりつ
如来の正法に準拠する律の意.江戸時代後期,慈雲飲光によって提唱された戒律運動.直ちに如来の所説に基づくことを目指す.慈雲は河内の高貴寺(大阪府南河内郡河南町)に活躍した僧で,悉曇学でも著名.不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不綺語・不悪口・不両舌・不貪欲・不瞋恚・不邪見の〈十善戒〉を重視し,身口意の三業において〈十善〉を実践することを主張した.十善戒は大小の諸戒を統摂するものであり,かつ人間の務め行うべき根元であると位置づけ,『十善法語』『人となる道』などを著したが,それらの著作の中には神儒仏の三教一致思想が認められる.〈神下山高貴寺規定〉には「正法律とは聖教の名目にして,外道邪宗に対して仏法の尊向を表せる名なり」とある.法系的には南山四分律に属するが、重要視したものは有部律であり、ほぼ一切の経律を重視する立場を取る。
『岩波仏教辞典』岩波書店
ここでは正法律についてまず「如来の正法に準拠する律の意」などという、率直に言って見当違いの解釈が記されています。そして、十善については妥当といえるものの、むしろ本筋以外の情報が詰め込まれた、まったく具体性を欠いたものとなっています。かろうじて『高貴寺規定』の一節が最後に引用されてはいますが冒頭に頓珍漢な解釈をしているので、おそらくこの項担当の編者は理解せずこれをとりあえず示したのみのことであったのでしょう。
また「慈雲飲光によって提唱された戒律運動」とありますが、これも正確ではない。慈雲は特に「戒律運動」をせんとして正法律復興を提唱したわけではありません。そして、「法系的には南山四分律に属するが、重要視したものは有部律であり」などとありますが、これも事実誤認です。
まず、慈雲が重要視したのはあくまで『四分律』であり、南山律宗の伝統です。その上で広く諸律蔵を参照して依用していますが、中でもそれまでの南山律宗がいわば不倶戴天の敵としてほとんど顧みることが無かった義浄『南海寄帰内法伝』および根本有部律の諸典籍をくまなく参照し、特に袈裟衣をそれまでの誤ったものから修正する際に多く依拠しています。この点、従来とは異なる新しい動きではあったと言えるでしょう。いや、それはすでに栄西の昔に行われていたことでもあるのですが、いずれにせよ重要視したというのとは異なります。
結局、『岩波仏教辞典』のこの項目は、何のことだかよくわからないだけではなく、そもそも不正確です。岩波書店の仏教辞典とはいえ、項目によっては所詮この程度のもの。これでは話にならない。
ではまた他に、『密教大辞典』を参照してみましょう。そこには以下のように記されています。
ショウボウリツ 正法律
慈雲尊者飲光が唱道せし律にして、釈尊所説の正しき律法の意なり。
『密教大辞典』法蔵館
この『密教大辞典』にいたっては岩波のそれ以上に的外れな、完全な錯誤となっています。まず「慈雲尊者飲光が唱道せし律にして」とありますが、正法律は「尊者が唱道した律」などではない。そして、正しき法と律とあるならわかりますが「正しき律法」…?これは一体なんでしょうか。
『密教大辞典』は、『慈雲尊者全集』の編纂を遂げた長谷宝秀 も監修者として参加するなど戦前・戦後の名だたる碩学らによって編まれたものです。しかし、この項担当の編者が誰であったか知れませんが、その者は全く理解せずなおざりに執筆したとしか思えません。これは全く論外というべき記述です。
では中村元による『仏教語大辞典』ではどうか。
【正法律】 しょうぼうりつ
①正しい法と律。(P) satthu-sāsana(釈尊の説かれた教え。)〈『雑阿含経』一〇巻 T2. P67a: AN. III, p.297: Vinaya I, 19〉
②延享、寛政のころ、慈雲尊者によって唱道された真言律のこと。
中村元『仏教語大辞典』東京書籍
ここではまず、①に正法律という語の原意が示されていますが、その原語としてパーリ語のsatthu-sāsana(師の教え)を挙げているのは全く不適切です。vinaya(律)はどこにいったのか。挙げるならばdhamma-vinayaであるでしょうし、その用例は実際にパーリ仏典にもあります。次いで②に慈雲のそれに触れているものの、まるでそれが何かの具体的言及がありません。なにより加えて言わなければならないことは、正法律は決して「真言律」などと言われるものではないことです。それは真言宗あるいは密教に限ったものでもなかったし、慈雲が己の門流のために創作した如き、「慈雲尊者によって唱道された真言律のこと」でもなかったのだから。
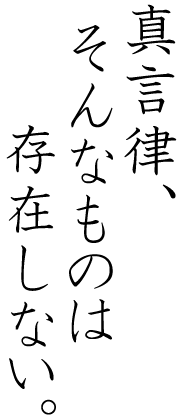
そもそも、何か名称としてはともかく、実体として「真言律」なる特殊なものなど存在しません。このことを理解している学者は今ほとんど無く、名があるのだからその実体があるのだろうと見誤って云う典型の一つとなっています。中村元も、といってもこの手の字引を実質的に作ったのは彼の研究室の研究生や大学院生らでありましょうが、これについて特に研究したわけでもなかったので、他と同じように的外れな記述をしたのでしょう。
結局、この正法律については仏教学の辞書どれ一つ取っても、何も正確なことは記述されていません。これは慈雲について、学的にも未だ正確な理解と評価がなされていないことを意味したものだと言って良い。そもそも、少なくとも二十世紀の仏教学者や史学者らは一般に、近世における仏教を「堕落した仏教」であるとして卑下し、あえて研究対象としなかった傾向が強くありましたが、それがこのような点にも現れています。
ここで参照する辞典の分野を変え、史学において正法律がどのように記述されているかも確認しておきましょう。
正法律 しょうぼうりつ
江戸時代、慈雲飲光の主唱した律の一派。正法とは元来正当な法を意味するが、仏教においても『涅槃経』『無量寿経』に「誹謗正法」「宏宣正法」、あるいは『華厳経』(貞元本)にも「菩提心諸正法」などとみえ、仏法それ自体を指す用語となった。わが国においても天平十五年(七四三)正月癸丑の勅に「宣揚正法」とみえ、鎌倉時代になると『愚管抄』『摧邪輪』をはじめ叡尊の『興正菩薩御教誡聴聞集』などにも、仏法を正法と称している例が多い。したがって正法律とは仏法に准拠する律の意とみてよい。提唱者慈雲は晩年慈雲尊者とも崇敬されたように、内典・外典をはじめ神道などにも造詣が深く、人格も高潔で、諸国を遊歴したが、延享元年(一七四四)に河内国高井田の長栄寺で親証・覚法らに四分律による具足戒を授け、翌年に正法律を唱えた。鎌倉時代の唐招提寺覚盛の遺範をつぎ、近くは野中寺慧猛らの戒律復興の影響をうけたもので、先師先匠の釈義に拘泥せず、また私意をまじえず、仏説に基づき僧尼として修行するのを正法律と名付けた。正法律は、江戸時代各寺院各宗派によってまちまちに行われていた戒律の反省から生まれたもので、一宗に限らず広く共通の戒律順守を仏教界に呼びかけたものであった。その基本は菩提心を戒体とし、十善戒を受得することによって戒律を体得し、僧尼として菩薩の行願を果たそうとしたもので、道宣の南山四分律を基本に、大乗戒律によってこれを補ったものである。僧尼の行動は戒律によることを規定し、『方服図儀』を著作して三衣の制を定めたのもそのあらわれであり、慈雲は安永五年(一七七六)に河内国高貴寺(大阪府南河内郡河南町)に遷ってから、当寺を結界し、戒壇を設けて正法律の普及につとめ、高貴寺をもって正法律の本山とした。
[参考文献]
諦濡編『正法律興復大和上光尊者伝』(『慈雲尊者全集』首巻)、慈雲『戒学要語』(同六)、同『十善法語』(同一一)、常盤大定「慈雲尊者の正法律」(『慈雲尊者会報』三)
(堀池 春峰)
『国史大辞典』吉川弘文館
堀池春峰によるこの『国史大辞典』での記述もまた不正確で所々に誤謬を含んだものとなっていますが、皮肉なことに以上に挙げた仏教系の辞典より詳しく、比較的錯誤の少ないものとなっています。
もっとも、まず先程から繰り返しているように、正法律は「律の一派」などではありません。そして、「正法律とは仏法に准拠する律の意とみてよい」などと、堀池は先に示した『岩波仏教辞典』(『国史大辞典』の数年後に出版)と同様に言っていますが前述したようにこれは誤りです。また「その基本は菩提心を戒体とし、十善戒を受得することによって戒律を体得し」ともありますが、慈雲自身はたとえば『根本僧制』にて「戒体を語するときは、法界塵沙の善法なり」として菩提心を戒体にはしていない。また慈雲は十善戒を『大智度論』の説に準じて一切戒の根本とし、また仏教に限らない古今東西に普遍の徳行としていますが、「十善戒を受得することによって戒律を体得」などという乱暴な主張はしていません。
また、「鎌倉時代の唐招提寺覚盛の遺範をつぎ」とありますが、確かに中世の戒律復興のため通受自誓受という「発明」したのは覚盛ではありますが、近世の戒律復興は覚盛の同志であった西大寺の叡尊に範をとったものであって覚盛ではありません。その両者の戒律に対する考えは似たようで異なり、覚盛がある意味「いい加減」であったのに対し、叡尊は厳格でした。同じく挙げられている野中寺の慧猛などは、直接的に西大寺と関わり、叡尊由来の密教の法脈(西大寺流・菩薩流)を受けた人であって、慈雲もまたその流れにあります。慈雲と慧猛との関係については「影響を受けた」どころでなく玄孫弟子です。したがって、この点も誤識に基づいた記述となっています。
(ただし、慈雲は十善の法脈については叡尊でなく、なぜか覚盛の系統を取っています。しかし、堀池はそれを意図してこう言ったのでなく、当時の学者は大体が同じようなものであったのでしょうけれども、中世から近世にかけての戒律の流れや動向に対する無知から単純に「覚盛の遺範をつぎ」などと記したのでしょう。)
堀池春峰は東大寺に勤めた僧職者でありまた学者であった人ですが、彼自身もよくわかっておらず特に確かめもせずなんとなく、いわゆる憶説でこのように述べたようです。
なお、特に仏教にも歴史にも限定しない辞典においては目も当てられない記述があります。
しょうぼう‐りつ 【正法律】
江戸時代、真言宗の高僧慈雲が唱えた真言律の一派。秘密三摩耶戒の精神に立ち、また梵網等の義によって十善戒を立て、これに大小経律を収めたもの。葛城山高貴寺を本山としたが、のち衰微した。
『日本国語大辞典』小学館
「秘密三摩耶戒の精神に立ち、また梵網等の義によって十善戒を立て」…、この『日本国語大辞典』の編者はその語のどれ一つとして全く理解せず、冒頭からその最後まで見事なまでにこのような杜撰な執筆をしてしまっています。そもそも、前項でも述べたように、慈雲はかつて真言宗に属したことなど一度も無かった人です。
まず、慈雲が出家した法樂寺は当時、唐招提寺や西大寺とは異なる律宗一門(一派律宗総本山)を構えていた野中寺の末寺です。そして慈雲が出た後しばらくしてから、これはおそらく野中寺が慈雲を除籍したことがきっかけであったと思われますが、中世以来、北京律を標榜し四宗兼学を旨としていた泉涌寺の末寺に転籍しています。愚考するに、それらの寺院が明治・大正期から昭和にかけての宗派再編の際、ほとんどすべて真言宗に属するものとなったことから、多くの学者ですらそう誤解しているのだと思われます。
さて、時にその原典に直接当たってもその表現があまりに冗長もしくは難解で到底理解不能という場合があります。あるいは逆に、あまりに簡潔または抽象的に過ぎてその内容が全く理解できない、ということもあるでしょう。しかし、正法律とは何かを知るには、やはり直接慈雲の著作に当たるに如くものでは無い。
そこで、慈雲は「正法律とは何か」についてどのように言っていたかを見たならば、以下のように端的に、しかもその典拠を併せて記されています。
一此正法律外。別有相似正法及僧坊。其中龍蛇混雑眞偽難辯。非經簡擇則不得共法及席
正法律と云フは世尊の宗名なり。外道の不正義邪説に対して、自ら我が正法律と称し玉ふなり。大般若経。処々正法毘奈耶と云ふ。有部諸律に多く正法律と云ふ。其ノ中一例を挙レば、阿黎沙ノ偈に、此の正法律出家云云ト是也。相似ノ正法とは、末世の弊儀人師の所立なり。瑜伽論には像似の正法と云フ。
《本文》
一.この正法律の外に、別に「相似の正法」および「(相似の)僧坊」がある。それは龍と蛇とが混雑しているようなもので、その真偽を弁別するのは困難である。(正と邪とが)選別されていないのであれば、(そのような者らとは)法および席を共にすることは出来ない。
《自注》
「正法律」とは世尊〈釈迦牟尼〉の宗名である。外道の不正義・邪説に対し、(世尊)自ら「我が正法律」と称されたものである。『大般若経』には処々に「正法毘奈耶」〈正法律に同じ。毘奈耶はvinayaの音写で律の意〉と説かれ、「有部律」〈根本説一切有部の律蔵〉やその他の律蔵には多く「正法律」と説かれている。その中の一例を挙げたならば阿黎沙の偈〈阿黎沙伽他.阿黎沙はārṣaの音写で賢者の意.阿利沙あるいは阿梨沙とも。『大智度論』では聖主と訳〉に、「この正法律出家」云云〈「正法律出家」という語は『雜阿含経』にしばしば見られるが偈文としては無い〉とあるのがそれである。「相似の正法」とは末世の弊儀、後代の人師が捏ち上げたものをいう。『瑜伽師地論』にて「像似の正法」と称されるものである〈『瑜伽師地論』に「像煮正法」が詳しく定義されている〉。
慈雲『枝末規縄』(『慈雲尊者全集』, vol.6, p.77)
ここで慈雲は「正法律とは世尊の宗名なり」と定義しており、それはすなわち「正法律とは仏教である」ことを云ったものです。そして何より、正法律という言葉自体もあくまで仏典に基づいたものであることを示しています。事実、仏陀は自らの教えを「我が正法律」と称していたと諸々の経律に伝えられています。
慈雲の言った「正法律」とは、仏典に「正法律」と仏陀が説かれていたからこそ「正法律」であった。それは決して慈雲が考案した語でも、初めて尊者が提唱したものでもない。そのようなことからすれば、「慈雲は正法律を定義した」のではなくて、その言葉通りに使用したに過ぎない。遠く釈尊の昔に説かれ、仏滅後に諸々の仏弟子らによって経律論の三蔵としてまとめられ、伝えられたものが正法律であった。そしてそのような仏陀の法と律とをこそ日本で再び宣揚するのだ、と慈雲とその一門は理解し志していた。まさにそのように解するのが正確でありましょう。これについてはまた後述します。
慈雲は「正法とは何か」について、また以下のようにも述べています。
正法とは、経律論を多く記したを云ふでない。神通あるを云うでない。光明を放つを云うでない。無碍辯舌を云ふでない。向上なるを云ふでない。唯だ佛の行はせられた通りに行ひ、佛の思惟あらせられた通りに思惟するを云ふ。佛の思惟し行はせられた通りとは、近くは八正道じゃ。八正道とは正見正思惟、正語正業、正命正精進、正念正定のハつじゃ。正見とは諸法無我等を観じ断滅の見を起さぬことじゃ。正思惟とは諸法の自相平等相を思惟して疑はぬことじゃ。正語とは口四の悪を慎み守り失命の因縁にも犯ぜぬことじゃ。正業とは身三の善を守り刀杖火水難にも犯ぜぬを云ふ。正精進とは如是の法において精進修行するを云ふ。正念とは如是の法を憶念して日夜に忘れぬを云ふ。正定とは如是の法において一心憶持決定一相なるを云ふ。是れが正道の基じゃ。委きことは次第に先輩に聞て憶念したがよい。是の中に先ず正見が第一大切な事じゃ。見處が正しからねば餘事は皆黒闇じゃ。餘事の法の如くならぬは皆見の正しからぬ故じゃ。
正法とは、経典・律蔵・論書の数々が記されたのを言うものではない。神通力〈超常的能力〉のあることを言うものではない。光明を放つこと〈不可思議な現象が生じること〉を言うのではない。無碍辯舌〈立て板に水が如くに弁舌すぐれること〉を言うのではない。向上〈他より優れていること〉を言うのではない。ただ仏陀が行われた通りに行い、仏陀が思惟せられた通りに思惟することを言う。仏陀の思惟し行われた通りとは、近くは八正道のことである。八正道とは正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定の八つである。
正見とは、諸法無我等を観じて、断滅の見〈唯物論的見解・因果応報を否定する思想〉を起さぬことである。正思惟とは、諸法の自相平等相を思惟して疑はぬことだ。正語とは、口四〈妄語・綺語・悪口・両舌〉の悪を慎み守り、命を落すようなことがあってもこれを犯さぬことである。正業とは、身三〈不殺生・不偸盗・不邪淫〉の善を守り、刀杖火水難に際しても犯さぬことを言う。正精進とは、如是の法〈仏教〉において精進修行することを言う。正念とは、如是の法を憶念して日夜に忘れぬことを言う。正定とは、如是の法において一心憶持決定一相〈心を一処に留め、集中して揺るがぬ心の状態〉たることを言う。
これらが正道の基である。詳しいことは次第に先輩に聞き、憶念したらよい。これらの中で、先ず正見が第一に大切な事である。見処〈思想・世界観〉が正しくなければ他事はすべて黒闇となる。他事が法の如くでないのすべて、見の正しくないが為である。
『慈雲尊者法語集』(『慈雲尊者全集』, vol.14. p.331)
仏法というからにはもちろん、経律論の三蔵に基づいたものでなくてはなりません。しかし、「この経典ではカクカクシカジカ説かれている」・「あの経ではああだか、この経ではこう」などといった、それはそれですこぶる重要にして不可欠のことではあるのですが、ただ学者のように衒学的解説する態度や、オウム返しに繰り返すだけ、あれやこれやと列挙するだけといった態度を、尊者は非常に嫌いました。これは臨済禅師など、最初期の禅の祖師らと共通した態度でありましょう。
三蔵に基づくといっても、ただ伝えられた内容、その書物だけ奉じて信じれば良いというのではありません。文字の羅列、言葉の蓄積など情報としてだけあるならば、その内容がいくら「正法」すなわち「正しい教え」あるいは「真理」であったとしても、その情報は確かに無上の価値を持ったものであるとして、祭壇に据えて拜むだけではまさしく宝の持ち腐れとなってしまう。そこでその真価を知るには、どうしても自ら行い、現実に自らのうちに証しなければならない。でがそのためにはどうすれば良いか。それは「唯だ佛の行はせられた通りに行ひ、佛の思惟あらせられた通りに思惟する」ことが肝要で、実際それを慈雲は自身らの立場・状況の中で可能な限り行ったのでした。
三蔵の所伝に基づき、それを行うことの中に真の正法があると、慈雲はここで述べています。
ところで現代、世間には「ゴータマは『仏教』を説かなかった」などという学者輩があります。確かに、釈迦牟尼が「我が教えは『仏教』である」だとか、「私は『仏教』を説く」などと説かれたことは無く、それは後代の人が仏陀の教えであったからそれを便宜的に「仏教」だとか「仏法」であると呼称し、我々もそれをそのまま使用しているものです。それは例えばキリスト教においても同様の事態でありましょう。
(もっとも、分別説部が伝持してきたパーリ語仏典においては、それもKhuddaka Nikāyaに限ってのことですが、仏陀ご自身が自ら語るその内容をしてbuddhavacanaであると言われています。vacanaとは話・言葉・表現の意です。現在南方においてパーリ語でいわゆる仏教というときにはBuddhavāda、あるいはBuddhavacanaという語を用いるのが一般的です。)
そして、そのような「仏教」という言葉。それがさらに世間で用いられるときには、またさらに違った様相をみせます。それは時に、いや往々にして、インドの釈迦牟尼の教えを淵源とするものではあろうけれども、しかし、もはや原型をまるで留めていないもの、仏教聖典に全くの根拠もない、もしくは合理的整合性の認められない思想や習慣をすらまとめて言うのに使われている言葉ともなっているでしょう。文化、などというすこぶる便利な言葉で、乱暴に一括りにされてしまっている場合がある。
しかし、むしろそのような意味での仏教を説く輩こそ、しかもそれが僧形で僧侶を自称する人であったのが江戸期の日本には多かったようです。いや、それは現在もまったく同様、むしろ彼らをある程度は縛っていた法度などの俗法すら明治維新を迎えて廃棄されたため、さらにひどい有り様となっているとも言えるでしょう。
思えば安土桃山から江戸初期の日本において、中世以来殺人・略奪、他領地の略取など暴虐の限りを尽くし、数多の大名・豪族らと紛争関係にあった多くの大寺院は、まず豊臣秀吉の刀狩りによって武装解除され、そして所有していた地方の豪族など思いも及ばぬほど広大な荘園・領地ほとんどが没収されていました。この秀吉の政策はまことに効果的で、実にうまいやり方であったと言う他ありません。信長の側で、秀吉は寺院勢力のおそるべきことを嫌というほど経験していた、ということがあるのでしょう。
そしてさらに、豊臣家が滅びて徳川家康の代となると、家康は秀吉の政策を継承し、それまで「仏教どこ吹く風」といった態度で傍若無人に振る舞ってきた諸大寺院にとっては非常に厳しい内容の寺家の諸法度が次々発布され、経済的にも組織のあり方についても締め付けられて、諸寺院の勢力は急速に衰退していきました。
(そんな寺院諸法度で第一に出されたのが『高野山法度』。そして寺院諸法度の制定に深く関わっていたのは臨済僧、黒衣の宰相ともいわれた以心崇伝。)
中世以来の強大な経済基盤のほとんどを失った諸寺院は、しかし替わりに徳川幕府によって、いわば為政者の地方管理組織の中に組み込まれる形で存在が許され、それによる一定の収入が安堵されるようになっていました。いわゆる寺檀制度(檀家制度)です。結果、それまでのように多くの僧侶らはおおっぴらに殺人や略奪、女犯等を行えぬようにはなったものの、その実生活は相変わらず仏教者として誠に頽廃したもので、その多くが奉じる思想、唱えられる教えもまた「世間でいわれるような意味での仏教」でした。
もちろん、ようやく乱世もしずまって天下泰平を迎えた慶長年間から江戸最初期には、慈雲はまさしくその流れにある人でありましたが、槇尾山の明忍によって戒律復興がなされ、そのような頽廃した仏教を復興せんとの動きが確かにありました。しかし、それは様々な影響を随所に与えるものではありましたが、その動き自体が大きく大勢を巻き込むまでのものとはなりませんでした。
そして、慈雲尊者が活動された江戸中期ともなると、そのような運動の流れの中にても旧来の悪い癖が現出して「戒律が派閥化・宗派化」する事態が生じています。そこでは内部での身びいき・隠蔽体質が生じるなどして、「何のための戒律か」というその意義など全く履き違え、ただ泊を付けるためだけに看板だけ律院であるとか僧坊であるとか云う輩の出現が多くあったようです。
そのような当時の様相はまさに、この言葉は慈雲もその著『十善法語』で引用しているのですが、鎌倉初期の明恵が残し盛んに江戸期に出版されていた、以下のような言葉で形容されるものと再びなっています。
若し近代の学生の云ふ様なるが実の仏法ならば、諸道の中に悪き者は、仏法にてぞ有ん。
もし近代の学生〈学僧〉らの言うようなのが本当の仏教なのだとしたら、諸々の道〈諸宗教〉の中で悪しきものは、他ならぬ仏教であるのに違いない。
高信『栂尾明恵上人遺訓(阿留辺畿夜宇和)』
明恵が言うところの「近代の学生の云ふ様なる仏教」、あるいは先程から菲才も「世間でいわれるような意味での仏教」と表現してきましたが、それを慈雲は「像似の正法」であると指摘しています。そして、その「像似の正法」という語もまた、慈雲が上掲の『枝末規縄』で「相似ノ正法とは、末世の弊儀人師の所立なり。瑜伽論には像似の正法と云フ」と述べているようにやはり仏典に基づいたものであり、それはまさに正法律に対置されたものです。
では、そのような「近代の学生の云ふ様なる仏教」すなわち「像似の正法」に対し、「正法律」という言葉はどうか。それはまさに、先に述べたことの繰り返しとなりますが、釈迦牟尼が意識的にその自らの教えと定めとをして「正法律である」と宣言されている言葉であり、それは多くの経律において認められるものです。その典籍の大小乗を問わずして。したがって、先に述べたように、慈雲の意図した意味でも「正法律とは仏教である」として何ら問題はない。
慈雲が宣揚した正法律とは、決して尊者が独創した言葉ではなく、そしてただ単に仏典にあるというだけで我田引水・牽強付会して用いた言葉でもなく、あくまで仏典に記されたままの意味のものとして用いられた言葉です。それを「復興」せんとする慈雲の、いや元を質せば弟弟子たる愚黙の、釈尊が昔に立ち戻ってその法と律とに従わんとする根本指針を表する言葉でもあります。
先に正法律の立役者として愚黙を紹介する中に示した「過去帳」に、「尊者の正法律再興は偏えに禅師の力に依るものなり」とあるのは、慈雲の正法律に対する見方をまさしく示したものです。
あるいはまた、慈雲は正法律をして以下のようにも説明しています。
一正法律之護持不有怠慢。比丘沙彌之受戒。并密教灌頂等。一切可爲如法事
正法律とは、聖教の名目にて、外道邪宗に對して佛法の尊尚を表せる名なり。若シ但に正法と云ハば、像似ノ法に對せる名にも用ゆ。瑜伽菩薩戒本に於像似法、或自信解。或隨他轉。是名第四他勝處法と。これなり。今正シく私意を雑へず、末世の弊儀によらず、人師の料簡をからず、直に金口所説を信受し、如説修行するを、正法律の護持と云フなり。
《本文》
一.正法律の護持に怠慢してはならい。比丘・沙弥の受戒、ならびに密教の灌頂など一切の行事は如法でなくてはらない。
《自注》
正法律とは、聖教〈経・律・論の三蔵〉の名目〈名称〉であって、外道邪宗に対して仏法の尊尚であることを示したものである。もし単に「正法」といった場合には「像似法」に対する称にも用いる。瑜伽の『菩薩戒本』にある「於像似法。或自信解。或隨他轉。是名第四他勝處法」、このことである。今、正しく私意を雑えず、末世の弊儀に依らず、人師の料簡をとらず、直接に金口所説を信受し、如説修行することを「正法律の護持」というのだ。
慈雲『一派真言律宗総本山神下山高貴寺規定』(『慈雲尊者全集』, vol.6. p.63)
ここで「正法律とは聖教の名目」、すなわち(仏説として経・律・論の三蔵に伝えられてきた)仏教そのものである、と宣言されています。この言葉によってより明瞭に、慈雲の言った「正法律」が決して戒律に限って言われたものではないことが明確となるでしょう。また、ここでも対置されている「像似の正法」とは、『瑜伽師地論』にいかなることか詳細にされていますが、慈雲はそれを意図していることも明白です。
上来述べてきたことの繰り返しとなりますが、正法律とは、現代の諸辞典が云うような「如来の正法に準拠する律の意」ではなく、ましてや「慈雲尊者飲光が唱道せし律にして、釈尊所説の正しき律法の意」といったものでもありません。そもそも仏教において、その法と律とどちらが重いか軽いかなどというものではない。そのいずれをも備えたものが仏教です。
いや、戒律の復興は、正法の復興を志したときに、必然的に行われるべきものであるから戒律復興は勿論行われるべきものであった。大乗小乗の別など問わず仏教の修行は戒・定・慧といい、これを三学というのですが、戒を修めることによって禅定が達成され、禅定によって智慧を得ることが出来るとする大原則があります。その故に、仏教(正法)を復興せんとするには、まず順序としてどうしても戒律を正しく実践する必要が出てきます。
事実、たとえば明堂による慈雲『戒学要語』の序文では、まさしくそのように述べられています。
戒定慧三學。猶鼎之三足不可偏廢也。然有戒而後有定慧。論其次序則戒居其首矣。
戒・定・慧の三学とは、鼎からその三足のいずれか一本でも取り去ることなど出来ないようなものである。もっとも、(仏教の修道においては)先ず戒があって後に定・慧がある。その順序を言うのであれば、戒がまずその初めとなる。
慈雲『戒学要語』序(『慈雲尊者全集』, vol.6, p.36)
このようなことから、慈雲もまたなにより先ず戒律を護持した。その故もあり、一般に正法律とは「慈雲尊者らによる戒律復興運動」の憲章と誤解されるのでしょう。けれども、はなはだクドいようですけれどもあえて繰り返し強調しますが、正法律とは「正しい法と律」であり、慈雲が云っているように「正法律と云フは世尊の宗名」・「正法律とは聖教の名目」です。それは「末世の弊儀人師の所立」を雑えぬものであり、また「正シく私意を雑へず、末世の弊儀によらず、人師の料簡をからず、直に金口所説を信受」すべきもの。後代の祖師と言われる人々の解釈にのみ依存せず偏向しない、三蔵所伝の仏陀の教えのことです。
そのような正法律を如何様に日本の近世において現実に行うべきかの大原則が記された最初のものが『根本僧制』です。『根本僧制』は、慈雲のその後の人生における活動がいかなる精神に貫かれてなされたのかを知るに必ず読まれるべき書であり、また現代日本において正法律を求める人が再び現れた時には、近世における稀有なる先師の蹤として甚だ価値ある書となるでしょう。
貧道覺應 稽首和南