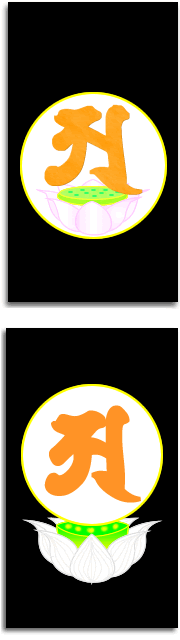
阿字観の修習に際しては一般に、それが絶対に必要ということは実は無いのですが、右に示したような図が書かれた軸が用いられます。
瑜伽の修習において、なんらか一つの図像・図形などを対象としてこれを観念・集中すること、それは一般に「止〈śamatha. 奢摩他〉」の修習とされます。また、そのように修習について何か図像を用い、さらにその色形に様々な意味付けをすることは密教に始まるものでも独自のものでもなく、部派仏教などにおいても行われてきたことです。
たとえば、三、四世紀頃の南印度における分別説部の大徳、優波底沙〈Upatissa〉による典籍『解脱道論』には、瑜伽の修習法の一つとして円形・方形・三角形など様々な形状の図像・曼荼羅〈密教におけるそれとは異なる〉を対象とすべきことが説かれています。ただし、密教における様々な瑜伽法で用いられる図像は、部派におけるそれよりも象徴化・意義付けが複雑かつ多様化しており、それはここで講述している阿字観についても同様です。
したがって、阿字観が図像を用いるものであるからと言って、それをただちに「奢摩他の修習である」と言うことは出来ません。なんとなれば、上に述べたような阿字の意義を知見することは、すなわち観〈vipaśyanā. 毘鉢舎那〉の修習の領域に属するものとなるためです。実際、阿字観を修する中でその始終、阿字の図像を凝視するなどということは無く、それを文字通り見つめるのは最初のみに過ぎません。いつまでもこれを凝視し続けるべきものではない。
実は、もちろん阿字を含めた何か梵字を対象とする修習法について、それを「止観としてどのように理解すべき」かという問題意識は、(これはむしろ「当然のことながら」というべきことでありますが)空海在世当時から持たれていました。
その回答を極めて簡潔に示しているのが、空海の高弟の一人であった真済が遺した『高雄口訣』です。
初觀字相者是止也。觀字義者是觀也。是名曰止觀倶行也。
初めに字相〈その文字の形〉を観じることは「止」である。その字義〈その文字が示す意味〉を観じることは「観」である。これを名付けて「止観倶行」という。
真済『高雄口訣』止観(T78, p.36a)
(念の為述べておきますが、支那や日本で「観じる」と表現することは、必ずしも「毘鉢舎那〈vipaśyanā. 観〉を行じること」を意味しません。しばしば単に「修習の対象とすること」が意図され、事実ここではそのような意味で用いられています。なお、「観法」という語についても同様で、それは特に「観の修習」を意味せず、広く修禅の法を意味する語です。)
『高雄口訣』とは、真済が空海から直接密教の瑜伽法や法具等々についての意義を説き明かされていた内容〈口訣〉を、彼自信が書き留めて纏めていたものです。真済が空海在世時から没後に至るまで、長らく京都は高雄山神護寺を中心として活動していたことから、『高雄口訣』といいます。特に今示した箇所は、真済が空海の最晩年にかかる天長九年二月十一日〈832〉の夜に聞いたことであったと記されています。
いずれにせよ、以上のように、密教における梵字(ひいては三昧耶形などの形像)を対象とした修習法についても、空海自身やその弟子もまた、止観という枠組みでいかに捉えるべきかという問題意識を持っていたことが明瞭でありましょう。なんであれ、それが経論に基づいた正統のものであるならば、密教をもちろん含めた仏教の修習は止観です。
さて、阿字観に用いる図像、それは白い円形の中に蓮華が描かれ、その上に阿字が載っているという形態で比較的単純なものです。しかし、いま挙げた『高雄口訣』にも関わることですが、やはりそのそれぞれが仏教の教義を、といっても特に大乗のものですが、象徴的に表現したものとなっています。そのようなことから、阿字観を修習せんとする者は、先に示した阿字が象徴する本不生の意義など事前にそれらを十分に学習・理解している必要があります。でなければ、仏教では種々様々なる修習法・瑜伽法が説かれている中で、特に阿字観を行ずるその意味も利益も全く無い。
いや、そもそも仏教における修習あるいは修定、いわゆる瞑想というものが、いかなるものであってどのような目的を持つものであるのかを知らなければならない。空海の言葉には以下のようなものがあります。
医王之目觸途皆藥。解寶之人礦石見寶。知與不知何誰罪過。
優れた医師の目には道の(傍に生える様々な草木)全てが薬として映り、宝石に詳しい人には(大地に転がる)鉱石を見れば宝となる。(事物の真価を)知ると知らないとでは、一体誰の罪過となるであろうか。
空海『般若心経秘鍵』(弘全, Vol.3, p.11)
何も知らない者に、それと伝えないまま希少な薬草を渡し、あるいはうちに金剛石〈ダイヤモンド〉を含む鉱石を与えたところで意味はなく、与えられた者からすればそれらはただのゴミ・ガラクタであってたちまち捨てられてしまうでしょう。
では、阿字観にて用いられる図像のそれぞれの意味とは何か。何故に白い円形が描かれ、また先に述べた本不生を意味する阿字が、蓮華の上に描かれるのか。その意義を示す典拠の一つ、それが『金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論』いわゆる『菩提心論』です。
諸佛大悲。以善巧智。説此甚深祕密瑜伽。令修行者。於内心中。觀日月輪。由作此觀。照見本心。湛然清淨。猶如滿月光遍虚空無所分別。亦名覺了。亦名淨法界。亦名實相般若波羅蜜海。能含種種無量珍寶三摩地猶如滿月潔白分明。何者。爲一切有情。悉含普賢之心。我見自心。形如月輪。何故以月輪爲喩。謂滿月圓明體。則與菩提心相類。凡月輪有一十六分。喩瑜伽中金剛薩埵至金剛拳有十六大菩薩者。《中略》
又摩訶般若經中。内空至無性自性空。亦有十六義。一切有情於心質中。有一分淨性。衆行皆備。其體極微妙。皎然明白。乃至輪迴六趣。亦不變易。如月十六分之一。凡月其一分明相。若當合宿之際。但爲日光。奪其明性。所以不現。後起月初。日日漸加。至十五日圓滿無礙。所以觀行者。初以阿字發起本心中分明。只漸令潔白分明。證無生智。夫阿字者。一切法本不生義
准毘盧遮那經疏釋阿字。具有五義。一者阿字短聲是菩提心。二阿字引聲是菩提行。三暗字長聲是證菩提義四惡字短聲是般涅槃義。五惡字引聲是具足方便智義。又將阿字。配解法華經中開示悟入四字也。開字者卽開佛知見。雙開菩提涅槃如初阿字。是菩提心義也。示字者。示佛知見。如第二阿字。是菩提行義也。悟字者。悟佛知見。如第三暗字。是證菩提義也。入字者。入佛知見。如第四惡字。是般涅槃義。總而言之。具足成就。第五惡字。是方便善巧智圓滿義也
諸仏は大悲により、善巧智を以て、この甚深なる祕密瑜伽を説かれ、修行者の内心の中にて、日月輪を観想させる。この観想を行じることによって本心を照見するに、湛然として清浄なること、あたかも満月の光が虚空に遍じて分別することが出来ないようなものである。これをまた無覚了と名づけ、また浄法界と名づけ、また実相般若波羅蜜海と名づける。能く種種無量の珍宝三摩地を含むこと、あたかも満月の潔白にして分明なようである。何故ならば、一切有情は悉く「普賢心」を包含しているからである。我が自心を見るに、その形は月輪のようである。何故に月輪をもってその喩えとするかと言えば、満月の円明なる体とは、則ち菩提心と相類するためである。凡そ月輪には十六分ある。それをまた瑜伽の中の、金剛薩埵から金剛拳に至るまでの十六大菩薩〈『金剛頂経』所説の大日如来以外の四仏を囲繞する菩薩〉があることに喩える。《中略》
また『大般若経』の中に、内空より無性自性空に至るまで、また十六義がある。一切有情〈生きとし生けるもの〉はその心質の中に於いて、一分〈若干〉の浄性があって(その徳によって生来的に、菩提を得るための)諸々の行をすべて備えている。その体は極めて微妙であって、皎然として明白である。そしてそれは、(今生を終えて)六趣に輪廻したとしても変易することはない。それはまるで月の十六分の一のようなものである。凡そ月のその一分の明相は、もし合宿〈朔日〉の際に当たったならば、日光によってその明性を奪われるため、(月の姿を)現わすことが無い。後に起つ月の初めから、日日漸く加していって十五日に至ると円満無礙(の満月)となる。そのようなことから、観行者は、初めは阿字を以て本心の中に一分の明を発起して、ただ漸く潔白分明とならしめ、無生智を証する。
そもそも阿字とは、一切法の本不生なることを意味する。『大日経』の疏〈『大日経義釈』〉の説に准じたならば、阿字を解釈するに具さに五つの義があるという。一には阿字短声〈〉、これは菩提心。二には阿字引声〈
〉、これは菩提行。三には暗字長声〈
〉、これは証菩提の義。四には悪字短声〈
〉、これは般涅槃の義。五には悪字引声〈
〉、これは具足方便智の義である。
また、阿字をもって『法華経』の中の「開示悟入」の四字に配当して解釈する。「開」の字は仏知見を開く。すなわち並びに菩提涅槃を開くのである、初めの阿字〈〉のように。これが菩提心の義である。「示」の字は仏知見を示す、第二の阿字〈
〉のように。これが菩提行の義である。「悟」の字は仏知見を悟る、第三の暗字〈
〉のように。これが証菩提の義である。「入」の字は仏知見に入る、第四の悪字〈
〉のように。これが般涅槃の義である。総じてこれを言えば具足成就であって、第五の悪字〈
〉である。これが方便善巧智円満の義である。
不空訳『金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論』(T32, p.574a-b)
『菩提心論』とは、伝説に依れば龍猛菩薩が著したとされるもので、空海が最も重要なるものであって真言宗の後学の徒は須らく学習すべしとした典籍の一つです。実際、日本における密教を理解するのに『菩提心論』を読まず、等閑視することなど決してありえない、とまで言えるものとなっています。
もっとも、龍樹著とするには数々の不審点があり、今示した一節でも善無畏三蔵および一行禅師が逝去して以降に成立した『大日経義釈』の説が引かれ、また『法華経』の「開示悟入」に阿字の諸義を配当するなどといった極めて支那的解釈が説かれているため、特に日本の天台宗からは平安の昔以来、龍樹作ではなく不空が支那で著したものであろうと見られています。そしてその見方はおそらく正しいものです。不空は印度出身であり、その師たる金剛智〈Vajrabodhi〉も印度僧であったとは言うものの、しかし幼少の頃から支那で暮らし育ったのであって、印度よりもむしろ支那仏教に非常に通達していた不空によってこそ、『菩提心論』は著されたものであろうとの見方です。
参考までに併せて挙げはしましたが、『菩提心論』における (a)・
(a)・ (ā)・
(ā)・ (aṃ)・
(aṃ)・ (aḥ)・
(aḥ)・ (āḥ)という阿字および阿字を元とする四字の義を述べ、またそれらを『法華経』の「開示悟入」の四字に配当する等といった(『菩提心論』が印度撰述ならば、決してありえる筈のない)説は、阿字観には直接関係が無く、今は特に気に留める必要もありません。
(āḥ)という阿字および阿字を元とする四字の義を述べ、またそれらを『法華経』の「開示悟入」の四字に配当する等といった(『菩提心論』が印度撰述ならば、決してありえる筈のない)説は、阿字観には直接関係が無く、今は特に気に留める必要もありません。
さて、以上示した『菩提心論』においてはまず、心(の本性)は満月のようなものであること、また満月の姿が菩提心に相似たものであるとされます。そして満月には十六分があって、それはまた『金剛頂経』系の密教にて説かれる十六大菩薩に喩えられること、さらには『大般若経』などにて説かれる「十六空」に比せられるものである、とされます。もっとも、そのように満月を十六大菩薩や十六空に比する典籍があるからといって、それで舞い上がってしまってはいけない。それはただ、いわばその位置づけのためやその背景にあるものとしての名目として言われているだけであって、実際の阿字観の修習に関するものではない。いずれにせよ、阿字観にて用いられる図像の円形は満月を模ったものであって、それは吾人それぞれの浄菩提心の象徴とされます。
そもそも浄菩提心、菩提心とは何でしょうか。密教においていわれる菩提心とは、一般的な菩提心の意とされる「悟りを求める心」などといったものではなく、特に「無自性空なる心の実相」を示したものです。ここを抑えていなければ密教を理解することは出来ません。
祕密主心不住眼界。不住耳鼻舌身意界。非見非顯現。何以故。虚空相心。離諸分別無分別。所以者何。性同虚空即同於心。性同於心即同菩提。如是祕密主。心虚空界菩提三種無二。
秘密主〈金剛薩埵〉よ、心は眼界になく、耳・鼻・舌・身・意界にもない。見えるものではなく、現れるものでもないのだ。なんとなれば、心は虚空のようなものであって、諸々の分別・無分別から離れているのだから。その故は何かと言えば、その本性が虚空と同様であれば、それは心と同じであり、その本性が心と同様であれば、それは菩提と同じであるから。そのように、秘密主よ、心と虚空界と菩提との三種は別々のものではない。
『大毘盧遮那成仏神変加持経』巻一 入真言門住心品第一(T18, p.1b-c)
従来の密教学者や僧職の人々には、上に示したような諸典籍の説を、(文献学的にはそのようにしなければならないという場合もあるでしょうけれども、)それぞれ明確に統合すること無く、全く別個のものとして理解・説明する傾向があったように思われます。しかし、それでは全然いけない。もちろんそれらは明瞭につながったものであって、それぞれ全く一つの方向を向いて同じことを言わんとしたものです。散乱した点をつなげて線としてついに一箇の図とすることもなく、ただ点を点として表現するだけに留めたならば、その全体を理解することなど出来ません。
現代における文献学としての密教学にてそうしているように、点ばかりあれこれいじくってどうしようというのでしょうか。点をどれほど積み重ねてみても点は点でしかない。
今示した『大日経』における、「なんとなれば、その本性が虚空と同様であればそれは心と同じであり、その本性が心と同様であれば、それは菩提と同じであるから。そのように、秘密主よ、心と虚空界と菩提との三種は別々のものではない」という一節。そして、『大日経疏』にある一節であって空海もまた『吽字義』において引いた、「もし本不生際を見る者は、実の如く自心を知る。実の如く自心を知るとは即ち、それが一切智智である」という一節。さらに、『菩提心論』の「本心を照見するに、湛然として清浄なること、あたかも満月の光が虚空に遍じて分別することが出来ないようなものである。《中略》 我が自心を見るに、その形は月輪のようである。何故に月輪をもってその喩えとするかと言えば、満月の円明なる体とは、則ち菩提心と相類するためである」という一節。これらは全て一つのことを示しています。
それは、心とは無自性空なるものであること、本不生なるものであることです。繰り返しますが、ここでいわれる菩提心とは、そのような本不生なる心の正体のこと。そしてそれが、いわゆる自性清浄心〈prakṛti-pariśuddha-citta〉です。また心が本不生であることを真に知ることが菩提であり、それが『大日経』に説かれる「如実知自心」です。
さて、阿字と月輪とがそのような意味内容の真理の象徴であるとして、ではなぜさらに紅蓮華でも青蓮華でもない「白蓮華」が描かれるのか。白蓮華は何を象徴したものであるのか。その答えの一例は、『大日経疏』における以下の一節にあります。
内心妙白蓮者。此是衆生本心。妙法芬陀利花祕密摽幟。花臺八葉。圓滿均等如正開敷之形。此蓮花臺是實相自然智慧。蓮花葉是大悲方便也。
内心の妙白蓮とは、衆生の本心の妙法なる芬陀利花〈puṇḍarīka. 白蓮華〉、祕密の摽幟〈象徴〉である。花臺・八葉(の形状)は、円満均等にして正しく開敷している形である。この蓮花臺は実相、自然の智慧(の象徴)であり、蓮花葉は大悲方便(の象徴)である。
一行記『大毘盧遮那成仏経疏』巻五(T39, p.631c)
このように『大日経疏』では、といってもこれは特に大悲胎蔵生曼荼羅の中台八葉院についての所説ではあるのですが、白蓮華の花臺〈蓮のうてな〉は実相・自然智の象徴であるとされます。そしてその実相・自然智とは結局、本不生・一切智智の換言です。
そのようなことからもまた、『阿字観用心口訣』では、いま挙げた『大日経疏』の一節を引用しつつ、なぜ阿字観において用いられる形像に蓮華が描かれるのかを、以下のように述べています。
如此諸法本來不生不滅義顯教盛談之。故此不生不滅之名言不密教不共談。然今密教規模者。所不及凡夫見聞覺知。不生不滅體直顯種子三摩耶形令知見之令修之。是顯教都所不知也。所言本不生體者。種子字三形八葉蓮花也。《中略》
内心妙白蓮者。此是衆生本心也。妙法芬陀利華者心也。此心蓮可觀也。其觀想樣心中可觀有八葉蓮花。蓮花形世間如蓮花形。唯此蓮花計可觀也。又蓮花者
心是也。
心住此蓮花。此二心暫時不離故蓮華上可觀月輪。月輪者
心也。
心形實如月輪形也。月輪形圓形事如常水精珠等。又蓮花種子
字也。故月輪中可觀
字。
このように、諸法が本来「不生不滅」であることは、顕教でも盛んに論じられていることである。よって不生不滅という名言は、密教において独自に語られるものではない。しかしながら今、密教が語るところのそれは、凡夫〈prithagjana. 凡庸の人〉の見聞覚知が及ぶものではない。「不生不滅」の本質を直に種字〈字による象徴〉・三摩耶形 〈形像による象徴〉によって表し、(密教行者に)知見させ、実体験させるものである。これは顕教のうちいずれの教えにも説かれていないことである。いま言うところの本不生の本体とは、種字が字であり、三摩耶形は八葉の蓮華である。 《中略》
「内心の妙白蓮」とは、衆生の本心である。妙法芬陀利華とは、心〈誤字。梵字はhṛtaとなっているが正しくはhṛda. 心臓〉である。そのような心蓮を観じなければならない。それを観想する際には、「心中に八葉の蓮華がある」と観ぜよ。蓮華の形は世間の蓮花の形と同様である。ただこの蓮花ばかりを観ぜよ。また、蓮花とは
心〈誤字。梵字はsitaとなっているが正しくはcitta. 心・意識〉である。
心とはその蓮花に住するもの。これらの(心臓と意識との)「二つの心」は、一瞬足りとも離れない不可分のものであることから、蓮華の上に月輪を観想するべきである。
月輪とは心である。
心の形は、まったく月輪の形に同じである。月輪の形が円形であることは、水晶の珠などのような(平面の円ではなくて球形の)ものである。また、蓮華の種字は
字である。このことから、月輪の中に
字を観想すべきである。
伝:空海述 実恵筆『阿字観用心口訣』
ここでは阿字の下に描かれている蓮華は心臓の象徴ともされ、また月輪は意識の象徴ともされます。そしてそれら、いわば物理的な心臓と精神的な意識という「二つの心」が不可分であることをもその理由として、蓮華の上に月輪を観想すべきであると述べられています。
そこで、では何を根拠に心臓と心意識とが不可分であるなどと言われるのか。それは、小乗諸部派が構築した教義体系である阿毘達磨[あびだるま]において、「心臓とは意識の座である」とされるのを受けてのことです。現代の大脳生理学が、心とは頭蓋骨に収まっている大脳の機能に過ぎないであろうとしているのに対し、仏教では、心とは単なる脳の機能などではない、心臓に坐するものと見做しているためです。
さて、上に二種の阿字観に用いられる図を示しましたが、その二種の図の違いは、蓮華が月輪の中に描かれているか下に描かれているかにあります。では、何故そのような違いがあるかと言えば、その観相の仕方について根拠とする典籍を『大日経』・『大日経疏』とするか『金剛頂経』あるいはその系統の経軌とするかに依ります。今示した『阿字観用心口訣』の一節では、明らかに『大日経疏』の所説に依拠した月輪の観相の仕方を取り、それに基づいた阿字観の仕方が述べられています。
ところで、今一般に阿字観とは、阿字と月輪と蓮華との三つの要素で構成される、それら全ての組み合わせを観想することが必須のものとされています。しかしながら、実は必ずしもそうではない、ということが『阿字観用心口訣』にて云われています。
今此字蓮花月輪三中。若蓮花計觀。若蓮花月輪觀。若蓮花
字可觀。可任行者意也。
今これら字・蓮華・月輪の三つにおいて、あるいは蓮華だけを観想し、あるいは蓮華と月輪とを観想し、あるいは蓮華と
字とを観想しても良い。行者の意に任せるべきことである。
伝:空海述 実恵筆『阿字観用心口訣』
このように言われるのは、上に示してきたように、 字・月輪・蓮華のいずれもが、結局全く同じことを意味する象徴であることに尽きます。
字・月輪・蓮華のいずれもが、結局全く同じことを意味する象徴であることに尽きます。
そもそも、いわゆる阿字観を含めた密教の瑜伽法とは、その真理を自ずから全く把握することを目指したものに過ぎません。その真理とは、この世のあらゆる存在・事象が縁起せる無常なるものであること、無自性空なるものであること、すなわち本不生であることです。そしてそれは、仏教が、大乗が全く悟るべきとして目指すものです。
したがって、阿字観とは、 字・月輪・蓮華の全てを観想し、そのそれぞれが示す意義を逐一観察する必要は必ずしも無いということになる。事実、この『阿字観用心口訣』に「可任行者意也(行者の意に任せるべきことである)」と明白に言われています。すなわち、何であれ諸法の本不生や縁起生を観る修習であれば、それは広義の阿字観となります。
字・月輪・蓮華の全てを観想し、そのそれぞれが示す意義を逐一観察する必要は必ずしも無いということになる。事実、この『阿字観用心口訣』に「可任行者意也(行者の意に任せるべきことである)」と明白に言われています。すなわち、何であれ諸法の本不生や縁起生を観る修習であれば、それは広義の阿字観となります。
密教において特徴的・独自であると言えるのは、真理を悟るため様々に象徴を駆使するその修習法、すなわち方法論においてのことに過ぎません。一般に密教の瑜伽法とは、厳密に経軌と正統な阿闍梨の所伝に則って修めなければならないとされるものではあります。が、特に狭義での阿字観においては、そしてこれはその嚆矢である『阿字観用心口訣』の所説に拠れば、厳密に規定されたものでは全くありません。
そのようなことからも、一般に阿字観とは「初心の人であっても修しやすいものである」などと言われるのかもしれません。いや、そもそもそのような言は、『阿字観用心口訣』にかくあることによります。
入此觀門行者雖初心生死輪迴永絶。行住坐臥無離皆是阿字觀也。易行易修而速疾頓悟也。若既座逹必非半跏法界定印行住坐臥悉字事思。
この観門に入る行者は、たとい初心であったとしても生死輪廻を絶ち、行住坐臥の常時にこの阿字観を離れる事はない。行ない易く修し易く、速疾に頓悟するものである。もしすでに座(して阿字観を修すること)に熟達したならば、必ずしも半跏坐して法界定印など結ばずとも、行住坐臥の常日頃から字を思うようになるであろう。
伝:空海述 実恵筆『阿字観用心口訣』
しかし、これは繰り返しの言とはなりますが、そもそも阿字に象徴される奥旨すなわち本不生の示す意味・語義を、表面上ではあってもまずは論理的に知っておかなければ、いわゆる阿字観を修する必然性も価値もありません。