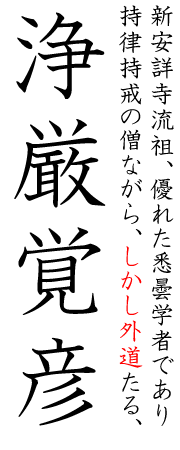
江戸時代前期、真言宗と他宗との別異、すなわちその優位性・独自性を主張せんとするがあまり、阿字諸法本不生の意義をも独自に解釈し、さらに極端に敷衍して「釈迦の説いた縁起は虚妄」などとまで宣わった真言僧がありました。浄厳覚彦です。
「釈迦の説いた縁起は虚妄」、それは仏教者から発せられたものとは到底思われぬ、まったく呆れてものも言えなくなるほどの主張です。
浄厳とは、もと高野山の学侶であった人です。学侶とは、高野山には中世以来、学侶方・行人方・聖方という三種の僧の立場・あり方があったうちの一つです。学道を専らとし、経論や修法についての知識を蓄え、伝法会や論議という法会の中で、その見解を他の学侶と戦わせて切磋琢磨する学問僧を、学侶と言います。
もっとも、元来高野山にはいわば学侶しか存在していませんでした。しかし、平安後期には学侶の下に仕えて諸堂の荘厳や法会・行事の裏方など雑事を行う行人という立場が、そして鎌倉中期には日本各地を巡って勧進を募る半僧半俗の聖(非事吏)という立場が生じ、それが定着しています。
いわば本来的な僧侶である学侶、そして学侶に仕え高野山諸堂の維持・経営を司る行人。さらに、高野山に属してほとんど嘘八百である弘法大師信仰や浄土信仰(時宗)などを各地に広めながら勧進を行う、実際としては俗人の聖とで、それぞれの立場とその役割を超えず「高野山を維持管理する」という目的のもと協力関係にあったようです。しかし、時代とともに行人は武装集団化(常時帯刀する僧兵化)していき、その勢力はいや増して学侶に匹敵。中世末期から近世初頭に入ったとき、その互いの立場の違いによる対立は決定的深刻なものとなって、その諍いが幕府の仲介に由って収束するまで一世紀近い時を要しています。
閑話休題。さて、そのような高野山の学侶の一人であった浄厳は、しかし、その優秀さからかその性格からか、ある他の学侶の深い恨みを買い、高野山の子院の一つ釈迦文院にて密教の修法中、突如として襲われ刺殺されかけています。瀕死の重傷を負った浄厳は高野山を降り、しばらく河内の実家に滞在して養生していたものの、最終的に関東に行った人です(その後、生家に建てられたのが河内延命寺で現存)。
やがて、江戸初期の江戸にて真言宗の戒律復興を図った最初の人となり、またさかんに各地の人々に授戒や結縁潅頂を行って非常に多くの人を教化しています。また、将軍綱吉ならびに母公の帰依を受け、湯島に霊雲寺を建立。
彼の行業のうち特筆すべきは、高野山南院に相伝されていた真言宗の事相(小野流)における一流派、安詳寺流を再編集し、のちに新安詳寺流〈新安流〉と呼ばれる一流を興したことです。もっとも、浄厳自身には、新しい流派を自ら立てたという意識は微塵もなかったようです。彼からすると経典や儀軌など確かな典拠に基づいて、古のあるべき姿に安詳寺流を古のあるべき姿に「修正しただけ」というほどのものでした。
浄厳によって復古された安詳寺流は、後に「御簾流みすりゅう」と称されるようになっています。それは、浄厳によって再編された安祥寺流が、たとえば御簾の中にある者からは外をよく見通せるけれども外からは御簾の中を伺い知ることは出来ないのと同様に、安詳寺流からは広く他の諸流を見渡せることが出来るものの他流から安詳寺流を窺い知ることは出来ない幽遠なるものである、という最大の賛辞でした。
その故に、浄厳は、現代における真言宗でも大変著名な人で、「事相家」などといわれる僧職の人々から特に尊敬、いや、崇敬されています。そしてまた、現代の(特に古義)真言宗の僧職者の多くが、意識的・無意識的に浄厳の思想を継承しており、彼と似たようなことを説法と称して触れ回っています。、
しかしながら、浄厳は高野山の学侶であったとはいうものの、教相面で顕教の理解が全くお粗末であり、あるいは密教に関して独善的に過ぎたものとなっており、彼の著作に見られる論理も全く見当違いの方向へ飛躍してしまっていました。そして浄厳を信奉する現代の事相家といわれる人々の中には、それを理解している者も理解し得るだけの知見・能力を持った者などほとんど絶無と言って良い。
実は、浄厳の思想内容がいかなるものであったかは学問的にもほとんど知られておらず、これはそもそも近世の仏教が仏教学会から軽んじられきたためであるようにも思いますが、今なお密教学者や史学者でそれを研究しようとする者は非常に稀です。
しかし、浄厳の思想がいかに異常であったかは当時すでに知られており、同時代、南都諸大寺や京都叡山などに遊学するなど広く顕教を修めたうえで密教に深く通じた近世稀代の大学僧であった智積院の泊如運敞〈1614-1693〉は、浄厳を「外道」とまで呼んで非常に激しく非難しています。
浄厳はまた事相だけではなく、悉曇についても優れた業績を残した人でもありました。特に浄厳による『悉曇三密鈔』は、同時代の悉曇に関する書物の中では白眉というべきものです。もっとも、より後代に出た、日本における悉曇学の頂点に達した人である慈雲尊者などは、浄厳の悉曇に関する業績に対して一定の敬意を示しつつも、しかしその理解や知識が浅く、誤り多いものであると批判しています。
実は、浄厳が『悉曇三密鈔』を著して出版するに際し、運敞は浄厳の学識とその内容を称える序文を寄せていました。運敞は当初、浄厳を若いながらも当代のすぐれた学僧として認知していたのです。しかしながら、浄厳が特に阿字に対する自身の解釈を開陳しだすや、そのあまりの非仏教なる見解に驚いた運敞は猛烈な批判を開始。これに対し、浄厳は運敞を「老人」として自身の見解があくまで正しいと反論し、激しい応酬が繰り返される一大論戦となっています。
そこで現存する浄厳の著作を読めば、確かに仏教者として驚きを通り越して呆れてしまうようなこと、あまりに飛躍した持論を浄厳は書き散らしており、その見解は外道と非難されて至極当然と言えるものです。そして、そのような彼の「とんでも仏教理解」は、彼に依って編纂された安祥寺流の聖教次第の中にても随所に開陳されており、特に「字輪観」という密教の行法の中でもっとも重要な箇所にても遺憾なく発揮されています。
近世初期はその時流として、朱子学に対して山鹿素行が古学を、そして伊藤仁斎が古義学、荻生徂徠が古文辞学を起こし、また後代の無根拠で杜撰な説を廃して記紀に直に基づいて理解すべしとした国学が本居宣長によって隆盛するなど、様々な復古主義的態度を取った優れた学者が現れていました。浄厳もそのような時流に影響され、密教の修法に関しては、儀軌に忠実に基づいて再編せんとする復古的態度を同じく取った点では高く評価すべき人です。
繰り返し強調しておきますが、彼の顕教に対する理解は復古的などでは全然なく、そこかしこで我田引水や牽強付会を繰り返す惨憺たるものです。そして、それは密教者として致命的な点でした。結局、密教の作法などを儀軌に忠実なものにしたとしても、彼が信条とし前提とした仏教・密教理解が極端に誤っていたことから、浄厳の事相面での業績はすべて台無しであった、と断じて全く過言ありません。
また浄厳は、江戸前期の真言宗における「吾が仏尊し」精神を遺憾なく発揮した、宗旨がたまりの典型です。むしろ自身の密教を特別視しようとする態度の故に、いきおい真言宗についてひどく独善的な理解をしたようです。結果としてその見解がまるきり外道そのものとなっていることから、浄厳は範とすべき人などでは決してありません。
浄厳のごとき仏教徒の仮面をかぶった外道の人、いわば八世紀の印度に現れ「仮面仏教徒」とも言われた印度教のŚaṅkaraの逆を言ったような者になってしまわないためにも、密教はもとより阿字観を行ぜんとする人もまた、顕教の確かな理解が不可欠です。

繰り返しますが、密教は顕教の理解なしに触れて良いようなものではなく、顕教の前提なくしては到底理解しえないものです。阿字のなんたるかを理解せずして行うことに意味など全く無い。そのように修習の前提とされる何事かを理解しておかなければならないことは、何も阿字観に限ったことではなく、仏教の瞑想すなわち止観の根本的修習法である安般念などを修するに際しても全く同様です。
それは例えば、非常に高い高い難所たる山に登ろうとするには、すでにその登頂に成功した先達にその行程とその状況とを聞いて地図を得てその情報を自らじっくりと考え、またコンパスを準備し、そうして初めて実際に登攀に赴く、というようなもの。
そのように段階を踏んで実際の修習に望むことを仏教では、三慧と言います。
もしなんら行くべき道を知らず、ただ闇雲に山頂を目指すようでは、たちまち麓の森などで迷うばかりとなってしまうでしょう。この場合、とにかく理屈はどうあれやってみれば良いのだ、ただひたすら歩いていたならばいつかは目的地に着くであろう、ということは決してありません。そのようにして山に入った愚か者は、たちまち(必然的)遭難者となって山岳救助隊のご厄介となり、ついには世間から白眼視されるのと同じような結果を生み出すでしょう。瞑想して頭をますます違えてしまったようなのや、突き抜けた増上慢の輩となるようなのは、それこそ世間にはゴロゴロ存在します。
しかしながら、真言門徒の中には、先に触れた浄厳と同じように、ただちに「真言宗では何々」・「密教では云々」と、前提としての顕教を踏まえず理解せず、にも関わらず密教の顕教に比しての優位性・独自性を牽強付会の説でもって述べようとし、その言動がそのまま外道になっている者が少なからず見られます。
この『阿字観用心口訣』という書自体においてそう説いているため、このように云うのことは甚だ矛盾となりますが、一部の人が巷間盛んに宣伝する「初心の者でも容易に修し得、達しやすい」などと言えるようなものでもありません。本書にそう書いているとはいえ、そのような言は自ら達してこそ放ち得るものでしょう。そしてまた、自らが阿字観を真剣に行なってみたならば、そのような言が文字通りのものでないことを容易く、自ずから知ることになる。
いや、普段の生活を離れ、閑処に座って瞑想もどきのことを数十分でも体験することにより、多少ながらも我が心を平安とする功徳を体感することはあるでしょう。けれども、それは別に阿字観を修めたからこそのことではありません。その程度のことであれば、わざわざ仰々しく阿字の描かれた軸など用意する必要はなく、しかつめらしく座禅を組む必要もない。あるいは小鳥さえずる山林にじっと佇み、木々や鳥や虫たちの音に耳を澄ませるほうがよっぽど精神にも健康にも良いでしょう。形ばかり瞑想の真似事をしてみたとしても、それは時間の無駄とすら言える。
ところで、阿字観について述べようとする人がほとんど必ずと言っていいほど口にする、以下のような歌があります。
阿字の子が 阿字の古里立ちいでて
また立ち帰る 阿字の古里
この歌は、空海によって作られたものだ、その愛弟子智泉が早逝した際に詠まれたものだ、などと巷間伝説されています。しかし、それは事実などでは到底無い、実に拙い伝説に過ぎません。
この歌は歌であるからが故に、様々に解釈し得るものではありましょう。けれども、これをそのまま読んだならば、阿字という根源から生み出た者は、やがてまた死んで阿字という根源に還っていくのだ、ということになる。そして一般にそのように理解されており、またここにいう阿字とは「母なる大日如来である」・「生命・宇宙の根源・原初」などと受け取られています。どうしてもその「始まりがあって欲しい」人間の性向が表出したものといえましょう。
しかし、それもまったく取るに足らない幼稚な理解であり、そもそもこの歌は空海作のものとして見なすべきでも、阿字の意義を示すものなどとして取り上げるべきでもありません。それが人を容易く誤解させ、妄想を膨らませるだけの、いわば浪漫仏教を象徴するが如き詮無いものであるからです。
それを揶揄した歌を一句。
阿呆の子が 阿呆な古歌立ち聞いて
また口ずさむ 阿呆の古歌
現在、真言宗の各派には、阿字観を一般の人々に公開し実習させているところが少なからずあります。それは1970年代から90年代における世間の一部において、瞑想ブームとでも言えるものを迎えていたことに対し始まったものです。

また、真言宗は瑜伽宗などとも言われるその建前上、実は教学的に何の根拠も無く、馬鹿の一つ覚えのように「南無大師遍照金剛」などと繰り返すだけの、到底仏教とも密教とも思われない大師信仰に寄りかかっていては不十分かつ時代に不適合であり、禅宗がそうして一定の成功を収めているように、やはり密教らしく独自の瞑想を用いた布教をするべきではないか、などという程度の、そして今更とすら言うべき動機によったものでした。
他がやっているから己もやらなければならない、兎にも角にもなんでもやってみればいい、と言うものではありません。
いずれにせよ、そのように始まった阿字観を一般にも実習させようとする流れには、あるいは独自性をさらに強めようとして、阿息観だの阿字観体操だのと、奇妙奇天烈なものを考案して実行させる者が出現。あるいはその実修中、「宇宙が云々」・「大生命の息吹が脈々と云々」などと、実に抽象的で滑稽な誘導の言葉を、始終並べ挟んでみる者が続出しています。ひどいのになるとアンビエント音楽や指導者の愛好曲を終始流してみたりなどと、もはや「住職の娯楽」と呼ぶべきものをすら通り越し、何かのご冗談とすら言えるような意味不明・根拠不明のアジカンを行わせている輩共があります。
(これは高野山真言宗が阿字観布教なるものを始めだした初期、公式にそうするべきなどと言って、いわばその「指導要領書」まで出していたことに基づく愚行です。それはつまり、その最初から実は何もわかっていない、しかし「その道の権威」などと言われていた人々が、とりあえずそれっぽいこととして始めてしまっていたことの証でもあります。)
これらの事から推して知られるでしょうが、そもそもその指導に当たっている本人が、実はまるで瑜伽について素人。「指導歴は長いが、瞑想に関する経論の知識はほとんど絶無であって、自身のまともな瞑想歴も無いに等しい」などという、馬鹿げた話も決して珍しくありません。そんな嘘のような本当の話が、日本の仏教界では普通にあるのですから、笑えませんが、面白いものです。
実際、宗団が与える瞑想指導であるとか阿字観指導「資格」なるものを持つ指導員らなど、せいぜい阿字観について概説書の類を二、三冊を読んだことがある程度、そして宗団の開講するなおざりな講義を一、二度、数日間受けた程度ということがほとんどです。その手合の者は、たいてい「阿字観とは密教の瞑想法であり、呼吸法である」であるとか、「阿字観とは母なる大宇宙と私という小宇宙の合一、同一であることを感じ、知るための瞑想法です」などと宣うでしょう。
しかし、それはその者が何も解らず人に説いていることの、紛れもない証です。
先程述べたように、「宇宙」だとか「生命」だとかいう言葉を持ち出してくる時点でその者にはなんら期待できないことが明瞭となる、と言えるのですが、さらに阿字観をして「呼吸法である」などというのは全くの論外です。阿字観は呼吸法などではありません。これもよくあることなのですが、中途半端に聞きかじったことのある、婆羅門教の瑜伽学派にて説かれたprāṇāyāmaやKumbhakaを持ち出して混同してしまっているのでしょう。
世間には、これは特に阿字観に限ったことでもなく、仏教の修習についてどうしても「呼吸法である」と見なしたがり、言いたがる輩が一定数あるのです。
(もっとも、『無畏三蔵禅要』では、これは本稿本文の脚註にても述べることですが、いわゆるプラーナーヤーマに該当する「調気」が若干ながら説かれています。しかし、それはただ阿字観の修習の前段階として、心身を健やかにする術として触れられている程度のことであって、阿字観そのものでは全くありません。)
無論、経論の所説に通じていればいるほど良い、その経験が長ければ長いほど良い、などということは決してありません。ですが、全体としてはその内容がまったくお粗末極まりなく、まったく不確かで無根拠なる、阿字観に興味を持った人々をあらぬ方向に誘導させていくだけのものとなっています。
瞑想を修める格好を取り繕うのは、多くの人に出来てしまうことです。しかし、ではその結果はどうかと聞かれても、
「え~っと、気持ちが良かったです」
「(なんとなく)宇宙を感じました」
「あぁ、これはいいですねぇ。これはそう…、癒しですね?」
「阿とか何とかはチンプンカンプンでよくわかりませんが、こんな素晴らしい体験初めてです!感動しました!」
では、阿字観など行う必要など全く無い。それはむしろ害悪にすらなり得る。それは結局、ただ観光客など人集めのための余興に過ぎません。実際、各宗団もただ観光客相手の余興としてやらせており、その意味では目的は達せられているのでしょうけれども。
先にピアノの喩えをもってしたように、これは何も瞑想に限らず世のほとんどのことに該当することですが、何でも段階を踏んで基本から徐々に、そして確実に修めていくことが不可欠です。そして何よりもまず、杜撰な説ではなく確かな根據に基づき、本人の意思を以て真剣に取り組み探求しなければならないことは言うまでもありません。
仏教は、人それぞれの立場・能力に応じて様々に説かれたものであり、その原理・原則は唯一であるとはいえ、修行法は唯一ではありません。そして、仏陀という偉大な法王が遺し、僧伽という相続者らが引き継ぎ守り磨いてきた、その全てが価値ある宝です。密教もその数ある宝のうちの一つで、確かに独自で優れた方法論を伝えています。
しかし、いま密教でなければ必ず駄目なのだ、ということは全くありません。自身が真言宗徒である、密教徒であるからといって、ただそれだけの理由で阿字観(狭義での阿字観)を修する必要は無い。そのように漠然と阿字観を修めたとて、それは時間の無駄であり、仏教を理解・体得するのに甚だしい遠回りをすることになりかねません。自らの機根と縁とに従い、様々な経論にあたって仏教の理解を進めつつ、五停心観などから漸漸として瞑想を進めていけば良い。いや、しばしば多くの経論の知識を備えることがむしろ障碍となって、その人を多岐亡羊として迷わせることがあります。
なんでも知れば良いということは決してなく、反対に無闇に知らぬほうが良いことは、この世にそれこそ無数にあります。もし、自らの器が値するものであり、縁あり機が満ちて密教を正しく修め得ることが出来たならば、それをまた本格的に、真剣に修めれば良いでしょう。
たとえば近世江戸後期の昔、大阪を中心に仏教復興運動を展開した慈雲尊者などは、野中寺にて二十歳を過ぎて比丘となり、懸命に多くの経論を読み漁って修学に励んでいました。ところが、ある日いくら該博な知識・教養を得たところで人生の苦難を解決し乗り越えることなど出来ないことを「多聞は生死を度せず、仏意とはるかに隔つ」と、律蔵に伝わる仏滅直後に行われた第一結集に至るまでの経緯を読んだことで気づいています。
そこで尊者は、法楽寺に帰って師の忍綱から住職位を継いだものの、たった二年で住職を放棄して法弟に譲ってしまいます。そして、仏教の肝心は戒律を正しく護持した上で修禅し、自らの心を明らめなければならないと、万事擲って懸命に阿字観を修したのでした。
若き尊者がまず阿字観を選んだのは、それ以前、十九山村墓寺の大輪律師という人から阿字観についてかなり詳細に教授されていた、ということがあるのでしょう。またそれ以外にも、当時の世間でも阿字観が「初心の者でも容易に修し得、達しやすい」などと謳われていたことを素直に受けてのことでもあったのでしょう。しかし、それで尊者が突如として証悟したということは当然なく、「やや証入する所あり」という程度のことであったといわれます(『正法律興復大和上光尊者伝』)。
それは結局、特に阿字観を修めたが為のことではなく、はじめてまともに取り組みだした修禅であっても多少なりとも功徳のあることを認め得た、ということであったように思われます。しかし、それはそれで満足出来るものでは決してありませんでした。尊者が野中寺にあった頃、その経蔵にて必死に多くの経論を読み漁って仏典について多くの知識を蓄えていたとは言え、修禅の基本、根本的な事項を誰かに教授されたことはなく、いきなり「修禅せねば」などと決意し阿字観を修めたとて、それはいわば暗中模索のことであったのでしょう。
そのようなこともあり、慈雲尊者は信州の正安寺にあった洞上における当代の禅師、大梅法撰〈1682-1757〉のもとに足掛け二年参禅。それは当然曹洞宗の伝統においてのことでしたが、修禅のイロハを一から学んでいます。
しかし結局、尊者は洞上の禅師らと仏教に対する見解は一致することはありませんでした。そこで独り山中において生涯を送るべきと考えるようになっていた中、故あってに還っています。そして、そこで独坐する中、ついに尊者は開悟したといいます。その後、尊者は開悟の楽しみを享受し、修禅を続けていたようですが、それは傍に雷が落ちても気づかなかったほどの深い禅定に達するものであったといいます(『正法律興復大和上光尊者伝』)。
尊者がその時、どのような修習を行じていたかの伝えはありませんが、それはおそらくもはやいわゆる阿字観などに依るのではなく、先程から言及する広い意味での阿字観によるものであったのでしょう。それを強いて「広義の阿字観」などと表現する必要などありはしませんが、阿字観というものの目指す所、開陳しようとしている真理が密教に特殊なものでないことを示すため、ここではあえてそう言っておきます。
阿字観を修すといっても、阿字の字義を知ることは勿論のこと、修禅・瑜伽ということ自体について何も知らないで修めるのと知って修めるのとでは雲泥の差があります。そもそも、これも前述したことのさらなる繰り返しとなりますが、仏教の修習、中でも大乗における瑜伽法はすべて、広義の意味での阿字観です。なんとなれば、その悟得を目指すものが、もとより自心を含めた一切法の本不生を知見することであり、それが阿字の象徴するものであるのだから。そして阿字観とは、仏教の修習の核心である止観という枠組みを、観想という術によっていずれも実現するものです。
「好むと好まざると、ただ永遠に生き死にし続けなければならない」輪廻というおそるべき苦海を脱するための術、安般念や不浄観、界分別観や三密瑜伽などの修禅・瑜伽法を、少しでも多くの人がそれぞれ自ら正しく修め、漸漸としてであってもその功徳を自ずから証することを、願ってやみません。
一般に、人は三昧を修めることを好まず、また自ら修めたことなくして悪しきものと考え、あるいは中途半端に修して挫折・放棄し価値なきものと見なしてきました。それは別段、今に限った話ではなく、仏陀御在世の当時から同様であったようです。しかし、戒を護持し、定を真摯に修めずして、ただ学解や知識を深めても己を真に救うことなど、「決して」出来はしません。
定を修めること、止観を修習すること。それは決して容易いことではなく、その証果をただ机上においてアレコレ想像し得るものでもありません。しかし、自ら意を決して真摯に修めたならば、たちまち小分であってもその功徳のあることを、己が目の当たり知ることの出来る、真に尊く稀有なるものです。
沙門覺應 稽首和南