支那以来、日本や朝鮮でも、瑜伽戒にならぶ奉持された菩薩戒の典拠として『梵網経』は信受されてきました。
現在通用する大乗の『梵網経』には、鳩摩羅什の高弟の一人であった僧肇によると伝説される序文が付されており、そこに以下のような一節があります。
夫梵網經者。蓋是萬法之玄宗。衆經之要旨。大聖開物之眞模。行者階道之正路。《中略》
弘始三年淳風東扇。於是。詔天竺法師鳩摩羅什。在長安草堂寺。及義學沙門三千餘僧。手執梵文。口翻解釋。五十餘部。唯梵網經。一百二十卷六十一品。其中菩薩心地品第十。專明菩薩行地。是時。道融道影三百人等。即受菩薩戒。人各誦此品。以爲心首。師徒義合。敬寫一品八十一部。流通於世。
そもそも『梵網経』とは、けだしこれ万法の玄宗にして衆経の要旨。大聖〈釈尊〉が物〈事物の真理〉を明らかにされた真模〈最上の手本〉にして、行者が道を階る正路である。《中略》
弘始三年〈401〉、淳風東扇〈淳風は「美しい習俗」の意であるが、ここでは鳩摩羅什が東方すなわち支那に来訪したことの意〉す。そこで(後秦の姚興は)天竺の法師、鳩摩羅什〈Kumārajīva〉を召して長安の草堂寺に入らせた。するとたちまち(鳩摩羅什から)学ぼうと集まった沙門は三千余僧に及んだ。(そこで鳩摩羅什は)手に梵文〈仏典のサンスクリット原典〉を執り、これを口で翻じて解釈すること五十余部となった。ただ(鳩摩羅什により翻訳された)『梵網経』は百二十卷六十一品あって、その中「菩薩心地品」第十はもっぱら菩薩行地を明らかにしている。その時、道融〈僧肇に同じく鳩摩羅什の高弟の一人〉・道影など三百人が(『梵網経』所説の)菩薩戒を受けた。その人らはそれぞれこの品〈「菩薩心地品」第十〉を誦え、これを以て心首〈精神的柱〉とした。師〈鳩摩羅什〉と徒〈弟子〉と心を同じくして、その一品八十一部を敬い写し、世間に 流布させたのである。
《伝》僧肇作『梵網経』序(T24, p.997a-b)
この序によれば、もともと『梵網経』は百二十巻六十二章からなる大部の経典であったと言います。しかし今流布しているのはその第十章である「心地品(盧舍那佛説菩薩心地戒品)」のみであり、それは上記の理由によってそうなったものであるとされます。
ところが、僧肇によるという序文ではそう言うものの、しかし『梵網経』は、支那でも古くは訳者不詳、いや偽経の疑い濃厚と見られていました。誰に由って支那へ請来され翻訳されたかもわからぬ、むしろ支那にて何者かにより捏造された経であろうとの強い疑いが掛けられていたのです。
たとえば隋代の開皇十四年〈594〉に法経と廿人の学僧らによって撰述された訳経目録たる『衆経目録』、いわゆる『法経録』では、『梵網経』について以下のように記載されています。
衆律疑惑五 一部二卷
梵罔經二卷諸家舊録多入疑品右一戒經依舊附疑
衆律疑惑 第五 一部二卷
『梵網経』二巻諸学者による古来の経録では多く(偽経の疑い濃厚とされる典籍の目録)「疑品」に収録されている。右の一戒経〈『梵網経』〉は、従来の見解に依って(偽経と)疑われる。
法経等『衆經目録』卷第五(T55, p.140a)
少なくとも594年以前までの支那では、『梵網経』は鳩摩羅什による翻訳などとされておらず、その出自と真偽が疑われてきたものであったことが、ここから知られます。したがって、古説に依れば、先に示した僧肇によるとされる序文も実は僧肇によるものでは決してなく、またその内容もいわば真っ赤な嘘と言えたものです。
そもそも印度や吐蕃など印度亜大陸の大乗が信仰され行われていた諸地において、『梵網経』が流布し、また梵網戒が行われていたという痕跡は全くありません。
ところが、何を根拠とし、何故そのようにしたのか全く知られませんが、わずかその三年後の開皇十七年〈597〉に彦琮によって著された新しい『衆経目録』、いわゆる『彦琮録 』では、これを「大乗律」を説いた典籍の範疇に入れ、ごく簡単に鳩摩羅什が後秦代〈384-417〉に訳出したものと言い出しています。
大乘律單本 一十四部三十卷
《中略》
梵網經二卷 後秦世羅什譯
大乗律単本 一十四部三十巻
《中略》
『梵網経』二巻 後秦の世、鳩摩羅什による翻訳
彦琮『衆經目録卷』第第一(T55. p.153a)
以来、つぶさにはその前後に鳩摩羅什訳であると仮託されたのであろうことを物語る典籍が色々あるのですが、『梵網経』は鳩摩羅什の訳経であるとされてしまっています。
これについて特に留意すべきことがあります。『梵網経』には、これがいつ頃著されたものかは不明ですが、現存する最古の注釈書として天台大師 智顗によるとされる『菩薩戒義疏』が著されています。その『菩薩戒義疏』には、当時(隋代)菩薩戒の典拠として通用しているものに六種あるとし、『梵網経』がその第一に挙げられています。
次論法縁。道俗共用方法不同。略出六種。一梵網本。二地持本。三高昌本。四瓔珞本。五新撰本。六制旨本。優婆塞戒經偏受在家。普賢觀受戒法。身似高位人自譬受法。
次に法縁を論じる。道俗共用の(菩薩戒を受ける)方法は様々にあって、今は略して六種を示す。一には「梵網本」〈『梵網経』〉、二には「地持本」〈『菩薩地持経』〉。三には「高昌本」〈「暢法師本」とも。大凡『地持経』の授戒法に大同ながら、受者に十遮を問う点で異なる〉、四には「瓔珞本」〈『菩薩瓔珞本業経』〉、五には「新撰本」〈凡そ十八科からなる「近代諸師所集」の授戒法。戒相として十重を説く。この十重は『梵網経』あるいは『本業経』に依ったものであろう。これが「新撰本」とされていることからすれば、智顗の当時に初めてそれらが流通しだしていたのであろう〉、六には「制旨本」〈『菩薩戒義疏』はその内容を全く省略しており詳細不明〉である。
《伝》智顗説 灌頂記『菩薩戒義疏』巻上(T40, p.568a)
その伝説通りこれが真に智顗によるものであったならば、智顗は従来の訳経僧・学僧らによる疑いを無視し、これを鳩摩羅什による真経であると断じて『梵網経』の注釈を施した、ということになるでしょう。あるいは、むしろ智顗がそうしたことによって、『彦琮録』にて鳩摩羅什訳とされた、ということであったのかもしれません。『彦琮録』が編纂されたのは智顗が死去したまさにその年です。
支那では当初、菩薩戒(大乗戒)として通用していたのは『菩薩善戒経』あるいは『菩薩地持経』に基づく、いわゆる「地持戒」〈玄奘によって『瑜伽師地論』等が訳されて以降は「瑜伽戒」の称に変化。内容はほぼ全同〉です。それは求那跋摩〈Guṇavarman〉によって智顗などが出る150年程も前に支那にもたらされ、行われていたものです。そこに加え、智顗の没年頃、地持戒とはまた異なる菩薩戒を説く『梵網経』が、真経として受容されたのでした。そしてそれはまた、『本業経』の所説を加えて混じえてのことです。
いずれにせよ、支那において智顗がこれを重視し、依用したことを契機とした『梵網経』の受容以来、日本においても同じく『梵網経』はまぎれもない仏説であって偽経ではない、いや、むしろ大乗戒を代表する得難い経典であって、大乗の人はすべからく受持すべきでものであるとされてきました。それは、詳しくは後述しますが、『梵網経』所説の梵網戒(の正統)をもたらした道璿や鑑真に由来するもので、日本におけるおよそほとんどの僧俗は梵網戒を「大乗戒である」、「仏説である」と受容してきたのです。
しかしながら現代、知恩院の門跡を勤めた浄土僧にして仏教学者であった望月信亨が、『梵網経』は偽経であることを文献学的裏付けをもって主張。以来、現在の仏教学者・文献 学者等もまた、やはり訳者は鳩摩羅什などでは決してなく、またその内容などからして、五世紀中頃の支那で撰述された偽経であると見ています。それはもはや学会では定説となっています。
そしてまた、『梵網経』と併せて信受された『本業経』ついても、やはり望月博士が、『梵網経』に同じく妄説の偽経であるとの説を初めて主張。以来、『本業経』とは五から六世紀の支那において先行する『梵網経』の影響を受けて撰述された偽経であると、完全に確定されるまでには至っていませんが、おおよそ学者らの間で承認されています。
特に『本業経』は、先にも指摘しておきましたが、内容にその他多くの経典と比してもかなり特殊な文言が見られます。この経が文献学者らがいうように偽経であるならば、これを撰述した輩は、先行する『瑜伽師地論』や『優婆塞戒経』そして『梵網経』の説を統合しつつ、その上を行って注目されようと、より特種で過激な説を大乗経典の名のもとに加上して捏造したということであるのでしょう。
いずれにせよ、支那・日本において行われてきた菩薩戒を知り、また学ぶには『梵網経』と『本業経』、そしてもう一つ加えたならば『占察善悪業報経(占察経)』が必須の経典です。そこでしかし、また非常に皮肉なこととなるのですが、その『占察経』こそ、現代の文献学者らがそう言い始められて判明したというのでもなく、支那でもかなり早い時期から依るべきでないとされていた「紛れもない偽経」です。
これは特に日本仏教においてその傾向が一層強くなるのですが、そのような偽「菩薩戒経」の影響をあまりに色濃く受け、それをまた支那の伝統からも離れて独自に解釈していったがために、世界でも類を見ない、もはや仏教を逸脱したと言って誤りない、極めて特殊な戒の理解がされていくことになります。
『梵網経』の所説の一大特徴として、また現代では『梵網経』が支那撰述の偽経であるとされるその根拠の一つとして、しばしば取り上げられる一節があります。
爾時釋迦牟尼佛。初坐菩提樹下成無上覺。初結菩薩波羅提木叉。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法孝名爲戒亦名制止。
その時、釈迦牟尼仏は、初めて菩提樹の下に坐して無上覚を成就し、初めに菩薩の波羅提木叉を結したまわれた。
「父母・師僧・三宝に孝順せよ。孝順は至道の法である。孝を名づけて戒とし、また名づけて制止という」
《伝》鳩摩羅什訳『梵網経』盧舍那佛説菩薩心地戒品第十 卷下
(T24, p.1004a)
就中、「孝名爲戒(孝を名づけて戒とす)」などという、ことさらに特異と言える点。それはまさしく支那の儒教思想をそのまま仏教に紛れ込ませた証である、支那の民衆に仏教を根付かせるため、あるいはしばしば軋轢のあった仏教と儒教との融和のために、儒教思想を仏教にねじ込んで捏造した経典の証である、と学者らに見られているのです。
もっとも、ただ単純に孝という言葉・思想があるから仏教では無い、偽経であると言われているわけではありません。例えば、先に示した四十八軽戒のうち、「第十六 為利倒説戒」や「第四十四 不敬経律戒」などを現実に行うことは、純然たる孝を尊ぶ支那人からすれば、到底受け入れられるものではありません。というのも、支那では仏教の出家者が頭髪を剃ることや死者の亡骸を荼毘に付すことすら「孝に反する」などと激しく批判しており、ましてや生身の身体を意図的に傷つけるなど、常軌を逸したものと一般に思われた行為であるからです。
なんとなれば、儒教でいう「孝」とはそもそも以下のようなものであるから。
身體髪膚。受之父母。不敢毀傷孝之始也。
身体髪膚、之を父母に受く。敢えて毀傷せざるは孝の始めなり。
『孝経』
「孝」の語を用いてその意義を仏教的に換骨奪胎し、支那の人々を仏教側に引き寄せようとしたものにすぎないと言えばそれまでです。が、『梵網経』には部分的に支那人にとって相当強烈で反発を招くであろう内容が説かれているのです。
また、父母や親族・師・三宝など敬うべきを敬って養うこと、恭順すべきこと。それは、その他の経典、たとえば現代の仏教学者によって初期経典などといわれることがあるMaṅgala sutta(吉祥経)やSiṅgālovda sutta(『六方礼経』・『善生経』)などでも、それこそ孝という言葉が使われてはいないものの、まさに「孝」にあたる行為が説かれ推奨されています。儒教の言う「孝」そのままではないにしろ、相似する内容の行為を徳行・善行であるとする思想は古くインドにもあるのです。
けれどもしかし、全体として『梵網経』を見た時には、やはり現代の仏教学者がそう見る通り、それが支那において『華厳経』や『涅槃経』そして既存の戒経の思想を部分的に取り入れて造られた偽経であろうとの嫌疑がかけられることが免れられないような、支那的内容をもっていることは事実です。その内容が支那的であるというだけではなく、まともに読もうとすればするほど、その記述が非常に曖昧模糊としたり雑然としたりしているなど、理解し難い記述が散見されもします。
また、『梵網経』が偽経では無かったとしても、しかしその訳文には問題がありすぎ、鳩摩羅什訳とは到底思われません。まともに読もうと思えば思うほどわからない、ひどく杜撰な記述に満ちているのです。
しかしながら、それが現代の見方からすれば明瞭に支那的臭いのただよう儒教思想が強く織り込まれたものであったとして、当時はあくまでこれをまごうことなき仏説である、印度伝来の真経であるとして受け入れられたのでした。その故にこそ、智顗や法蔵などは『梵網経』に対し、それまで伝わり護持されていた律や菩薩戒と撞着・衝突をきたすことのない解釈をするために、注釈書を著したのでありましょう。
支那仏教史上の巨人とも言える彼ら両人は、共に生粋の支那人ではあります。かといって、彼ら大徳らが、儒教のいう孝思想そのままでもって、「孝名爲戒」のいう孝を解釈していたのかといえばそうではありません。それぞれがあくまで仏教者として、時に儒教的な孝思想とはまったく反した形で、これを理解していたことが知られます(他に注釈書を残した支那僧・日本僧の中には、まるきり儒教的孝によってこれを理解した者もありますが)。
いずれにせよ支那以来、日本の仏教史上においても、『梵網経』はどこまでも仏説の大乗戒を説くものとして奉持され、さまざまな祖師といわれる人らによってもやはり同様に重要視されたのでした。
日本において『梵網経』がいつごろ請来され、信受されだしたかははっきりしていません。
しかし、これは先にすでに示したものの再掲となりますが、すでに養老元年には『梵網経』がただもたらされていただけではなく、その所説の戒を文字通り実行していた者があったことが知られます。行基です。
壬辰。詔曰。《中略》 方今小僧行基。并弟子等。零疊街衢。妄説罪福。合構朋黨。焚剥指臂。歴門假説。强乞餘物。詐稱聖道。妖惑百姓。道俗擾乱。四民棄業。進違釋教。退犯法令。
(養老元年〈717〉四月)壬辰〈23日〉、詔して曰く、「《中略》 まさに今、小僧行基ならびにその弟子等は、街衢〈市街地〉に零疊 〈無闇に群衆すること〉し、みだりに罪福を説いて朋党を合わせ構えている。そこで(仏・菩薩への供養として、人々の)指や腕の皮膚を剥いだり焼いたりし〈行基らは梵網戒の第十六軽戒・第四十四軽戒を現実に行わせていたが、それは「僧尼令」第二十七 焚身捨身条に違反する行為〉、家々を経巡って不可思議なことを説きまわり、強いて(食以外の)余物を布施するよう乞いている〈「僧尼令」第五 非寺院条および第二十三条 教化条に違反する行為。『令義解』では「余物」とは「衣服の類」であってそれを規制の対象としているが、実際に行基らが布施として要求していたものは衣服に限らずあらゆる雑多な金品であったろう〉。それは聖道〈仏教〉を詐称するものであって、百姓を妖惑〈「僧尼令」第一 観玄象条に抵触〉し、道俗〈出家者・在家者〉を擾乱。ついに四民〈全ての階層の人々〉はその業〈職業。義務〉を放棄している。(行基らは)進んで釈教〈仏教〉に違え反し、また法令〈『大宝律令』「僧尼令」〉を退ぞけ犯している」
『続日本紀』巻七 (元正天皇) 養老元年四月壬辰条
この中、行基が民衆に行わせていた行為には、まさしく梵網戒が菩薩として必ず実践せよと義務としていることです。
昭和以降の史学者などは、「僧尼令」の特に「第五 非寺院条」などに見られる僧尼に対する朝廷の見方・態度こそ 歪で抑圧的であったとし、律令体制下における行基およびその教団に対して非常に同情的に見ることが支配的でした。そしてその傾向はそのまま無反省に今も続いています。
しかしながら、非寺院条は前時代の学者らがそう見なしたようなものではない。当時、誰もまだ正規の仏教僧たり得ない状況にあって、しかも国家の管理が行き届かないまま誰も彼もが巷のそこかしこに寺院以外の道場など立て回って良い訳もなく、それを規制したのが非寺院条です。実際、行基らが巷で行っていたそれは、まさしく今で言うカルト教団の所業に他なりません。朝廷がこれを嫌い行基をして「 小僧」と称したのも当然であったと言えます。
上記に挙げ連ねられた諸々の行為は、現代日本でも特に昭和四十年代から平成にかけて、街の拝み屋・霊能者などと言った類、そして諸々の新宗教教団が行っていたこととほとんど同様のものと言って良いでしょう。したがって、これは現代の価値観を過去に持ち込んでそういうのでなく、当時からその手の行為、その手合の輩が問題あるものとされていたのは変わりありません。
そもそも、大宝元年〈701〉に施行された『大宝律令』の「僧尼令」は、明らかに『梵網経』の所説を前提とした条項がいくつかあり、それを行基の教団が悉く実行したことによってむしろ法令を破っていたことが、この『続紀』の記述から知ることが出来ます。
「僧尼令」は、唐の道教および仏教の宗教者と寺院に関する法「道僧格」から、日本に直接関係のない道教についての条項を取り除いて編纂されたものとされます。そこでその条例の根拠の一つでもあった『梵網経』が、『大宝律令』施行以前のいまだ編纂されている時期、すなわち七世紀中には日本にもたらされており、僧ばかりでなく藤原不比等など俗人にも読まれ研究されていた可能性も充分に考えられます。
さらにまた、当時の日本社会にどれほど『梵網経』が流布していたかを示す史料として、以下のものがあります。
鴨縣主黑人年廿三 山背國愛宕郡賀茂鄕𦊆夲里戸主鴨縣主呰麻呂戸口
讀経法花部一部 最勝王経一部
涅槃経一部 方廣経一部
維摩経一部 弥勒経一部
仁王経一部 梵網経一部雑経合十三巻誦経方廣経上巻 觀世音経天平六年〈734〉七月廿七日
多心経 読陀羅尼
羂索陀羅尼 佛頂陀羅尼
大般若陀羅尼 法花経陀羅尼
虚空蔵経陀羅尼 十一面経陀羅尼
八名經陀羅尼 七佛八菩薩陀羅尼
結界唱礼具 浄行八年
「優婆塞貢進解 正倉院文書」(『大日本古文書』編年文書, vol.1, p.583)
これはいわゆる「優婆塞貢進解」で、在家信者が出家を希望し、朝廷にその願いを届出た文書です。そこで一在家居士が学び読んでいた経典の中に『梵網経』を挙げていることは、それが既に広く民衆にもよく知られていたことの証です。
また、鑑真一行が渡来するに先んじて懇請され、天平八年〈736〉来朝し、大安寺西唐院に止住していた道璿は、これも何年のことであったかは知られぬものの、『梵網経』下巻の注釈書三巻(『註菩薩戒経』)を著していたことが知られます。それが道璿が自ら積極的に著したものであったか、日本の僧俗に求めに応じて著したものであったかは不明です。いずれにしても、現在その注釈書は現存せぬものの、今知れる限りではそれが日本において初めて著された『梵網経』の注釈書でした(日本人僧による初めてのものはやや後代に善珠が著した『梵網経略抄』)。
例えば最澄は、その師であった行表の師であった道璿の行跡について、若干の伝承を遺しています。
大唐大光福寺道璿和上日本國大安寺西唐院
天平寶字年中。正四位下太宰府大貳吉備朝臣眞備纂云。大唐道璿和上。天平八歳。至自大唐。戒行絶倫。教誘不怠。至天平勝寶三歳。聖朝請爲律師。俄而以疾退居比蘇山寺。常自言曰。遠尋聖人所以成聖者。必由持戒以次漸登。和上毎誦梵網之文。其謹誦之聲。零零可聽。如玉如金。發人善心。吟味幽味。律藏細密。禪法玄𣸧。遂集註菩薩戒經三卷。非我輩之所逮。更何得以稱述。自餘行迹。具載碑文。其前序云。昔三藏菩提達磨。天竺東來至於漢地。傳禪法於慧可。可傳僧璨。璨傳道信。信傳弘忍。忍傳神秀。秀傳普寂。寂即我律師所事和上也。本在嵩山。流傳禪法。人衆多歸。故有勅請入東都。常在華嚴寺傳法。故曰華嚴尊者。璿和上四季追福文云。春季三月内。奉爲達磨和上。乃至第七華嚴和上。及陽澤和上。並十方法界無邊三寶。滅除根本無明十地罪障。一切微細所知煩惱。夏季六月内。奉爲無始時來一切師僧。乃至禪河和上。及并府三師七證。并盡未來際。十方法界一切師僧善友。一日一夜。供禮盡法界。虚空界一切三寶。永斷身口七支破戒。及三業毀破三聚淨戒之罪。秋季冬季二節。如願文説。天平寶字三年三月二十五日。峰林下發願也。謹案。璿和上書云。又吾院堂内所供之燈。自今已後。至禮佛時。加炷令明。禮佛了。即唯留一莖燈心也。如是可得免燻佛像之罪過也。行表。數數自親看檢之也。付法之文。具如遺言。
大唐大光福寺 道璿和上日本国大安寺西唐院
天平宝字年中〈757-765〉、正四位下太宰府大弐であった吉備朝臣真備の纂〈『道璿和上伝纂』〉にこのようにある。大唐道璿和上は、天平八年に大唐より来朝された。戒行絶倫であって、教誘怠ることがなかった。天平聖宝三年、朝廷の要請によって(僧綱に任ぜられて)律師となった。しかし突如、病に見舞われたために比蘇山寺に隠居されたのであった。(道璿和上は)常に自ら言われていた。「遠く聖者の聖となる所以は何かと尋ねたならば、それは必ずまず戒を持つことであって、そうして初めて次に(定と慧とを修めて)漸く(聖者の高みへと)登る」と。和上は毎に『梵網経』を読誦されていた。その謹誦される聲は、零零として聞き惚れるものであって、それはまるで宝玉のような、黄金のような、聞く者をして善心を生じさせるものであった。(仏法において)吟味幽味にして、律蔵について非常に詳しく、禅法にも深く通じ達していた。遂には『註菩薩戒経』三卷を著されたが、それは我輩など到底及べるものではない優れたものであって、それ以上何も付け加える必要など無いものであった。(道璿和上の)その他の行跡については、詳しく碑文に載せている。その冒頭の序にはこうある、「昔、三蔵菩提達磨が天竺より東来して漢地に至られ、禅法を慧可に伝えられた。慧可は僧璨に伝え、僧璨は道信に伝え、道信は弘忍に伝え、弘忍は神秀に伝え、神秀は普寂に伝え、普寂はすなわち我が律師が仕えた和上である。本は嵩山にあって禅法を伝え広め、多くの人々が帰依した。そのようなことから、皇帝の勅によって東都に入ることとなり、常に華厳寺で仏法を伝えていた。このことから、華厳尊者と称された」と。『璿和上四季追福文』には、「春季三月のうちは、達磨和上 乃至 第七華厳和上、及び陽澤和上、並びに十方法界無辺の三宝の奉為に、根本無明・十地罪障・一切微細の所知煩惱を滅除せん。夏季六月のうちは、無始以来の一切の師僧、乃至禅河和上、及び並びに府の三師七證、並びに盡未來際十方法界の一切の師僧・善友の奉為に、一日一夜、盡法界・虚空界の一切の三寶を供養・礼拝し、永く身・口七支の破戒、及び三業によって三聚淨戒を毀破した罪を断ずる。秋季・冬季の二節は、願文に説いたとおりである。天平宝字三年三月二十五日、峰林の下にて發願する」とある」〈已上『寧楽遺文』下〉
謹んで考えてみるに、『璿和上の書』〈未詳〉には、「また我が院の堂内に供するところの燈明は、今より以降、仏を礼拝する時には、灯心を加えてより明るくし、仏を礼拝し終わった時には、唯だ一茎の灯心のみを残すようにすること。そのようにすれば、仏像を(ススで)燻じてしまう罪過を免れることが出来よう」とある。(我が師たる)行表はしばしば自ら親しくこれ〈『璿和上の書』〉を開き見られていた。付法の文は、詳しくは遺言のとおりである。
最澄『内証仏法相承血脈譜』(『伝教大師全集』, vol.1, pp.211-213)
道璿律師の行業について詳しく伝えるものは決して多く残っておらず、この最澄の筆による伝承は、その点非常に貴重です。
また、これは鎌倉期という相当後代に著されたものではありますが、おそらくこの最澄の『内証仏法相承血脈譜』あるいはここに言われる「吉備真備の纂」〈『道璿和上伝纂』〉に直接基づき、虎関師錬は道璿について以下のように伝えています。
釋道璿唐國人。居東都大福先寺。留學普照榮叡諭誘赴東。天平七年來。敕館大安寺西唐院。璿善禪律。于時本朝乏戒學。朝廷請爲戒師。璿不倦授受。嘗曰所以成聖必由持戒。常誦梵網。其音清亮如出金石。聞者感動。
釈道璿は唐国の人である。東都の大福先寺に居していたのを、留学していた普照と栄叡の懇請によって東国(たる本朝)に来られた。天平七年〈736〉、勅によって大安寺西唐院に住された。道璿は禅と律とに通じていたが、当時の本朝では戒学を欠いていたため、朝廷の要請により戒師となり、(戒を人々に)授受するのに倦むことがなかった。当時(道璿は)「聖者(の境地)に至るのには必ず持戒に由る」と言われ、常に『梵網経』を読誦していた。その声はどこまでも清涼で、まるで金の石が現れるかのようであり、聞く者をして感動させたものである。
虎関師錬『元亨釈書』巻第十六
道璿律師の来朝後、時を経ること十八年の天平勝宝六年(754)、ようやく鑑真を忠臣とした大衆が来朝。ついに正統な規定に基づいた律儀の授受が行われるようになって、晴れて日本仏教にも正しく「僧宝」が備わることとなります。
鑑真はただ律をのみ伝えただけではありません。同時にまた菩薩戒(その内容は未詳)を、聖武上皇(沙弥勝満)と光明皇太后、そして孝謙天皇を初めとする僧俗およそ440名に、東大寺大仏殿前に一時的にしつらえた戒壇において初めて授けられています。そもそも、大乗の比丘が菩薩戒(三聚浄戒)と具足戒とを別個に受けて菩薩比丘となることは、印度以来の伝統的、正統なことであって、特別なことではありません。
支那においては、智顗や法蔵などの学匠、そしてまた鑑真もまさしくそうであったように、沙弥出家したものが別途に菩薩戒(三聚浄戒)を受け、また進んで具足戒を受けてはじめて仏教の正式な出家者たる比丘となることが普通でした。
その後、朝廷はただちに東大寺大仏殿の西側の空地に、常設の戒壇を設置した戒壇院を建立。以降、仏教僧となる者はすべて、必ず例外なくこの戒壇院で具足戒(律)を受けなければならないことが、国家として定められます。これによって、日本に仏教が伝来しておよそ二百年余りを経てようやく、正しく日本に仏・法・僧の三宝が現実のものとして成立したのでした。さらにその後には、西方の僻地にある者のために筑紫の観世音寺、東方の僻地にある者のために下野の薬師寺それぞれに戒壇が建立され、併せて「天下の三戒壇」とされるようになります。
当時の戒壇院は、境内に回廊を巡らせ講堂や三面僧坊などがある、ただ具足戒を受けるための戒壇だけではなくて新学の受者らの居住・修学のための施設を備えたかなり規模の大きなものでした。
ところで、鑑真大和上の渡来後程なくして聖武上皇の皇太夫人、藤原宮子が崩御していますが、ここで注目すべき法会が創始されています。
太皇太宮藤原宮子
聖武天皇之母也神亀元年二月天皇即位為大夫人三月為皇大夫人贈正一位太政大臣不比等之女也勝宝六年七月十九日壬子崩平城宮佐保山西陵兆域東西十二町南北十二町守戸五烟国忌於戒壇院修之梵網会是也
太皇太宮藤原宮子
聖武天皇の母である。神亀元年〈724〉二月、聖武天皇が即位したことによって大夫人となり、三月には皇太夫人となる。贈正一位太政大臣・藤原不比等の娘〈長女〉であった。天平勝宝六年〈754〉七月十九日壬子、平城宮にて崩御し、佐保山西陵に葬られる。その兆域は東西十二町・南北十二町〈1.69㎢〉。守戸〈墓守〉として五烟〈五家〉が置かれた。その国忌は東大寺戒壇院において行われたが、それが梵網会である。
『東大寺要録』巻第四
それまでの太上天皇が崩御した時など、七大寺などに『華厳経』や『涅槃経』等の経典を七日毎などに誦経させ、その死を悼み後生を祈ることはされていました。が、それは決して『梵網経』ではありませんでした。何故に聖武上皇の母君の国忌として、戒壇院が完成するのは翌七年(755)のことですが、俄然としてしかも殊更に、『梵網経』を講讃する法会たる「梵網会」が行われたのか。
聖武帝は、そもそも『華厳経』をこそ最も重要な、国家を治め民を安んずるための根幹の経典とし、さらに大乗小乗すべての経律論等を転読・講説すべきことの詔をすら出していました。天平勝宝元年(749)五月のことです(『続日本記』巻第十七)。そのようなことから、おそらく東大寺の毘盧遮那大仏も『華厳経』所説のものであろうと推定されています。そこで国家経営の思想基盤として『華厳経』がその根幹に据えられ、また護国の経典として『仁王般若経』・『金光明経』、あるいは『大般若経』や『大集経』、『法華経』などが頻繁に転読されていたのです。
しかし、母御の藤原宮子が崩御するまさにその年の初め、国家としても待望のことであった正統な律の伝来が、鑑真一行によってなされていました。そして、鑑真に随行してきた唐僧の法進・思託など弟子らは『梵網経』を重んじていたのです。事実、法進はその注釈書『梵網経註』を著しています(現存せず)。これは当時の唐代の菩薩戒の流行、特に天台僧のそれが反映されてのことであったと思われます。もっとも、上に示したように、当時の日本では少なくとも半世紀近く前からすでに『梵網経』は僧俗に信受され、それがたとえ国禁を犯す行為につながるものであったとしても、行われていました。
しかしここでさらに、待望の伝戒の大徳らがあらためて梵網戒の重んじるべきことを説いていたことは、聖武上皇にとって、国の長たる公人としてだけではなく個人として、非常に大きなことであったのでしょう。梵網会が初められたのは、まさに鑑真一行の到来に触発されて梵網戒の所説に従わんとした、その意志の表れと見ることが出来ます。
(ここで一点、注意すべき点があるのですが、聖武上皇らが受けた大仏殿前にて受けた菩薩戒が何であったのか、実は未だよくわかっていません。一般にはそれは梵網戒であったろうと従来見られており、不佞も漠然と、と言うより深く考えること無くそう思っていました。しかし、どうにも腑に落ちない点がいくつかあり、さらにそれが梵網戒であったとの確証もありません。この問題は少々混み合っています。彼らが梵網戒を重視していたことは確実なのですが、あるいは鑑真は、東大寺戒壇院では、すなわち公的には瑜伽戒の三聚浄戒を、私的には唐招提寺の戒壇にて梵網戒の受戒を行っていた可能性もあります。)
では何故に『梵網経』を講説する法会が、特に「死者の追福」として行われたのか。それは、先に触れた『梵網経』が「孝を名づけて戒とす」と説いているような経自体の説もその根拠の一つではあるでしょう。しかし、そのより具体的な根拠が、まさしく『梵網経』下巻に説かれる四十八軽戒の内にあるためです。
若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經福資亡者。得見諸佛生人天上。若不爾者犯輕垢罪。
「もし父・母・兄弟が死亡した日には、法師に請願して菩薩戒経〈『梵網経』〉を講説してもらい、その福徳によって亡者を助けて諸仏に見えしめ、ついに人または神の世界に転生させようとしなければならない。もし、これを行わなければ軽垢罪となる」
《伝》鳩摩羅什訳『梵網経』盧舍那佛説菩薩心地戒品第十 卷下
(T24, p.1006b)
これは梵網戒の四十八軽戒のうち「第廿 不行放救戒」を説く経文の一節です。
ここでは、一周忌などの命日ではなく、父母など家族が死んだまさにその日に法師に依頼して『梵網経』を講説してもらい、それをもって死者の(「ジョーブツ」などでは決して無い)より良い後生の助けとすべきことが説かれています。死者の追福のため、法師に経の講説をしてもらうことが義務として、「戒として」説かれているのです。
もっとも、この戒の主要部分は、智顗による「不行放救戒」という戒の称にも表れているでしょうが、「生きとし生けるものすべては、無始輪廻の中で父母であったものであるから、もし捕われるなど苦しみの渦中にある動物にあったならば、これを救って放生しなければならない」ということにあります。今の日本にも、それほど多くは無いようですが放生の習慣が残っていたり、放生池という名の池があったりするのは、この仏教の放生という行、『梵網経』に説くところに由来するものです。
「過去世において屹度、父あるいは母であったに違いない、囚われの苦しみにある鳥獣を助けて放て」というのがこの戒の主旨であって、決して「死者の追福のために『梵網経』を読誦・講説し、その追福とせよ」ということを主としたものではありません。
いずれにせよ、「した方が良い」と推奨しているのではなく「しなければならない」と義務として説き、「しなければ罪である」と説いている点、注意しなければなりません。先ほど述べたように梵網戒が、五戒など一般的な戒とはまるで性質の異なっている点です。
あるいはまた、四十八軽戒には以下のような規定も存しています。
若疾病國難賊難。父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日。及三七日乃至七七日。亦應讀誦講説大乘經律。《中略》 而新學菩薩若不爾者。犯輕垢罪。
「もし疾病・国難・賊難に遭い、あるいは父・母・兄弟・和上〈師僧〉・阿闍梨〈先生・教授〉が死亡した日、および死後三七日〈二十一日〉乃至七七日〈四十九日〉においても、またまさに大乗経律〈『梵網経』〉を読誦し、講説しなければならない。《中略》 しかるに新学の菩薩で、もしこれを行わなければ軽垢罪となる」
《伝》鳩摩羅什訳『梵網経』盧舍那佛説菩薩心地戒品第十 卷下
(T24, p.1008b)
これは「第三十九 修福慧戒」が説かれている経文の一節です。この戒の主旨は、「僧坊や仏塔を処々に建て、生きとし生けるものために大乗の教えや戒を講説して教化しなければならないこと」です。これに法蔵は応講不講戒なる称を付していますが、その内容を正しく言い表すものとなっています。
しかし、「第三十九 修福慧戒」ではその副次的なものとして、人あるいは国家が諸々の困難・災厄に遭遇したときにはその除災を期して『梵網経』を読誦し講説し、もしくは家族や自身の師僧または先生が死去したならば、やはりその追福を祈っていわゆる四十九日の間、『梵網経』を読誦し講説しなければならないとあります。家族や師僧、先生などが死去した時、その厚恩に報いようと、「生きているものが生きているもののためになす大乗戒の読誦・講説・持戒による功徳」によって、その後生の安楽の助けとすること。それは、まさしく「孝」を実践する方法の一つであって、それがまさに戒(の一部)となっているわけです。
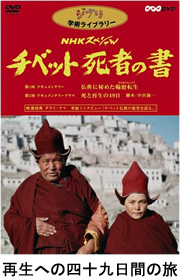
ところで、人が死して後に転生するまでのいわば猶予期間については、実は仏教諸派において諸説あって一定していません。ある派(分別説部など)においては、死後一瞬の間をすらおかずただちに転生する、とされています。しかし、支那・チベット・日本に伝わった仏教(説一切有部そして大乗諸派)では、人は死後四十九日を限度として、転生するまでその意識が彷徨うとされます。その期間(あり方)のことを中有あるいは中陰と言います。今の日本でも、人が死してその死後四十九日を迎えることを満中陰と言い法事を行うのは、そのような仏教の生命観・世界観に基づくものです。
もっとも、大乗が依拠する説一切有部における中陰の有無とその期間についての主流の説は、実は「中陰はあるけれども、特に四十九日と限られたものでなく、しかしかなり短い」というほどのものです。故に、現代における日本の無知無学なる僧職の人々が言うような「亡き人の霊は四十九日にわたってご遺族の近くにあるのですよ」などということは決してない。誰も彼もが律儀にその死後四十九日きっかりと微細な意識となって、これを意成身というのですが、漂うとされるわけではないのです。
ある場合には、たとえば生前は非常に怒りの強い人であったり、その行いが総じて悪しき者であったりすれば、死後間を置かずしてただちに地獄に転生、ということがあるとされています。そのようなことから仏教では最後の一念、すなわち「死を迎える瞬間の心の状態」・「己が死をいかに迎え入れるか」も非常に重要であるとされます。
いずれにせよ、死者が(一応、餓鬼を除く)いずこかに生まれ変わってしまえばもうどうしようもありません。その故にこそ、死者が次に転生するまでの、いわばその猶予期間である中陰の間(最長で死後四十九日間)に、追福のために菩薩戒を講説し、読誦し、実際に受持するという法事を設け、死者のより良い後生を願うということが為されている次第です。
裏を返せば、四十九日を過ぎて後に行う法事のあれこれは、たとえば一周忌や三回忌・七回忌などなどは、生きている人間が死者に対するただ敬意・敬慕から人情として行うもの、あるいは三回忌などまさにそうですが、儒教の影響から行われているものであって仏教はまったく関係がなく、それで死者がどうこうなるとかいうものでは決してありません。例えば、巷間よく法事などの場で言われる、「みんなこうして集まって、きっとあの世であの人も喜んでいる」だの「先祖が喜ぶ」「天国で見守ってくれている」だのいうことは、仏教からすれば絶対にありえないことです。
天平勝宝八年〈756〉五月二日、聖武上皇は崩御されます。すると、その実娘たる孝謙天皇もまた同様に、亡き父聖武上皇のため、皇太子や殿上人らを東大寺を始めとする諸大寺に遣わして『梵網経』を講讃させています。さらには、六十二部を写経して全国六十二カ国にても講説させることを、これも国家として行っています。
己酉。 勅遣皇太子。及右大弁従四位下巨勢朝臣堺麻呂於東大寺。《中略》 講梵網経。講師六十二人。其詞曰。皇帝敬白。朕自遭閔凶。情深荼毒。宮車漸遠。號慕無追。万痛纏心。千哀貫骨。恒思報徳。日夜無停。聞道。有菩薩戒。本梵網經。功徳巍々。能資逝者。仍寫六十二部。将説六十二國。始自四月十五日。令終于五月二日。是以。差使敬遣請屈。願衆大徳。勿辞攝受。欲使以此妙福无上威力。翼冥路之鸞輿。向華藏之寶刹臨紙哀塞。書不多云。
(天平勝宝八年〈756〉十二月)己酉〈三十日〉。(孝謙天皇の)勅により、皇太子および右大弁従四位下巨勢朝臣堺麻呂を東大寺に遣わし、《中略》 『梵網経』を講じさせた。その講師は都合六十二人。天皇の詞に曰く、
「皇帝敬って白す。朕、閔凶〈親の死〉に遭い、その心痛は荼毒よりも深い。(父の命を載せた)宮車は次第に遠のいて、(亡父を)慕って叫べどもこれを追うことは出来ず、耐え難き痛みが心を覆って、尽きぬ哀しみが骨を貫く。ここに(亡父の)徳に報いようとの思いが常にあって、日夜に止めることは出来ない。聞くところによると、菩薩戒は『梵網経』を本とするものであり、その功徳は高大であって、よく死者に資するものであるという。そこで(『梵網経』を)六十二部写経して、まさに六十二国において講説させようと思う。四月十五日より初めて(父の一周忌にあたる)五月二日までの間である。このようなことから使いをやって、(諸国の諸大徳を)敬って屈請したい。願わくは諸大徳らよ、我が願いを固辞されること無きように。この(『梵網経』の)妙福にして無上の功徳力をもって、(亡父・聖武上皇の)冥路の鸞輿〈天皇の乗る輿〉を助け、華蔵の寶刹に向かわせたいと切に望むのである。今、紙面に対して我が悲哀を書き連ねようとしているが、それを十分に書き表すことなど出来はしない)」と。
『続日本紀』巻第十九
父を失った強く深い哀しみに満ちた孝謙天皇の言葉を伝えるものです。ここで孝謙天皇自らが言及しているように、『梵網経』を講説の法会を設けることは、亡者の追福、より善き後生の資助となることが明瞭に期待されてのものでした。それは先程示した『梵網経』の所説に、孝謙天皇も受けていた梵網戒にまさしく従ってのことです。
孝謙天皇もまた聖武上皇に同じく『梵網経』の所説を固く信じ、実際に行ったのでありましょう。これはやはり鑑真らの渡来と、その活動による影響が大きいに違いありません。さらに孝謙天皇は明けたばかりの翌年、天平宝字元年、全国の国分寺において『梵網経』を講説させる勅令を出しています。
甲寅。 勅。始自來四月十五日。至于五月二日。毎國令講梵網經。
(天平宝字元年〈757〉正月)甲寅〈五日〉。勅す。きたる四月十五日より五月二日までの間、国〈国分寺・国分尼寺〉ごとに『梵網経』を講説させる。
『続日本紀』巻第廿
さて、ここで『梵網経』は、いわゆる追善・追福のための法要、今の俗間に言うところの法事を営む根拠としても用いられ、国家としてこれが執り行われました。国家として行われたという点、そして、東大寺大仏建立などその背景や周辺には様々な問題が惹起されたということがあったにせよ、その後の日本仏教に少なからぬ影響を及ぼした聖武上皇によってそれが創始されたという点で、後代に及ぼした影響は甚大であったでしょう。
日本において、『梵網経』は、大乗を奉ずる者にとって重要な菩薩戒の典拠というだけではなく、またこれはその戒に直接関連したことでありますが、死者に良い後生をもたらしえる経典としても受け入れられていったのです。現代における多くの人がその根拠と意義などほとんど知らず、またその必要性も見いだせず、しかし社会的習慣として惰性的に行われている、今の法事なるものの淵源は、これは私見ながら、いま上に述べたような天平の昔の聖武上皇の死、そして『梵網経』に説く戒にあります。
故実先例に倣うことを良しとした朝廷や公家、そして武家らの習慣が、様々な風習や信仰を巻き込みながら、時代とともに民衆に降りていったのでありましょう。いや、そもそも日本人の精神性自体が、奈良・平安時代からほとんど変わっていないようにすら、私には思われます。そして一般的な組織・体制のあり方については、江戸幕府の官僚制から旧日本軍などのそれから、一歩も出ていないようです。
しかし、だからといって、現代の寺院・僧職者らが人々に勧め、また地方の人らが因襲的に自らすすんで行っている法事の内容やその意義の可否はまったく別問題であって、それで単純に「だから法事はするべきなのだ!」などとは決してなりはしません。けれども、以前、以上のような『梵網経』と法事についての私見を、とある地方の年配住職に話しついでに語ったところ、彼はたちまちその話をもって以下のように改変し、あろうことか彼の檀家らの前で得意げに披露していました。
「最近は法事をする人が減ってけしからんことです。亡くなった人たちはあの世で泣いている。いや、法事をすることはホトケ様の戒でもあるのです。そして、それは聖武天皇以来の伝統・文化であって、日本のココロ!ご先祖様も喜ぶ。あの世にいる人々への恩に報いるためにも、法事を欠かしてはいけないのです!」
その住職が意図的にそのように改変した、というよりも彼の頭ではそのようにしか理解できなかったのでしょう。けれども、私からすればまこと不本意にも、その住職のいわば営業の口上に都合よく用いられてしまったので非常に情けなく、げんなりとして居たたまれなくなった経験があります。いまや法事など、寺家からしたならば「お商売」以外の何者でもありません。
いずれにせよ、日本において行われる法事というものの淵源は、まさに『梵網経』の所説にあり、それを現代の人はまったく知らずただなんとなく慣習として行っているものです。したがって、『梵網経』など全く知らずとも、日本のほとんど多くの人はその影響下になおある、と言うことが出来ます。