
鑑真一行の渡来以降、ついに日本にも正規の仏教の出家修行者たる比丘を誕生させうる、印度以来の正統な受具足戒法(三師七証・別受)が導入され、また僧に関する行政上の制度にも改革がなされてその体制が整っています。鑑真らの渡来により、日本にようやく三宝の一画を担う僧法が日本で成立したのです。
もっとも、制度が整ったからといって、それで途端にすべての出家者が「純粋無垢でその行業極めて尊し」となることなど無論ありません。為政者からの帰依を受けたことによる権力・財力など影響力の増大に伴う宗教者の堕落・頽廃、そして宗教者同士の醜い権力争いなど、宗教の別も古今東西人も問わない世の常というもの。
仏教の出家者は本来、そのような世俗的社会や為政者らから一定の距離をおき、僧伽という自治権をもった組織に身をおいて、解脱を目指し修行することを第一義とするものです。出家者が律を守っている限りは、その成員に自他彼此の差別や、その扱いの不公平は生じ得ません。しかし、特に日本の場合、鑑真渡来以前にすでに形成されていた仏教界の様相、特に南都諸大寺のあり方は、地縁・血縁で門閥を形成した縁故主義によっており、至極閉鎖的なものとなっていたようです。
そしてそのような諸大寺のあり方は、はるばる僧宝の成立と育成の為に海を超えた鑑真らの活動を著しく制限するものでした。発心し浄行を経てようやく沙弥となり、また新たに比丘となった者らであっても、諸寺との縁故がなければその経済的背景も居場所も有し得ず、ために多く退転する事態が生じていました。
鑑真が僧綱を辞して私に唐招提寺を建立したのには、そのような南都の諸大寺のあり方に異を唱え、本来の僧伽を形成し、そこで新発意を育成することを目的としたものでした。
天平寶字元年中更有別勅。加大和上之號。詔。天下僧尼。皆師大和上習學戒法也。自爾以来。二百五十戒授與此土佛弟子。時有四方來學者。緣無供養。多有退還。同年十一月廿三日勅賜備前國水田一百町。充十方僧供料。一聽大和上處分之。三年八月三日有恩勅。以薨新田部親王舊家施之。大和尚卽以此地奉爲聖朝造僧伽藍。其號稱招提寺。卽大和上聞此國行事者。寺家雖有衆供而不通外來僧。亦客僧供雖開三日分。若不相識終不資供。由是塞十方僧路。行人爲此幸苦。大和上發願。奉爲代代聖朝開廣大福田。別立十方僧往來修道之處。設無遮供。及日時望寺向堂。不簡僧沙彌。不論斗升。兼及資供。准天竺鷄頭末寺。大唐五臺山華嚴淸凉寺。衡岳寺。將行之。亦如仁王經所説。不立官籍。若貫籍綠衆僧。我法隨滅。但修六和。同崇如水乳之。是故十方行者。共住此伽藍。住持佛法。鎭護國家。然後彼授戒儀式。迄至今時。經數年而尚爲一道無別異矣。惟和上住持當契於佛意趣。
天平宝字元年〈757. 『続紀』では天平宝字二年。豊安の誤認であろう、以降の時系列が倒錯している〉、更に別勅あって、(鑑真に)「大和上」の号が下され、詔して「天下の僧尼は皆、大和上を師として戒法を習学せしめよ」とされた。それより以来、二百五十戒をこの国の仏弟子に授けてきた〈これも豊安による事実誤認であろう。具足戒の授戒は天平勝宝六年(755)から執行されていた〉。当時、(鑑真の元に)四方から来たって学ぶ者があったものの、供養〈経済的支援〉が無いことによって多く退還していた。そこで同年十一月廿三日〈『東征伝』説。『続紀』では29日〉、勅により備前国の水田一百町を賜り、十方僧の供料に充てられた。ひとえに大和上がこれを自由に使うことを許されたのである。天平宝字三年〈759〉八月三日〈『東征伝』では八月一日にその名を「唐招提寺」としたとあり、ならば新田部親王の旧宅が寄進されたのはそれ以前のことでなければならないため、ここでの豊安の説は誤認であろう〉、また恩勅あって、薨した新田部親王の旧家を施された。大和尚はそこで、その地をもって聖朝の奉為に僧伽藍〈saṁghārāmaの音写、僧伽藍摩の略。僧伽の精舎の意〉を造られ、その号を招提寺と称された。というのも、大和上は、この国の行事〈僧徒のあり方・行儀〉について聞いていたためである。寺家には衆供〈僧衆への経済的供養〉があるとはいえ、しかし、それを外来僧の為に用いることはなく、また客僧に対しての供養は三日分のみ許されているけれども、もし縁故・面識が無ければ資供〈滞在に必要な諸物品・経費を提供すること〉することは無く、その故に十方の僧路〈仏教僧や仏教寺院のの本来のありかた〉は塞がれて、行人はその為に幸苦していたのである。そこで大和上は、代々の聖朝の奉為に広く大福田を開き、別して十方僧の往来修道の場所を立てて、無遮の供〈なんら制限を設けずに供養すること〉を設けることを発願された。(長い)日時に及んで寺に望み堂に向かう僧〈比丘。具足戒を受けた仏教の正式な出家者〉・沙弥〈小僧。具足戒を未だ受けていない見習い〉を区別せず、斗升〈供養の量〉を論ぜず、兼ねて資供に及んだのである。それは天竺の鷄頭末寺〈Kurkuṭārāma. 鶏園寺・鶏雀寺。Magadha(摩伽陀)はPāṭaliputra(華氏城)にAśoka(阿育王)が建立した大寺院〉や、大唐の五台山華厳清凉寺・衡岳寺〈南岳衡山の般若寺か?〉に准じたあり方であって、それをまさにここで行うものであった。
また、『仁王経』の所説にあるとおり(唐招提寺は)官籍を立てなかった〈『仁王経』に、国王など国家が仏弟子を世俗の官人や軍人のように管理し制限すれば、仏法は久しからずして滅びる、とされる。羅什訳『仁王般若経』「大王。未來世中一切國王太子王子四部弟子。横與佛弟子書記制戒。如白衣法如兵奴法。若我弟子比丘比丘尼。立籍爲官所使。都非我弟子。是兵奴法。立統官攝僧典主僧籍。大小僧統共相攝縛。如獄囚法兵奴之法。當爾之時佛法不久」〉。「もし貫籍して衆僧を録せば我が法は滅びるであろう。ただ六和〈六和敬。僧伽の行動指針。比丘が三業と戒と見と利において互いに尊重し協調すること〉を修し、同じく水と乳との如くに(和合して)崇めあうべし」とされた。このことから、十方の行者は共にこの伽藍に住み、仏法を住持して国家を鎭護したのである。そしてその後も、かの授戒の儀式は今時に至るまで数年を経ているけれども、なお一道であって別異無い〈鑑真当時と全く同様であること〉。これは和上の住持がまさに仏陀の意趣にかなっていたからこそである。
豊安『鑑真和上三異事』(日仏全, vol.113, p.150b-151a)
ここには当時の寺院のあり方の一端が具体的に描かれています。就中、唐招提寺(鑑真)が「但修六和。同崇如水乳之(ただ六和を修し、同じく崇めること水と乳の如し)」としていたと特記されているのは、当時の僧徒らのあり方がそれと真逆であったからのことに違いありません。
六和とは、六和合あるいは六和敬ともいい、比丘が互いに①身(礼拝)・②口(讃嘆)・③意(信心)・④戒(戒律)・⑤見(見解)・⑥利(施食・寄進)の六点について等しく、皆が共有し同一とすることを意味します。印度以来、僧が根本指針としてきたものであって、これらを護持することにより僧伽が運営され保たれます。六和とは、「一味和合とは何か」を具体的に示したものです。
(一般に、今の僧職者のほとんどは、一味和合の意味を事なかれ主義的・事大主義的に理解し、なんらの律儀や規律、そして自浄作用も持たずしてただ馴れ合うばかりの「烏合」をもって和合の意味と捉え違いしています。しかし、一味和合とは、同一の思想すなわち仏教を奉じ、厳密な規律を有てこれを維持する僧伽のあり方を意味するものであって、無戒・破戒の僧形者らが口にするようなものではありません。)
しかしながら、当時の寺院は、これは今に至るまで同様だと言って良いことですが、まったく縁故主義であって、仏教本来の四方僧伽であるとか一味和合などというあり方など全くとられていなかったことが、この記述によって知られます。そして、いくら具足戒を皆が受けるようになっていたとしても、本来は決して持ち込んではならないはずの出家以前の出自や門閥がそのまま出家社会に持ち込まれてしまったいた旧来のあり方を正すことは出来なかったのでしょう。ましてそれを官職・官寺にあっては為し難いものであったことから、鑑真は天皇や公卿の後援を受けて唐招提寺を建立したのでした。
そうした鑑真の遺志をその弟子らもよく意識し、その没後以降も平安初期の豊安の頃までは確かに継承されています。
孝謙天皇の次なる淳仁天皇の治世には、恵美押勝の乱が勃発。ついに孝謙天皇は称徳天皇として重祚するなど政変があって、その政権の中枢に僧ながらも道鏡が坐すなど異例の体制となります。けれども、結局は道鏡は失脚して、称徳天皇も崩御。次の光仁天皇代の朝廷では、血なまぐさい権力争いにあけくれ、それに基づく恐れから御霊信仰もますます盛行。その頃には南都の諸大寺の権力・財力は大きくなりすぎてもいたようです。
そのような娑婆における、人のおぞましき性が遺憾なく発揮される中、期せずして帝の地位に登ったのが山部親王、すなわち桓武天皇でした。

桓武天皇は、政権の行き詰まりと政変次々と勃発する朝廷のありかたを打開し、また強大になりすぎた南都諸大寺の影響から逃れ、またそれを弱めるため、都を平城京から長岡京、そして平安京へと遷します。そこで、新たな都における政権を支える新たな仏教の担い手たる者として桓武帝に見出され、期待された人が最澄でした。
実際、最澄は桓武帝の内供奉十禅寺にも抜擢されるなど桓武帝に寵愛・期待されていました。ついには、桓武帝の肝いりによって新たに制度化された還学生(短期留学生)に選ばれ、遣唐使に随行して渡唐。そこで最澄は、『法華経』をこそ至高のものとし核心とする教義を擁する天台宗を、数ヶ月という極短い間ながら天台山にて学び、日本へと伝えています。その翌年正月、最澄が天台宗の開宗の勅許を申請すると、一月も経たずに認められ、その年分度者二名が許されています。
最澄はそれから前途洋々となる、はずでした。しかし、その後すぐに最大の後ろ盾であった桓武帝は崩御。いや、おそらくは桓武帝の健康状態が思わしくなかったために、最澄の天台宗開宗の申請は早急に処理されたようです。いずれにせ最澄は、新たに自ら立てた天台宗を広め、またその勢力を拡大すべく活動を展開していくのですが、そのほとんど全ての面において、彼の思うようにいくことはありませんでした。
天台宗の立宗が許されてからわずか十二年余り、最澄は突如、極めて常識外れの主張と要望を朝廷に提出しています。それが一般に『山家学生式』と称される、弘仁九年〈818〉から翌十年〈819〉の間に立て続けに上奏された三部の表です。
『山家学生式』とは要するに、自身の天台宗の僧徒だけは国家から特別扱いされることを求めたものでした。具体的には、天台の僧徒となる者については、従来の行政上の手続きと異ならせ、また印度の釈尊以来の出家法および受戒法に依るのではなく、ただ十善戒を受けることによって沙弥出家とすた上に、『梵網経』所説の戒を受けることによって菩薩比丘させ、なおかつ十二年間は比叡山から降ろさせないことを認めてほしい、というものです。
年分度者二人柏原先帝新加天台法華宗傳法者凡法華宗天台年分。自弘仁九年。永期于後際。以爲大乘類。不除其籍名。賜加佛子號。授圓十善戒。爲菩薩沙彌。其度縁請官印
凡大乘類者。卽得度年。授佛子戒爲菩薩僧。其戒牒請官印。受大戒已。令住叡山。一十二年。不出山門。修學兩業
年分度者二人 柏原先帝〈故桓武帝〉は、新たに天台法華宗の伝法者を加えられた《第一条》
およそ法華宗天台の年分度者は、弘仁九年〈818〉より永く後際〈未来世〉のために、これを大乗の類とする。(民部省が管理する)その本籍の名を除かずに「仏子」の号を加え賜り、圓の十善戒を授けて(まず)菩薩沙弥とする。その度縁には、(太政官の)官印を請う。
《第二条》
およそ大乗の類は、すなわち得度の年に、仏子戒を授けて菩薩僧とし、その戒牒には(太政官の)官印を請うこと。大戒を受け終わったならば、比叡山に住させ、十二年間、山門から出させること無く、(止観業と遮那業との)両業を修学させる。
最澄『山家学生式』「天台法華宗年分学生式」(『伝教大師全集』, vol.1, p.2)
当然、このような最澄の突拍子もない上表の内容は、その逐一について僧綱は批判を加え、いかなる根拠をもってそのような主張が仏教として正当たるのかを問うています。
(ここには一つだけではなく複数の問題発言が含まれているのですが、その詳細は別項「最澄『山家学生式』」を参照のこと。)
例えば、最澄は、従来いかなる宗に属そうともその年分度者として抜擢された者は、正月八日から一週間にわたって行われた御斎会の最終日に得度する習わしとなっていましたが、それから天台宗徒に限って除外させ、別途に比叡山にて桓武帝の忌日に(しかも十善戒を受持することによって)得度するよう変えるよう求めていました。しかし、そのようにするにはもちろん何らかの根拠、正当な理由が必要です。そこを僧綱に問われた最澄は、以下のように答えています。
開示宮中出家非清淨明據五十三
僧統奏曰。何以宮中出家非清淨已上奏文 論曰。宮中功徳。雖是清淨。而出家度者。未盡清淨。乃有山家度者不愛山林。競發追求。已背本宗。跉𨂲貧里。又不顧眞如。不畏後報。爲身覓財。爲名求交。如來遺教。因玆沈隱。正法神力。亦復難顯。若不改其風。正道將絶。若不求清淨。排災無由。是故。五臺山五寺。永置山出家。興善寺兩院。常立爲國轉經。未度之前。住山諳練。已度之後。住十二年。是豈非清淨也
宮中での出家が清浄にあらざることの明拠の開示 第五十三
僧統は(嵯峨天皇に)奏して曰く、「(最澄は)何を根拠に宮中〈大極殿(清涼殿)〉での出家が清浄ではない、というのか(根拠不明であります)」已上奏文と。
(私最澄はこの僧統の奏文について)論じて曰う。宮中の功徳は清浄であるとはいうものの、しかし(そこでの)出家度者は未だ盡く清浄でありはしない。というのも、山家〈天台宗〉の度者〈年分度者〉でありながら山林(に起居すること)を愛せず、競って(世事を)追求する者があって、すでに本宗〈天台宗〉に背き、貧里に跉𨂲している。また真如を顧みることなく、後報〈業果・後生〉を畏れず、身のために財を覓め、名誉のために(地位ある者や裕福な者と)交ることを求めている。如来の遺教はこれに因って沈み隠れ、正法の霊妙な力はまたさらに顕れ難くなっている。もしこのような風潮を改めなければ、正道はまさに絶えるであろう。もし清浄であることを求めなければ、災いを排うことなど出来はしない。このようなことから、五台山の五寺は永く山に(新たに得度した)出家者を置き、大興善寺の両院は常に国家のために経を転読する者を立てたのである。得度する前には山に住させて(経文など)諳んじるなど習練させ、すでに得度した後には十二年、(山に)住させるのである。それがどうして清浄でないというのか。
最澄『顕戒論』下巻(『伝教大師全集』, Vol.1, p.181)
御斎会の最終日に得度することは日本独自の風習であるため、これを仏典の根拠に因って云々することは出来ません。そこで最澄が求めた得度の場所を変更することの理由は、「宮中における得度が清浄でない」というものでした。ここで最澄が述べる理由は結局、自身の門弟である天台の年分度者が「逃げてしまう」ことであって、どこまでも「そりゃ手前の責任であろう」という話です。しかし最澄は、その原因が「宮中で得度たから天台門徒が逃げるのだ」という、責任転嫁も甚だしい言をもってしています。
(大方、最澄が僧綱からの批判やその根拠の問いに対して答えんとした『顕戒論』は、以上のようなはぐらかしや責任転嫁、あるいは自身の誤読や誤解に基づく論調に満ちたものとなっています。)
これは、「最澄の純粋に大乗を志求する高邁な精神、その理想を具現化するための教育構想」などでは到底なく、完全に自宗の門徒が他に逃散しないようにするための行政的拘束を仕掛けるためのものです。十二年間籠山させるというのも、ただ単に行政的に拘束するのではなく、身体的にも徒弟を長期間強制的に拘束して洗脳教育するためもので、その(当時としても異常であると批判された)仕組みを、やはり行政的に認定してほしいことをいったものです。比叡山で今もそのごく一部の者が行っている十二年籠山行とは、そのような発案のもとに生み出されたものであって、最澄の言に従えばすべての天台宗徒が絶対的義務として履行しなければならない筈です。
いずれにせよ、そのどれもこれもが否定的な意味で驚天動地の主張というべきものでした。まず仏典にその正統な根拠がなく、また印度以来の伝統的にも全くありえないものだからです。当然そのような主張に対し、僧寺を統制する国家機関であった僧綱に属する諸学僧だけでなく、南都諸大寺もまた猛烈な批判を加えています。それは朝廷としても認めることなど出来るものではありませんでした。
そこで最澄はその批判に逐一反論して朝廷に自身の主張を認めてもらうべく、『顕戒論』およびその他の上表文を矢継ぎ早に提出しています。しかし、それもただ論点をずらそうとしたものであったり、根拠として挙げた仏典の誤読や我田引水に基づくものであったり、単に僧綱を罵倒するだけとなっていたりなど、まともな反論とはなっていません。
ところで、前時代の史学者や仏教学者には、一時代を席巻した唯物史観に基づき、あるいは何でも政治的闘争・階級闘争などとして歴史を眺めようとした者が多くあり、理知的でなくむしろ感情的・信条的にアレコレ競って立論していたように思います。
そこで、この最澄と僧綱や諸大寺との論争について、「仏教改革を推し進めようとする若き革命家たる最澄と、旧態依然として既得権益者であり、堕落した南都六宗の利益代表たる僧綱との対決であった」などといった類の理解をする人が非常に多くありました。そして最澄は「ほとばしる人間性を開花させるため、僧綱という政治的権力からの抑圧から脱すべく、純粋な宗教的情熱をもって闘争した戦士」といった類の、今からすると実に滑稽で奇異に感じられる表現が様々になされ、理解されてきました。そしてそのような従来の理解・態度に対する反省・批判は、いまだ学者の間でもほとんど見られません。
しかし、そのような前時代のポン助学者らの多くは、この論争の本質をまったく理解しておらず、彼らが言ったようなことでは全くありません。
最澄が何故そのようなことを云い出したのか。その理由、動機は一体何であったか。それは、立宗間もない天台宗がすでに衰亡して無くなろうとしていたことの一点にあります。
鑑真一行の渡来以降、戒壇院が創立されてからは、どの宗派において出家する者であっても、正統な出家者(比丘)として認められるためには、どうしても天下三戒壇(東大寺戒壇院・筑紫観世音寺戒壇・下野薬師寺戒壇)のいずれかにて具足戒を受け、そのすぐ後の雨安居期間はそこで律儀の基本的事項について修学する必要がありました。
最澄もまた数え年二十のおりに戒壇院で具足戒を受けて比丘となっていたのであり、そのようにしなければならないのはもちろん新立の天台宗の徒であっても例外ではありませんでした。そこで、天台の年分度者らもやはり比丘となるには南都にて具足戒を受けています。しかし、戒壇院にて具足戒を受けたが最後、最澄の元に帰ってくるべき者が帰ってこず、そのまま他宗に転向、といった事態が頻発していたのです。
最澄は天台宗がそのような惨状・窮地にあることを朝廷に訴えています。
而今圓宗度者。受小乘律儀。忘圓三聚。爭求名利。各退無漏。自去大同二年至于弘仁十一年。合一十四箇年。兩業度者二十八口。各各随縁散在諸方。住山之衆。一十不滿。
しかしながら今、円宗〈天台宗〉の度者〈年分度者〉は小乗律儀〈具足戒〉を受けて円の三聚〈三聚浄戒。最澄はここで瑜伽戒ではなく梵網戒をもって「円の三聚」などと称している〉を忘れ、名利〈名聞利養。名誉と富〉を争い求めて、それぞれ無漏〈ここでは大乗、特に天台宗を意図した語〉から退転しております。去る大同二年〈807〉より弘仁十一年〈820〉に至るまでの合わせて十四年間、( 止観業〈807〉と遮那業〈807〉との)両業の度者〈年分度者〉は二十八口でありました。しかしながら、それぞれがなんらかの原因で諸方に離散してしまい、山〈比叡山。天台宗〉に留まっている者は十人にも満ちません。
最澄『上顕戒論表』(『伝教大師全集』, vol.1, p.256)
天台宗に年分度者二人が充てられてから十四年を経、一連の『山家学生式』を上奏してからは一年たらず後の弘仁十一年〈820〉二月二十九日にまた重ねて上奏した書にある一節ですが、最澄は天台宗の窮状を訴え、嵯峨帝にいわば泣きついています。
ここで最澄は、自身の天台宗の年分度者となりながら他宗に転向した、あるいは比叡山に留まるのを拒否していずこかに去った者について「名利を争い求め、各無漏を退く」などと批判して言っています。しかし、実際のところ、最澄の元から去った彼らの動機や目的などわかりはしません。まさか最澄に対して直接「わたくし、名利を求めておりますので、お暇を頂戴いたします」などと断りをいれた者などないでしょう。あくまで最澄からして、自身の元を去った者はおしなべてそのような類であると断じ、あるいは帝の手前そう言って(多くの年分度者に逃散されてしまった)自らを正当化しただけのことであったのでしょう。
それにしても、これは相当に深刻な事態です。天台宗開宗後十四年、その年分度者として僧となった二十八人中のうち、たった十人未満しか天台宗に残留していなかった。若干名が病死したのを除いても、その約七割が他宗に転向していたという事実。この残留率30%強というあまりに低い数字。ここで引き合いに出すのはいささかナンセンスですが、軍隊であれば間違いなく「全滅」とされる数字です。それは、その組織の発展・拡張など期す以前に、維持していくことも困難となる数です。
最澄は追い詰められていました。いや、離散した僧の最大の受け皿は法相宗であってこれを最澄が恨んでいたことは彼自身の文言から知られますが、しかし法相宗など他者が積極的に最澄を追い詰めていたというのでなく、自身の徒弟・門弟が次々離れていくという絶望的状況が、最澄を追い込んでいました。
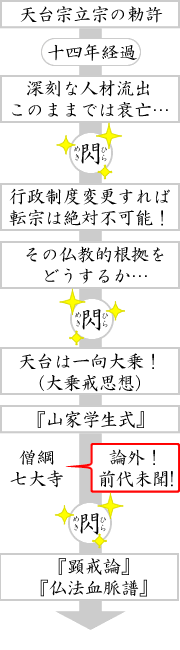
この残留率のあまりの低さが示しているのは、最澄自身の教育者としての人格、一宗の長としての人徳に問題があった、ということを意味したものと言えます。少なくとも、「最澄は優れた教育者であった」などと評価できるような数字では全然ない。最澄自身がこぼしているあまりに少ない残留率をして「教育者としてに優れていた」「指導者として卓越していた」などと言うことなど、どうやっても出来ません。
最澄はそれ以上、自宗の僧徒が逃散しないための方策として、随所に「先帝(桓武帝)の遺志である」などと亡き桓武帝の威光をちらつかせつつ『山家学生式』を上奏したのですが、しかし、まさか「このままでは我が天台宗は滅びてしまうから」などというだけの理由で、国家に行政制度を変更させ、あまつさえ仏教として従来の伝統的あり方をその根底から覆すことなど出来ないん。もしその主張が正当なものであり、真であるならば、それを自ら仏典に依って論証しなければならない。事実、最澄はそうすべきことを求められていました。
そこで最澄は、さまざまな典籍を縦横に駆使してその論拠としながら、実は自らの説こそが大乗本来の正統なものであったと主張するに至ります。といっても、『山家学生式』は僧徒の行政上の取り扱い、すなわち制度の変更をただ求めたものであって、そこに論拠など全く示されていません。その論拠を示すのは僧綱や諸大寺から批判された後に提出した『顕戒論』を初めとするその他の表においてのことです。
『山家学生式』は、自ら天皇に要望する動機は国家・天皇・人々のためとしながら、具体的に行政制度の変更を求めたのみの書です。
なお、天台宗における伝説によれば、彼は『山家学生式』を提出するに際し、驚くべき行動に出ていたと言われています。
以九年暮春《中略》自今以後。不受聲聞之利益永乖小乘威儀卽自誓願棄捨二百五十戒已
弘仁九年〈818〉の暮春、《中略》「今より以後、声聞の利益を受けず、永遠に小乗の威儀にそむく」と自ら誓願し、二百五十戒〈律・具足戒〉を捨て去った。
釈一乗忠『叡山大師伝』(『伝教大師全集』, Vol.5, 附録 p.33)

これは最澄自身の著作にある言ではなく、あくまでその伝記にあるものであって、その真偽は定かではありません。しかし、以上のように天台宗での伝説では、最澄は弘仁九年暮春すなわち『山家学生式』を提出する年、自ら具足戒をすすんで放棄したとされています。これが事実であったならば、最澄は比丘をやめて沙弥となっていたことになります。しかし、後の彼自身の言動や彼への僧綱の態度からして、これが事実であったとは考えにくいことです。
そもそも天台の実質的開祖たる智顗および天台宗第六祖たる湛然における比丘律儀と菩薩戒に関する理解とその実際と、最澄の主張と行動は到底同じとは言えない、まるで異なったものです。
例えば、入唐した最澄の天台教学の師となった道邃と行満の師であった湛然は、智顗に帰せられる『菩薩戒義疏』冒頭の一文を引きつつ以下のように述べています。
戒序云。聲聞小行尚自珍敬木叉。大士兼懷寧不精持戒品。今戒爲行本猶是小乘。棄而不持大小倶失。
『戒序』〈智顗『菩薩戒義疏』〉にこうある、「声聞の小行すら、なお自ら波羅提木叉〈比丘律儀の戒本〉を珍敬して(受持して)いる。大士〈菩薩〉の兼懐であれば、なおさら戒品〈比丘律儀および菩薩戒〉を厳しく受持しないということがあろうか」と。今、戒〈文脈からして律儀のこと〉を行の本としてなお是れを小乗と言い、棄てて持たざれば大乗・小乗ともに失うであろう。
湛然『止観輔行傳弘決』(T46, p.162b)
最澄の主張は、むしろ最澄が至高とした本家の天台宗における最も重要な諸典籍によって破綻します。以上挙げた他にも、最澄の主張を真っ向から否定するような大乗の典籍は枚挙に暇がありません。
しかし、最澄は以下のように主張しています。
凡佛戒有二
一者大乘大僧戒 制十重四十八輕戒。以爲大僧戒
二者小乘大僧戒 制二百五十等戒。以爲大僧戒
凡佛受戒有二
一者大乘戒 依普賢經。請三師證等 《中略》
今天台年分學生。幷回心向大初修業者。授所説大乘戒。將爲大僧
二者小乘戒
依小乘律。師請現前十師白四羯磨。請清淨持律大德十人。爲三師七證。若闕一人不得戒今天台年分學生。幷回心向大初修業者。不許受此戒。除其久修業
《第三条》
およそ仏の戒には二種ある。
一つは大乗大僧戒。十重四十八軽戒を制し、以って大僧戒とする。
二つは小乗大僧戒。二百五十等の戒を制し、以って大僧戒とする。
《第四条》
およそ仏の受戒には二種ある。
一つは大乗戒。『観普賢菩薩行法経』にしたがって三師証等を請じる。《中略》
今の天台年分学生ならびに回心向大の初修業者には、すでに説いたところの大乗戒を授け、それによって大僧〈比丘〉とするのである。
二つには小乗戒。小乗律に従って(受戒の)師として現前の十師を請じて白四羯磨〈僧伽における重要事項を決定するための形式〉する。清浄持律の大徳十人を請じて、三師七証とする。もし(十人のうち)一人でも欠ければ戒を得ることは出来ない。今の天台年分学生、ならびに回心向大の初修業者には、この(小乗)戒を受けることを許さない。ただし久修業の者は例外である。
最澄『山家学生式』「天台法華宗年分度者回小向大式」(『伝教大師全集』, vol.1, pp.7-9)
先に挙げた「天台法華宗年分学生式(六条式)」における「授圓十善戒。爲菩薩沙彌(圓の十善戒を授けて菩薩沙彌と爲す」というのも、常識外れで根拠も無く、当然前例も無いことでありましたが、この「天台法華宗年分度者回小向大式(四条式)」においても最澄の無理な主張を見ることが出来ます。先ずは「一者大乘大僧戒 制十重四十八輕戒。以爲大僧戒(一つには大乘大僧戒。十重四十八輕戒を制して以て大僧戒と爲す)」というのが大問題で、そのような主張を支える正当な根拠はありません。
いや、これはむしろ最澄の恣意的な詭弁・強弁であったと見たほうが自然です。智顗の『摩訶止観』にしろ湛然の『止観輔行傳弘決』にしろ、彼は間違いなく読んで、いや、読み込んでいたのであるから。
ここで最澄が「今天台年分學生。幷回心向大初修業者。不許受此戒。除其久修業(今の天台の年分學生、幷に回心向大の初修業の者には、此の戒を受くることを許さず)」などと言っているのは、そのためには必ず東大寺戒壇院で受けなければならず、しかし僧徒がこれを受けたに南都に言ったならば天台宗から逃げられ、ほとんど帰ってこなくなるに違いない、と思っていたからに他なりません。彼は自らの門弟を信じていなかったのです。
もっとも、最澄がいう「仏教の戒には、大乗大僧戒と小乗大僧戒がある」などということについて、それをもって言わんとした最澄の意図は兎も角としても、ただ言葉として言うのであれば根拠がまるでないわけでもありません。たとえば、仏教の戒に大きく分けて二種あることについて、大乗の『涅槃経』において、戒には声聞戒と菩薩戒とがあることを説いています。
戒復有二。一聲聞戒。二菩薩戒。從初發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩戒。若觀白骨乃至證得阿羅漢果。是名聲聞戒。若有受持聲聞戒者。當知是人不見佛性及以如來。若有受持菩薩戒者。當知是人得阿耨多羅三藐三菩提。能見佛性如來涅槃。
戒にはまた二種がある。一つは声聞戒、二つには菩薩戒である。初めて菩提心を発してからついに阿耨多羅三藐三菩提〈無上正等覚。この上ない悟り〉を得るに到るのを名づけて菩薩戒という。白骨を観じてよりついに阿羅漢果を証得するのを名づけて声聞戒という。もし声聞戒を受持すれば、まさに知るべし、その者は仏性および如来を見ることがない。もし菩薩戒を受持すれば、まさに知るべし、その者は阿耨多羅三藐三菩提を得て、よく仏性と如来と涅槃を見るであろう。
曇無讖訳『大般涅槃経』巻第二十八 獅子吼菩薩品(T12, p.529a-b)
ここで『涅槃経』は、戒の内容の異なりで声聞と菩薩の違いがあるというのではなく、その修行(菩提心の有無・六波羅蜜の有無)と見解の内容によって、声聞と菩薩との異なりがあることを言っているに過ぎません。
結局、最澄の言う「小乗大僧戒」とは完全に異なった「大乗大僧戒」なるものの根拠は、最澄はそれを『梵網経』に求めているのですけれども、そのような主張を支える一節は『梵網経』のどこにもありはしません。最澄は天台教学に基いて法華一乗を標榜していたものの、この点について全然、本来の天台的でもなく一乗でもないむしろ排他的・一向的態度を採っており、本家の天台教学からしても完全に逸脱したものとなっています。
いや、最澄自身はそれが「三国伝来」だとか「印度以来の正統なるあり方」などと懸命に主張していはしますが、それらはまるで事実と異なるものとなっています。そして最澄は、自身の主張が極めて常識外れで全く伝統に乖いたものであることを十分承知していたようです。
例えば、最澄の遺言として伝えられるものの中に面白い一節があります。
一。又我同法中。第一定階也。先受大乘戒者先坐。後受大乘戒者後坐。若會集日。一切之所。内祕菩薩行。外現聲聞像。可居沙彌之次。除爲他所讓者。
一つ。また我が同法侶〈一門〉においては、第一(に重要な事項)は定階〈序列〉である。先に大乗戒〈梵網戒〉を受けた者が先〈上座〉に坐し、後に大乗戒を受けた者は後〈下座〉に坐さなければならない。ただ、もし会集の日〈他宗の僧侶も出仕する宮中や官寺などにおける法会〉など、すべての場所においては、「内に菩薩行を秘め、外に声聞の像〈声聞僧と同じ姿・振る舞い〉を現し」〈『法華経』の一節〉、(他宗の)沙弥の下座に坐さなければならない。ただし、他宗の比丘や沙弥に(上座を)譲られた場合を除く。
『根本大師臨終遺言』十箇条之内第五(『伝教大師全集』 Vol.1, p.299)
この『根本大師臨終遺言』が真に最澄の遺言であったものかは知られません。しかし、これが最澄の真の遺言であったならば、彼はやはり大乗戒を受けただけで比丘になりえないことを知っていたことになります。ここで、「可居沙彌之次(沙彌の次に居すべし)」と言っていることは、最澄が「天台法華宗年分学生式}(「六条式」)で主張した、そもそも十善戒を受けさせて沙弥とすることからすでに非常識で、他に通用するもので全くないことをよくわかっていた証となるものです。
ここで彼は、決して「大乗の僧は常に謙虚でなければならず、よって常に謙譲して他者より下座に座さなければならない」などという意味で言っているのではありません。自宗内においてのみ、彼に依って捏り出された単受梵網戒による序列によって厳密にその上下を定めるべきことを言いつつ、しかしそれは他で通用する筈もないことを彼は十分認識しており、故にその点を間違えないようにわざわざ遺言にまでして弟子に残していた、ということになるでしょう。
現在の天台宗では、最澄は『顕戒論』によって僧綱や南都の諸大寺からの批判をく完全に、残りなく論破したものとしています。しかし、それも事実と異なります。
実は僧綱は、最澄の不合理な主張の真意を直接質すべく、彼を直接呼び出して天皇の御前でその是非を問おうとしていました。しかしながら、最澄は、そのような僧綱からの召喚に対し、「文字上のやり取りだけで充分である」などと拒否。それは、自身の旗色が非常に悪いことを自覚してのことでもあったのでしょう。
もし最澄が、その主張に全面的な自信と信仰とがあったならば、それをむしろ天皇の御前など宮中にて堂々と開陳し、僧綱や奈良の学僧らを堂々と論破し、自らの正しきを論証した筈です。けれども、彼はそれを拒否した。そしてさらにはおそらく、この問題について旗色の非常に悪かった最澄のいわば公式敗北を危惧した公卿の配慮によっても、ついに実現されませんでした。
実際問題、もし天皇の御前など宮廷において、この問題について最澄が僧綱との対論で敗北してしまったならば取り返しがつかないことになり、最澄の天台宗は文字通り「終わっていた」でしょう。朝廷としても、亡き桓武帝の肝いりで天台宗が立宗されたという、その遺志を承知していた手前、それは避けなければならない事態でした。結局、最澄はその論争の決着をつけることも出来ず、また朝廷からの許しが降りることもなく、不遇な晩年を過ごし、ついに死を迎えています。この問題は最澄の生前には、どうしても決着出来なかったのでしょう。
最澄の主張は本来、一乗三乗であるとか声聞菩薩がどうのといった宗論では決してなく、まったく天台宗を存続させるためにひねり出された政治上のものであったのですが、しかし最澄は宗論の土俵に上げていったのでした。

この最澄の大乗戒壇論争について、現代において理解されている構図は、おおかた「南都諸宗の利益代表ともいうべき僧綱は、戒壇という権威・既得権益を、新興勢力の天台宗(最澄)に奪われるのを防ごうとし、最澄は自らの信念を貫き、あくまでそれに抗って革命を起こそうとした」などという、いわば「権力者・既得権益者(悪) 対 孤軍奮闘する革命者(善)」といった、まことお粗末で短絡的な団塊世代的左傾化した思考によるものが多いようです。
しかしながら、この大乗戒壇についての争点は、従来の権威や因習、既得権云々などといったものでは全くありません。それはただ、最澄の切迫した政治状況からひねり出されたもので、彼にとっては妙案であり、またその唯一の解決策でした。
それを強いて好意的に見、旧弊を打ち破ったとか、大乗の真面目であるとか、革新的な一大功績であったとか、人間主義的であったとか賛嘆する人もあるのでしょう。しかし、それを契機として現実に何が日本仏教において起こり、日本史上その「人間主義的」・「核心的な人々」が何を起こしてきたのか。もう一度よく確認をする必要があるでしょう。
最澄の『山家学生式』における主張、見方を変えたならばそれは、日本に鑑真一行が比丘律儀を伝えた以前の、むしろ仏教として未開・不完全なる状態への「先祖返り」を志向したものであった、と評すべきことです。
というのも、鑑真一行渡来以前における日本で僧であると称していた者のほとんど多くは、自誓受戒という方法で具足戒を受けて比丘となり得ると考えており、実際『占察経』の所説にしたがって自誓受戒するだけで済ましてたからです。最澄の主張は結局、その典拠を『占察経』から『梵網経』(受戒法としては『観普賢菩薩行法経』)に変えただけのことでした。そこで生じた大きな問題が生じたのも、やはり鑑真渡来以前の僧らと同じく、その説の正当性が無く、また伝統としても正統なものでなかったことによります。
(鑑真渡来とその後については別項「真人元開 『唐鑑真過海大師東征伝』」を参照のこと。)
そうした最澄の動きは、ただ鑑真以前に戻ろうとするものであったと評し得るばかりではありません。当時僧綱は、『山家学生式』に対して激しい批判を加える中、最澄をして往古のインド以来悪名名高い僧Mahādeva(大天)と同一視していました。
開示叡山不類大天明據十一
僧統奏曰昔依大天。部分二十。佛法因斯。遂令衰滅。今比叡山。部判人法。則知。是滅法之先兆也。已上奏文
論曰。滅後大天者。有犯過人罪。像末叡山者。無犯過人罪。昔五事者欺誑弟子。故令佛法衰滅。今四條者。依經引導。故令佛法中興。僧統卜兆。不足可信也。《中略》
明知。大天五事。爲隱己過。叡山四條。爲傳圓戒。五事之僞。出於胸臆。四條之式。據於聖典。回小向大。一乘正義。執三謗一。諸佛不印。耆年上座。順理小衆。少年大天。違理多衆。遂使少年乘船。百妄頓絶。耆年移國。一眞來今也。
比叡山〈最澄〉は大天に類したものでないことの明拠を開示する 十一
【僧統】:その昔、大天〈Mahādeva〉によって(僧伽が)二十にまで分裂しました。仏法はこれを契機として、ついに衰滅してしまったのです。今、比叡山は(大天のように)人と法とを判別して(これを決定的に分裂させようとして)おります。すなわち知られるのです、これはまさしく滅法の先兆であると。已上奏文
【反論】:仏滅後の人である大天は、過人の罪〈大妄語。達していない境地に達したとの宗教的嘘言。波羅夷罪。大天は自身を偽って阿羅漢であるとしていた〉を犯していた。しかし、像法・末法の世にある比叡山〈最澄〉は、過人の罪など犯してはいない。その昔、(大天が主張した)五事は仏弟子を欺誑し、その故に仏法は衰滅した。今、(私最澄が先に奏上した)四条〈『法華宗年分度者回小向大式(四条式)』〉は、諸経典に基いて(仏弟子を)引導せんとするもの。その故に(私最澄の主張は)むしろ仏法を中興するものである。僧統の卜兆〈占い。僧綱の上奏を「占い」の類の怪しげなものと揶揄し批難した言〉など、信ずるに値しない。 《中略》
明らかに知られるであろう、大天の主張した五事とは、彼自身の過失を隠そうとするためのものであったことが。比叡山が主張するところの「四条」とは、円戒を伝えんがためのものである。五事という虚偽は(大天の)胸臆〈思惑。根拠なき感情的意図〉から出たものであるのに対し、「四条の式」は聖典に依拠したものである。(私最澄の主張する)「回小向大」は、一乗の正義である。(特に法相宗の宗義である)「執三謗一〈三乗に執着して一乗を謗ること〉」は、諸仏が意図されたことではない。(出家して年を経ており仏意を心得ていた)耆年の上座僧らは、理に順じたものであったがその数は少なかった。しかし(出家して間もなく仏意も知らぬ)少年の大天らは、理に違うものでありましたがその数が多かった。(それはまさしく比叡山の天台宗と、南都の法相宗・三論宗らとの勢力差が同じような状況であるかのようなものである。)遂に(仏意を知らぬも大勢であった)少年〈南都諸大寺の学僧、僧綱ら〉を船に乗せて遠くに遣れば、(法相宗・三論宗らの宗義たる)「百種の妄教」はたちまち絶える。対して、(仏意を知るも少数である)耆年〈私最澄が主張する天台宗〉が国を移ったならば、一乗の真実が今に実現するのである。
最澄『顕戒論』上(『伝教大師全集』, Vol.1, p.59)
大天とは、仏滅後百二十年ほどのインドに実在した比丘の名で、それまで一枚岩のごとくであった僧伽(サンガ)を大分裂すなわち「破僧」にいたらせた首謀、とされる者です。破僧は五逆罪といわれる仏教における大罪の一つで、その故に支那・日本に伝わった仏教においても、ほぼ通じて大悪人と評される人です。
平安の当時、その大天に最澄は比せられていました。無論、最澄はそのような僧綱からの批判に、上記のように「私は大天などと同様では決してない」と猛反発しています。「自分は仏典を論拠として主張しているのであって、大天のように恣意的な、無根拠なる妄説を主張しているのではない。むしろ私こそが正しいのであって、奈良の学僧らこそが悪しく誤っている輩である!」と。
しかしながら、前述の通り、最澄は仏典を牽強付会している点があまりに多く、また彼が前提としている「伝統」や「印度でのあり方」について明らかな誤りが多々あって、しかもそれをおそらくは自覚しながら強弁していたと思われる傍証もありすぎるほどにあります。
そしてなにより、これは結果論でありましょうし、最澄自身からすればまさに不本意極まりないことになるでしょうけれども、その主張が現実化した結果、自身の膝下である比叡山およびその後の日本仏教がどのような状態となっていったかを見たならば、僧綱の学僧らが最澄を大天に比していたのは、まさしく炯眼であったと言うべきです。いや、ある意味、最澄の主張とその影響は、日本という極東の僻地に限ったものではあったにしろ、大天のそれをさらに上回って次元すら異なった、はなはだ悪しきものとなってしまったともいえます。
日本仏教における、戒律についての世界にも例を見ない異常な思想とあり方の元凶は、まさしく最澄にこそ帰せられると断言して可なるものです。
そのような見方は、何も仏教学・文献学の成果に基づき得る今であるからこそ持ち得るような、特殊なものでもありません。先程から述べてきたように、往古の日本においても最澄の梵網戒の位置づけ、梵網戒単受で比丘となり得るなどという主張が異常であると認識されていました。
これはすでに平安期が終わり鎌倉期初頭におけることでありますが、すでに長らく天台宗のそのようなあり方が認知されていた当時にあっても、やはり最澄の主張は異常であったとする見解を持つ僧がありました。
頃有大徳自看讀戒藏云。山門別授菩薩戒非正。破云。遠截七佛遺流等云云。親聞此言。哀慟無極。其人已堕魔網。千佛無能救乎。其人欲生般若。還燥般若種子。尤可悲矣。學般若者。惡尚不可憎。況善哉。凡觀達迷中是非。是非倶非。夢裏有無。有無倶無。其是般若也。何況如來説教區區。大士弘經品品也。傳教大師別授菩薩戒。有何過失哉。我大師若建立別授菩薩戒者。此土末代無持律人。因何結戒縁哉。況彼時。賢人名匠。乏其人哉。何況別授菩薩戒。特有由乎口訣有別。 《中略》
自今已後。只守汝自情。莫説伝教大師別授菩薩戒之正否矣。大師已逝。誰會汝謗難哉。汝破大師云。截七佛遺流云云。予代大師救汝云。開三惡之門戸。可哀可哀。善戒經文有會釋。如別文。異梵網經意也。
最近、ある大徳がみずから戒蔵を研究して、「山門〈比叡山・天台宗〉で別授にて行われている菩薩戒は正統なものではない」とし、これを批難して「往古からの七仏の伝統を断じたものである」などと言われていた。私はこれを直接(彼から)聞いたのだが、あまりの哀しみに衝撃を受けたほどである。その人は、すでに魔網に絡み取られてしまったようである。千人の仏陀によってしても救うことなど出来ないであろう。その人は、(自ら)般若〈智慧〉を生じようとしながら、むしろ般若の種子を乾かしてしまっている。もっとも哀しむべきことである。般若を学す者は、悪をすら憎むべきではない。善については言うまでもない。およそ「迷いの中の是非」を達観したならば、是非は共に誤りなのである。たとえば夢の中の有無は、有無ともに無なのであるから。そのような認識が般若というものである。ましてや如来の教説はまちまちであって、菩薩の弘経〈大乗経典〉はさまざまであることは言うまでもない。
伝教大師の主張された別授の菩薩戒に、一体どのような過失があるというのか。我が大師がもし別授の菩薩戒を創始されていなかったならば、この日本における末代において、持律の人など無かったであろう。(彼は)何の由縁で戒縁を結ぶことが出来たというのか。ましてや彼の時、賢人・名匠がその人の周りに乏しかったわけでもなかろう。言うまでもなく、別授の菩薩戒が創始されたのには、特にその由縁があってのことである口訣が別にある。 《中略》
今より以降、ただ汝の自情〈自身の私的見解。栄西は批判者の主張を「私的」で「誤ったもの」とみなした。しかし、批判者のそれこそむしろ諸仏典およびインド以来の伝統に基づいたものであって、最澄の主張こそ「自情」であった。ところが栄西は、それを認めることが出来ず、よってここで感情的な反論を展開している〉を守り(口を閉ざして)、伝教大師が説かれた別授の菩薩戒の正否を論じてはならない。大師はすでに逝去されているのである。一体誰が汝の誹謗について反論しえるであろうか。汝は大師を批難して「往古からの七仏の伝統を断じたものである」云云と言った。私栄西は、大師に代わって汝を救うために言おう、「(そのような言は)三悪の門戸を開くものである」と。哀れむべきことである、哀れむべきことである。『善戒経』にある一節会釈有り。別文に同じは、『梵網経』の意図することとは違うのである。
栄西『出家大綱』
ここで俎上に載せられている「ある大徳」。その人は具体的に誰であるか栄西は明らかにしていませんが、当時高名であって戒律に通じた人であったに違いありません。それは、時代背景を考えたならばおそらく解脱上人貞慶その人であり、あるいはその弟子興福寺常喜院の戒如など関係深い人であったでしょう。解脱上人や戒如の薫陶を受け、やや後代に実際に戒律復興を果たした叡尊や覚盛などが同様の見解を持っているので、具体的に誰かであるかは不明ですが、この流れにあった人と見て間違いありません。
(栄西については別項「栄西『出家大綱』」を参照のこと。)
最澄が主張したところの梵網戒理解とその位置づけに対する批判は、上に述べているようにむしろ最澄生前の当時から公的になされていたことであって、その「ある大徳」は、いわばそれをなぞったものです。そしてそれがむしろ正常な見方でした。
いくら時を経て時代が変わろうとも、根拠がないこと、合理性が無いことが有るように変わりはしません。その根拠を捏造でもしない限りは。実際、現在においてもなお、仏教における戒と律との大原則やその歴史など伝統をまもとに学んだならば、やはり最澄の主張がいかに常軌を逸したものであって、栄西が憤った「ある大徳」に同じく、「遠截七佛遺流(遠く七佛の遺流を截つ」ものであるとの結論に達するに違いありません。
けれども、そのような主張は鎌倉期初頭にもなると、特に天台宗の流れにある人にとっては、むしろ逆に極めて非常識な「とんでもないこと」として見られ、決して受け入れることなど出来ない言となっていました。実際、そのような見解を持つ「ある大徳」に対し、栄西はかなり感情的に、言を極めて批判しています。そして、彼に対しては「伝教大師の主張された梵網戒の授受については決して、一言も批判してはならない」と、むしろそれがために説得力が全くないのですが、やはり随分と感情的な主張を展開しています。
鎌倉期初頭、古巣でもあった比叡山天台宗の僧徒らをするどく批判し、対立すらしていた栄西にしても、最澄とは絶対的な権威者であって、その主張や行業を「批判するなど以ての外である」という認識にあったことが知られます。
平安中後期には、高野山の空海と比叡山の最澄とは、日本仏教界における大巨人である、聖者であるとして、これは宗派を問わず一般社会にも広く認識されていました。ここにあるように、禅師にとって最澄は「我が大師」でやはり特別な存在であり、「(間違っているのはあくまで現在の天台宗徒であって、)最澄は特殊な理由からこれを創始されたのである」と理解しています。
もっとも、皮肉なことに、『興禅護国論』における栄西の主張と最澄のそれとを精細に見た時には、むしろ栄西は最澄を無意識的にしろ厳しく批判し、否定しているに変わりありません。最澄を祖師とする日本天台宗から浄土教や日蓮教などしばしば「仏教ではない」「新仏教」などと言われる者らこそ次々排出しているものの、戒律復古の契機となった者がほとんど現れなかったのは、その故無きことではありません。実に栄西とは例外的存在です。

最澄の死後ただちにその門弟らは権力争いを開始してしばらく収集がつきませんした。円仁や円珍が座主となった頃にひとまず落ち着いたかと思えば、彼らの死後ほどなくして、おそらくは最澄が夢にも思わなかったほどに比叡山は荒廃。その僧徒ほとんどが堕落の極致へと突き進んでいます。
なんとしたことか、いや、娑婆では珍しくもない話であり、鑑真以前の頃から続く寺家における門閥や縁故主義の悪しき性癖がここでも発露したに過ぎないのでしょう、比叡山では円仁と円珍との門弟らが門閥争いによって対立を深めていました。円珍が延暦寺第五世座主となって以降、第十五世に至るまで、その座主職のほとんど皆が円珍の門流で占めており、いわば円仁の門流は権力の座から排され不満が高まっていったのです。
そんな中、比叡山における一部の学生(学僧)を除いた大衆(行人)などといった者の中に、僧の衣体を纏いつつ鎧を着し、刀杖を携えて麻の白袈裟(裹頭袈裟)で顔を隠した武装集団、いわゆる僧兵が誕生しています。
特に、彼らが好んで携帯・愛用していた薙刀は非常に強力・効果的な武器で、都の検非違使など武士らに畏れられていたといいます。ここで、日本天台宗独自の制度としてそれを受けるのみで僧たりえるとしたその梵網戒においては、武装するということについて、いったいどのように説かれていか。
若佛子。不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬪戰之具。及惡網羅殺生之器。一切不得畜。而菩薩乃至殺父母尚不加報。況餘一切衆生。若故畜一切刀杖者。犯輕垢罪。
仏子は、いかなる刀・杖・弓・箭・鉾・斧など戦闘のための道具を所有してはならない。および(漁猟・狩猟のための)悪しき網羅など殺生を目的とした道具など、すべて所有してはならない。菩薩たる者、もし父母を殺されたとしても、決して報復してはならない。一切衆生は言うまでもない。もし故意にいかなる刀杖でもこれを所有したならば軽垢罪となる。
《伝》鳩摩羅什訳『梵網経』盧舍那佛説菩薩心地戒品第十 卷下
(T24, p.1005c)
梵網戒のみで事足りるとした比叡山は、その梵網戒の諸々の学処など完全に馬耳東風となって、むしろ軍事力を強めこそすれ弱めること、武装蜂起することなど決してありませんでした。
しかし、それがたとい政治的動機からとはいえ、結果的に梵網戒を至高とし、純大乗であると謳った最澄の門流からそのような輩が次々生まれてきたのは、最澄からすれば不本意極まりない事態であったでしょう。最澄の理想は、「大乗戒のみによって僧となった純然たる菩薩僧によってこそ、国家も人々も安泰となり、あちこちにひそむ悪僧は駆逐されて、大乗の教えがいよいよ盛んとなるに違いない」というものでした。
事実、最澄は生前、このように天皇に訴えています。
誠願先帝御願。天台年分。永爲大類。爲菩薩僧。然則枳王夢猴。九位列落。覺母五駕。後三増數。
誠に願わくば、先帝〈桓武天皇〉の御願でもあった天台宗の年分度者をもって、以降は大類の僧として菩薩僧とされんことを。そうすれば、訖哩枳王の夢に現れた(十匹の)猿のうち、(国や人々を混乱させる悪しき僧に比せられる)九匹〈南都六宗および諸大寺〉はまたたくまに追いやられ、文殊菩薩の(羊乗行・象乗行・月日神通乗行・声聞神通乗行・如来神通乗行という)五つの籠のうち、(菩薩乗であって無上正等正覚を得ることが定まっている)後の三つは、その数をいよいよ増して繁栄することになるでしょう。
最澄『山家学生式』「天台法華宗年分学生式」(『伝教大師全集』, vol.1, p.1)
最澄の中では天台宗比叡山の僧徒こそ「唯一の正しき猿」となるべきものだったのが、現実は真逆となって、むしろ比叡山の僧徒こそが真っ先に、こぞって「国家・人々を混乱に陥れる九匹の猿」となっていました。武器を持つだけならまだしも、彼らは人を殺めるのにも躊躇せず、それを往々にして「仏法」・「護法」にかこつけてさえいます。
仏教の威光や比叡山の地主神である日吉神の威光、そして京都鎮護の山とされた威光(宗教的権威)にかこつけ、また比叡山が桓武帝の肝いりで開かれたという威光(世俗的権威)にかこつけて、朝廷や貴族らに事あるごとにゆすりたかる、恐るべき悪質なゴロツキ集団、いわゆる山法師の嚆矢です。しかも京(洛中)から目と鼻の先の山中に巣食う。
それが生じたのはちょうど、比叡山中興の祖ともいわれる元三大師良源(912-985)が、第十八世天台座主の位に昇り詰めた頃のことでした。良源は、当時の叡山に跋扈するそのような僧徒らの堕落を嘆き、『梵網経』の読誦と梵網戒の護持などを訴えています。とは言えそれは、「ことさらに言わなければならない必要性があったからこそ」のこと。結局、当時の比叡山のゴロツキたちには、良源の持戒だ誦経だのを推奨する言などやはり全くどこ吹く風で、その諫言などまったく意味でした。
ついに良源は、むしろ彼ら無法者らを戒めていたのにも関わらず、四百年ほども時代が下った応永十六年(1409)に著された『山家要記浅略』において、あわれにも「僧兵の初めは良源にあり」などといった汚名を着せられるに至っています。
もっとも、円仁の門流(山門派)であった良源は、そのような僧兵などと言われる者らを厳しく戒め排していた反面、当時すでに深い敵対関係にあった円珍の門流(寺門派)の居していた叡山内の千手院を、配下の僧徒をそそのかして放火し、焼き落とさせるという暴挙にも出ています。
そのような良源の寺門派に対する苛烈な行動があったこともあり、また彼がその当時の比叡山では抜きん出た学僧であって、後代に名を残した者であったがために、「末法の世において正法を擁護するためであった」などという大義名分が付されておためごかされてはいますが、「僧兵の初め」としてかこつけられたのでありましょう。
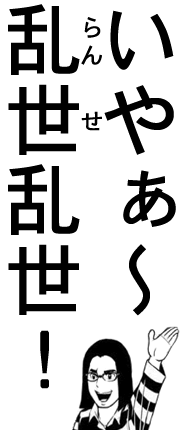
結局、その多くは比叡山上ではなく山麓の坂本に居していた、立場としては上座である学生(学僧)らも、僧兵たる堂衆・行人らが暴走して御しかねる事態もしばしばあったようですが、僧兵を便利にも使い始めています。そして、学生と行人との対立はやがて激化し、平安末期には互いに殺し合うまでになります。例えば、すでに円珍の門流は比叡山から完全に排斥され、園城寺(三井寺)を本拠としていましたが、その園城寺が「我らも独自の大乗戒壇を建立したい」などと主張し、これを南都諸宗はむしろ認めようとしたときなど、たちまち抗議の大声を上げたのみならず、比叡山の僧徒は園城寺に攻め寄せ、火を放ち回ってはその門徒を殺傷しています。
最澄の苦心の策とその死によって、ようやく認められた比叡山の大乗戒壇であったはずですが、その比叡山はこれを他所に作られることを徹底的に阻もうとしました。それは結局、一山を挙げて行われた、すでにただの既得権益に過ぎなくなっていた大乗戒壇を守るための武力行使でした。
思えば随分と理不尽な話でありましょう。
最澄の当時、先にも述べたように、大乗戒壇について南都の僧綱と最澄は激しく論争していますが、それはあくまで仏教としての根拠や伝統的あり方としての可否、そして論理的合否をもって争いました。鑑真一行の来日によって確立され、国家の制度の中に組み入れられていた戒壇院での受戒は確かに権威ではあったものの、いわゆる「既得権益」などというのとは全く異なるものです。
しかし、この時の比叡山はひたすら「比叡山は王城鎮護の山である」とか「桓武帝の後援によって建立された寺」などという(世俗的)権威を振りかざし、自身らの思うままに天台僧を製造する装置たる、まさに「既得権益」となっていた戒壇を他所にも造るなど「もっての外である」などというのみで、「仏教として」など一切の有無をいわさず、たちまち暴力に打って出たのですからお話になりません。
あるいはまた、日本天台の教学自体についても、その僧徒らは舌先三寸では最澄を「オソシサマ」などと持ち上げておきながら、その実際は「最澄なにする者ぞ」といわんばかりの極端な本覚思想へと変容させていきます。いわゆる中古天台です。それはもはや支那の天台宗などと似ても似つかない、一体どのあたりが「天台」なのか見当もつかないようなシロモノとさえなっています。
このような事態はいずれの宗旨宗派でも大なり小なり見られることですが、最澄はその門流によって都合よくかこつけられてしまったのでした。
最澄が天台宗を存続させるためにでっち上げた「菩薩戒のみで比丘となり得る」とする主張の果ては、その門徒の堕落を加速させ、またその教学面にも非常に大きな影響を及ぼしたのでした。詮無い宗派意識、派閥意識などまったく有せずして、このように彼の大乗戒に関する主張で何が生じていったかを見たならば、まさに最澄は日本仏教における大迷導師であったということが出来ます。
貧衲慧照