三聚浄戒とは、漢訳四阿含や漢訳諸律蔵およびパーリ三蔵など声聞乗の伝統において説かれることの無い大乗特有の戒、いわゆる菩薩戒です。菩薩としてその完成を目指すべき六波羅蜜の一角であり、また四摂法(四摂)の具体であって、菩薩が菩薩たりえる核心として備えるべき徳の総称、それが三聚浄戒です。
言葉としての三聚浄戒は、[S]trividhāni śīlāniの玄奘による漢訳、これが今一般に最も通用した語です。しかし、他の漢訳仏典においてはまた三種浄戒・三種戒聚・三浄戒などの訳語も見られ、また三聚戒蔵・三受門という語でも表されています。
なぜ「三聚」浄戒あるいは「三種」浄戒などというのか。それは先ず、その訳語として、原語のtrividhāniのtriが数の三を意味し、vidhaが種類または組み合わせの意であることから「種」あるいは「聚〈あつまり〉」とされます。そして、その内容としては、それが律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒(摂衆生戒)の三つの戒(徳・良い習慣)を包摂したものであるためです。それぞれがいかなる内容のものであるかは後に詳述します。なお、漢訳では「浄戒」などとありますが、原語はただśīla、つまり戒であって浄の語は漢訳時に付加されたものであり、特に意味などありません。
ところで、日本仏教各宗派の教義、宗学において頻繁に三聚浄戒の名目が用いられることから、それが一体いかなるものかと調べようとする僧俗の人があります。しかし、そうしたとしても結局、「三聚浄戒とは律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒の三つをまとめて言ったものです」という程度のことを知るのみで何故か納得し、満足してしまう者が大半のようです。けれども、それでは何一つ解ったことになりません。
また、仏教学者と言われる人々ですらこれを正確に理解している者など甚だ稀で、巷間用いられる字引きの類にも、なにやら頓珍漢であったり極めて曖昧であったりする定義を載せているものがまま見られます。そもそも現代、三聚浄戒についてまともに説いた書籍自体が何故か存在していません。
そのようなこともあり、三聚浄戒は大乗において極めて重要で必須のものとされてきたにも関わらず、今や日本において三聚浄戒についてまともに理解している者も詳しく説き得る者もほとんどありません。仮にあったとしてもそれは仏教者ではなく、仏教学者など研究者のうちでも極一握りの人が、ただ単に学問の対象として学術論文の中にてその極一部・一側面について云々するのみであって、生きた仏教としてどのようなものであるかを知りたい者にはまるで不満足のものとなっている。
そのようなことから、ここでは三聚浄戒を、拙い口説による非常に長く少々込み入った内容とはなりますが、その種々の典拠を一々示しつつ、仏教としてどのようなものであるかを示します。
三聚浄戒とは具体的にいかなるものか。それは先ず『華厳経』に説かれる言葉です。今ここで「まず『華厳経』に」などと言うのは、支那において盛んになされた経相判釈において、それも特に智者大師智顗による五時八教説では「『華厳経』は仏陀成道の直後に説かれたものである」とされていた理解を、その是非は一応横に置き、仮になぞってのことです。
於諸佛所。立深志樂。常自安住三種淨戒。亦令衆生如是安住。
諸々の仏陀のもとに深い大志を立て、常にみずから三種浄戒〈三聚浄戒〉に安住しつつ、また衆生にも同じく安住させる。
実叉難陀訳『大方広仏華厳経』巻第廿七 十廻向品(T10, p.149b)
このように、『華厳経』では、菩薩とは三種浄戒をみずから備え実現したものであり、またそれを他の生ける者どもにも勧め修得する存在であることが説かれています。この三種浄戒とは、ただ訳語が異なるのみのことであって、いわゆる三聚浄戒に相違ないものです。しかし、この一節はもちろんのこと『華厳経』通じてそれが何かは全く明らかにされていません。『華厳経』において、三聚浄戒はいわばただ名目だけ言及されるばかりであり、何がどう三種であってその内容がそれぞれいかなるものかなどについてなど、全く説かれていないのです。
そこでしかし、『華厳経』十地品の同本異訳である『十地経』に対する世親〈Vasubandhu〉の注釈書『十地経論』では、離垢地に関して解釈される中に三聚浄戒がいかなる内容のものであるか言及されています。
論曰。菩薩如是已證正位依出世間道因清淨戒説第二菩薩離垢地。此清淨戒有二種淨。一發起淨。二自體淨。《中略》
自體淨者有三種戒。一離戒淨。二攝善法戒淨。三利益衆生戒淨。離戒淨者謂 十善業道。從離殺生乃至正見亦名受戒淨。攝善法戒淨者。於離戒淨爲上。從菩薩作是思惟。衆生墮諸惡道。皆由十不善業道集因縁。乃至是故我應等行十善業道。一切種清淨故。利益衆生戒淨者。於攝善法戒爲上。從菩薩復作是念。我遠離十不善業道。樂行法行乃至生尊心等
論じて曰く、菩薩がそのように已に正位〈初地歓喜地〉を証したならば、出世間道に依り清浄戒に因って、第二の菩薩の離垢地を説く。この清浄戒には二種の浄がある。一つには発起浄、二には自体浄である。《中略》
自体浄には三種の戒がある。一つには離戒浄〈律儀戒浄〉、二には摂善法戒浄〈摂善法戒浄〉、三には利益衆生戒浄〈饒益有情戒浄〉である。離戒浄とはすなわち十善業道である。(『十地経』本文の)「殺生を離れ乃び正見に至る」までを受戒浄という。摂善法戒浄とは、離戒浄より上位のものである。(本文の)「菩薩はこのように思惟する、『衆生が諸々の悪道に堕すのは、すべて十不善業道を多く行じた因縁に由る。乃至、その故に私はまさに等しく十善業道を行じるべきである。一切種は清浄であるが故に』」とあるのがそれである。利益衆生戒浄とは、摂善法戒より上位のものである。(本文の)「菩薩はこのような想いをなす、『私は十不善業道を遠離し行法を願って行じ、乃至、尊心を生じる』」等とあるのがそれである。
菩提流支訳 世親『十地経論』離垢地第二 (T10, p.145b-c)
ここでは離戒・摂善法戒・利益衆生戒として三聚浄戒が挙げられ、その重層的関係が明らかにされて、そのそれぞれが「十善業道」を実現するものと説明されます。が、やはりその具体に踏み込んだものではありません。そして、これはしかも、特に十地の第二地である離垢地に至った高位の菩薩について云われるものとなっています。
これもまた三聚浄戒を理解するのに適したものではありません。
そこで伝統的に、三聚浄戒についてその詳細を示す根本的な(論書・注釈書ではなく)経典として見なされてきたものに、『菩薩善戒経』(以下、『善戒経』)の九巻本があります。『善戒経』こそまさに、伝統的に三聚浄戒を知らんとする欲する者が必ず披覧すべき経典として根本のものとなります。
云何名菩薩摩訶薩戒。戒者有九種。一者自性戒。二者一切戒。三者難戒。四者一切自戒。 五者善人戒。六者一切行戒。七者除戒。八者自利利他戒九者寂靜戒。《中略》
一切戒者。在家出家所受持者名一切戒。在家出家戒有三種。 一者戒。二者受善法戒。三者爲利衆生故行戒。
何を菩薩摩訶薩戒と云うであろうか。戒には九種ある。一つには自性戒、二つには一切戒、三つには難戒〈難行戒〉、四つには一切自戒〈一切門戒〉、 五つには善人戒〈善士戒〉、六つには一切行戒〈一切種戒〉、七つには除戒〈遂求戒〉、八つには自利利他戒〈此世他世楽戒〉、九つには寂静戒〈清浄戒〉である。《中略》
一切戒とは、在家・出家が受持する戒を名づけて一切戒としたものである。在家・出家の戒には三種がある。 一つには戒〈律儀戒〉、二つには受善法戒〈摂善法戒〉、三つには為利衆生故行戒〈饒益有情戒〉である。
求那跋摩訳『菩薩善戒経』巻四 菩薩地戒品第十一(T30, p.982b-c)
『善戒経』は、まず菩薩戒に九種の別があることを示して列挙。別といっても、それはいわば九種の見方・範疇あるいは理念ということなのですが、そこで「一切戒」の名目を挙げています。一切戒とは、在家出家の文字通り「すべての戒」であってそれに三種戒があるといいます。そして、その三種とは具体的に、戒・受善法戒・為利衆生故行戒の三種であると云われます(それぞれ玄奘訳の律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒に該当)。
この一節以下、それぞれが具体的にいかなる意味内容のものかを『善戒経』は解き明かしていくのですが、それをさらに詳細に明かしているのが、『瑜伽師地論』(以下、『瑜伽論』)〈Yogācārabhūmi-śāstra〉の菩薩地瑜伽処戒品(以下、「瑜伽処戒品」)です。『瑜伽論』とは、玄奘によれば弥勒菩薩の所説を無着〈Asaṅga〉が聴聞して著したとされるもので、広く大乗において最も重要な書の一つです。特に法相宗など瑜伽行唯識学派では根本典籍の一つとされます。
『瑜伽論』では、その所説の戒がいかなるものかを以下のように明らかにされています。
復次如是所起諸事菩薩學處。佛於彼彼素怛纜中隨機散説。謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒。今於此菩薩藏摩呾履迦綜集而説。菩薩於中應起尊重住極恭敬專精修學。
また次に、以上の様に起てた諸々の菩薩の学処は、世尊が彼此の経に於いて様々な機会にて散説されたものである。いわゆる律儀戒〈saṃvara-śila〉・摂善法戒〈kuśala-saṃgrāhaka śīla〉・饒益有情戒〈sattvārtha-kriyā-śīla〉に拠って、今この菩薩蔵〈bodhisattva-piṭaka〉の摩呾履迦〈mātṛkā. 論〉において総集して説く。菩薩は(この菩薩戒を)尊重して最も恭敬し、勤め励まなければならない。
玄奘訳 弥勒『瑜伽師地論』巻四十(T30, p.521a)
ところで、印度では菩薩戒すなわち三聚浄戒といえば、いわゆる瑜伽戒のことであったようです。瑜伽戒とは『瑜伽論』に詳しく解き明かされた『善戒経』所説の戒のことであり、それを玄奘は直接当地にて受学し、その典拠たる『瑜伽論』と併せてその受戒法式も支那にもたらしています。菩薩戒と言えば瑜伽戒であったのは、印度から直接仏教がもたらされた西蔵においても同様です。
では実際に、『善戒経』の一節と重複してさらに長くなりはますが、その「瑜伽処戒品」における該当箇所を示します。
云何菩薩戒波羅蜜多。嗢拕南曰自性一切難 一切門善士謂九種相戒名爲菩薩戒波羅蜜多。一自性戒。二一切戒。三難行戒。四一切門戒。五善士戒。六一切種戒。七遂求戒。八此世他世樂戒。九清淨戒 《中略》
一切種遂求 二世樂清淨
如是九種相 是名略説戒
云何菩薩一切戒。謂菩薩戒略有二種。一在家分戒。二出家分戒是名一切戒
又即依此在家出家二分淨戒。略説三種。一律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒
律儀戒者。謂諸菩薩所受七衆別解脱律儀。即是苾芻戒。苾芻尼戒。正學戒。勤策男戒。勤策女戒。近事男戒。近事女戒。如是七種。依止在家出家二分。如應當知。是名菩薩律儀戒
攝善法戒者。謂諸菩薩受律儀戒後。所有一切爲大菩提。由身語意積集諸善。總説名爲攝善法戒。此復云何。謂諸菩薩依戒住戒。於聞於思於修止觀於樂獨處。精勤修學。如是時時於諸尊長。精勤修習合掌起迎問訊禮拜恭敬之業。即於尊長勤修敬事。於疾病者悲愍殷重瞻侍供給。於諸妙説施以善哉。於有功徳補特伽羅。眞誠讃美。於十方界一切有情一切福業。以勝意樂起淨信心發言隨喜。於他所作一切違犯思擇安忍。以身語意已作未作一切善根。迴向無上正等菩提。時時發起種種正願以一切種上妙供具供佛法僧。於諸善品恒常勇猛精進修習。於身語意住不放逸。於諸學處正念正知正行。防守密護根門。於食知量。初夜後夜常修覺悟。親近善士依止善友。於自愆犯審諦了知深見過失。既審了知深見過已。其未犯者專意護持。其已犯者於佛菩薩同法者所。至心發露如法悔除。如是等類所有引攝護持。増長諸善法戒。是名菩薩攝善法戒
云何菩薩饒益有情戒。當知此戒略有十一相。何等十一。謂諸菩薩於諸有情能引義利。彼彼事業與作助伴。於諸有情隨所生起疾病等苦。贍侍病等亦作助伴。又諸菩薩依世出世種種義利。能爲有情説諸法要。先方便説先如理説。後令獲得彼彼義利。又諸菩薩於先有恩諸有情所善守知恩。隨其所應現前酬報。又諸菩薩於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等畏諸有情類。皆能救護。令離如是諸怖畏處。又諸菩薩於諸喪失財寶親屬諸有情類。善爲開解令離愁憂。又諸菩薩於有匱乏資生衆具諸有情類。施與一切資生衆具。又諸菩薩隨順道理。正與依止如法御衆。又諸菩薩隨順世間。事務言説。呼召去來。談論慶慰。隨時往赴。從他受取飮食等事。以要言之。遠離一切能引無義違意現行。於所餘事心皆隨轉。又諸菩薩若隱若露。顯示所有眞實功徳。令諸有情歡言進學。又諸菩薩於有過者。内懷親昵利益安樂増上意樂調伏訶責治罰驅擯。爲欲令其出不善處安置善處。又諸菩薩以神通力。方便示現那落迦等諸趣等相。令諸有情厭離不善。方便引令入佛聖教歡喜信樂生希有心勤修正行。
何が菩薩の戒波羅蜜多であろうか?嗢拕南〈Uddāna. 無問自説〉に曰く。自性と一切と難と、一切門と善士と、すなわち九種の相の戒を菩薩の戒波羅蜜多と云う。一には自性戒、二には一切戒、三には難行戒、四には一切門戒、五には善士戒、六には一切種戒、七には遂求戒、八には此世他世楽戒、九には清浄戒である。 《中略》
一切種と遂求と、二世樂と清淨、
これらの九種の相を略して戒を説くと云う。
何が菩薩の一切戒であろうか?菩薩戒には略して二種ある。一つには在家分〈gṛhi-pakṣa〉の戒、二つには出家分〈pravrajita-pakṣa〉の戒であって、これらを一切戒という。また、この在家と出家との二分の浄戒には、略説して三種がある。一つには律儀戒〈saṃvara-śīla〉、二つには摂善法戒〈kuśala-dharma-saṃgrāhaka śīla〉、三つには饒益有情戒〈sattvārtha-kriyā-śīla〉である。
律儀戒とは、諸菩薩が受けるところの七衆別解脱律儀〈sapta-naikāyikaṃprātimokṣa-saṃvara-samādāna〉である。(七衆とは)すなわち、①苾芻〈bhikṣu. 比丘〉・②苾芻尼〈bhikṣuṇī. 比丘尼〉・③正学女〈śikṣamāṇā. 式叉摩那〉・④勤策男〈śrāmaṇera. 沙弥〉・⑤勤策女〈śrāmaṇery. 沙弥尼〉・⑥近事男戒〈upāsaka. 優婆塞〉・⑦近事女戒〈upāsika. 優婆夷〉である。以上の七種(がそれぞれ受持する律儀)は、在家・出家の二分の依止するものであると、まさにそのように知らなければならない。これが菩薩の律儀戒である。
摂善法戒とは、(在家・出家の)諸菩薩が律儀戒を受けて後、一切のあらゆる大菩提を得るために行う身・語・意による諸々の善を積むことを、総じて摂善法戒という。(具体的には)どのようなことであろうか。それは、(1) 諸菩薩が戒に依って戒に住し、これを聞き、これを思い、止観〈śamatha-vipaśyanā〉を修する時、閑静で孤独な土地にあることを楽しみつつ、努め励んで修行すること。(2) 時時に諸々の尊者〈guru〉に会ったならば合掌して起ち上がって出迎え、(体調や最近の動向を伺うなど)問訊して礼拝・恭敬することを努めて行うなど尊者に対して敬意をもって接すること。もし(病や老いなどで)弱っていたならばいたわり、心を尽くして介護すること。(3) 諸々のすぐれた教えに対しては「善い哉〈Sādhu!〉」と言って賛嘆し、徳ある人を心から賞賛すること。(4) 十方界に於けるすべての有情のあらゆる福徳に対して意楽〈āśaya〉をもって浄らかな心を生じ、さまざまな言葉を発して喜び、他者の行為のあらゆる過ちについて批判的に考察〈pratisaṃkhyā〉しつつもこれを(怒らず)耐え忍ぶこと〈kṣama〉。(5) 身・語・意によって為されたあらゆる善業を無上正等菩提に廻向〈pariṇāma〉し、時時に様様な正しき誓願〈samyak-praṇidhāna〉を起こして、あらゆる上等の供物を仏法僧の三宝に献じ、諸々の善品を常に熱心に努めて修習して、身・語・意において不放逸に住すること。(6) ①諸々の学処〈sikṣā-pada〉において注意深く〈smṛti〉、明らかに知りつつ〈saṃprajanya〉行ずること〈cārikā〉。②(知覚対象に惑わされぬよう眼・耳・鼻・舌・身・意の)根の門衛となること。③食について(己に過不足無い)量を知ること。④初夜と後夜とに覚醒〈jāgarikā〉して(惰眠を貪らず)いること。⑤善人〈satpuruṣa〉と親しみ、善友〈kalyāṇamitra〉に交わること。⑥自身の犯した過誤を明瞭に知ってその誤りを見、その過失を知ったならば、いまだ犯していない点があればそれを決して犯さぬよう勤めること。⑦仏・菩薩・同法者等に対し、自身の犯した過誤を発露し懺悔すること。このような類の諸々の善法を獲得し、護持し、増長する戒が、菩薩の摂善法戒である。
何が菩薩の饒益有情戒〈sattvānugrāhaka-śīla〉であろうか。それには略して十一の相〈ākāra〉があると知るべきである。何が十一の相であろうか。①諸々の有情の利益〈artha〉となる様々な事柄を手助けし、もし生じた病苦があったならばその看病をして介添えすること。 ②世間・出世間における種々な利益に基づいて、よく有情の為に諸々の法要を説くこと。先ず方便〈upāya〉して説き、あるいは理〈nyāya〉に従って説いて、次に此彼の利益を獲得させること。③以前恩〈upakāra〉を受けた有情に対し、決してその恩を知って忘れず、その恩に報いること。④獅子・虎狼・死霊・王・盗賊や、火難・水難など種々の恐怖〈bhaya〉に苛まれている有情を悉く救護し、その脅威から離れさせること。⑤財産や親族を失った有情の為によく開解し、愁憂を離れさせること。⑥日常生活の資具にさえ事欠く有情の為に、全ての不可欠な品々を施与すること。⑦道理に従い、正しく依止を与えて如法に衆〈gaṇa. 徒衆〉を率いること。⑧世間における挨拶・会話・(食事の招待への)承諾・(招待への)去来・談論・慶弔などあれば、時に隨って赴き、他者から飲食の接待を受けるなど(世俗のしきたり・世俗の人々のもてなしに)随順すること。その要は、まったく無意味で、(有情や世俗の)意志に反する行いをしてはならず、その他のことについても(有情の)心を喜ばせるようにすることである。⑨あるいは密かにあるいは露わに、あらゆる真実の功徳〈guṇa〉を説き示して、有情を歓喜させて修得させること。⑩過悪ある者に対して、内心では親昵〈親しみなじむこと〉・利益安楽の大いなる意楽を懐きつつも、しかし調伏〈nigraha-kriya〉し、訶責〈avasādanā〉し、治罰〈daṇḍakarma〉し、驅擯〈pravāsanā〉すること。その者をして不善なる処〈akuśala-sthānā〉から善なる処へと(移り)置かせようと思うからこその措置である。⑪神通力を用い方便して地獄〈naraka〉等の諸々の(悪しき)趣〈gati. 境遇〉の有り様を示現して、有情に不善を厭わせ離れさせ、方便して仏陀の聖教に教え導き、歓喜・信楽・希有の心を生じさせて、勤めて正行を修めさせることである。
玄奘訳 弥勒『瑜伽師地論』巻四十 本地分中菩薩地第十五(T30, P511a-c)
今示した『瑜伽論』の一章である「瑜伽処戒品」には、それのみの部分訳であり同本異訳である『菩薩地持経』(以下、『地持経』)があります。これは玄奘によって『瑜伽論』が訳出されるおよそ二百年も以前、すでに曇無讖によって訳され、支那における菩薩戒の重要な典拠とされていました。そこで玄奘が『瑜伽論』を訳出する前までは、その戒は「地持戒」と称されています。
(今伝わる『瑜伽論』の梵本と、『地持経』ならびに『瑜伽論』とを比較した時には、前者がより簡潔で原書たる梵本に沿っており、後者には玄奘自身によるものか、より解りやすくした解説の如き挿入語句が相当あることが知られます。そこで、ここでは『瑜伽論』を掲げましたが、その現代語訳に際しては梵本と『地持経』を適宜参照してその原語も示しています。また、現代語訳では新羅僧遁倫による『瑜伽論』の注釈書『瑜伽論記』の所説に従って摂善法戒の徳目を七種とし、またそれぞれ便宜的に番号を振っています。)
| 律儀戒 | 別解脱律儀 (菩薩律儀戒) |
① | 比丘 | 具足戒 (比丘律儀) |
断徳 止悪 |
出家分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 比丘尼 | |||||
| ③ | 正学女 | 六重法 | ||||
| ④ | 沙弥 | 十戒 | ||||
| ⑤ | 沙弥尼 | |||||
| ⑥ | 優婆塞 | 八斎戒 五戒 |
在家分 | |||
| ⑦ | 優婆夷 | |||||
| 摂善法戒 | 三慧 | (1) | 聞・思・修の三慧を修め、閑静な地で止観を修習すること | 智徳 修善 |
大乗独自 | |
| 三業 | (2) | 尊者を恭敬・礼拝し、敬意をもって接すること | ||||
| (3) | 善く説かれた教えと徳ある人を「善哉」と称えること | |||||
| (4) | 他の徳業を随喜し、他の犯した過ちを怒らぬこと | |||||
| 廻向発願 | (5) | 善業を菩提のために廻向して正しく誓願を起し、三宝を供養して不放逸たること | ||||
| 七善 | (6) | 正念・正知して五根を護り、食について量を知り、惰眠を貪らず、善友に交わり、自身の過失を明らかに知って再び誤らぬよう気をつけ、過ちを発露・懴悔すること | ||||
| 饒益有情戒 (摂衆生戒) |
同事 | ① | 他に協力して助けること | 恩徳 利他 |
||
| 愛語 | ② | 他に法要を説いて、様々に利益すること | ||||
| 布施 | ③ | 以前受けた恩に報いること | ||||
| ④ | 何か畏れある他者を助け、安心させること | |||||
| ⑤ | 財産・親族を失って失意にある者を慰めること | |||||
| ⑥ | 貧しく飢えた者に必要な物を施すこと | |||||
| ⑦ | 道理に従い、如法に衆徒を擁して御すこと | |||||
| 利行 | ⑧ | 世の慣習・交際にある程度従い、世人の意を無益に損なわないこと | ||||
| ⑨ | 他に真の功徳とは何かを説き示して勧めること | |||||
| ⑩ | 過失・違犯ある者を、適切に調伏・苛責・懲罰・追放すること | |||||
| ⑪ | 他に神通力をもって地獄等の苦趣を示現し、その因となる悪業を厭い離れさせ、仏陀の教えに導くこと | |||||
三聚浄戒の第一である律儀戒とは、出家在家それぞれの立場によって異なる戒または律であることから、あるいはそれによってそれぞれ別個の条項に関する悪しき・あるいは不適切な行為から離れるものであることから、別解脱律儀〈prātimokṣa-saṃvara〉などとも言われます。
そして、摂善法戒とは、菩薩が阿羅漢果ではなく無上正等菩提をこそ得るための資糧を積集するためのものです。その日常にて具体的に為すべきこととしては、上記のように種々に規定されています。
最後の饒益有情戒とは、他者を積極的に利益するためのものです。『善戒経』・『瑜伽論』では具にはこれに十一種あるとして、以上のように現実的に他者に対して行うべきことが説かれています。
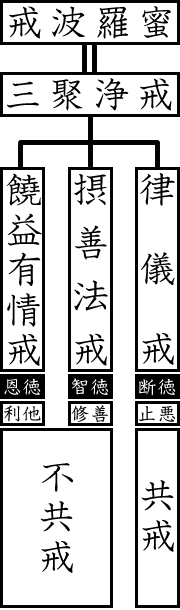
この『瑜伽論』の一節において、律儀戒は七衆の別解脱律儀であるとその概要を示すのみです。対して摂善法戒と饒益有情戒それぞれについて説かれているのは、積極的に「なすべき事柄」、行動規範が説かれています。すなわち、これらは世間一般にて理解されている意味での戒、「なすべきでない事柄」いわゆる禁則ではなく、まさしく戒(śīla)の原意、すなわち「(良い)習慣」・「道徳」そのものです。
いわゆる禁則を、仏教では「学処([S]śikṣāpada / [P]sikkhāpada)」と言いますが、そもそもその原語が異なっているように、学処と戒とは異なるものです。
(戒と学処、その違いについては別項「戒とは何か」を参照のこと。)
そこで三聚浄戒とは、それぞれ独立して関連しない戒の総称ではありません。三聚浄戒とは、大乗に奉じて自身を菩薩であると規定する者が受けその身に備えるべき、菩薩が菩薩たる所以となるもの、六波羅蜜の戒波羅蜜の具体です。
そして、三聚浄戒のうち律儀戒は声聞乗と菩薩乗とで(その心的相違はあるとされるにせよ、外的には)まったく共通となっています。大乗に特有であるのは摂善法戒と饒益有情戒の二戒です。その摂善法戒と饒益有情戒とを「後二の戒」あるいは「(菩薩の)不共戒」ともいうのですが、後二の戒が大乗に特有と言っても、それらはあくまで律儀戒を前提とし、それに立脚して初めて有効なものとされます。
後二の戒の具体的内容、すなわち戒相は『瑜伽論』にて別途説かれており、それが一般に地持戒もしくは瑜伽戒、あるいは四重四十三軽戒などと称されます。
さて、ここでそうすることは重複する点も多くあって冗長となる感は否めません。しかし三聚浄戒の理解をより確かなものとするためには、その典拠の所説を直に披覧することがどうしても必要なことであるため、敢えて更に印度の諸大徳の書典で三聚浄戒に言及したものをいくつか以下に示します。
まず『摂大乗論』〈Mahāyānasaṃgraha〉(以下、『摂論』)から。『摂論』とは、現代では四世紀頃の人と云われ、伝統的には仏滅後一千年頃に誕生したとされる印度僧、無着〈Asaṅga〉によって著された、その題目通り「大乗の綱要書」です。『摂論』は「そもそも大乗とは何か」・「大乗と声聞乗との相違点は何か」を簡潔に示した概説書の如きものです。
そして大乗でも特に唯識の教理が体系的にまとめられ示されているものであることから、大乗の二大潮流の一つである瑜伽行唯識における根本典籍の一つとなっています。
云何應知諸波羅蜜差別。由各有三品知其差別。《中略》
戒三品者。一守護戒。二攝善法戒。三攝利衆生戒。
この諸々の波羅蜜多の相違をどの様に見るべきであろうか。まさに知るべきである、(六波羅蜜多の)それぞれに三品あることを。《中略》
戒の三品とは、一つには守護戒〈律儀戒〉、二つには摂善法戒、三つには摂利衆生戒〈饒益有情戒〉である。
真諦訳 無着『摂大乗論』巻中 入因果勝相第四(T31, p.125b)
無着は六波羅蜜について明かす中、戒波羅蜜に律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒の三種の別あることを言います。しかし、その内容を明らかにはしていません。そこでこの『摂論』の一節に対し、無着の実弟であった世親〈Vasubandhu〉は、その註釈書『摂大乗論釈』(以下、『摂論釈』)にて以下のように広説しています。
論曰。戒三品者。一守護戒。二攝善法戒。三攝利衆生戒
釋曰。守護戒是餘二戒依止。若人不離惡。攝善利他則不得戒。若人住守護戒。能引攝善法戒。爲佛法及菩提生起依止。若住前二戒。能引攝利衆生戒。爲成熱衆生依止。復次守護戒由離惡故。無悔惱心。能得現世安樂住。由此安樂住故。能修攝善法戒。爲成熟佛法。若人住前二戒。能修攝利衆生戒。爲成熟他。此三品戒即四無畏因。何以故。初戒是斷徳。第二戒是智徳。第三戒是恩徳。四無畏不出此三徳故。言即四無畏因。由具此義故説戒有三品
『摂大乗論』本文:戒の三品とは、一つには守護戒〈律儀戒〉、二つには摂善法戒、三つには摂利衆生戒〈饒益有情戒〉である。
『摂大乗論』註釈:守護戒とは、他の(摂善法戒と摂利衆生戒との)二戒の依止〈拠り所〉である。もし人が悪を離れることがなければ、善を行って他者を利することは出来ない。もし人が守護戒に従って生活していたならば、よく摂善法戒を行い得て仏法および菩提を生起する依止となる。そしてもし、(守護戒と摂善法戒との)最初の二つの戒に従って生活したならば、よく摂利衆生戒を行い得るようになって、衆生を教え導く依止となるであろう。
また次に、守護戒を持して悪を離れることに由り、(「以前悪を為した」と)後悔して悩むことがなくなり、現世において安楽に過ごすことが出来るであろう。そのように安楽に過ごせることに由って、摂善法戒を行うことが出来るようになる。仏法を成就するためである。もし人が(守護戒と摂善法戒との)前の二戒に従って生活したならば、よく摂利衆生戒を行い得る。他者を教え導くためである。
この三品の戒は、すなわち(仏陀の)四無畏の因である。なんとなれば、初戒〈守護戒〉は断徳である。第二戒〈摂善法戒〉は智徳である。第三戒〈摂利衆生戒〉は恩徳である。四無畏はこれら(仏陀が具える)三徳に過ぎたものではないことから、四無畏の因と言う。これらの意義を具えていることから、「戒に三品あり」と説かれる。
真諦訳 世親『摂大乗論釈』巻第九 釈入因果勝相第四
(T31, pp.218c-219a)
ここで世親は、これは先に示した『十地経論』と同様、三聚浄戒それぞれの重層的・階層的関係を明らかにしています。
ところで、本章の小題において、三聚浄戒が重層的構造を持ったものであることから、これを「重楼戒」と表現しましたが、それは『菩薩善戒経』において出家・在家の律儀戒の重層的構造を「重楼四級〈四階建ての楼閣〉」と喩えているのに基づき、支那の賢首大師法蔵がその著の中で「重楼戒経」と称しているのに準じたものです。なぜ重楼すなわち多層階の楼閣にこれを喩えるかと言えば、まず確固とした一階を建てなければ二階はありえず、二階がなければ当然三階など無く成立しないのと同様に、三聚浄戒も律儀戒をその根本としてこそ、その上に摂善法戒があり、さらにその上に饒益有情戒がありえる為です。
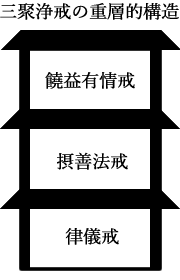
『摂論』は具体的に、「守護戒是餘二戒依止(守護戒は是れ餘の二戒の依止なり)」と、守護戒すなわち律儀戒こそ最も重要な基礎、拠り所であることを強調。菩薩たる者は先ず律儀戒を受け、これを護持して初めて摂善法戒が実現可能となり、次いで摂善法戒を護持することによってようやく饒益有情戒が果たし得るとしています。
なお、律儀戒は三聚浄戒を受ける以前、別途にそれぞれの分際に応じた戒あるいは律を受けていなければならない、と規定されます。故に、これは三聚浄戒を理解する上で極めて重要な点の一つとなりますが、三聚浄戒の中に名目として律儀戒があるとはいえ、ただ三聚浄戒を受けただけでは律儀戒を受けたことにはなりません。
また、三聚浄戒とは四無畏の因であるともされていますが、これは無上正等正覚の因であると換言して良いものです。
このような世親による理解は、実は『摂論』で後に以下のように説かれているのを根拠としたものです。
云何應知依戒學差別。應知如於菩薩地正受菩薩戒品中説。若略説由四種差別。應知菩薩戒有差別。何者爲四。一品類差別。二共不共學處差別。三廣大差別。四甚深差別。品類差別者。有三種。一攝正護戒。二攝善法戒。三攝衆生利益戒。此中攝正護戒應知是二戒依止。攝善法戒是得佛法生起依止。攝衆生利益戒是成熟衆生依止。
どのように戒学に依る差別を知るべきであろうか。それには「菩薩地正受菩薩戒品」にて説かれているままに知らなければならないが、それを略説したならば四種の差別に由る。菩薩戒に差別のあることを知れ。
何をもって四種とするのか。一つには品類の差別、二つには共不共学処の差別、三つには広大の差別、四つには甚深の差別である。品類の差別には三種がある。一つには摂正護戒〈律儀戒〉、二には摂善法戒、三つには摂衆生利益戒〈饒益有情戒〉である。この中、摂正護戒は二戒の依止であることを知らなければならない。摂善法戒は仏法を生起することの依止であり、摂衆生利益戒は衆生を成熟する依止である。
真諦訳 無着『摂大乗論』巻下 依戒学勝相第六(T31, p.126c)
この一説について、世親はさらに三聚浄戒の三種戒の具体に踏み込んで、それぞれどういったものかを以下のように詳説しています。
論曰。品類差別者有三種。一攝正護戒
釋曰。謂比丘比丘尼。式叉摩尼沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。此戒是在家出家二部七衆所持戒
論曰。二攝善法戒
釋曰。從受正護戒。後爲得大菩提。菩薩生長一切善法。謂聞思修慧及身口意善。乃至十波羅蜜
論曰。三攝衆生利益戒
釋曰。略説有四種。謂隨衆生根性。安立衆生於善道及三乘。復有四種。一拔濟四惡道。二拔濟不信及疑惑。三拔濟憎背正教。四拔濟願樂下乘。云何此三與二乘有差別。二乘但有攝正護戒。無餘二戒。何以故。二乘但求滅解脱障。不求滅一切智障。但求自度不求度他。不能成熟佛法及成熟衆生。是故無攝善法戒及攝衆生利益戒
論曰。此中攝正護戒。應知是二戒依止
釋曰。若人不離惡。能生善及能利益衆生。無有是處。故正護戒是餘二戒依止
論曰。攝善法戒是得佛法生起依止。攝衆生利益戒是成熟衆生依止
釋曰。攝善法戒先攝聞思修三慧。一切佛法皆從此生起。何以故。以一切佛法皆不捨智慧故。攝衆生戒所謂四攝。初攝令成自眷屬背惡向善。第二攝未發心令發心。第三攝已發心令成熟。第四攝已成熟令解脱。《中略》
此三種戒以何法爲體。不起惱害他意。生善身口意業爲體。離取爲類。此三種戒以何法爲用。正護戒能令心安住。攝善法戒能成熟佛法。攝衆生戒能成熟衆生。一切菩薩正事不出此三用。由心得安住無有疲悔故。能成熟佛法。由成熟佛法故能成熟衆生
本文:(菩薩戒の)品類の差別には三種がある。一つには摂正護戒〈律儀戒〉
註釈:すなわち比丘・比丘尼・式叉摩尼〈正学女〉・沙弥・沙弥尼・優婆塞・優婆夷など、この戒は在家・出家の二部七衆が受持する所の戒である。
本文:二つには摂善法戒
註釈:正護戒〈律儀戒〉を受けたことに依り、後に大菩提を得る為に菩薩は一切の善法を生長する。すなわち聞思修の慧〈三慧〉、及び身口意の善〈十善業〉、乃至十波羅蜜である。
本文:三つには摂衆生利益戒〈饒益有情戒〉
註釈:これに略説すれば四種がある。すなわち衆生の根性〈機根〉に従って衆生を善道〈人道・天道〉および三乗〈菩薩乗・独覚乗・声聞乗〉に導く。また四種がある。一つには四悪道〈地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道〉から抜済する。二つには不信及び疑惑から抜済する。三つには正教〈正法〉を憎み背くことから抜済する。四つには下乗〈独覚乗・声聞乗〉を願楽することから抜済する。
この三聚浄戒には二乗〈独覚乗・声聞乗〉とどのような差別があるであろうか。二乗にはただ摂正護戒があるのみであって、他の二戒は無い。どのような理由から(二乗には他の二戒が無いの)であろうか。二乗はただ解脱障〈煩悩障〉を滅することのみを求めて一切の智障〈所知障〉を滅することを求めず、ただ自度を求めて度他を求めず、仏法を成熟し及び衆生を成熟することは出来ない。そのようなことから、摂善法戒及び摂衆生利益戒とが(二乗には)無いのである。
本文:この中で摂正護戒とは、まさに知るべきである、(摂善法戒と摂衆生利益戒との)二戒の依止であることを。
註釈:もし人が悪を離れることがなければ、よく善を生じ、またよく衆生を利益することは出来ない。そのようなことから正護戒とは他の二戒の依止である。
本文:摂善法戒とは仏法を生起することの依止であって、摂衆生利益戒とは衆生を成熟することの依止である。
註釈:摂善法戒は、先ず聞・思・修の三慧を包括するもので、一切の仏法は皆これより生起する。なんとなれば一切の仏法は皆、智慧を捨てることが無いためである。摂衆生戒〈饒益有情戒〉はいわゆる四摂である。初めの摂は自らの眷属を成じて悪に背き善に向かわせるものである。第二の摂は未だ発心していない者を発心させるものである。第三の摂は已に発心しているものを成熟させるものである。第四の摂は已に成熟している者を解脱させるものである。《中略》
この三種戒〈三聚浄戒〉は何れの法を体〈本質〉とするのであろうか。他の生命を悩ませ害する心を起こさず、善なる身口意の業〈十善業〉を生じることを体とし、取〈執着〉から離れることを類とする。
この三種戒は何れの法を用〈作用〉とするのであろうか。正護戒はよく心を安住させ〈止悪・断徳〉、摂善法戒はよく仏法を成熟し〈修善・智徳〉、摂衆生戒はよく衆生を成熟する〈利他・恩徳〉。一切の菩薩の正事〈菩薩として為すべき行〉はこの三用〈三徳〉を過ぎるものでない。心が安住すれば疲悔〈後悔・自己嫌悪〉すること無く、その故によく仏法を成熟する。そして仏法を成熟しているからこそ、よく衆生を成熟することが出来るのだ。
真諦訳 世親『摂大乗論釈』巻第十一(T31, p.232b-c)
律儀戒が七衆の別解脱律儀であるとする点、これは当然のことながら『瑜伽論』に全く同じであって声聞乗と全く共有されるものです。またそれが俗法や外道などとも共通するものでもあることから、それを共学処とも云います。そして、これは『瑜伽論』にて弥勒(無着)が言及していない点ですが、摂善法戒とは聞思修の三慧・十善業・十波羅蜜を成就するものであり、饒益有情戒は四摂を達成するものであるとしています。
もっとも、この四摂とは、一般にいわれる布施・愛語・利行・同事の四摂法ではなく、衆生を化導する四つの段階を意味するものです。すなわち、先ず四悪趣へと繋がる悪しき行いから人を離れさせ、次に道徳・倫理に対する不信・疑惑を払拭し、そして仏法を忌み嫌うことを止めさせ、さらに仏法に信を託したならば声聞乗あるいは独覚乗を信楽することを防ぐ。そのような化導の段階を示したものが、ここにいわれる四摂です。
そして世親はまた『摂論』の所論を受け、律儀戒と摂善法戒と饒益有情戒とが階層的に次第して行じていかなければならないものであることを、その理由を含めてより詳しく述べています。
一般に、三聚浄戒について最も詳しいのは『瑜伽論』とされ、それはその通り事実です。しかし、このようにして見たならば、『摂論』および『摂論釈』の所論も決して等閑視出来ない、非常に重要な詳細を明かしたものであることが知られるでしょう。事実、その昔の支那及び日本では、『摂論』は菩薩戒についての重要な典拠としても扱われています。
もはや蛇足となるかもしれませんが、伝統的に言及されてきたものであることから最後にもう一点、やや後代ながらやはり印度の論師が三聚浄戒について触れている述作を示します。
戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒饒益有情戒。《中略》
戒學有三。一律儀戒。謂正遠離所應離法。二攝善法戒。謂正修證應修證法。三饒益有情戒。謂正利樂一切有情。此與二乘有共不共甚深廣大如餘處説。
戒には三種ある。すなわち律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒である。 《中略》
戒学には三種ある。一つは律儀戒、正しく離れるべき法〈事物・行為・思想〉から遠離すること。二つには摂善法戒、正しく修証すべき法を修証すること。三には饒益有情戒、正しくすべての有情を利楽することである。
玄奘訳 護法『成唯識論』巻第九(T31, pp.51b-52a)
『成唯識論』とは、世親によって著された三十の偈頌からなる唯識についての典籍『唯識三十論頌』を六世紀の印度僧、護法〈Dharmapāla. 達磨波羅〉が注釈したものです。
護法とは、若くして那爛陀寺〈Nālandā-saṃghārāma〉の学頭を勤めたという当代きっての秀才ながらも、三十二歳という若さで大菩提寺にて早逝してしまったという人です。玄奘三蔵が渡天時、那爛陀寺にて師事した戒賢〈Śīlabhadra〉はその弟子で、よって玄奘は護法の孫弟子にあたります。玄奘は、その学徳の高さに深く帰依していた戒賢が師として仰いでいた、亡き護法の唯識教学を非常に重視して支那にもたらしていますが、その結果、玄奘の弟子の基法師によって立てられたのが法相宗です。故に『唯識論』は法相宗における最も重要な論書の一つとなっています。
『唯識論』にて護法は、十波羅蜜の戒波羅蜜に三種あり、それがいわゆる三聚浄戒であるとしています。しかし、これは先に示した世親の『摂論釈』の説を踏襲したものでしょうけれども、それぞれがいわゆる止悪・修善・利他を目的としたものであることを言うに留め、それ以上詳らかにしてはいません。とはいえ、三聚浄戒それぞれがどのような類いのものであるかを、もっとも簡潔にあらわした一節となっています。