『梵網経』にて説かれる十重波羅提木叉、いわゆる十重禁戒の戒相を要約して示せば以下のとおり。
| 1 | 殺戒 | いかなる生き物でも、これを故意に殺傷してはならない。他人に行わせてもならない。 |
|---|---|---|
| 2 | 盗戒 | 一草であっても、与えられていない物を盗んではならない。他人に行わせてもならない。 |
| 3 | 婬戒 | 相手を問わず、いかなる性行為も行ってはならない。他人に行わせてもならない。 |
| 4 | 妄語戒 | 「禅定を得た」・「聖者の境地に達した」と虚言してはならない。他人に行わせてもならない。 |
| 5 | 酤酒戒 | 酒を販売してはならない。他人に行わせてもならない。 |
| 6 | 説他罪過戒 | 仏弟子の罪過をあげつらってはならない。他人に行わせてもならない。 |
| 7 | 自讃毀他戒 | 自身の徳を賞讃して、他者を謗ってはならない。他人に行わせてもならない。 |
| 8 | 慳惜加毀戒 | いかなる物(財施・法施)でも物惜しみしてはならない。他人に行わせてもならない。 |
| 9 | 瞋不受悔戒 | 殊更に怒り、それを悔いないことがあってはならない。他人に行わせてもならない。 |
| 10 | 毀謗三寶戒 | いかなる場合でも、三宝を謗ってはならない。他人に行わせてもならない。 |
ここに挙げた各戒の称は、支那の天台宗祖たる智者大師智顗〈538-597〉によって説かれ、その弟子灌頂によって筆記されたものと伝説される『菩薩戒義疏』によっています。『梵網経』あるいは梵網戒に対する注釈書は数多く遺されていますが、それらに載せる戒の呼称は相違しています。けれども無論、それはただ戒の条項それぞれについての呼称が異なるだけであって、まったく別の戒であるというわけではありません。
ただし、これは後述する四十八軽戒については顕著に見られる傾向ですが、戒の内容の記述に不明瞭であったり曖昧であったりする経文があちこち見られるために、注釈者の宗義や立場によって異なる解釈がされ、戒の具体的内容が相違して示されている場合もあります。
ところで、これとまったく同じ十重を説く経典があります。それは『菩薩瓔珞本業経』(以下、『本業経』)です。
不殺不盜不妄語不婬不沽酒不説在家出家菩薩罪過不慳不瞋不自讃毀他不謗三寶。是十波羅夷不可悔法。
①不殺・②不盗・③不妄語・④不婬・⑤不沽酒〈不酤酒〉・⑥不説在家出家菩薩罪過・⑦不慳・⑧不瞋・⑨不自讃毀他・⑩不謗三寶、これが十波羅夷不可悔法である。
《伝》竺佛念訳『菩薩瓔珞本業経』卷下 釈義品第四(T24, p.1022c)
十重の戒相で、五戒や八斎戒などと比較してみた場合に大きく異なって目につくのは、まず第五番目の酤酒戒であるしょう。五戒や八斎戒では、「酒を飲まない(不飲酒)」です。しかし、上に示したとおり、『梵網経』および『本業経』は「酒を販売しない(不酤酒)」となっています。
では、梵網戒がただ酒の販売を厳しく禁じているだけで酒を飲むことを禁じていないかというと、もちろん禁じています。しかもかなり厳重に。梵網戒において飲酒戒は、後述する「四十八軽戒」の中に含まれ、厳しく「酒を飲むこと・飲ませること」を禁じています。
(飲酒については別項「不飲酒 ―なぜ酒を飲んではいけないのか」を参照のこと。)
一般に、酤酒戒とは目新しく、あまり耳にしない語であるかもしれません。しかし、十重の戒相を同じくする『本業経』にも説かれているのはもちろんのこと、また『優婆塞戒経』においても説かれています。『優婆塞戒経』とは、特に大乗の在家信者に対して一般的な五戒を説くのに併せ、大乗独自の戒やその行うべき徳行を説く経典です。阿含における『六方礼経』や『善生経』と基本的に同内容ながら、六方に六波羅蜜を掛けて説くなど、その大乗版とでもいうようなものです。
『梵網経』などでは、すなわちこれを「支那・日本における大乗においては」と換言できるでしょうが、酒を飲むことを不善とすることは言うまでもなく、酒を飲む原因を造ることをよりずっと悪しき行為であると見ています。酒を飲むことよりも売ることのほうがずっと重い罪となり、大乗を奉じる徒であるならば酒を飲まないことは当然として、酒の販売に決して携わってはならないし、人にさせてもならない、と説いているのです。
それは現代、先進各国における麻薬に関する法律でも大概そうであるように、その使用よりも製造や販売がより重い罪に問われるのと同様であります。酒も飲むことは通仏教的に悪しきことであるとされますが、そこで酒を酒として作り、売る者はさらに悪しき行為とされるのです。
なお、これは梵網戒が僧俗の通戒であるが故の事態なのですが、十重のうち第三の「婬戒」は、出家者と在家信者とで、その内容が異なって理解されています。出家者の場合は律とまったく変わりありません。すなわち、「相手が同性であれ、異性であれ、動物であれ、神であれ、口・性器・肛門などいかなる方法でも性交渉してはならない」となります。しかし、在家信者の場合は邪淫戒、すなわち「不適切な男女関係を結ばない。不倫・売買春しない」となって、五戒や八斎戒と同様のものとなります。
もっとも、それは『梵網経』の本文に「在家の場合は不邪淫」などと説かれているのではなく、そのように古来解釈されてきたことに過ぎません。故に、この婬戒について、出家在家を問わず、文字通り一切の性行為を禁じたものであるとして理解した人も過去にあったようです。
次に、十重禁戒の他に併せて説かれる四十八軽戒について示しますが、十重に同じく、その名目は『菩薩戒義疏』に基づいています。
ところで、十「重」に対して四十八「軽」という語感から、四十八軽戒はそれほど重要な戒めでは無いと捉えられがちであるでしょう。けれども、『梵網経』に説かれる一々の戒条を見た時には、それが決して「軽」いものとは程遠いことを知るに違いありません。
世間では「大乗戒は小乗戒に比べてユルく、おおらかである」などという甚だしい誤解を抱いている者が多くあります。ところが、それは全くの事実誤認であり、無知に基づく思い込みにすぎません。支那以来日本において瑜伽戒に並んで奉じられた梵網戒は、「大らかである」とか「寛大である」とか言い得るものでは全然ない。
| 1 | 不敬師友戒 | 仏弟子が国王・大臣・官役に就くときには先ず菩薩戒を受けなければならない。そのとき和上・阿闍梨や同行の人を軽んじてはならない。 |
|---|---|---|
| 2 | 飲酒戒 | 故意に、酒を飲んではならない。酒を人に与えて飲ませてはならない。その相手が神や動物であれ、酒を飲ませてはならない。 |
| 3 | 食肉戒 | 故意に、それがどのような種類(鳥・肉・魚)のものであれ、肉を食べてはならない。 |
| 4 | 食五辛戒 | 大蒜〈葫𮏉〉・革葱〈薤〉・慈葱〈葱〉・蘭葱〈小蒜〉・興渠〈蒠蒺〉の五辛を、故意に食べてはならない〈*ここでは智顗説を例として示すが、五辛が具体的に何を指すかは諸説あり〉。 |
| 5 | 不教悔罪戒 | 諸々の戒を犯した者を見過ごし、その罪を教えて懴悔・悔過させないことがあってはならない。 |
| 6 | 不供給請法戒 | 大乗の法師、客比丘の来訪があった時、これを種種にもてなし、その説法を請わないことがことがあってはならない。 |
| 7 | 懈怠不聽法戒 | 何処であれ比丘が律蔵や経典を講説をしていたならば、その場所に行ってそれを聴聞しないということがあってはならない。 |
| 8 | 背大向小戒 | 大乗常住の経律に背いて(大乗は)仏説では無いと言って、声聞・縁覚や外道の、誤った禁戒や経律を受持してはならない。 |
| 9 | 不看病戒 | 病に苦しむ者に出会ったならば、これを仏の如くに供養しなければならない。怒りなど悪心をもって、助けぬ事があってはならない。 |
| 10 | 畜殺具戒 | 刀や槍、弓矢、鉾や斧など戦闘のための武器を所有してはならない。および生類を殺傷するための道具を蓄えてはならない。 |
| 11 | 国使戒 | 自分の利益や悪人の為に、国の使者となって軍隊の陣に出入りしてはならない。軍を動かし、大量殺人の助長をしてはならない。 |
| 12 | 販売戒 | 人身や牛・馬・犬・羊・豚・鶏など家畜の販売をしてはならない。および人の遺体を納める棺などを販売してはならない。 |
| 13 | 謗毀戒 | 悪心に基いて、根拠無く、善人や法師・師僧・国王・貴人など他者が七逆・十重を犯したなどと、誹謗してはならない。 |
| 14 | 放火焼戒 | 悪心に基いて、山林・広野を四月から九月の間、火を放って焼いてはならない。および他家や田畑、官庁、神を焼いてはならない。 |
| 15 | 僻教戒 | 仏弟子や外道、親戚や善知識に大乗の経律を教えず、悪心に基いて、声聞・縁覚の経論や、外道の論書を教えてはならない。 |
| 16 | 為利倒説戒 | 大乗の経律を求め来る新学の者には、まずその身や腕、指を焼かせて諸仏を供養しなければならない。そして、利養のためにその問いに答えず、大乗を誤って教えてはならない。 |
| 17 | 恃勢乞求戒 | 自らの名聞・利養の為に、国王や大臣など権力者におもねり、さまざまにその権勢を頼みに利益を求め収得してはならない。 |
| 18 | 無解作師戒 | 戒を学び読誦する者は、常に菩薩戒を憶持してその義利と、仏性とを解しなければならない。しかるにそれを解せずに偽って解すといい、他者の師となって戒を授けてはならない。 |
| 19 | 両舌戒 | 持戒の比丘が菩薩行を行じているのを見て、悪心をもって、彼らが相争うようにしたり、嘘言して悪行を行っていると謗ってはならない。 |
| 20 | 不行放救戒 | 六道の衆生は、生死輪廻の中、ことごとく我が父母であったものである。囚われた畜生があれば放生し、また父母兄弟の命日には、法師を屈請して菩薩戒経を講説せしめなければならない。 |
| 21 | 瞋打報仇戒 | 怒りに対し怒りをもって返し、危害に対して危害をもって報いてはならない。たとえ父母・兄弟・親戚を殺害されたとしても、復讐してはならない。 |
| 22 | 憍慢不請法戒 | 出家して間もなく、いまだ理解していないところが多くあるのに、己の才覚や出自・財産を誇り、先学の法師であるけれども出自が悪く、あるいは年下であると蔑んで、教えを受けないことがあってはならない。 |
| 23 | 憍慢僻説戒 | 仏滅後、菩薩戒を受けようと志す者で、親しく面前に授戒しえる師がいない場合は、仏・菩薩像の前で七日以上および一年間、好相を得るまで懺悔しなければならない。そこで、新学の菩薩が来たって様々な質問をされた時、軽蔑や慢心、悪心に基いて、それに答えないことがことがあってはならない。 |
| 24 | 不習学仏戒 | 大乗の正法を、学び修習する価値の無いものとして捨て、むしろ誤った声聞・縁覚や外道、俗典や阿毘達磨、書法や数学などを学ぶことは、道の障害となるものである。学んではならない。 |
| 25 | 不善知衆戒 | 仏滅後、能化や禅師・威儀師となるならば、慈心をもって僧達の争いを鎮めず、三宝物を管理して私物化してはならない。 |
| 26 | 独受利養戒 | 客比丘の来訪があったならば、これを迎えて様々にもてなし、送り迎えしなければならない。施主があって衆僧を供養する時には、客比丘をその招きから外してはならない。 |
| 27 | 受別請戒 | 施主があって特定の僧に対する供養の招き(別請)があったとき、これを受け、あるいは受けた布施を衆僧に分かたず、個人のものとしてはならない。 |
| 28 | 別請僧戒 | 僧であれ俗であれ、僧に布施をするのに際しては、特定の僧を指定して招いてはならない。 |
| 29 | 邪命自活戒 | 悪心によって、利益を得るために、売春したり、調理したり、男女の占い、夢の占い、呪術、書画・彫刻に携わったり、鷹匠の法を学び行ったり、毒薬を調合したり、金属加工に関わったりしてはならない。 |
| 30 | 不敬好時戒 | 悪心によって、三宝を謗っていながら表面的には敬意を示したり、口だけで空を説きつつもその行いは有に執していたり、在家の男女に交際を薦めて淫行に及ばせ、六斎日・三長斎月に、殺生・偸盗など破斎・犯戒させてはならない。 |
| 31 | 不行救贖戒 | 外道や悪人・盗賊が、仏・菩薩像や経律を売り、比丘・比丘尼を売り、または大乗の菩薩を売って奴隷とされていたならば、それらすべてを慈心をもって買い取らないことがあってはならない。 |
| 32 | 損害衆生戒 | 刀や槍、弓矢などや、不正な秤や重りを販売してはならない。権力を傘にきて人の財産をかすめ取ったり、捕縛したり、失脚させてはならない。猫・狸・猪・犬を飼ってはならない。 |
| 33 | 邪業覚観戒 | 悪心によって、いかなる種類のものであれ、男女の諍い、戦争、盗賊の争いを観たり、音楽を鑑賞してはならない。囲碁・将棋・サイコロ・鞠・投石・投壺・髑髏などによって、占いをしてはならない。盗賊の使いをしてはならない。 |
| 34 | 暫念小乗戒 | 固く禁戒をまもり、常に戒を誦しなければならない。自らを未成の仏、諸仏は已成の仏であると知って菩提心を発し、一瞬たりとも忘れてはならない。一瞬たりとも、声聞・縁覚や外道を求めてはならない。 |
| 35 | 不発願戒 | 常に誓願を立てなければならない。父・母・師僧・三宝に従い、師・同朋・善知識が、自分に大乗の経律と十発趣・十長養・十金剛・十地とを教えて悟りに導いて、法に違わず修行し、戒を持って、命に変えても捨てないという願いを持たないことがあってはならない。 |
| 36 | 不発誓戒 | 十大願を立て、仏陀の禁戒を持ったならば、以下の願を立てなければならない。 ① むしろこの身が猛火・深坑・刀山に墜ちるとも、三世諸仏の経律を損って、どのような女性とも性交しない。
これら十三願を発さないことがあってはならない。② むしろこの身に灼熱の鉄の羅網が千重にも巻きつくとも、破戒の身でありながら、信者からの衣服(などの布施)を受けない。 ③ むしろこの口に熱い鉄玉や溶鋼を呑んで、百千劫を経るとも、破戒の口でありながら、信者からの飮食を受けない。 ④ むしろこの身が猛火の羅網・高熱の鉄板に臥せるとも、破戒の身でありながら、信者によって設けられた座に着かない。 ⑤ むしろ三百の鉾によって貫かれ、一劫二劫を経るとも、破戒の身でありながら、信者からの医薬を受けない。 ⑥ むしろこの身が高熱の鉄鍋に落ち、百千劫を経るとも、破戒の身でありながら、信者からの建物・園林・田地を受けない。 ⑦ むしろこの全身が鉄槌によって打ち砕かれるとも、破戒の身でありながら、信者からの尊敬・礼拝を受けない。 ⑧ むしろ百千の熱鉄の刃物で両目をえぐられるとも、破戒の心をもって、他の好ましき物を見ない。 ⑨ むしろ百千の鉄錐で鼓膜を突き刺され、一劫二劫を経るとも、破戒の心をもって、好ましい音を聞かない。 ⑩ むしろ百千の刃物で、鼻を削ぎ落とされるとも、破戒の心をもって、好ましい香りを嗅がない。 ⑪ むしろ百千の刃物で、舌を切り落とされるとも、破戒の心をもって、他からの食事の布施を食しない。 ⑫ むしろ鋭利な斧で、身体を切り刻まれるとも、破戒の心をもって、好ましい肌触りの衣類を着ない。 ⑬ 願わくは、一切衆生を悉く成仏に導かん。 |
| 37 | 冒難遊行戒 | (比丘は)春・秋は頭陀行を、冬・夏には坐禅し、雨季には如法に安居しなければならない。常に楊枝・澡豆・三衣・瓶・鉢・座具・錫杖・香炉・漉水囊・手巾・刀子・火燧・鑷子・縄床・経・律・仏像・菩薩像の十八物を用いなければならない。これらは頭陀を行ずる時は必ず携帯しなければならない。月二回の布薩の日には、各自三衣をまとい、十重四十八軽戒を誦しなければならない。ただし布薩に何人集まろうとも、誦すのは一人でなければならない。頭陀を行ずる時は、どこであれ危険や困難ある難処に入ってはならない。 |
| 38 | 乖尊卑次序戒 | 先に受戒した者は前に、後に受戒した者は後ろにと、(布薩など儀式が行われる時には)席次を守って如法に坐らなければならない。年齢の老少、比丘・比丘尼、国王・王子など貴族、性的不能者や奴隷など、その社会的地位や出自等によって席次を決めてはならない。 |
| 39 | 不修福慧戒 | 一切衆生を教化し、僧坊を建て、山林や田園地帯に仏塔を建立しなければならない。冬・夏の安居や坐禅処など、すべての修行の場にて、それは行われなければならない。そこで一切衆生のために、大乗の経律を講説しなければならない。様々な苦難・危機の時や、家族・和上・阿闍梨が亡くなった日や四十九日までの七七日の節目にも、貪・瞋・癡が盛んなる時、多病なるときにも、大乗の経律を読誦・講説しないことがあってはならない。 |
| 40 | 揀擇受戒 | 人の為に授戒する時は、その受者の、社会的地位や出自、神や悪鬼、不具などを問うて拒絶せず、ことごとく授戒しなければならない。ただし、七逆を犯した者には、戒を授けてはならない。(出家者が)身に着ける袈裟・座具などは、(くすみ濁った)青・黄・赤・黒・紫などの壊色としなければならない。袈裟衣は、その土地独自の衣服があったとしても、かならずそれらと異なった(如法の)ものでなければならない。出家者は、国王・父・母・親族・鬼神を礼拝してはならない。法を求め来る者があるのに関わらず、悪心によって、誰であれ戒を授けないことがあってはならない。 |
| 41 | 為利作師戒 | 人を教化して信心を起こさしめ、戒を授けるために、人の教誡師〈教授師〉となる時は、和上と阿闍梨とを請わさせなければならない。和上と阿闍梨とは、受者に七遮〈七逆を犯した過去の有無〉を問わなければならない。もし十重禁戒を犯していたのであれば、戒を誦させ、また三千仏を礼拝させて、その上で好相を得るまで懴悔させなければならない。四十八軽戒を犯していた場合は、対首懴〈僧侶に面と向かって罪を告白し、懺悔すること〉にて出罪させる。大乗の経律など諸々の教えを理解していないにも関わらず、名聞利養を得ようと求めるが故に、理解していると詐り、人に戒を授けてはならない。 |
| 42 | 為悪人説戒 | 利養を得る目的で、いまだ菩薩戒を受けていない者や国王を例外として、誰であれ外道・悪人・邪見の人の前で、この菩薩戒を説いてはならない。 |
| 43 | 無慚受施戒 | 信心を起こして出家し、仏の正戒を受けておきながら、意図的に聖戒を犯したならば、いかなる信者からの供養も受けてはならない。また国王の土地を通行し、国王の水を飲んではならない。五千の大鬼が常にその前を遮って、鬼から「大賊め!」と言われるであろう。すべての世俗人は罵って「仏法中の賊である」と言って、見ることすら厭うであろう。犯戒の人は畜生、木頭と異ならない。正戒を(意図的に)犯してはならない。 |
| 44 | 不供養経典戒 | 常に大乗の経律を受持・読誦しなければならない。その(自らの)皮を剥いで紙とし、その血をもって墨とし、その髄をもって水とし、その骨を割いて筆として、仏戒を書写せよ。木皮・穀紙・素絹・竹帛にも、戒を書いて持たなければならない。様々な宝などで納める箱を作り、経律を納めて如法に供養しなければならない。 |
| 45 | 不化衆生戒 | 常に大悲心を起こし、どのような場所であれ一切衆生を見たならば、「汝ら衆生、ことごとく三帰十戒を受けよ」と唱えなければならない。牛・馬・猪・羊などあらゆる畜生を見たならば、「汝は畜生であるが、菩提心を発せ」と、心に思い、口に言わなければならない。どこにあっても、菩薩は、一切衆生をして菩提心を発させるべきである。衆生を教化しないということがあってはならない。 |
| 46 | 説法不如法戒 | 常に教化を行じ、大悲心を起こして、信者や貴人の家など人々に交わった時、立ちながら在家信者の為に説法してはならない。在家人の前で説法などする時には、高座の上に坐ってなさなければならない。法師の比丘は、比丘・比丘尼・在家男・在家女の四衆の為に説法するときには、法師は高座に座して如法に説法し、四衆は地に座って法師を香華などで供養しなければならない。 |
| 47 | 非法制限戒 | 国王・王子・百官、あるいは(比丘・比丘尼・沙弥・沙弥尼、もしくは出家・在家の)四部の弟子であろうとも、自らの権勢を傘にきて、仏法の戒律を改変し、新たな禁則事項を作って四部の弟子を管理し、出家・修行などしてはならない。また、仏像・仏塔を建立し、経律を印刷することを制限したならば、破三宝の罪となる。行ってはならない。 |
| 48 | 破法戒 | 好ましい動機によって出家したにも関わらず、むしろ名聞利養を目的として、国王・百官の前で七仏戒を説いて(仏弟子の罪過をあげつらい、)菩薩たる比丘・比丘尼を逮捕・拘束させることは、獅子身中の虫に等しい。もし仏戒を受けたならば、その仏戒を護持することは「我がひとり子」を護るように、父母に仕えるようにしなければならない。外道や悪人が、仏戒について誹謗中傷するのを聞き放しにしてはならない。自身が誹謗中傷することについては言うまでもなく、また人に教えてさせてもならない。 |
四十八軽戒の条文には、律蔵の中で禁じられている行為や規定している行為をそのまま倣い言っているようなものもあります。また逆に、律蔵の規定からすれば完全に非法となるような行為を、むしろ推奨している場合があります。
しかしながら、『梵網経』の文言や規定には明瞭さが決定的に欠けており、注釈書無しには理解することなど出来ないものとなっています。それが為に、注釈する者によって相当内容が変わりうる点があり、実際諸師の説は異なっています。しかも、そのような注釈書を通して読んでなお、未だ不明瞭で得心のいかない点をまま残した如何ともし難いものです。
また、これは歴史的にもよく混同されてきたことでそれは現在も同様であるものの、よくよく注意すべきことは、『梵網経』はその所説の戒を三聚浄戒と絡めて説いてなどいないことです。『梵網経』に三聚浄戒の名目は一切ありません。ところが、これを支那や朝鮮の諸学僧のほとんど多くは三聚浄戒の範疇で理解しようと勤めており、上掲の十重四十八軽戒を三聚浄戒のいずれかに配当しようとアレコレ自説を展開したのでした。というのも、前述したように、『本業経』は『梵網経』と同じ十重禁を説き、それをまた三聚浄戒(三受門)に関連付け説いているためです。
けれども、そのような営為は、むしろ三聚浄戒を説く『菩薩善戒経』や『瑜伽論』の所説との撞着をもたらすものとなっており、なにより印度以来の伝統に全く無いことであって、その故に大きな問題を孕むものとなっています。
一般に、戒として説かれる学処とは「~してはならない」と説かれるものです。それはいわば止悪、すなわち悪をなさないための行動規範です。あるいはある具体的行為を挙げ、そこから離れるべきことをいうものです。ところが、『梵網経』が軽戒として挙げる中には、「~してはならない」という禁則を挙げつつ、併せて「~しなければならない」との行動規定が、しかも多岐にわたってなされている場合が多くあります。それはいわば修善、すなわち善を積極的になすための行動規定となったものとは言えるでしょう。
実際、四十八軽戒の中には、かなり具体的な行為について言及している項目が多くあります。また四十八軽戒には、一つの戒条として説かれている中に、複数の戒として別出しえるような、しかも互いに関連性の全然認められない内容が説かれています。それは梵網戒が、印度以来のその他の戒と甚だしく異なっている点であり、その正確な理解を困難にしている原因の一つとなっています。
あるいは、例えば第八の「背大向小戒」のように、これを文字通り理解した時には、外道に対してならば理解できますが、声聞・縁覚の二乗いわゆる小乗に対しても極めて排他的なあり方を要求したものなっています。しかし、それは「三宝」について、特に「僧宝」において大きな混乱を生じさせるものであり、また当時の支那の仏教事情として甚だ非現実的な条項です。すなわち、これは文字通りに理解することが出来ない条項となって、書かれたとおりには行わないよう解釈する必要を生じさせています。
というのも、一世紀中頃に仏教は支那に伝わっていたとはいえ、六世紀頃から七世紀にかけてようやく請来・整備され、出家者に必須のものとして行われるようになった律(具足戒)との整合性が全然とれなくなる条項であるためです。それはまた、『大智度論』や『瑜伽師地論』など既に大乗として不可欠の重要な論書における戒(三聚浄戒)や律についての所説とも、大きく矛盾する規定となっています。
四十八軽戒の中にはさらに理不尽、もしくは極端と思える事項が義務として説かれている箇条もあって、それらもまた大きな問題を孕んだものとなっています。たとえば、第十六の「為利倒説戒」や第四十四条の「不供養経典戒」などです。
もっとも、そのような「自身を損ねることによって諸仏を供養すること」を賛嘆・推奨するのは、たとえば『法華経』においてなされていることではあります。
若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者。能燃手指乃至足一指供養佛塔。勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供養者。
「もし無上正等正覚を得たいと思う者があって、みずからの手の指および足の指を燃やして仏塔を供養したならば、それは国や城や妻子、および三千大千国土の山・林・河・池や諸々の珍しき宝物を供養する者に勝るのであろう」
鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』薬王菩薩本事品第廿三 (T9, p.54a)
しかしながらこれは、いわゆる捨身飼虎の本生譚とは全然本質を異にするものです。
また、譬喩など表現上のこととしてならば兎も角として、実際にそのような行動をなすことは、律からすればあきらかに非法(突吉羅・悪作)であって、出家者のなすべきでない行為です。さらに社会として云えば、これをそこらの巷で行われてしまったならば、社会に混乱をきたすことでもあります。その故に、『梵網経』の所説が仏教としてあれこれ自己撞着したものとならぬよう、そして現実的に解釈する必要性が生じてきます。
繰り返しますが、ただ単にわかりにくいというだけで注釈が必要であったわけでもなく、むしろ文字通りに理解してしまうと重大な矛盾をきたしてしまうためにも注釈が必要となったのでしょう。そこで結局、過去の支那ひいては日本の比丘達はどうしてきたのかというと、これは必然的というべきか、むしろ律の所説を優先し、インド以来のあり方を踏襲しています。
また、それは日本の僧尼に対する世法たる『僧尼令』においてもまさしく禁止されている行為でもありました。
第二十七 焚身捨身條
凢僧尼不得焚身捨身。若違。及所由者並依律科罪。
第二十七条 焚身捨身条
およそ僧尼が、身を焚き身を捨ててはならない。もし違反したならば、および所由の者は、いずれも律に依って罪を科せ。
『養老律令』令第三「僧尼令」
現代的見方のみからして「理不尽」・「極端」と思えるわけではなく、それは千年以上昔の支那や日本でも同様でした。そしてそのような過激な行動を実際に行う者は、社会や人心を惑わし不安にさせるものです。であるからこそ、世法としてわざわざそれを明文化し、禁止したのでありましょう。
そのように『梵網経』に説かれているからと言って、そのすべてがそのまま文字通りの意味で支那でも本邦でも古来行われたわけではありません。いや、惜法規利戒や不敬経律戒についていえば、鑑真渡来以前の日本において文字通りなされていたことが知られます。
壬辰。詔曰。置職任能。所以敎導愚民。設法立制。由其禁斷姧非。頃者。百姓乖違法律。恣任其情。剪髪髠鬂。輙著道服。貌似桑門。情挾姧盗。詐僞所以生。姦宄自斯起。一也。凢僧尼。寂居寺家。受敎傳道。准令云。其有乞食者。三綱連署。午前捧鉢告乞。不得因此更乞餘物。方今小僧行基。并弟子等。零疊街衢。妄説罪福。合構朋黨。焚剥指臂。歴門假説。强乞餘物。詐稱聖道。妖惑百姓。道俗擾乱。四民棄業。進違釋教。退犯法令。二也。僧尼依佛道。持神咒以救溺徒。施湯藥而療痼病。於令聽之。方今僧尼輙向病人之家。詐禱幻恠之情。戾執巫術。逆占吉凶。恐脅耄穉。稍致有求。道俗無別。終生姧乱。三也。
(養老元年〈717〉四月)壬辰〈23日〉、詔して曰く、官の役職を置いて能力ある者を任命するのは、愚民を教導するためである。法を設けて制を立てるのは、その姦非〈よこしま。悪〉を禁断することを目的としたものである。この頃、百姓〈あらゆる階層の人々、公民〉には法律に乖違して、恣にその情に任せて髪を剃り鬂〈もみあげ〉を剃って安易に道服〈袈裟衣〉を着け、その容貌のみ桑門〈śramaṇaの音写。一般には沙門。遊行者、特に仏教僧〉に似せながら〈「僧尼令」第二十二 私度条に抵触する行為〉、その情は姦盗〈たちの悪い盗賊〉に変わりない者がある。しかし、それは詐欺の生じる所以であり、姦宄〈心が邪で悪いこと〉が起こる(一也)。
およそ僧尼とは、寺家に寂居して教えを受けて道を伝えるものである。令〈「僧尼令」第五 非寺院条〉に准じれば、「もし乞食を行じようとする者があれば、三綱〈当時の各寺院における三人の寺院管理者。上座・寺主・維那〉は連署して(官にまず報告し、その許可を得てから)、午前に鉢を捧げて行乞せよ。その許可を得たことにかこつけてさらに他の物〈食以外の物品・金品〉を乞うことは出来ない」。しかしまさに今、小僧行基ならびにその弟子等は、街衢〈市街地〉に零疊〈無闇に群衆すること〉し、みだりに罪福を説いて朋党を合わせ構えている。そこで(仏菩薩への供養と称して)指を焼いたり(経文を書くために)腕の(生皮を)剥いだりし〈行基らは梵網戒の第十六条・第四十四条を現実に行わせていた。しかし、それは「僧尼令」第二十七 焚身捨身条に反する行為であった〉、家々を経巡って不可思議なことを説きまわり、(食以外の)金品を布施するよう強いている。それは聖道〈仏教〉を詐称するものであって、百姓を妖惑し、道俗〈出家者・在家者〉を擾乱。ついに四民〈全ての階層の人々〉はその業〈職業〉>を放棄している。(行基らは)進んで釈教〈仏教〉に違え反し、また法令を退ぞけ犯している(二也)。
僧尼が仏道に基づき、神咒を持すことによって溺れる者〈救いを求める者〉を救い、湯薬を施して痼病〈長患い〉を療やすことは、令に於いても許されてることである。(しかしながら)まさに今、僧尼が軽はずみに病人の家に向かい、詐って幻怪の情を祈り、戾って〈道理にもとること〉巫術を執り、逆しめて〈道理に背くこと〉吉凶を占っている。それは耄穉〈老いて耄碌した者。知性の低い者〉を脅迫するものであり、(そのようにして)次第に(自身らが)求められるよう誘導しているのだ。(これを放置すれば)道俗の別を無くし、終には姦乱を生じるであろう(三也)。
新訂増補『国史大系』普及版(『続日本紀』前篇, pp.68-69)
『続日本紀』巻七 養老元年四月壬辰条
以上の記述から、鑑真渡来以前の日本では、むしろ巷間において『梵網経』を信受して文字通りに行う者があり、その故に法令を悉く犯していたことが知られます。
しかしそれは、朝廷からすると仏教を理解していない無知の輩らによる治安擾乱の振る舞い以外の何物でもなかったようです。実際、現代でも、それがいくら仏教の一部で説かれていることであったとしても、自らの指を「供養である」などと称して焼かせ、あるいはその皮を剥がせてそこに経文を血肉で書かせるなどという一団があったならば、そのような極端で非理知的な説にむしろ惹かれて信者となる者も一定数現われることでしょうが、社会はたちまち拒絶反応を示すでしょう。
この一説の後半では、現代の拝み屋じみた寺社や新興宗教団体などが人の無知や窮乏に漬け込んでさらに宗教的恐怖を煽り立て、自身らに依存させる方向に導いていくという典型的な手法が、当時から行われていたことが描き出されています。それは実は正史にすら載る、伝統的・古典的手法であったかとただただ驚くばかりでありましょう。それは「道理にもとる」ものであると1300年の昔においても見なされていたのであって、自然科学のある程度発達した今だからこそそう見なし得ることではない。
聖武天皇代となると、「小僧行基」と貶称されたその評価が「行基大僧正」という前例のない官職を与えられるなど真逆のものとなっています。しかし、一代前の元正天皇時において、行基の一団は今で言うカルト教団、あるいは反社会的勢力扱いされていました。
後代、行基は東大寺建設の功労者とされたことからも様々な伝説に彩られます。そこで、行基に関してはむしろ積極的に評価され、むしろ当時の朝廷が宗教的救いやその自由を縛らんとしたけしからんものであった、などといった調子で見る者こそ、昭和以来今もなお多くあるように思われます。しかし、以上のような『続紀』の記述を見たならば、行基の教団の振る舞いは、現代でカルトとされる新興宗教そのものと評する以外にありません。
このような事実から、鑑真渡来により戒壇院で具足戒の授戒前後に行われた菩薩戒とは『梵網経』所説の梵網戒ではなく、『菩薩善戒経』や『菩薩地持経』・『瑜伽師地論』所説の三聚浄戒いわゆる瑜伽戒であった可能性があります。しかし、当時の戒壇院で授受されていた菩薩戒が具体的に何であったかについては、そこにおける受戒が茶番劇化し単なる通過儀礼となって律学も行われなくなった平安後期にはすでに不明瞭となっており、今なおわかっていません。もっとも、日本の史学者や仏教学者からは一般に、それは梵網戒であったろうと漠然と見なされています。が、実はそれも確たる根拠あってのことでは必ずしもありません。
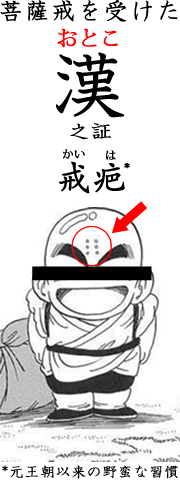
なお、これは元朝以来の比較的新しいことであるようですが、支那では現在も実際にこれを行う習慣がいまだあります。戒疤(香疤)です。
(文革以降、次第にその勢力を宗教を否定し徹底的に弾圧していたはずの共産党の支援のもとに急速に大きくしている中国の仏教者は、基本的に具足戒を受ける前に必ずこれを行っています。事実、私の友人らは男僧は頭に、尼僧は腕や太腿などに九箇所あるいは十二箇所していました。)
また、すでに『僧尼令』などまったく空文化してその存在自体無視されていた日本の近世に実施された戒律復興運動においても、前述の『梵網経』の所説を文字通り実行し、実際に身のどこかを香で焼かなければ(大体が肘で行ったため、これを「肘香」などとも称した)、受戒させないなどという僧らがありました。彼らは全く戒律など滅んで絶無となっていた時代であったからこそ、まさしく経典に書かれている通りのことを忠実に実践しようとし、それをまた自身らの正当性の根拠ともしていたのです。
もっとも、そのように梵網戒の一々の細部を見たならば種々の、しかも決して小さくない問題があり、忌憚なく言ってしまえば実に愚かしく馬鹿らしいと思われる点が多々あります。しかし、それらにかまけて梵網戒の底に通じて流れる一つの徳を見逃してはならない。それは慈悲です。
あくまで輪廻を前提とし、生きとし生けるものが生まれ変わり死に変わりする様を大なる苦しみと見、しかもそのように生死流転する中で、互いに父母となり子となってきたこと。それを真であるとするからこそ、すべての生けるものに対して慈悲を持って対することを説き、そこから脱する道をその対象を問わず広く示すこと。それがまさに孝であると説かれていることです。
慈悲とは、単純に言えば「怒らず、害さないこと」です。とは云え、しかし、ただ単に「やさしくて朗らかであること」ではありません。ある場合、ある観点からすれば、それは非常に厳しい態度が求められるものでもあります。その内容に差異こそあれ、すべての仏教に通じて説かれる、どうしても人が解脱に達するのに必要な徳であります。経典としての真偽問題は別問題として、『梵網経』の根底に慈悲が流れていることは確かです。