戒を受け、それを護持することについて、『梵網経』はどのように説いているのか。
一切有心者 皆應攝佛戒 衆生受佛戒 即入諸佛位
位同大覺已 眞是諸佛子
すべての心ある者よ、皆まさに仏戒を摂受せよ。衆生が仏戒を受けたならば、たちまち諸仏の位に入り、位が大覚に同じとなったならば、真にそれは諸仏の子である。
《伝》鳩摩羅什訳 『梵網経』盧舍那佛説菩薩心地戒品第十 卷下
(T24, p.1004a)
先に挙げた偈文の中で、衆生(人)は戒を受けることによって諸仏に等しい者、すなわちそれは完全な覚りを得るに至りえると述べられています。梵網戒の功徳、それは仏果であると。
仏教は声聞乗・縁覚乗・菩薩乗の別があって、また諸宗諸派並び立って様々に見解を異にしているとはいえ、「戒学」を第一とする戒・定・慧の三学を修めることを必須とすることは通じています。大乗においてその修道法として強調される六波羅蜜は三学を敷衍展開したものであり、戒波羅蜜はまさに戒学に同じです。そこでもし、戒を軽視もしくは戒を不要として「信こそ重要」あるいは「信心を持つことが戒である」等と喧伝し、それを「真の仏教である」などと謳う者があれば、それは仏教ではありません。
ここで『梵網経』もまた戒を受けることの重要性を強調しているのですが、しかし、この一節で「衆生受佛戒 即入諸佛位(衆生、佛戒を受くれば、即ち諸佛の位に入る)」というのを文字通り理解したならば、それを実行するかどうかはともかく、「戒を受けたならば、たちまち諸仏の位に入る」かのように思われるかもしれません。
しかし、これは別項「戒律という言葉」および「戒とは何か」において強調していることですが、そもそも戒とそれを実現するための学処とは異なります。戒([S]śīla)とは目指すべき指針、理想的状態です。そして学処([S]śikṣāpada)とは、その状態に自らをあらしめるための禁則、あるいは行動規定であって、まさに「学ぶべきところ」です。ところが、支那において戒と学処との違いは明瞭に理解されず、往々にして同一視され、それらの漢訳も厳密になされずに混同されてきた事実があります。
そこで一般に「戒を受ける」と云われます。しかしそれは、実は「学処を受ける」ことに他なりません。学処を受けただけで戒が実現することなど決してありません。
ところが、支那において『梵網経』と同系統の菩薩戒経として重要視され用いられた『本業経』では、特に「大乗戒を受けること自体」について、一見すると非常に特異と言える説が示されています。
佛子。若過去未來現在一切衆生。不受是菩薩戒者。不名有情識者。畜生無異。不名爲人。常離三寶海。非菩薩非男非女非鬼非人。名爲畜生名爲邪見。名爲外道不近人情。故知菩薩戒有受法而無捨法。有犯不失盡未來際。若有人欲來受者。菩薩法師先爲解説讀誦。使其人心開意解生樂著心。然後爲受。
又復法師能於一切國土中。教化一人出家受菩薩戒者。是法師其福勝造八萬四千塔。況復二人三人乃至百千。福果不可稱量其師者。夫婦六親得互爲師授。其受戒者。入諸佛界菩薩數中。超過三劫生死之苦。是故應受。有而犯者勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。 《中略》
一切菩薩凡聖戒盡心爲體是故心亦盡戒亦盡。心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒。但解語得戒不失。
「仏子よ、もし過去・未来・現在のすべての衆生で、この菩薩戒〈十無尽戒・十波羅夷不可悔法〉を受けない者など、知性ある者であると言えない。畜生〈動物〉に異なるものでなく、人と言えない。常に三宝という海から離れている。菩薩でなく、男でもなく、女でもなく、鬼〈死霊・餓鬼〉や神でもない。畜生である。邪見である。外道であって人情に近いものでない。故に知るであろう、菩薩戒に受法は有っても捨法は無いことを。犯すことがあっても失うことはなく、未來際を尽くす。もし人が来たって(十無尽戒を)受けることを望んだならば、菩薩の法師は先づ(その者の)為に解説し、読誦し、その者の心を開かせ、意を解かせ、楽著の心を生じさせて後、その為に受けさせよ。
また、法師がいかなる国の中においてであれ、一人の出家者を教化して菩薩戒を授けたならば、その法師の福〈功徳〉は八万四千の仏塔を建てることに勝る。ましてや(それが)また二人・三人、乃至、百千人に及べば、その福果は計り知れない。その師たるのに、夫婦や六親眷属が互いに師となり受者となることが出来る。その戒を受けた者は諸々の仏界の菩薩衆の中に入り、三劫に生死流転の苦を超過するであろう。そのようなことから(十無尽戒を)受けるべきである。(十波羅夷不可悔法を受けて)有って犯す者は、無くて犯さない者に勝る。(十無尽戒を受けて)犯す者を菩薩といい、犯さない者を外道という。 《中略》
すべての菩薩、凡聖の戒は尽く心を体〈本質〉とする。そのことから心がまた尽きたならば戒もまた尽きるであろう。(しかしながら、)心が尽きることなど無いことから、戒もまた尽きることはない。六道の衆生は(誰であっても)戒を受けることが出来る。ただ(戒の内容を述べた)言葉を解すならば戒を得て失うことはない。
《伝》竺佛念訳 『菩薩瓔珞本業経』卷下 釈義品第四(T24, p.1021b)
以上のように、『本業経』では、戒を授受する両者に大きな功徳があるといい、特に「戒を受けること自体」を何より最も重要視しています。
就中、「不受是菩薩戒者。不名有情識者。畜生無異。不名爲人(是の菩薩戒を受けざる者は、情識有る者と名づけず。畜生に異なることなく、名づけて人と爲さず)」といい、「有而犯者勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道(有て犯ずる者は無くて犯ぜざるに勝る。犯有るを菩薩と名づけ、無犯なるを外道と名づく)」などという文言は、それを端的に表したものです。
『本業経』は『梵網経』に同じ十無尽戒を説く中、一々「若有犯非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯(もし犯あらば菩薩行に非ず。四十二賢聖法を失う。犯ずることを得ず)」などと言っており、破戒を推奨してなどいはしません。しかし、上に示した一節でそう言っているように、持戒することより受戒することこそ尊ばれています。
常識的な見方からすれば、今ここに示した『本業経』の一節は途方も無い、上記を逸したことを主張したものです。
しかし、このような常軌を逸した説は、むしろその故に支那の諸学僧の眼を引くものとなっています。そもそも支那で『本業経』を最初に着目し、取り上げてその説に組み入れた人は智顗です。これは『梵網経』にもほぼ同じくいえることですが、『本業経』が智顗以前に信受され、行われた痕跡はありません。智顗はこの経を梵網戒の注釈を行う中で取り上げ(『菩薩戒義疏』)、またその主著においても言及しています。
法才王子及涅槃中退轉菩薩。從初已來歸依一體三寶熏修戒善。有受法無捨法。心無盡故戒亦無盡。一切戒善爲此所熏。
法才王子〈文殊師利〉および涅槃における退転菩薩は、その(発心の)始めより、一体三宝に帰依して戒善を薫修してきた。(菩薩戒〈『梵網戒』・『本業経』所説の戒〉には)受法は有るけれども捨法は無い。心が無盡であるから戒もまた無盡である。すべての戒善は、そのようなことから薫じえるのである。
智顗 『摩訶止観』卷第三之下(T46, p.35b)
智顗の後、法蔵もまたその注釈『梵網経菩薩戒本疎』において、むしろ菩薩戒の功徳の重大なことと戒がいかに重要であるかの根拠として挙げています。そしてそれ以降も、支那ばかりでなく新羅の学僧らも続々と『本業経』の説を菩薩戒を講じる中で取り上げています。
このような見解はやがて日本でもおのずから受け入れられ、例えば日本天台宗の第三代となった円仁〈794-864〉は、その著『顕揚大戒論』菩薩受戒法式において以上の一説をまるごと引用しています。菩薩戒について「一得永不失」すなわち「一度得たならば永久に失うことはない」との『本業経』の説は、天台宗にとどまらず華厳宗や法相宗、そして禅宗などにも広く伝播していったのでした。
とはいえ、それら学僧はあくまで持戒厳重たることを前提として論じる中で引用したものであり、ただ受戒するだけで良しなどとする論拠として用いてはいません。
ところが、時代が下り、また国が変わって日本の古代末期から中世ともなると、特に中古天台の僧徒には自身らの甚だしく堕落したあり方を肯定し得るものとして、「一得永不失」は非常に魅力的な一節として受け止められていきます。実際、『本業経』の説は日本の中古天台の僧徒をはじめ、やがてはその影響を受けた律宗の者にまで珍重されるようになっていきます。たとえば、「無戒の比丘より破戒の比丘」などということが平然と言われるようになり、さらには平安後期から世に流行を見だした末法思想、浄土教の流行も手伝って、「むしろ破戒して可なり」となっていくのです。
『本業経』は「佛戒を受くれば、即ち諸佛の位に入る」、あるいは「その戒を受けた者は諸の佛界の菩薩數の中に入て、三劫生死の苦を超過する」といい、さらに「有て犯ずる者は無くて犯ぜざるに勝る。犯有るを菩薩と名づけ、無犯なるを外道と名づく」などと断言されており、それを文字通り読んだならば、受戒すること自体が非常なる功徳あるものとされ、持戒の意義や価値には全然言及されていないのだから。
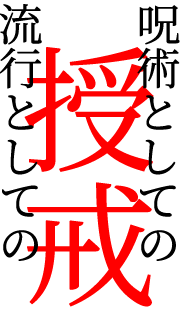
さこでまた、平安中期頃からは巷間、といっても主として貴族の間でのことですが、『本業経』を根拠として「菩薩戒を受けること」が流行していきます。病気になったならば平癒を願って受戒、身重となったならば安産を期して受戒。けれども受けた戒など守るつもりなど端から毛頭無いし実際守らない、となっていくのです。受戒することが現世利益を叶え得る「アリガタイもの」と見なされるようになり、いわば呪術的・祈祷的性格色濃い儀礼となっていったのです。
この極めて愚かで浅ましい理解は、しかし、現在にいたるまで脈々と受け継がれています。おそらくはまったく無意識的に。
事実、現在の多くの総本山といわれる大寺院や地方寺院などにおいて、常時あるいは時々行われている在家信者・檀家相手の「お授戒」なる儀式など、その戒の内容は問わず、現実的に戒が受持されることなど期待してもされてもおらず、受けるだけで「アリガタイ, アリガタイ, ナムナム」「イミ? ムズカシイコトハ, ワカラン」以上のものでありません。
ある場合には現世利益などすら期待されたものもないでしょう。そもそも、その正体が一体何かもわからずに行っているのだから。それはただ、暇を持て余している地方の高齢者、いわば仏教などほとんど知らず関心もなく、しかしただ因襲的に祖霊崇拝の装置として檀家寺との関係はもってきた高齢者らをのみ対象とした、宗教的風味ただよう気晴らし(リクリエーション)となっている、と言って過言でない。そして日本仏教の各宗派それぞれは、戒律についてほとんど明確な根拠を持たず、ただその独自性を主張した所見を持つに至っています。
とは言え、しかし、そもそも総じてどの宗派に属する者であれ、「戒律?時代が違う」・「そもそもインドなど南アジアとは気候風土習慣が異なるのだ」・「そんな前時代的・不合理な規定にかまけるよりも重要な事があるだろう?」等といった釈明をする者はあっても、結局のところまるで戒も律も守るつもりも守ることも皆目ない点では全く同様です。
これは高野山や比叡山、そして南都諸宗に限らず、ほとんどすべての(今や律宗・真言律宗をすら含めた)日本仏教の宗派に言えることですが、もはや日本仏教における授戒(受戒)などと言うものは、その授受する両人とも誰一人として一つ一つの儀式・儀礼の由縁も意味もわからぬまま行う、単なる通過儀礼に過ぎません。
しかし、寺を継がなければならない者、あくまでも日本のボーサンをやりたい者は、 何某かのオジュカイという儀礼を受けておかなければ「宗門が与える僧侶という職業資格」が得られないため、その意味もわからないし、その意義もまるで無いことを分かっていても、皆必ず受けなければなりません。世間の人々は、そのような従来の寺院・僧職者らのあり方について、多くの疑問や嫌悪感すら感じるようになり、それは年々多く、そして強くなっていっているようようです。いや、もはやそのような批判を起こす程の興味すら失われているといったほうが現実的でしょうか。
そのような現状にあって、そのような僧職者らが、営業時間内だけ袈裟衣をまとって取り澄ました顔をしながら、「日本は大乗であるから大乗戒をこそ」だとか「これはアリガタイ大乗戒であるから、受けるだけで意味があるのデス」などと力んで宣伝してみたところで、それを一体どうしてどのような形であれ現実的価値あるものとして、社会が望み、人々が受けいれることがあるでしょうか。
これは、現代の葬儀につきまとう戒名(そして戒名料)という、受ける側(すなわち死者とその親族)はまったくその意味も価値も見出せない、どこまでも不合理としか思えぬ因習にも、大いに関連する問題でもあります。
梵網戒すなわち十重四十八軽戒は、僧俗に通じて説かれた戒であって、大乗を奉じる者であるならすべからく受けたもつべき、菩薩戒であるとされたものです。その中でも十重禁戒の一々は、もっとも厳重に守るべき戒として示されています。
しかしながら、梵網戒を受けるのその全てではなく、その一部をのみ受ける「分受」ということが支那および日本で行われてきました。しかし、その分受ということの根拠を『梵網経』に求めることは出来ません。それは先に言及した『本業経』における、「有て犯ずる者は無くて犯ぜざるに勝る。犯有るを菩薩と名づけ、無犯なるを外道と名づく」に続く、以下の一説に依るものです。
以是故。有受一分戒名一分菩薩。乃至二分三分四分。十分名具足受戒。
「この故に一分の戒を受けた者を一分の菩薩と名づけ、乃至、ニ分・三分・四分、十分〈十無尽戒〉(の全て)を受けることを具足受戒と名づける」
《伝》竺佛念訳 『菩薩瓔珞本業経』卷下 釈義品第四(T24, p.1021b)
このような戒の一部のみを受けるという発想は、『本業経』にのみ見られるものではありません。実は『梵網経』とも密接なつながりを有すると思われる、大乗経典『優婆塞戒経』に分受ということが説かれています。
善男子。諦聽諦聽如來正覺説優婆塞戒。或有一分。或有半分。或有無分。或有多分。或有滿分。若優婆塞受三歸已。不受五戒名優婆塞。若受三歸受持一戒。是名一分。受三歸已受持二戒。是名少分。若受三歸持二戒已若破一戒。是名無分。若受三歸受持三四戒。是名多分。若受三歸受持五戒。是名滿分。汝今欲作一分優婆塞作滿分耶。若隨意説。
「善男子、諦かに聴き、諦かに聴け。如來正覚が優婆塞の戒を説かれるのに、あるいは一分あり、あるいは半分あり、あるいは無分あり、あるいは多分あり、あるいは満分ある。もし優婆塞が三帰を受けたならば、五戒を受けなくとも優婆塞と名づける。もし三帰を受けて一戒を受持したならば、これを一分と名づける。三帰を受けて二戒を受持したならば、これを少分と名づける。もし三帰を受けて二戒を受持しながら、もし一戒を破ったならば、これを無分と名づける。もし三帰を受けて三、四戒を受持したならば、これを多分と名づける。もし三帰を受けて五戒を受持したならば、これを満分と名づける。汝は今、一分の優婆塞と作ろうと欲するか。満分(の優婆塞)と作ろうと欲するか。意に隨って説け」
曇無讖訳 『優婆塞戒経』卷三 受戒品第十四(T24, p.1049a)
以上のように、『優婆塞戒経』では、在家仏教徒たる優婆塞(ひいては優婆夷)とは「三帰依した者」のことであることを説き、そうしてなお五戒を受ける者は受けるべきことを云います。そして五戒を受けるにも五種の別があるとされています。そしてそれはその戒を受ける者の意に従ってなされるものです。それがまさに分受です。
五戒の受に五種の別があって五種の優婆塞があるとされるのは、実は『大智度論』にても同様に説かれることです。そこではしかし、挙げられるその五種というのに少しく相違が見られます。
是五戒有五種受。名五種優婆塞。一者一分行優婆塞。二者少分行優婆塞。三者多分行優婆塞。四者滿行優婆塞。五者斷婬優婆塞。一分行者。於五戒中受一戒。不能受持四戒。少分行者。若受二戒若受三戒。多分行者。受四戒。滿行者。盡持五戒。斷婬者。受五戒已師前更作自誓言。我於自婦不復行婬。是名五戒。
この五戒には五種の受があって、五種の優婆塞と名づく。一つは一分行の優婆塞、二つには少分行の優婆塞、三つには多分行の優婆塞、四つには満行の優婆塞、五つには断婬の優婆塞である。一分行とは、五戒の中、一戒を受けて四戒を受持することが出来ないもの。少分行とは、もしくは二戒を受け、もしくは三戒を受けるもの。多分行とは、四戒を受けるもの。満行とは、ことごとく五戒を持つもの。断婬とは、五戒を受けて師の前にて更に自誓し、「我は自らの婦に対してもまた婬を行じない」というものである。これを五戒と名づける。
龍樹 『大智度論』卷十三 釈初品中尸羅波羅蜜義第廿一
(T25, p.158c)
そもそも、釈迦牟尼ご在世の当時、その信者としてAmbapālī(菴摩羅)というその美貌で知られた裕福な芸者、今でいう高級娼婦がありました。彼女は仏法僧の三宝に帰依し、また五戒を受けていました。けれども彼女は娼婦であったため、五戒のうち邪淫戒を守ることは端から出来ることではありませんでした。
しかし、だとしても、それを問題視する者など誰もおらず、五戒いずれかを保てなかったとて、それで「仏教徒としての波羅夷罪である」などと断罪されることなどありません。五戒を犯したことによって仏教徒として他の仏教徒から罰せられるなどということも無く、また「ホトケサマがバチを当てる」などということも決して無く、あくまでその行為に応じた結果を自ら受けるのみ。自業自得です。
例えばもし、在家の信者が殺人を犯したとしたならば世法によって裁かれ、またその果報を自身が受けるのみのことです。しかしそれで仏教徒でなくなる、教団から排除される等ということはありません。
戒(śīla)の本義「道徳」からすれば、それを学処として受けようが受けまいが、そこで忌避すべきとされる行為が不道徳、不善であることに変わりありません。そのようなことからすれば、戒を分受というのはおかしな話となります。そして、『梵網経』の所説からしても、「分受」ということはおそらく認められず、故に説かれてはいないのでしょう。なお戒を分受するというのは、受けた学処を犯すことを忌避し、どこまでも固く護持しようとする精神から成されだしたことであったのでしょう。
そこで、所説の十重を同じくする『本業経』がそれを良しとしていることによって、実際には梵網戒は分受されています。特に日本の往古、天皇や公家などは習慣として、またはその立場としても、複数の女性と関係を結ぶことがごく当たり前になされ、むしろそうしなければならなかったため、婬戒(邪婬戒)を守ることが端から無理である場合がありました。そこで『優婆塞戒経』や『本業経』の説に拠り、最初から婬戒などを除いて受戒していたのでした。
ただし、分受というのはあくまで在家においてのみ許されることであって、比丘や沙弥において許されることではありません。
ここでまた翻って、『本業経』の説と綯い交ぜにされながらも、そもそも菩薩戒の根本的な経典として奉じられてきた『梵網経』では、どのように持戒について説いているのかを改めて示します。
善學諸仁者。是菩薩十波羅提木叉。應當學。於中不應一一犯如微塵許。何況具足犯十戒。若有犯者不得現身發菩提心。亦失國王位轉輪王位。亦失比丘比丘尼位。亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果。一切皆失墮三惡道中。二劫三劫不聞父母三寶名字。以是不應一一犯。汝等一切諸菩薩今學當學已學。如是十戒應當學敬心奉持。八萬威儀品當廣明
「波羅提木叉を)善く学ぶ諸々の仁者よ、これは菩薩の十波羅提木叉である。まさに学ぶべきものである。この中の一一を犯すことなど、微塵ばかりとしてもあってはならない。ましてやすべて十戒を犯すなどあってはならない。もしこれを犯したならば、(その者は)現身に菩提心を発すことが出来ない。あるいは国王の位・転輪王の位を失い、あるいは比丘・比丘尼の位を失い、十発趣・十長養・十金剛・十地・仏性常住の妙果を失うであろう。全てを失って(地獄・餓鬼・畜生の)三悪道に堕ちて二劫・三劫の間は、父・母・三宝の名をすら聞くことが無いであろう。そのようなことから一つとして犯してはならない。汝らすべての諸菩薩で、今(これを)学び、まさに学ぼうとし、すでに学んでいる者らよ、このような十戒をまさに敬意をもって奉持し、学ぶべきである。(これについては本経の)「八万威儀品」にてさらに詳しく明らかにするであろう」
《伝》鳩摩羅什訳 『梵網経』盧舍那佛説菩薩心地戒品第十 卷下
(T24, p.1004a)
『梵網経』では、その偈文において「衆生が仏戒を受けたならば、たちまち諸仏の位に入り、位が大覚に同じとなったならば、真にそれは諸仏の子である」と戒が仏果の因であり、また仏果という果報をもたらすものといいますが、そこで受戒自体が尊いなどとはまったく意図されていません。前項にて示した四十八軽戒のいくつかでも言及されているように、『梵網経』が破戒を非常に厳しく諌めていることは明白です。
とはいえ、現実問題、そもそも人がいわゆる「受戒」したからと言って、その内容にも依るでしょうが、たちまちそれらを完璧に身に備えることなどほとんど誰も出来かねることです。
「過ちて改めざる。是を過ちと謂う」と言い、あるいは「過ちては改むるに憚ること勿れ」と言うは古今東西の道理。仏教における戒律とは、まさにこれら諺に言われるような態度を人に求めるもので、それによって自身が自身を正してその徳を身に備えて救い、また他を化していかんとするものです。
これは戒であろうと律であろうと同様で、律の伝統を堅持してきた上座部を信奉する南方の国々における比丘らも、その受持する律をすべて完璧に守っているなどということは決してありません。そして、律をどの程度厳しく守っているかも、国や地域そして派の異なりによって、相当の違いが見られます。実際、比丘が細かい律儀を守っていないことで「破戒僧だ!」などといわれることはありません。
律蔵にて定められる諸々の律儀、比丘の学処にはそれを犯した場合の罪の軽重・優先度の高低といったものが存しており、その制度や構造を知ったならば、それは容易に理解できることです。
例えば、現代社会において、制限速度60キロのところを80キロで走ったり、歩行者が赤信号を無視して渡ったならば、それはもちろん道路交通法違反ですが、それを「違反者」ということはあっても「犯罪者!」と言う人は普通無いでしょう。そしてまた、制限速度60キロの道を90キロ以上で走ったとして、実はそれは刑事罰の対象となって犯罪となり「前科」が付されるものですが、しかし一般的には、それで人を跳ねたなどとなると全く話が異なりますが、やはりそれだけで社会が「犯罪者」と言われることもありません。
戒であれ律であれ、その学処のすべてを常に護持しきることなど出来なかったとしても、それらが「重要なもの」・「護持すべきもの」として存在すること自体にも意味があり、それに対する理想と敬意とを持つことは、すこぶる必要なことであります。
そこで非常に問題となるのは、そもそも保つべき規定自体が存在していない場合や、あったかもしれないが知らないし守る気も無いなどといった場合。あるいは細かい点は守っていても、しかし重罪とされる条項を完全に破っており、やはり守る気もない場合などです。
『梵網経』においてもそう説かれているように、戒は受けただけで良いなどということは決して無く、十全とはいかなくともその学処を守り、戒を実現しよう努めなければ意味などありはしません。なんとなれば「戒律は仏教の命脈」というのが、(現代におけるおよそ全ての日本の僧職者を除く)世界の仏教者の共通理解であるためです。いや、その昔の日本でも、そのような認識は確かにあった。
厥佛法者齋戒爲命根。不可不識其命根焉。 《中略》
七佛通戒云諸悪莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教文。一代金言八教大抵只此一偈意也。何依佛法乍出家不從佛誡哉。
そもそも仏法とは斎戒〈戒律〉を命根〈命を存続するための源。ここでは仏教が仏教として存続する所以の意〉とする。(仏教者でありながら)その命根を知らないなど、あってはならない。《中略》
七仏通戒偈にて「諸々の悪を為すこと無く、諸々の善を行い、自らその意を清める。それが諸仏の教えである」と説かれる。仏陀一代のあらゆる説法、また今に伝わる八宗の綱要は、ただこの一偈に集約されているのだ。一体どうして仏法によって出家しておきながら、仏陀の誡めに従わないというのか。
栄西『出家大綱』序
ここで栄西は「佛法は齋戒を命根と爲す」と、「齋戒」が仏教の寿命を支えるものであると言っていますが、その本来は「斎戒」でなく「律」とするのが正しいものです。当時、律学をよくした人であった栄西とはいえ、戒と律とを混同しているのです。
対して、同じ鎌倉時代ながら、貞慶や栄西、そして明恵、叡尊らよりやや後の人で、しかし実に博覧にして仏教を深く理解していた無住道暁による、まこと優れた仏教説話集『沙石集』にては、(戒ではなく)律が仏教の興亡に関わるものであるとの正確な認識によって、同じく言及されています。
近代の學者、年に隨ひ偏執我相ふかくして、聖法の滅せむ事を思はざる哉。かなしむべしかなしむべし。夫戒律は釋子の威儀、毘尼は佛法の壽命也。正法を興隆する軌則、皆律藏の中より出でたり。諸宗の妙解の後、妙行を立つるには必ず律儀による。
近代の学僧らは、年を重ねるごとに偏執我相〈誤り偏った思想に固執すること〉を深くするようになり、聖法がまさに滅せんとしていることを考えもしない。嗚呼、かなしむべきことである、かなしむべきことである。
そもそも戒律は釈子〈仏弟子〉の威儀であり、毘尼〈vinaya・律〉は仏法の壽命である。正法を興隆する規則はすべて律蔵の中に示されている。諸宗それぞれに(仏陀の教えに対する)妙解〈宗祖の優れた解釈・思想〉があったとしても、妙行〈思想の実行〉を現実のものとするには必ず律儀〈律蔵の規定〉による。
無住道暁 『沙石集』巻第四
ところで、栄西の法孫でもあり、日本に曹洞宗を伝えてその祖となった道元は、持戒ということについて、以下の様な言葉を残しています。
亦云く、戒行持斎を守護すべければとて、強て宗として是を修行に立て、是によりて得道すべしと思ふも、亦これ非なり。只是れ衲僧の行履、仏子の家風なれば、随ひ行ふなり。是れを能事と云へばとて、必ずしも宗とする事なかれ。然あればとて破戒放逸なれと云には非ず。若亦かの如く執せば邪見なり、外道なり。只仏家の儀式、叢林の家風なれば、随順しゆくなり。是を宗とする事、宋土の寺院に寓せし時に、衆僧にも見へ来らず。実の得道のためには唯坐禅工夫、仏祖の相伝なり。是によりて一門の同学五眼房故葉上僧正の弟子が、唐土の禅院にて持斎をかたく守りて戒経を終日誦せしをば、教て捨てしめたりしなり。
懐奘問て云く、叢林学道の儀式は百丈の清規を守るべきか。然あれば、彼れはじめに受戒護戒を以て先とすと見へたり。亦今の伝来相承は根本戒をさづくとみへたり。当家の口訣、面授にも、西来相伝の戒を学人にさづく。是便ち今の菩薩戒なり。然あるに今の戒経に日夜に是を誦せよと云へり。何ぞ是を誦するを捨てしむるや。
師云く、しかなり。学人最とも百丈の規繩を守るべし。然あるに其の儀式は受戒護戒坐禅等なり。昼夜に戒経を誦し専ら戒を護持すと云は、古人の行履に随て祇管打坐すべきなり。坐禅の時何れの戒か持たざる、何れの功徳か来らざる。古人行じおける処の行履、皆深き心なり。私しの意楽を存ぜずして、衆に随ひ古人の行履に任せて行じゆくべきなり。
また(道元は)こうも言われた。
「戒行持斎を守らなければならないとし、強いて宗としてこれを修行の(核として)立て、これによって得道〈菩提を得ること〉できると思っていたとしてら、またこれは誤りである。ただ戒行持斎というのは仏教僧の行履〈起居動作〉の規定であり、また仏子としての家風であるから、従い行うものである。これを(仏教者として)能事〈なすべきこと〉であると言われているからといって、必ずしも宗としてはならない。かと言って、破戒し、放逸であれなどと言っているわけではもちろん無い。 もしそのような見解を抱いたとしたら、それは邪見であり、外道である。ただ(戒律とは)仏家の儀式であり、叢林の家風であるから、(当然のこととして)これに随い順ずるのである。戒行持斎を宗とする者など、宋の寺院で過ごしていた時も、衆僧の中にいはしなかった。実に得道するためには、ただ坐禅工夫すること、それが仏祖の相伝である。そのようなことから、一門の同学であった五眼房という故葉上僧正〈栄西〉の弟子が、唐土の禅院で持斎を固く守って『戒経』〈『梵網経』下巻〉を終日読誦していたのを、(それは誤っていると)教えて止めさせたのである」
と。そこで懐奘は、
「叢林学道の儀式は(百丈懐海の)『百丈清規』を守るべきでしょうか。だとしたならば、彼〈『百丈清規』〉には始めに受戒・護戒をもって第一とするとあります。また、今の伝来相承には根本戒を授けるともあります。当家〈曹洞宗〉の口訣・面授においても、天竺相伝の戒を学人〈修行者〉に授けています。それがすなわち今の菩薩戒でしょう。その上さらに、今の『戒経』にも「日夜にこれを読誦せよ」と説かれています。何故に、これを読誦することを止めさせたのでしょうか」
と問うた。すると師〈道元〉は、
「懐奘の言うとおりである。学人たる者は必ず『百丈の規繩』〈『百丈清規』〉を守らなければならない。そこで説かれる儀式は、受戒・護戒・坐禅等である。昼夜に『戒経』を読誦して専ら戒を護持すべきと説かれるのは、古人の行履に従って祇管打坐すべきであるとの意味である。たとえば、坐禅している時、いったいどの戒を破っているというのであろう、どのような功徳が得られないというのであろうか。古人が行じてきた所の行履であり、すべて深い考えあってのものである。私的な意楽〈思い・望み〉を交えること無く、衆〈僧伽〉に従って古人が行ってきた行履にまかせて修行していくべきである」
と答えられた。
懐奘編 『正法眼蔵随聞記』
まず、栄西や無住などと異なって道元はただ比叡山にて梵網戒を受けたのみで具足戒を受けておらず、したがって僧(比丘)ではなかったため、当然のことながら入宋した直後に天童山での入衆を拒まれていました。そこでしかし、道元は天童山の大衆と揉めに揉めて一悶着起こしており、これは外国僧だからという理由であったかどうか知れませんが、結果的に特別扱いを受けたようです。
道元は自分が僧(僧伽)の一員であると思っていたのでしょうけれども、その根拠としていたのは平安初期に最澄がなした菩薩戒を受けることのみで比丘となり得るという仏教として甚だしく非常識で非正当な理解に基づきます。最澄の死後、日本において国法としてはそれでも僧として認められるようになっていましたが、それは外国で認められる筈もないものでした。
栄西の弟子であり、道元の師であった明全は、道元とともに入宋していたのですが、日本の天台宗における戒律理解など支那(というより世界)で全く通用しないことを知っていました。そのため、明全は渡宋直前に東大寺戒壇院で具足戒を受けたとする戒牒(比丘としての公的証明書)を取得しています。当時、どうやら東大寺戒壇院は、宋に渡る留学僧のために戒牒を「販売する」という商売を行っていたようです。実際のところ、明全が本当に受戒したかどうかは不明であるものの、その戒牒の実物が現存しており重要文化財となっています。しかし、どうしてか道元はそうしていませんでした。
同じ比叡山出身でその師筋にあたる栄西とは異なり、道元は戒律についての知識が乏しく根本のところで誤っており、相当な思い違いをしています。そこで上掲の一節で言及される「戒行持斎」というのも、ただ梵網戒についてのみ云われたものです。たとえば『戒経』を読誦することと持戒とが絡めて語られ、また道元がそれを戒めているのは、律についてはまったく念頭におかれず、ただ『梵網経』の所説のみを前提としているからこそのことです。
また、『正法眼蔵随聞記』では更に「百丈の清規」、すなわち唐代の百丈懐海による『百丈清規』に言及されています。この清規というものについて、しばしば「戒律」と同一視する者がままありますが、これはいわば憲法や法律に対する地方条例のようなもので、禅宗やある一部の寺院における限定的なローカルルールに過ぎず、仏教としての普遍的規則ではありません。『百丈清規』はあくまで百丈が個人的に、律蔵の律儀やそれに基づく律宗の行儀と諸々の菩薩戒の学処を独自に斟酌し折衷したものであって、「禅宗の戒律」などと言い得るものではない。
そこで一般に、それが古いものであるならばなおさら、清規は律蔵の規定に則して定められたものが多いのですが、必然的にその根本となる律儀の何たるかを知らねば正しく理解できません。それはただ梵網戒など菩薩戒をのみ知るだけでは理解できるようなものではない。実際、それを今の禅の門徒はほとんど知っていませんが、その行儀の多くが律蔵の規定に基づき、また支那の律宗の風儀を受け継いたものであって、実は禅家独自のものではありません。
そこでしかし、「衲僧の行履」や「仏子の家風」であれ「清規」であれ、それを菩薩戒をのみ前提に謂うものとしていたならば、大きな誤解を生じます。ここで道元が言及している、栄西の弟子で五眼房という者が「唐土の禅院にて持斎をかたく守りて戒経を終日誦せしをば、教て捨てしめたりしなり」というのは、まず持戒ということについて梵網戒をのみ前提としており、また『梵網経』に「誦」と「持戒」とが並列的に説かれていることに基づいてのことでしょうが、それを実際に等価値のものと誤認していたことを示すものです。
では道元が持戒ということについて正しく認識していたのか。「昼夜に戒経を誦し専ら戒を護持すと云は、古人の行履に随て祇管打坐すべきなり」という言は、確かにそういうことも可なるものであるでしょう。しかし、ここで道元のいう「古人の行履」とは、あくまで『梵網経』と『百丈清規』に過ぎず、またそれを彼のいう意味での祇管打坐に直結させています。
道元は「古人行じおける処の行履、皆深き心なり。私しの意楽を存ぜずして、衆に随ひ古人の行履に任せて行じゆくべきなり」と言ってはいるものの、しかし先に触れたように、彼は律儀(具足戒)を自ら受けてもおらず、それで一悶着起こしていたことからすれば、まったく自己撞着した言となっています。すなわち、彼のいう「古人」も仏陀やその直弟子などでなく、あくまで道元が「私しの意楽を存」して認めたばかりの、幾世代か前の支那の禅僧にしか遡れないものであって甚だ怪しいものです。さらに謂うならば、後に道元が「仏祖正伝菩薩戒」などと称して後進に示した、三帰依と三聚浄戒と梵網の十重とを合した十六条戒なるもののは、結局「私しの意楽を存」したものに過ぎず、最澄の大乗戒に同じくなんらの正統な根拠なく主張されたものでした。
しかしながら、それを道元自身が実は伝えていないのは誠に皮肉な話でありますが、文字通りの意味としては、ここで道元が「古人行じおける処の行履、皆深き心なり。私しの意楽を存ぜずして、衆に随ひ古人の行履に任せて行じゆくべきなり」と述べていることは、まさに真であります。
古人の第一は釈迦牟尼に他なりません。その釈迦牟尼はどのように説かれていたのか。
汝等比丘。於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明貧人得宝。當知此則是汝大師。若我住世無異此也。
「比丘たちよ、私の滅後は波羅提木叉〈prātimokṣa. 戒本〉を尊重して珍敬せよ。それは暗闇の中で光明に出会うようなもの、貧しい人が宝を得るようなものである。まさにこのように知れ、これこそ汝等の大師であると。もし私が(入滅せず)命を留めたとしても、波羅提木叉に異なること(をさらに説くこと)はない」
鳩摩羅什訳 『佛垂般涅槃略説教誡経』(T12, p.1110c)
ここでいわれる波羅提木叉とは菩薩戒のそれでなく、あくまで律蔵に伝えられる諸々の学処ではあります。しかし、大乗教徒においてはここに菩薩戒のそれを含めてなんら差し障りなく、実際そのように理解されています。