『四十二章経』は、支那にて史上初めて漢訳されたと伝説される仏典です。後漢時代のいまだ仏教を知らなかった支那人に、「仏教とは何か」を端的に示したものとして古来、支那および日本にても特別視され、今に至るまで非常によく引用されてきたものです。
本経はその題目の通り、仏教の修行者とはいかなるものかや聖者の階梯、修道における心構えや要点、その世界観などを、四十二篇に渡って示したものです。より詳しくは後述しますが、これは元から『四十二章経』という経があって翻訳されたというのでなく、諸々の経典からその要を抜粋して略したもの、抄出本であったともされます。いわば仏教の概説書の漢訳です。
実際のところ、『四十二章経』は仏教の大枠を良くかいつまんで説き示しており、入門書・概説書として優れたものとなっています。その内容にはいわゆる大乗の教義・思想などほとんど見られません。ただし、最も古い漢訳仏典いわゆる古訳であることもあって、本経のみで十二分に仏教を理解できるとはとても言えません。そもそも数ある仏典の中に、ただ一書のみで仏教を理解し得る、それだけで事足るようなものは存在しません。
翻訳された当初の形態、その古形をよく留めたのが、唐の智昇により編纂された『開元釈教録』に基づき十一世紀の高麗において開版された、「高麗版大蔵経」(および十三世紀の「海印版大蔵経」)に収録されており、これを今一般に「高麗本」と云います。
しかしながら、『四十二章経』にはまた、唐代から宋代までに編集の手が加えられ、改変された異本が存在しています。経の頭と末に一般的な経典の形式に近い一節が足され、また内容としても大乗に基づく語句、一節があちこち加えられたものです。その改変された本がどのようなものかは、北宋の第三代、真宗皇帝(趙元侃)〈968-1022〉が註釈を加えた『註四十二章経』によって知られます。これを元とした『四十二章経』が、明代に開版された「明版大蔵経」(ここでは「明本」と仮称)に脩められています。
そしてさらにもう一本、『四十二章経』には異本が生じています。それが南宋における洞上〈曹洞宗〉の人、守遂が『仏説四十二章経註』として著したその底本となっているものです。これを今一般に「守遂本」と云い、現在の禅宗にでは『仏遺教経』および『潙山警策』に並んで「仏祖三経」の一つとして用いています。
なぜ禅宗で『四十二章経』を「仏祖三経」などと特別視するかと言えば、宋代の守遂がそれら三経の注釈書を残していることによるのでしょう。中で守遂は『四十二章経』をして仏陀最初の説法を記したものとし、『仏遺教経』を最後の説法としています。そのような説は守遂が初めて言い出したものではありません。それ以前、五代(南唐)時代の禅僧、静と筠なる二人が著したという『祖堂集』に、『四十二章経』をして仏陀最初の説法であるとされています。当時、『四十二章経』について、初めての漢訳経典というばかりでなく「仏陀最初の説法」なる理解、位置づけがなされていたようです。
なお、『潙山警策』は、唐代の禅僧、潙山霊祐により、仏教の肝心および修行の用心が簡便にまとめ記された書です。唐から宋代の頃に重視され用いられていたようです。そして『仏遺教経』は、隨唐から広く諸宗にて重要視され、よく読まれていた経です。『仏遺教経』については、その題目はもとよりその内容からも、これを最期の説法とするのは至極当然というべきことであるでしょう。しかし、『四十二章経』をもって「仏陀最初の説法」などと称するのは笑止千万、その内容を知ってそう言ったとしたならばなおさら噴飯ものの御冗談とすらいうべき説であります。
けれども、それら三つの仏典は、いつ・誰によってかは知られぬものの、禅門において「仏祖三経」と称されるようになり、今に至るまでその説が継承されています。
いずれにせよ、『四十二章経』には、後漢から南北朝時代に漢訳された古形を伝える「高麗本」と、十世紀頃に大きく改変された「明本」と「守遂本」があって、それぞれその内容をやや異にした三本の系統が今に伝わっています。現在、世に知られ、その解説本や訳本が出回っているのは、ほとんどすべて禅宗で用いられる「守遂本」に基づくものです。しかし、本稿では後代の 改竄がほとんど、あるいはそれほど加えられていないであろう「高麗本」を元としています。
先に『四十二章経』とは「仏教とは何か」を示したものであると述べましたが、実際その内容は、今の日本でも仏教について語られる時、必ず俎上に載せられるであろう話に満ちたものとなっています。それは、往古の支那において「漢訳経典の祖」とされ重視されてきた『四十二章経』が、今の日本人における仏教理解にすら影響を与えていることの証であるとも言えます。
一般に、仏教が支那に初めて伝来したのは永平十年〈67〉のことであるとされます。そして、その仏教伝来の話と『四十二章経』が漢訳されたという話は密接につながっており、『四十二章経』が漢訳されたことをもって支那に仏教が伝わった最初とされています。
「そんな歴史などややこしいことは知りたくない。知りたいのは『四十二章経』の内容だけである」という人もあるかも知れません。しかし、これは『四十二章経』をより理解するうえで踏まておくべき背景であり、またあくまで伝説としてではあるものの、常識の一つとして知っておくべき話でもあります。そこでここで、そのあたりのことに触れておきます。
梁代の僧祐〈445-518〉により著された、現在伝わるものとしては最古の経録『出三蔵記集』巻二には、『四十二章経』の翻訳について以下のように記されています。
四十二章經一卷舊録云孝明皇帝四十二章安法師所撰録闕此經右一部凡一卷。漢孝明帝夢見金人。詔遣 使者張騫羽林中郎將秦景到西域。始於月支國遇沙門竺摩騰。譯寫此經還洛陽。藏在蘭臺石室第十四間中。其經今傳於世
『四十二章経』一卷旧録には「孝明皇帝四十二章」という。道安法師の撰じた録〈『道安録』〉にはこの経を闕く。右一部凡そ一卷。漢〈後漢〉の孝明帝〈劉荘〉が夢に金人を見たことにより、詔して使者張騫と羽林中郎将〈近衛中将〉秦景を遣わして西域に至った。始め月支国〈中央アジアの古代国家〉にて沙門竺摩騰〈Kāśyapamātaṅga〉に遇い、この経を訳し記させて洛陽に還った。(それを)蔵して蘭台〈帝の書庫〉の石室第十四間の中に納めた。この経は今も世に伝えられている。
僧祐『出三蔵記集』巻二(T55, p.5c)
ここで僧祐は、今は散失して全く無いものの当時よく信頼されていたらしい道安による経録(『道安録』〈現存しない〉)に『四十二章経』が載せられていないことを指摘しつつ、旧録〈未詳〉には「孝明皇帝四十二章」という書名で記されていたとしています。なぜ『道安録』に記録されていないのかは、もたらされた後、直ちに蘭台に秘蔵されていたから、という理解であったのでしょう。
ところで、ここには『四十二章経』を支那に直接もたらした人として張騫の名を出しています。実はこれは史実として受け入れがたい伝承であるのですが、それは僧祐が同じく『出三蔵記集』巻六に収録している、作者未詳の序文にただ従って記したものであったようです。
四十二章經序第一 未詳作者昔漢孝明皇帝。夜夢見神人。身體有金色。項有日光。飛在殿前。意中欣然甚悦之。明日問群臣。此爲何神也。有通人傳毅曰。臣聞天竺有得道者。號曰佛。輕擧能飛。殆將其神也。於是上悟。即遣使者張騫羽林中郎將秦景博士弟子王遵等十二人。至大月支國寫取佛經。四十二章在十四石函中。登起立塔寺。於是道法流布。處處修立佛寺。遠人伏化願爲臣妾者不可稱數國内清寧。含識之類蒙恩受頼。于今不絶也
『四十二章経』序第一 作者は未詳昔、漢の孝明皇帝が、夜の夢に神人を見た。身体が金色に輝き、その項には後光がさしているのが飛んで殿前にあったのである。(皇帝の)心は欣然〈喜ぶ様子〉となって、甚だこれを嬉しく覚えた。翌日、(その夢について)群臣に問うた、「あれは何の神であったろうか」と。すると通人〈博識な人〉傅毅が、「臣は、天竺〈印度〉に道を得た者があって仏と称し、軽挙〈神通により身軽に浮遊すること〉にして飛ぶことが出来ると聞いております。まず間違いなくその神でありましょう」と言った。そこで帝はこれを知ると、ただちに使者張騫〈前漢の人であり誤伝。異説では蔡愔〉、羽林中郎将〈近衛中将〉秦景、博士弟子王遵等の十二人を遣わして大月支国〈中央アジアの古代国家〉に至り、仏経を写し取らせた。(そこで)『四十二章』は、(帝の書庫である蘭台の)第十四石函中に納められた。そしてさらに塔寺〈鴻臚寺(白馬寺)〉を起立〈建立〉して、ここ〈後漢〉に道法〈仏教〉を流布させ、処処に修めて仏寺を立てた。すると地方の人々も、仏の教えに教化され、自ら願ってその臣妾〈追従者〉となる者は数知れないほどとなった。国内は清寧となり、含識〈生物〉の類で、その恩を蒙って頼を受けるものは今も絶えない。
僧祐『出三蔵記集』巻六(T55, p.42c)
先に示した『出三蔵記集』巻二には、「於月支國遇沙門竺摩騰。譯寫此經還洛陽(月支国に於いて沙門竺摩騰に遇い、此の経を訳写して洛陽に還った)」とありますが、この巻六に採録された『四十二章経』序では、ただ「至大月支國寫取佛經(大月支国に至って仏経を写取す)」とあって、竺摩騰の名が挙げられていません。この序文を文字通り理解したならば、中央アジアの大月氏国に派遣された張騫により(梵本が)書写され、支那に持ち帰られたものということになります。
しかし、後漢の孝明帝の時に張騫の名が出されていることは、これが杜撰な伝承であることを示すものです。というのも、彼は孝明帝より二世紀程も先の前漢の武帝に仕えた武人であって、ここに名が挙げられる筈も無い人であるためです。
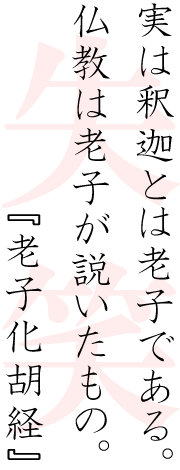
なぜ、ここに張騫の名が出されたのか。それは西晋〈265-316〉の道士王浮により、老子が釈尊より優れていることを言わんとして偽作された、道教の『老子化胡経』にそう書かれていたのが世間で流布していたのを、むしろ仏教側が無批判に踏襲したことによるものと考えられます。『老子化胡経』とは、仏教とは実は老子が胡人〈支那からみて北あるいは西にある夷狄〉を教化するため創始したのものである、と主張したいわゆる「トンデモ本」です。
もっとも、この説は王浮が初めて思いついて主張したのでなく、それ以前から支那で老子を奉じる人々の間でまことしやかに云われていたものでした。いわば支那における土着信仰である神仙思想と『老子』や『荘子』とが習合していたもの(いわゆる道教の源)を奉じた人々により、外来思想ながら次第に世に受け入れていった仏教に対抗し、むしろ取り込んでしまおうとでっち上げた話であったのです。しかし、その影響は仏教側にも小さくなく、実際に仏教伝来の話にまさにそれが現れています。
(『老子化胡経』が記す仏教の支那伝来説に関する一部は、一応その淵源・根拠となるものはあり、そのすべてがでたらめというわけでもありません。)
もっとも、それが歴史的にありえないことがそれほど時を経ぬ後に気づかれ、同じ梁代の慧皎により著された『高僧伝』(以下、『梁高僧伝』)や北斉の魏収が撰じた『魏書』では、張騫でなく祭愔であったとし、その派遣先も大月氏でなく天竺であった修正(?)が加えられています。
いずれにせよ、支那への仏教初伝の伝承は、仏教と道教との鍔迫り合いの中で形成された話であったということが出来ます。史実としては、永平十年よりも半世紀以上早く、ちょうど紀元前後頃の前漢には仏教が何らかの形で伝わっていたと考えられています〈『三国志』巻三十「魏志」の記事に基づく〉。そしてまた、後漢では伝説の通り後漢の孝明帝ではないものの、その異母弟であった楚王英が仏教を奉じた人であったことが史実として考えてよいとされます〈『後漢書』巻七十二「列伝」第三十二「楚王英伝」の記事〉。
少なくとも現存する最古の経録において、『四十二章経』の訳者が誰であったかは必ずしも確定的に述べられておらず、僧祐はおそらく当時伝えられていた話をとりあえず記したに過ぎなかったようです。
その後、『出三蔵記集』が編纂されてからしばらく時を経た隋代は開皇十七年〈597〉、翻経学士〈訳経に専従する役人・学者〉であった費長房により、支那に仏教が伝わってからの由来やそれまでの経録、そして訳経者の伝記などを総じて編じた『歴代三宝紀』十五巻が著されています。そこにやはり、漢土における経の初めとして『四十二章経』に関する記載が所々になされています。
後漢四十二章經一卷
右一經一卷。明帝世中天竺國婆羅門沙門迦葉摩騰譯。或云竺攝摩騰。或直云攝摩騰。《中略》
永平年隨逐蔡愔至自洛邑。於白馬寺翻出此經。依録而編。即是漢地經之祖也。舊録云。本是外國經抄。元出大部。撮要引俗似此孝經一十八章。道安録無出。舊録及朱士行漢録僧祐出三藏集記。又載但大法初傳人未歸信致使摩騰蘊其深解不復多翻。後卒雒陽。載其委曲備朱士行漢録及高僧名僧等傳諸雜記録。寶唱又云。是竺法蘭譯。此或據其與攝摩騰同時來耳
《中略》
明帝世翻初共騰出四十二章。騰卒。蘭自譯。
後漢四十二章経一巻
右一経一卷。明帝の世、中天竺国の婆羅門沙門迦葉摩騰〈Kāśyapamātaṅga〉の訳。あるいは竺摂摩騰と云い、あるいは直に摂摩騰とも云う。《中略》
永平年間、蔡愔に隨逐して洛陽に至り、白馬寺に於いてこの経を訳出した。(諸々の)経録にって言えば、これこそ漢地における経の祖である。『旧録』に、「これは外国における経抄であって、その元は大部(の諸経に)基づくもの」とある。その要を撮り俗を引いた内容は、『孝経』十八章に似ている。『道安録』〈道安『綜理衆経目録』.現存せず〉にはその記録が無い。『旧録』及び『朱士行漢録』、僧祐『出三蔵集記』〈『出三蔵記集』〉には、またただ大法〈仏教〉の初伝を記載するのみである。人は未だ(仏教に)帰信するに至らず、摩騰をしてその深い理解を積ませたけれども(『四十二章経』以外に)また多くを翻訳することなく、後に洛陽にて卒した。その(生涯の)詳しくは『朱士行漢録』〈現存せず〉にあり、及び高僧・名僧等の伝記〈慧皎『高僧伝』・宝唱『名僧伝』(現存せず)〉や諸々の雑記録に記載がある。宝唱〈『名僧伝』?〉はまた云う、「これは竺法蘭の訳である」と。それはあるいは、(竺法蘭が)摂摩騰と時を同じくして来たというだけのことであろう。
《中略》
明帝の世、翻じて初めて迦葉摩騰と共に『四十二章』を出す。迦葉摩騰が卒した後は、竺法蘭が訳した。
費長房『歴代三宝紀』巻四(T49, pp.49d-50a)
費長房は、『四十二章経』は迦葉摩騰により訳出されたものであるとしつつ、竺法蘭との共訳であるとする説も一応紹介しています。実際、梁代の慧皎により著された『高僧伝(梁高僧伝)』には、竺法蘭を本経の訳者の一人としています。すなわち、同じ梁代であっても、僧祐は迦葉摩騰のみが訳したと伝え、慧皎は竺法蘭との共訳であったとする伝承を遺していました。そこで費長房は、竺法蘭もその訳に関わっていたとする説も、若干の迷いを持ちながら併せて紹介したようです。
もっとも、『四十二章経』が迦葉摩騰と竺法蘭との共訳であるとの認識は、『歴代三宝記』より半世紀近く早く、北斉〈554〉において成立していた正史『魏書』の「釈老志」にすでに記されていました。
後孝明帝夜夢金人項有日光飛行殿庭乃訪群臣傅毅始以佛對帝遣郎中祭愔博士弟子秦景等使於天竺寫浮屠遺範愔仍與沙門攝摩騰竺法蘭東還洛陽中國有沙門及跪拜之法自此始也愔又得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工圖佛像置清涼臺及顯節陵上經緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛城雍關西摩騰法蘭咸卒於此寺
後、孝明帝が、夜に金人で項に日光を有し、(虚空を)飛行して宮殿の庭にあるのを夢見た。そこで(翌日、)群臣にこれを尋ねた。すると傅毅が始めて「それは仏です」と答えた。帝は郎中〈宮中の警護長官〉祭愔と博士弟子秦景等を天竺に遣わし、浮屠〈Buddha〉の遺範〈Buddha〉を写させた。祭愔はそこで沙門摂摩騰と竺法蘭と共に東の洛陽に帰還した。中国に沙門と跪拝〈ひざまずいてする礼拝.五体投地〉の法が有るのは、この時から始まる。祭愔はまた仏経『四十二章』と釈迦の立像を得ていた。明帝は画工に仏像を描かせ、清涼台〈訳経場〉と顕節陵〈明帝が生前に築いた自身の陵墓〉の上に置かせて、経は蘭台〈帝の書庫〉の石室に緘蔵〈封印しての保管〉した。祭愔が還った時、白馬に経を背負わせ漢土に至ったため、それに因んで白馬寺を洛陽城の雍關〈洛陽西側の南から第二の城門〉の西に立てた。摩騰と法蘭は皆この寺にて卒している。
『魏書』志第廿 釈老十(『魏書釈老志』)
このように、それまでの伝承がまとめられ正史に記載されたことは決定的で、以降の支那ではほぼこの通りに認識されていくようになっています。
ところで、費長房は、『四十二章経』には三国時代に呉の 支謙によって再訳されたものがあるとしています。しかし、それは早い時期に散逸したようで、そもそもそれが事実であったことの確認を取ることが出来ません。
なお、『歴代三宝紀』には訳者以外に注目すべきことが記されています。それは、『四十二章経』は「外國經抄」すなわち外国にて編纂されていた諸経の抄出本であるという説と、またその体裁として儒教の『孝経』に似たものであることの指摘です。
実際、ここに「撮要引俗」とされているように、『四十二章経』は、諸々の経典からの抜粋あるいはその内容の抄出を短く四十二章立てにしたもので、特に儒教の「孝」を、そしてまた道教における「道」の概念をその説に一部紛らせたものとなっています。『四十二章経』は、支那における儒教的価値観と対決した内容を持つものでありますが、そこでその融和も図られたものでありました。
現代、『四十二章経』は支那において編纂された偽経であると主張する学者があります。しかし、そもそもが「経抄」であったならば、いわゆる偽経などと云うに及ぶものではありません。また本経の訳出、あるいは編纂が後漢ではなく三国時代頃と断定する学者等の意見も、必ずしも全く首肯し得たものでもありません。
しかし、これ以上、『四十二章経』の訳者や伝承について踏み込むことは、本稿を示す目的から外れるため控えます。実際のところ、訳出がいつであるとか、誰に拠るとかいうことはもはや大した問題でなく、重要な事実はそれが支那にて「漢訳仏典の最初」とされ、故に重要視されて広くそして長く読み継がれてきたことです。
最後に一点、支那における初めての仏教経典とされる『四十二章経』にまつわる面白い(?)話を紹介しておきます。
先に仏教の伝来にともない、支那の道教との衝突があって、道教こそ仏教の根源でありより優れたものであることを言う者らがあったことに触れましたが、まさに『四十二章経』もそれに利用されています。巷で初の仏教経典とされ奉じられていた『四十二章経』は、その半分ほどが道教的改変を加えられて『真誥』に編入されています。
『真誥』とは、梁の道士、陶弘景によって編纂された書です。書名の『真誥』の真とは道を体得した人(真人)、誥とはお告げのことであって、「真人のお告げ集」を意味します。支那における雑多な土着信仰である神仙思想と老荘思想が習合したのを、いわゆる道教として体系化したもので、上清派の根本聖典とされます。しかしそこに、『四十二章経』にある諸々の仏説の抄出が道教の経典である、として語句を都合よくあちこち道教のものであるかのように改竄し利用したのでした。
仏教が支那に伝わると、儒教そして道教とのせめぎあいはその直後から生じていますが、それをよく伝えているのが後漢に著されたとされる牟融『理惑論』(『牟子理惑論』)です。『理惑論』には、まさに『四十二章経』およびその仏教伝来説が引かれていますが、そこには当時、支那人達がどのように仏教を理解し、また批判していたかがよく伝えられています。
『理惑論』は現代の我々が読んでも、それがまず漢文であり、さらに儒教や老荘の典籍を縦横に駆使したものであることによって敷居が高く感じられるものではあるでしょうが、その内容としては非常に優れたものです。この書に触れたならば、今の日本人が漠然と「仏教とはこういうものだ」と思っている見方が、実は仏教を儒教や老荘思想から眺めた往古の支那人らのそれに非常に似たものであること、いや、場合によってはそのままですらあることを知るでしょう。そしてそのような見方への牟子の反駁が、実に舌鋒鋭く理路整然としたものであることの愉快さを、また感じることも出来るに違いありません。
仏教・儒教・道教との衝突や融和は唐代・宋代にまで続き、展開していますが、それによって支那仏教には儒教や道教の思想が多く流れ込み、またその逆も然りで、道教や儒教にも仏教の影響が顕著に入り込んでいます。道教における一例は前述の通りですが、儒教においてはより後代、宋代に出たいわゆる宋学(新儒教)、朱子学は仏教の多大な影響によって形成され成立したものです。
したがって、支那仏教を理解しようとした時、またその影響をこそ受けた日本仏教を理解する時、さらには朱子学とは何かを見る時、この辺りを知るのと知らぬとでは、その深浅に大きな差が出ることとなるでしょう。特に『四十二章経』および『理惑論』を確実に読み知っておくことは、今の(仏教徒に限らない)日本人における仏教理解の源、その宗教観の淵源を知るに必須のものであるとすら言えます。
支那における仏教と道教との関係は日本における仏教と神道との関係に非常によく似たものですが、それを理解するにも有益であること間違いありません。
ただ仏教を知る、学ぶというのでなく、我々日本人一般の精神はどこから来たのか、我々日本人が諸々の事物について自然と「そういうものだ」と考えるその由来は何か、その答えの一つとなるものとして、また日本人としての知の源流を示すものの一端として、支那における最初の漢訳仏典とされる本経に誰でも触れ得ることを期し、ここに拙訳を付して紹介するものであります。
何より、『四十二章経』の古形に触れることにより、仏教をはじめて知り、あるいはより仏教を深く理解し、自らが日々を生きる糧、その指針とし得る人が現れれば欣幸の極み。
愚衲覺應 識
一.本稿にて紹介する『四十二章経』は、唐代までに大きな編集・改変の手が加えられ禅宗で用いられてきたいわゆる「守遂本」でなく、「高麗本」の系統に属する「宮内庁宋版」を底本としている。
一.底本ではいわゆる章立てが為されておらず、その区切りも明瞭でないが、本稿では経題に従って仮に四十二章に区切って示した。そこで各章の最初に《第〇〇章》として示したが、これは底本に無いもので、本稿筆者による付加である。
一.原文および訓読にては、底本にある漢字は現代通用する常用漢字に改めず、可能な限りそのまま写し用いている。これにはWindowsでは表記されてもMacでは表記されないものがある(表記できない文字は□と表示される)。Macにて表記されない漢字を表示させるには、別途「PMingLiU-ExtB(新細明體-ExtB)」をシステムフォントとしてインストールすることを要す。ただし、Unicode(UTF-8)に採用されておらず、したがってWindowsでもWebブラウザ上で表記出来ないものについては代替の常用漢字などを用いている。
一.難読あるいは特殊な読みを要する漢字や単語など、今の世人が読み難いであろうものには編者の判断で適宜ルビを設けた。特殊な読みを要する字に付したルビは、『類聚名義抄』および『字鏡集』の例から適宜選び付したものである。ただし、ルビについては旧仮名遣いを用いず、現代通用する仮名遣いを用いた。
一.漢字の読みについて固有名詞、特に僧名は全て呉音で訓じている。その他の人名は支那人は漢音にて訓じている。仏教用語は一部の慣用音を除き、全て呉音で訓じた。
一.現代語訳においては読解に資するよう、適宜に常用漢字に改めた。また、読解を容易にするために段落を設け、さらに原文に無い語句を挿入した場合がある。この場合、それら語句は括弧()に閉じてそれが挿入語句であることを示している。しかし、挿入した語句に訳者個人の意図が過剰に働き、読者が原意を外れて読む可能性がある。そもそも現代語訳は訳者の理解が十分でなく、あるいは無知・愚かな誤解に由って本来の意から全く外れたものとなっている可能性があるため、注意されたい。
一.現代語訳はなるべく逐語訳し、極力元の言葉をそのまま用いる方針としたが、その中には一見してその意を理解し得ないものがあるため、その場合にはその直後にその簡単な語の説明を下付き赤色の括弧内に付している(例:〈〇〇〇〉)。
一.補注は、特に説明が必要であると考えられる語に適宜付し、脚注に列記した。
一.本論に引用される経論は判明する限り、すべて脚注に『大正新脩大蔵経』に基づいて記している。その際、例えば出典が『大正新脩大蔵経』第一巻一項上段であった場合、(T1, p.1a)と記している。
懸命なる諸兄姉にあっては、本稿筆者の愚かな誤解や無知による錯誤、あるいは誤字・脱字など些細な謬りに気づかれた際には下記宛に一報下さり、ご指摘いただければ幸甚至極。
非人沙門覺應
info@viveka.site