「仏教はこの世を否定的に見ている」などという話をしますと、大抵の場合、たちまち感情的反論の言葉が帰ってきます。そしてそのような仏教の世界観・人生観をして厭世的である、ペシミズム〈pessimism〉である、という人もあります。実際、この世を無条件に肯定的に仏教が見ることは決してないので、厳密に言えば西洋のペシミズムとは異なりますが、厭世的というなら確かにその通りです。
なお、しばしばその違いを理解できず混同して捉える者があるので念のため確認しておきますが、この世を否定することと否定的に見ることは異なります。否定しても仕方ありません、現前としてあるのですから。そして仮に否定したとして、身近な物事を少しばかり壊すことは出来たとしても、世界を滅ぼすことなど誰も出来はしません。
さて、その程度と方向性は多様でありますが、現代においてなお仏教に信を置く人はそれなりに多くあります。しかし、仏教を信じると言いながら、仏教が世界を否定的に見ていること自体を否定し、「そうではない、実は仏教は世界を肯定し、生を肯定し、人を肯定した教えである」と喧伝する輩があります。また、そのような輩の説に同調し、さらに敷衍して様々に言おうとする者もあります。
そこで、そのような彼らがよく引き合いに出す経の一節があります。釈尊がその死の三ヶ月前、その生涯においてよく遊行され滞在されていた土地の一つ、Vesālī〈[S]Vaiśālī. 毘舎離。現在のビハール州パトナー北方に位置した都市〉(以下、ヴェーサーリー)においてしばらく過ごされていた際の一節です。
atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya vesāliṃ piṇḍāya pāvisi. vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi — “gaṇhāhi, ānanda, nisīdanaṃ, yena cāpālaṃ cetiyaṃ tenupasaṅkamissāma divā vihārāyā”ti. “evaṃ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā nisīdanaṃ ādāya bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi. atha kho bhagavā yena cāpālaṃ cetiyaṃ tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. āyasmāpi kho ānando bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ ānandaṃ bhagavā etadavoca — “ramaṇīyā, ānanda, vesālī, ramaṇīyaṃ udenaṃ cetiyaṃ, ramaṇīyaṃ gotamakaṃ cetiyaṃ, ramaṇīyaṃ sattambaṃ cetiyaṃ, ramaṇīyaṃ bahuputtaṃ cetiyaṃ, ramaṇīyaṃ sārandadaṃ cetiyaṃ, ramaṇīyaṃ cāpālaṃ cetiyaṃ.
そこで世尊〈bhagavant〉は、朝早くに(下〈下衣。腰巻き〉と上〈上衣。上半身から膝下までを覆う衣〉の)衣を着け、鉢と衣〈大衣。外出時に着用あるいは携帯すべき衣〉を携えて、ヴェーサーリー〈vesālī〉に托鉢のために入って行かれた。ヴェーサーリーを托鉢のために歩まれ、托鉢から戻られ食を終えられると、尊者〈āyasmant. 原意は「長寿ある」で具寿と漢訳される。一般に尊者の意〉アーナンダに告げられた。
「アーナンダよ、坐具を持っていけ。私はチャーパーラ〈Cāpāla. ある夜叉(yakkha)の名〉の祠〈Cetiya. 神霊を祀る処。塚や祠、あるいは大樹。ここでは夜叉の住まいとされた大樹。チャーパーラの樹の所在地を仏陀は精舎としていた〉に向かおう。食後の休憩〈divā vihāra. 昼間の休息〉のために」
「そのとおりに、世尊」
と、尊者アーナンダは世尊に応じ、坐具〈nisīdana. 尼師檀〉を持って世尊のすぐ後に付き従った。そこで世尊は、チャーパーラの祠に近づいて行かれた。そうして近づかれると、設けの坐処に座られた。尊者アーナンダは世尊を礼拝し、その一方に座った。そして、一方に座った尊者アーナンダに、世尊はこのように言われた、
「アーナンダよ、ヴェーサーリーは楽しい〈ramaṇīya. 楽しい・喜ばしいの意。漢訳では楽〉。ウデーナ〈Udena. 夜叉の名〉の祠は楽しい。ゴータマカ〈Gotamaka. 夜叉の名〉の祠は楽しい。サッタンバ〈Sattamba. 七人の王女に因む夜叉の名〉の祠は楽しい。バフプッタ〈Bahuputta. Nigrodha樹(Banyan)に住まう夜叉の名。Nigrodha樹が枝から幾本もの気根を生やしつつ巨木になることにあやかって子授けを祈願したことからbahuputtaすなわち多子と称されるようになったとされる〉の祠は楽しい、サーランダダ〈Sārandada. 夜叉の名〉の祠は楽しい。チャーパーラの祠は楽しい」
《以下、高位の修行者ならば死期をより遅める選択肢があり、仏陀もそれが可能であることを暗示されるが、アーナンダはそれに気づかず無視する。》
Mahāparinibbānasutta, Nimittobhāsakathā (DN 16.14)

これは釈尊がヴェーサーリー近郊のチャーパーラと称されていた大樹のもとで食後の休憩をされている時、それはどうやらその樹のある場所を精舎とされていたからのことであったようですが、永くその随行を勤めてきたアーナンダ尊者に向かって語られた言葉です。
三十有五歳で出家されてから八十歳に至るまで一処に永く留まることなく、長い長い遊行の旅を続けられてきた釈尊が、それでも多くの時間を過ごされたヴェーサーリという地にあって、その縁の場所のいくつかを挙げて「楽しい」という率直な感慨を述べられていたことは、しかもその時はご自身の死がすぐ迫っていることを知られていたとされることから、なおさら何か人に強い印象を与えるものです。このような一節に現代の人が注目するのも宜なること。それは人の文学的琴線に触れるものであるでしょう。そしてこの一節だけ見れば、仏教をして厭世的だなどとする主張は一面的で誤っているのでないか、と思われるに違いない。
まず、ここで理解しておくべき重要なことは、このように釈尊がアーナンダに向かって言われたのが、自身の死を三ヶ月後とすべきかどうかを決意するための文脈においてのことです。
釈尊は、すでに死の病の足音が近づく時に、そのような「楽しい地」ある世に今しばらく生き続けていくことも可能であったものの、それを自ら望まれてはいませんでした。しかしもし、長年随行してきたアーナンダからの懇請があったならば、その死をより後に引き延ばすことが出来るとされ、それをそれとなくアーナンダに三度に渡って尋ねられています。しかし結局、三度まで繰り返し仏陀に問われたにも関わらず、アーナンダはその真意をわからず聞きすごし、ついに仏陀は三ヶ月後に死を迎えることを決意された、と伝えられています。
(アーナンダ尊者はここで迂闊にもそれを聞き過ごして釈尊に死の決断をさせただけでなく、その他多くの過失があったとして、釈尊の滅後三ヶ月に行われた第一結集が開かれる直前に厳しく批判されています。アーナンダは長年釈尊の随行をしていたにも関わらず、第一結集の行われる早朝まで阿羅漢になれていませんでした。アーナンダは非常に優しい性であったようですが、阿羅漢となるまではどこか抜けた、少しボヤッとしたところのある人であったようです。)
さて、この「パーリ三蔵」所伝のMahāparinibbānasutta(以下、『マハーパリニッバーナ・スッタ』)は支那に伝わっておらず、故に漢訳されたことはありません。しかし異系統ながらおおよそ同内容の経典のいくつかが伝わり翻訳されています。その中でも法顕によって訳された『大般涅槃経』の一節は、上掲の一節とほとんど一致したものとなっています。
爾時世尊。而與阿難。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。還歸所止。食竟洗漱。收攝衣鉢。告阿難言。汝可取我尼師壇來。吾今當往遮波羅支提。入定思惟。作此言已。即與阿難。倶往彼處。既至彼處。阿難即便敷尼師壇。於是世尊結跏趺坐。寂然思惟。阿難爾時去佛不遠。亦於別處。端坐入定。世尊須臾。從定而覺。告阿難言。此毘耶離。優陀延支提。瞿曇支提。菴羅支提。多子支提。娑羅支提。遮波羅支提。此等支提。甚可愛樂。
その時、世尊は、アーナンダと晨朝〈早朝〉、衣を著け鉢を持ち、城〈ヴェーサーリの街〉に入って乞食された。(托鉢から)帰られ、食を終えて(手と口と鉢を)洗って漱ぎ、衣と鉢とを収められると、アーナンダに言われた、
「アーナンダよ、私の坐具を持ってきなさい。私は今これからチャーパーラの祠〈遮波羅支提〉に行って、入定思惟〈修禅。いわゆる瞑想〉しようと思う」
と。(世尊が)そのように言われると、アーナンダと共にその処に行かれた。その処に至られると、アーナンダは(世尊の為に)坐具を敷き、そこに世尊は結跏趺坐され、寂然として思惟された。アーナンダはそこで仏陀からそれほど離れていないまた別の処において端坐し入定した。(しばらくすると)世尊はたちまち定より覚め、アーナンダに言われた。
「このヴェーサーリー、ウデーナの祠〈優陀延支提〉、ゴータマの祠〈瞿曇支提〉、サッタンバの祠〈菴羅支提〉、バフプッタの祠〈多子支提〉、サーラの祠〈娑羅支提〉、チャーパーラの祠など、これらの祠はとても楽しい〈愛楽〉ものだ」
法顕訳『大般涅槃経』巻上(T1, p.191b)
『大般涅槃経』もまったく同様に、釈尊がヴェーサーリーを始め、チャーパーラなど諸々の大樹のある地を楽しいもの、喜ばしいものといわれたと伝えています。法顕の訳した梵本でもその語は同じくramaṇīyaであったと考えて間違いなく、その原意は「楽しむべき」・「楽しい」ですが、これを法顕は「甚可愛楽」と訳しています。愛楽とは「願い求めること」・「楽しむこと」、あるいは「執着すること」などの訳で用いられる語です。
なお、ここでは全くの余談となりますが、この『大般涅槃経』の記述からすると、チャーパーラと言われた夜叉の棲まう大樹は、精舎の境内(区域内)など側近くにあったのでしょう。もし精舎の外にあったならば、釈尊たちはまた大衣など着けなければならないのに、そうはされていないためです。境内の中であれば三衣のすべてを身につけ、あるいは携える必要はありせん。そしてそれは「パーリ三蔵」の注釈書の所伝とも一致したものであり、また後述するサンスクリット本での記述とも一致します。
釈尊が涅槃する頃には、もうすでに樹下坐臥などといった比丘の基本生活指針、いわゆる四依法はいわば空文化して理念となっており、所々に坊舎を有する精舎が形成されていたため、チャーパーラという樹の祠周辺には何らかの建築物があったように思われます。
釈尊はご自身がそれまでいくらかでも過ごし、目にされてきた、神霊の棲み家とされていたあちこち大きな樹のある地の情景について「楽しい」と述懐されていたと、諸々の経典にて等しく伝えられています。それは現存する種々の「涅槃経」の類本で最も古く漢訳されたものの一つである、失訳〈訳者および翻訳年が不明であること〉の『般泥洹経』においても同様です。
しかしながら、これには『マハーパリニッバーナ・スッタ』や『大般涅槃経』には無い一句が、その一節の後にあります。
佛請賢者阿難。倶至維耶離。受教即行。既到止猨猴館。行乞食畢。滌鉢澡洗。又與阿難倶。到急疾神地。佛言。阿難。維耶離樂。越施亦樂。今此天下。十六大國。其諸郡邑皆樂。熙連然河。多出黄金。閻浮提地。五色畫。人生於世。以壽爲樂。
仏陀は賢者アーナンダに、共にヴェーサーリー〈維耶離〉に行くことを求められた。(アーナンダは)それに応じて(共に)行った。そして猿猴館〈未詳〉に至って留まった。托鉢して食を終え、鉢を洗い(口を)漱がれた。そして、またアーナンダと共に急疾神地〈未詳.急疾は[S/P]Cāpālaあるいは[P]Sārandadaか?神地は[S]Caitya, [P]Cetiyaであろう〉に至られた。そこで仏陀は、
「アーナンダよ、ヴェーサーリーは楽しい、ヴァッジ〈越施・越祇。[S]Vṛji, [P]Vajji. ヴェーサーリ周辺を治めていた部族〉(の土地)もまた楽しい。今、この天下に十六大国あるけれども、その諸々の町や村〈郡邑〉はみな楽しい。ネーランジャナラー〈熙連然河.[S]Nairañjanā, [P]Nerañjarā. 尼連禅河〉は多く黄金を算出し、閻浮提〈[S]Jambudvīpa, [P]Jambudīpa〉の地は五色の絵〈五色画〉のようであり、人はこの世に生まれ、生きること〈壽〉をもって楽しみとしている」
失訳『般泥洹経』巻上(T1, p.180b)
この『般泥洹経』の一節は、『マハーパリニッバーナ・スッタ』などと比較すると、大幅に略されているような点や全く一致しない点などいくつかあるものの、その概要は同じです。ここでもやはり、釈尊はいくつかの地について「楽しい」と言われていたと伝えていますが、その後さらに「閻浮提地。五色畫。人生於世。以壽爲樂(閻浮提の地、五色の画の如し。人、世に生じて寿を以て楽と為す)」とも述べられていたとしている点、大いに毛色が異なっています。
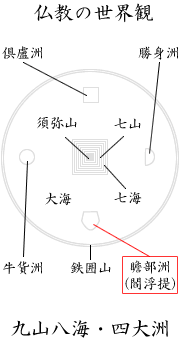
閻浮提とは、サンスクリットJambudvīpaの音写で、 仏教古来の世界観において須弥山の南方の海に浮かぶ大陸の称です。Jambu という下膨れの果物の上下をひっくり返したような形であることからこの名があります。須弥山をヒマラヤであるとすると、まさにインド亜大陸に該当する土地の名です。 瞻部洲だとか閻浮利とも言われます。
また『般泥洹経』に同じく最初期に漢訳された「涅槃経」の類本に、 白法祖の訳とされる『仏般泥洹経』があります。失訳『般泥洹経』と白法祖訳『仏般泥洹経』のどちらが早く漢訳されたものかは不明ですが、いずれも最初期の漢訳経典であるだけに後代のものと比べるとその訳文はまるで熟 れておらず、全く意味も不明で見当もつかないような語があるなど極めて読み難いものです。
しかし、その『仏般泥洹経』にもまた、『般泥洹経』にあるのと同様の一句を伝えています。
佛從竹芳聚。呼阿難。且復還至維耶梨國。阿難言受教。佛還維耶梨國。入城持鉢行分衞。還止急疾神樹下露坐。思惟生死之事。阿難遠在一樹下。思惟陰房之事。起至佛所。爲佛作禮已。住白佛言。何以不般泥洹。佛告阿難。維耶梨國大樂。越耶國大樂。急疾神地大樂。沙達諍城門大樂。城中街曲大樂。社名浮沸大樂。閻浮利天下大樂。越祇大樂。遮波國大樂。薩城門大樂。摩竭國大樂。滿沸大樂。鬱提大樂。醯連溪出金山大樂。閻浮利内地。所生五色如畫。人存其中生者大樂
仏陀は竹の生えた村〈竹芳聚.[S]Veṇugrāmaka. パーリ仏典では[P]Veḷuvagāmaka(Beḷuvagāmaka)〉からアーナンダを呼ばれ、
「またヴェーサーリー〈維耶梨國〉に戻ろう」
と言われた。そこでアーナンダは、
「そのとおりに」
と応じた。仏陀はヴェーサーリーに戻ると、鉢を携えて城〈ヴェーサーリの街〉に入り托鉢〈分衛〉した。(托鉢を終えて精舎に(?))戻られると、急疾神樹〈未詳.[S/P]Cāpālaあるいは[P]Sārandadaか?〉の下に留まって露坐され、「生死の事」を思惟された。アーナンダは遠くの一本の樹の下にあって「陰房の事〈未詳〉」を思惟していた。そこで(座から)起って仏陀のところに近づいた。そして仏陀に礼拝をなしおわると、(その側に)坐して仏陀に申し上げた。
「どうすれば(仏陀は)般涅槃されないでしょうか?」
そこで仏陀はアーナンダにこう告げられた。
「ヴェーサーリー〈維耶梨国〉は大いに楽しい。越耶国〈未詳〉は大いに楽しい。急疾神地〈急疾神樹に同じ〉は大いに楽しい。沙達諍城門〈未詳〉は大いに楽しい。街中の雑踏〈城中街曲〉は大いに楽しい。社名浮沸〈未詳〉は大いに楽しい。閻浮利〈閻浮提に同じ〉の天下は大いに楽しい。ヴァッジ〈越祇〉(の土地)は大いに楽しい。チャンパー〈遮波国.[S/P]Campā〉は大いに楽しい。薩城門〈未詳〉は大いに楽しい。マガダ〈摩竭國国.[S/P]Magadha〉は大いに楽しい。マッチャ〈滿沸.[S]Matsya, [P]Maccha〉は大いに楽しい。鬱提〈未詳.[P]Udena?〉は大いに楽しい。ネーランジャラー河〈醯連溪.尼連禅河〉は金を多く出して大いに楽しい。閻浮利の地にあるものは五色の絵のようであり、人がその中にあって生きることは大いに楽しい」
白法祖訳『仏般泥洹経』巻上(T1, pp.164c-165a)
この経において先の一節は、「閻浮利内地。所生五色如畫。人存其中生者大楽(閻浮利内地の所生は五色の画の如し。人、その中に存して生けるは大楽なり)」と訳され、『般泥洹経』のそれと一致しています。その原文は、サンスクリットであったか中央アジアいずこかの胡語で書かれたものであったかはわかりませんが、『般泥洹経』のそれとほぼ全く同様であったろうと考えてよいでしょう。
いずれにせよ、古訳の漢訳の二経には、「世界は多彩な絵のようであり、人にとってその中で生きることは楽しいものだ」と仏陀が言われたという一句が見られます。
それはまた、中共により侵略されたウイグルのトルファンにて現代発見された混交サンスクリットによって書かれたMahāparinirvāṇaśūtra(以下、『マハーパリニルヴァーナ・スートラ』)においても同様で、「ヴェーサーリーは楽しい」の件の直後に極似た短い一句があります。
a(tha bhagavān) vaiśālīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścād bhaktapiṇḍapātaḥ pratikrāntaḥ |
(pātracīvaraṃ pratiśamayya) yena cāpālaṃ caityaṃ tenopajagāma |
upetyānyataraṃ vṛkṣamū(laṃ niśritya niṣa)ṇṇo di(vā)vihārāya |
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate |
ramaṇīyānanda vaiśālī vṛjibhūmiś cāpālaṃ caityaṃ saptāmrakaṃ bahupattrakaṃ g(autamanya)grodhaḥ śālavanaṃ bhurānikṣepaṇaṃ mallānāṃ makuṭabandhanaṃ caityam |
citro jambudvīpo madhuraṃ jīvitaṃ manuṣyānām |
そこで世尊は、托鉢のためにヴァイシャーリー〈Vaiśālī. ヴェーサーリー〉(の街中)を行かれて食を摂られ、托鉢の食を終えると(精舎へ)戻られた。(そして)鉢と衣を収められてから、チャーパーラの祠〈Cāpāla caitya〉に近づいていかれた。そこで世尊は、尊者アーナンダに告げられた、
「アーナンダよ、ヴァイシャーリー、ヴリッジ族の土地〈vṛjibhūmi. ヴァッジ族の地〉、チャーパーラの祠、(そして)サプタームラカ〈saptāmraka. 七本のマンゴー樹〉(の祠)、バフパットラカ〈bahupattraka. 多くの葉が茂る樹〉(の祠)、ガウタマというニアグローダ樹〈gautamanyagrodha. バニアン樹〉(の祠)、シャーラの林〈śālavana. 沙羅の樹の林〉(の祠)、マッラ族の荷を降ろしたところ〈bhurānikṣepa malla〉(の祠)、冠飾りされた祠〈Makuṭabandhana caitya〉は楽しい。閻浮提〈Jambudvīpa〉は多彩であり〈citra. または多様な・素晴らしい、あるいは絵の意〉、人々にとって生きること〈jīvita. または生物・生活・寿命あるいは蘇生の意〉は喜ばしい〈madhura. または甘い・楽しい・快いの意〉ものである」
Mahāparinirvāṇaśūtra(E. Waldshmidt, DAS Mahāparinirvāṇaśūtra, Teil II, pp.203-204)
(ここでは地名など固有名詞は原文のサンスクリットに依った)
先の『般泥洹経』とこのサンスクリットで伝わった『マハーパリニルヴァーナ・スートラ』とは、パーリ語の『マハーパリニッバーナ・スッタ』と他のや訳の諸本に比べて一致点がより多く見られます。特に最後の一節(黄色下線部)の原文はほとんど同一であったと考えられます。
さて、二十世紀ちょうど半ば〈1950〉にドイツの文献学者〈エルンスト・ヴァルトシュミット〉によってこのような事実が発表されていたことを日本で広く紹介したのが、戦後の昭和後半に名を馳せた仏教学者中村元です。昭和以降の仏教者、仏教学者でその名を知らぬものなど無い、文献学的にも仏教的にも大変な貢献を果たした学者です。

中村は、『マハーパリニッバーナ・スッタ』を『ブッダ最後の旅』〈岩波文庫, 1980〉として現代語訳し出版した後に出した、同経の類本である『遊行経 』の翻訳と解説をする書〈仏典講座『遊行経』上, 大蔵出版, 1984〉にて、『マハーパリニルヴァーナ・スートラ』における「citro jambudvīpo madhuraṃ jīvitaṃ manuṣyānām」という一句を、「世界は美しいもので、人間の生命は甘美なものだ」と訳し披露しています。これは往古の支那の訳経僧が、「閻浮提地。五色畫。人生於世。以壽爲樂(閻浮提の地、五色の画の如し。人、世に生じて寿を以て楽と為す)」としていたもので、ずいぶんニュアンスが異なっています(拙訳は上記の如し)。
citraとはサンスクリットで、形容詞としては「明るく輝いた」・「多彩な」・「多様な」、また名詞として「絵画」などの意がある語です。漢訳者はその両義を採って「五色畫」すなわち「様々に彩られた絵画」と訳したのでしょう、なかなか考えられた訳です。中村はこれを単に「美しい」としています。そして漢訳では「楽」または「大楽」とされ、氏が「甘美なもの」としたmadhuraという語ですが、これは「蜜」・「甘さ」等を意味するmadhuから派生したもので、その原意は「甘さ」あるいは「甘いもの」、転じて「喜ばしい」・「楽しい」・「快い」の意です。
翻訳というのは難しい作業で、特にごく短い文章を訳す場合は、それが思想的・宗教的であればなおさら、よりその文意を顕すのに異常に難渋することが多いように思います。そこでしかし、中村によるこの訳は、その翻訳方針と信条に基づくものであり、また彼個人の人生観・世界観を反映したものであったのでしょうけれども、人に非常な誤解を招かせるものこと大なるものであった点において問題あるものとなっています。
何故そのように不佞が言うのか。それは、中村は特にこの一節の注釈として以下のような言説をもってしているためです。「人が死ぬとき、この世の名残りを惜しみ、死に際していまさらながらこの世の美しさと人間の恩愛にうたれる。それがまた人間としての釈尊のありのままの心境であった、と昔の佛教徒も考えていたのである」〈前掲書, pp.304-305〉などと。しかし、「この世の名残りを惜しみ、死に際していまさらながらこの世の美しさと人間の恩愛にうたれる」とはこれいかに。
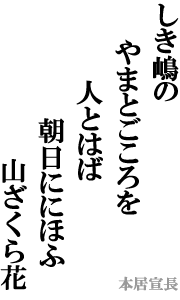
幾ばくかの時を過ごし、見慣れてもなお心打たれる素朴な情景、たとえば朝もやたつ中で旭にきらめく草葉についた朝露、あるいは悠々たる大地の上に夕日で真っ赤に染まる空の美しさを、率直に「楽しい」・「素晴らしい」と言うことはわかります。そして、荒涼と広がる大地にポツリポツリとその姿をみせる枝葉を縦横に伸ばした堂々たる大樹、それが昼間つくる広々とした木陰は非常に涼しく、文字通り楽しいものです。
そのような、中北インド(ビハール州)の郊外で今なお見られる光景に心を打たれ、その場所にあることを素朴に楽しいと思うこと。それは日本では決して見られない光景ですが、しかし情感としては日本でいう赤心における感動、「もののあはれ」や「やまとごころ」に通じたものでしょう。
けれども、「名残を惜しむ」であるとか「人間の恩愛にうたれる」などと、一体どこからそんな言葉が出てきたのか。特に「人間の恩愛にうたれる」とは。これはまさに「何を言っとるんだ」という話で、中村はあきらかにこの短い一句を詠み味わってしまっています。これだけのことで「人が死ぬとき、この世の名残りを惜しみ、死に際していまさらながらこの世の美しさと人間の恩愛にうたれる。人間としての釈尊のありのままの心境であった、と昔の佛教徒も考えていたのである」とは過言も甚だしいもので、もはや解説ではなくて小説です。これはいけません。
人が人生の終わりを意識した時、これは人によって全く異なることでしょうが、そのように感じることもあるでしょう。けれども、それを特に根拠も無しにここに持ち込み、誰でも同じに違いないとして理解してしまうのは、日本人の非常に悪い癖です。日本人には「一人よがりで同情心がない」という鋭い指摘が、大戦中の過酷な虜囚生活を経験した小松真一氏〈『虜人日記』ちくま学芸文庫〉によってなされていますが、そのような日本人の性癖がここにもこのような形で表れています。
「一人よがりで同情心がない」、それは一般的な日本人自身の感覚や見方からすると真反対のことであるかのように思われ、そのような指摘はたちまち反感をもたれるかも知れません。しかし、それはまた山本七平氏〈『比較文化論の試み』講談社学術文庫〉も取り上げその事例や理由を様々な側面から論じていますが、まさにその通りと首肯せざるを得ないものです。
また、当時は現代的価値観にそぐわない点を徹底的に削ぎ落とし、「人間ブッダ」をはじめとして「人間〇〇」をトコトン強調することがいわば一つの流行となって増谷文雄において甚だしいものとなっており、中村元もまたその中心人物の一人だったのですが、そのような時代を表した言葉でもあったのでしょう。

当時、中村によって未だ世間一般にはほとんど知られていなかった「パーリ仏典」の数々が平易な訳でもって次々出版された、その功績は非常に大きなものでした。その訳に際しては、一般には取っ付きにくい伝統的術語を用いることを極力避け、平易な現代的語をもって表現することを徹底。その結果、むしろ逆に非常にわかりにくくなってしまっている点や原意からの飛躍がある点、そして伝統的立場からその訳文に荘厳さや尊厳が見られないなどといった点に対する批判があがっています。
しかし、それはそれまでの権威主義的な慣習に対する一つの果敢な挑戦であり、また画期的な試みでもあって、後学の徒に大きな影響を及ぼすものでした。今ここで言及している氏の著作としての『遊行経』もまた優れた労作であり、今も仏教の学徒は必ず読むべき書の一つです。けれども、ここでの氏の注釈について言えば、完全に中村個人の人間観・人生観をもってした、紛れもない牽強付会 です。
この種の理解を菲才は以前から「浪漫佛教」と称し、揶揄しています。
非才は、釈尊の言動を訳すならばより荘重なる表現をもってしなければならない、なんでも必ず伝統に則してのみ言わなければならない、などと考えてそう云うのではありません。しかし、これはいけません。
ところがこれが…、いわば当たりました。その本が売れに売れたというのではなく、しかしその「中村訳の一句」は取り沙汰され、いわばバブル好景気まっさかりで浮かれた当時の人々の思想に合致して大変好まれたのでした。いや、バブル崩壊した後の今も人はこの表現を好んでいます。しばしば中村訳であることも知られず、「これこそ仏教の真の世界観、人間観である」などといった体で言及されています。「『世界は美しいもので、人間の生命は甘美なものだ』と、仏陀すらその生涯の最後に言われていたのだ!」と。
なお、その本の主題である『遊行経』には、『マハーパリニルヴァーナ・スートラ』や『般泥洹経』に見られる一句はもとより、『マハーパリニッバーナ・スッタ』や『大般涅槃経』にある「楽しい」云々という一節すらまるごとありません。そもそも、現代人による恣意的な訳がされた一句の前に、それまで釈尊が積み重ねられてきた教説・教誡が吹き飛ぶはずも無い。
大体、「楽しい」云々と言われる前後の文脈が重要なはずですが、それが顧みられることはあまりないようです。あってもそれは中村訳の影響のもとに浪漫的に読み解かれています。一時代を築いたとすら言える中村元という大学者の権威の前に大概の人はみなひれ伏し、そのような彼の言葉に疑問を持つ人は多くありません。
そしてまた、世人にとってそんなことなど「美しい」・「甘美だ」と訳された一句の前にはもう全くどうでもよいことで、自身らの世界観は仏陀からのお墨付きが出ていたと大喜び。今もなお、あちこちで「中村訳の一句」は珍重され、「まさかという衝撃を覚えた」であるとか「仏陀がその死を目前として、率直な人間らしいお姿を見せられていたことに感動した」だの言う人が続々出てくるのですから面白いものです。世界についてそう言って欲しい人、世界はそうであって欲しい日本人の要求に、見事に応える言葉であったのでしょう。
しかし、それはまさに「一文をとりて万経を捨てる」という態度に他なりません。いや、この場合、それは中村流の浪漫訳であることから「一文」にも該当しないかもしれない。

とは言え、そもそもそのような事態は世間一般あちこちで生じており、これはただ仏教におけるその一例に過ぎません。巷間で有名な例を挙げれば、「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」があります。これは勿論、福沢先生による『学問のすゝめ』にある一文で、あるいはトーマス・ジェファーソンによるアメリカ独立宣言の引用ではなかったかと思われているものです。そして福沢先生はそれを導入としての言葉として用い、しかしながら…と続けたのであって主題では全くないし、福沢先生も現実にそうだと思ってはいない。
ところが、『学問のすゝめ』を実際に読んでおらず、あるいは読んでも理解したのでない者がただこの一文だけを取り沙汰し、もって「福沢諭吉は人の平等をうたっていた」などと甚だしい誤解をして使っているようなものです。
そのようなよくある事態が、ここでも生じているに過ぎないということでしょう。しかしそれはまた、現在の日本では自分たちに都合が良く、世間受けしそうな「使える」経文の拾い読みとその継ぎ接ぎによって仏教が語られ、そのようなのこそ巷では好まれているという現実を垣間見せるものであるとも言えます。