前項で示したように、朝廷が相当なる歳月と人員を動員してようやく「僧尼令」を施行し、僧尼の監督職として僧綱が設けられていました。しかしながら、「僧尼令」が発布されて以降、僧尼が令によく従っていたかと言えば決してそのようなことはありませんでした。むしろしばしば令に違反した者があったことが『続紀』の端々に記されています。
「僧尼令」が施行されてから二十年後には、僧尼を監督すべき僧綱すらまともに機能しておらず、それに対する苦言がなされています。
己卯。太政官奏言。内典外敎。道趣雖異。量才揆軄。理致同歸。比來僧綱䒭。既罕都座。縦恣横行。既難平理。彼此往還。空延時日。尺牘案文。未經決斷。一曹細務。極多擁滯。其僧綱者。智徳具足。眞俗棟梁。理義該通。戒業精勤。緇侶以之推讓。素衆由是歸仰。然以居処非一。法務不俻。雜事荐臻。終違令條。冝以藥師寺常爲住居。又奏言。垂化設敎。資章程以方通。導俗訓人。違彝典而卽妨。近在京僧尼。以淺識輕智。巧說罪福之因果。不練戒律。詐誘都裏之衆庶。内黷聖敎。外虧皇猷。遂令人之妻子剃髪刻膚。動稱佛法。輙離室家。無懲綱紀。不顧親夫。或負經捧鉢。乞食於街衢之間。或僞誦邪說。寄落於村邑之中。聚宿爲常。妖訛成羣。初似脩道、終挾姧乱。永言其弊。特須禁斷。奏可之。
(養老六年〈722〉七月)己卯〈10日〉、太政官が奏言した。
「内典〈仏典〉と外教〈儒教や道教〉とは、その道の趣が異なっているといっても、その才を量って職を司ることなど、その理致は同一であります。この頃、僧綱〈玄蕃寮に属す寺院・僧尼の監督職〉等が都座に旗さして縦恣に横行すること久しく、もはやこれを糺し裁くことすら難しくなっております。(僧綱に任じられた僧徒らは)ただあちこち往還するだけで空しく月日を過ごし、 尺牘〈書簡〉の案文〈審議すべき事案〉は決断することなく放置し、一曹〈一官職〉としての細務〈細々とした事務〉を極めて擁滞〈滞ること〉させることあまりに多くあります。そもそも僧綱とは、智徳を具足した真俗〈出家と在家〉の棟梁であります。理義〈道理と正義〉に該通〈該博な知識を有すること〉し、戒業に精勤なる者です。緇侶〈出家者〉はその故に(僧綱の職位に)推讓〈自ら譲って人を推薦すること〉し、素衆〈在家者〉はその為に帰仰〈帰依し鑽仰すること〉するものです。にもかかわらず、その居処が一つでないことを理由に法務を全うせず、雑事ばかり頻りに起こして終には令条〈「僧尼令」〉に違反しております。(そのようなことから以後は)よろしく薬師寺をもって(僧綱職に任じられた者の)常の住居とさせたまえ〈これ以降、機関としての僧綱は薬師寺に置かれ、その職位に任じられた者も同寺に居することとされた。しかし以降も、僧綱職に任じられた僧は必ずしも薬師寺に住さなかった〉」
また(太政官は)さらに奏言した。
「化を垂れ教えを設けること〈仏法を広め教導すること〉は、章程〈規則・法式〉に従うことに依ってこそ四方に通じるものであります〈普遍的になること〉。俗を導き人を訓じる〈教え諭すこと〉のに彝典〈常道〉に違ったならば、それが成功することはありません。近頃、(平城)京の僧尼が、その浅はかな知識と軽い智慧でもって巧みに罪福の因果を説きまわり、戒律を練行することなくして都裏の衆庶〈民衆〉を詐誘〈欺き騙して誘うこと。ここでは仏教の名を借りて邪道に導くこと〉しています。内には聖教〈仏教〉を蔑ろにして外には皇猷〈帝による治国の道〉を損なっているのです。遂には人の妻子に剃髪・刻膚〈自らの皮膚を一部剥いで経文などを刻むこと〉させていますが、(そんな者は)ややもすれば仏法と称してたやすく室家を離れ、綱紀に則ること無く、親や夫を顧みることがなくなっております。あるいは経典を持ち鉢を携えて食を街衢〈巷〉の間に乞い、あるいは(あたかもそれが正法であるかのように)偽って邪説を誦し、村邑〈村里〉の中に寄落し聚宿〈集団で泊まること〉することが常態化して、妖訛〈でたらめ。ここでは妖しく邪な思想を吹聴する輩〉が群れをなしております。(その輩共の振る舞いは)初めは(正法の)修道に似たものではありますが、終には姦乱の様相を呈しております。長期的にその弊害を考えてみたならば、特にすべからく禁断しなければなりません」
よって、これを奏可した。
『続日本紀』巻九 養老六年七月己卯条
(新訂増補『国史大系』普及版 続日本紀』前篇, pp.93-94)
この『続紀』の記述には、当時の僧綱(僧正義淵・大僧都観成・少僧都弁静・律師神叡)すらもまともに機能していなかった様子が見え、それに対して苦々しく思っている公卿の苛立ちが感ぜられます。そこで、これ以降、僧綱は機関として薬師寺に設置され、また僧綱に任じられた僧も常住することが定められています(平安京遷都以降は西寺)。
また、おそらく行基の教団が相変わらず「僧尼令」を無視し、妖しげな布教活動を行っていたことも記されています。国が「小僧行基」と名指しして批判したものとして、今もよく知られるのは「養老元年四月壬辰条」です。しかし、それから五年を経てもなお依然として街に跋扈する、その教団を取り締まることは出来ていなかったことが伺えます。
律令の整備により国法として僧尼に対する法整備はなされたものの、しかし仏法としては未だ全く不十分であって、正規の僧侶が不在であることに変わりはありません。「僧尼令」にせよ僧綱にせよ、それが整備されたことで、孝徳天皇や文武天皇が望んだように僧尼が「如法」になることはありませんでした。
何故か。それは戒法が未だ伝わっておらず、その理解もまったく足りていなかったことによります。その意味では、推古朝において百済僧観勒が奏上した「僧尼が未だ法と律りとを習わずを以て、たやすく悪逆を犯す」という状況が、その程度はかなり異なったものとなっていたであろうとは言え、引き続いていました。しかし、当時と明らかに違っていたのは、多くの日本僧が入唐留学し、印度ではなく支那におけるそれではあるものの、「如法」とは何かを知る者が幾人もあったことです。
そんな中、日本仏教に戒律が欠落していることを嘆き、その整備の必要性を強調する僧が現れています。唐に留学僧として足掛け十七年の長きに渡り修学し、養老二年〈718〉に帰朝。大官大寺を平城京に遷して新たに大安寺として創建した、三論宗の道慈〈?-744〉です。
冬十月辛卯、律師道慈卒。天平元年爲律師。法師俗姓額田氏。添下郡人也。性聡悟爲衆所推。大寶元年隨使入唐。渉覽經典。尤精三論。養老二年歸朝。是時釋門之秀者唯法師及神㲊法師二人而已。著述愚志一巻論僧尼之事。其略曰。今察日本素緇行佛法規模全異大唐道俗傳聖敎法則。若順經典。能護國土。如違憲章。不利人民。一國佛法。万家修善。何用虛設。豈不愼乎。
(天平十六年〈744〉)冬十月辛卯、律師道慈が卒去した。(道慈は生前、)天平元年に律師に任じられている。法師の俗姓は額田氏、添下郡の人である。その性が聡明であったことから人々から推され、大宝元年〈701. 実際は大宝二年〉に遣唐使に随って入唐した。(道慈は、長安の西明寺に滞留し)経典を広く披覧したが、中でも最も三論に詳しかった。養老二年〈718〉に帰朝。当時の釈門〈仏教僧〉で秀でていたのは、ただ(道慈)法師及び神叡法師〈新羅で法相を学び帰朝した僧〉の二人のみであった。(帰朝後に)『愚志』一巻〈『続紀』が以下にその要略を伝えるのみで現存しない〉を著述し僧尼の事を論じているが、その概略は以下のようなものである。
「今、日本の素緇〈在家信者と出家者〉が仏法を行う様を見ると、その規模〈規矩〉が全く大唐の道俗が伝える聖教の法則に異なっている。もし経典(の所説)に順じたならば、能く国土を護るであろう。しかし、もし(仏教の)憲章に違えたならば、人民を利すことはない。(日本)一国の仏法、そして万家の修善において、どうして虚設〈実のない見せかけ〉を用いるのであろう。なぜ慎まないのであろうか」
『続日本紀』巻十五 天平十六年十月条「道慈卒伝」
(新訂増補『国史大系』普及版『続日本紀』前篇, p.179)
道慈は、かつて南山律宗祖道宣が拠点とした寺であり、また律の学匠でもあった義浄や密教の大阿闍梨であった善無畏が訳経に従事した長安の終南山西明寺にて滞在し、修学していました。唐代の西明寺は、印度の祇園精舎を模したものと伝説される南山律宗の本拠であって大規模な伽藍が建ち並んで壮麗を極め、内外の行学兼備の諸学僧が雲集して仏教を研鑽した、長安でも指折りの大寺院です。
道慈は、これは高い確度で言えることですが、入唐直後に具足戒を受け比丘となっていたと考えて間違いありません。そして、唐でも最先端の寺院にてその実際を長年目の当たりにしていたが故になおさら、日本における僧尼および俗人らがまるであるべき威儀を備えていないこと許せず、それを嘆き批判したのでしょう。それはこの『続紀』「道慈卒伝」が略して伝える、その著『愚志』の概略から伺い知ることが出来ます。
道慈の、実は仏教者としては至極まっとうと云える理念的・感情的なものでなく確たる根拠に基づいた批判精神。それはしかし、いまだ仏教のなんたるか、戒律の重要性やその正統を知らない、あるいは知りながら敢えて無視していた当時の人々には、むしろ彼が実に頑固で不協調的であるとの印象を与えていたのでしょう。「虚設」の中で生きる人には「虚設」こそが正義であってその生きる道であるのに、それを横から批判する者は彼らにとってはやっかいな加害者、その和を乱す不埒者でしかない。そのような構造は、現代の日本社会においてもしばしば見られる事態です。
編者不明ながら日本初の漢詩集『懐風藻』「道慈伝」には以下のような一節があり、そこからその様子が伺えます。
養老二年。歸來本國。帝嘉之。拜僧綱律師。性甚骨鯁。為時不容。
養老二年〈718〉、(道慈は)本国に帰来した。帝はこれを喜び、僧綱の律師に任命した。(しかし、道慈の)性格は甚だ 骨鯁〈意志強固で不屈であること〉であって、その時代に(仏教者として正しくあるべきという主張が)受け入れられることはなかった。
『懐風藻』「道慈伝」
『懐風藻』にわざわざ伝記付きでその歌を載せられているのは、道慈が当時「性甚骨鯁。為時不容」とされたとはいえ、そのような態度が仏教者として正しいと編者によって高く評価されていたからこそのことでありましょう。もっとも、道慈は当時の朝廷からもその知見と学徳とはやはり評価されており、天平元年〈729〉、律師として僧綱の任につけられています。
そんな道慈の志が他に直接影響を与えたのか、あるいは当時そのような自省と求法の志が気運として高まっていたのかしれませんが、ついにその実現のための契機を作る人が現れています。元興寺の隆尊です。隆尊の場合は道慈と立場が異なり、「自らが出家していながら無戒であり、実は正しく出家者でないことを嘆いている」のですが、舎人親王 を通じて帝に戒師招聘の必要性を上奏したとされています。
五年癸酉。《中略》又有元興寺沙門隆尊律師者。志存鵝珠。終求草繋。於我国中。雖有律本。闕傅戒人。幸簉玄門。嘆無戒足。卽請舎人王子處曰。日本戒律未具。假王威力。発遺僧榮叡。隨使入唐。請傅戒師。還我聖朝。傅受戒品。舎人親王卽爲隆尊奏。勑召件榮叡入唐。於是興福寺榮叡。與普照倶奉勑。四月三日。隨遺唐大使多治比眞人廣成。到唐國。
(天平)五年癸酉〈733〉、《中略》 また元興寺の沙門、隆尊律師という者があり、その志は鵝珠〈小さな命でも決して害わず守ろうと努めること。ある比丘が、托鉢に訪れた宝玉職人の家で誤って宝玉を飲み込んだ鵝鳥の命を護るため、自らの身命を擲とうとした、という『大乗荘厳経論』巻十一にある説話に基づく語〉にあって終に草繋〈どれほど小さな律の条項であってもこれを厳密に守ろうとすること。またはそのような比丘のこと。賊により地面から生えた草でもって捕縛された比丘達が、生草を損傷してはならないという律の条項を守るために、たやすく引きちぎることが出来る草であってもこれを害わなかった、という『大乗荘厳経論』巻三にある説話に基づく語。「結草の比丘」とも〉たることを求めていた。
「我が国の中には律蔵の典籍は有るけれども、(肝心のそれを実行する)伝戒の人が欠けて無い。(私は)幸いにも玄門〈出家。玄は鼠色で、支那以来僧侶の衣の色を象徴・代表したもの〉に交わることが出来たとはいえ、戒足の無いこと〈戒足とは戒が出家の根本であることの譬え。日本に正統な律の伝来・実行が無いこと〉を嘆くばかりである」
と。そこで舎人王子〈天武天皇の第三皇子、舎人親王。淡路廃帝(淳仁天皇)の父〉のもとに参じ、
「日本には戒律が未だ具わっておりません。王の威力を借り、僧栄叡を派遣し大使に随行させ唐に入らせたまえ。そして伝戒師を請うて我が聖朝に還らせ、戒品を伝受させたまえ」
と請い求めた。舎人親王は隆尊の為にこれを上奏し、勅にて件の栄叡を召して入唐させることとなった。そこで興福寺の栄叡は普照と共に勅を奉じ、(同年)四月三日、遺唐大使多治比真人広成に随行して唐の国に至ったのである。
『東大寺要録』本願章第一 (筒井英俊校訂『東大寺要録』, p.7)
これは、平安後期に当時蒐集し得た東大寺に関わる諸資料を集成・編纂した寺誌『東大寺要録』の一節です。同時代の思託が『延暦僧録』に「高僧沙門釈隆尊伝」として記していることからすると、隆尊が戒師招聘のために運動したことはおそらく事実であったと思われます。
隆尊もまたその三十三年後の天平勝宝三年〈751〉に律師として僧綱に任じられ、また翌四年四月九日に修された東大寺の盧遮那仏落慶法要の際には講師として出仕するなどそれなりに学徳の人で、特に華厳に詳しかったようです。道慈と若い頃の隆尊との繋がりを示す直接の史料は、拙には今のところ見いだすことはできません。しかし、道慈の問題意識が隆尊に影響を与えていたことは十分考えられます。
道慈ばかりでなく、長年唐に渡って修学した留学僧達は唐に渡ってすぐ具足戒を受けていたと、それをわざわざ伝える史料こそ無いものの、しかしそれが出家として至極常識的なこととして考えられるため、彼等は皆正式な僧、比丘となっていた。しかし、その多くは帰国すると忽ち日本における相似僧らの現状に口をつぐみ、結局はそれと同じ類となってしまっていたかのようです。が、道慈は違いました。彼からすると周囲がまったく律儀を備えておらず非法であることを「何ぞ虚設を用いんや」と歎いた。そして、隆尊の場合は、留学経験が無く律儀を正しく受け得ていないことから、世間的には僧であっても真に僧ではないことを自覚し、「戒足の無いことを嘆いた」のでしょう。
仏教として正規の僧になるためには、諸々の条件を満たし、三師七証・白四羯磨という正規の手段によって具足戒を受けるという一点にのみあります。その正規の条件と手段は律蔵に詳らかにされており、これを何人も変えることは出来ません。その故に鑑真およびその一行のような、それを執行し得る伝戒師の招聘が要請されたのでした。
天平勝法六年、共に発った栄叡は唐土において病に没してしまっていましたが、苦節二十年あまり、五度の渡航失敗を経て、普照はついに伝戒するに相応しい僧鑑真およびその一行を日本に招聘しています。鑑真は普照の要請に応え、共に数々の失敗と苦難を乗り越え日本渡航を目指すなか、光を失っていたことはあまりにも有名な話です。
これもまたしばしば誤解されている点ですが、仮に伝戒師として鑑真が当時最適の人であったとしても、鑑真ただ一人のみ渡来したのでは「全く」意味をなしません。戒(といっても特に出家の律儀戒である律)を「授ける」・「伝える」のは僧伽であって、誰か比丘個人ではありません。そして律を授けることが出来る僧伽は原則として十人以上の比丘によって構成されるものに限られます。したがって、鑑真はその通り自身を含めて十人以上の比丘を伴い渡来しています。
ただし、『続紀』においては、その人数について以下のように伝えています。
壬子。《中略》 入唐副使從四位上大伴宿祢古麻呂來歸。唐僧鑒眞。法進等八人隨而歸朝。
(天平勝宝六年〈754〉正月)壬子〈16日〉、《中略》 入唐の副使、従四位上大伴宿祢古麻呂〈唐の玄宗皇帝の朝賀において、その席次が日本より格下の新羅の下であったことに抗議し、席次を交換させた人。帰国後は正四位下に加階された。橘奈良麻呂の乱で獄死〉が来帰し、唐僧の鑑真・法進等八人を随えて帰朝した。
『続日本紀』巻十九 天平勝宝六年正月壬子条
(新訂増補『国史大系』普及版, 『続日本紀』前篇, p.197)
この『続紀』の記事では、鑑真と法進などただ八人が、大伴宿祢古麻呂に伴われて来朝したと伝えています。しかし、ここに記される八人という数は、鑑真に要請された伝律の目的、すなわち正しく受具足戒を執行し得る十人以上の比丘、いわゆる三師七証による授戒の実現に全くそぐわないものです。
鑑真が乗船したのは、当初は大使・副使らが合議して遣唐使の帰船に同乗させるのを取りやめることとしていたものの、しかし大使にも黙って秘密裏に乗船させていた副使大伴宿祢古麻呂の第二船です。もし平城京に到来した当初の鑑真一行が八人で正しかったのであれば、あるいはその一行全員が第二船には同船しておらず、その一部が同じく副使であった吉備真備の第三船に乗って前年の十二月七日に益久嶋(屋久島)に着き、またそこから紀伊国牟漏埼(室崎、現:燈明崎)に漂着して、ようやく平城京にて合流したのでしょう。事実、『東征伝』によれば、鑑真を招聘した功第一等の人、普照は最後の最後に遣唐使の帰国便に合流していたようで鑑真と同船しておらず、吉備真備の第三船に乗船し帰着しています。
なお、鑑真らの乗船を拒否した大使藤原清河の第一船は、阿兒奈波嶋〈沖縄本島〉までは第二船と共に着いたものの、不幸なことにその後座礁。どうにか奄美嶋〈奄美大島〉を目指して再出発するも逆風に遭って押し戻され、なんと驩州〈現在のベトナム北部に置かれた州〉に漂着。ついにその後も帰国することが出来ず、皇帝から任官されて唐にてその生涯を終えています。皮肉なことに、帰還に失敗して鑑真らを乗船させていることが唐の官憲に発覚するのを恐れて鑑真を同船させることを拒否した清河は、その予想が一部現実のものとなったのでした。
一行の人数についてはただ『続紀』の記録が不正確であった、という可能性もまたあります。しかし、これほどの数の誤まりは考え難いものです。私見としては、あくまで推測にすぎませんが、やはり唐僧は第二船と第三船とに分乗していたと考えています。なお、淡海三船による鑑真の伝記、いわゆる『東征伝』においては以下のように伝えられています。
相隨弟子。揚州白塔寺僧法進。泉州超功寺僧曇靜。台州開元寺僧思託。揚州興雲寺僧義靜。衢州靈耀寺僧法載。竇州開元寺僧法成等一十四人。藤州通善寺尼智首等三人。揚州優婆塞潘仙童。胡國人寚最如寚。崑崙國人軍法力。膽波國人善聽都廿四人。
(ついに成功することになる、鑑真六度目の日本渡航に)相従った弟子は、①揚州白塔寺僧法進・②泉州超功寺僧曇静・③台州開元寺僧思託・④揚州興雲寺僧義静・⑤衢州霊耀寺僧法載・⑥竇州開元寺僧法成など十四人。そして藤州通善寺の尼智首等の三人。また揚州の優婆塞〈upāsaka. 在家信者の意であるが、比丘が旅をするには、原則として必ず戒律護持の助けをする在家者すなわち浄人を要するから、単なる随行者ではなく浄人としてであったろう〉潘仙童、胡国〈中央アジアの国〉の宝最と如宝、崑崙〈現在のベトナムからカンボジア、マレー半島にかけての地域〉国の軍法力、膽波国〈現在のベトナム中部あたりに存した国〉の善聴、総勢二十四人であった。
真人元開『唐大和上東征伝』(丸数字は訳者)
(新版『大日本佛教全書』, vol.72, p.28b-c)
この中、具体的にその名が挙げられているのは僧十四名のうちわずか六名、尼僧については三名中一名。浄人として随行したとおぼしき在家者六人の名は全て挙げられています。なお、その詳細な名については、これも凝然が著したものであって後代の史料とはなりますが、その著『律宗瓊鑑章』〈または「りっしゅうけいかんしょう」〉(以下、『瓊鑑章』)に記されています。
來朝之後總經十年。初之五年住東大寺戒壇院。唐禪院卽常居住處也。後之五年居唐招提寺。随從弟子中呈名後代者。仁韓仁幹の写誤大徳。法進大僧都。曇靜大徳。法顆大徳。思託大徳。義靜大徳。智威大徳。法載大徳。法成大徳。靈曜大徳。懷謙大徳。此十一人於唐受具。如寶少僧都。惠雲律師。惠良大徳。惠達大徳。惠常大徳。惠喜大徳此之六人竝亦唐人。而於此國受具足戒。沙彌道欽是亦唐人。此十七人随從來朝。始終随逐助師化儀。
(鑑真が)来朝して後、総じて十年を経るなか、初めの五年は東大寺戒壇院にあって唐禅院〈鑑真のために東大寺内に創建された寺院。後にこの南側に戒壇院が建立された〉が常の居住の処であった。後の五年は唐招提寺に居した。随従の弟子の中、その名を後代に残している者は、①仁幹大徳・②法進大僧都・③曇静大徳・④法顆大徳・⑤思託大徳・⑥義静大徳・⑦智威大徳・⑧法載大徳・⑨法成大徳・⑩霊曜大徳・⑪懐謙大徳であり、これら十一人は唐において受具しており、⑫如宝少僧都・⑬恵雲律師・⑭恵良大徳・⑮恵達大徳・⑯恵常大徳・⑰恵喜大徳の、これら六人は皆唐人〈ここでの「唐」は必ずしも唐国を意味せず「外国」の意〉であったがこの国で具足戒を受けている。そして沙弥道欽もまた唐人であった。この十七人が(鑑真に)随従して来朝し、始終随逐して師〈鑑真〉の化儀を助けたのである。
凝然『律宗瓊鑑章』巻六(『日本大蔵経』 Vol.15, p.50)
この『瓊鑑章』の所伝が正しいものと仮定し、『東征伝』の所伝と併せて鑑みたならば、当初の僧十四人のうち十一人が比丘であり、三人が沙弥であったということでなるでしょう。『東征伝』は二十四人としているのに対し、ここで凝然が(鑑真を除いて)十七人としているのは、単純に見たならば、日本で比丘や沙弥となった者を含む出家者の総数であったと考えられます。
いずれにせよ、朝廷の使命をおびた普照によって、鑑真一行はようやく日本に渡来しています。しかしながら、その渡来と伝戒は、日本の僧徒から必ずしも両手を挙げて歓迎され、受け入れられてはいませんでした。
自至聖朝合國僧不伏。無戒不知傅戒來由。僧數不足。先於維摩堂已具叙竟。從此已後伏受戒。其中志忠靈福賢璟引占察經許自誓受戒。便將瑜伽論決擇分第五十三巻詰云。諸戒容自誓受。唯聲聞律儀不容自受。若容自者。如是律儀都無規範。志忠賢璟等杜口無對。備以衣鉢受戒。
(普照・鑑真・思託らが)聖朝〈日本〉に到着しても、国中の僧は(鑑真らによってもたらされた正統な戒律を改めて受けることを)承服しなかった。(彼らは)無戒であって伝戒の来由〈正統な受戒法やその内容〉を知らず、また(正統な受戒のために必要な)僧〈比丘〉の員数〈原則として授戒は最低十人、いわゆる三師七証の比丘が揃わなければ出来ない。例外として辺地では五人以上〉も不足していたのである。そこで先ず(普照は、興福寺)維摩堂にて(正統な戒律とその受戒について、旧僧らを集めて)詳細に講述した。するとそれ以降、(旧僧の大半は鑑真からの)受戒を受け入れていった。
しかしながら、その中でも志忠・霊福・賢璟は、『占察経』を引用して自誓受戒(によって比丘となりえること)が許されていると主張(し、自身らが自誓受戒によって比丘となっていると反発。鑑真から改めて受戒することにあくまで反対)した。そこで(普照は)『瑜伽師地論』決択分巻五十三の所説を示して彼らを詰問した。菩薩の諸戒は自誓受が許されているものの、しかし唯だ声聞律儀〈『瑜伽師地論』本文には「苾蒭律儀」と限定して説かれている。しかし、これを普照(あるいは思託)は出家者の律儀全てを代表しての言であると解し「声聞律儀」と変えて言ったようである。律の規定に従えばそのような理解は正しく、より正確な表現となっている〉のみは自誓受が容認されていないこと。もし(声聞律儀の)自誓受を許したならば、如是の律儀〈仏陀以来の出家の律儀〉は全て無規範なものとなってしまうことを諭したのである。すると志忠・賢璟等は口をつぐんでもはや反論出来なかった。(そこで彼らも、改めて鑑真のもとにて)衣鉢を以て受戒することになった。
宋性『日本高僧伝要文抄』第三 「高僧沙門釈普照伝」
(新版『大日本佛教全書』, vol.62, p.52c)
以上のように、旧僧の相当数が自身らはすでに『占察経』の所説に基づき自誓受戒したことによって比丘となっていると主張し、鑑真ら唐僧から授戒することを拒否していたようです。その中には、鑑真一行が河内国から平城京へ向かう途上で出迎えていた、志忠・賢璟(賢憬)・霊福(霊祐)がありました。そのように名が挙げられていることからすると、彼等は当時、すでに一定の地位にある者であったのでしょう。
実際、彼等が自身らはすでに比丘として得戒していることの根拠とした『占察経』には、以下のように説かれています。
復次未來世諸衆生等。欲求出家及已出家。若不能得善好戒師及清淨僧衆。其心疑惑不得如法受於禁戒者。但能學發無上道心。亦令身口意得清淨已。其未出家者。應當剃髮被服法衣如上立願。自誓而受菩薩律儀三種戒聚。則名具獲波羅提木叉。出家之戒名爲比丘比丘尼。
復た次に、未来世の諸衆生が出家すること欲し、あるいはすでに出家しているけれども、もし善好の戒師および清浄の僧衆を得ることが出来ないならば、その心に疑惑があって如法に禁戒を受けることを得ない者は、ただよく発無上道心〈発菩提心〉を学び、また(『占察経』の説く懺悔と占いの方法によって)身口意を清浄とさせてから、いまだ出家していない者は剃髮して法衣を被服し、先に説いたように誓願を立て、自誓して菩薩の律儀である三種戒聚〈三聚浄戒〉を受けよ。さすれば具さに波羅提木叉たる出家の戒を獲得したものとし、名づけて比丘・比丘尼とする。
『占察善悪業報経』巻五十三 摂決択分(T17, p.0904c)
しかし、そもそも『占察経』の所説があまりに他とかけ離れて妖しくまた不合理なものであることから、実際これを読むと杜撰極まりない内容に呆れるばかりと言えたものですが、支那において代々偽経とされ続けてきた経の一つでした。それがちょうど八世紀の始め、何故か武則天がこれを真経として扱うように勅命したことから『武周録』に初めて真経として収録され、続く『開元録』〈730頃成立〉においても真経として収録されてしまっています。そもそも隋唐における仏教は皇帝の庇護の下に行われたものでしょうけれども、政治介入によって偽経が真経にされるという不可解な事態が生じています。
そうして『開元録』成立して間もない頃、そこに収録された五千余経を日本にもたらしていたのが玄昉です。玄昉は霊亀七年〈716〉に入唐、帰朝したのは天平七年〈735〉のことです。実は玄昉は必ずしもその目録にある経典すべてを請来してはいないのですが、しかし『占察経』はその将来した中に含まれており、それがおそらく日本への初伝です。玄昉のもたらした経典、というより最新の経録である『開元録』の影響は非常に大きく、光明皇后に御願によるいわゆる「五月一日経」は、その『開元録』に記載されたものを基準として「一切経」としたものでした。
以上のことから、これは未だ仏教学や史学などの学者が指摘していないことですが、鑑真渡来当時、志忠や賢璟などによって『占察経』に基づく受戒が行われていたといっても、それは玄昉以降のそれほど年月を経ていない比較的新しい行法であったと考えられます。なにより、特に受戒に関しての『占察経』の所説は、印度以来の常識からかけ離れたものであって、『開元録』などに真経として収録されたとはいえ支那においても直ちに受け入れられ、実行されたものでは到底ありませんでした。
そこで、それが非法であることの説得交渉にあたったのが、鑑真らを招聘するのに第一等の功あった普照でした。その時、その論拠として出されていたのが、『瑜伽師地論』(以下、『瑜伽論』)巻五十三の一節であったといいます。ではそこには実際どのように説かれているか。それを確実に知っておくことは、古代ばかりでなく中世・近世の日本仏教における戒律の動向を知るために極めて重要です。
隨轉差別者。謂有堪受律儀方可得受。此中或有由他由自而受律儀。或復有一唯自然受。除苾芻律儀。何以故。由苾芻律儀非一切堪受故。若苾芻律儀。非要從他受者。若堪出家若不堪出家。但欲出家者。便應一切隨其所欲自然出家。如是聖教便無。軌範亦無。善説法毘柰耶而可了知。是故苾芻律儀無有自然受義
隨転の差別とは、律儀を受けるに堪えてはじめて、まさに受けることが可能たることである。これ〈受戒〉について、あるいは他者に由り〈従他〉または自らに由って〈自誓樹〉律儀を受ける方法がある。あるいはまたさらに一つ、ただ自然受〈従他でも自誓でもなく、自然に戒を備えること。釈迦牟尼の受具、あるいは定共戒や道共戒〉がある。ただし、苾芻律儀〈苾芻は[S]bhikṣuの音写。比丘に同じ。ここでは比丘律儀の名を以て出家すべての立場に該当するものとして挙げていると解すべき〉は例外である。なんとなれば、苾芻律儀は万人が受けるに堪えるものではないためである。もし「苾芻律儀は、必ずしも従他受によるもので無い」などとしてしまえば、出家に堪えようが出家に堪えなかろうが、ただ出家を望んだならば、たちまちの誰であっても思うがままに自然と出家(であると自称)することが可能となってしまうであろう。もしそのような主張がまかり通るのであれば、聖教〈仏教〉は軌範など無いものとなり、また理解すべき善説の法〈Dharma. 教え〉と毘柰耶〈Vinaya. 律〉とは無きに等しいものとなろう。したがって、苾芻律儀には自然受の義は成立しない。
『瑜伽師地論』巻五十三 摂決択分(T30. p.589c)
この一節はいわゆる難解なものでは全くなく、一度読めばたちまち理解できる内容となっています。ここでは出家の五衆をすべて苾芻律儀としてまとめて言っていますが、出家者の律儀戒は自誓受も自然受も有り得ないことが明瞭に断じられています。なお、これは何も唯識教学に限定されたものはなく通仏教的理解であって、『瑜伽論』に説かれた法相宗においてのみ通用する説ではありません。
『瑜伽師地論』はその一世紀以上前から日本にもたらされており、法相宗ならば尚更よく読まれ研究されていたはずです。それが、むしろ普照によって突きつけられるまで、このような常識的であり、誰でも読めばただちにわかることが知られていなかった、理解されていなかったことからすると、当時は修学の主眼が唯識教学に関する点に絞られ、戒や律について説かれている箇所は等閑視されていたのではないかと思われます。
『瑜伽論』は全百巻という比較的大部な典籍であるため、当時重点的に学習される範囲に『瑜伽論』「摂決択分」が無かったと考えざるを得ません。あるいは主に読まれ研究されたのが『瑜伽論』ではなく、『成唯識論』であったのかもしれません。実際、これは後代の延暦二十五年〈806〉に発布された年分度者に関する太政官符におけることではありますが、法相宗僧が必ず学ぶべき典籍として『瑜伽論』ではなく『成唯識論』が挙げられています。
(かといって、官符で義務付けられていないから学ばれなかったことも考えにくく、実際その抄本はしばしば写経されているため、その程度は知られぬ者の、必ず学ばれてはいたことが知られます。)
鑑真からの受戒を反対する者のほとんどが法相宗僧であったと思われますが、確かに『占察経』にそう説かれているとは言え、『瑜伽論』でこのように明瞭に説かれていることを突きつけられたならば、それで納得せざるを得なかったことでしょう。
なお、この記述からは、彼等は普照との対論でたちまち説得し、改めて受戒することをすぐに受け入れたかのように感じられるものですが、実際は数ヶ月から一年の月日を要したようです。あるいは、その可能性は低いと思いますが、興福寺維摩堂において彼等を説得したのが翌年のことであったのかもしれません。
大和尚傳云。《中略》
其年四月初勑於盧舎那佛前立壇。爲沙彌證修等四百卅餘人受戒。後有内道場興行僧。神榮行潜等五十五人重受大小乘戒。至勝寶七歳於盧舎那佛前爲沙彌受戒。後有實行僧志忠。靈福。賢璟。善頂。道緣等八十餘人。遠起臥具進隆和光之族類者。來云受具足戒。已上
『大和尚伝』〈思託による鑑真伝。全三巻。散逸〉が伝えるところでは、 《中略》
その年〈754〉の四月初め〈5日〉、勅して盧舎那仏の前に壇を立て、沙弥證修〈異本には澄修〉など四百三十余人〈四百四十余人の誤写であろう〉に受戒した。その後、内道場興行僧〈内道場は宮中に設けられた仏殿。興行僧は後代の内供奉にあたる宮廷で帝に側仕え仏事に携わった僧〉の神栄・行潜など五十五人が重ねて大小乗戒を受けた。
(天平)勝宝七年〈755〉となって盧舎那仏の前にて沙弥の為に受戒した。その後、(当初は鑑真らから具足戒を受けることを拒絶していた)実行僧〈志忠らについて『大和尚伝』の前段では「布衣高行僧」、『東征伝』では「高行僧」と表している〉の志忠・霊福・賢璟〈元興寺僧.法相宗〉・善頂・道縁など八十余人の、遠く臥具から起ち進んで和光〈和光同塵〉を興隆する族類の者らが、来たって具足戒を受けると言った。已上
『東大寺要録』巻四 諸院章
(筒井英俊校訂『東大寺要録』, pp.96-98)
鑑真らから受戒を当初拒んでいた僧らに対し、思託は非常に気を使っていたようで、彼等をして「高行僧」あるいは「実行僧」などと称し、また「起臥具進隆和光之族類者」などという不自然に思える形容の辞を以てしています。それまでの文脈からして、この一節だけなにか含みのある大仰な表現となっています。したがって彼等と鑑真など唐僧が以降も衝突していたとは必ずしも考えられません。そもそも鑑真など唐僧からこれを師として受戒を受け入れて以降、彼らを敵視するような動機など、少なくとも仏教の教学的な点においては存し得ないと思われます。
(ただし、鑑真が私寺として唐招提寺を創建した際には「後、眞和上唐寺に移住す。人の謗讟 を被る」とあることから、その具体的な理由は今もよくわかっていないないのですが、鑑真に対して反感を持つ僧らが後にも存在していたことは確実です。それは、官位や私寺の建立、その継続のための寺領の寄進など、鑑真に対する帝からの特別な処遇について、当時の僧のあり方から考えると、経済的そして政治的な点における妬みややっかみに基づいた、低俗な中傷であったように思われます。)
例えば、以下に少し述べますが、鑑真と共に来朝した法進は、天平勝法八年〈756〉に鑑真と共に僧綱に任じられていますが、後に賢璟が律師に任じられた際には少僧都としてありました。少なくともその両名が反目しあっていたとは到底思われません。
なお、「普照伝」・『大和尚伝』・『東征伝』にて、鑑真ら唐僧からの受戒を当初拒んでいた旧僧としてその名が挙げられている志忠・霊祐(霊福)・賢璟・善頂・道縁・平徳・忍基・善謝・行潜・行忍の中で、その出自など詳細が今知られている人は賢璟と善謝のみ。また、名前が比較的今も知られているのは忍基です。
賢璟は尾張、荒田井氏出身の法相宗の人で、宝亀五年〈774〉に律師に補任され、同十年〈779〉に少僧都、延暦三年〈784〉に大僧都となり同十二年〈793〉に没しています。室生寺を創建した人であり、また長岡京から遷都するにあたって藤原小黒麻呂など公卿らと共に今の平安京の地を選んだことで知られた僧でもあります。善謝は美濃、不破氏出身の同じく法相宗の人で、延暦九年〈790〉に律師に任じられ、同廿三年〈804〉に没しています。
忍基に関してはその出自等は知られぬものの、旧僧の中でも後に鑑真の門弟となり、唐招提寺講堂の梁が折れる夢を見たことを鑑真の滅度を知らせる凶相であるとして、急ぎかの有名な塑像を作るのに主導的役割を担った人として『東征伝』に伝えられています。
そもそも、先に述べたように、自誓受戒や三聚浄戒を受けることによって人が比丘などに成り得ないことは、印度以来、支那においても極めて常識的なことであり、それは今にいたるまで変わりありません。
戒是佛法壽命。衆生福田。三學依之立。七衆因之成焉。有云。若總受三聚淨戒者。雖不別受比丘別解脱戒而成菩薩比丘性。地持等説。攝律儀戒中有七衆別解脱戒。故淨影破云。此義不然。菩薩戒中雖復通攝七衆之法。一形之中不可竝持七衆之戒。隨形所在要須別受。如人雖復總求出道隨入何地別須起心方便趣求。此亦如是云云 道璿和上同淨影意也。故大小乘一切苾芻皆別得其別解脱戒成苾芻性。
戒とは仏法の寿命、衆生の福田である。三学はこれより立ち、七衆はこれより成じる。ある者は言う、
「もし三聚淨戒〈菩薩戒〉を総受したならば、比丘の別解脱戒を別受せずとも菩薩比丘性を成じる。『菩薩地持経』等に「摂律儀戒の中に七衆別解脱戒が含まれる」と説かれている」
と。しかし、故淨影〈浄影寺慧遠。支那隋代の高僧〉は(そのような主張を)論破して、
「そのような理解は正しくない。菩薩戒の中にもまた通じて七衆の法を包摂しているとは言え、一形〈一つの立場〉で(出家・在家の)七衆戒全てを併せ持つことなど出来はしない。その形〈立場〉の所在に応じて必ず別受しなければならないのだ。それは、あらゆる人が解脱の道を求めたとしても、各々の様々なる境地にあって、それぞれ異なる決心に相応しい方法によって、その道を歩むようなものである。この(三聚浄戒とは別途に律儀を別受しなければならない)ことについても同様である」
と云っている〈『大乗義章』〉。道璿和上〈鑑真以前に渡来し大安寺にあった天台と律に通じた支那の学僧〉も淨影の見解と同様であった。故に大小乗の一切の苾芻〈bhikṣu. 比丘〉も皆、別してその別解脱戒を受けてこそ苾芻性〈比丘性.比丘たること〉を成じることが出来るのだ。
実範『東大寺戒壇院受戒式』(新版『大日本佛教全書』, vol.49, p.26c)
これは平安後期、すでに滅びて無くなっていた戒律を復興するため運動を開始した中川上人実範による言ですが、ここで挙げられているように、隋代の支那の高僧、浄影寺の慧遠は当時からすでにこの点をはっきりとさせており、また鑑真に先駆けて日本に請来されていた道璿もその見解を同じくしていたとされます。
(この点について本題の最澄に関して述べておくと、彼にとって鑑真や道璿がそのような見解を同じくしていたことは、彼の大乗戒に関する主張にとっては非常に都合の悪いものでした。そして、おそらく最澄は天平の昔に何があったかを知っていました。というのも、最澄の主張にとって最も都合の良い筈の『占察経』をその根拠として『顕戒論』において出していないためです。したがって最澄は、後に僧綱との論争において、このあたりのことを避け全く別の典拠をもって論述しています。)
いずれにせよ、日本に仏教が伝来して二百年を経て、ようやく具足戒が伝来されて正統な仏教僧が日本で生み出されるようになり、ここに初めて僧伽が成立。日本仏教における三宝がようやく形成されたのでした。そして国家の制度としても、東大寺など三戒壇いずれかにて、律蔵の規定する諸々の条件を満たした上で具足戒を受けなければ正規の僧(比丘)として認められないことが定められています。
そこでまた必然的に、国家として僧の身分を認証する行政上の制度にも変更が加えられていました。しかし、その変更は悪手であったと官に考えられたようです。
○二月丙戌。治部省言。承前之例。僧尼出家之時。授之度縁。受戒之日。重給公驗。據勘灼然。眞僞易辨。勝寳以來。受戒之日。毀度縁停公驗。只授十師戒牒。此之爲驗。於事有疑。如不改張。恐致姦僞。伏望不毀度縁。永爲公驗者。許之。但其度縁。自今以後。僧者請太政官印。尼者用所司之印。至于受戒之時。省並於度縁末。注受戒年月并官人署名。即以省印印之。其尼於外國受戒者。當所之官。准此行之。承前所授僧戒牒者。惣進僧綱。即送所司。所司計曾。明知不詐。署印其末。然後還授。進盡之期。斟量立限。限内不進。後齎白牒者。不得爲驗。一同私度。若有身亡并還俗者。其度縁戒牒。早令進省。省即年終申官毀之。庶令姦人屏跡。源流自澄。
◯(弘仁四年〈813〉)二月丙戌〈3日〉、治部省が、
「承前〈前例〉の例では、僧尼が出家する時、これに度縁〈得度の許可証〉を授け、受戒の日に重ねて公験〈公的証明書.ここでは受戒の証明書〉を給付していました。(その制度は)拠勘灼然〈身元を調査・証明するのに明瞭であること〉として、真偽を見分け易いものでありました。ところが天平勝宝〈749-757. ここでは鑑真渡来により開始された受具足戒の年、天平勝宝六年のこと〉以来、受戒の日に度縁を破毀して公験を給付することも停め、ただ(戒壇院における三師七証の)十師の(署名が記された)戒牒を授けることをもって、公験としております。しかし、この制度について疑いがあり、もし改正されなければ、おそらく姦偽〈邪な偽り.僧尼の身分詐称〉を生じることになりましょう。伏して望むことには、度縁を廃棄せず、永く公験として下さいますいよう」
と進言してきたため、これを許した。ただし、その度縁について、今より以後は、僧については太政官印を請い、尼については所司〈玄蕃寮〉の印を用いるようにせよ。そして受戒の時には、省〈治部省〉はすべての度縁の末尾に受戒の年月ならびに官人の署名を記し、そこに省印を押印せよ。もし(僧)尼で、外国において受戒した者については、所管の官司が、この方法に准じて行え。(天平勝宝から)これまでの、すでに授けられている僧の戒牒は、すべて僧綱に提出させ、これをまた所司〈玄蕃寮〉に送ること。所司はこれを審査し、明瞭に嘘詐りのないことを知ったならば、その末尾に署印せよ。そうした後に(戒牒をその所有者の僧尼に)還授させるように。提出期間については斟酌して期限を設けよ。もし期限内に(戒牒を)提出せず、後に白牒〈官の署名・押印の無い戒牒〉を用いたならば公験とせず、偏に私度〈私度僧.官許なく出家した者〉と同様の扱いとする。もし(僧尼が)死亡あるいは還俗したならば、その度縁と戒牒は、速やかに省〈治部省〉に提出させること。省は年の終りに官に申告した上でそれを破毀せよ。願わくば姦人〈悪人.ここでは特に悪僧〉が現れることがなくなり、その源流〈仏教.ここでは特に僧伽〉がおのずから澄み清らかとなっていくことを。
『日本後紀』巻廿二 弘仁四年二月丙戌条
(新訂増補『国史大系』普及版, p.122)
これは度縁と公験、そして戒牒という公的証明書に関する、行政上の仕組みについての治部省からの建言です。すでにそのような事例が生じていたためのことかもしれませんが、戒牒だけではあまりに簡略に過ぎたものであって、不正が多発するのを治部省が危惧してのことでした。
度縁(度牒)とは、出家して僧あるいは尼となった者に官が与える許可証で、公験は官許の僧尼であることの公的証明書です。「僧尼令」においては告牒と称されています。そして公験も同じく公的証明書のことですが、ここでの場合は、鑑真渡来以前の僧が得度した後に受戒した際に与えられる、その証明書のことです。しばしば度縁と公験は同じものであると説明されることがあり、実際度縁は公験の一種であるのですが、以上のことからすると、厳密に言うとその初期における度縁と公験とは異なったものです。
この建言は直ちに裁可され、以降は度縁に太政官印を押印し、受戒の際にはこれを公験としてそのまま利用してそこに受戒の日付や官人の署名、そして治部省印を押印するという、二重三重の安全策をとった厳密なものとなっています。
現代日本においても身分証明書など公的証明書や国民保険に関して偽造や不正流用などが跡を絶たず、社会問題の一つとなっていますが、それは当時も同じことでした。そのような不正を防ぐ手立てを官は常に考えなければならず、その時々に法改正がなされています。特に、租庸調など脱税の温床となり得る僧尼の場合、身分詐称や籍の不正流用が多発していたようです。そのような点についても、数多存在する宗教法人や寺社を利用した脱税がそこらで行われている現代と変わりありません。
以上を踏まえた上で、必ず峻別して理解しなければならない非常に重要な点ながら、日本では僧俗問わず、ほとんど混同され捉え違いさられてきたことについて指摘しておきます。
「正式な仏教僧となるためには必ず正規の条件下で具足戒(律儀)を受けなければならない」ということ。それは、そもそも仏教が印度で誕生して以来、その後の各地に伝わっても必ず行われてきた、仏教としての標準であり常識です。今も昔も、そしてその信奉するものが大乗であろうが小乗であろうが関係なく、具足戒を受けて最低限これを護持していなければ、仏教僧を名乗ることは出来ません。
しかし、それと国家がその行政上、人を僧として認定し扱うことは、全く別次元の話です。
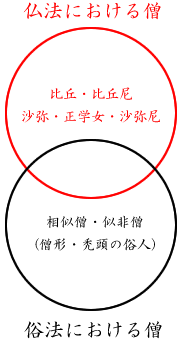
仮に国がその制度上、僧として認定した者があったとしても、それでその者が仏教として正規の僧(比丘)であることには「全く」なりません。俗法でどう規定されようと、それが仏教における僧たることの根拠には全くならないのです。すなわち、俗法において僧とされる人と仏法において僧とされる人とは、必ずしも等しくありません。すなわち「俗法における僧≠仏法における僧」であるわけです。
けれども、それが異なっていては、これは社会的にも宗教的にも種々様々な問題や不都合が生じます。
鑑真渡来以前の旧僧のほとんど多くは、朝廷がその制度上は僧として認定し扱っていた者です。前述のように受戒後に公験を給付する制度があったことから、彼等が何らかの戒をしかも国家の管理下において受けていたことは間違いない。しかし、それは未伝であるため決して具足戒ではなく、したがって仏教からすれば彼等は正規の僧ではありませんでした。
そもそも、仏教僧というものについて厳密に言ったならば、鑑真渡来以前の僧の殆どが誰か比丘の弟子として出家したのでも無かったため、実は沙弥ですらありませんでした。似非僧の弟子もまた、必然的に似非僧となってしまうためです。もっとも、では正しく僧であったと言える者が日本に絶無であったかといえばそうではなく、遣隋使や遣唐使に伴って支那に渡っていた留学僧たち、そして幾人かの渡来僧たちは例外です。
留学僧でもなく渡来僧でもなく、しかし正規の出家をしていたと確実に言える人の一例としては、『東征伝』を著した淡海三船の名を挙げることが出来ます。彼は天平年間、道璿の弟子として出家して元開との法名を得て修学に励んでいました。ところが、天平勝宝年間に勅により還俗させられ、真人姓を賜って入唐の学生に指名されています。結局、それは病を得たために実現していません(『日本高僧伝要文抄』第三)が、おそらく淡海三船は道璿の膝下にあったことから漢語も相当程度話せたのでしょう。しかし、そんな彼等は例外であって、大勢としてはその出家も受戒も非正統ながら、国家からは僧とされていた「相似僧」によって占められてたと言えます。
彼等は、仏教僧としての根拠を欠いた状態ではありましたが、ただ国がそう認めたという理由において僧と称していただけに過ぎません。冒頭示した凝然が「相似」と言っていたのは、そのような事実に基づいてのことです。
その何が問題であるのか。それは僧たる根拠が欠落していることであり、その立場における規律と罰則がなく、また自浄作用も生じ得ないことです。したがってそのような似非僧たる状態は、堕落・腐敗を容易に招くものであり、社会的秩序の点からも大きな問題です。そもそも正統な僧でないのならば、斎会において布施を受ける根拠と権利も無いことになります。そのようでは国を挙げて仏教をその核として信仰し、事ある毎に布施してきた帝や公卿、そし庶民としても、期待する布施の功徳と意義とを失ってしまいます。なにより、国家として「正統では無い」とされるのを、そのまま放置して奉じるわけにはいきません。
そしてまた僧徒としても無戒であって実は正しく僧とは言えないことの自覚が、たとえば先に示した隆尊がそうであったように、すでに一部では確かになされています。そのような問題意識が僧俗の双方にあり、そこでそんないわば歪んだあり方を解消し、その差異を無くすためにこそ鑑真など唐の大徳らが招聘されたのでした。そして鑑真一行の渡来により、ついに俗法における僧と仏法における僧の差異、矛盾が解消され、体制としては等しくなり得るようになったのです。
繰り返しますが、仏教の僧とは、国家ではなく、仏教にて定められた法に則って出家した者です。しかし、ただ出家しただけであれば沙弥といういわゆる見習い身分であるため、正規の僧である比丘となるには、必ず具足戒を規定の条件下で受けなければならない。したがって、たとい国家が認定していなくとも、当時の制度的にそれは考えづらい事態でありますが、正規の条件と方法に依って出家・受戒した者であれば、その人は仏教僧です。
これは現代日本においても全く同様に言えます。たとえば、ある者が属する宗派から僧であると認定され免状などを取得し、自身も「坊さん」であると自認・自称し、社会も坊さんであると認知していたとしても、しかしその者は仏教僧ではありません。何故か。それは現今の日本仏教には宗派が多数存しているとはいえ、もはや僧を生み出す仏教としての組織すなわち僧伽やその授戒の伝統も完全に失われているため、仏教の僧になることはどの宗派に属していようとも決して出来ないためです。
すなわち、「日本の坊さん≠仏教僧」という図式でいうとわかりよいでしょう。
日本の坊さんが東南アジアや南アジア、あるいはチベット仏教圏などを尋ねた際、率直に言ってそこらのニイチャンやオッサンの格好をしておきながら平然として「私も僧侶だ」などと恥ずかしげもなく言ったところ、鼻で笑われて僧として全く扱われず、帰国後それに憤慨して「彼の国の僧は高慢で鼻持ちならない」などと愚痴をこぼしたり批判したりする者が度々あります。しかし、それは以上の理由から至極当然のことです。実はそれと似たようなことは中世、南宋代の支那に渡った道元が経験しており、彼はそこで一悶着おこしています。道元は比叡山にて梵網戒のみ受けただけの人であったため、当然ながら支那の禅僧から比丘として認められず小僧(沙弥)扱いされて入衆を拒絶されたのでした。
(これを現代の一類の人々は以て差別であるとか不合理な教条主義に基づく蛮行であったなどと断ずるのですが、それは仏教僧として、その組織として当然の措置です。しかし結局、道元は無戒であるのに比丘として自身を扱えとの主張を押し通し、支那の禅寺はやむなく外国の留学僧として特別扱いし受け入れています。)
現代、日本仏教にもはや正規の仏教僧が全く不在であることは、比較的よく他の仏教国に知れ渡っています。どこかの宗派やその一部団体が公式行事として、彼の地に何らかの名目で多額の寄付や表敬訪問の類をなす場合には、日本の坊さんであっても辛うじて儀礼的に「特別扱い」されることもあります。しかし、彼等は内心、日本の坊さんのことを甚だ軽蔑して俗人と見なしており、同じ仏教僧として遇すことは決してありません。
明治維新以降、仏教も僧も国家の庇護や管理を離れているため、それぞれの宗派が独自に僧であると認定し、往古の制度である「僧籍」の模倣をしてその免状を発行していますが、それを得たからといって人は仏教僧となったことの証明にも根拠にもなりません。現代ともなると、往古に「相似」や「名字」といわれた似非僧にすら及ばないものとなっています。
さて、日本仏教において「俗法における僧≠仏法における僧」であったのを、長きに渡る僧俗の努力によって「俗法における僧=仏法における僧」または「俗法における僧≒仏法における僧」としたのが鑑真の渡来によって確立された戒壇院における具足戒の受戒制度でした。ところが、それをまたひっくり返して鑑真以前に戻してしまおうというのが、実は最澄による大乗戒問題です。
最澄は単純にそのような先祖返りを意図的に行っただけではなく、その主張が制度化されたことにより、ある宗派では僧であっても他宗では僧としては認めない、という前例をここで作っています。
これはどういうことかというと、現在、日本の各宗派ではそれぞれ僧と自称させる仕組みを持っていますが、例えばAという宗旨で僧としてやっていた某という者が、何らかの事情で異なるBという宗旨に転向しようとしても、Bではその某がどれほど長い経験を有していたとしても僧として受け入れることは決してありません。某は必ず改めて得度の最初から行うことを要求されるでしょう(同一宗旨内の「転派」の場合は話が少々異なる)。
これは制度上の話ですけれども、その故にその根本的なあり方として表れており、それはもはや仏教における「僧とは何か」の規定に従っているのではなく、ただそれぞれの派閥の内のみで通用する独自の仕組みにのみ従っているということであります。すなわち、異なる宗旨宗派の者が席を同じくした時はその外交上、僧であるとして儀礼的に対しはしますが、根本のところでは互いに僧であるとは見なしていません。
そのようなあり方は、最澄の天台宗において始まり、それがやがて比叡山から派生した亜流の宗派に引き継がれ、さらに現代の各宗派すべてにおいて見られることとなっています。それはもはや、互いに異なる宗教であると見なしあっているようなものです。事実、その宗派のいくつかには、仏教という看板を挙げてはいても全く違う宗教にしか思えぬ教義を構築し、そのあり方もおよそ仏教から程遠いものとなっています。今、そのようなあり方がそもそもおかしなものであることに疑問を持つものは実に少なく、むしろ当然のことであると無批判・無反省に考える者こそ多くあります。
現代、以上に挙げたいくつかの点を指摘すると、たちまち「傲慢である」とか「偉そうに言うな」・「失礼であろう」などといった感情的な反論が湧くのですけれども、これはそのような「傲慢」であるとか「失礼」などといった類の話では全くなく、また「本物のぼーさん」などという理念的・観念的なことを言っているのではなく、仏教の規定に基づいた、その事実に関する話です。
最澄の大乗戒問題を理解するためには、この点を確実に把握し、今の日本人の多くが持つ「坊さん観」というべきものを棄てなければ、当時その何が問題であったのかも、後代生じた様々な問題が何故起こったかも理解することは出来ません。