「国宝とは何物ぞ。宝とは道心なり。道心あるの人を名づけて国宝となす」、この『山家学生式』の冒頭は、国文学あるいは日本古代史など学んだ人には比較的よく知られたものと言えるでしょう。
國寶何物。寶道心也。有道心人。名爲國寶。故古人言。徑寸十枚。非是國寶。照于〈千の誤写。あるいは千を于とした誤読〉一隅。此則國寶。古哲又云。能言不能行。國之師也。能行不能言。國之用也。能行能言。國之寶也。三品之内。唯不能言不能行。爲國賊。乃有道心佛子。西稱菩薩。東號君子。惡事向己。好事與他。忘己利他。慈悲之極。釋教之中。出家二類。一小乘類。二大乘類。道心佛子。即此斯類。
国宝とは何でありましょうか。宝とは道心であります。道心ある人をこそ国宝というのであります。故に古人〈斉の威王〉は言っております、「(兵車の前後を照らしだす)径寸十枚〈直径3cmの鏡のように輝く宝玉十枚〉など国宝ではない。照千一隅、それこそまさに国宝である」と。古の哲人〈牟子〉はまた「よく語ることが出来てもよく行うことが出来ない者は、国師である。よく行うことは出来ても語ることが出来ない者は、国用である。よく行なってよく語り得る者は、国宝である。これら三種三様の人があるが、しかし、ただ語ることも行うことも出来ないような者は、国賊である」とも言っております。
すなわち、道心ある仏教者をして西〈印度〉では菩薩と称し、東〈支那〉では君子と号します。悪しき事柄は自らに向かわして好ましき事柄を他者にあたえ、己を忘れて他を利することは、慈悲の極みというものです。釈尊の教えにおいて、出家者には二類の別があります。一つは小乗の類、二つには大乗の類であります。そこで、この(忘己利他の)人こそ、この(大乗の)類であります。
最澄 『山家学生式』(『伝教大師全集』, vol.1, p.279b)
この一節の中にある「照千一隅」は、現代の天台宗が「お祖師様のお言葉」として「一隅を照らす」などと読み世間向けの宣伝文句としているものであって、「国法とは何物ぞ」の一節に並んでよく知られています。そしてその典拠として、『山家学生式』を実際に読んだことはなくとも、その題目だけは比較的世に知られたものとなっています。

ところが、実は最澄は「一隅を照らす」などと書いても言ってもいません。そのような事実が社会に明らかにされたのは今から五十年ほど前、昭和四十年になってからのことです。それは学者であり真宗寺院の住職でもあった薗田香融、および天台宗の木村周照によってなされたものでした。
「一隅を照らす」とは、『山家学生式』の冒頭の一節にある「照千一隅」を「照于一隅」と恣意的に読んだことによる訓であって完全な誤読、というよりもはや捏造とすら言える読みです。何故ならば、最澄の自筆にはあまりにもはっきりと「千」と書かれているためです(右図参照)。
最澄真筆が残されており、往古は極限られた者のみであったろうとはいえ、いくらでもそれを目にする機会があったはずの天台宗はしかし、これはいつからのことからはわかりませんが、その原本を無視して従来なんとなく「照于一隅」すなわち「一隅を照らす」と読み継いでいました。近代、大正十五年(1926)に編纂され発刊された『伝教大師全集』には当然「学生式」が収録されていますが、それは何故か最澄を真筆を全く差し置いて、江戸期・明治期の版本を元にしたものであって、やはり「照于一隅」とされています。
もっとも、光定の『伝述一心戒文』に載せる「学生式」の一節は、「千」でも「于」でもなく「十」とされています。往古の写本・刊本に誤写や誤読、あるいは脱字があることはある意味当たり前のことですが、しかし、これについては真筆が現存している以上、まことに杜撰な編纂であったと言わざるを得ません。
いうまでもなく、「千」とは文字通り数字の千であって、しばしば具体的な数ではなく漠然と「多く」・「多数」を意味する語。そして「于」とは、「~に於いて」・「~で」・「~を」・「~より」などを意味する助字(前置詞)です。しかし、もし「一隅を照らす」と言いたい場合には「于」は不要であり、「照一隅」のみで事足ります。すなわち、「照于一隅」では漢文として誤ったものとなり、そんな単純な誤りをこの実に短い一句において最澄がするとは考えづらいことです。
両名によって提起されたこの問題は当時の天台宗を騒がすこととなっています。なにより当時、天台宗は世間向けのプロパガンダとして「一隅を照らす運動」なるものを開始していました。ここから現代日本的、あるいは昭和的とでも評すべき滑稽な、ある意味で悲劇的な論争が展開されています。宗として久しく「照于一隅」と読んできた手前、そしてまた世間向けの運動を開始してしまっていたため、その誤りであることを容易く受け入れられなかったのでしょう。しかし、そのような指摘がなされてしまった以上は無視するわけにもいかない。そこで「照千一隅」説に対抗すべく、御用学者らが動員されて「どちらが正しいのか」が盛んに争われています。
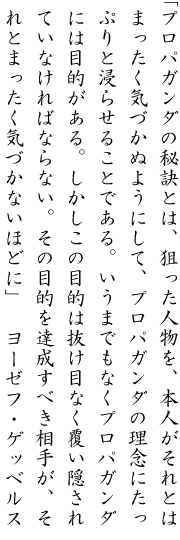
客観的にはどう考えても、いや、その筆順や運筆をじっくり分析するまでもなく、どう見ても「千」であることは一目瞭然で疑いないのですが、御用学者等は「いや、そうではない。千のように見えるかもしれないが実は于だ。最澄は于を千のように書く癖があった。これは于だ」と強弁するなど、実に奇妙で無理筋な反論を次々展開しています。そしてなんと結局、「やはり『照于一隅』すなわち『一隅を照らす』と読むのが正しい」と、実は最初からそう決めていたのであろうと甚だ疑われるものでありますが、天台宗として会議まで開いて公式に決定してしまったのでした。
当時「照于一隅」真正説に立って展開された御用学者等の論説を、今あらためて眺めてみたならば噴飯やむなしといったもので、あれを笑えないならばちょっとどうかしているとすら言えるほどです。学者にいくらか議論させ、しかし最後は会議を開いて公式に「これは于だ」などと決定したからと言って、最澄が明らかに「千」と書いている事実が変わるわけでは勿論ありません。
しかし、彼等にとっては「どう見ても千という事実」より「会議で『これは于だ』と決定された事実」こそ重要であって、もはやこれを公的に疑問視あるいは再度問題提起することは許されなくなっています。そんなことをするとすでに開始されて久しい「一隅を照らす運動」の欺瞞が露呈し、破綻してしまうためです。
そのように、偽を真であるとどこまでも強弁して平然とする精神構造、そしてそれを良しとする社会・組織の構造が、昭和初期から悲劇を生み出してきたものとまるで同じであることを思うと、実に暗澹たる気持ちになります。それは、大東亜戦争中、自身らの時局の展望や作戦立案が誤りであったことをどこまでも認めず、あるいは誤りであると知りながら将兵に決行させ、しかしその責任はとらず精神論を振りかざして責任転嫁を繰り返した軍参謀のようであり、また戦後の官僚や大企業の経営者や重役らが繰り返した種々の社会や自然への悪影響への結果責任など一切取らずにきた種々の欺瞞・理不尽のようであって、まさに昭和的な、多く悲劇を生み出し続けてきた喜劇です。
そのような精神でもって一体どこの何を「照らす」というのでしょう。
(まったく本件とは関係の無い話ではありますが、しかし構造として似たような、いや、それ以上に酷い出来事が真言宗において近年生じていたことを、この話は想起させます。空海が出生したのは伝統的に讃岐の現在善通寺がある場所であったとされてきました。しかし現代、文献学者である武内孝善により、空海は讃岐では生まれても育ってもおらず、母方の里である奈良で生まれ育ち、だからこそ高度な教育を受け得たであろうことを諸史料の極緻密で丁寧な考証によって「学術的に」論じられています。それは実に説得力のある、高い確度でその説が正しいであろうと人に首肯させるものでした。ところが、善通寺はそのような「学説」を唱えた武内に激怒。最終的には武内に土下座で謝罪させるという、信じがたい暴挙に至っています。善通寺の無知蒙昧ぶり、そのあまりの横暴と厚顔無恥さには呆れるどころか戦慄さえ覚えさせられます。その程度の強弱があるとはいえ、どちらも似たような精神構造を有しているからこそ生じた事態であると言わざるを得ません。)
それ以来世間の人は、その典拠とされる『山家学生式』など一度として直接読むこともないまま、そもそも現代社会においてこれを読む必要性などまったく無く、仮に直接読んだとしても普通はまるで意味不明の語の羅列に過ぎないでしょうが、恣意的誤読である「一隅を照らす」という現代の天台宗が宣伝文句とした言葉に踊り、踊らされています。そして、それを個々がさらに浪漫仏教的に解釈し、「最澄のすばらしいお言葉」などと信じて言うに至った者もずいぶん出来上がりました。
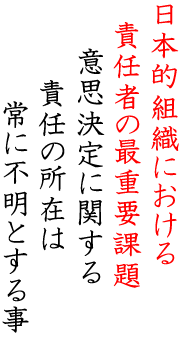
また一方、これについて一騒動あったことを知り、「一隅を照らす」はやはり誤りに違いないと考えている者もおそらく多くあると思われますが、その大体が口をつぐんで静かにしています。それが天台の門徒であるならば、これについて何か言えば逆に不利益を被りかねないが為のことでもあるのでしょう。だとすれば、それもなんとも昭和的、いや日本的な振る舞いです。
あるいはまた、それまで「一隅を照らす」なる天台宗の言葉に踊らされ、なんとなく浪漫的に理解して好み、あまつさえ座右の銘にすらしてしまっていた人が、実は「照千一隅」が正しいことを知った場合には、非常に滑稽でまた憐れとすら思えることを言い出す場合がしばしば見られます。
自らが好み用いてきた「一隅を照らす」が誤読であってそんなことを最澄は書いておらず、正しく読んだ場合には全く意味が違ったものであったことを認めることが出来ない。いや、もはやその内容がどうこうではなく、自分が誤ったものを長年信奉してきたという事実を認めることが出来ないのでしょう。実際、そういう者のほとんど多くが後期高齢者であると思われますが、呆れたことに「そのいずれの言葉も伝教大師様の言葉として受持し伝えればよいのでは?」であるとか、「どちらも深い意味のある尊い言葉だ」などといった諦めの悪いことを言い出しています。
実に失笑を禁じ得ない。まこと醜く老いた、卑しい精神の発露でありましょう。
「老い」とはまさに変化そのものです。しかし、精神的に老いた者はまったく皮肉なことに変化を好まず、変化に堪えることが出来ずに眼をつぶり、耳を塞ぐか、逆にがなり立てて他の声を消し去ろうとするようです。それはまさに老醜というべきものです。「山高きが故に貴からず。樹あるを以て尊しとす」。歳を重ねても智恵は重ねることは出来なかったのでしょう。どこまでも詮無い話であります。
「一隅を照らす」とは誤読に基づく、どこまでも虚偽の説であることは明白であるとして、では最澄自身が実際はそう記していた「照千一隅」が意味するところは何であったか。
それは八世紀の唐代の天台宗の学僧、 湛然(妙楽大師・荊渓和尚)が著した『止観輔行伝弘決』(以下、『弘決』)にある一節の趣意を引用したものでした。湛然は、最澄が唐の天台山で受学した道邃の師で、智顗を初祖とする天台宗第六祖として挙げられる人です。智顗による『法華玄義』・『法華文句』・『摩訶止観』のいわゆる天台三大部を初めとしたその著作の多くを注釈した人であり、その中で『摩訶止観』を注釈したのが『弘決』です。
天台三大部は天平勝宝の昔、すでに鑑真らによってもたらされて東大寺や唐招提寺にありましたが、『弘決』は最澄が初めて日本にもたらした典籍です。そして最澄が引いたのは、『摩訶止観』巻五にある「自匠匠他、兼利具足す。人師國寶、此に非ずんば是れ誰ぞ」という一節を注釈した、『弘決』における以下の一節でした。
自匠等者。匠者成物也。器之工師也。明自他功成。若行解不周自他咸失。故大師與吉藏書云。若有解無行不能伏物。有行無解外闕化他。人師等者歎也。行解具備堪爲人師。是國之寶。後漢靈帝崩後。獻帝時有牟子深信佛宗。譏斥莊老著論三卷三十七篇。第二十一救沙門譚是非中。立問云。老子曰。知者不言言者不知。又云。大辯若訥。又曰。君子恥言過行。設沙門知至道何不坐而行之。空譚是非虚論曲直。豈非徳行之賊耶。答。老亦有言。如其不言吾何述焉。知而不言不可也。不知不言愚人也。能言不能行國之師也。能行不能言國之用也。能行能言國之寶也。三品之内唯不能言不能行。爲國之賊。今云自匠匠他。故云國寶。牟子又云。懷金不現人。誰知其内有瑋寶。披繍不出戸。孰知其内有文彩。馬伏櫪而不食則駑與良同群。士含音而不譚則愚與智不分。今之俗士智無髦俊。而欲不言辭。不説一夫而自若大辯。若斯之徒坐而得道者。如無目欲視無耳欲聽。豈不難乎。故今自行滿須以教利人。譬能説行堪爲國寶。如春秋中齊威王二十四年。魏王問齊王曰王之有寶乎。答。無。魏王曰。寡人國雖爾乃有徑寸之珠十枚。照車前後各十二乘。何以萬乘之國而無寶乎。威王曰。寡人之謂寶與王寶異。有臣如檀子等。各守一隅則使楚趙燕等不敢輒前。若守寇盜則路不拾遺。以此爲將則照千里。豈直十二乘車耶。魏王慚而去
「自匠(匠他)」等 (の『摩訶止観』にある一節)について、匠とは物を作り上げる者である。器の工師である。(ここでは)自利利他の功を成就することを明かしたものである。もし、行と 学解 とを等しく満足していなければ、自利利他のいずれも得ることは出来ない。したがって、大師が吉蔵に送った書には、「もし学解があっても行が無ければ、物を伏すことは出来ない。行はあっても学解が無ければ、外に他を教化することを闕く」とある。「人師(国宝)」等(の『摩訶止観』にある一節)は、(そのような人を)讃歎したものである。行と学解とのいずれも備えてこそ、人師とするに堪える。それが国宝である。
後漢の霊帝が崩御した後の献帝の時、牟子〈牟融〉という者があって深く仏宗を信じ、荘老〈老荘思想.道教〉を譏り斥けて、論三巻〈『理惑論』〉を著した。それには三十七篇あって、その第二十一において沙門の是非を語ってこれを擁護する中に問を立て、(仏教およびその沙門を批判する者に)このように言わせている。
「老子は『知る者は言わず。言う者は知らず』と言い、また『大弁〈優れた弁士〉は訥〈口下手〉なるがごとし』〈『老子』〉と言った。さらに(孔子は)『君子は言いて行いに過ぐることを恥ず』〈『論語』〉とも言われている。もし沙門が至道を知る者であるならば、どうしてただ坐してこれを行じないのであろう。(牟子のような仏教を奉じる者が)空しく(道についてその)是非を語り、虚しく曲直を論じることは、どうして『徳行の賊』でないことがあろうか」
と。(牟子は)これに対し、
「老子にもまた言葉〈『老子道徳経』五千言〉がある。もしその言葉がなければ、私もまた何を述べることがあろう。(道を)もし知って言わないのであれば、それも良い。何も知らず何も言わないのは愚人である。(『荀子』にあるとおりである、)『よく語ることが出来、しかし行うことが出来ない者は国の師である。よく行っていても、しかし語ることが出来ない者は国の用である。よく行い、よく語ることが出来るのは国の宝である』と。それら三品のうち、ただ語ることも出来ず行うことも出来ないのを国の賊という」
と答えている〈『弘明集』(T52, p.5a)〉。今、(『摩訶止観』に)「自匠匠他」とあるが、そのようなことからそれを「国宝」と言うのだ。牟子はまたこうも言っている。
「黄金を懐中にしまって人に見せることがなければ、誰がその内に珍宝があることを知り得るであろうか。繍を着ていても家を出ることがなければ、誰がその内に文彩があることを知り得ようか。馬が厩に伏したままでろくに食べることがなければ、駑馬でも良馬でもその群を同じくしたままである。士大夫が音を含んで語らないならば、その人が愚人であるか智者であるかは分からない。今どきの俗士は、その智が髦俊〈群を抜いて優れた人〉でなくとも何も言わず語りもしないでいようとしている。誰一人として説かないでいながら、自らあたかも大弁のように振る舞っている。そのような徒などが『坐して道を得る』と言うことは、目が無いのに視ようと求め、耳が無いのに聴こうと求めるようなものである。なんとも不可能な話ではないか」
と〈該当する一節は『弘明集』に収録された『理惑論』には無い〉。したがって今、まず自らの行を満たし、(その後に)教導して他の人を利すべきである。(そしてそのように、)よく説き、行う者こそ国宝とするに堪えることを、(「自匠匠他」と)譬えているのだ。
春秋戦国時代、斉の威王在位二十四年の時、魏王〈恵王.恵成王〉が斉王に尋ねた。
「王には宝はございますか?」
(斉王は)答える。
「ありません」
そこで魏王が、
「寡人〈王侯貴族などが自らをへりくだっていう一人称〉の国には、(貧しく小さいとはいえ)しかし径寸の珠〈直径3cmの鏡のように輝く宝玉〉十枚があります。それは兵車の前後を照すことそれぞれ十二車にも及ぶほどです。一体どうして(斉ほどの強大な軍事力を誇る)万乗の国であるのに宝が無いなどと言われるのでしょう」
と言うと、威王は、
「寡人が宝というのは魏王の言われる宝とは異なったものです。(寡人には)檀子等のような家臣があってそれぞれ一隅を守り、それによって楚・趙・燕等(の他国)は容易に攻め込んで来ることはありません。そして盗賊を取り締まったことにより、路に(誰かが)落とした物を(我が物にしようと)拾うことすらなくなりました。その家臣たちを以て(宝であると)し、それは(国土の)千里を照らしております。どうしてただ十二乗ばかりの車(を照らすような珠が宝)でしょうか」
と答えた。すると魏王は(自らの言葉に)慚じて去った。
湛然『止観輔行伝弘決』巻五(T46, p.279b)
当時、南朝頃から随そして唐代にかけ、牟子の『理惑論』は儒家や道家または神仙思想に対する非常にすぐれた護教の書として僧徒によく読まれ引用されており、湛然もまたここで引用しています。もっとも、湛然は『弘決』において、牟子が「荘老(老荘)」すなわち老子と荘子の思想を斥けたかのように言っていますが、それは誤読というものです。牟子は『理惑論』において決して老荘を偏に排してなどおらず、むしろ仏教と併せて信奉しており、後漢当時に老荘と神仙思想が習合して無闇に引き合いに出されていたその言葉の真意を糺そうとしているのみです。
(『理惑論』については別項「牟子『理惑論』」にてその解題と原文、そして対訳を示している。参照のこと。)
なお、湛然が引いた『理惑論』の中でいわれる「能言不能行國之師也。能行不能言國之用也。能行能言國之寶也。三品之内唯不能言不能行。爲國之賊(よく言て行うこと能わざるは国の師なり。よく行て言うこと能わざるは国の用なり。よく行いよく言うは国の宝なり。三品のうち、ただ言うこと能わず行うこと能わざるを、国の賊となす)」の一節は、牟子が『荀子』を引用して言ったものです。
口能言之。身能行之。国宝也。口不能言。身能行之。国器也。口能言之。身不能行。国用也。口言善身行悪。国妖也。
口のよく之を言い、身の能く之を行うは国の宝なり。口の能く言わざるも、身の能く之を行うは国の器なり。口の能く之を言うも、身の能く行わざるは国の用なり。口に善を言い、身に悪を行うは国の妖なり。
『荀子』大略 第二十七
そしてまた、湛然が牟子の『理惑論』を援用した後の、斉の威王に関する下りは司馬遷『史記』の故事を引いたものでした。
二十四年、與魏王會、田於郊。魏王問曰、王亦有寶乎。威王曰、無有。梁王曰、若寡人國小也、尚有徑寸之珠、照車前後各十二乘者十枚。奈何以萬乘之國而無寶乎。威王曰、寡人之所以為寶與王異。吾臣有檀子者。使守南城。則楚人不敢為寇東取、泗上十二諸侯皆來朝。吾臣有肦子者。使守高唐。則趙人不敢東漁於河。吾吏有黔夫者。使守徐州。則燕人祭北門、趙人祭西門、徙而從者七千餘家。吾臣有種首者。使備盜賊。則道不拾遺。將以照千里。豈特十二乘哉。梁惠王慚、不懌而去
(斉の威王)二十四年の時、魏王〈恵王.恵成王.魏が梁を都としたことから梁王とも〉と会って、郊外で狩りを楽しんでいた。魏王は、
「斉王には宝がありますか?」
と尋ねた。すると威王は、
「ありません」
と言う。梁王〈魏王.恵王〉は、
「寡人〈王侯貴族などが自らをへりくだっていう一人称〉の国は小さいものではありますが、なお径寸の珠〈直径3cmの鏡のように輝く宝玉〉で兵車の前後を照らすことそれぞれ十二車にも及ぶものが十枚あります。一体どうして(斉ほどの強大な軍事力を誇る)万乗の国でありながら、宝が無いなどと言われるのでしょう」
と尋ねた。そこで威王は、
「寡人が宝とするのは魏王と異なります。私の臣下に檀子という者があり、南城を守らせております。すると楚人は、あえて(斉のある)東に侵略してきません。そこで泗上〈泗水の沿岸〉の十二諸侯〈春秋時代の有力国すべて〉は、皆来朝いたしました。また私の臣下に肦子〈孫子.孫臏〉という者があり、高唐〈現在の山東省斉河県西部〉を守らせております。すると趙の人は、敢えて東にある河にて漁をしなくなりました。また私の官吏に黔夫という者があり、徐州を守らせております。すると燕の人は(斉の)北門で祭り〈祭祀.平伏の意を表すこと〉をし、趙の人は(斉の)西門で祭りをして、移住し(私の国の民として)従うようになった者が七千余家にのぼります。そして私の家臣に種首という者があり、盜賊を取り締まらせました。すると道に落ちた物を(我が物にしようと)拾うことも無くなりました。(このように、私に従う優れた家臣という宝は)まさに千里を照らすものであります。どうしてただ十二乗ばかり(を照らすような珠が宝)であるでしょうか」
と答えたのだった。梁の恵王は(みずからの言葉と考えに)慚じ入り、気落ちして立ち去った。
司馬遷『史記』巻四十六 「田敬仲完世家」第十六
この故事の大要は、斉の威王が魏の恵王から宝について問われた時、「物理的に強い光を放つ宝玉など我が国では宝とは言わない。我が国では、(檀子のような優れた)家臣それぞれが(外患内憂に対して)己の持場・領分を守っており、それにより国土の千里が照らしだされているのであって、そのような臣民こそ我が宝である」と答え、その答えを聞いた恵王は恥じ入るばかりとなった、というものです。
最澄は、湛然の『弘決』にある一節に倣い、それは結局『理惑論』および『史記』の孫引きであって一つとして「最澄サマのお言葉」などでは無いのですが、まず「国宝とは何物ぞ。宝とは道心なり」と言って、宝とは「道心」であると言い換え、「道心ある者を印度では菩薩といい、支那では君子という」としています。
そして、『弘決』にある「徑寸之珠十枚」を「径寸十枚」、「各守一隅 《中略》 以此將則照千里」を「照千一隅」とそれぞれ省略し、文辞を変えて用いています。そのようにした最澄の意図は、「径寸十枚」と「照千一隅」とを対句にして調子を整えているのであり、その意を汲めば「照千一隅」を無理やり読み下す必要はありません。それはどういうことかを再度以下に示せば明瞭となるでしょう。
徑寸十枚。非是國寶。照千一隅。此則國寶。
径寸十枚、これ国法にあらず。照千一隅、これ則ち国法なり。
最澄 『山家学生式』(『伝教大師全集』, vol.1, p.11)
このように、わざわざ最澄が「各守一隅 《中略》 以此將則照千里」という一節を約め、「照千一隅」としてたのは「径寸十枚」の対句としてこのように読ませたかったからに違いありません。これをわざわざ「千の一隅を照らす」などと読むのは最澄の意を汲んだものでもなくまた修辞として美しくない。ましてや「一隅を照らす」などと恣意的に誤読するなど笑止千万。
一応念のため言っておくと、この「一隅」とは一角、いわば一つの領分のことであり、それぞれ家臣らがその領分を守って睨みを効かせたならば、外敵から侵略されることもなく、また国内の治安がよくなって隅々まで君主に依る治が行き渡ることを「照」としたものです。
最澄はしかし、『弘決』にある故事をそのままの意味で用いてはいません。これが最も肝心な点ですが、最澄がこの故事を用って言わんとしたことは、「その道心ある者とは菩薩のことであるけれども、日本において正しく菩薩と言い得るのは我が天台宗の僧だけであり、これを国が重用して国土に満たせば、その隅々まで陛下の御威光で照らされて聖朝安穏なること間違いなし」というほどのものです。しかし、その当時はいまだ天台の僧(年分度者)であっても三戒壇における受具足戒が行政制度化されているために「大類」とは言い難いものであるから、その実現のために法を改正して欲しい、というのでした。
「照千一隅」をどう読むかなど所詮、文辞上の些末なこと。しかし、これを「一隅を照らす」などと誤読することは、そのような汲むべき最澄の主張の核心をまったく読み取らず、はぐらかしたものとなります。「照千一隅」を為し得る臣下、道心ある菩薩は私最澄の天台宗の門徒のみである。そのような主張をさらに具体的に、より強調しているのが前項でも示した続く一節です。
今我東州。但有小像。未有大類。大道未弘。大人難興。誠願 先帝御願。天台年分。永爲大類。爲菩薩僧。然則枳王夢猴。九位列落。覺母五駕。後三増數。
今、我が東州〈日本〉には、ただ小像〈小乗に類した教え。南都六宗を卑下し腐した語〉のみがあって、いまだ大類〈真の大乗。最澄は自身の天台宗をのみそう見なした〉がありません。大道がいまだ広まらないでいるならば、大人が現れることは難しいでしょう。誠に願わくば、先帝〈桓武天皇〉の御願でもあった天台宗の年分度者をもって、以降は大類の僧とし菩薩僧とされんことを。そうすれば、枳王〈訖哩枳王〉の夢に現れた(十匹の)猿のうち九匹〈乱暴狼藉を働く邪悪な猿.最澄はこれと南都の諸宗に類比した〉はまたたくまに追いやられ、文殊菩薩の(羊乗行・象乗行・月日神通乗行・声聞神通乗行・如来神通乗行という)五つの籠のうち、(菩薩乗であって無上正等正覚を得ることが定まっている)後の三つは、その数をいや増すことになるでしょう。
最澄 『山家学生式』(『伝教大師全集』, vol.1, p.11)
ここで最澄がいう「枳王夢猴。九位列落」は、『守護国界主陀羅尼経』巻第十にある説話に基づいたもので、それは要するに「天台宗以外は小乗であり、その僧らは堕落し尽くして国に害を為す粛清排斥すべき悪しき猿である」という、南都の他宗を糾弾し、甚だしく中傷するものでした(詳細は本文の脚注を参照のこと)。
最澄は嵯峨天皇へ上奏した『山家学生式』の冒頭において、まず自宗を称揚し、続いてそのような過激な文言をもって、他宗をもはや批判などでは無くむしろ誹謗しているのです。その攻撃的な文言の裏には、前項で述べたように、自宗の年分度者となった徒弟のほとんどが法相宗に離散、最澄の表現でいうと「相奪」されていたことへの恨みがあり、早くも衰亡しようとする自宗に対する焦りがあります。
このような最澄の意図は、従来まるきり無視され、ただ「国法とは何物ぞ」の一節だけ取沙汰されてきました。
それが平安の昔に漢文で書かれ、しかも種々の漢籍からの引用を以てした迂遠なものであり、漢文にしろ仏教にしろその素養をほとんどまったく失っている現代人にそれが理解できず、全然ピンとこないのもやむを得ないことではあるでしょう。また、これが実は最澄から南都六宗への誹謗であり、彼の強い憤りに基づいたものであったといわれても、前項に示したように、従来のほとんど多くの歴史学者や仏教学者などの歴史的見方や評価が思想的に偏り、甚だズレたものが多く、彼らがなしてきた言説とあまりに乖離した見方を提示されても混乱するのも無理はありません。
そしてまた、世間体が著しく悪くなるため、最澄がそのように自宗を称揚して他宗を謗った文脈にある一節という事実は明らかにしたくない、という現代の天台宗の意図もあるのでしょう。
けれども、そのような内容と背景をもつ一節であるのにも関わらず、いや、だからこそかもしれませんが、これをただ「一隅を照らす、これ則ち国宝なり」などという誤読に基づくホンワカ・フワフワした言葉に注目させ誤魔化してしまったのです。これではもう普通の人は浪漫的になにやら意味ありげで奥ゆかしい言葉のように読んで受け取るしか他ありません。
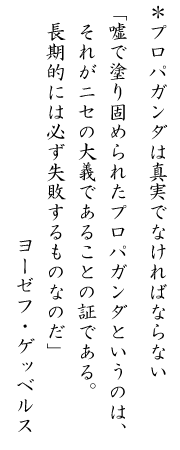
しかし、それはまず文章としておかしく、また最澄の言わんとしたことなど全く伝えられておらず、まるで違った「お話」とされたものです。しばしば日本仏教の諸宗は「祖師無謬説」などと揶揄されるように、「お祖師様のお言葉」なるものを金科玉条にし、仏陀釈尊の言葉をうっちゃってまで崇め奉ることが普通に見られます。ところが、これはその「お祖師様のお言葉」をも手前勝手に捻じ曲げて変え、当然その意図も完全に無視しているのですから始末に負えません。
その言葉自体には意味も真実も無い。けれども、結果として何らか好ましいイメージが付帯される。そのような事態を意図的に狙ってすることは、世間にては別段珍しいことではない。現代のテレビや新聞・雑誌、インターネットの中で行われている商品の広告などまさにそれであります。販売元も広告代理店も、それが実は中身などまるで無いイメージ(妄想)、あるいはその実際からすれば全くの欺瞞であったとしても、それで消費者の購買行動につながれば何であろうが良い、といった次第なのでしょう。
人の無知や恐怖心に漬け込み、自らの利益を得るために誘導・扇動しようとする手口は、何も恐怖の独裁者やカルトの教祖だけが行っていることではなく、我々が日々に接する企業などによる宣伝・広告で普通にみられることです。
それは、ただその真意など理解出来なくとも、とりあえず耳に心地よく聞こえる文句だけ切り取って繰り返してさえおけば、人はそれでなんとなくわかったつもりで済ましてしまう、といういつまでも変わらぬ世間の傾向を利用したものです。けれども、そのような欺瞞に基づいた宣伝は、短期的・即物的には利潤をもたらすかもしれませんが、決して最終的に良い結果をもたらすことはない。それが元で大きな損失、災いをすらもたらすことがある。
ところで、最澄が「国宝とは何者ぞ」などと言い、『弘決』から引用してその趣を帝に述べるその着想となった可能性のある書があります。それは先程から幾度か引用してきた日本の正史、『続紀』です。
癸丑。爲讀金光明㝡勝王經。請衆僧於金光明寺。其詞曰。天皇敬諮四十九座諸大徳䒭。弟子階緣宿殖嗣膺寶命。思欲宣揚正法導御蒸民。故以今年正月十四日。勸請海内出家之衆於所住處。限七七日転讀大乘金光明最勝王經。又令天下限七七日。禁斷殺生及斷雜食。別於大養德國金光明寺。奉設殊勝之會。欲爲天下之摸。諸德䒭或一時名輩。或萬里嘉賓。僉曰人師咸稱國寶。所冀屈彼高明隨茲延請。始暢慈悲之音。終諧微妙之力。仰願梵宇増威。皇家累慶。國土嚴淨。人民康樂廣及羣方綿該廣類。同乘菩薩之乘並坐如來之座。像法中興實在今日。凢厥知見可不思哉。
(天平十五年〈743〉正月)癸丑〈13日〉、『金光明最勝王経』を読ませる為に、衆僧を金光明寺〈金鐘寺(東大寺)〉に(参来することを)請いたまわれる。その詞に曰く、
「天皇〈聖武天皇〉、敬て四十九座〈弥勒菩薩の四十九院に擬した数〉の諸大徳等に諮る。弟子〈天皇はここで「(仏)弟子」と自称〉は、階縁宿殖〈前世で長く多くの善業を積むこと〉して宝命〈天皇位〉を嗣膺〈先代から受け継ぐこと〉した。そこで正法〈仏教〉を宣揚して蒸民〈万民〉を導御〈統治〉しようと思い欲している。故に今年正月十四日を以て、海内〈国内〉の出家の衆を所住の処に勧請し、七七日〈49日間〉を限って大乗の『金光明最勝王経』を転読させる。また、天下をして七七日に限って殺生を禁断し、及び雑食〈肉類を交えた食事〉を断たせる。別に大養徳国 〈日本〉の金光明寺に於いて、殊勝の会〈盛大な法会〉を設け奉って、天下の規模とすることを欲する。諸徳等、あるいは一時代の名輩、あるいは万里の嘉賓、それらはすべて『人師』といい、ことごとく『国宝』に称うものである。冀う所は、その高明〈すぐれた智慧と徳〉を屈して、この延請に応じ参じてくれることである。始めには慈悲の音を暢べ、終りには微妙の力を諧えよう。仰ぎ願わくば、梵宇〈仏教寺院〉がその威を増して皇家は慶を累ね、国土厳浄・人民康楽にして広く群方〈国のすみずみ〉に及び、長く広類を該ねて同じく菩薩乗〈大乗〉に乗り、共に如来の座に座すことを。像法〈仏教の教えが廃れはじめた時代〉を中興する時は、まさに今日にこそある。およそこれ〈時代が像法にあること〉を知見する者で、これを思わないものなどあろうか」
『続日本紀』巻十五 天平十五年正月癸丑条
(新訂増補『国史大系』普及版,『続日本紀』前篇, p.171)
『続紀』全四十巻の編纂が完了したのは延暦十六年〈797〉のこと。最澄が、その昔に聖武帝が僧をして「人師」であり「国宝」であるとしていた表現に倣い、またそれに自ら宗とする天台の章疏の言葉を用い重ねていった可能性のあることをここで指摘しておきます。
優れた僧をして「国法」であると表現することは、『大唐西域記』や『大唐大慈恩寺三蔵法師伝』などに見られ、すなわち印度および支那にも先例が一応あったことです。聖武天皇が独自にそう言ったのか、あるいは何かの典籍に基づいてそうしたのか今のところわかりません。しかし、優れた僧を「人師」そして「国法」と並び称することは、当時は未伝であった筈の『摩訶止観』に、偶然であったのでしょうが同じくしたものです。
最澄はその著述からして、非常によくそれまでの史書の類をよく読み、そこにある語句や表現を所々に使用していることが知られます。これは何も最澄だからということではなく、当時の知識人として当然の態度でもあったものです。そこで聖武天皇を特に意識していたであろう桓武天皇の遺志を重んじていた嵯峨天皇に対する書で、最澄がこのような聖武天皇の先例に重ねて述べていることは、特に意図したものであったろう、と私見ながら考えています。
最澄が『山家学生式』によって陳情していた構想を認める勅許が下されたのは最澄の死後一週間、弘仁十三年〈822〉六月十一日のことです。
当初は桓武帝の期待の新星であった最澄の晩年が、法相宗の徳一との三一権実諍論などに明け暮れ、また空海とも決別し、さらに僧綱や南都諸大寺との戒壇論争にかかずらって、しかもそれぞれ追い詰められた状況のまま死を迎えたことに、同情する声が朝廷内であがったことによるものだとも言われます。すなわち、最澄の大乗戒構想は、仏教として充分な根拠あるものとして認められたものなどではなく、最澄の後援者であった公家や弟子によって展開された政治運動により、失意の中で最後を迎えることになった最澄に対する帝からの憐れみによって終に許されたものです。
しかし、その経緯がどのようであったにせよ、これによって最澄の念願であった独自の構想により天台僧を決して離散させ得ない国家の制度が布かれるようになり、やがて最澄の死後六年を経て比叡山上に大乗戒壇院が建立される運びとなります。
面白いことに最澄の遺弟、いや、最澄の同志であったというべき義真の主導により比叡山に建立された大乗戒壇なるものは、彼が必死でその権威と意義を否定しようとしていた東大寺戒壇院の戒壇堂を模そうとしたものでした。その建立に際しては、東大寺戒壇院の土を請い受けて用いたと云います。結局なんだかんだ言いながらも、東大寺戒壇院というものの権威は、彼らにとって拭いがたいものであったのでしょう。
今延暦寺戒壇者。出最澄之新儀不見釋尊之正説。於五印度之中者依何所圖哉。至四主之間者。寫何國壇哉。爰以昔弘仁 聖朝御時。延暦寺最澄。叡山可建戒壇之由雖經 官奏。諸寺僧侶不許。故 天判更不成。最澄終不遂素懐而歿畢。然後延暦寺別當國道朝臣伺賢政漸隱之尅。得佛法衰微之此。重歴 奏聞。蒙 勅許。後義眞爲立叡山戒壇。謁南都戒壇院第九和上常詮僧都乞請東大寺戒壇院四角之土。籠叡岳戒壇令建立壇場畢。其義眞請文卽在東大寺。
今の延暦寺の戒壇とは、最澄の主張した「新儀」から出たものであって、釈尊の正説に根拠あるものではない。(比叡山の戒壇は)五印度の何れの所の図〈図面〉に依ったものであろうか。四主〈四洲〉について言えば、何れの国の壇を写したものであるのか。このようなことから、昔弘仁の聖朝の御時〈嵯峨天皇の治世〉、延暦寺最澄は、比叡山に戒壇を建てられるよう官奏したけれども、諸寺の僧侶〈僧綱および南都七大寺〉はそれを許さなかった。故に天判による許可が下されることはなく、最澄は終にその素懐を遂げずに死去した。
ところがその後、延暦寺別当の国道朝臣〈大伴国道〉が、(天皇自らによる)賢政が漸く衰えだした時制を伺い、仏法もまた衰微していく機会を得て、重ねて奏聞して(最澄の『山家学生式』にある要望に対する)勅許を得たのであった。そしてまた後に義真〈日本天台宗初代座主〉は比叡山戒壇を立てる為に、南都の戒壇院第九和上常詮僧都に謁し、東大寺戒壇院の四角の土を乞い受けて、叡岳戒壇に籠めて壇場を建立したのであった。その義真の請文は東大寺に今もある。
貞慶『南都叡山戒勝劣事 又云法相天台両宗戒勝劣事』
(新版『大日本佛教全書』, vol.61, p.10b-c)
さて、その死後とはいえ、ついに最澄が『山家学生式』および『顕戒論』において主張し、夢に見ていたことが国の認定を受け、以降はその理想が実現されていくはずでした。最澄によれば、大乗戒のみによって比丘となったと称する者は「国法・国師・国用」となり、国家・社会を脅かす悪僧は駆逐されて、いよいよ大乗の教えが反映することになる…、はずでありました。
誠願先帝御願。天台年分。永爲大類。爲菩薩僧。然則枳王夢猴。九位列落。覺母五駕。後三増數。
誠に願わくば、先帝〈故桓武天皇〉の御願でもあった天台宗の年分度者をもって、以降は大類〈純大乗〉の僧として「菩薩僧」〈最澄の用法では「純大乗の僧」の意〉とされんことを。そうすれば、 訖哩枳王の夢に現れた(十匹の)猿のうち、(国や人々を混乱させる悪しき僧に比せられる)九匹はまたたくまに追いやられ、文殊菩薩の(羊乗行・象乗行・月日神通乗行・声聞神通乗行・如来神通乗行という)五つの籠のうち、(菩薩乗であって無上正等正覚を得ることが定まっている)後の三つは、その数をいよいよ増して繁栄することになるでしょう。
最澄 『山家学生式』「天台法華宗年分学生式」
(『伝教大師全集』, vol.1, p.11)
ところが現実は、最澄がこう言ったのとはまったくの逆となっています。
最澄の死後直後にその後継問題で弟子たちは争い、それが光定の奔走によってようやく沈静化しています。とはいえ、その火種は消えること無く後も争いは続き起こり、結果として最澄死後百年もせぬうちから、むしろ比叡山こそが国家(朝廷)および京の都の人々を脅かす恐るべき暴虐集団いわゆる山法師の巣となり、次第にその力を大きくしていくことになっています。特に円仁と円珍(すなわち義真の門流)の徒弟らが対立し、法性寺および延暦寺座主の就任問題でその争いは激化してもはや収集がつかなくなると、天台宗は山門派(延暦寺)と寺門派(園城寺)とに分裂。彼ら天台宗の僧徒らこそが「訖哩枳王の夢に出てきた九匹の猿」となっています。
日本における天台法華宗の本拠たる比叡山は、最澄の死後それほど間を置かぬうちに王城守護・国家鎮護が聞いて呆れる、忌憚なく言ってしまえば羽織ゴロならぬ袈裟ゴロ、仏教ヤクザの根城と化したのでした。そしてそれは、もはや逝去してなかった最澄からすれば、あまりにも大きな大きな誤算であったに違いないことです。まこと哀れにも最澄は、むしろその死後、彼の目論見・遺志にまったく真逆なる、悪しき方面において非常なる影響力を日本仏教全体に及ぼしていくこととなっています。
最澄における悲劇は、不如意と失意に満ちた晩年を送って最後を迎えたことではなく、不本意にもそのような事態がむしろ彼の構想の実現によって導きだされたことにある。
比叡山から始まったとされる僧兵なるものは当初、比叡山内の円仁と円珍の門流との血みどろの醜い権力争い、いわば内紛でその威を奮っています。しかし、やがては自身らの主張・利権を朝廷や他寺院に脅迫して認めさせるための、対外的暴力・軍事力として利用されるようになっています。
やがて天台宗に限らず興福寺や東大寺、高野山などほとんどすべての大寺院が僧兵を組織・所有し、それぞれその規模・軍事力を大きくしていきます。これは十世紀初頭には律令(僧尼令)が機能しなくなったことによる悪僧の武装集団化と、貴族・大寺院が領するようになっていた広大な荘園を地方豪族の略奪から守護させる自衛手段ともなっています。
その代表が比叡山の鎮守、日吉山王の神輿を盾にして武装した山法師らが担いで都に押し入って暴虐の限りを尽くした強訴です。
賀茂川の水、双六の賽、山法師、これぞ我が御心に叶はぬものと、白河の院も仰せなりけるとかや。鳥羽の院の御時も、越前の平泉寺を山門へ寄せられける事は、当山を御帰依あさからざるによつてなり。非を以て理とすと宣下せられてこそ、院宣をば下されけれ。されば江帥匡房卿の申されしは、山門の大衆、日吉の神輿を陣頭へ振り奉て訴訟を致さば、君はいかが御計らひ候ふべきと申されければ、法皇、げにも、山門の訴訟はもだし難しとぞ仰せける。
「加茂川の水、双六の賽、(比叡の)山法師。これらこそ我が御心に叶わぬものだ」と、白河法皇も仰せられたということである。鳥羽法皇のご治世でも、越前の平泉寺を山門〈延暦寺〉の末寺とされた件については、(そもそも道理の通らぬ話であったが、法皇が)当山〈比叡山〉に深く帰依されていたからこそ、「不条理なことであるが理とする」と宣下され、院宣を下されたのである。そのようであったから、江帥匡房卿〈大江匡房〉が(法皇に)お尋ねになって「山門の大衆〈比叡山延暦寺の僧徒〉が、(比叡山の鎮守である)日吉神社の神輿を陣頭へ振り奉って強訴してきたならば、陛下はどのようにお計らいなさられますか」と申し上げたならば、法皇は「まことに山門の強訴は看過できないことである。(しかし、彼らの非法・暴虐なる振る舞いはどうにもならない)」と仰られた。
『平家物語』巻一(原文のカナを適宜漢字に改めた)
帝や上皇、貴族などの仏教への信仰と、平安京を打ち立て平氏の祖ともなった桓武天皇の威光を傘に着て利用した延暦寺の大衆らの悪しき振る舞いは、弁護の余地など一切ありはしません。それでいて彼らは比叡山こそ鎮護国家の要衝であると謳っていたのですから、傍ら痛いというもの。
さらに彼らは、強訴という物理的暴力だけではなく、呪詛という精神的脅迫をも貴族らにしばしばかけていました。なんとなれば、平安当時の貴族らは、祈祷や呪詛の力を信じ、頼っている者がほとんどであったためです。事実、誰かが誰かを呪詛しているということが発覚した時には、その者が捕縛され、何らか重い刑に処せられてしまうほどに。そのため、「お前を呪詛しているぞ?」などといった叡山のいかめしい脅しを耳にして実際に体調を崩す者があり、また何か不吉な天候・天変があれば呪詛によるものだと捉え、恐れおののく者らがありました。
実に面白おかしく思える話ですが、当時はそのような、現代的感覚からすると無知蒙昧にして未開なる、むしろ非仏教的信仰が仏教にまつわるものとして、ごく普通の当たり前に行われていたのです。いや、今もなおこの類の信仰を有する人が巷にはままあることを、私はよく知っています。
あるいはさらに時代が下ると、一向一揆・法華一揆などといった一応仏教(真宗・日蓮宗)の名のもとに武装集団が形成されてもいきますが、いずれも世を大いに乱す一大要因となっています。
ところで、ここで日本天台宗の歴史やその基たる最澄自身の著作・思想に言及し、これを批判しているのは、なにも「最澄憎し」などといった詮ない心情からでも、宗論などという不毛の戦端を開かんとしてのことでもありません。ましてや「吾が仏、尊し」であるとか「我が宗、独り貴し」などといった派閥意識・宗派意識をもって依怙贔屓し、他を誹謗中傷しようとしているのでも全くありません。
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。
今から千二百年余り昔の最澄がなしたことを現代において批判的・客観的に眺めることは、当時行われた僧綱や南都と比叡山との間で繰り広げられた論争を現代において再び起こさんとするものでも、いずれか宗派に拘泥したいわば宗論として行おうとするものでもありません。
それは、まず平安初頭における仏教界に何があったかを知り、さらには平安中後期から中世鎌倉期における日本仏教の戒律復興運動がいかなるものであったか、また近世において生じた諸宗における戒律復興や持戒に関する見解を正しく捉えるためのものでもあります。
そして、現代の日本仏教のあり方その今後を観る上でも、もはや遠い過去のことであって現代には関知するもので知る必要など無いと思う者もあるでしょうが、それは必須のことです。
釈迦在世に宗派無し。
そもそも菲才自身には、拙いながらもただ仏家の沙門たらんとする意思のみあって、愚かしい宗派意識・宗我など微塵も持ち合わせていません。語弊を恐れずに言えば、こう云われることを好まない人は多くありますが、そのような意味での宗旨宗派なんぞどうでもよろしい話です。
しかし、日本仏教なるものが本来の仏教から、これは特に初期仏教または上座部だけを意図したものではなく広く印度および支那を含めた声聞乗と大乗とを意図したものですが、あまりに乖離して時に異常とすら言える様態を示しているとしばしば批判されます。それは事実その通りだと思いますが、その原因を作ったきっかけや要因を探った時、最澄の存在とその主張を無視し、その真偽可否を判じるのを避けることは決して出来ません。
実際、最澄の要望がその死後とは言え認められ実行されたことは、後世ただ天台宗だけにとどまらず、日本仏教全体に波及していきます。そして最澄の影響は今の日本仏教においてもなお強く存しています。それは、日本仏教における戒律の不在であり、また「不在であっても良い」などとする日本仏教の僧職者・信徒に根深く浸透した思想となっています。
もちろん、現今の日本仏教における戒律の欠落が、ただ最澄一人の責にあるなどということは決してありません。律令制の崩壊や、皇族・貴族らが続々出家していって俗世の階級性を仏教界に持ち込んでいったこともその要因の一つです。しかし多くの宗派における教学やあり方として戒律を無視することを容認するようになった一大要因が、最澄であったことは間違いありません。その問題の根源とその影響などを知り、いささかでもそれを解決せんとしたならば、どうしても歴史的経緯やその思想的根拠や合理性の可否について触れないわけにはいかない。そしてそれが仏教という伝統的観点からして誤っているならば、それを看過することなど出来はしません。
しかし、このように言うと必ず、「日本には日本独自の仏教があって良い。それがたとい本来の仏教とやらと異なっており、印度や支那のそれと違っていたとして、それの何が悪いのか。自由でいいじゃないか。仏教とはもっと鷹揚で自由なもののはずだ」 などと言った類の言を振るう者が現れます。
笑止。そのような主張を認める祖師といわれる者など一人として無かったと断言出来ます。
なんとなれば、彼ら日本で祖師と言われる人々のほぼ全員が、自身が信奉し宣布しようとした宗義の正当性を、印度から支那を経て伝来した三国伝来であって独自なものなどでないことを証明せんとし、それこそ必死で訴え、その著に書き記しているためです。その主張の可否真偽は別として、最澄がその著作の多くで行っていることはまさにそのことです。本稿『山家学生式』に引き続いて最澄が朝廷に提出した『顕戒論』や『仏法血脈譜』などがそれです。
そんな彼らが「日本独自の仏教」なるものを認めるわけが無い。
日本独自の仏教ということは正統なものではなく、よって「仏教では無い」ということになってしまうためです。そして仏教とは、そんな意味で自由なものではない。したがって「日本独自の仏教で何が悪い」という類の主張は結局、自身らの堕落し怠慢なる現状を否定されることを恐れてのお為ごかしに過ぎず、むしろ自身らが「お祖師様」と崇める人の努力を全く否定するに全く等しいものです。あるいは単に、自身の「オソシサマ」について何も知らず分かってはいないことの証です。
巷間、「他宗のことに首を突っ込んで批判することは正しくない。余計なお世話で控えるべき下品なことである」などという、忌憚なく言って愚昧なる物言いをする者もしばしばあります。が、他宗のことに首を突っ込んで批判をしなかった祖師といわれる人など、まず無い。そもそも仏教自体、印度におけるバラモン教への批判から生まれたという側面があり、また大乗における八宗の祖といわれる龍樹菩薩の中観派など、破邪顕正といって他の学説・思想を徹底的に批判することによって、無自性空の理を顕していかんとするものです。
そして最澄についてこれを言えば、上来示したように、彼は他宗を批判して大論争を展開したばかりではなく、しばしば誹謗中傷すらしており、またその制度・あり方について帝に上奏して実際に手を入れた人です。よって、そのような物言いは、そのまま自身らの宗祖に対しての批判となることを知らなければならない。
人の世に栄枯盛衰はつきものであって、それはまさしく釈迦牟尼によって示された諸行無常なる、世にありありと目にすることができる有り様です。また人は過つもの。そして、人は堕落するもの。戒律があろうとなかろうと、それは変わりありません。しかし、であるからこそ、それを戒めるもの、また人が過ちを犯しあるいは堕落した際にこれを罰する規定、そして自浄作用をもつ規則が人の組織には求められます。
これはただ仏教という宗教のあり方にとどまる話ではありません。一般社会における様々な組織において非常によく問題視される構造です。その規則規定を放棄した結果どうなるか。具体的で広範な規則や自浄作用を持つこと無く、ただ高邁な理念だけを謳うだけだとしたら、どのような結果がもたらされるか。それはまさしく、最澄の日本天台宗の歴史というもの、そこから派生した宗派の有り様や思想がどのようなものであったか、どのようになっていったかを知れば、あるいは今現在の日本仏教の僧徒らの有り様を見渡してみたならば、自ずから理解されることであるでしょう。
小苾蒭覺應 記