仏教伝来してこのかた、朝廷は唐の制度に倣いつつ、日本における寺院および僧尼の監督する制を試行錯誤しながら構築していました。大宝元年〈701〉に発布された「僧尼令」、そして天平勝宝六年〈754〉にもたらされ開始された具足戒の授受、および弘仁四年〈812〉に改正された度縁と戒牒の制は、国法としては一つの成果であり到達点です。
ところが、弘仁九年〈718〉から翌十年〈719〉にかけて最澄が上奏した『山家学生式』の内容は、印度以来支那でも前代未聞の、しかも鑑真渡来によりようやく布かれた制度を根底から覆すことを要求したものでした。しかもその最初の表「天台法華宗年分学生式」の序文は、既存の南都六宗を「小像」であると貶し、あるいは「枳王の夢猴」などと一群の邪悪な猿扱いするものとなっています。
今我東州。但有小像。未有大類。大道未弘。大人難興。誠願 先帝御願。天台年分。永爲大類。爲菩薩僧。然則枳王夢猴。九位列落。覺母五駕。後三増數。
今、我が東州〈日本〉には、ただ小像〈小乗に類した教え。ここで最澄は法相宗や三論宗など南都六宗を卑下してそう言っている〉のみがあって、いまだ大類〈真の大乗の宗。最澄は自身の天台宗をのみそう見なした〉がありません。大道がいまだ広まらないでいるならば、大人が現れることは難しいでしょう。誠に願わくば、先帝〈桓武天皇〉の御願でもあった天台宗の年分度者をもって、以降は大類の僧とし菩薩僧とされんことを。そうすれば、枳王〈訖哩枳王〉の夢に現れた(十匹の)猿のうち九匹〈乱暴狼藉を働く邪悪な猿.最澄はこれを南都六宗に類比した〉はまたたくまに追いやられ、文殊菩薩の(羊乗行・象乗行・月日神通乗行・声聞神通乗行・如来神通乗行という)五つの籠のうち、(菩薩乗であって無上正等正覚を得ることが定まっている)後の三つは、その数をいや増すことになるでしょう。
最澄『山家学生式』「天台法華宗年分学生式一首」
(『伝教大師全集』, vol.1, p.11)
この一節はその冒頭の「国法とは何者ぞ」に比してあまり取り上げられることがないものですが、最澄はここで甚だしく敵対的な言説をもって他宗を形容しています。ここにはそのように言う根拠など一切示されていないため、批判ではなくただの中傷でしかありません。そしてこの表は、当時の制度上、彼が「小像」・「枳王の夢猴」と腐した他宗の僧で構成されている僧綱が必ず目にすることを知った上で書かれたものであって、僧綱や南都諸大寺からすれば過激な挑発以外の何物でもない。
そのようなひどく他宗に対する敵意に満ちた文言で構成された書を上奏したのは、最澄が当時置かれていた状況を鑑みたならば、彼のひどく切迫した心情の反映であったのでしょう。最澄は、法相宗との宗義上の論戦を展開する以前、弘仁四年〈813〉頃に天台宗が法相宗より優れたものであることを主張し初めたばかりの時点では、そのような攻撃的な態度は取っておらず、むしろ穏健な態度で自宗を広めていこうとしていたことが知られるのです(『大唐新羅諸宗義匠依憑天台義集』)。
しかし、その四年後の弘仁八年〈817〉頃から開始された法相宗との論争、いわゆる三一権実諍論が開始されてからはそんな穏健な態度は鳴りを潜めていきます。そもそも一乗を奉じる天台宗と三乗を奉じる法相宗とでは、三論宗と法相宗とがそうであったように、教学的には決して相容れることない不倶戴天の論敵同士です。朝廷は、平城京において法相と三論の間で繰り広げられる論争、というよりも勢力的に法相のみが優位となっていたことを問題視していました。そこで平安京においては桓武天皇の遺志が介在し、南都諸宗とりわけ法相と新来の天台との宗論の場を設けられて論争が行われています。圧倒的とすらなっていた法相宗の優位を崩すことによって、仏教界の勢力図に一種のバランスがもたらされることが期待されたのでしょう。
最澄としても新来の天台宗がそれまでの諸宗とはどのように異なり、何が他より優れた点かを義務として公に論述しなければならず、そのような衝突は避けて通れない道であったのですが、その論戦は次第に苛烈を窮めていきます。特に平安初期を代表する僧として空海と最澄の名を挙げるならば、必ず並列して挙げなければならない徳一という法相宗における優れた大徳は、最澄にとって最大の論敵となっています。
とは言え、ただそれだけであれば、それまでの三論宗と法相宗と同じような関係に過ぎず、宗論を戦わせるにしても切磋琢磨と言える関係に留まったものです。論争を行うこと自体は何ら悪いことでなく、むしろ健全とすらいえるものです。けれども最澄の場合、法相宗は自身の門徒のほとんどの流出先、その実に憎き受け皿であるという問題、私怨が重なっています。そして、最澄にとって最大の問題は、三一権実諍論といった教学面のことよりも、むしろ相次ぐ門徒の流出という一点にありました。
したがってこの時点で最澄は、僧綱および南都の諸大寺と相当な敵意を以て全面対決する覚悟を決めていたと見て間違いありません。それは、彼の天台宗が当時そこまで追い詰められていた、といっても僧綱や南都諸宗が最澄を意図的に追い詰めていたというのでもなく、先に述べたように天台宗における年分度者が次々逃散した結果としての絶望的残存率という現実があってのことです。
実は最澄は弘仁三年〈812〉五月には死を意識して遺書をすら認めており、まさに土壇場における覚悟であったのでしょう。他にもまた、それまで蜜月にして「一乗の旨、真言と異なることなし」とその受法を渇望していた真言宗の空海とも弘仁五年頃には決定的に決裂。同七年〈816〉には彼に対する批判の辞を述べているように、もはや最澄は全く孤立無援の四面楚歌となって久しい状況にありました。
人は往々にして追い詰められるほどにその思想は先鋭的かつ独善的となり、その言葉は過激なものとなっていきます。そこで人材流出を防ぐ具体的術、決め手に成りえる方法として最澄が考案したのが、一連の『山家学生式』に記された内容です。
それは要するに、自身の天台宗だけ特別扱いされることを求めたものでした。その主張の根底にあるのは、天台宗の年分度者のほとんどが東大寺戒壇院にて受戒し正規の僧となった途端に他宗に転向するなど離散してしまうならば、そもそも天台の年分度者に関しては従来の僧籍とは異なったものにしてしまい、また戒壇院で受戒させる必要がないよう国家の制度として変えてしまえば良いのだという、非常に短絡的な、しかし極めて現実的な発想です。
その主張の根拠とするのに矛盾なく、一定の合理性を装うものとして発案したのが、実は天台宗だけが「大類」すなわち真の大乗に属するのであって、南都六宗はすべて「小像」であり「邪悪な猿」であるという、上掲の一節に集約された思想です。最澄は論拠の核心は、自宗こそが唯一の大乗であるから、その扱いは小乗に類する既存のものとは別個にして然るべきである、といったものとなっています。そこでそれを国家として認め、国法により制度化して欲しい、というのです。
そもそも僧籍とは、今のように現代の仏教各宗派が手前勝手に出すようなものでなく、文字通り「僧尼の名籍」・「出家の籍」として国家が制度化し管理したものです。僧籍がそのような行政上の制度であるがために、最澄はこれを天台宗だけは上記を理由に独自のものとして変更し、運営するように求めたのです。それが変えられることによってどうなるのか。天台宗の年分度者のみ他宗と同様の僧籍として管理されなければ、それまでのように年分度者として僧籍を得た者がそのまま横滑りで他宗に転じることは不可能になります。
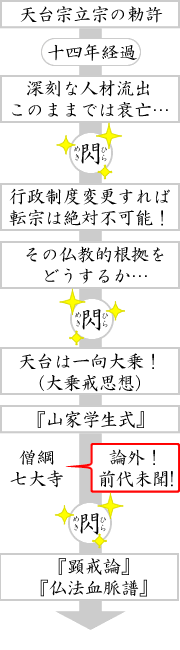
それは最澄にとって、天台の年分度者を比叡山に縛り付け、他宗に絶対的に離散させないようにする最大の妙案でした。そして、ここがこれを理解する上で最大の要点であり、ために繰り返し強調しておきますが、そのような「国家の制度を変更するための根拠」として練り上げていったのが、最澄の大乗戒思想です。
これは従来まったく逆さまに理解されてきたことです。最澄には大乗戒思想が先ずあってそれを実現するために行政の制度変更を求めたのではなく、人材流出対策のため制度変更を求める大義名分として独自の大乗戒思想を構築していったのでした。すなわち、最澄がいわゆる梵網戒を以て称するところの円戒思想は、天台宗衰亡の危機に際して発案した人材流出防止策、現代いうところの「囲い込み戦略」を、法的・仏教的に合理的で正当なものとして糊塗しようとした結果生み出されたものです。
なお、最澄が最後まで空海から受法することを渇望していた真言密教については弟子泰範の離反があったとはいえ、その泰範に対して「法花一乗と真言一乗と、何ぞ優劣有らんや」と自ら言うほど同格に考えていたため、この問題に関して「小像」とする彼の批判の範疇に入れていません。そもそも当時の真言宗には未だ年分度者は認められておらず、また空海もその時点では僧綱に任じられていなかったため、この問題に全く関知していません。
空海が僧綱に任じられるのは最澄の死後、天長元年〈824〉三月のことであり、また真言の年分度者三人が許されるのは承和ニ年〈835〉のことです。
『僧綱補任』によれば、最澄が一連の「学生式」を奏上した当時の僧綱は、以下の僧らによって構成されていたとされます。
同九年 戊戌 春於延暦寺申立戒壇。
大僧都護命 少僧都長惠
律師 修圓 修哲
勤操 施平
豐安 前大僧都玄賓 六月十七入滅。河内國人。俗姓弓削連。
同十年 己亥 五月十五日。護命大僧都依奏狀。不被行一乘戒壇。
大僧都護命 少僧都長惠
律師 修圓 修哲
泰渲 在早部而不載此巻。可尋 勤操 正月十四日癸巳任少僧都。
施平 豐安
弘仁九年 戊戌〈818〉 春於延暦寺申立戒壇。
大僧都護命〈法相宗・元興寺〉 少僧都長恵〈律宗.長慧とも〉
律師 修圓〈法相宗・興福寺〉・修哲〈未詳〉・
勤操〈三論宗・大安寺〉・施平〈法相宗・元興寺〉・
豊安 〈律宗・唐招提寺〉 《前大僧都玄賓 六月十七日入滅。河内国人。俗姓弓削連。》
弘仁十年 己亥〈819〉 五月十五日。護命大僧都依奏狀。不被行一乘戒壇。
大僧都護命 少僧都長恵
律師 修圓 修哲
泰渲〈泰演の誤写〉早部には在るがこの巻に不記載。要調査。・勤操 正月十四日癸巳、少僧都に補任。
施平・豊安
『僧綱補任』第一(新版『大日本佛教全書』, vol.65, p.8b-c)
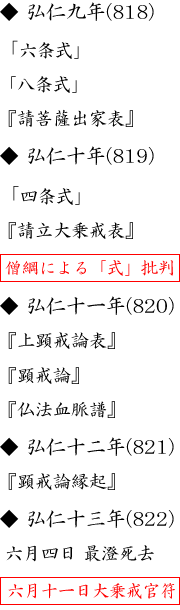
ただし、最澄の表によれば、当時の僧綱の成員は大僧都護命・少僧都長慧(長恵)・律師施平・律師豊安・律師修圓・律師泰演と、狭山池にあって京に不在であった少僧都勤操であったとされます。したがって最澄は、当時の僧綱をして 六統や六綱と称しています。
いずれにせよ護命を筆頭とする僧綱は、最後の『四条式』が上奏されてから二ヶ月後の弘仁十年五月十九日、最澄が奏上した一連の表と式の内容について審議した結果、それが全く非であることを帝に報告しています。
最澄の主張と要望は、上来示してきたような日本に仏教伝来してから特に鑑真を請来するに到るまでの経緯と成果とを否定するに等しいものであり、何よりも仏教として根拠薄弱であって印度以来の伝統にも乖いたものでした。故に僧綱は最澄の表を完全否定したのであり、その理由は僧綱の成員の多くが最澄が目の敵にした法相宗僧であったため、などといったいわば私怨が絡んだものではありません。また、世間ではそのような誤解が通用して久しくありますが、僧綱あるいは南都の諸大寺が掌握して既得権となっていた授戒権が分割されることを恐れたためなどでもありません。そもそも権益としての「授戒権」などといったものを僧綱や諸大寺は有していません。いや、そのようなもの自体、初めからどこにも存在していない。
「授戒権」などという理解を一体どこの左巻きポン助が持ち出し、言い始めたのかわかりません。しかし、一昔前にはそのように南都における授戒を権益として理解する学者が多くありました。
そんな彼等がいうところの「授戒権」なるものは、むしろ後代の比叡山こそ振りかざしたものです。最澄の主張の死後ただちに門弟らによる内紛が相次いで生じていますが、特に円仁と円珍の門流間における争いは熾烈をきわめています。最澄の徒弟には、いわば彼の長年の同志であった義真に対して強い反感を持つ者が多かったようです。そこで比叡山は、円珍(義真の徒弟)の門流の拠点となった園城寺の僧徒に対し、叡山の戒壇における授戒を盾にして脅迫しています。それこそがまさに「授戒権」と表現し得るものであったでしょう。
しかし、繰り返しますがそのような問題は、最澄と僧綱および南都の諸大寺の間に存していません。
そしてまた並行してよくなされた「奈良仏教は堕落していた」という見方についても、極めて一面的かつ一方的なものであると言わざるをえません。そのような見方の背後には称徳天皇代において道鏡により皇位が伺われた事件、それは確かに一大事件と言えるものでしたが、そのような事実があるのでしょう。
また法相宗の徳一が若くして東国に去ったのは、僧徒の堕落を嫌ってのことであったと云われます。実際、これは良弁の上奏によって「四位十三階」の僧位を設けることが許されて以降、それは僧の堕落を防ぐために階位を設けることを建言されたものであったのですが、むしろ僧らがそのような階位制度に組み込まれたことに因って奢侈に流れ貴族化していた、と云うことは出来ます。けれども、最澄の最大の論敵となった徳一はそのような僧徒の貴族化を嫌った木食の人であり、したがってこの問題に堕落を持ち出すことは不当です。
また、それを無闇に南都の仏教界に一般化・普遍化し、しかも桓武帝および嵯峨帝の代にまで引きずって見ることは全く正しくない。最澄の直弟子たちもまた、そのような階位制度における称号や位階、席次などにかなり拘っていたことが知られるのです。
前時代の史学者や仏教学者には、一時代を席巻した唯物史観に基づき、あるいは何でも政治的闘争・階級闘争などとして歴史を眺めようとした者が多くあり、理知的でなくむしろ感情的・信条的にアレコレ競って立論していたように思います。
そこで、この最澄と僧綱との論争について、「仏教改革を推し進めようとする若き革命家たる最澄と、旧態依然として既得権益者であり、堕落した南都六宗の利益代表たる僧綱との対決であった」などといった類の理解をする人が非常に多くありました。そして最澄は「ほとばしる人間性を開花させるため、僧綱という政治的権力からの抑圧から脱すべく、純粋な宗教的情熱をもって闘争した戦士」といった類の、今からすると実に滑稽で奇異に感じられる表現が様々になされ、理解されてきました。そしてそのような従来の理解・態度に対する反省・批判は、いまだ学者の間でもほとんど見られません。

しかしそれは、この論争の本質が全然捉えられていないものであって、まず戒律というものに対する無理解や、しかも他でもない最澄を淵源として日本に定着した偏見というものがあり、さらに戦後の日本的左派思想に心酔することが知的であり上流であるとする風潮や教育に汚染された思考による歪んだ見方です。彼等は最澄をして腐敗した権威の破壊者、正義の革命家だと見なしたのでしょう。
あるいは新仏教と言われる日本独自の浄土教や日蓮教団、もしくは曹洞宗など日本の禅宗を信仰・信奉あるいは共感する者により、その源である比叡山の最澄を認めなければそれぞれ宗祖・教祖の権威も宗派の立場も認められなくなってしまうため、彼の主張はなんら批判的に考証されること無く、ただただ称揚され続けてきました。
(途中、最澄を直接的には否定することなく、しかし戒律の極めて重要であることを訴える動きも中世および近世にいくらか生じてはいます。それは中世においては栄西と俊芿であり、また近世においては妙立慈山であり霊空光謙です。同時代、これに反発した者として義瑞性慶および顕道敬光も、しかしその関係者として重要です。とはいえ、それは最澄より遥か後代のことです。)
しかし、最澄の主張は、純粋なる宗教的動機からなどでなく、まったく組織の存亡を賭けた純然たる政治的動機から発せられたものであったことは、彼を取り巻く状況の推移と動向を見れば明らかです。けれども、宗の存続が危ぶまれているからといって、ただそれだけを理由に国家の制度、行政を恣意的に変更させるわけにもいかず、僧であり、また仏教について云う以上は何につけその主張に仏教としての根拠が求められます。
そこで最澄は、前述したように、自宗は他宗と異なる純然たる大乗の宗である、という主張を論拠の核心に据えることによって、自らの説にそぐう経論を縦横に駆使し、その辻褄を合わせようとしたのでした。それは相当に試案を重ね、練り上げたであろう実に苦心の案と言えたものです。
仏教がどうのということを全く脇に置いたならば、その案は人材流出防止策として当時の法制度の隙を突いた奇策と言えるものであって、なるほど最澄は才知に長けた人であったと感心すらできる程です。しかし、それは僧のあり方に関する仏教の核心問題であってこれを脇に置くことなど出来よう筈もなく、印度以来の伝統や日本におけるそれまでの経緯からすると、これを認めることなど出来る訳が無いものでした。
僧綱や南都の諸大寺の並み居る学僧から種々様々な点について批判され、その全く非であることを指摘された最澄は、これに逐一反駁すべく『上顕戒論表』・『顕戒論』・『内証仏法相承血脈譜』(以下、『仏法血脈譜』)、続いて『顕戒論縁起』を著し猛反論しています。僧綱がどのように最澄を批判したかの文書はそれ自体としては残っていません。しかし、『顕戒論』において最澄は、まず僧綱が「学生式」の内容が認められないものであると上奏した文を全て引き、その一節毎に割注して一々「箴して曰く」もしくは「弾じて曰く」と自ら反駁していく形態を取っているため、僧綱からの最澄の主張への批判は『顕戒論』において知ることが出来ます。その後、最澄は五十八ヵ条に渡り、自身の主張がどこまでも正しく、僧綱や諸大寺からの批判が誤っているかを論述しています。
『仏法血脈譜』にて最澄が自ら主張するところでは、自身が支那にて受法・相承したのは天台だけではなく、禅と菩薩戒ならびに密教であったとしています。しかし、それはあくまで(自身の擁護者であった桓武帝とは異なる)嵯峨帝に対して自らの短期留学の成果を相当過大に言い、自身が正統な法脈に連なる者であることを言わんとしたに過ぎないものです。天台の書典籍の多くをもたらした以外は、最澄がいう「相承」の内実など伴ったものではありませんでした。たとえば、密教については「大したことを受けていない」と空海に述べており、故に自ら空海から受法することを望んでいます。それは禅についても同様で、彼が学んだというのはあくまでその典籍程度のことです。
すなわち、『仏法血脈譜』とは、(漢語も話せなかった)最澄がわずか数カ月間ばかり、しかも支那の都長安でなくただ辺境の地に行っただけであったのを僧綱から突かれていたことに対する、それは彼にとって非常に痛いところであったに違いないものですが、精一杯自身を正当化するための反論でもあったと考えられます。これが提出された時機が帰国直後であったならまだわかりますが、そのような論争が開始されてから出されたものであることも、そう考える根拠の一つです。
そんな『顕戒論』を見ることにより、むしろ僧綱が無闇矢鱈に最澄の主張を否定したのでは決してなく、あくまで仏教として根拠不明な不審点、彼の主張の不合理な点、印度以来の伝統的あり方や解釈として前代未聞である点を突いて批判してたことが知られます。繰り返し強調しておきますが、僧綱の最澄に対する批判に「授戒権という既得権益」を守ろうとする意図などまったく見られず、そもそも南都に「授戒権」なるものは存在していません。
そして、『顕戒論』に続いて提出された自身が入唐求法から叡山上にて独自に出家・受戒することを要望して論争を惹起するまでの様々な資料を収集した『顕戒論縁起』もまた、最澄の主張を知る上で極めて重要です。ただし、『顕戒論縁起』上下巻のうち下巻には南都の七大寺(法隆寺を除く)の諸大寺がそれぞれ僧綱に提出した最澄の奏上への批判が含まれていたのですが、まったく残念なことに下巻のみ散逸して現存していません。
(『顕戒論縁起』は、見方を変えたならば、彼の言っていることが種々に撞着していることを自ら証明してしまっているようなものでもあります。まさしく「問うに語らず、語るに落ちる」と言えたものですが、最澄はむしろ自身の主張が正しいことの根拠の一つとして堂々と提出しているから面白いものです。)
しかし、そのような仏教的裏付けは、行政の制度変更の裁可を得るために後から被せられたものです。特に最澄は戒律に関して決定的な誤解をしながらそれを元に立論し、しかもしばしば論点のすり替えを行っているため、その主張はそこかしこで牽強附会あるいは堅白異同したものとなっています。とは言え、僧綱の批判は常識的なものではあったのですが、いくらか小さな穴のある不用意なものでした。
最澄はそこで、そのような僧綱の批判の隙を突いて長々と反論しています。僧綱からしてみれば単に「無根拠かつ前例がなく、また非常識な主張で容認できない。却下」と処理しようとしたものであったでしょう。まさか僧綱も、最澄がそこまで苛烈に反論してくるとは思っていなかったようです。しかし、最澄にとっては自宗の存亡を賭けた論戦ですから、それに対する準備から熱量が全く違い、その論説も非常に攻撃的で徹底的です。僧綱の批判の中でも本旨に関しない様な極小さな点まで、その批判の正否は別として、それは執拗なまでにやり玉に挙げています。
そのような苛烈さは、朝廷に対し、僧綱の主張がどこまでも誤っているのに比べて自身がごく些細なことまで徹頭徹尾正しいことを訴え心象を良くするための、いわば戦略でもあったのでしょう。この大乗戒に関する最澄と僧綱との諍論や朝廷とのやり取りについては、その天台宗の最初の天分度者で唯一残留して最澄の元を離れなかった、光定による『伝述一心戒文』(以下、『一心戒文』)にも所々にその経緯や資料が記されています。これにより、当時の最澄の動向や言動などをより詳しく知ることが出来ます。
以上のことから、ここで紹介する『山家学生式』だけを読んで最澄の言わんとしたこと、その主張の全容を知ることは出来ません。それには相当に仏教や当時の律令など社会制度に関する素養と読解のための根気とを要しますが、『顕戒論』および『一心戒文』も詳しく見なければなりません。
ところで、実は最澄は「天皇の御前に召し出してこの問題を対面にて議論すべし」と僧綱から求められていました。
沙門護命等謹言
僧㝡澄奉獻天台式幷表奏不合敎理事
《中略》
入唐學生。道照道慈等。往逢明師。學業㧞萃。天竺菩提。唐朝鑒眞等。感德歸化。傅通遺敎。如是人等。德高於時。都無異議。《中略》 而僧㝡澄。未見唐都。只在邊州。卽便還來。今私造式。輙以奉獻。《中略》 其文淺漏。事理不詳。《中略》 非紊亂法門。兼復違令條 彈曰。備三學。非是紊亂。屈滯直表。何違令條也 誠須召對僧身。依敎論定。彈曰。已有式文。邪正易定更召僧身。問何難定也。
沙門護命等、謹んで(帝に)言しあげます。
僧最澄が奉献した天台の式ならびに表が(仏陀の)教理に合わないことを奏する事
《中略》
入唐の学生であった道照や道慈など、(唐の都に)往って明師に逢い、その学業は抜きん出たものでありました。天竺の菩提僊那や唐朝の鑑真などは、(日本の帝の)徳を感じ化に帰して、(仏陀の)遺教を伝通されております。これらのような人などは、その徳が当時も高いものでありましたが、なんら異議〈最澄が主張したような「一向大乗」のあり方〉などありはしませんでした。《中略》 しかるに僧最澄は、未だ唐の都に行って見たこともなく、ただ(明州・台州・越州という)辺境の州に行っただけで、しかもすぐに帰国しているのに、今私に式を造り、たやすくそれを奉献しております。《中略》 その文は浅漏〈浅はかで杜撰なこと〉なものであって、事理〈道理.ここでは具体的な典拠の意〉も詳しいものではありません。《中略》 それは法門〈仏教〉を紊乱〈秩序を乱すこと〉するのみならず、兼ねてまた令条〈「僧尼令」や格など〉に違反するものであります。 弾劾して曰く、三学を備えることは紊乱ではない。(むしろ法門が)滞っていることについて直に表することは、何の令条に違反するというのか。 誠にすべからく僧身〈最澄本人〉を召し出し、(その奏した式の内容について)仏教に依って論じ(その是非を)定めるべきであります。弾劾して曰く、すでに式文を提出しており、その邪正を定めることは容易であろう。更に(我が)僧身を召し出して、どのような定め難いことを問うというのか。
最澄『顕戒論』巻上(本文中、割注が最澄による反論。一部割愛)
(『伝教大師全集』, vol.1, pp.33-35)
ところが最澄は、以上のように「すでに『式』は提出してあり、その文面を審議すればよいのであって、私自身を召し出して何を決めようというのか」とこれを拒否しています。この最澄の弁解は実に不合理で、確かに最澄は一連の「学生式」を上奏しているものの、そこには具体的な典拠など一切示されていないため幾多の不審点を持たれてむしろ当然です。僧綱も朝廷もそれだけで決裁など出来る筈がありません。
従って僧綱はそれを審議した上で、その問題点・不審点を問い糾すために「誠に須く僧身を召し對し、敎に依て論定せしむべし」と言っているのであり、また最澄自身はそれに答えるために『顕戒論』を著しているのですから、その『顕戒論』の中で「『式』にもう書いているから召し出されて対論する必要はない」などと言うのは実におかしな話です。また、本来は僧綱や玄蕃寮を通して奏上しなければならないところを、自ら帝に直接上奏したけれども、帝に呼ばれて御前でその話はしたくない、書いたものだけ読んで理解しろ、では道理が全く通りません。
結局、彼の前後の行動を見たならば、自身の主張が無理筋であってこれを天皇の御前で論議しても負けてしまう可能性が高いことを、どうやら自ら知っていたようです。そして、御前での論戦で負けてしまったならば、それこそ取り返しがつかないことを自覚していたのでしょう。というのも、もし最澄が『顕戒論』の中で長々述べている通りに自身の主張に充分な根拠があり、まったく印度以来の伝統に乖離しない正統なものであると自信を持っていたならば、それはむしろ天皇の御前で僧綱を論破し説き伏せることの出来る、絶好の機会であった筈のためです。しかし、彼はそうしなかった。いや、出来ませんでした。朝廷としても最澄にそのような「悪手」を打って欲しくは無かったと思われます。
あるいは、最澄が文字・文章にどこまでも拘る人であったことも、その理由の一つとして考えることが出来ます。それはもちろん重要なことであり根本的なことではありますが、彼がそのような思想信条の人であったが故に、空海から密教の受法を最終的に断られたうえ、さらに「文は是れ 糟粕、文は是れ瓦礫 なり。糟粕瓦礫を受くれば則ち粹実至実を失う。真を棄てて偽を拾うは愚人の法なり。愚人の法には汝隨うべからず。また求むべからず」などと、遠慮の全くない、非常に厳しい言葉で諌められたのでしょう。これはあくまで密教の授受についての言であったものですが、空海にそう言わしめて結局決裂することになるのは、他でもない最澄の性格でありその行動に因るものであったと考えられます。
最澄はその後、このように空海から言われたことに対し「真言家は筆授の伝受を泯 す」(『依憑天台集』)などと恨み言を言っています。それは、最澄が空海の言葉の意味をついに理解できなかったことを示すばかりでなく、自身が唐で相承してきたと「仏法血脈譜」にて主張している禅宗についても、その実など全く無い形だけ、文書の上だけのものであったことをも自ら暴露したに等しい言葉です。これもまた「問うに落ちず、語るに落ちる」と言えたものでした。
もっとも、どこまでも筆授に拘って伝法は文字に依るべき、あるいはそれだけで可能だと考えていた最澄からすれば、その何が問題であるか全然理解できなかったのでしょう。
菲才はそのような最澄の思想・信条について、彼が唐に数カ月間渡っていたとはいえ自ら漢語を話すことが出来ず、常に義真という通訳を介し、いわば間接的に天台にしろ戒にしろ受けていたいうことがその裏にあったのではないか、と考えています。これは現代でも留学経験のある者であればわかることであるでしょうが、たとえその対象は同じであっても直接自ら会話して学びとることと通訳を介して話し受けることとは全く違うからです。ごく短期の間、しかも通訳を通してのみ学んだのみであったため、必然的にそこで収集した典籍に書かれた文字こそ価値あるものとなってそれに徹底して拘泥していったのであろう、と思われるからです。
さて、最澄は直接天皇に建言したことに対して「法門を紊乱するのみに非ず、兼て復た令條に違す」という僧綱からの批判について、「何の令條に違するや」と述べています。しかし、その行為は『僧尼令』の「第八 有事可論条」に明白に抵触したものでした。もっとも、これについて最澄は『顕戒論』巻下にて、もはや屁理屈としか評し得ぬ理由をごく短い一文ながら挙げ、その批判の当たらないことを述べています。
朝廷としては、最澄の建てた天台宗の後ろ盾が先の桓武天皇であったことを当然知っており、また最澄自身が事ある毎にその「先帝」の威光を自ら持ち出してくるため、その処遇はおのずから難しいものであったことでしょう。仮に最澄が令に違反していたとしても、「いや、これは先帝の制であったのを私が今言っているに過ぎない」などと言われてしまえば、実際最澄はそう言っているのですけれども、それを訴追することなど出来るわけもなく、実際していません。
ただし、いくらそれが故桓武天皇の意向を受けていた最澄からの陳情であるとはいえ、そこに大なる疑義が多数あるとされている以上は、嵯峨天皇(朝廷)としてこれを容易く裁可することは出来ませんでした。桓武帝の遺志がある以上、天台宗が自滅するのを放置することは出来ず、かといって最澄の要求をそのまま認可するわけにはいかず、帝としては困った事態であったことでしょう。もっとも、朝廷の中には最澄の後援者として藤原良房という非常に有力な公卿があり、また大伴国道(後に伴国道と改姓)があって、なんとか最澄の上表に対する勅許を得ようと運動していました。
そこで弘仁十三年六月四日、最澄が死去したことにより、ついにその時が訪れています。
◯允許大乘戒官符
檢傳燈法師位㝡澄奏狀偁。夫如來制戒隨機不同。衆生發心大小亦別。所以文殊豆盧上座異位。一師十師羯磨各別。望請。天台法華宗年分度者二人。於比叡山毎年三月 先帝國忌日。依法華經制令得度受戒。仍卽一十二年不聽出山。四種三昧。令得修練。然則。一乘戒定永傳聖朝。山林精進遠勸塵劫。謹副別式謹以上奏。者被右大臣宣偁。奉 勅宜依奏狀。者省宜承知依宣行之。符到奉行
弘仁十三年六月十一日
◯大乘戒を允許する官符
伝灯法師位最澄の奏状〈天子に奏上する文書〉を精査して云うに、
「『そもそも如来の制戒は(衆生の)機根に随ったものであって同じではありません。衆生の発心も大と小とまた別であります。所以に文殊菩薩と賓頭盧とを上座とすることに位の異なりがあり、(菩薩戒の戒師は)一師と(具足戒の戒師は)十師と羯磨〈戒律の用語としての場合、南都では「こんま」と特殊に読むが天台ではこれを「かつま」と読む〉はそれぞれ別であります。どうかお願い致します、天台法華宗の年分度者二人は、比叡山において毎年の三月、先帝の国忌の日に、『法華経』の制に基づいて得度・受戒させ、その後は十二年間、比叡山から出ることを許さず、四種三昧によって修練させることをお許し下さい。それをお許しいただけたならば、一乗の戒と定とは永く聖朝に伝わり、山林精進によって遠く未来の果てまで勧められることになりましょう。謹しんで別の式を添付し、謹んで以上を奉ります』〈以上、最澄が弘仁十年に奏した『請立大乗戒表』〉 ということで、右大臣の宣を受けて云うに、『勅を奉るに、よろしく奏状に依れ』ということであり、よろしく承知して、宣に依ってこれを行え。符が届けられたならばただちに執行せよ」
弘仁十三年〈822〉六月十一日
「允許大乗戒官符」
(『伝教大師全集』, vol.5, 付録, p.109)
朝廷は、彼が弘仁十年に上奏していた『請立大乗戒表』における要望、そしてその詳しい案が書き連ねられた一連の「学生式」をその通り允許したのでした。
しかしながらそれは、最澄自身がその正統性をアレコレ主張していたとしても、朝廷自ら「法務の綱維」として設置した諮問機関でもあった僧綱の審議で認められたものでなかった以上、どこまでも世俗的・政治的に許されたものに過ぎません。国家の承認を得たと言っても、最澄の主張が仏教として認証されたわけではありませんでした。
それは、前項において「俗法において僧と承認されること、及び承認された僧」と、「仏法において僧と承認されること、及び承認された僧」は必ずしも一致せず、異なると指摘しておきましたが、まさにその歪んだ構造が(再び)日本で生じることになった瞬間です。
とはいえ、最澄の遺志を実現しようと動いていた天台宗徒(特に光定)からすればついに実現した最も喜ばしいことであり、早速翌年の桓武天皇の忌日において、その年分度者二名を得度させています。
弘仁十三年六月四日。大師遷化。遷化之一七日後。菩薩僧官符下畢。弘仁十四年三月十七日國忌日両箇之人。得度已畢。
弘仁十三年〈822〉六月四日、大師が遷化された。遷化の七日後、菩薩僧の官符が下された。
弘仁十四年〈823〉三月十七日の国忌の日〈桓武天皇の命日〉、(天台の年分度者)二人が得度した。
光定『伝述一心戒文』巻中
(『伝教大師全集』, vol.1, p.568)
なお、ここで得度したという二名は、「六条式」に則り、ただ十善戒を受けることもって出家したこととする、極めて特異な方法に依るものでした。人を十善戒によって得度させる。それもまったく仏教としての根拠も前例も無い、故に他宗(というより仏教)で通用するはずもないことです。
十善戒にしろ梵網戒にしろ、それらは「僧俗共通して受ける戒」ではありますが、それで沙弥にも比丘にも成ることは出来ません。ただそのような戒を個人的に受けるか受けないかのことに過ぎず、それで立場が変わるものではありません。したがって、天台の年分度者となった者を他宗が僧として受け入れることは決してなく、むしろだからこそ、最澄がそこに目をつけて実行しようとしたのでした。
そして、十善戒によって得度させたと称する者には続いて梵網戒を受けさせ、以降十二年間は山を降ろさせずとことん思想教育するというのですから、彼に依る人材流出防止案は実に四重五重に張り巡らされた、恐ろしいまでに徹底的なものです。
その結果、最澄にそのような意図など無かったことでしょうけれども、純大乗に事寄せて様々な対策案を練り上げたことによって、実に皮肉なことに脱仏教の僧が生み出されていったのでした。後代の中世鎌倉期、比叡山から「新仏教」と肯定的に称され、その一方では「もはや仏教ではない」と評される、種々の浄土教徒や日蓮などが排出されていく淵源は、まさに最澄による大乗戒にまつわる主張とそれが実行されたことにあります。
ところで、その勅許が下った時期について、上記のように天台宗の伝える文書には明らかに弘仁十三年六月十一日であるとされており、従来そのように考えられてきました。しかしながら、六国史の一つ『日本後紀』に、といっても逸文として『類聚国史』に伝えられているものにではありますが、以下のように最澄の死の前日、弘仁十三年六月三日に勅許があったとされています。
嵯峨天皇弘仁十三年六月壬戌。傳燈大法師位㝡澄言。夫如來制戒。隨機不同。衆生發心。大小亦別。伏望。天臺法花宗年分度者二人。於比叡山。毎年春三月先帝國忌日。依法花經制。令得度入海。十二箇年。不聽出山。四種三昧。令得修練。然則。一乘戒定。永傳聖朝。山林精進。遠勸塵劫。許之。
嵯峨天皇弘仁十三年〈822〉六月壬戌〈3日〉、伝灯大法師位最澄が言うところの、「そもそも如来の制戒は(衆生の)機根に随ったものであって同じではありません。衆生の発心も大と小とまた別であります。どうかお願い致します、天台法華宗の年分度者二人は、比叡山において毎年の三月、先帝の国忌の日に、『法華経』の制に基づいて得度・受戒させ、その後は十二年間、比叡山から出ることを許さず、四種三昧によって修練させることをお許し下さい。それをお許しいただけたならば、一乗の戒と定とは永く聖朝に伝わり、山林精進によって遠く未来の果てまで勧められることになりましょう」〈以上、最澄が弘仁十年に奏した『請立大乗戒表』〉について、これを許す。
『類聚國史』巻百七十九 仏道六 諸宗
(新訂増補『國史大系』普及版, 『類聚国史』, vol,4, p.238)
菲才など『類聚国史』においてこの条を見た時には、その日付を甚だ不審に思いはしたものの、ただの誤記か誤伝であろうなどと端から考え、それ以上気にもとめていませんでした。しかし、二十世紀末に佐伯有清『伝教大師伝の研究』により、この記述の信憑性が高いことが指摘されています。すなわち、『類聚国史』における記述は正しく、最澄の死の前日に勅許があってそれが死の一週間後に允許として下った、ということのようです。
なお、この大乗戒勅許を得るため直接に天皇に具申したのは、藤原良房でも大伴国道でもなく、最澄や空海が入唐した際の遣唐大使であった 藤原葛野麻呂の七男、藤原常永であったとされています。
一乘戒牒書御筆文延暦遣唐大使葛野麻呂七男也承和遣唐大使師嗣之弟也
弘仁十四年六月。先師忌日。爲報於恩。達殿上。御書戒牒事。彼狀云。弟子先師承命。彼時師云。爲我勿作佛。爲我勿寫經。述我之志。者臨終之時。深欲傳一乘戒。寄此之旨。爲果師志。美作介藤原常永大夫。寄遺言事。達弘仁大皇。大皇勅許。嚴筆書微僧戒牒。而恩勅賜之。《後略》
一乗戒牒書御筆文延暦遣唐大使の藤原葛野麻呂の七男であり、承和遣唐大使師の藤原常嗣の弟である。
弘仁十四年〈823〉六月、先師忌の日、恩に報いるために殿上に達した御書戒牒の事。その状に云く、「弟子、先師〈最澄〉の命を承わる。その時、師が『我が為に仏を作すこと勿れ。我が為に写経すること勿れ。我の志を述べよ』と云われた。そのように、(師は)臨終の時にも、深く一乗戒を伝えることを望まれていた。この旨により、師の志を果たすために、美作介〈現岡山県北東部の次官〉藤原常永大夫が(最澄の)遺言の事について弘仁大皇に上達すると、大皇は勅許された。厳筆を揮って微僧〈光定〉の戒牒〈嵯峨天皇宸翰 光定戒牒(国宝)〉を書したまわれ、そして恩勅を賜れたのである。《後略》」
光定『伝述一心戒文』巻中
(『伝教大師全集』, vol.1, p.576)
ここには勅許を得たその日付は記されておらず、今までそのように読まれてきたように、普通に読んだならばそれは最澄の死後のことであったと解されるものです。そこでしかし、近年指摘された六月三日に勅許があったのが真であるならば、ここにいわれる「臨終」とは死の直前というより、死の床に着いてからのことであったということになるでしょう。
従来は最澄がその志を果たすことなく死去したことに同情が寄せられ、また最澄の死をもってそれまで対立してきた僧綱の口をつぐませ大乗戒の勅許がなされたと考えられてきました。いずれにせよ、「最澄の死」がきっかけとなった勅許であることに変わりなく、もはや明日をしれぬ死の床にあって一刻の猶予も無いことから藤原常永が嵯峨天皇に上奏し、ついにその間際に裁断を得たということであったようです。
このように見たならば、最澄の臨終の言葉として取り沙汰される、上掲の「我が為に仏を作すこと 勿 れ。我が為に写経すること勿れ。我の志を述べよ」という一句は、しばしば一般に理解されているようなホンワカした高尚な意味の言葉ではなく、明瞭に「私が死んでも、大乗戒の勅許を得るための政治運動を続行せよ」というものであったと解さなければなりません。
徳一との論争も中途半端なまま一方的に終了を自ら宣言し、空海から密教を伝受されることも頓挫するなど不如意の連続であった最澄。そんな彼にとって、天台宗の相次ぐ僧徒離散を止められずいずれは衰亡、という最悪の事態だけはどうしても避けなければならず、現実問題それが最後の砦となっていたことから、これはどうしても弟子にそう強調しておいたのでしょう。
もっとも、勅許が下ったのが最澄の死前日であったとして、もし最澄がその知らせを聞いたならば必ずや何らか喜びの言葉を述べ、あるいは何がしかの喜悦の反応を示したに違いなく、それを光定も漏らさず記録したことでしょう。勅許が下ったことの知らせは、比叡山であれば半日で届けられる距離。最澄の死が目前であることを知っている者であれば、いや、必ず知っていたでしょうから、ただちに山に知らせたに違いない。
けれども光定にせよ『叡山大師伝』を著した一乗忠にしろ、そんな最澄の姿があったことを書き遺していません。したがって最澄は少なくとも二日以上は意識なく朦朧としたまま、すなわち勅許があったことを知らぬままにその最後を迎えたと考えられます。
(藤原常永が当時美作介であったならば、その官位は従六位であったと思われますが、いくら火急とはいえその上奏が容易く天聴に達して直ちに勅許されるとも思われないため、やはりそこには藤原良房などの力添えがあったであろうと愚考しています。)
現在、天台宗では、最澄は『顕戒論』によって僧綱からの「根拠がない」であるとか「前代未聞」などといった批判をすべて残り無く論破し、誠実に答え尽くして問題は解決した、ということになっています。そしてその故に最澄の主張はついに認可されたものと考えられています。けれども、それはあくまで日本における天台宗内における甚だしく独善的な評価であって、全く事実に反するものです。
『顕戒論』を直に、そして確かに読んだならば、僧綱に対する最澄の反論とは、その挙げた根拠を過剰解釈や誤読したものであったり、時にただの論点のすり替えやこじつけであったり、まったく問題の本質に触れずにやり過ごそうとしていたり、あるいは僧綱からの批判の中でも瑣末な点をことさら取り上げて文字通りただ罵倒しているだけとなっていることがままあることを知るでしょう。
特に最澄の論拠として致命的であった点の一つは、玄奘や法顕、義浄など天竺を長年周遊した僧による『大唐西域記』や『仏国記』、『南海寄帰内法伝』における印度や故国における僧院のあり方に関する記述についての誤解・誤読です。そしてまた自身が唐で受けたとする梵網戒に関する、支那の諸徳におけるその扱いや位置づけなどに対する曲解でした。それらに対する最澄の理解はあまりに乏しく、それでいてしかしそれを自身の主張が正しいことの根拠として長々と挙げ連ねているために、甚だしい我田引水となっています。
すなわち、繰り返しますが、最澄は僧綱との論争に勝利した、などと到底言えるものではありません。
さて、いま最澄の主張を詳しく知るには『顕戒論』を見なければならない、と述べたばかりです。しかし、無知という眼帯をかけ、あるいは「吾が仏尊し」といった宗我に凝り固まっった色眼鏡をかけ続けているようではそれを読んだとて、最澄の主張の理非曲直を見分け、その是非を問うことは出来ません。
そして現代には、『山家学生式』をして「最澄のすぐれた教育理念が表れたもの」などであるとし、「最澄は偉大な教育者であった」と評価するための根拠とするような輩があります。笑うべし。そのような者は、この『山家学生式』や『顕戒論』をまともに読んだことなどないか、一応ひと通り目を通したことはあってもまるで理解できていない。もし彼最澄がすぐれた教育理念をもつ「偉大な教育者」であったならば、そもそもこの『山家学生式』などといわれる一連の書を帝に上奏する必要など最初から全く無かった。
それは、『韓非子』にある有名な「矛盾の喩え」によって表され揶揄された事態が、最澄において現出したものです。
歴山之農者侵畦。舜往耕焉。期年甽畝正。河浜之漁者争坻。舜往漁焉。期年而譲長。東夷之陶者器苦窳。舜往陶焉。期年而器牢。仲尼歎曰。耕漁与陶非舜官也。而舜往為之者。所以救敗也。舜其信仁乎。乃躬耕処苦而民従之。故曰聖人之徳化乎。或問儒者曰方此時也。堯安在。其人曰堯為天子。然則仲尼之聖堯奈何。聖人明察在上位。将使天下無姦也。今耕漁不争陶器不窳。舜又何徳而化。舜之救敗也。則是堯有失也。賢舜則去堯之明察。聖堯則去舜之徳化。不可両得也。楚人有鬻楯与矛者。誉之曰吾楯之堅莫能陥也。又誉其矛曰吾矛之利。於物無不陥也。或曰以子之矛。陥子之楯。何如。其人弗能応也。夫不可陥之楯。与無不陥之矛。不可同世而立。今堯舜之不可両誉。矛楯之説也。
歴山〈現在の山東省済南にある千仏山とされる山〉の農民が、田畑の境界について争っていた。そこで 舜 〈古代中国の伝説的帝王.儒教において聖人とされる〉が行って(その農民らと共に)農耕に従事したところ、一年で田畑の境界が正しく定められた。河浜の漁民が漁場を争っていた。そこで舜が行って(その漁民らと共に)漁業に携わったところ、一年で年長者に(漁場を)譲るようになった。東夷の陶工の器は質が悪く歪んでいた。そこで舜が行って(その陶工らと共に)陶芸に関わったところ、一年でその器は固くしっかりしたものとなった。(この話を聞いた)仲尼〈孔子〉は感歎し、
「農耕と漁業、そして陶芸とは、舜の官としての役目ではないにも関わらず、舜自身が行ってこれを為したことは、(社会の)誤りを正しためである。舜とはまことに仁の人である。自らが農耕するなど困難に対処し、民衆はこれに従ったのだ。これぞまさに聖人の徳化というものである」
と言った。そこで、ある者が儒者に質問した。
「この時、堯〈実子ではない舜に帝位を譲ったとされる支那古代における伝説的帝王。舜と共に儒教では聖人とされる〉はどこで何をしていたのか」
するとその儒者は、
「堯は天子〈皇帝〉であったのだ」
と応えた。
「そうであるならば、仲尼が堯を聖人とするのはどういうことであろう。聖人が(世間のことに)明察であって(国・社会の)上位にあるのであれば、まさに社会に悪しきことを無くならせるであろう。(堯がそのように天下を治めたならば、)その時、農民も漁夫も争うことはなく、また陶工も真っ当な仕事をするであろう。すると、舜が出て民を徳化する余地などない。舜が(社会の)誤りを正したということは、すなわち堯に失政があったからこその話である。もし舜を賢人であるとするならば、それは堯が明察でなかったことを意味する。もし堯を聖人であったとするならば、舜の徳化の出る幕はない。(堯と舜とが聖人君主であったという)その両立はありえないのだ」
(それがどういうことであるかの譬えを言おう。)
「楚の人で、楯と矛とを売る者があった。その者は(その自らが売る盾を)誉め、
『私の楯の堅いことは、これ貫き破るものは無いほどである』
と言い、また同時にその矛を誉めて、
「私の矛の鋭いことは、物で貫き破るものが無いほどである』
と言った。そこである者が、
『おまえの矛でもって、おまえの楯を突いたならばどうなるのだ」
と聞いた。するとその人は何も答えることが出来なかった。そのように、突き破ることが出来ない楯と突き破れないものがない矛とは、世において同時に並び立つことは出来ない。今、堯と舜との二人を(そのいずれもが聖人であると)誉め称えることが出来ないことは、この矛と楯との説に同じである」
『韓非子』難一
韓非が、孔子など儒家によって堯と舜とのいずれも聖人として眺め崇拝されることの不合理であることを批判するのに用いたこの譬えは、そのまま最澄と『山家学生式』および『顕戒論』との関係についても当てはまります。最澄が真に優れた教育者であり宗教指導者であったならば、『山家学生式』や『顕戒論』などを著す必要に迫られる状況になることなど決して無かったためです。
そしてまた『山家学生式』は、その内容が僧綱に批判され否定されたのも無理もないものとなっており、その批判に反駁しようとして著された『顕戒論』もまた、『山家学生式』の無理をさらに強弁するため、種々の仏典の我田引水や牽強付会で糊塗し、あるいは僧綱に対する罵倒を繰り返すものとなってしまっています。
小人の過つや必ず文る。
(過ちは誰でも犯すものだけれども)小人〈君子の対義語.小人物〉は過ちを犯したならば、必ず(その非を認めず)誤魔化しの言葉を述べ立てる。
『論語』子張
自身の主張の正しいこと、その論拠がいかなるもので、それが合理的であり正当であるのを証明するのは必ずなすべき重要なことです。しかし、ただ何でもこじつけて反論すれば良いというものではありません。いや、最澄が聡明な人で、その学徳も優れていたことは間違いなく、そのことは『山家学生式』に見られた彼の人材流出防止案を見ても明らかです。けれども、その主張と根拠はあまりにも無理筋であり、また最澄自身のそれまでの言動とも種々に撞着したものとすらなっています。
最澄の当時の状況と、そのような主張をなすにいたった経緯を客観的に見たならば、彼にとってもはやそうする他に術はなかったのでしょう。
上来示したように、最澄が天台宗存亡の危機を打開するための一手として考案し、上奏した『山家学生式』。それはあくまで「天台宗から徒弟離散を防ぐための行政制度変更を求めた政治的構想の陳情書」です。これを「最澄の高邁な教育理念を実現するための宗教的構想の陳情書」であったなどと捉えることは、といってもそのような人こそ世間には非常に多いのですが、まったく宛の外れたものです。