先に述べたように、『仏説無常経』本文自体は極めて短いものでわずか漢字296文字に過ぎず、『般若心経』の274文字とほぼ同程度の小経です。
その内容は老病死の厭うべき不如意なるものであること、生命として不可避の根本的苦であることを強調するものです。そしてまた、そもそも仏陀が出家してついに仏陀となり、その所証の真理を法〈教え〉と律〈戒律〉として説かれたのも、生ある者が逃れることの決して出来ない老病死という苦が存ずるからこそであるとも説かれています。
『無常経』とはまさにその経題通り、無常をその主題とするものです。無常と言えば、たとえば仏陀の教えの特徴として挙げられる「諸行無常 諸法無我 涅槃寂静」の三法印、あるいは「諸行無常 諸法無我 涅槃寂静 一切皆苦」の四法印として挙げられる「諸行無常」を想起するかもしれません。
しかし、この『無常経』では「諸行」などとは言わず、より生命として直截的に感じ経験せられる、老・病・死とそれにまつわる苦を通して、一切世間の無常なることを示すものです。そこで仏教では、苦に四苦八苦あるいは三苦があると分析されています。
| 1. | 生苦 jātipi dukkha |
誕生に伴う苦しみ | |
|---|---|---|---|
| 2. | 老苦 jarāpi dukkha |
老いに伴う苦しみ | |
| 3. | 病苦 byādhipi dukkha |
病に伴う苦しみ | |
| 4. | 死苦 maraṇampi dukkha |
死に伴う苦しみ | |
| 5. | 怨憎会苦 appiyehi sampayoga dukkha |
不快なものと関わることによる苦しみ | |
| 6. | 愛別離苦 piyehi vippayoga dukkha |
好ましいものと別れ離れることによる苦しみ | |
| 7. | 求不得苦 yampicchaṃ na labhati tampi dukkha |
求めるものを得られないことによる苦しみ | |
| 8. | 五蘊盛苦 saṃkhittena pañcupādānakkhandha dukkha |
五薀への執着、五取蘊による苦しみ | |
世間にて、それが仏教に由来するものであると知らずに「四苦八苦」という言葉が比較的用いられていても、その原義は意外と知られていないようです。その意味は、今上に示したような実に具体的な人生における様々なる、それは誰でも必ず不可避に味わなければならない、苦しみどもです。
しかし、また苦しみを四苦八苦とは視点を変えて分類した場合には、苦苦・壊苦・行苦という三苦が言われます。仏教とは、平易にそして端的に云うならば、苦しみからの解脱を目標とする宗教です。故にその脱すべき苦しみについて、様々に考察してきました。
| 1. | 苦苦 dukkha-dukkha |
痛み等の肉体的苦しみ |
|---|---|---|
| 2. | 壊苦 vipariṇāma-dukkha |
自分が好ましい・愛おしいと思うモノが、痛み・病み・壊れ・死にゆく等、好ましくない状態に変化するときに感じる精神的苦しみ |
| 3. | 行苦 saṅkāra-dukkha |
存在すること自体の苦しみ、根源的苦 |
このうち苦苦・壊苦を理解することは誰しも容易いことです。人は、それが苦しみであることを日常の経験のうちに知りうる。いや、ある程度年を重ねた者なら誰でも、もうすでに十分すぎるほど知っていることでしょう。そして苦苦とは、生きてその身体がある限り、これは仏陀であろうと例外なく、決して逃れることの出来ないことであることもたやすく理解できることでありましょう。
しかし、行苦は異なります。これはそう簡単に理解しうるものではありません。これを完全に理解するということは、すなわち悟りに至ることとほとんど同じです。
この行苦ということについて、説一切有部から出て経量部という部派を設立したと云われる尊者Kumāralāta〈鳩魔羅多〉という紀元一、二世紀頃の大学僧によると伝承される偈文で、譬喩をもってよく表現したものがあります。
如以一睫毛 置掌人不覺 若置眼睛上 為損及不安
愚夫如手掌 不覺行苦睫 智者如眼睛 緣極生厭怖
一本のまつ毛を手のひらに置いても人はそれを覚知することがない。しかし、もし眼球の上にそれを置いたならば、(眼を)傷をつけ、あるいは不快感を覚えるようなものである。愚か者は手のひらのようなもので、行苦というまつ毛を覚知しない。智者は眼球のようなものであり、これ〈行苦〉に大変な畏れを抱く。
世親菩薩『阿毘達磨倶舎論』賢聖品(T29, p.114b)
行苦とはそのような普通の人は何とも思わない、それが苦であるなどと全く思いもしないものです。
そもそもこの場合にいわれる行とは、サンスクリットsaṃskāraあるいはパーリ語saṅkāraの漢訳ですが、実はこの行というもの自体、理解するのが中々難しい概念です。行という漢訳語一文字では、一見して何を意味するのかまるで理解できないため、現代日本の仏教学者は大体これを「潜在的形成力」などと訳して言う場合が多くあります。しかし、率直に言ってそれはわかるようで全然何のことだかわからない訳です。
そして結局、ただ先例に従ってそういうだけの庸流の学者も、またそれに倣うだけの僧職者も大概の場合、「やあ、行とは現代的にいえば潜在的形成力のことであって、実にめでたい」といった調子で、結局なんだかわからないまま済ましてしまっています。けれども、この行というものは仏教を行じていく上でその理解が不可欠の、非常に重要な概念です。
行とは何か、その定義は伝統説に従ったならば明瞭で、以下のようなものとされます。
問五蘊有爲皆應名行。何縁於一獨立行名。答如十八界雖皆是法。而但於一立法界名。廣説乃至三寶三歸雖皆是法而但立一法寶法歸。如是五蘊雖皆是行。而但於一立行蘊名亦無有過。復次行蘊有一名。餘蘊有二名。一名者。謂共名。謂五種蘊皆是行故。二名者謂共不共名。共名如前。不共名者。謂餘四蘊欲令易了顯不共名。行蘊更無不共名故。但顯共名故名行蘊。《中略》 行謂造作。有爲法中能造作者思最爲勝。思但攝在此行蘊中。故此行蘊獨名爲行
問:(色・受・想・行・識の)五蘊とは有爲〈saṃskṛta. 造られたモノ。因縁所生法〉なのであるから、(五蘊の)すべては行〈saṃskāra〉の名が付されるべきであろうのに、どのような理由で一つに限って行蘊と言われるのであろうか。
答:(六根・六境・六識の)十八界すべては法〈dharma. 存在するモノゴト〉であるのに、しかしただ一つをもって法界と名付けるようなものである。あるいは(仏・法・僧の)三宝や(仏帰依・法帰依・僧帰依の)三帰依もすべて法〈dharma. 真理〉であるのに、しかしただ一つをもって法宝・法帰依とするようなものである。そのように、五蘊はすべて行ではあるけれども、しかしただ一つをもって行蘊と名づけることに、何の過失も無い。また次に、行蘊はただ一つ名のみであるが、他の蘊には二つ名がある。一つ名とはいわゆる共名である。すなわち五種の蘊はすべて(本来的には)「行」であるからである。二つ名はいわゆる不共名である。共名については前述の通り。不共名とは、すなわち他の四蘊がいかなるものか解しやすくしようと(それぞれ)不共名を以て表したものである。しかし、行蘊は(つけるべき)不共名が無いために、ただ共名を以て「行蘊」と称するのだ。《中略》
行とは「造作」のことである。有為法の中において、よく造作するのは思〈cetanā. 意思〉が最たるものである。そして思はこの行蘊の範疇に包摂されることから、この行蘊にのみ行の名が冠される。
五百大阿羅漢造『阿毘達磨大毘婆沙論』巻七十四(T27, pp.384c-385a)
これは五蘊のうち行蘊について論じられている一節です。
そもそもこの世の存在全ては因(原因)と縁(条件)によって「造られたモノ」すなわち有為であり、よって(本来的にはこの世の一切は)「行」に包摂されるべきものである。けれども、行蘊以外の諸法は他の名をもって表することが出来るからその他の名を用いてその範疇に納める。ただ特に行蘊に包摂されるのは、「行」以外に表しようのないものであるから特に行蘊というなどと説明されています。
そして、そこでそもそも「行とは造作 のことである」と定義されます。造作とはすなわち「(物事を)作り出す働き」のこと、つまり「(ある行為に基づいて)結果を生じさせる力」のことです。
いきなり「行とはsaṃskāraの漢訳で、現代で言えば潜在的形成力です」などと言われてもまったくわかりはしません。むしろここで「行とは造作」との伝統的定義のほうが、といってもそれは行の原語を直訳したようなものですが、しかし最も端的でその原義を比較的把握しやすいものといえます。
そしてこのように見たならば、ようやく学者の言う「潜在的形成力」とはそれをなんとか現代的に表しようと苦心して捻り出されたものだったか、と理解することも出来る。けれどもそれは同時に、一面的で舌足らずな言葉・表現であることも判ってしまう。伝統説ではまた、そのうち最も力の強いものが思であるとも定義されるためです。
では思とは何か。思とはcetanā の訳で、いわゆる意思のことです。しかし、そこでまた「思とは意思のことです」などといわれても、やはりちょっとピンとこない。それは心の根本的働きであり、より具体的には「考えようとする精神的働き」あるいは「(知覚対象を)求めようとする精神的働き」です。人が閑処に修定して普段の粗雑な心の動きを鎮めていった時、しかしそれでも最後まで残って動き続ける何らか心の働きがあることを知るでしょうが、まさにその一つが思です。
これはつまり、(思という)心の行為が諸々の事象の元となり、それらを生み出し形作る、ということです。そのような理解はそもそも阿毘達磨において初めて為されたのではなく、これは無論と言うべきか、そもそも仏語に基づいたものです。
心為法本 心尊心使 中心念善 即言即行 福樂自追 如影隨形
心は法〈dharma. 存在するモノゴト〉の本である。それは心を先とし、心が作るもの。心に善を念じてあるいは言い、あるいは行えば、福楽は自らに追いしたがう。影が形に従うように。
『法句経』双要品法句経第九(T4, p.562a)
随分横道にそれてしまいましたが、行苦とは存在すること自体、および我が心を元にして未来に存在を作り出すことを苦しみとするものです。しかし、言葉としてはそのようなものかとある程度は理解できても、それを恐るべき苦として受け止めることは、やはり尊者鳩魔羅多がそう言ったように、普通の人には無いことでしょう。
行苦とは、「死んじゃおうかしら、人生が嫌になったから」「もう生きたくない、消えてなくなりたい」などと言う人の感ずる人生へのそれとは異なるものです。それは無有愛といわれる存在しなくなることへの憧れ・欲求であり、渇愛(根本煩悩)の現れの一つに過ぎません。
さて、しかしこの『仏説無常経』は、いや『三啓経』は、誰しも正常なる意識ある人や神であれば理解できる苦しみたる老・病・死を通し、生命の無常なることを説いたものです。一般に、その教えや思想の内容が高尚で難解であることをもって、卑近で平易なものより勝れ、尊いとすることがあります。確かにそう言えることもあるでしょう。が、それはあくまでその卑近で平易なるものを確実に理解し、踏襲してこそのこと。
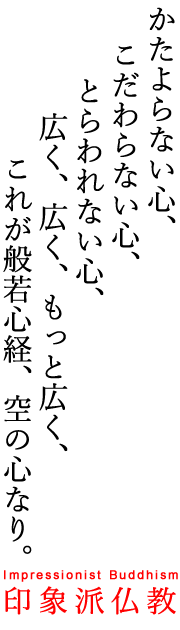
たとえば、同じような分量の『般若心経』など日本ではあまりに有名で、自身を仏教徒だと意識しない人ですら暗誦することが出来るのも珍しくありません。そして信じられないほど多くの人・出版社からその解説本が出されて書店の棚のあちらこちらに並んでいます。が、非常に面白いことに、その内容をまともに解する人は著者・読者ともにほとんど存在していません。むしろ、まったくの見当違い、的外れの理解をして済ましている者こそ多くある。
あるいは抽象的・情緒的で全然わからない、頓珍漢な解説者の話を聞きもしくは読んで、『般若心経』だけでなく仏教への興味をすら失ってしまったり、仏教など所詮前時代の遺産に過ぎない、蒙昧の人の教であると断じてしまったりする者もあります。
なぜか。
それは仏教の基本とするところ、仏教の世界観や価値観、そして釈尊の生涯など全くなおざりにして理解せず、また理解もさせず、いきなり身近にあって短いからというような理由で「猿でもわかる 般若心経」といった調子を取るからでありましょう。しかしそれは、決して猿ではわかり得ることでない。
あたかもそれは、そもそも四則演算など算数が出来ない者に数学を教えようとするようなもの。そしてその数学も段階をまったく無視して、いきなり高等数学を教えようとするようなものです。しかも、理系の学習過程を全く履修しておらず無論理解もしていない、純然たる文系の人がその教鞭を取っているというのであれば、それはもはや何かの冗談、喜劇以外の何者でもありません。
ここまでいくともはや笑えないと思えるかもしれません。が、しかしそれと同様の事態が『般若心経』などについては平然と、ごく当たり前のように行われています。結局、それは現代における日本仏教の程度、というものを端的に示したものであるのでしょう。
繰り返しの言となりますが、平易で短く誰しもが憶えやすいもので、またその意義は解しやすく、しかも音楽的詠唱が許されており、日常に度々用いて親しむことが出来る『無常三啓経』は、その故にもっとも身近で根本的な我が身命の無常を憶念させるものです。
仏陀の随行として最も長く二十五年もの間側仕え、その教えに最も多く触れてきた阿難尊者は、しかしその偉大な師であり親族でもあった釈尊の死が目前に迫っていることを知って、それを受け入れられず、独り泣いていました。
そんな阿難尊者に対し、まもなく死を迎えようとする釈尊は優しくなぐさめ、またたしなめられています。
alaṃ, ānanda, mā soci mā paridevi, nanu etaṃ, ānanda, mayā paṭikacceva akkhātaṃ ―‘sabbeheva piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo aññathābhāvo’; taṃ kutettha, ānanda, labbhā. Yaṃ taṃ jātaṃ bhūtaṃ saṅkhataṃ palokadhammaṃ, taṃ vata tathāgatassāpi sarīraṃ mā palujjī’ti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
「やめよ、アーナンダ、悲しむな。嘆くな。アーナンダよ、私はあらかじめこのように(繰り返し)説いたではないか。――『すべての愛しいもの、喜ばしいものからも別れ、異なるに至る』と。アーナンダよ、それはなんであれ、生じ、存在し、つくられ、滅びるものである。それを一体どうして『如来の身体が滅びないように』などとしえるであろうか。そのような理は存在しない」
DN, Mahāparinibbānasutta, Ānandaacchariyadhamma
預流果を得た聖者ではあっても、いまだ阿羅漢に達していない阿難尊者にとって、偉大な師との別離は、それが必ず訪れるものだと頭ではわかっていても、しかし真にわかりはしませんでした。そう、無常という真理、死が誰にも等しく訪れてくるということ。そしてそれが多くの場合、いつ訪れるかわからず、突如としてやってくるということ。それは、誰しもがたやすくわかったつもりになることで、しかしその実わからないことです。
そのような、人が迷いのうちに死に、迷いのうちに生まれてまた死んで際限の無い様をして、空海はこのような言葉で表現しています。
悠悠たり悠悠たり、太だ悠悠たり。内外の縑緗、千萬の軸あり。《中略》
杳杳たり杳杳たり、太だ杳杳たり。道と云ひ道と云ふに百種の道あり。
書死え諷死へなましかば、本何がなさん。知らず知らず、吾れ知らず、
思ひ思ひ思ひ、思ふに聖も心ること無し。牛頭、草を甞めて病者を悲しび、
断菑、車を機つりて迷方を愍ぶ。三界の狂人は狂せることを知らず、
四生の盲者は盲せることを識らず。生れ生れ生れ生れて生の始めに暗く、
死に死に死に死んで死の終りに冥し
それ生は吾が好 にあらず。死また人 悪む。しかれども猶を生まれ之き生まれ之いて六趣に輪転し、死に去り死に去て三途に沈淪す。我を生じる父母も生の由来を知らず、生を受くる我が身もまた死の所去を悟らず。過去を顧れば、冥冥としてその首を見ず。未来に臨めば、漠漠としてその尾を尋ねず。三辰、頂に戴けども暗きこと狗眼に同じく、五嶽、足を載すれども迷えること羊目に似たり。日夕に営営として衣食の獄に繋がれ、遠近に趁り逐て名利の坑に堕る。《原漢文》
限りなし限りなし、なんと限りないことであろうか、《中略》
内外の縑緗〈仏教および外教の書物〉には千も万もの巻軸がある。
暗く深し暗く深し、なんと暗く深いことであろうか、
道〈思想・宗教〉という道には百種の道がある。
書を絶やし、諷誦〈素読・暗誦〉することも無ければ、真理をいかに知られよう。
(もしそうなれば)知らず、知らず、私も知ることはなく、
思い、思い、思い、思ったとして聖者も知ることはない。
牛頭〈神農〉は草から薬を作って病める者を哀れみ、
断菑〈周公旦〉は車を操り方角を示し迷った者を愍んだ。
三界〈全ての宇宙〉の狂人は自ら狂っていることを知らず、
四生〈全ての生物〉の盲者は己が盲ていることを識らない。
生れ、生れ、生れ、生れて、生の始めに暗く、
死に、死に、死に、死んで、死の終りに冥し。
そもそも生〈生まれ、そして生きること〉は私の好むことではなく、また死は人の憎むものである。しかしながらなお、(我々人は)生まれ変わり、生まれ変わりしながら(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天いずれか)六趣に流転して、死に去り、死に行きながら(地獄・餓鬼・畜生の)三途に沈淪している。私を生んだ父母であっても、(我が)生の由来を知らず、生を受けた我が身もまた、死の行き先を悟れはしない。過去をかえりみたとしても、冥冥としてその始まりを見ることは出来ない。未来を臨んだとしても、漠漠としてその終わりを知ることなど出来はしない。三辰〈太陽と月と星々〉をこの空に頂いていながら暗暗としていることは犬の眼に同じく、五嶽〈支那における五名山、神話で盤古が死んで出来た山とされる。ここでは「大地」の意〉を足下に踏んでいたとしても迷えることは羊の目に似ている。昼夜に営々として衣食に追われる監獄に繋がれ、遠近わかたず追い求めて、名誉と財産という深い坑に堕ちている。
空海『秘蔵宝鑰』巻上(『底本 弘法大師全集』, vol.3, pp.113-117)
これではいけない。しかし、我々人は、どうにもならず、どうにも出来ずに生まれては死に、生まれては死んで、ひたすら苦しみの循環の中に漂うのみ。
日本の近世の大阪・京都で活躍した慈雲は、空海と慈雲とでは時代が随分異なりますが依って立つところと向いている方角はまさしく同じで、無常を憶念することについてこのような言を残しています。
此の五尺の身が、暫くは穏かに、暫くは病悩し、平癒して壮健に復るかと思へば、また諸の疾病を生ずる。日を送り、月を送り、歳を累ねて、何事か有ると思へば、終に衰老に帰する。膚は皺む。歯は落る。鬚髪は白くなる。腰はかゞむ。目は暗くなる。耳は遠くなる。此に極ったことぞ。たとひ智者の天地古今の理に通達するも、此を免れ得ぬ。勇者の力萬鈞を擧げ、一人千人に當るも、此を免れ得ぬ。此の事を决徹して疑はねば、聖智見を得る基となる。斷常二見の深坑は、此の中に超過する。今日且く少壮なるまゝに諸の戯笑遊興に心をよせ、悠然として月日を送るを迷と云ふじゃ。 此の身が如是世界に在る間に、或は水火風難に遇ふ。饑饉闘諍などに逢ふ。王難賊難に逢ふ。臣たる者は、侫者に隔てられて、忠義有りながら、身を亡し家を敗る。君たる者は、姦臣に欺かれて、國をあやまり身を危くする。妻子眷属、朋友隣里の間、十に八九は憂悩じゃ。心に適はぬじゃ。或は大にもあれ、小にもあれ、敵と云ふ者も出で來たる。古書にも、女無美悪。居宮見妬。士無賢不肖。入朝見疑とある。威勢ある家は、鬼神其の短を求むる。才能ある士は、衆人憎み謗る。古今同様じゃ。此の事を决徹して疑はねば、聖智見を得る基となる。 《中略》 暫くは憂来り、暫くは喜來り、此の愁去れば又彼の愁來り。此の喜びごと満ずれば又余の願求を起して、日夜に忽忽として止むこと無きうち、遅きか早きか、終に無常に帰する。世相斯の如し。極ったことぞ。たとひ月は熱なり。日は冷なりと云ふとも、此の事は云ひ消されぬじゃ。此を决徹して疑はねば、聖智見を得る基となる。斷常二見の深坑を此の中に超過する。今日も徒らに過し、明日も徒らに過し、更に百年千年の營みを思ふを迷と云ふ。多少の人が、近きを棄てゝ、遠きに走る。内を忘れて外に求むる。邪見に墮ることじゃ。
この五尺〈約150cm〉の身体は、一時は穏かであったり一時は病に悩まされたりし、平癒して壮健になったかと思えば、また様々な病に罹る。日を送り、月を送り、歳を累ねてどうなるかといえば、終には老衰に至る。皮膚は皺む。歯は落ちる。鬚髪は白くなる。腰はかがみ、目は暗くなり、耳は遠くなる。人とはそう決まったものである。たとえ智者であって天地古今の理に通達していたとしても、老死を免れることなど出来はしない。すさまじい筋力を持つ勇者で、一人で千人に相当するようなのも、老死を免れられはしない。この事を確信して疑いなければ、聖なる智見を得る基となる。「断常二見」という深い坑を超過する。今のところしばらくは健康であるからといって、様々に戯れ遊び、遊興に心をよせて、悠然と月日を送ることを迷いと云う。
この身体がこの世にある間に、あるいは水難・火難・風難に遇う。飢饉や戦争、闘争などに逢う。王難・賊難に逢う。家臣たる者は、侫人〈言葉巧みにへつらう腹黒い者〉にそそのかされて、忠義がありながらも身を亡ぼして家が衰える。為政者たる者は、姦臣〈邪悪な家臣〉に欺かれて政を誤り、身を危くする。妻子や親族、朋友・隣里の関係も、十に八、九は憂い悩みである。決して己の心に適いはしないのだ。あるいは大なり小なり敵とすら云う者も出て来るであろう。(支那の)古書〈『史記』〉にも、「女は美しくとも醜くとも宮廷に勤め暮せば妬まれ、男は賢かろうが不肖であろうが朝廷に勤めて政治に関わったならば疑われる」とある。威勢ある家は鬼神からその付け入る隙を伺われ、才能ある者は人々から憎まれ謗られる。これは古今同様の有り様である。この事を確信して疑い無ければ、聖智見を得る基となる。 《中略》
一時は憂い、一時は喜び、この愁いが去ったとしても、また別の愁いが生じる。この喜び事が満たされたとしても、また他の願い事を起こして、日夜に一瞬たりとも止むことが無い。そのうち遅かれ早かれ、終には死を迎えることになるのだ。世間の有り様はそのようなもので、そう決まったことである。たとい月が熱き星で太陽が冷たき星であったとしても、それは否定の仕様もないことだ。この事を確信していれば、聖智見を得る基となる。「断常二見」という深い坑を超過する。今日も徒らに過ごし、明日も徒らに過ごし、さらに百年千年の営みがあるなどと考えることを迷いと云う。甚だ多くの人々が、(自分がまさに経験する我が人生という)近くを捨てて(言葉の上だけ崇高で深遠な思想という)遠くに走り、(自分が最も見るべき我が有り様という)内を忘れて(自分が決して経験し得ない空理空論というべき)外に求めている。そのようにして人は、邪見に堕ちるのだ。
慈雲『十善法語』巻第十二 不邪見戒之下
人は往々にして我が足元、依って立つその場所を顧みることをしません。いや、「しない」というより「したくない」という場合もあるでしょう。良く言えば、夢見がちなのが人であり、悪く言えば、ほとんど妄想の中に生きるのが人です。
ここで慈雲が口にする「断常二見」とは、断見と常見との二つの誤った思想、モノの見方です。断見とは、いわば唯物論であり、全ては所詮物質であって生命は死ねば全て終わりとする思想。常見とは、例えば死後には「不滅の魂」の如きものとなって永遠なる死者の世界や神の世界に往くという考え。あるいは永遠不滅にして絶対の、救いを与えてくれる神がいるとする思想。いずれも仏教からすれば事実誤認の、その故に邪な思想・モノの見方すなわち邪見とされます。
全ては必ず変化し滅びいく無常なるものであるということは、滅んだ状態すらまた永続せず再び生じてまた滅びる、というのが世界の真の有り様です。永遠に存するものはなく、永遠に滅することもありはしません。
"Handadāni, bhikkhave, āmantayāni vo, Vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādetha". Ayaṃ tathāgatassa pacchimā vācā.
「さあ、比丘たちよ、諸々の作られたもの(諸行)は衰え滅びる性質のものである。怠らずに励んで目的を果たせ」
これが如来の最後の言葉であった。
DN. Mahāparinibbānasutta, Tathāgatapacchimavācā
『無常経』とは、我々人が常に「知ったつもり」となっている我が老・病・死そして他の老・病・死を念じて忘れざらしむものです。またそれは、所伝の部派や重用してきた部派が異なるものであったとしても、同じ仏教徒としてその所説の内容に異論を挟む余地などありはしないことです。
その故に『無常三啓経』は、今の人もまた同じく奉じて日々に重用すべき、まさに「正法」を説く経典の一つです。
非人沙門覺應 識