『盂蘭盆経』あるいは『報恩奉盆経』の所説、悪趣(地獄・餓鬼・畜生)に生じた者を「盂蘭盆」によってそこから脱させる方法、これを視覚的に直ちに理解できるよう示したならば以下のようになります。
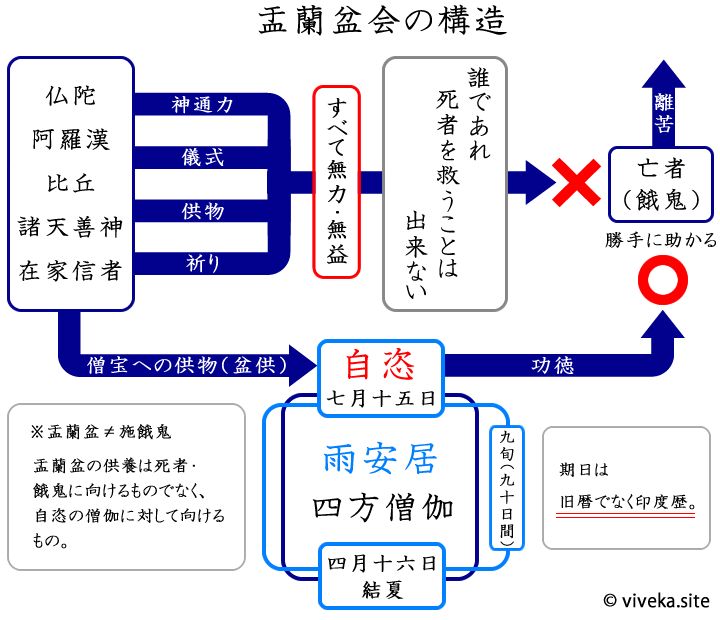
「誰であれ死者を救うことは出来ない」、ひいては「人は他者を救うことは出来ない」。これは仏教というものを知らない人、学ぼうとしている者が常に念頭に置くべき、非常に重要な点です。
(死者を救うことは出来ない、それを仏陀が端的に誰でも解しやすく説かれた教説として、「Asibandhakaputta sutta ―死者を救うことは出来ない」がある。また、そもそも読経の意義、目的とは何かを端的に示す、「『法句譬喩経』塵垢品第二十六」を参照のこと。)
『盂蘭盆経』にある「汝の母は罪根深結なれば、汝一人の力の奈何とする処に非ず。汝、孝順の聲、天地を動かすと雖も、天神・地神・邪魔外道・道士・四天王神も亦、奈何とする能わず」という一節は、そのような仏教における根本的な思想に基づいたものでもあります。そしてまたここで、仏陀の直弟子の中、最もその神通力が優れていたという人、目連が本経における対告衆となっていることが、それをより一層示唆したものとなっています。
というのも、それは目連尊者がいかにその最期を迎えたかに関わることであるからです。
実は目連の死は、外道の暗殺によってもたらされています。目連はそれが自身の宿業の果報であって、神通によって一時的に回避できたとしても畢竟じて避けがたいものであると諦観し、その持てる神通力を用いることなく凄惨な死を甘んじて受け入れたとされるのです。それと類似した話は、釈尊の氏族であった釈迦族の滅亡についても語り継がれています。人あるいは集団による何らかの業が、ひとたび結果する機と縁と熟したならば、誰であれ避けがたく救い難く、如何ともしがたい。そのような、業果というものに対する仏教の見方がそこに明瞭に現れています。
しかしそこで、そのような結果してしまった苦しみの状態から脱れさせる例外的な術として説かれたのが、自恣の日における僧伽への供養である、というのが『盂蘭盆経』の所説であり、盂蘭盆会の構造です。
そんな盂蘭盆会が大前提とするのが僧伽の存在です。またその僧伽が「印度歴の四月十六日」(旧暦では五月十六日)に始まる雨安居を正しく三ヶ月間行っており、その最終日である自恣を無事迎えていることです。安居を正しく過ごした自恣の日であるからこそ、そこに「威神の力」なる功徳がある。その生じた功徳が 廻向されることによって、現世の父母・七世の父母や六種親族が悪趣より自ずから脱するであろう、というのが本経の主張となっています。ただし、本経では「廻向」といわれず「呪願」とされる点には一応留意。
(僧伽とは何かについては別項、「七衆 ―仏教徒とは」および「Saṅgha vandanā(礼僧)」にて詳説。)
したがって、僧伽がなければ盂蘭盆会は成立しません。上図で示したように、誰であれ死者に直接供物を捧げたところで、あるいはその抜苦を懸命にどれほど祈ったところで、それら一切に意味はなく、どうにかなることはない、と仏教では説かれます。
ところで、世間には盂蘭盆会をして施餓鬼と同一視している者が、僧職者にすら非常に多くあります。しかし、盂蘭盆会は施餓鬼ではありません。盂蘭盆会とは、毎年の自恣の日における僧伽への布施の功徳により、縁者の「餓鬼ひいては三悪趣における生を終わらせること」を目的とするものであって、餓鬼など死者あるいはその他の境涯の者に直接何かを施すものでは無いからです。
今、日本で行われている「お盆」は、仏教の名の元、その行事であるとして一般に行われています。しかし、その実としては、仏教などほとんど全く関係のない習俗です。
では何らの宗教も一切関係ないかと言えばそうではない。それは、仏教に対抗してその諸々を摂取しつつ形成された、支那の道教における「 中元」の習慣、その前提にはそもそも古代支那における祖霊信仰があったのですが、まるきりそれを今の日本人が知らずに行っているものです。それは、儒教が特にもてはやされた江戸期にこそ始まる、比較的新しい庶民における仏教でなく儒教・道教に基づく俗信です。
今の日本人で仏教はもとより「道教とは何か」を知る者などほとんどありません。そもそも、道教が日本で宗教として明確に伝わり、信じられたことは歴史上ないことですから、ここでいきなり道教を持ち出されても困ってしまうかも知れない。しかし、祖霊・死霊がどこからか戻って来る、還ってくるなどという思想・世界観は、輪廻転生を大前提とする仏教には「全く」ありません。本来的にありえない。そして、祖霊を祀る、家としてこれを祭祀するというのは、儒教における極めて重要な思想・習慣で、また古代印度にも類似した思想・習慣はあったのですが、やはり仏教にはありません。
(ただし、支那における血族の祀りを欠かさず、父母を敬い、自らの血筋を絶やさないという「孝」や「悌」と全く同じでは無いものの、しかし、類似した思想は仏教にもあります。母父をよく敬い、また親族を養って、祖先を敬う、という思想です。それは例えば「Maṅgala sutta (吉祥経)」などに現れています。)
そもそも、安居明けの自恣の日に、在家信者らが僧伽を特別供養することは、仏陀釈尊以来行われ続けてきたことです。それは祖霊信仰・祖霊祭儀に特別関わることでなく、人々が僧伽に属する出家者への信頼、尊敬そして信仰があってこそ成り立つもので、実に印度以来、釈尊以来の伝統に基づいて行われ続けています。
日本仏教は祖霊信仰を容認し、包摂してきたからこそ存在し得た、などという見方を開陳する学者などもありますが、飛鳥・奈良・平安そして鎌倉時代といわゆる祖霊信仰を主題とし、言及して行った僧などありません。もし祖霊信仰・先祖崇拝が日本仏教存続に不可欠の条件であったと言うならば、近世以前の仏教は何であったというのか。いま祖師と云われる僧達が、先祖崇拝などほとんどまったく眼中になかった事実はいかがするのか、ということになるでしょう。
盆供が日本で単なる「祖先崇拝のイベント」に化したのは、江戸幕府により寺請制度が始まったことがまず一番大きくあると考えられます。そして近世以降のほとんどの僧徒がその制度の中で経済的に安住し、仏教など二の次となって安居などするわけもなく、故に庶民もそれが何かすら知る由もありません。安居が無ければ自恣もありません。したがって「盂蘭盆会」は成立しない。けれども七月十五日という日だけは古来の何か風習として取り沙汰され独り歩きし、それは先に述べたように道教の「中元」に当たるのですが、それとは気づかず仏教としての祖霊崇拝の日になった。そこで僧職者らは、その中元の日などにおける祖霊崇拝の装置、サービスとしての読経という儀礼を提供する業者となってしまいました。
僧職者らも本来的な僧など出来たものでないし、そもそもそうする積りなどまるで無いことから、その責務を「ホトケサマ」なる仏陀とは別物の何かに丸投げしてアリガタヤ、アリガタヤというばかりと自然となった。そうすると彼らの負うべき役割はあくまで「アリガタイ何か」との仲介者となり、その責務は最小となって最も楽な在り方となります。盆供を意味あるものとし得る存在はホトケでもカミでもなく、他でもない「僧」であるのですが、そんなものでは自分は全く無い。けれどもあくまで「僧」は自称したい、という経済的・社会的都合も、またそこにはある。
すなわち、日本で行われる盂蘭盆会には仏教的意義など一欠片としてありません。と、このように言われると脊髄反射的に「いや、そんなことはない」・「それは言い過ぎである。ここには仏教としての意味が必ず存在する!」と反論し、何とか仏教的意義を見出そうとする人もあるでしょう。そういう人はもう一度、本『盂蘭盆経』を頭から最期までしっかり読んでみると良い。
また、「我が宗では安居を今も確かに行っているのを知らないか!」と言う者もあるでしょう。しかし、それはただ夏であるから安居と銘打っただけの興行。せいぜい数日間、あるいは一ヶ月ほど、何ら正統な仏典の根拠もなく独自に行われる、別の何かに過ぎません。自身らが「仏教の安居」を行っているなどと誤認している人は、そもそも安居や自恣とは一体何であるかを律蔵など直接読んで知らなければならない。
「いやいや、日本は神道の国であり、八百万の神々を祀るものである。私はそんな神道に共感して愛着を感じる。そこでお盆とは、確かに仏教の形式は採っておりながらその意義も無いかも知れないけれども、むしろ神道的情緒によって行われてきたものでは?」と言う者も近年あります。が、神道とは何かをまるで知らずわからず、ただ何となくそう言うだけの人のどれほど多いことか。今日本独自などといわれる神道とは、仏教だけでなく儒教と道教の思想が極めて色濃く流れ込み形作られたものであり、また明治期以降に国家神道として恣意的に変質させられたものの名残りです。
(別項、「慈雲と神道」を参照のこと。)
なお、儒教をして「宗教ではない」とする市井の見方は無知に基づく誤認、あるいは無意識的に儒教の思想を絶対視していることによる客観の不在です。儒教がもっともよく成功し、表層的な名分・形式だけでなく、その説く倫理的・道徳的精神性が真に根付いたのは日本のみである、とすらいわれることがありますが、それはその一つの証でもある。しかし、日本人はそれに全く気づいていないのですが、それこそまさに絶対的信仰というべきものです。
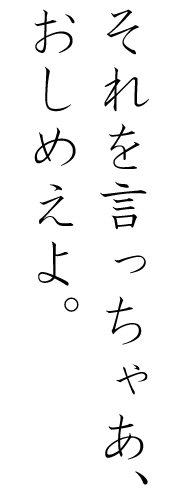
日本の僧職者らはそれに気づいてはいても、商売上そうハッキリ言う者はほとんど無く、むしろなんとかこれを擁護し正当化しようと妙な理屈をこねまくったおかしなことを言う者もあります。が、仏教の立場からして率直に言えば、今の日本で行われている意味での「お盆」などする必要は無い。また、それに付随して墓参りをする必要も、いや、そもそも必ずしも墓を作る必要すらありません。
とは言え、すでに日本の習俗・因習として定着しており、「毎年してきたことをいきなり止めるのも何だかなぁ」と思うのであれば、やるもよし、やらぬもよし程度に考え、どうしてもやりたければやれば良い。ただし、そこで「先祖の御魂が還ってくる」・「死んだあの人が私の所に戻ってくる」などと本当に信じてやるのは、仏教的には全く勧められません。そういうと、「いやいや、仏教思想に無いからといって、そう目くじら立てて排除することもないじゃない?」という、いわば穏健な意見も出されることでしょう。しかし、これに関しては仏教としてそう言うことが出来ない事情があります。それは、「有身見」という煩惱、しかもごく低級な思想・見方に位置付けられるものに直結することになるためです。
人の奥底には死んでも変わらぬ「魂」があり、人が死ぬとその「魂」だけが肉体を抜け出し、この世とあの世を行き来する。それはまた仏教が二極端として排斥する「常見」にも連なる思想です。したがって、これを安易に「まぁいいじゃないか」と容認することは、仏教本来としては出来ません。もっとも、このように本来をああだこうだと言ったところで、人の大半は中身よりまず習慣に従うもの。ズルズルと、しかしその故に時代や環境によってまた変質しつつ、なんとなく行い続けていくことでしょう。
近代、支那にキリスト教が重ねて伝えられたときも、やはり祖霊信仰・崇拝をキリスト教として容認するかどうかがかなり大きな課題となっていました。しかし結局、それはキリスト教の教義・世界観からすれば当然の処置であったのですが、ローマ教皇がこれを認めないものとしています。一般に、仏教は伝わった土地の俗信・風習をある程度容認し、取り込んで各地で展開するのが常ですが、キリスト教が支那でそう考えたのに同じく、こと支那の祖霊信仰についてはどうしても相容れない点があります。
先祖の魂、故人の霊が我が元に戻ってくることはありません。
そもそもそういう意味での魂など存在しない、と見るのが仏教の根本的な見方です。したがって、盆に先祖が還ってくる、故人が家に戻って来るなどというのは、キリスト教圏における俗習として、クリスマスの日に煙突からサンタクロースが贈り物を届けに来てくれる、という子供相手の絵空事と同じようなものです。
とはいえしかし、それらは今や社会全体として大規模な経済的諸活動に結びつけられ、人も物も大きく動く便利な興行の一つとなっています。一般に「宗教は危険だ」、「現代社会にもはや宗教の居場所はない」、「宗教に金が絡むのはおかしい」等とする見方が大勢を占めるようになった今。しかし、近年では恵方巻などまさにその一つの例ですが、企業が宗教に基づくアレコレを「文化」という非常に便利な詞で包み隠して利用・便乗し、新たな商売を開始あるいは拡大して何としてでも金を稼ごうとしていること、そしてそれに庶民もホイホイ踊らされているのは一体どうしたことでしょうか。
そのような娑婆の営みにおいて、(そもそもクリスチャンでもないのに)クリスマスツリーなど家に飾り、暖炉の前に靴下を釣らす必要などないように、暑い最中に墓参りだの盆飾りだの強いて行う必要はありません。いや、それも一興であるとやりたい者はやれば良い。それと同様、いわゆるお盆の時期に薦の上に茄子やきゅうりで造った馬や牛を作って置くことは、文化人類学的面白みあるものとして、ただ余興だと思ってやりたい人はやれば良し。
日本の僧職者には、近年の墓仕舞いであるとか葬式の簡素化といった社会の傾向を、「日本文化の危機」であるとか「日本の伝統的精神性が消失する」などといって騒ぐ者があります。しかし、盆を止めた、墓を無くしたところで、日本古来の精神性が消失することも、伝統文化が消滅の危機に瀕することも「決して」ありません。そもそも遺骨をやたら重視し、骨や墓に異常なまでに拘るようになったのは近世も終わってからのこと、特には昭和以降のことであって古い話では全くない。
骨に魂が宿る、故人の想いが籠もってあるなどというのは、元をただせば儒教における霊には魂魄の二種ありとするうちの魄に基づく見方とも言えるでしょう。
とは言え、現代日本人が異常なまでに骨に執着するようになった直接的原因は、「大戦に負けた」ということが大きかったように菲才は考えています。徴兵され、南方などに派遣された父親や夫の死を、名前と戦死したらしい場所が書かれた木切れの入った小さな木箱だけ渡され、「お国のため、立派に戦死なさいました」などと告げられた家族。それで「父は、あの人は死んでしまった」と割り切れなかった人がどれほどいたか。そして南方の島々にてどれほど兵士たちが過酷で悲惨な中で散っていったかを帰還兵から戦後しばらくしてようやく聞き、またその遺骨がいまだ山野に散乱していることを知った者が、そこに敗戦のやるせない悲しみと怒りとを重ね、骨にその感情を移入して「連れて帰ろう」と思い実際そうしたことが、社会的に同調されて今にいたります。
もっとも、今の場合はただ人が極めて即物的になり、いわゆる死生観が極浅はかなものとなって、「骨という物」にしか故人の寄す処を見出すことが出来なくなったことに由るようにも思われます。
ならばそこで、わざわざ田舎の寺の人を読んで「棚経」などというものを、あたかも義務として家に招き仏壇などの前で読ませる必要も無い、ということです。どうせ聞いても何もわからず、聞く気もなく、信じてもいないことをやらせる必要など無い。坐って何か読み出したかと思えば「あれ、もう終わり?」で、世間話すらほとんどせずただ「毎年のことながら暑いですね、たまりませんな」などと言って、布施袋と茶菓子だけヒョイと取って懐にしまって帰ってしまうのを、いつ来るのか、まだ来んのかなどとヤキモキ、イライラして毎年待つことは実に無益なことです。
(なぜ経を読むのか。読経して死者が安まる、死者がジョーブツすることなど決してない。仏教としての意義・目的の真については、別項「『法句譬喩経』塵垢品第二十六 ―何故読経するのか」に詳説。)