若佛子。自酤酒教人酤酒。酤酒因酤酒縁酤酒法酤酒業。一切酒不得酤。是酒起罪因縁。而菩薩應生一切衆生明達之慧。而反更生一切衆生顛倒之心者。是菩薩波羅夷罪。
《中略》
若佛子。故飮酒而生酒過失無量。若自身手過酒器與人飮酒者。五百世無手。何況自飮。不得教一切人飮。及一切衆生飮酒。況自飮酒。若故自飮教人飮者。犯輕垢罪。
もし仏弟子が、自ら酒を売り、他人に教唆して酒を売らせれば、そこに酒を売る原因・酒を売る条件・酒を売る法・酒を売る行いがある。いかなる種類の酒であれ売ってはならない。酒は罪を生じる原因・条件である。そもそも菩薩は、あらゆる生けるものに涅槃に向かう智慧を生じるようすべきものである。にも関わらず、(酒を売ることによって)あらゆる生けるものに顛倒な心を起こさせるのであれば、それは菩薩としての波羅夷罪〈[S]/[P]pārājika. 死罪に等しい最も重い罪。断頭罪とも〉である。
《中略》
もし仏弟子が、故意に酒を飲んだならば、酒による過失が生じること無量である。もし自身の手ずから酒の器を他人に渡して酒を飲ませれば、(後生は)五百世に渡って手無きものとして生まれ変わる。ましてや自ら飲むことについては言うまでもない。誰であれ人に勧めて飲ませ、およびあらゆる生けるものに酒を飲ませてはならない。ましてや自ら酒を飲むなど論外である。もし故意に自ら飲み、人に勧めて飲ませれば、軽垢罪〈[S]duṣkṛta, [P]dukkaṭa. 悪しき行為。十重禁に比すれば軽微な罪〉となる。
《伝》鳩摩羅什訳『梵網経』盧舍那佛説菩薩心地戒品下(T24, p.1004c, p1005b)
『梵網経』とは、隋代〈589-618〉の支那以来、特にその下巻が大乗戒の典拠として重要視され依行されてきた、鳩摩羅什 〈Kumārajīva〉(以下、クマーラジーヴァ)により漢訳されたと伝説される大乗経典です。漢訳経典には他に、同じく「梵網」の語を冠した『梵網六十二見経』があり、これもまた『梵網経』と称されます。しかしそれはまったく別内容の、いわゆる阿含に属する経です。「パーリ三蔵」の「長部」に収録されるBrahmajālasuttaがそれに対応します。
現在通用する大乗の『梵網経』には、鳩摩羅什の高弟の一人であった僧肇によると伝説される序文が付されており、そこに以下のような一節があります。
夫梵網經者。蓋是萬法之玄宗。衆經之要旨。大聖開物之眞模。行者階道之正路。《中略》
弘始三年淳風東扇。於是。詔天竺法師鳩摩羅什。在長安草堂寺。及義學沙門三千餘僧。手執梵文。口翻解釋。五十餘部。唯梵網經。一百二十卷六十一品。其中菩薩心地品第十。專明菩薩行地。是時。道融道影三百人等。即受菩薩戒。人各誦此品。以爲心首。師徒義合。敬寫一品八十一部。流通於世。
そもそも『梵網経』とは、けだしこれ万法の玄宗にして衆経の要旨。大聖〈釈尊〉が物〈事物の真理〉を明らかにされた真模〈最上の手本〉にして、行者が道を階る正路である。《中略》
弘始三年〈401〉、淳風東扇〈淳風は「美しい習俗」の意であるが、ここでは鳩摩羅什が東方すなわち支那に来訪したことの意〉す。そこで(後秦の姚興は)天竺の法師、クマーラジーヴァ〈鳩摩羅什〉を召して長安の草堂寺に入らせた。するとたちまち(鳩摩羅什から)学ぼうと集まった沙門は三千余僧に及んだ。(そこで鳩摩羅什は)手に梵文〈仏典のサンスクリット原典〉を執り、これを口で翻じて解釈すること五十余部となった。
ただ(クマーラジーヴァにより翻訳された)『梵網経』は百二十卷六十一品あって、その中「菩薩心地品」第十はもっぱら菩薩行地を明らかにしている。その時、道融〈僧肇に同じく鳩摩羅什の高弟の一人〉・道影など三百人が(『梵網経』所説の)菩薩戒を受けた。その人らはそれぞれこの品〈「菩薩心地品」第十〉を誦え、これを以て心首〈精神的柱〉とした。師〈鳩摩羅什〉と徒〈弟子〉と心を同じくして、その一品八十一部を敬い写し、世間に 流布させたのである。
《伝》僧肇作『梵網経』序(T24, p.997a-b)
この序によれば、もともと『梵網経』は百二十巻六十二章からなる大部の経典であったと言います。しかし今流布しているのはその第十章である「心地品(盧舍那佛説菩薩心地戒品)」のみであり、それは上記の理由によってそうなったものであると言います。ただ序文ではそう言うものの、しかし『梵網経』は、支那でも古くは訳者不詳、いや偽経の疑い濃厚と見られていました。誰に由って支那へ請来され翻訳されたかもわからぬ、むしろ支那にて何者かにより捏造された経であろうとの強い疑いが掛けられていたのです。
たとえば隋代の開皇十四年〈594〉に法経と廿人の学僧らによって撰述された訳経目録たる『衆経目録』、いわゆる『法経録』において、『梵網経』について以下のように記されています。
衆律疑惑五 一部二卷
梵罔經二卷諸家舊録多入疑品
右一戒經依舊附疑
・衆律疑惑 第五 一部二卷
『梵網経』二巻諸学者による古来の経録では多く(偽経の疑い濃厚とされる典籍の一覧である)「疑品」に収録されている。
右の一戒経〈『梵網経』〉は、従来の見解に従って(偽経と)疑われる。
法経等『衆經目録』卷第五(T55, p.140a)
少なくとも594年以前までの支那では、『梵網経』はクマーラジーヴァによる翻訳などとされておらず、その出自と真偽が疑われてきたものであったことが、ここから知られます。したがって、古説に依れば、先に示した僧肇によるとされる序文も実は僧肇によるものでは決してなく、またその内容もいわば真っ赤な嘘と言えたものです。
そもそも印度や吐蕃など印度亜大陸の大乗が信仰され行われていた諸地において、『梵網経』が流布し、また梵網戒が行われていたという痕跡は全くありません。
ところが、何を根拠とし、何故そのようにしたのか全く知られませんが、わずかその三年後の開皇十七年〈597〉に彦琮によって著された新しい『衆経目録』、いわゆる『彦琮録』では、これを「大乗律」を説いた典籍の範疇に入れ、ごく簡単にクマーラジーヴァが後秦代〈384-417〉に訳出したものと言い出しています。
大乘律單本 一十四部三十卷
《中略》
梵網經二卷 後秦世羅什譯
・大乗律単本 一十四部三十巻
《中略》
『梵網経』二巻 後秦の世、クマーラジーヴァによる翻訳
彦琮『衆經目録卷』第第一(T55. p.153a)
以来、つぶさにはその前後にクマーラジーヴァ訳と仮託されていったことを物語る典籍が色々あるのですが、『梵網経』は彼の訳経であるとされてしまっています。
ところで、『梵網経』には、これがいつ頃著されたものかは不明ですが、現存する最古の注釈書として天台大師智顗によるとされる『菩薩戒義疏』があります。その『菩薩戒義疏』には、当時菩薩戒の典拠として通用していたものに六種あるとし、『梵網経』がその第一に挙げられています。
次論法縁。道俗共用方法不同。略出六種。一梵網本。二地持本。三高昌本。四瓔珞本。五新撰本。六制旨本。優婆塞戒經偏受在家。普賢觀受戒法。身似高位人自譬受法。
次に法縁を論じる。道俗共用の(菩薩戒を受ける)方法は様々にあって、今は略して六種を示す。一には「梵網本」〈『梵網経』〉、二には「地持本」〈『菩薩地持経』〉。三には「高昌本」〈「暢法師本」とも。大凡『地持経』の授戒法に大同ながら、受者に十遮を問う点で異なる〉、四には「瓔珞本」〈『菩薩瓔珞本業経』〉、五には「新撰本」〈凡そ十八科からなる「近代諸師所集」の授戒法。戒相として十重を説く。この十重は『梵網経』あるいは『本業経』に依ったものであろう。これが「新撰本」とされていることからすれば、智顗の当時に初めてそれらが流通しだしていたのであろう〉、六には「制旨本」〈『菩薩戒義疏』はその内容を全く省略しており詳細不明〉である。
《伝》智顗説 灌頂記『菩薩戒義疏』巻上(T40, p.568a)
この短い記事の中だけでも本当にこれが智顗の撰述であるか怪しまれる点があります。しかし、その伝説通りこれが真に智顗によるものであったならば、智顗は従来の訳経僧・学僧らによる疑いを無視し、これをクマーラジーヴァによる真経であると断じて『梵網経』の注釈を施した、ということになるでしょう。あるいは、むしろ智顗がそうしたことによって、『彦琮録』にてクマーラジーヴァ訳とされた、ということであったのかもしれません。『彦琮録』が編纂されたのは智顗が死去したまさにその年です。
(現代、往古の支那でもそれが偽経であるとされていたように、『梵網経』はほぼ間違いなく偽経であると、学者らに見なされています。しかしながら、『梵網経』が隋代以降の支那、そして古代以来の日本では真経とされ行われてきた事実を踏まえ、基本的にはここでそれを問題としていません。)
支那では当初、菩薩戒(大乗戒)として通用していたのは『菩薩善戒経』あるいは『菩薩地持経』に基づく、いわゆる「地持戒」〈玄奘によって『瑜伽師地論』等が訳されて以降は「瑜伽戒」の称に変化。内容はほぼ全同〉です。それは求那跋摩〈Guṇavarman〉によって智顗などが出る150年程も前に支那にもたらされ、行われていたものです。そこに智顗の没年頃、地持戒とはまた異なる菩薩戒を説く『梵網経』が、真経として受容されたのでした。
そのようなことから、日本においてもまた『梵網経』はまぎれもない仏説として受け入れられています。ただ日本に『梵網経』がいつごろ請来され、信受されだしたかはっきりしていません。しかし、すでに養老元年には『梵網経』がもたらされていただけではなく、その所説の戒を文字通り実行していた者のあったことが知られます。行基です。
壬辰。詔曰。《中略》 方今小僧行基。并弟子等。零疊街衢。妄説罪福。合構朋黨。焚剥指臂。歴門假説。强乞餘物。詐稱聖道。妖惑百姓。道俗擾乱。四民棄業。進違釋教。退犯法令。
(養老元年〈717〉四月)壬辰〈23日〉、詔して曰く、「《中略》 まさに今、小僧行基ならびにその弟子等は、街衢〈市街地〉に零疊 〈無闇に群衆すること〉し、みだりに罪福を説いて朋党を合わせ構えている。そこで(仏・菩薩への供養として、人々の)指や腕の皮膚を剥いだり焼いたりし〈行基らは梵網戒の第十六軽戒・第四十四軽戒を現実に行わせていたが、それは「僧尼令」第二十七 焚身捨身条に違反する行為〉、家々を経巡って不可思議なことを説きまわり、強いて(食以外の)余物を布施するよう乞いている〈「僧尼令」第五 非寺院条および第二十三条 教化条に違反する行為。『令義解』では「余物」とは「衣服の類」であってそれを規制の対象としているが、実際に行基らが布施として要求していたものは衣服に限らずあらゆる雑多な金品であったろう〉。それは聖道〈仏教〉を詐称するものであって、百姓を妖惑〈「僧尼令」第一 観玄象条に抵触〉し、道俗〈出家者・在家者〉を擾乱。ついに四民〈全ての階層の人々〉はその業〈職業。義務〉を放棄している。(行基らは)進んで釈教〈仏教〉に違え反し、また法令〈『大宝律令』「僧尼令」〉を退ぞけ犯している」
『続日本紀』巻七 (元正天皇) 養老元年四月壬辰条
この中、行基が民衆に行わせていた行為には、まさしく梵網戒が菩薩として必ず実践せよと義務としていることです。
昭和以降の史学者などは、「僧尼令」の特に第五非寺院条などに見られる僧尼に対する朝廷の見方・態度こそ歪で抑圧的であったとし、律令体制下における行基およびその教団に対して非常に同情的に見ることが支配的でした。そしてその傾向はそのまま無反省に今も続いています。
しかしながら、非寺院条は前時代の学者らがそう見なしたようなものではない。当時、誰もまだ正規の仏教僧たり得ない状況にあって、しかも国家の管理が行き届かないまま誰も彼もが巷のそこかしこに寺院以外の道場など立て回って良い訳もなく、それを規制したのが非寺院条です。実際、行基らが巷で行っていたそれは、まさしく今で言うカルト教団の所業に他なりません。朝廷がこれを嫌い行基をして「小僧」と称したのも当然であったと言えます。
上記に挙げ連ねられた諸々の行為は、現代日本でも特に昭和四十年代から平成にかけて、街の拝み屋・霊能者などと言った類、そして諸々の新宗教教団が行っていたこととほとんど同様のものと言って良いでしょう。したがって、これは現代の価値観を過去に持ち込んでそういうのでなく、当時からその手の行為、その手合の輩が問題あるものとされていたのは変わりありません。
そもそも、このような行基およびその教団の行動が問題視される以前、大宝元年〈701〉に施行されていた『 大宝律令』のうち「僧尼令」には、明らかに『梵網経』の所説を前提としている条項がいくつか定められていました。
「僧尼令」は、唐の道教および仏教の宗教者と寺院に関する法「道僧格」から、日本には形の上では全く受け入れられていなかった道教に関する条項を取り除いて編纂されたものとされます。そこでその条例の根拠の一つでもあった『梵網経』が、『大宝律令』施行以前のいまだ編纂されている時期、すなわち七世紀中には日本にもたらされており、僧ばかりでなく藤原不比等など俗人にも読まれ研究されていたことは充分に考えられます。
『梵網経』の所説を文字通り実際に行うことは、「僧尼令」で具体的に禁じなければならなかったように、様々な問題を生じさせるものであったのですが、それが一般社会において信受され行われていたことが確かです。朝廷としても『梵網経』自体を否定することなど出来なかったでしょうが、しかしその所説を文字通りやらせるわけにもいかず、国家としての『梵網経』および「梵網戒」の扱いは中々難しいものであったでしょう。
しかし、そのような朝廷の村落に跋扈するカルトめいた行基教団に対する処遇は、たびかさなる不幸に迷い苦しみ、都をあちこち遷していた聖武天皇によって変化し、毘盧遮那仏建立のための強力な助けとして引き立てられ、それまでの行基の違法行為の数々は不問にされています。その裏には聖武天皇の『仁王経』の為政者が僧尼を支配・管理してはならないという所説に裏打ちされた、個人的反省もあったに違いありません。また、国家事業の助けに成り得るほど行基の民衆における求心力は高く、その教団は統率が取れていたのでしょう。聖武天皇は、(行基教団に)出家を希望する者の条件も緩和しています。そしてついに行基は、巷の非合法教団の一指導者から、国家機関の僧綱における最高位、しかも行基の為に新設された大僧正の位にいきなり補任されたのでした。
そして東大寺建立の立役者の一人として、良弁に並んで行基が祭り上げられることとなります。
これがまた鑑真による伝律伝戒がなされると、さらに話が変わります。鑑真やその弟子たちの影響により、聖武天皇を始め、特に孝謙天皇(称徳天皇・高野天皇)が『梵網経』を信じ、梵網戒を受持してその所説に従った行動を国家の規模で起こしていたのです。以降、『梵網経』の日本における地位も確固たるものとなり、貴賤僧俗を問わず信奉される菩薩戒の典拠となっています。
そうしてさらに平安初期、最澄がその弟子たちに具足戒を受けることを無用とし、ただ「梵網戒」をのみ受けることに依って比丘たり得るし真の大乗僧はそうでなければならない、と『山家学生式』や『顕戒論』などで主張したことで、大きな変化が起こっています。そしてそれが後代へ与えた影響は甚大なものとなりました。
今の学者でこれをそう見て指摘する者などありませんが、最澄の主張は、鑑真渡来以前の僧徒における無戒状態への先祖返りに他なりません。最澄自身にそのような意識は皆無です。しかし彼の主張がその死後、朝廷に認められたことは、鑑真の伝戒の意義・業績を全く覆したのに等しいものとなっています。そしてそれが日本仏教が世界でも異常、その僧徒のあり方や思想がきわめて特異とされる決定打となり、ついには無戒を良しとする思想に繋がっています。
古来、日本仏教は我が邦をして「大乗相応の地」といい、またその宗派はすべて大乗に属するものとなっています。日本仏教の宗派には八宗を始めとし、またその亜流の宗派が幾多もありますが、前述したように『梵網経』を否定し、あるいは梵網戒を受けないものは、真宗を除いてありません。ただし、それも合って無きに等しいもので、あくまで建て前上のことです。
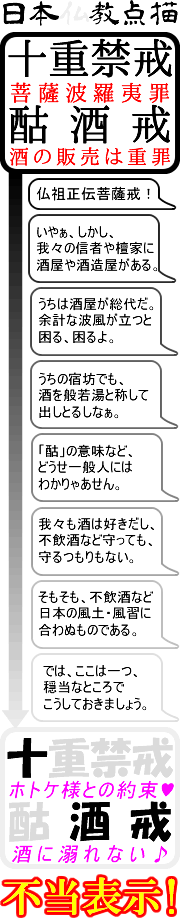
『梵網経』は、「酒類を販売すること」ならびに「酒類を飲むこと」の二つを戒めています。酒類を販売することをまず重罪として挙げ、次に重罪に比せば相対的に軽罪として酒を飲むことを戒めています。それは言わば、現代日本における刑法で麻薬は一部の例外を除きその所持・使用・販売等すべて禁じられていますが、使用者よりも販売者の方がより罪が重いようなものです。
梵網戒に説かれる十重のうち、その第五が酤酒戒となっています。酤とは「売ること」・「販売」を意味する漢字です。
なぜ菩薩は酒を売ってはならないのか?ここで菩薩とは「完全なる悟りを求める者」という意味であって、また大乗を信奉する者という意味ですが、その菩薩は、他者に智慧をこそ生じるよう勤めなければならない者であるのにも関わらず、何らか罪・迷妄・狂気の元となる酒を他に売りつけるなど言語道断、といった理由に基づきます。
そして菩薩でありながら、といってもそれはこの『梵網経』に基づく梵網戒を受けた者に対してですけれども、酒を売った者は「菩薩の波羅夷罪」であると強く断罪されています。
波羅夷とは、サンスクリットまたはパーリ語pārājikaの音写で、本来は律の用語です。波羅夷は、僧侶の絶対に行ってはならない極重罪であり、僧侶でありながらこれを犯せばただちに僧伽から追放され、いくらその罪を悔いて懺悔しても二度と僧侶となることは出来なくなります。これを犯すことは出家者としての死を意味するものであり、その罪は一般社会における死刑に相当するものであることから「断頭罪」とも意訳され、あるいは懺悔贖罪出来ない罪であることから「不応悔罪」と意訳されています。
『梵網経』においては「菩薩の波羅夷罪」が十種あることから「十重」あるいは「十重波羅提木叉」とされています。後代の日本の学僧らはこれを「十重禁戒」と称し、今もそれが一般に用いられていますが、それは実はほとんど日本に限られ用いられた語です。
しかし、『梵網経』の場合、その意味が律と異なっています。酤酒戒等の十種の行為を犯すことは波羅夷罪である、などと言いながら、律蔵と異なって贖罪不可の永久追放を意味していません。十重禁を犯したとしても、『梵網経』の規定する方法、例えば読経や礼拝などによる 懺悔を、ある一定の条件を満たすまで行ったならば許されるとしているのです。これは、『梵網戒』が出家者だけでなく在家信者もその受戒対象としている為でもあるのでしょう。そもそも、梵網戒はあくまで「戒」であって「律」ではなく、にも関わらず律の用語が用いられていることによって、その理解に混乱を招くこととなっています。
(『梵網経』が支那撰述の偽経であるとする観点からすれば、先行する『菩薩地持経』などの印度由来の菩薩戒経の規定・説を、偽作者が取り入れてさらに独自の説を加上しただけ、ということですけれども。)
いずれにせよ、『梵網経』においては、酒類を販売することは菩薩の極重罪であるとされます。
そこで『梵網経』はさらに、ここが『梵網経』独特な言説となっているのですが、梵網戒を受けた者が自ら酒を売り、あるいは他に酒を販売させたならば、「酤酒因・酤酒縁・酤酒法・酤酒業」があるとしています。しかし、これだけでは具体的にそれがどのような意味かほとんど全く理解できません。『菩薩戒義疏』以来、数多く著されてきた注釈書の中でそれぞれその意の注釈が試みられていますが、それぞれの解釈は相違しています。よくある話ですが、端的すぎると逆にわからず、ある場合にはどうとでも解釈できてしまうため、混乱を招くのです。
ここでは一応、先に智顗による注釈書と伝説されるものとして紹介した『菩薩戒義疏』における解釈に従います。ただし、ここでその原文を挙げると冗長となるため、その要のみ示します。『菩薩戒義疏』によれば、「酤酒因・酤酒縁・酤酒法・酤酒業」の四句は成業 を明かしたものだといいます。ここで成業とは、「どの様な行為が成された場合に犯戒が成立するか」、すなわち破戒の構成要件を意味します。
『菩薩戒義疏』は、「因・縁・法・業」を逆から釈していますがここではその最初から言いますと、「因・縁」とは①衆生〈生命ある者〉・②衆生想〈生命ある者だとの認識〉・③希利貨貿〈利潤を求めて売ること〉・④真酒〈酒。酔わせるもの〉・⑤授与前人〈目前の人に与えること〉の五条件を備えることだといいます。
「売る」というからにはその相手がいなければ成立しません。そこでその相手は「①衆生 」、すなわち人にかぎらず生き物すべて、であると先ずしています。そこで次に売る者は、買い手が生き物であると認識していなければならない。人形や山川草木を相手に売買は成立しません。そこで「②衆生想」。また売る、ということは何らかの価値あるものの交換がなければ成立しません。故に「③希利貨貿」。売ると言っても水を売るなら問題はない。酒であるから、すなわち酔わせるものであるから問題であるので、販売する物が本当の酒でなければならない。そこで「④真酒」。そして売り手が「売る」と言い買い手がも「買おう」と言うだけであれば、実際の売買は成立しない。この場合、相手に物を渡してようやく売買が成立したと見なされます。そこで「⑤授与前人」。なお「人」とありますが、その相手は神であろうが畜生であろうが同じであり、人にすべての生き物を代表させています。神にも酒を売るな、与えるな、というわけです。
これら五条件が揃って「酒を売ること」が成立し、それが最初の二句の「酤酒因・酤酒縁」だというのです。
そして次の二句については極簡単に、「酤酒法」は酒を売る手段・方法、「酤酒業」は「手を用いて(酒を)運ぶこと」であると、『菩薩戒義疏』は注釈しています。それほど煩雑な注解となっておらず、このように注釈されると「なるほど、そうかな」と思えるものとなっています。しかし、後代次々と著された他の注釈書では、それぞれ独自性を発揮するためのことでもあるのでしょうが、迂遠で煩雑な理解が付されてます。
『梵網経』の説く四十八軽戒のうち、その第二が飲酒戒となっています。
『梵網経』では、「生酒過失無量」と酒を飲むことの過失は限りがないとし、「なぜ酒を飲んではいけないのか」の理由を一々挙げていません。少々乱暴にも思われますが、とにかく非常に悪いからやめろ、といったところでしょう。
そこでむしろ、もし酒を人に酌して飲ませたならば「五百世無手」と、五百世に至るまで手の無い生物として生まれ変わるなどと警告しています。これは先に示してきた諸経典とは異なる点です。また、まず人に飲ますことを戒め、次に自ら飲むことを戒めるなど、他に対する行為を先としているのは大乗の立場が表わされたものと言えます。
『菩薩戒義疏』には、この「第二飲酒戒」について以下のように記されています。
第二飮酒戒。酒開放逸門故制。七衆同犯大小倶制。《中略》
有五五百。一五百在鹹糟地獄。二五百在沸屎。三五百在曲蛆蟲。四五百在蠅蚋。五五百在癡熟無知蟲。今之五百或是最後。與人癡藥故生癡熟蟲中也。不得教此第二制不應。教人及非人并自飮皆制。若故下第三段擧非結過。自作教他悉同輕垢。必重病宣藥。及不爲過患悉許也。未曾有經未利〈末利の誤写〉飮酒此見機爲益。不同恒例。
第二の飲酒戒は、酒は放逸の門を開くものであるから、制されたものである。七衆〈出家・在家の七種の仏教徒すべて〉同じくこれを犯ずることは、大乗・小乗ともに制される。《中略》
(経に説かれる「五百世」について、)五百には五種ある。一の五百は鹹糟地獄〈あらゆるものが腐っている地獄〉、二の五百は沸屎〈屎尿に満ちた地獄〉、三の五百は曲蛆蟲〈ウジ虫〉、四の五百は蠅蚋 〈ハエとブユ〉、五の五百は癡熟無知蟲である。今の(経がいうところの)五百世は、あるいは最後のものであろう。人に癡薬〈酒〉を与えたために癡熟蟲の中に生まれるのだ。(経文の)「不得教(教えることを得ず)」から下は、第二にすべきでないことの制である。人および非人〈一般に神のこと。人ならざるもの〉に勧め、ならびに自ら飲むこと全てが制されている。(経文)の「若故(もし故に)」から下は第三にその非であることを挙げ、その過失であることが言われている。自ら酒を飲むことも他に勧めることも悉く同じく軽垢罪である。(ただし、)もし重病に対する薬として、および 過患〈あやまち〉をなさないのであれば悉く許される。たとえば『未曾有経』〈『未曾有因縁経』〉にある、末利夫人〈Mallikā. コーサラの波斯匿王([S]Prasenajit, [P]Pasenadi)の妻〉が酒を飲んだという故事のように。(ただし、)それは機〈物事のきっかけ。時機〉を見て益を為すためのものであって、通常(の人々が酒を飲むこと)と同じではない。
《伝》智顗説 灌頂記『菩薩戒義疏』巻下(T40, p.575a)
『菩薩戒義疏』は、「なぜ酒を飲んではならないのか」を「酒開放逸門」(酒は放逸の門を開く)」からであると言います。そして経文にある「五百世無手」について、酒という「痴薬」を人に与える果報として「癡熟蟲」という虫に五百世にわたって生まれ変わり続ける、ともしています。この「癡熟蟲」なる虫が一体何なのか不明ですが、「無手」というからには何か這い回る虫で、しかも「癡熟」ということですから途轍も無く馬鹿な這う虫ということなのでしょう。
さて、もし梵網戒を受けた者が人に酒を飲ませ、あるいは自ら飲んだならばどうなるか。それは「軽垢罪」であると『梵網経』には説かれます。軽垢罪とは、これも本来は律の用語でサンスクリットduṣkṛta、あるいはパーリ語dukkaṭaの漢訳です。しばしばこれの音写、突吉羅という語が用いられます。
それは律における用法としては、出家者として何事かなすべきでない行為、悪しき行為であるものの最も軽微な罪とされ、悪作なども意訳されています。そして律での場合、これを犯した際は、誰か他の一人以上の比丘に対してその罪を発露懺悔したならば許される行為です。もし他に比丘が無い場合には、心の中で自ら反省するだけでも許されます。そのように本来は実に軽微な罪ではあるのですが、やはり『梵網経』では違います。
先に述べたように、これは重に比せば軽いという比較上でのことであって、酒を人に飲ませ、あるいは自ら飲んだならば「五百世無手」というのですから相当重いものです。ただし、それも前述したように、「菩薩の波羅夷罪」と同様、懺悔によって出罪が可能とされます。それは一見、重いんだか軽いんだかわからないことになるかのようです。また、その点においては梵網戒が寛容と言えなくもない。しかしながら、『梵網経』のいう懺悔というのはそんな簡単な、生易しいものではないため、やはり厳しいと見て間違いありません。
ところで、『菩薩戒義疏』における飲酒についての注釈の中、その最後にある一節は刮目 すべき点です。
まず、酒を飲むと言ってもその全てが犯戒となるのでなく例外があることを言っています。その一つ目は病に対する薬として用いる場合。そしてその二つ目が、『 未曾有因縁経』の所説に基づいた、酒を飲んでも過失とならない場合です。その『未曾有因縁経』の説とは、仏陀ご在世当時に強大であった国の一つ Kośala 国王、 Prasenajit 〈[P]Pasenadi. 波斯匿王〉とその夫人 Mallikā 〈末利夫人。ジャスミンの梵名〉との間に起こったある出来事に基づいたものです。
その概要は、ある時、王が大変な空腹となっていたにも関わらず、不意のことで食事を用意することが出来なかった料理人に激怒して、王自らが死刑を宣告。その不合理を聞いた夫人は急遽、肉と酒とを用意して王の元に至り、共にそれを飲み食いし、さらに歌い踊ってその怒りを沈めさせます。そして密かに家臣に命じ、料理人の死刑を中止させたのでした。その翌日、先の横暴を非常に悔い憂いていた王が、実は夫人の機転によって料理人は処刑されていないことを知らされ、大いに喜んで憂いが晴れたのでした。王は、仏陀と会ったとき、そのようなことがあったことを仏陀に話します。夫人は仏陀から五戒を受け、また六斎日には八斎戒も行じるなど飲酒はもとより諸戒を固く守っていたのに、自分の愚かな振る舞いによって危うくなった料理人の生命を救うため、その戒の多くを敢えて破ってしまった罪の軽重について、仏陀に質問したのでした。それに対し、仏陀は一切罪にならずむしろ大いなる功徳であったと答えられた、という話です。
飲酒戒がどうのと言う以前に、実に王の横暴たることこの上ない話であります。
しかし、『未曾有因縁経』にあるこの話は支那でも非常に古くからよく知られており、飲酒戒など持戒に関する話で諸師によく引用されています。そのようによく知られるようになった嚆矢は、そもそも『菩薩戒義疏』にあったようです。『菩薩戒義疏』は『未曾有因縁経』を根拠として、他を利益するためには犯戒しても罪とならず、むしろ功徳とすらなる場合のあることの一例として挙げています。これは持戒ということの本質に対する一つの見方を示したもので、その背景にはやはり大乗の精神というものが控えていると言えます。実際、諸師が『未曾有因縁経』の所説を注目したのもその点です。
ただし、先に挙げた『菩薩戒義疏』にあるように、これが「実は酒を飲んでも良いのだ」とおためごかしの詭弁に容易く用いられることも察してのことでしょう、「不同恒例(恒例に同じからず)」と言っています。それはあくまで例外であり普通に酒を飲むのとは異なる、とわざわざ釘を刺しているのです。
実際、『菩薩戒義疏』にある「不爲過患悉許也(過患を為さざれば悉く許す)」という一節は、今の日本でほとんど知られていないものではありますが、大乗を奉じている筈の、酒を好んで飲酒をなんとしても仏教的に肯定せんとする日本の酔狂の人に知られたならば、たちまち「かの天台大師智顗さまも、実は過ぎた酒でなければ飲んでよいと仰っしゃられていた」などといった戯言に用いられるに違いありません。そのようなそら言が述べられようことは、すでに千四百年ほどの昔から予想されていました。
娑婆 はどこまでも娑婆、人はいつの世も人です。まさに苦海であります。
Bhikkhu Ñāṇajoti(沙門覺應)