一不可飲僧房内酒縁起第十九
夫以酒是治病珎風除之寶矣。然而於佛家爲大過者也。是以長阿含經曰。飲酒有六種過等云云。智度論曰。有卅五種過等云云。亦梵網經所説甚深也。何况秘密門徒可酒愛用哉。依之所制也。但靑龍寺大師與幷御相弟子内供奉十禪師順暁阿闍梨共語擬曰。依大乘開門之法治病之人許塩酒。依之亦圓㘴之次呼平不得數用。若有必用從外入不瓶之噐来副茶秘用云云
一.僧房の内にして酒を飲むべからざる縁起 第十九
そもそも考えてみれば、酒は病を癒やす珍、寒さを除く宝である。しかしながら、仏家〈仏教〉においては、大きな禍を引き起こすものである。そのようなことから、『長阿含経』に「飲酒に六種の過失がある」などと説かれ、『大智度論』には「三十五の過失がある」などと説かれる。また『梵網経』が(酒を売り、また飲んではならない、と)説くところには甚だ深い意味がある。ましてや秘密の門徒〈密教徒〉が、酒を愛し飲んで良いわけがない。このようなことから(飲酒は)禁止されるのだ。
ただし、青龍寺の大師〈恵果和尚〉と、その兄弟弟子で内供奉十禅師であった順暁 阿闍梨とが共に語らい、仮の事として「大乗開門の法に依り、病気療養の人であれば、塩と酒とを(薬として用いる事が)許されている」と言われていた。しかし、この言葉に依拠して、円坐の次いで〈衆僧が集まった折〉に平杯でもって酒を飲み散らしてはならない。もし(治療薬として)必ず用いなければならないことがあれば、(僧房の)外で瓶〈酒瓶〉ではない器に移し替えて持ち帰り、茶にそえて(それが決して酒だと他に知られぬようにして)秘かに飲ませよ。
《伝》空海『御遺告』(『底本 弘法大師全集』, Vol.7, p.366)
『御遺告』とは、平安時代初頭、唐から真言密教を伝え、日本で真言宗(真言陀羅尼宗)の祖となった空海の遺言として古来伝承され、真言宗にて極めて重視されてきたものです。それは空海が死去する六日前、すなわち承和二年〈835〉三月十五日に弟子達に遺したとされるもので、二十五箇条からなっています。現在、高野山金剛峯寺大伽藍の御影堂に、空海真筆とされるものが所蔵されている、ことになっています。
もっとも、空海の遺言とされるものは『御遺告』だけに限らず諸本伝わっています。中でも『御遺告』以外に重視されたものとして、これらは空海から直弟子達や後代の弟子への遺誡であっていわゆる遺言ではないため『御遺告』とはやや性質を異にするものではありますが、弘仁四年〈813〉六月三十日になされたという弟子たちへの教誡「弘仁遺誡」、そして承和元年〈834〉五月廿八日の教誡であるという「承和遺誡」の二本があります。
(空海の「弘仁遺誡」および「承和遺誡」については、別項「空海『遺誡』」にてその原文と対訳を、解題を付して示している。参照のこと。)
ところが、その内容に空海によるものとは到底思えない怪しむべき杜撰な点が多いことから、『御遺告』は空海が著したものでは決して無く、また彼の遺言を直弟子たちが書き留めて編纂したものでもない、という見方が、近年の真言宗内でも仏教学会でも大勢を占めています。そんな怪しむべきこと甚だしい『御遺告』よりも、「弘仁遺戒」や「承和遺戒」こそ空海の真作であろう、とされたことも一時期ありました。しかし、それらにも空海の著とするにはそれを否定するに充分な種々の不審点があって、結局その両本もまた空海によるものでなかろう、とする学者があります。
もっとも、現代の真言宗内および学会などでその様に言われるようになってはいても、『御遺告』が平安中後期の昔から空海撰として伝えられ、真言宗徒にとって最も重要な書の一つであったという歴史的事実は動きません。よって、ここではその事実をふまえ、『御遺告』を空海の遺言であるものとし扱っています。ただし、空海(仮)によるものとして。
実際、これは『御遺告』ではなく「弘仁遺誡」のことではありますが、その昔の中世は鎌倉期初頭、興正菩薩叡尊が、まさに「弘仁遺誡」を空海の紛れもない遺誡であるとして読み、当時の真言僧はもとより仏教僧全般のあり方がいかに誤ったものであるかを知った衝撃を受けたことにより、すで当時滅んでなかった戒律を復興するべくその運動を開始しています。その運動は幾多の困難に直面するもやがて実を結び、西大寺を拠点とする新たな律宗が形作られ、叡尊は「生身の釈迦」として鎌倉前期の当時、全国で最も信仰を集めた存在となっています。
それにしても、偽作・偽撰というものを見聞するにつけ思うことですが、それはもちろん「お祖師様」などと普段崇拝しているはずの後代の弟子が捏造したのでしょうけれども、一体どのような精神でそれをなしていたのか実に不思議です。その人を本当に知り、真に尊敬していたならば、その人の名に仮託した書など捏造しようとの考えなど起こるはずも無いと、少なくとも不佞自身は思うためです。
偽撰と一口に言っても色々あります。しかし、その書がその同一組織内の一部の派閥を利益せんとする目的で書かれたものが明白であるならば、偽撰者は著者に擬した人に対する真の敬意などまるで持ち合わせていなかったとしか思えません。いや、人の心情というものは時に実に複雑であり、そう一概に断ずることも出来ないか。しかし、やはりその人を直接知って敬愛する人であれば、決してなし得ない 業 であろうことに違いありません。
廿五箇条ある『御遺告』の第十九条に、「僧房の内に酒を飲むべからざるの縁起」として、真言宗徒に対しての飲酒に関する戒めあります。
空海(仮)はその中で、酒が薬として有用なものであることを、これは『大智度論』の説を受けてのことであったでしょうが、まず一応認めています。しかしながら、すぐに続けて仏教者にとって酒は大なる禍をもたらすものであると、『長阿含経』や『智度論』、さらに『梵網経』に基づいて戒めています。中でも、『梵網経』の説く酤酒戒と飲酒戒を重んじています。
ただし、例外として酒を用いても良い場合のあることを、恵果と順暁 とが語り合った中での話に基づいて挙げています。恵果とは唐の都たる長安の青龍寺にあった密教の大阿闍梨で、はるばる日本から来た留学僧空海に当時の支那に伝わっていた密教の全てを伝えて継承者とした、その師です。順暁は、長安から遙かに遠い泰山に住し、後に越州〈現在の浙江省〉の龍興寺に居した密教僧で、最澄に密教を授けたことで日本では有名な人です。
そのような遠く地を隔ててあった二人が、しかも空海が長安にあるときに語らっていたのを聞いた、ということは甚だ不審に思われることです。あるいは過去にそのようなこと話があったということを、空海(仮)が長安にて伝え聞いた、という設定であったのでしょう。
いずれにせよ、その話の一節は、今もなお真言宗の僧徒の中では大変有名なものとなっています。「塩酒を許す」というのがそれです。実際、冒頭その一節をもって示したように、『御遺告』には「治病之人許塩酒(治病の人には塩酒を許す)」という一節があり、病気療養のためならば酒を塩とを用いても良い事が言われています。
それにしても、なぜ酒だけではなく「塩と酒」なのか。これはその昔、日本の人々は日本酒の肴として少量の塩を用いていた様で、それを意味するものと思われます。しかし、これも実に不合理な点であり、仮にその二人が実際に語らっていたとしても、支那の恵果と順暁が「塩酒」などと言うとは思われない。それに治病の薬としてならば、服用するには少量の酒で事足りるのであって、塩など無用です。
さらにここで重要な点は、その根拠として「依大乘開門之法(大乗開門の法に依て)」と記していますが、そのような説は大乗の経論に無いことです。もっとも、大乗に限らず言えば、典拠が無いとことはない。律蔵には、比丘が例外的に酒を用いても良い場合が定められているためです(『パーリ律』・『摩訶僧祇律』・『十誦律』・『五分律』には、この規定が波逸提の中に無い)。
不犯者。若有如是如是病。餘藥治不差以酒爲藥。若以酒塗瘡一切無犯。
(比丘および沙弥などその他の出家者が、飲酒しても)不犯となるのは、もし何事かの病を得て、その他に効果的な薬がない時に酒を薬として服用する場合である。あるいは酒を瘡〈傷・腫れ物。皮膚疾患〉に塗るのはすべて無犯である。
仏陀耶舍・竺仏念訳『四分律』巻十六(T22, p.672b)
鑑真により日本にもたらされて以来、東大寺戒壇院などで授受された具足戒の典拠は『四分律』で、当時空海も勿論それを受持していましたが、そこにも以上のように明瞭にその例外が規定されています。『四分律』についていえば、他に有効な薬が無い場合には、比丘およびその他の出家者が酒を治病の為に飲んでも罪とはならないとされます。そしてそれは、いわばいたって合理的思考による配慮です。
いずれにせよ、ここに挙げられている恵果と順暁との話は、「大乗開門の法」などという得体の知れない大げさなものではなく、本来律蔵の所説であるのを、空海(仮)が憶説でそう記したものであったのでしょう。
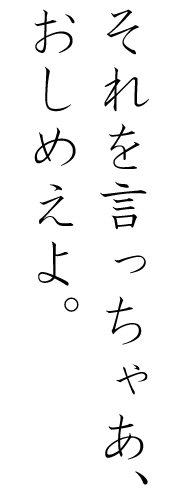
ところが、面白い事に、近年の真言宗徒はこぞって『御遺告』にあるこの一文「治病の人には塩酒を許す」を、「治病の人には飲酒
いっぱいはこれを許す」と、あたかも空海が飲酒を許可していたかのように改変して記憶しています。もちろん、『御遺告』を直接読めば明らかなように、空海(仮)は決して「飲酒」つまり「酒を酒として飲むこと」など許しておらず、むしろ厳に戒めています。
そもそもそのように「酒を飲むべからず」と遺言として書き記しているということは、「大道廃れて仁義あり」、空海(仮)の周辺で、僧徒らの酒にまつわる振る舞いが目に余るものであったからのことであったに違いありません。
ところで、これもまた非常に面白く思われるのは、「お大師様はありがたい」・「お大師様のオカゲサマ」などと常日頃言い、「南無大師遍照金剛」と何十万遍とその人生で積み唱えている真言僧らに、『御遺告』を含めた空海の著作をまともに読んでいる者が甚だ少ないことです。いや、その大学や修行寺院といった教育機関などで、誰でも義務としてその幾冊かを一通り目を通させられたことは必ずある。
けれども、それはそこに羅列する漢字の波を見たということに過ぎず、読んでなどいはしません。もし、確かに読んでいたならば、これは酒に関してに留まらず言えることですが、そのように改変したり恣意的な誤用をしたりするなど決して出来ないでしょうから。
しかし、真言宗の僧徒の多くは、「お大師様も酒を飲む事を戒めらなかった」、「お大師様はおちょこに一杯か、バケツにイッパイかはおっしゃらなかった」などと言い、彼らは本当にそう云うのですけれども、たいていの法要が終わった後にはウワバミのように酒をすすることを習いとしています。あるいは「高野山は標高が高く、冬はきわめて寒いため、暖を取るのに酒はとても有用であった。故にお大師様は酒を許されていたのである」といった、憶説も甚だしい戯言を垂れています。
小賢しいのになると、「いや、『御遺告』とは偽作であってお大師様の真作ではない。したがって、「飲酒いっぱいはこれを許す」などというのは蒙昧の小僧の戯言である。けれども、そもそもお大師様は酒を飲むなとはおっしゃられていないのだ」と言い、やはり当然のように酒をススルのであります。
その結果、「真言密教の聖地」・「密教の道場」などとして世界的にも有名になった高野山は、その内実はむしろ「酒の道場」と化して久しい。現代ともなると、高野山の宿坊寺院の中には、バーを具えたものまであるほどで、その宿坊の住職や寺族や役僧らも、それを恥ずかしいとも可笑しいとも、なんとも思ってはいません。
そういうならば僧徒だけではない。高野山を訪れる参拝者・観光客も、わざわざそこで酒を飲む事を求めます。日頃、「生臭坊主!」などと悪態を付きたがる人であっても、酒の出ない宿坊など泊まりたくはないのだと平気で言います。そしてこれを寺院側も十分心得ており、「当院には酒などはございません。いや、しかし、般若湯および麦般若ならばございます。これらは飲み放題、そして払い放題でございます」と出来上がった口上を、その宿坊の役僧などに声も高らかに言わせ、参拝者らもこれを大喜びして聞き、実際飲み散らかすのです。
もっとも、昭和から平成、そして令和の世ともなると、そんな彼らも昔ほどの痴態を晒すことは相当少なくなったようです。これは高野山に参拝し宿泊する人が少なくなり、その利用客が外人がほとんどとなってきたため、ということもあるのでしょう。
しかし、これはそもそも程度の問題ではない。
ところが、そのような空海(仮)が『御遺告』にて飲酒を戒めた文言のうち、今もしっかりと守られている点が一つだけあります。「不瓶之噐来副茶秘用( 瓶にあらざるの器に入れ来たって、茶に副えて秘かに用ひよ)」という一節がそれです。
これはたとえば高野山での法要などで出される、伝統的な形式・作法に則って振る舞われる食事、いわゆるお斎の席において、その最初にお茶と酒が「瓶にあらざるの器」すなわち湯桶 に入れられて出されます。と言っても、それは「薬としての酒」などではもちろんない。そしてその後にはビールはビール瓶で、酒は一合徳利で堂々と、しかも次々と出されます。
はじめから飲酒戒など無いわけで、釈尊の教誡はもちろんのこと「弘法大師のお言葉」もどこ吹く風ですが、この一点だけやたらとこだわり今も頑なに守っているのは、実に面白いことです。湯桶に酒を入れて出す習慣は、中世後期から近世になると真言宗に限らず社会でもある程度一般化したようですが、あるいはこの『御遺告』の説をさらに捏造した僧徒の習慣が、その嚆矢であったのかもしれません。
いずれにせよ、そのように酒に酔い、また痴の泥沼に自らどっぷり嵌まり溺れながら、「ほとけ様、お大師様はいつも私たちを見守って下さっている。あぁ、ありがたい、ありがたい。南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛」とありもしない幻想に救いを求め、あるいは「すべては大日如来の顕現であって、酒も大日如来。酒を飲むことも大日如来のお働きの一つだ」などと、途方もない妄言をうそぶくのも、故無きことではありません。
日本仏教はしばしば「祖師無謬説」などと言われるほどその祖師を絶対視・神聖視し、むしろ釈尊の言葉など他所において祖師の言葉をこそ優先する宗派がほとんど全てですが、その実態は「お祖師様のお言葉」など馬耳東風。あくまで建て前で「お祖師さま」を崇め奉っているに過ぎません。
そのような欺瞞を続けられているというのは、社会がそれを許しているからでもあるのでしょう。いや、すでに近世から日本仏教は、一部の例外はあるものの、その大勢は祖霊崇拝のための社会的一装置の如きものと化していました。そして明治以降、特に大戦後は、社会が仏教に求める役割など近世以来の葬儀の執行と祖霊崇拝に加えて日本の文化的習慣や文化財の保護程度であり、思想的・精神的にはまず無用となっています。その方面は、実に歪んだものではありますが、ほとんど仏教系および神道系の新宗教が担うようになっています。
したがって、その役割を果たす限りにおいて、その祭式執行者である僧職の者らが何を言い、何をやろうが社会は一向気にしない、ということであるのでしょう。
実に詮無いことであります。
Bhikkhu Ñāṇajoti(沙門覺應)