一、さけのむは、つみにて候か。
答、ま事にはのむべくもなけれども、この世のならひ。
《中略》
一、酒のいみ、七日と申候は、ま事にて候か。
答、さにて候。されどもやまひには、ゆるされて候。
(第五十七問)
問:酒を飲むのは、罪なのでしょうか?
答:本当は飲むべきものでは決してないが、この世の習い。
《中略》
(第百十二問)
問:酒の忌み〈未詳。飲酒戒を犯した際の物忌か?服喪中の禁酒のことか?〉は七日だと言われるのは、本当でありましょうか?
答。その通りである。しかしながら、病の場合は(酒を用いることが)許されている。
源空『百四十五箇条問答』(大橋俊雄『法然全集』vol.3, p.251)
『百四十五箇条問答』とは、古代平安末期から中世鎌倉初期の天台僧で、初老の頃に浄土教を称揚し、浄土宗の祖となった法然源空による、浄土信仰に関する信者らからの質疑応答集です。
『百四十五箇条問答』に記される法然に対する人々の質問の内容から、その質問者のほとんどが貧しく社会的地位の低い庶民であったであろうことが推測されます。そしてその答えは素朴、簡潔であり、その故に法然の日常的態度や思想、浄土信仰の細かな部分を知る事が出来ます。また、当時の庶民の風習や興味、そしてその信仰の実態も伺うことが出来る、非常に興味深い書となっています。
そのような法然の『百四十五箇条問答』の中に、浄土教信者からの飲酒についての質問があり、それに対する法然の答えがあります。法然の答えは、仏典も仏教用語も何一つ出てこず、非常に簡潔です。「ま事にはのむべくもなけれども、この世のならひ」、すなわち「本当は飲むべきものでは決してないが、この世の習い」という答え。
これはどうでしょう、簡潔にすぎてむしろその真意がつかみ難いものとなっています。今の感覚で普通にこれを解したならば、「仏教は飲酒を制しており、法然自身も飲んではならないと考えているけれども、俗人については世間の習慣として容認せざるをえない」といったところでしょうか。しかし、「この世のならひ」と体言止めして続く言葉がないことにより、他の解釈の仕様もあるところです。
『百四十五箇条問答』において法然は、大抵のことについて「くるしからず」などと容認していますが、それはある程度合理的思考に基づいてのことで、破戒や非道徳に直結することに対しては否定しています。しかしこの酒については、どうにも歯切れの悪い答えです。法然は「飲んでも良い」、「飲酒は罪ではない」と言ってはいません。しかし言外に、消極的ながら飲酒を容認しているかの答えとなっています。
彼の受持していた梵網戒が、酒を売ること、および他に酒を飲ませ自ら飲むことも厳重に禁じていることから、「飲んでも良い」とも言えず、また「罪ではない」とも言えないのでしょう。けれども、社会で酒が一般的に通用し、(僧俗ともに)人がこれを好んでいることもまた否めない事実であるから、このような答えになったやに思われます。
そしてもう一つ、酒にまつわる問いが『百四十五箇条問答』にはあるのですが、無知が過ぎる今の不佞にはその意を解しかねています。『百四十五箇条問答』には他にも、人が法然に対し「いみ(忌み)」について問うものが散見されることから、当時は物忌が人々の大きな関心事であったことが知られます。しかし、「酒の忌み」とはこれいかに。
ここでは仮に、人が不飲酒を破ってしまったことによる物忌み、あるいは服喪中の物忌みとしての禁酒かと解しましたが、当時の物忌の実際をまったく知らぬため、それは何の根拠もない憶測にしか過ぎません。ただ、何らかの物忌みで七日間は酒を飲んではならない、という世間の認識があったことは間違いありません。
法然は「忌み」ということ自体が仏教には無い思想・習慣であって気にする必要など無い、と基本的に考えていたことが知られます。しかし、ここでは一般的に「酒の忌み」が七日間であることを肯定しています。また続けて、「されどもやまひには、ゆるされて候」すなわち「病の場合は(酒を用いることが)許されている」としている点は、実に面白く感じられる点です。
これは、前項の14.最澄『臨終遺言』や15.空海『御遺告』でも言及し、次の喜海『栂尾明恵上人伝』にても関連して指摘していることですが、『四分律』にて「病の場合には酒を用いても良い」とされているのに基づく言であったのでしょう。法然はいわゆる天台僧であった人で具足戒を受けてはいないため、それが律蔵に根拠する規定であると自覚していたかは不明でありますが、「病の場合は酒を飲める」という認識があったことは間違いありません。あるいは9.『梵網経』にて指摘した、智顗撰とされる注釈書『菩薩戒義疏』にある説に基づいた言葉であったのかもしれません。
いずれにせよ、そのような律などの規定にもとづく話が世間で平安初期の昔から広く知られていたことが、ここで法然も言及していることによって知られ、それがまた当時は酒を飲むことの理由としてよく用いられていたのでしょう。
この『百四十五箇条問答』における短い質疑応答の中から、今はそれだけのことを知ることが出来ます。
法然は浄土宗を立てる以前、比叡山延暦寺の僧で黒谷別所に住した遁世僧で、天台僧として梵網戒(円頓戒)を受け、また天台教学を学び深めて「智慧第一の法然房」などと讃えられていたようです。
若かりしころから叡山で勉学に励んでいた法然は、いつしか「阿弥陀仏」を観想してその救済を俟つと言う、支那以来の浄土思想に傾倒。これは一種の冥想であり、阿弥陀仏の姿や極楽浄土の有り様を心の中で想起し、心を浄化して極楽に往生しようというものです。これを一般に観想念仏と言います。しかし、やがて法然は叡山を降りて後、ただ口に「南無阿弥陀仏」と唱えることによっても人は阿弥陀仏の誓願力によって救われ得るする、独自の浄土教を主張するにいたります。これを特に称名念仏、あるいは口称念仏と言います。
人が戒をまもって経を学び、修禅に励むのは困難な悟りへの道であって、ごく少数の者が実行し得るのみである。これは自力の道、聖道門である。しかし、ただ阿弥陀仏を信じて口に「南無阿弥陀仏」と唱えてその救いの力に預かるだけならば、これは万人が行える容易な悟りへの道である。しかも末法の世においては聖道門はもはや無益であってこれを捨て、今こそ念仏こそ行うべきである。これは他力の道であり、浄土門である、と言うのが彼の大まかな主張です。
彼のこの主張は、一部の公家や寺家、そして庶民から注目され支持され始めます。といっても、その大部分は、文字も読めないような無教養の一般庶民だったようです。彼らからすれば、なんだかよく判らないが救いに至る「やさしい道」というのですから、既存の近寄りがたく「むずかしい道」よりは良い、という単純な理由だったのでしょう。もっとも、そのような人々の宗教的欲求は非常に強く、当時様々に生じていた天変地異や疫病、そして政変など過酷な現実に対応する真剣なものでもあった。
ところで、法然は梵網戒を受持すること厳重なる持戒の人であったとされていますが、しかし法然は自らをそう考えていませんでした。その様な自己認識は、黒谷にて日々を過ごす中での真摯な自省で育まれていたものか、あるいは当時突如として現れもてはやされた、最澄撰とされる『末法灯明記』(偽書)の影響を受けてのことであったのかもしれません。
『末法灯明記』の内容は実に衝撃的なもので到底最澄が書いたとは思われない書ですが、しかし当時の人は紛れもなく最澄の真撰と見なしていました。その後に出た親鸞や日蓮などはその所説を全面的に信受し、自身らの思想の核心部分の根拠として据えつけています。
中でも以下の一節はあまりにも有名で、法然をはじめ親鸞・日蓮もこれに言及しています。
設末法中。有持戒者。既是恠異。如市有虎。此誰可信。
もし末法の世に持戒の者があったならば、それはもはや怪異である。市中に虎が現れるようなものである。そんな者を誰が信じるというのか。
《伝》最澄『末法燈明記』
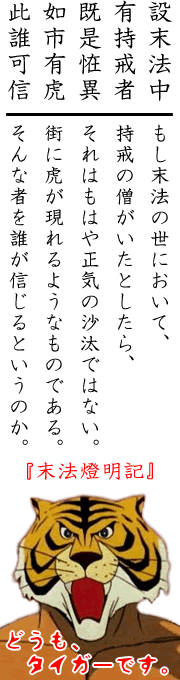
『末法灯明記』の所説に強い影響を受けた親鸞や日蓮などが持戒を実質的に放棄していたのに対し、法然は上掲の言葉を是認してはいたもの、自ら強いて梵網戒をことごとく捨て破ることはなかったようです。
これは法然の経歴と学徳に基づくことでもあったのでしょうが、その立場はある程度穏健で、浄土教を弘めようと運動を展開するものの、その独自色を強調して他を排斥する向きは強くありませんでした。それは天台宗の手前、そのような態度を取り得なかった、という政治的環境に由るところでもあったでしょう。
問題であったのは、法然の説く専修念仏を「純粋に」行おうとした地方の追従者・信奉者らで、念仏往生するのであれば持戒など一切無用と、むしろ積極的に非道得な行いをなすものが続出。その手合が生じるのはごく当然のことであり、法然の思想を突き詰めれば必然であったと思えますが、彼の説く浄土教が弾圧された原因の一つにもなっています。
彼の信奉者は、「南無阿弥陀仏」と称えれば救われるのだから、戒を守る事も善行を積むことも必要ない。いや、それらを行う者は愚か者だ。積極的に悪をなしても問題ない、ただ「南無阿弥陀仏」と称えればいいのだ、と主張して熱心にそれを実践修行していたのです。これを法然は一応戒めていますがほとんど効果なく、彼の教団の一部は今で言うカルト化していました。
そこでまた法然の主張した専修念仏思想、すなわち浄土教は、政治的・宗教的様々な原因から南都・北嶺の諸宗派によって猛批判されています。比叡山の専修念仏停止 のための『延暦寺奏上』を皮切りに、興福寺から同目的の『興福寺奏状』が提出されるなど、様々な理由から「法然が説くところの浄土教」は激しい反意にさらされています。南都にしろ北嶺にしろ、念仏それ自体ではなく、法然が主張した独自の浄土教を避難したのでした。
ついに彼の浄土教は禁止されて弟子の幾人かは処刑され、法然および弟子の親鸞は還俗させられたうえで流罪に処されています。これを彼の教団は「法難である」と言い、権力・既得権益者に由る大弾圧だと言いたがります。しかし、それは故なく無闇に行われたのでもなく、ましてや「法難」などでもなく、当時としてしかるべき理由のあったことです。
また、これは法然死後のことではありますが、同時代随一の聖僧とされた明恵上人は、法然の主著というべき『選択本願念仏集 』を実際に読んでみてその内容に衝撃を受け、『 摧邪輪 』(『於一向専修宗選択集中摧邪輪』)を著しています。明恵は「法然の浄土教(専修念仏による往生思想)」は「もはや仏教ではない」などと激烈な批判を加えたのでした。これは『興福寺奏状』でも同様であったのですが、阿弥陀信仰や念仏自体に問題があるとされたのでは全くなく、法然の浄土思想とその信仰には仏教的・伝統的に大きな問題がある、と見なされたのです。
そのような法然の思想をさらに突き詰め純粋にした、換言すれば極端にした親鸞のそれが、さらに大きな問題あるものと見なされたことは言うまでもありません。もっとも、親鸞のそれは「仏教がどうの」ということを逸しており、もはや法然に対する個人的、そして絶対的信仰となっていました。
親鸞にをきては、たゞ念仏して弥陀に助けられまひらすべしと、よき人のおほせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり。念仏は、まことに浄土にむまるゝたねにてやはんべるらん、また地獄におつべき業にてやはんべるらん、総じてもて存知せざるなり。たとひ法然聖人にすかされまひらせて、念仏して地獄に堕ちたりとも、さらに後悔すべからずさふらふ。
親鸞においては、「ただ念仏して弥陀に助けられなさい」という善き人〈法然〉の仰せを受け、これを信じる他には別の何も無い。「念仏が、本当に浄土に生まれる種でありましょうか、また地獄に堕ちる業でありましょうか」、いずれも(私親鸞の)知ったところではない。たとえ法然聖人に騙されており、念仏して地獄に堕ちたとしても、もはや後悔することはない。
唯円『歎異抄』(金子大栄校注『歎異抄』岩波文庫, pp.42-43)
親鸞における法然への絶対的信仰。彼はその法然の向こうに阿弥陀仏、そしてその阿弥陀仏について説かれた『阿弥陀経』等を説いた釈迦仏、そして支那において浄土教を扇動した僧らの存在を見てはいました。しかし、彼の信仰はもはやその正否・真偽など「総じてもて存知せざるなり」と言うほど絶対的なものとなっていたが故に、その浄土思想も絶対的な、いわゆる絶対他力ということになったのでしょう。
それはもはや仏教ではなく、むしろ外道たるインド教における Bhakti 〈神への絶対的信仰・信愛〉にまるで同じもの。あるいは現代的価値観をもって見ればまぎれもないカルトに他ならず、実際その定義にいくつも該当したものとなっています。
もっとも、親鸞は真宗という新たな浄土教の宗派を立ててなどいません。実際、彼は越後に流罪にされた際に還俗させられており、もはや僧でもなくなって妻帯しています。当時は僧で無いものが一宗派など立てられよう筈もありません。ただし、親鸞(還俗して藤井善信 )はそこで「非僧非俗」という、これは仏教からすると意味も根拠も不明の立場となるのですが、そう自らを見なすようになっています。彼はそこで僧形は捨てることなく「 愚禿 親鸞」と名乗り始め、流罪を赦されて京に帰ってからは盛んにその浄土思想を布教しています。とは言え親鸞自身は、「親鸞は弟子一人ももたず候ふ」と自分には弟子など一人もいないと、これは彼独自の絶対他力という思想からして必然的帰結といえますけれども、そう言っています。
弟子が無いならその一派を形成しようもありません。が、実際には親鸞の弟子を自認するものが大量にあり、親鸞の死後、その信奉者たちによって彼を祖とする宗派が形成されています。結局、浄土宗にしろ真宗にしろ、歴史の中でそれらの存在は既成事実化していき、今や日本仏教の代表とでもいうべき勢力と位置を占めるに至っています。
今もしばしば法然や親鸞の浄土教および日蓮の法華宗は「仏教ではない」と言われ、あるいは「新仏教」などと括られていますが、それを否定的に見るかあるいは肯定的に見るかいずれか一方に大体分かれるようになっています。
法然の「ま事にはのむべくもなけれども、この世のならひ」という答え。
それが後世の浄土門に残した影響力は絶大で、今もこの言葉を引用して飲酒について語る、その門徒は跡を絶ちません。この言葉をもって「御祖師様はこうおっしゃられているから、酒を飲んでもいいのだ」と結論されています。その門流の僧職者らが、酒を飲むことを正当化するのにもっとも便利な道具となっているのです。そのような事態を後に招くことになろうとは、法然も考えが及ばなかったのでしょう。
これはまさに「祖師仏教」などと揶揄される日本仏教徒の面目躍如といったところ。
この場合、数々の仏典にある飲酒を厳しく戒めている文言など、「お祖師さまのお言葉」の前にすべて消し去られます。「この世の習い」という言葉もまた、今の現代日本社会において大変強力なものと言えるでしょうが、さらに「お祖師さまのお言葉」ともなれば、もう仏典も何もまったく無くなってしまうのが日本仏教です。
しかし、前述したように、法然は必ずしも「酒を飲んでもよい」とも「罪ではない」とも言っていません。そのように法然の言葉にかこつけることは、当時カルト化していた一部の弟子となんら変わりなくなってしまう。そしてそれは、法然にとって最も不本意な事態となるに違いありません。
今、浄土教の門徒の多くは、「法然上人は持戒の清僧であった」と讃え、そして一方「大変フトコロのひろい方であって、自分に厳しく人に優しい、人間らしくおおらかな人であった」などと称えています。「人間らしい」とはなんでしょうか。大抵の場合、人が口にする「人間らしさ」とは「人情」の有無強弱を意味するようです。しかし、情によって行動するのは動物と同じであって、人間もまた動物の一種でありますが、故に「人間らしい(特有)」ものではありません。人間に特有といえるのは「知」であって「情」ではないのだから。
そのように都合よく、その内容や意図を無視してただ猿真似、鸚鵡返しすることは、まさしく畜生の所業に他なりません。菲才は動物全般が非常に好きでありますが、この種の畜生について面白いとは思いますが可愛いとはちょっと思われない。そんな私は彼らの言う意味ではきっと、まったく非人情で人間らしくないのかもしれません。
酒を飲むことはたとえ「この世のならひ」であったとしても、酒は「知」を増す薬には決してならず、むしろ「情」を奔放にさせて人を畜生に等しくするものです。
Bhikkhu Ñāṇajoti(沙門覺應)